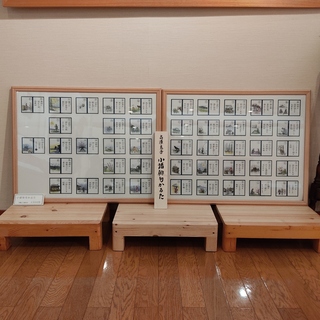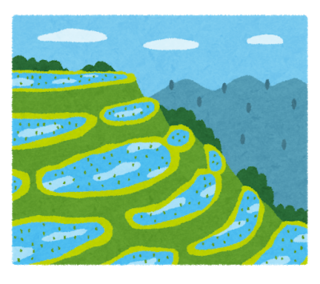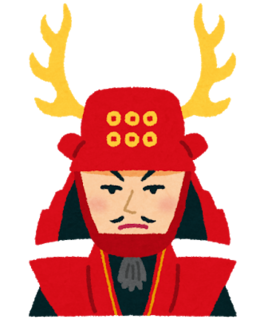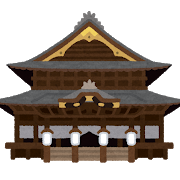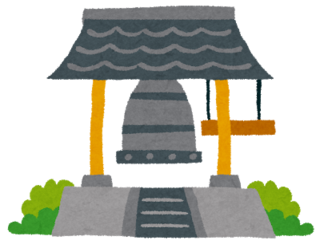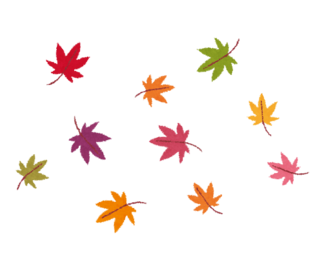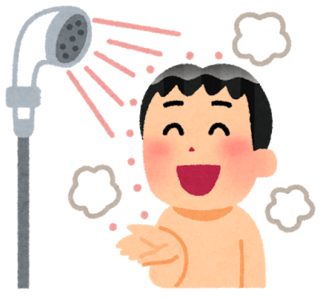この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2022年06月19日
歌人・俳人 〜高濱虚子〜
先日、お昼ご飯ついでに足を延ばして、市立 高濱虚子記念館に行って来ました。
親戚のおじいちゃんのおうちからは、ちょっと距離のある小諸。お出掛け前から、ちょっと怪しい天気だったのですが。高濱虚子記念館に着いたとたんに本降りの雨。噂によると、記念館の近辺が虚子の散歩道と呼ばれ、散策コースになっているそうなのですが...
よく見ると、高濱虚子記念館のパンフレットにも、虚子の散歩道の地図が入ってました。散歩道には与良古墳やお寺、神社、郷倉があるようです。小諸八幡宮では、毎年9月1日に八朔相撲という子供相撲が開催されているそうです。この八朔相撲には、その昔、あの雷電が出場したらしいですよ。雨さえ降っていなければ、もう少し足を延ばして、小諸の歴史が感じられる古い町並みも散策できたのに...
取り敢えずは、館内の展示物を見て回り。
そして、現在公開されている唯一の虚子旧宅で、当時のままの姿で保存されているという虚子庵...高濱虚子が戦火を避け小諸に疎開していた際に、使っていたという旧宅を訪れてみましたが。
結局、雨が止まないどころか、よりひどくなったので。
虚子の散歩道の散策は、中止に...o(T◇T)o
残念でしたが。
今度、またお天気のいい日に、虚子の散歩道だけじゃなく、歴史が感じられる小諸の古い町並みも散策してみたいと思います。
2021年08月16日
真田氏ゆかりの地 〜四天王寺〜
四天王寺 は、今から1400年以上も前の推古天皇元年(593年)に、四天王を安置する寺院を建立し、この世の全ての人々を救済するために聖徳太子によって建立されたという日本仏法最初の官寺。その伽藍配置は、四天王寺式伽藍配置と呼ばれ、南から北へ向かって中門、五重塔、金堂、講堂を一直線に並べ、それを回廊が囲む形式で、日本では最も古い建築様式のひとつなんだそうです。その源流は、中国や朝鮮半島に見られ6〜7世紀の大陸の様式を今日に伝える貴重な建築様式とされているそうです。
現在の伽藍は、1963年に再興されたもので、境内に聖徳太子の御霊を崇る聖霊院の太子殿や、日本庭園の極楽浄土の庭などが有ります。
毎年4月22日、聖徳太子を偲んで催される聖霊会舞楽大法要では、重要無形民俗文化財の天王寺舞楽が披露されるそうです。
大阪観光局公式サイト OSAKAINFO
NHK 新日本風土記アーカイブス みちしる
2021年05月16日
武田信玄 〜生誕500年〜
武田信玄 といえば、12年間で5回におよんだといわれる戦国武将で上杉謙信との川中島の合戦が有名です。武田軍の陣頭に、立てられた風林火山の軍旗は、『疾きこと風の如く、徐かなること林の如く、侵掠すること火の如く、動かざること山の如し』という、中国の孫子の兵法。菩提寺で信玄公のお墓もあるという、 武田信玄ゆかりの地 、甲州市の乾徳山恵林寺で観ることができるそうです。戦国時代、知将として人気の武田信玄。2021年は、大永元年11月3日に 信玄公が誕生してから500年 という記念すべき年なんです。山梨県では、色んな記念事業が開催予定らしいので、機会があれば訪れてみたいと思っています。
甲府市ホームページ 信玄公のまち
歴史博物館 信玄公宝物館
公益社団法人やまなし観光推進機構 富士の国やまなし
甲府市武田氏館跡歴史館(信玄ミュージアム)
2021年02月23日
山姥伝説 〜信州中条村、虫倉山の大姥様伝説〜
山姥伝説の残る 信州中条村 は、山間の小さな村。日本の棚田百選に選ばれた栃倉、大西、田沢沖という棚田が3つも存在する里山の風景は、誰もがどこか懐かしさを感じる日本の原風景ではないでしょうか。そんな、中条村、虫倉山に残っている山姥伝説は、私がそうであったように、皆さんが思っている山姥とは違っていると思います。
一般的には、人里を離れた山奥や森に棲み、迷い込んだ旅人に宿や食事を提供するが...寝入った隙に襲い食べてしまうというような話だと思うのですが。ここ 虫倉山に残る大姥様の伝説 では、子ども達の成長や村人達の生活を見守る優しい山姥の伝説です。
気になる山姥伝説。棚田100選に選ばれた棚田や信州百名山の虫倉山といった里山の素敵な田園風景や、おぶっこ、おやき、にらせんべいといった昔から地域で親しまれている郷土食も楽しんでみたいです。
2021年01月11日
平家落人伝説 〜湯西川〜
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり...という書き出しで始まる平家物語。平清盛は中国の宗との貿易や文化の発展、芸術の振興に力を注いだといわれていますが、64才でその生涯を閉じたそうです。そして、4年後の1185年壇ノ浦の戦いで、平家は源氏に敗れ...滅亡したと思われていた平家の人々が、日本各地に逃れ実は生き残っていたというのが平家落人伝説。
栃木県日光市湯西川 も、日本各地に残る平家落人伝説の地のひとつとして古くから知られ、平忠実が落ち延びたとされる 険峻峡の秘境ながら森閑に開けた里 には、多くの秘話、伝説や風習、芸能が連綿として継承されてきているそうです。
なかには、武具を納めたという平家塚や各家に伝わる平家ゆかりの品々などの伝説を裏付けるものが存在しているそうなんです。温泉の発祥は、1573年で400余年の歴史があり、平家の落人の子孫が発見されたと伝わっているそうです。追討から逃れ、身を潜める山村生活を営み生きるため、この地では今もなお端午の節句に鯉のぼりを揚げない、たき火をしない、鶏を飼わないなど独自の風習が残っているそうです。
2020年は、新型コロナウイルスの影響で中止になりましたが。毎年、6月上旬に「 平家大祭 」というお祭りが開催され、平家の武者や姫に扮した総勢200名余が練り歩く「平家絵巻行列」や琵琶演奏や雅楽など、平家に関する催しが繰り広げられるそうなんです。
2020年12月19日
真田氏ゆかりの地 〜真田庵〜
真田庵
は、慶長5年(1600年)に関ヶ原の戦いで敗戦した真田昌幸、幸村父子が、信州上田から紀州久度山に配流され、慶長19年(1614年)大阪冬の陣で真田幸村が、大阪城に入城するまでの14年間蟄居していた屋敷跡に建てられた寺院。境内や周辺には、真田幸村に関する伝説も多く残っているといわれています。
なかでも、真田古墳には、真田の抜け穴伝説が残っており...この穴の向こうは大坂城に続いていて、かつて真田幸村はこの抜け穴を使って戦場へ出向いた。といわれているそうです。
紀州九度山では、真田昌幸、幸村父子を偲んで、毎年春に真田まつりが開催されているそうです。鎧兜に身を包んだ真田幸村を先頭に総勢200名の武者行列が町内を練り歩くらしいですよ。
紀州九度山には、真田庵の境内にある真田宝物資料館や 真田ミュージアム
の他にも、 いろんな世界遺産
もあるんですよ。
2020年01月26日
真田氏ゆかりの地 長野市 〜信州 善光寺〜
信州 善光寺 は、今から約1,400年前に創建されたと云われているそうです。現在の本堂は、約300年前に建立されたと云われ、仏堂の前に大きな礼堂を配した撞木造りと呼ばれる独特の構造を持つ国内でも最大級の木造仏教建造物。1953年には、国宝に指定されたそうです。御本尊の一光三尊阿弥陀如来は、絶対秘仏であり、数え年で7年に1度、御本尊のお身代りとして同じ姿の前立本尊を本堂にお遷しているそうです。この盛儀が善光寺御開帳というそうです。
2020年2月3日(日)13:00〜14:30には、第69回善光寺節分会が行われる予定で、EXILE ÜSAさん、MAKIDAIさん、TETSUYAさん、FANTASTICS from EXILE TRIBE 澤本夏輝さんなどが特別来賓として予定されているそうですよ。詳細は、信州 善光寺の公式ホームページで確認して下さいね。
2018年11月10日
紅葉の名所 〜まだ間に合う? 2018〜
All About で「 これぞ絶景!全国紅葉名所ランキング15選【2018年版】 」という記事を見つけました。まだ紅葉の見頃に間に合うのかなぁ?ということで、ちょっと調べてみました。この記事は、全国の紅葉名所の中でも、写真を見ただけで、特別な絶景だと感じる紅葉狩りスポットを厳選して紹介しているそうです。詳しくは、All Aboutの記事を見て下さいね。
河口湖北岸(もみじ回廊)
河口湖北岸の付近には、「もみじ回廊」や「もみじトンネル」と呼ばれる紅葉並木があって、紅葉と世界遺産の富士山を一緒に楽しめるそうなんです。もみじ回廊は、紅葉のライトアップも行われるそうなんですよ。紅葉見頃時期は、例年11月上旬〜11月中旬らしいです。
2018富士河口湖紅葉まつり は、11/1〜11/23の予定で開催中ですよ。
国営昭和記念公園
国営昭和記念公園は、黄葉を中心とした絶景の紅葉スポットとして有名で、毎年、 黄葉&紅葉まつり が開催されているそうです。写真のカナ−ルと呼ばれるエリアには、全長200mの水路に大小5つの噴水、敷きつめられた舗石と樹木が織り成す欧州の庭園のような場所があるそうです。紅葉見頃時期は、例年11月上旬〜11月下旬らしいです。
星のブランコ・大阪府民の森ほしだ園地
関西を代表する紅葉スポットの星のブランコ。星のブランコと呼ばれるとっても大きな歩行者専用吊橋は、七夕伝説の里であり、星降る里のシンボルという意味合いで、この吊り橋に「星のブランコ」という愛称がつけられそうです。紅葉見頃時期は、例年11月下旬〜12月上旬らしいです。
明治神宮外苑銀杏並木
東京の絶景の紅葉スポットは、黄色い銀杏並木で有名で、六義園の紅葉とともに都内屈指の紅葉スポットになっている明治神宮外苑です。黄色の色合いが美しいだけでなく、美しい円錐形をしているのは、冬場に4年に1回、この形状に剪定して維持しているそうですよ。紅葉見頃時期は、例年11月下旬〜12月上旬らしいです。
2018年01月28日
スポーツバイクの発着基地? 〜暖かくなったら自然を楽しみながら…〜
昭和レトロな町 青梅のことを記事にするために色々調べていたら、こんな気になるショップを発見しました。スポーツバイクの発着基地 サイクルハーバー青梅 です。どんなお店かというと、スポーツバイクを預かってくれたり、レンタルできたり、点検やメンテナンスもお願いできるんです。
それだけじゃないんですよ。シャワーにロッカー、軽飲食までできるんです…ということは、青梅まで手ぶらで来て、そこから自転車で更に遠くに足を延ばすことができるんです。街中を走るのではなく、ウィークエンドとかに自然を満喫しながら、気になるところに寄り道してポタリングを楽しんだり、サイクリングやヒルクライムで身体を鍛えたりできるんです。(???人)?
それから、青梅のお土産も扱っているらしいですよ。暖かくなったら、名所、史跡、ビューポイント、ライドポイントなどのコースの情報やイベントも開催されているらしいのでホームページやFaceBookをチェックしてお出掛けしてみてはどうでしょうか。
2017年05月21日
真田氏ゆかリの地 〜松代城跡、真田宝物館、真田邸〜
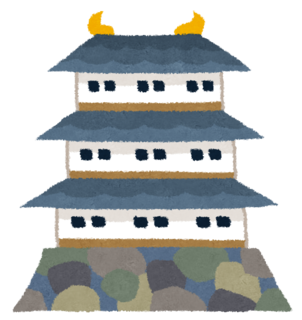
松代城跡
松城城は、戦国時代、武田信玄の命で山本勘助によって築城されたといわれてます。1622年に真田信之が上田城から移封されて以来、明治維新まで真田氏10代の居城となったそうです。1981年には、新御殿(真田邸)とともに国の史跡に指定され、櫓門、木橋、石垣、土塁、堀などが復元されました。
真田宝物館
真田宝物館は、1966年に真田家12代当主、幸治氏から譲られた武具、調度品、書画、文書などの大名道具を収蔵、展示している博物館です。松代藩真田家の歴史、大名道具を紹介する常設展示室、テーマに沿った企画展、特別企画展が行われる企画展示室があるそうです。
国の重要文化財である「青江の大太刀」や真田昌幸(幸村の父)所用の「昇梯子の具足」、武田信玄、豊臣秀吉、石田三成、徳川家康らの書状など、貴重な資料はおよそ5万点にもおよんで、年4回展示替えで、実物資料をほぼすべてを入れ替えしながら展示しているそうです。

真田邸
真田邸は、幕末に参勤交代制度が緩められ江戸在住を命じられた9代藩主の真田幸教の義母である貞松院の住まいとして1864年に建築された松代城の城外御殿です。のちに、隠居した真田幸教もここを住まいとしていたそうです。明治以降、伯爵となった真田氏の私宅となりました。1966年、12代当主の真田幸治氏により代々の家宝とともに、当時の松代町に譲渡されたそうです。
主屋、表門、土蔵7棟、庭園が江戸末期の御殿建築の様式を伝え、建築史の視点からも貴重な建物であるため、松代城と一体のものとして国の史跡に指定されているそうです。
真田邸庭園内の3番土蔵では、体験工房として、切り紙や筝の演奏などが体験できるそうです。
最後に、松代城跡、真田宝物館、真田邸、その他の近隣施設にお出掛けの際には、案内(展示と行事など)が、 真田宝物館のホームページ にありますので参考にして下さいね。