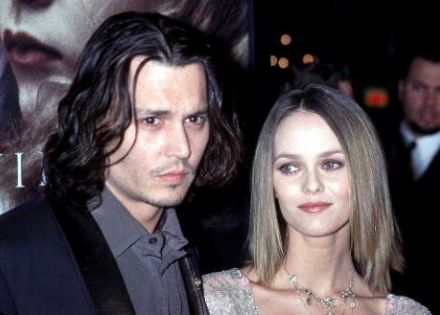首都アンマンへ
私は一体どこへ帰りたかったのだろう。
もう住む者のいなくなった信州の一軒家だろうか。それとも東京という名の砂漠で長年暮らしたマンションの一室?
今となっては、いや、その時さえもわからないどこか安全な場所、身の危険を感じることのない、暖かな安らげる場所をずっと探しているような気がする。
だから、旅に出たのかもしれない。
遠くからでも目印になる、巨大なキング・アブドゥラー・モスク
ハイリスク、ハイリターンだった ワディ・ラムと ペトラでの嵐のような2日間を何とか無事に生き延びたあと向かったのは ヨルダンの首都アンマン。
朝7時、またしても5ディナールで生活路線バスに乗り、子供のようなアジアン・ガールが一人で何しとる?的な好奇の目に晒されながらも4時間後、今度こそアンマンの市内中心部へと入った。
不毛な大地の中を真っ直ぐに伸びるデザート・ハイウェイをひたすら北上したこの4時間は、ごく稀に村とさえ呼べないような小さな集落を通り抜けたりもするが、ほとんど見渡す限りの土漠と、彼方にうっすらと横たわる岩山の世界が続き、ほの暗く垂れこめたブルーグレーの雲間から時折り天使の梯子が大地を照らす様に目を奪われてあっという間に過ぎた。
人間を見張る巨人のような鉄塔の間に白く光る街並みがだんだんはっきりと見えてくるにつれ、首都入りの期待も高まっていった。
ヨルダン入国以来あまりに体を酷使したため、アンマンでは少し贅沢してもいいよね、と自分に言い訳をして1泊24ディナール(約2,900円)の中級ホテルに3連泊。
冷蔵庫、テレビ、うるさいエアコン(ありがたい!)、更に何とシャワーブース付き(しかもちゃんとお湯が出る!)の比較的小綺麗な部屋に落ち着いて、ようやく人心地ついたのだった。
愛すべきヨルダンの女たち
ホテルで少し休むと見違えるほど急速にパワーが回復。快適な環境が人に与える癒しの力には驚かされる。
2時頃お腹に何か入れようと外に出てみることにする。気の向くまま歩いてホテル近くのモスクや国立美術館に立ち寄った後、住宅街に入り少し迷ってみる。
「地球の歩き方」の地図はやはり全く役に立たず真剣に迷ったので、運良く通りかかった主婦らしい女性に道を訊いてみた。
英語がわからないうえ、彼女自身その辺りの地理がわかっていないようで、近所の女性たちに訊きながら一緒に歩き、モスクが見える場所まで送ってくれた。
始めは目も合わさなかったのに、話しかけてみると案外気さくな彼女たちは世話焼きな日本のオバサン達と変わらず、何だか嬉しかった。
中東の女性たちは、未だに外出するときは必ず夫か兄弟が同伴する習慣が残っており、一人歩きはあまりしないのだそうだ。
アンマンでは女性だけで連れ立って歩く姿も見かけたが、その他の地域では女性たちは皆一様にスカーフやベールで顔を覆い肌の露出も避けて、家族以外の男性とは口もきいてはならないようだった。
そんな中でカメラは構えにくく、ヨルダンでは人の写った写真がないのが残念だ。
住宅街のお菓子屋さんで発見したエクレアとクッキー(そんな洋菓子にここでお目にかかれるとは思っていなかった)をゲットし、ホテルの隣のコーヒースタンドでホットココアを買って部屋に戻る。
このスタンドは毎日利用したので、店員の男の子たちは私の顔と名前を覚えてくれて(アジア人が珍しかったからだろう)私が行くたびに「今日もホットココアだね」と、ツーリスト価格ではない地元料金でサーブしてくれた。
さすがに大胆なセクハラにも慣れてきたので断固として断り去ろうとすると、「明日の朝までに人を集めておくから大丈夫だ」と請け負い、その場でたまたまドミトリーから出てきた若い男の子を捕まえると「明日半日のデザート・キャッスル・ツアーに行かないか」と声をかけた。
意外にもその男の子はすんなり快諾した上に友人も誘ってみるという。
この強引な集客力、恐るべし。
夕飯用に安食堂でテイクアウトしたサラダと炒め物は、店主の目を盗み勝手に接客した子供が盛り付け時に素手で触りまくっていたので不安だったが、案の定すぐに下痢をした。
あのクソガキ…
近代的大都市 アンマン
ヨルダンの最大観光地は世界遺産のある ペトラであり、アンマンにはさして有名な観光名所はないのだが、塩野七生ファンとしてはローマ時代の遺跡には興味があるので アンマン城(現地ではシタデルと呼ばれている)と ローマ劇場跡を目指す。
シタデルは急峻な岩山の頂にあり、三方を崖に囲まれ残り一方は尾根という天然の要塞でローマ、ビザンチン時代の廃墟と化した遺跡が城壁内に残る。
市内中心部のローマ劇場跡見学の後、どうやってシタデルへ行けばよいのかと使えない地図と睨めっこしていた私に、声をかけてくれた男性がいた。
サングラスをかけたアラブのビジネスマンを思わせるインテリ風のその初老の男性は、シタデルへ歩いて行くのは難しいからとタクシーを拾える道まで案内し、タクシーを止め、ドライバーに行先まで確認してくれた。
去り際に彼は、ヨルダン人男性の多くは英語ができるし皆親切だから躊躇せずにいつでも尋ねればいい、と言った。恐らくウロウロしていた私を暫く観察していたのだろう。
愛すべきヨルダンの男たち
ピーカンの天気の下で人の少ないだだっ広いシタデルをぞんぶんに歩き回り、心地よい疲れが訪れたところでダウンタウンに戻り夕食漁りを始める。
本当は一度くらい街中のカフェやレストランに入って食べてみたかったのだが、女性の一人歩きというだけで好奇の目で見られたり、カモとして狙われる危険のある旧態依然のアラブ社会では少し気が引けて、結局毎回テイクアウトのファストフードしか食べられなかった。
近代的な都会といえどもやはり、まだまだレストランの大部分は男性客で、女性には必ず男性の連れがいるのが現状だ。とはいえ、賑わうダウンタウンのお店を覗くのは案外楽しかった。
アンマン城の廃墟が残る岩山上のシタデル
チキンサンドをテイクアウトしたピザ屋では一階の半分がオープンキッチンになっていて、調理の様子を見ることができるのをいいことに、オーダーが出来上がるまでの待ち時間、存分に男ばかりの厨房を眺めさせて頂いた。
何人も立ち働く男達の中でも、部下に指示を出しながら調理していたお兄さんの手が物凄くキレイで目が釘付け状態に。
アラブ人なので勿論手が白い訳ではないのだが、薄力粉が付いて石灰色になった細くて長い指がピザの生地をこねては焼いていく様はちょっぴりセクシーで、働く男性の大きな手って魅力的だなぁ、とうっとり眺めてしまった。
アラブ人特有の濃く太い眉の真下に光る鋭い目で、今にも決闘に出かけるかのように生地を睨みながら恐ろしく真剣な顔で調理していた彼が、私に「できたよ」と伝えてくれたときの笑顔は思いのほか優しくて、私を穏やかな、暖かい気持ちにしてくれたのだった。
そのイケメン料理人はじめ、親切なインテリおじさん、コーヒースタンドの少年たち、そして迷った私を送ってくれた女性。
彼らのうち誰もカメラに収めることはできなかったけれど、大切な思い出として心に焼き付けておきたいと思った。不本意ではあるが、ナンパ男のナーサとストロングマンも…。
彼らが女性の体に触りたがるのは、宗教的なバックグラウンドによるところが大だろう。
イスラム教の男たちにとって、女性は人間というよりも所有物に近い。
そんな世界では、男たちは自然と一段低い女性には何をしても良いと思うようになる。
女性の体に触ることは、彼らにとってある意味当然の権利なのかもしれない。
もし私がホステルに泊まり、世界中からの旅行者と友達になってレストランや飲み屋に繰り出し、現地の人たちとも友達になれたら、その辺りのことも聞けたのになぁ、と少し残念に思う。
自分の英語に対する自信の無さと消極的で一人を好む日本人らしい性格のせいで、せっかくの自力旅でのチャンスを生かすことができないことが悲しい。
それにしても、全く何も決めずに、何の準備もせずに乗り込んだヨルダンで私はいろんな経験をした。その時は「最悪…」と思うことばかりだったが、これこそが旅なんだ、という思いも強く感じていたのは確かだ。
次に何が起こるかわからない、ちょっと困った愛すべき人々との出会い、追い詰められたときの賭けのような行動…。
運よく無事に帰国した今、最も懐かしく思い出す国、ヨルダン。
いつかもう一度、行きたいと思う。
★ 『ヨーロッパ前編?@ヨルダンからの脱出』 へつづく…
★世界一周旅の始まりは こちら へ戻る。