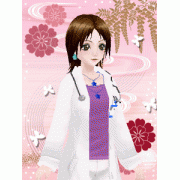テーマ: 赤ちゃんが欲しい!(9164)
カテゴリ: お仕事
昨日まで私が読んでいた論文(英語)で
先生たちの前で発表(抄読会と言います・・・)をしたのですが。
その論文がとても長いものだった!
私のつたない英語力では、すべてを読みきれたかは謎でしたが、
でも頑張って読んで皆に説明をしました!!
その論文の内容は
「卵を形だけではなくて時間的な変化も観察することで着床するものを選ぶことができる!」
というようなものです。
私たちは普段、卵を観察して卵のクオリティーを判定しますが、
それは瞬間、瞬間のもの。
卵をずっと観察していたい気持ちは山々ですが、
卵をお外に出しておくと、
培養液の温度やpHがどんどん変化して、卵に悪影響を及ぼしてしまう。
卵を光にあてると、活性が高くなってやっぱり卵に悪影響を及ぼしてしまう。
ここに再三書いていることですが、
卵をずっと長い時間見ていくことは、卵にはよくありません。
だから、観察する時も、ササっと見る。
顕微鏡にテレビモニターを繋げて、
複数人で素早くかつ丁寧に卵を見ます。
でも・・・。
卵の瞬間を見ただけでは、
実際にその卵がどういう経緯を辿って今の状態を見せているのかはわかりません。
ということは、
卵を観察するカメラが
卵を培養する培養器の中に設置しておければ。
もしくは、
卵を観察する顕微鏡が培養器のようになっていれば。
卵を時間を追って観察することが可能ではあります。
カメラに収めるということは、光をあてる、ということになるので、
ずっとビデオを回している訳にはいきません。
だから、こういう装置の開発はとても大変で、なかなか皆が出来るものではない。
・・・今回の論文では、カメラを培養器の中に設置して、
15分おきに撮影をしたそうです。
そして沢山の卵を観察して、その後妊娠したかどうかを確認し、
どういう条件が妊娠につながる卵か 、というのを調べています。
その妊娠につながる条件というのは以下の通り。
1)5細胞期胚になる時間が、顕微授精後48.8-56.6時間の間
2)2回目の細胞分裂(2cell→3 or 4cell)の時間が0.76時間以内
3)2細胞期胚である時間が11.9時間以内
・・・というものです。
普段私たちが観察するのは、
受精確認の時間と、2細胞期胚になった頃の時間、4細胞期胚になった頃の時間・・・
となっているのですが、
なかなか5細胞期胚はお目にかかれません。
でもこの論文ではなぜか一番5細胞期胚になった時間を強調していました。
いつ、どのタイミングでそうなるかを見極めるのはとても難しいのですが・・・・・。
受精してから、2細胞期以降どのタイミングの卵でも、
一番大切なのは
「 早すぎず、遅すぎず細胞分裂をすること 」
なのだそうです。
たとえば、遅すぎる場合は、染色体異常である可能性も大きいらしいので。
ひとつひとつのタイミングを見るというよりも、
この「遅すぎない、早すぎない、適切なタイミングで進んでいく卵」
というのを選ぶことができればベストなのだと考えられます。
難しい内容ではありましたが、、、、、。
なかなか読み応えがあって、
会が終わった後にも、Dr.達とプチ討論会になってしまって、白熱してしまいました
というわけで、今日もお読みいただきありがとうございました。
クリックの方をお願い致しまーす

にほんブログ村

にほんブログ村
先生たちの前で発表(抄読会と言います・・・)をしたのですが。
その論文がとても長いものだった!
私のつたない英語力では、すべてを読みきれたかは謎でしたが、
でも頑張って読んで皆に説明をしました!!
その論文の内容は
「卵を形だけではなくて時間的な変化も観察することで着床するものを選ぶことができる!」
というようなものです。
私たちは普段、卵を観察して卵のクオリティーを判定しますが、
それは瞬間、瞬間のもの。
卵をずっと観察していたい気持ちは山々ですが、
卵をお外に出しておくと、
培養液の温度やpHがどんどん変化して、卵に悪影響を及ぼしてしまう。
卵を光にあてると、活性が高くなってやっぱり卵に悪影響を及ぼしてしまう。
ここに再三書いていることですが、
卵をずっと長い時間見ていくことは、卵にはよくありません。
だから、観察する時も、ササっと見る。
顕微鏡にテレビモニターを繋げて、
複数人で素早くかつ丁寧に卵を見ます。
でも・・・。
卵の瞬間を見ただけでは、
実際にその卵がどういう経緯を辿って今の状態を見せているのかはわかりません。
ということは、
卵を観察するカメラが
卵を培養する培養器の中に設置しておければ。
もしくは、
卵を観察する顕微鏡が培養器のようになっていれば。
卵を時間を追って観察することが可能ではあります。
カメラに収めるということは、光をあてる、ということになるので、
ずっとビデオを回している訳にはいきません。
だから、こういう装置の開発はとても大変で、なかなか皆が出来るものではない。
・・・今回の論文では、カメラを培養器の中に設置して、
15分おきに撮影をしたそうです。
そして沢山の卵を観察して、その後妊娠したかどうかを確認し、
どういう条件が妊娠につながる卵か 、というのを調べています。
その妊娠につながる条件というのは以下の通り。
1)5細胞期胚になる時間が、顕微授精後48.8-56.6時間の間
2)2回目の細胞分裂(2cell→3 or 4cell)の時間が0.76時間以内
3)2細胞期胚である時間が11.9時間以内
・・・というものです。
普段私たちが観察するのは、
受精確認の時間と、2細胞期胚になった頃の時間、4細胞期胚になった頃の時間・・・
となっているのですが、
なかなか5細胞期胚はお目にかかれません。
でもこの論文ではなぜか一番5細胞期胚になった時間を強調していました。
いつ、どのタイミングでそうなるかを見極めるのはとても難しいのですが・・・・・。
受精してから、2細胞期以降どのタイミングの卵でも、
一番大切なのは
「 早すぎず、遅すぎず細胞分裂をすること 」
なのだそうです。
たとえば、遅すぎる場合は、染色体異常である可能性も大きいらしいので。
ひとつひとつのタイミングを見るというよりも、
この「遅すぎない、早すぎない、適切なタイミングで進んでいく卵」
というのを選ぶことができればベストなのだと考えられます。
難しい内容ではありましたが、、、、、。
なかなか読み応えがあって、
会が終わった後にも、Dr.達とプチ討論会になってしまって、白熱してしまいました
というわけで、今日もお読みいただきありがとうございました。
クリックの方をお願い致しまーす
にほんブログ村
にほんブログ村
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[お仕事] カテゴリの最新記事
-
生殖補助医療胚培養士 資格試験 (面接v… 2012.04.25 コメント(9)
-
生殖補助医療胚培養士 資格試験 (書類&… 2012.04.24 コメント(2)
-
排卵の仕組みがわかったらしい(汗) 2012.04.11
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.