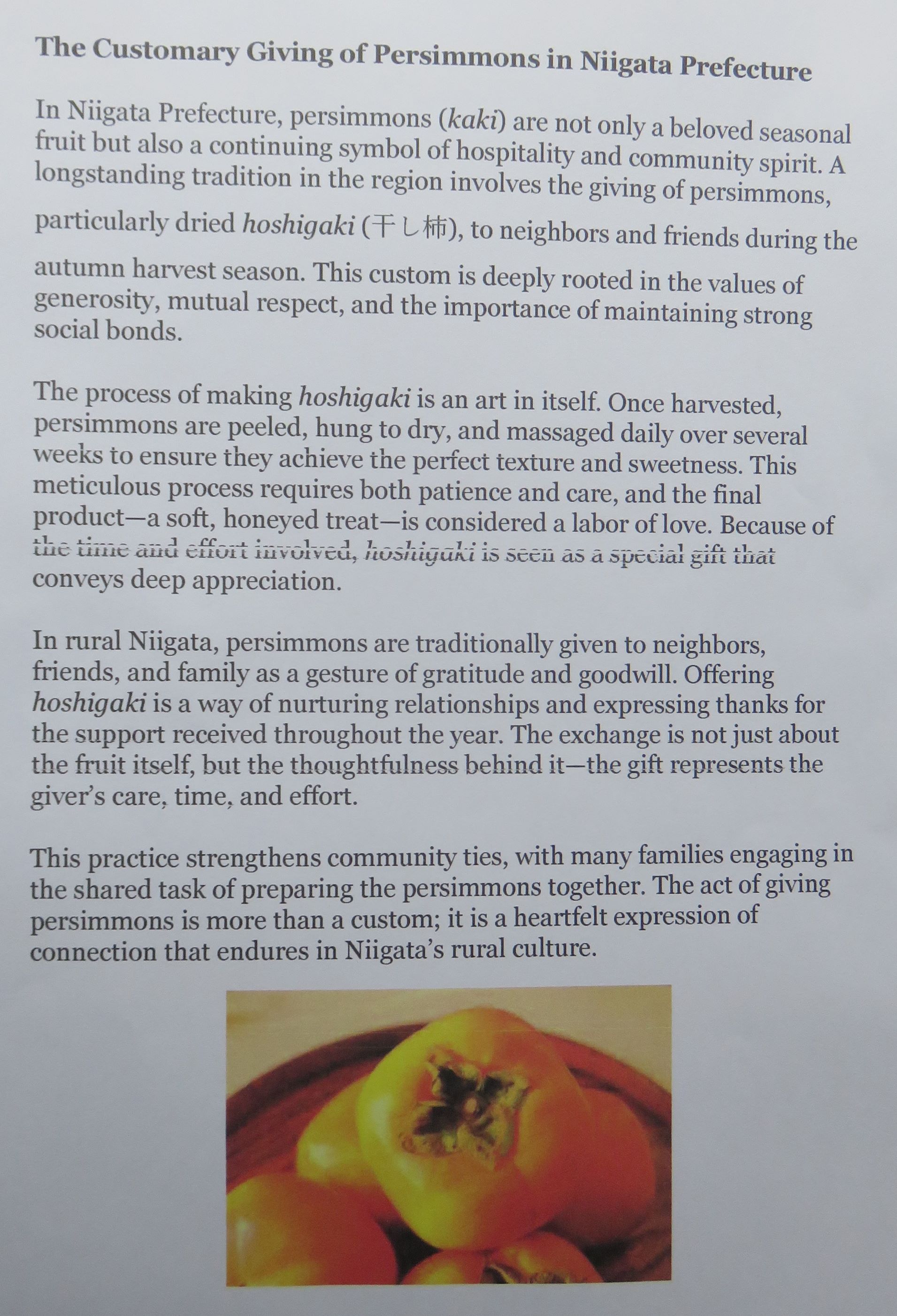10月のバラ 【5】




今朝私が乗った彼(彼女?)かどうかは余裕もなかったし(というかどっちみち)分からずじまいだった。
しかし、唱えるのだ。「あばれるなよ。走りだすなよ」
「荒野の7人」ならぬ「砂漠のぱっとしない4人」は様々な思いを乗せて蹄の音を聴く。
薄闇のなかで視界が開けたとたんに、黄金色に輝くクフ王のピラミッドが西の空を突かんばかりに現れた。朝日が射したのかと勘違いした。
幻想的であるが、とっさに観光客相手に「音と光のショー」と題して、その遺跡の生業を各国語のナレーション付で遺跡にレーザー光線を浴びせているのだと悟っ
た。
ルクソールのカルナック神殿やアブシンベル神殿など遺跡という遺跡でこのショーを観ることができる。
あらためて、この国は観光立国であるということを思い知らされる。
ピラミッドとスフィンクスを正面に見据えて、桟敷席に座り、ファラオの栄光を讃えるスピーチを拝聴し、自らの幻想を一層かき立てる仕組みなのだが、母国語でない時間帯のショーに当たると悲惨な目に遭う。事実、ルクソールのカルナックのショーに、時間が迫って勇み足を軽くとられたタクシーの運ちゃんに法外な値段でホテルから送ってもらい、何とか開演に間に合ったはいいが、当日の放送は「フランス語」だった。
いずれにせよ、現在の私たちが置かれている状況はといえば、ピラミッドをすでに遥か方にし、トコトコ歩く馬に揺られて、 とはいえかなりの距離を来た換算にな
る。
馬の上でもモーセスは相変わらず、妻になんたら、かんたらと話しかけては世話を焼いている姿を後ろから見ていると、どうみても私の存在が否定されている気にな
る。
そんなことはどうでもよいが、私はといえば昼間と同じようにモーセスの子分に馬を引かれて無口なまま続き、決して乗り心地よいファラオの気分とはいかなかった
のだ。
子分はやはり目をあわせようともせず、拗ねたように黙々と一人はしゃいでいるモーセスの後を、その目的と義務と責任を負うためのみ、の意思で続いている。
ピラミッド地区場内で撮った写真に彼の姿も何枚かあったが、彼はいつも顔を伏せていたかそっぽを向いていた。敬虔なイスラム教徒なのかも知れないが、写真によって彼と私たちに置かれた距離がはっきりしていたように思う。

視界からピラミッドが消えかかる頃、先頭の馬が左に道をとった。
--いよいよか--
村の中へ入っていくのだ。
ロッキー・ホラー・ショーの始まり、 始まり・・・。
通り過ぎて行く家々の窓からは明かりが洩れてこず、死者の町を思わせた。
ピラミッド大通りのきらびやかなネオンや、溢れんばかりの車や人の流れからは想像もつかないが、村へ少し奥に入るだけで世界は違っていた。
その昔、この村は、古く言い伝えだけであるかどうか定かでないファラオの財宝目当てにやって来た盗掘者たちが築いていった、ということは後に知る――。
この村の住民たちは、盗賊の末裔ということになる。
その時知っていれば、私はまたまた豊かな絵空物語を描いたに違いない。
小さな広場にでた。
カスバやメディナのような迷路状の村や町には何箇所かこうした広場がある。
迷路のような造りになっているのは敵の進入を最小限に迎えるためでもあり、またこうした広場は進入者を撃墜するための場でもある。平時は市場が立ったり、住民のコミュニティの場になったりする。この広場は恰好の遊び場でもあり、夕げ前に子供たちが剥き出しの皮のままのボールを素足で蹴りあいっこしていた。
私はホテルからここまでの道程を必死で頭の中で地図に描いていた。
「ヘンデルとグレーテル」の心境だったのだ。
しかし、それはむなしいことだと思い知らされる----。
この広場でモーセスは馬から降りるよう合図した。
そして、待ちかねられないように、
「急ごう、友よ」と、路地に佇む村人をすり抜け、走りだした。
「どうなるんでしょうか?」平静さを装う私の問いに妻は、無垢で力強く、
「これは楽しみ、楽しみ。最後まで楽しいぞ」と呼応した。聞いた私がバカだっ
た。
馬まで用意して周到で丁重なもてなしなのか、生贄である私にはさっぱりわからなかったが、妻は素直に続き、もう慣れたものでその後を私、そして子分が後塵を拝した。
ようやく広場で、村に人がいることと、無謬の湖畔で小石を投げて、スコーンと湖水に音がしたように安堵した。
私たちのアリバイは彼らが請け負うのだ、などとまたいつもの癖で後ろ向きな想像に戯れていた。
しかし、すぐに不安の波が容赦なく襲ってくる。
次々と角を曲がるモーセスの姿が消える度に----。
そして、そのうち後ろの気配がなく土埃にむせる中をゆっくり振りかえると、子分の姿がなかった。
一挙に4人と4頭から1人と4頭が消えたのだ。
-そしてだれも・・。-
私は覚悟を決めてモーセスの背中と妻の背中をそれぞれ違う思いで見つめたまま続いた。

暗闇と砂塵に包まれ、男の背を頼りにギザの旧市街地であるナズラット・サマーン村の一角を這いずりまわっている。
古めかしい住宅がひしめきあっているこの村の構造は、蟻の巣を思わせた。
角を何度曲がったか、もう数えるのはやめてしまった。袋小路は全く人の気配がない。
もう迷路に迷い込んでいたのだ。インシャアッラー(神のみぞ知る)。
私たちを先導するモーセスの後ろを、今朝と同じく遣る瀬無く、付いて行ってい
る。
この夜と2度までも、心あらず彼の「案内」を受けることになったのだ。
今朝の彼の私たちに対する言動を思うと、不安と混乱で心臓が波うつような状態だったが、ある角をまがった時、心臓音は聞こえてくる音に呼応するかのように、変調した。

いきなり、聞き覚えのある音が耳に飛び込んできたのだ。
漆黒の闇とそこらじゅうに充満している不安な空気から開放された珠玉の一瞬と、それから延々と続く幸福な時間と空間を取り巻く人々との共有を忘れることはなか
ろう。
聞いたことのあるラッパと太鼓の音が近づいてくる。
「最初の時とおなじだねー」
音楽が聞こえた始めた角を曲がり、妻はすぐに私に振り返って嬉しそうに叫んだ。そう、彼女もすぐに気づいたのだ、あの時と同じ音楽が流れ出していること

あの時とは、----私たちが記念すべきエジプトの第一歩をへリオポリス国際空港で踏み、「サラーム・アレイッコム」と私が挨拶したことに目を丸くして驚いてみせた柔和な入国審査を手伝ってもらった現地係員からホテルへの送迎者に引き継がれ、箱バンタクシーでカイロに入り、第3次中東戦争での電撃的勝利を収めた記念として、その勝利の日である「10月6日橋」と名付けられた橋をなんと10月6日に渡り、最初の宿 にしていたナイル川の小島であるゲジラ島シェラトンでのロビー横のホールで鳴り響いていた音楽と-同じ-だったのだ-----。
あの時と同じということは、この音楽が何を意味するのかもすでに心得ていた。
妻の言う最初の時と同じとは、そういう意味をも含んでいたのかもしれない。
私たちが駆け足でモーセスを追う一歩、一歩、聞いたことのあるラッパと太鼓の音が手招きするように近づいてくる。しかし、まだ不安な葛藤が勝っていた。
妻ははずみ、踊る心でもう一度角を左に曲がった。恐る恐る私も続いた。
すると、これまでゴーストタウンのように鳴りを潜めていたナズラットサマーン村が嘘のように、というより村中の老若男女が寄り集ったかのような凄い人込みと熱気の中へ竜巻に吸い込まれるがごとくに(なんとも、大仰だけど)、飲み込まれていった。
モーセスが私たちを手招きして人込みをかき分けて進んで行く。
過ぎ行く私たちへ投げかけられる視線はどこか安らぎとやさしさに満ち溢れている気がするのは、私のいつもの「悪い癖」で、それこそ気のせいだったのかもしれない。
「気分」の忙しい人なのだ。
凄い人の数で狭い路地はなおさら通行困難だったが、心は酔っており苦痛ではなかった。
数10メートル行き、今日の日のために装飾された馬車の上に乗った本日の主役のご両人とご対面と相成った。ご両人のうち一人は着せ替え人形のようなドレス姿。
そう、「あの時の音楽」とは結婚式の楽団の演奏だったのだ。ホテルのホールと同じく、思いもかけず遭遇できた披露宴をこうして再び間近にしているのだ。
モーセスは私たちを「ダンスパーティー」、すなわち結婚披露宴に招待していたことだ と、万難を拝しようやく安堵した。
「ハリーの災難」ではなく「雨に唄えば」だ!
モーセスは二人と二人を対面さし、私たちを何やら紹介している。
「サラーム、アレイッコム(あなたに平和を)」と私が強張った笑顔を投げかけ
る。
「ワアレイコムッサラーム(あなたにも平和を)」と、あのマイクタイソンをホンワカ温和にしたような顔の新郎は映画の役柄に例えると(そればっかり!)「アン
タッチャブル」のチョイ役だが、照れ笑いと消え入るような心もとない声で挨拶し返してきた。
事実、喧騒でその男の声は生かけの髭をした威風堂々たる容貌とは正反対にものの見事に書き消されていたのだが、私にとってこの一週間何度も交わしてきた数少ない知りうる現地言葉であるこの挨拶の言葉を、この時ほど真実味を実感したことはない。
-あなたに平和を-こんにちはと同じ意味である日常の挨拶は、まさにこの時のためにあるようなものだった。
「ゲーム」は終わった。フェスタが始まろうとしているのだ。
妻はというと、ここがギザであるとはいえ観光コースから外れていることからか、いや一生のうち最初で最後に目の当たりにする「東洋人」といった風情で、小さな愛くるしい女の子たちに取り囲まれ、矢つぎばやに自己紹介やら質問を浴びせら
れ、瞬く間にその人数は増していった。
美しい―――というものはいつのどの世界でも、得するようにできている。
その中でも、皆より少し背が高く、皆より少し年長で、少しおませで、おめかししているなかでも皆より少しお洒落で、そしてとびっきり美しいシャイマーと名乗る女の子に独占しようという彼女の思惑と他の女の子たちのせめぎ合いの渦中にいて戸惑っていた。
やがて独占権を得たシャイマーに手を取られて人込みへ消えて行こうとしている。
興奮さめやらぬ一時、空を見上げると幾層にも建て増しされた住宅の窓という窓にも通りを彩る花のように人の顔が覗いていた、というよりカラスが出窓に留まっている。
黒いスカーフを被った老婆たちが、アラブ独特の喉を裏返して発するようなかん高い声を出しているのだ。
アリア「魔笛」を歌うマリアカラースも真っ青だろう、というよりカラスも逃げ出す。
時が止まったような夢心地の、あの角を曲がった時から今まではほんの数分だった。
馬車は私たちを待っていたかのようにゆっくりと動きだした。
いや、待っていたのだ、私たちを・・・。とても贅沢な時間が流れている・・・。
アズ・タイム・ゴーズ・バイ。酒場でリックが愛しのバーグマンに再会した気分だ。
私たちは、黄色い合羽のような衣裳で統一した楽団に先導されながら進む馬車の後ろを祝福する人々の一員として付いて行っている。
モーセスはとても罪つくりな人だ。今日一日私はいろんな心境を味わうことができたが、何もかもが濃縮され、今宵の星葛とともに流されていった。とことん勝手なアタシ。
彼の言った「ファミリー」とは地縁的団結力の強いエジプトではごく当たり前のように口にする「他人」かもしれないし、また本当に血縁関係にあるのかもしれない。
しかし、その程度の英語力しか彼と私たちはお互いに持ち合わせていなかったの
だ。
それと、私の読解力以上に乏しい想像力はお粗末なものだった。
ナイル川はいつもやさしくキララとした光を反射させながらたゆたっているではないか!
馬車は私たちが来た道を引き返すようにして、音が聞こえてきて駈けだした角を真っ直ぐ進む方向へ進んだ。馬車が進むと列も進み人はいつの間にか増していく。
行列の面々は悪く言えば魑魅魍魎、良く言っても奇奇怪怪、 私らもその一員だ。
幼子たちも母親に抱えられて今宵の祝宴に参加するのか眠りも忘れさせられてい
る。
大人という大人が参加しているようなので、子供たちも今晩は無礼講であると心得ているのだろう。明らかに行列のスピードとは違う速度で跳ねている。
なかでもシャイマーは目立つ娘だ。ジーン・セバークみたいに子猫のように無邪気で、シャロン・ストーンみたいに猫のように気ままで妖しい。
いつの間にか、彼女は妻から離れて本日の真の主役である二人が乗った馬車の上にいた。
二人の間に割り込むようにして得意げに周囲を見渡しているその姿はオリーブの香りを運ぶアテネの女神のようでもあり、神秘と悲劇の古代エジプトの女王ネフェルティティの姿にも映った。お姫様を彷彿させる色気と仕種を彼女はまだ10才にも満たないであろう年齢で持ち合わせているのに少し不気味な気さえする。
「シュワイヤ、シュワイヤ(ゆっくり、ゆっくり)」と、楽団の先導役の腹の出た派手なシャツを着た男が叫ぶ。誰かが大声で叫び返す。あちこちで怒声が飛ぶ。
もったいぶったように進む行列は通りが広まると、 ピタリと止まり、 楽団が奏でる音楽が激しくなり、 人々が踊りだした。
いつかみたことのあるようなこの光景は、もう10年にもなろうとしている昔、はじめてのヨーロッパの旅で熱狂風に吹かされた陽光きらめくイタリアの水の都市ベネチアでの謝肉祭の前夜祭の夜であると思い巡した。
© Rakuten Group, Inc.