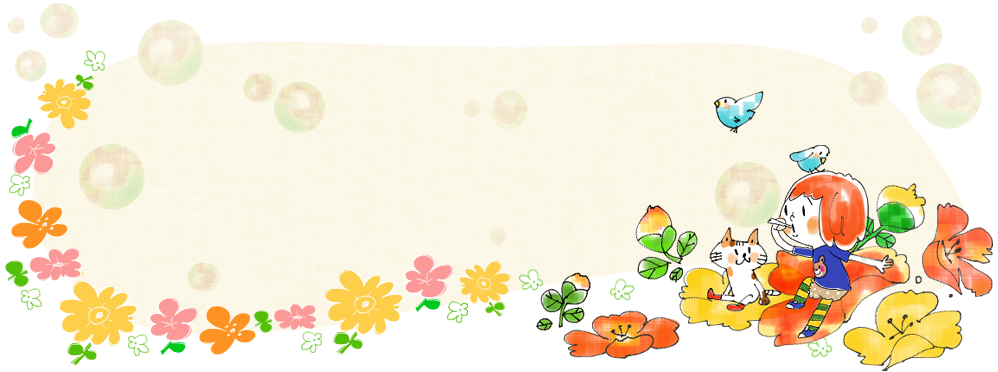5月19日(日)
近藤芳美「土屋文明」より(72)
岩波書店近藤芳美集第七巻「土屋文明 … 鑑賞篇」よりの転載です。
第八歌集『山下水(やましたみず)』より(4)
北支那より帰りし君を伴へど雪の下には採(つ)むべきもなく
(昭和二十一年)
北支から帰還して来た一人の青年が突然に雪に閉ざされた疎開地をたずねて来る。敗戦とともに幾百万の前線の兵らは、あるいは追われ、あるいは捕えられ、屈辱と困苦の日を重ねながらかろうじて祖国に帰りついていたのだった。その祖国さえすでに廃墟であり、人々は飢餓の中にさまよい生きていた。渓谷の奥の疎開地まで会いに来ることさえ容易ではない時代だったのである。
たずねて来た青年をともなって彼は山に登る。青年は汚れた軍服を着、長い戦場の苦労に頬もこけている。生死さえ本当はわからなかったのだ。山はまだ雪が深い。雪のため採もうとする山菜もない。
戦死した青年らの消息もしだいに伝えられて来る。「君をも還らぬ数にかぞへむか二三日こらへ遂にかなしぶ」「亡き数にかぞへむとする面影の逞しくして吾に堪へずも」などという歌も、同じころに作られている。
蟹ひとつ形のままに死にたるも沈みて春の泉は増しつ
(昭和二十一年)
疎開地の峡村にもおそい春が訪れて来る。「石の間にめぐる泉に朝ごとに目にたつ緑来りつつ踏む」 … 草の緑の色がしだいに深くなるころ、緑にかこまれた山の泉の水もしだいに増して行く。その清澄な水の底に、蟹が一匹、生きた時のままの形で死んでいるのも透いて見えている。春のめぐって来たよろこびをしみじみと知る季節である。
するどい把握の眼と、それにともなう細緻な言語の斡旋を感じさせる、清潔な作品である。文明の歌が前歌集『韮菁集』以後、再び技法の巧みさを加えて来ている。
「掬ひ飲む泉からだに染(し)みとほる健やかなればそれのみたのし」「目の下に釣橋ひとつ見え居りてただ世の中につながりをもつ」「一ところ白くかがやく枯草を韮野生地と気づくよろこび」「青き時青きよろこび黄なる時黄にしたしみてこの畦を行く」などの作品が「泉頭?」という題で並んでいる。
(つづく)
-
近藤芳美『短歌と人生」語録』 (28)… 2024.06.20
-
歌集「未知の時間」(前田鐵江第一歌集)… 2024.06.20
-
近藤芳美「土屋文明:土屋文明論」より 2024.06.20