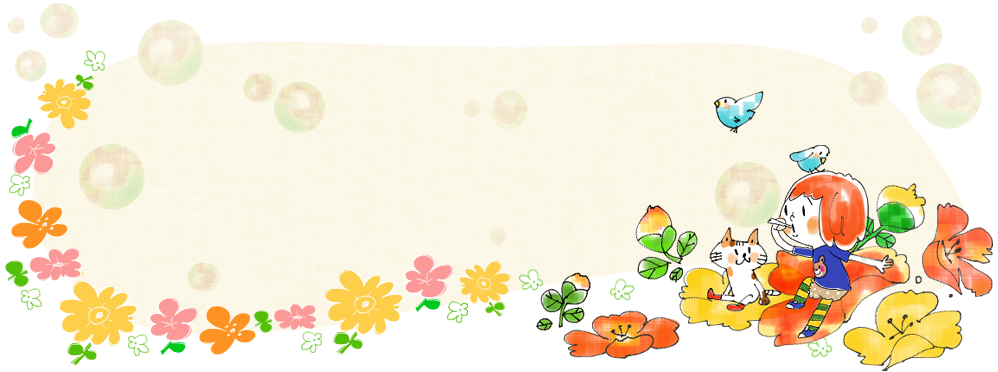5月26日(日)
近藤芳美「土屋文明」より(79)
岩波書店近藤芳美集第七巻「土屋文明 … 鑑賞篇」よりの転載です。
第九歌集『自流泉(じりゅうせん)』より(3)
潮を煮る小屋掛も多く捨てられぬ集めし薪乾く午(ひる)ごろ
(昭和二十二年)
「土佐雑詠」と題されている。二十二年の秋、土屋文明は高知県に旅行した。そのときの作品であり、高知から室戸崎にむかう途中の土佐湾の情景によって作られたものなのであろう。海岸のなぎさには潮を煮る小屋掛けがいたるところ朽ち傾いて残っている。戦争末期から戦後にかけて、そのようにして塩を得ようとした貧しい営みのあとである。平明な叙景歌であるが、作者が歌おうとしているのは単なる風景だけではない筈である。荒涼とした世界にむかう寂寥感が、沈んだことばでうたわれている。
「敗戦の話はここもあはれにて盗みて逃げし隊長にくむ」「若き兵死地にむけたる士官一人土橋にかくれ生き居りし話」などの歌も同時に作られている。日本のどこに行っても、敗戦の悲しみはまだなまなまとした現実として生きていたのであろう。そのような日を背景にした作品として味解すべき一首である。
朝(あした)来て夕べ又来る泉の上月のあたりは白きうす雲
(昭和二十二年)
朝来た泉のそばに、夕方またたずねて来る。峡の空にいつか出ている月に、白いうすぐもが静かにひろがっている … 疎開生活も足掛け四年に入る。「疎開人かへりつくしし春にして泉の芹を我独占す」などと歌われているように、狭い谷の村に幾人か住んでいた疎開者らも、いつか次々に立ち去り、残るのは自分たちだけになっている。「食ふなき韮を惜しみて分たざる村人を憎まむかはた肯ふべきか」と歌うように、今の生活が必ずしも満足なものではない。しかし、東京に帰るべきあてもない。そうした感慨が静かな述懐として歌われた作品である。どこといって目立ったところのない歌であるが、その表現技法に行きとどいた配慮がなされているのは他の場合と同様である。「おそれつつ冬すぎにきと登り立つ楚(しもと)光りてつばらなる芽ら」などの地味な秀歌がこの前後には多い。
(つづく)
-
近藤芳美『短歌と人生」語録』 (31)… 2024.06.23
-
歌集「未知の時間」(前田鐵江第一歌集)… 2024.06.23
-
近藤芳美「土屋文明:土屋文明論」より 2024.06.23