2024年10月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
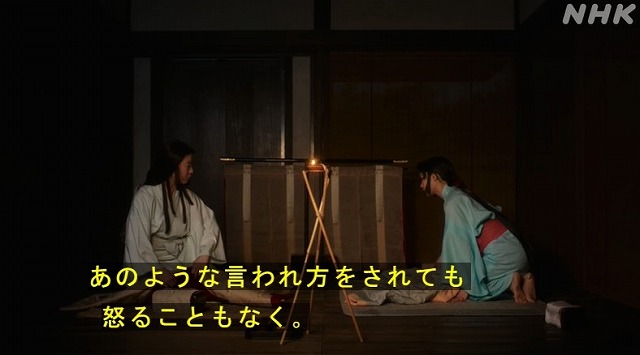
大河ドラマ『光る君へ』第41回~「揺らぎ」
2024年NHK大河ドラマ 『光る君へ』 の感想です。この回で全体を通して思ったのは、自分の思い描く世をつくるためにいかにして政治的な力を持つか、あるいは相手にそうさせないためにいかにして周囲を固めるか、ということでした。中宮・藤原彰子(見上愛さん)は父で左大臣の藤原道長(柄本佑さん)に対抗するために、実弟と義弟たちとのつながりをつくりました。でも力争いが強烈なのは、やはり男の世界でした。道長・嫡男の藤原頼通(渡邊圭祐さん)と、妾の次男の藤原顕信(百瀬朔さん)では扱いが違い、顕信はそれが不満で仕方ありませんでした。実際にどれだけの差になるのか、私にはちょっと実感がわきませんが、こういったことにも育った環境や本人の気質が大きく関係すると思ってます。嫡妻・倫子の嫡男として育った頼通は気持ちにも余裕があるのか、父・道長の言葉を素直に受け止めました。逆に顕信は、母の明子が妾としての劣等感が強い人で、他者から見下されないよう常に高い場所にいることを意識し、それが次男のほうに強く伝わったのでしょう。顕信には「今は我慢」ができませんでした。ここで思い出したのが、玉置玲央さんが演じた道長の実兄の藤原道兼でした。父・藤原兼家(段田安則さん)の愛を求め、家のために最後まで損な役割を引き受けていました。自分が妾腹とかならまだどこかで気持ちに折り合いがついたかもしれませんが、実の兄弟のために汚れ役を引き受けていました。でもやはり、最後は本人の気質でしょうか。道長の義兄の藤原道綱(上地雄輔さん)なら、母親は出世を強く望んでいたけど、道綱自身は「そこそこの地位でいいよ~。」って感じですから。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #光る君へ 寛弘8年(1011)、藤原賢子(南沙良さん)が町に行った時に盗人に襲われ危うくなった時に、そこを通りがかった双寿丸が賢子を助けてくれました。賢子は家まで送ってくれた礼にと双寿丸に食事を振る舞い、その時まひろ(藤式部;吉高由里子さん)が宿下がりをして帰ってきました。双寿丸が賢子にいささか失礼な物言いをしても賢子が、怒らないどころか笑っているのを見たまひろは、賢子の中に実の父である左大臣・道長を見ていました。(賢子は道長の気質を受け継いだかもしれないけど、でもこの場合は賢子は双寿丸に対して瞬間的に好意を抱いてしまったから、が大きいでしょうね。)一条天皇が崩御し、即位した三条天皇(帝)は内裏遷御という大事な役目をなぜか藤原公任(町田啓太さん)にふり、公任はもちろん帝の命を受けたのですが後から藤原道長(柄本佑さん)にやっかいだとか愚痴を言っていました。しかし人目がなくなると公任は、帝は自分たち(左大臣・道長と公任ら四納言)の結束を乱そうとしている、と考えを道長に伝えました。そこまでは考えが及んでなかった道長は、態度こそ淡々としていましたが、公任の忠言をしっかりと意識に留めていました。それから帝は自分の側近にと、道長の義兄(藤原道綱)、甥(亡き兄・道隆の子、藤原隆家)、そして道長・次男の藤原教通を選びました。道長・嫡男の藤原頼通(渡邊圭祐さん)は、なぜ自分ではなく弟がと納得がいかず、父に意見を求めました。道長は頼通に「帝に取り込まれなかったことをむしろ喜べ。お前が先頭に立つのは東宮(頼通の姉・彰子の子)が帝になる時だ。」と言って去っていき、父の言葉に頼通は何かを感じたようでした。一方、道長の妾の源明子(瀧内公美さん)にも2人の男子がいて、その出世が明子は常に気になっていました。道長に忠誠を誓う明子の兄の源俊賢は、道長のためにもなんとか自分が帝の心をつかんでみせると意気込み、道長も俊賢を頼りに思っていました。そして明子の2人の男子の藤原頼宗(上村海成さん)と藤原顕信(百瀬朔さん)が父・道長に挨拶にきました。自分たちも早く公卿の仲間入りをしたくてたまらない弟の顕信は、自分たちと歳がさほど変わらない頼通(道長の嫡妻・源倫子の長男)がすでに正二位の権中納言であることを引き合いにだし、兄と自分の出世を父に訊ねました。道長が「こういうことは帝のお心一つだ。いま少し待て。」と言っても顕信が食い下がるので兄の頼宗がたしなめましたが、顕信は不満そうでした。帝(三条天皇)は亡き一条天皇の四十九日にあたる8月11日に内裏に入り、公卿たちの挨拶を受けた後で道長だけを呼び、自分の関白になるよう求めました。道長には考えるところがあって関白になる話は丁重に断りました。すると帝は、ならば(自分が長年連れ添っていた更衣?の)娍子を女御とすると言い、道長は反対しましたが帝に押しきられてしまいました。いろいろと疲れた道長はふらりとまひろのところにやってきました。まひろはこの機会に、なぜ道理を飛び越えて敦康親王ではなく敦成親王を東宮にしたのか、より強い力を持とうとしたのかを、道長に訊ねました。道長は「お前との約束を果たすためだ。」と静かに言いました。「やり方が強引だったことはわかっている。でも俺は常にお前との約束を胸に生きてきた。そのことはお前にだけは伝わっていると思っておる。」と。そして「中宮(自分の娘・彰子)を支えてやってくれ。」と言って、まひろのところから去っていきました。秋も深まった頃、中宮・彰子のいる藤壺ではごく内輪の者だけが集まり歌の会が開かれていました。その折にききょう(清少納言;ファーストサマーウイカさん)が敦康親王の使いとして来て、彰子は中に入るのを許しました。しかしききょうは女房たちが喪に服していないのを見て怪訝な顔をし、彰子にはやたら亡き一条帝と定子と敦康のつながりを強調し、彰子が敦康の様子を訪ねると、それを彰子がもう敦康を忘れたことだと解釈しました。彰子が敦康のことで、どんな思いで父・道長に対峙したかを知らないききょうは、最後まで彰子に対してきつい嫌味な口調で物を言いました。言い返すすべを知らない彰子は、ききょうの言葉に黙って耐え、御簾の向こうでただ一人、涙を浮かべていました。(彰子が短気で気性が怖い人だったら、ききょうは後で無礼者として処罰されたのではないでしょうか。)後日、彰子はつばき餅の礼をしたためた文を敦康親王に送り、文にはいつでも藤壺に来てよいとあったので、敦康はすぐ彰子のところに駆けつけました。ただ以前と違って元服した敦康は御簾の内には入れず、それが物足りない敦康は我慢できずに勝手に御簾を上げて彰子の傍に行ってしまいました。彰子だけでなくお付きの者たちは皆、一瞬「源氏の物語」の光る君のことが頭をよぎりましたが、敦康はそのようなことはしないと言って、それからは二人で他愛ない話をして昔のように時を過ごしました。藤原行成(渡辺大知さん)が事の次第を左大臣・道長に報告すると、万一の事を危惧する道長は敦康を二度と内裏に上がれぬようにせよと行成に命じました。ただそのやり方は、行成から見たら敦康があまりにも可哀そうであり、行成はたまらず道長は敦康から多くのことを奪い過ぎだと進言しました。さらに道長の若い頃からずっと傍にいて道長をずっと見てきた行成だからこそ、(今の)道長はおかしいと進言し、行成は退室していきました。ある時、賢子が乙丸を供にして町を歩いていたら武者の集団と出あい、その中に双寿丸(伊藤健太郎さん)もいました。賢子が少しだけ話をしたら、双寿丸は主人・平為賢に従って盗賊を捕まえに行くところで、内心は双寿丸に惹かれる賢子は双寿丸を夕餉に誘いました。仕事が終わったら双寿丸は本当に賢子の家に来て、そうしたらちょうどまひろも宿下がりをして帰ってきたので、母娘と双寿丸で一緒に夕餉をとりました。双寿丸は自分の名前しか書けなくて字も読めないけど、武者であることに誇りを持っていて、仕える主人を慕い尊敬しているようでした。賢子は双寿丸が身振り手振りを交えて話すことを目が輝かせて聞き、いくらでも食事が進む双寿丸のご飯がなくなると自分の分を差し出していました。そして、そんな娘・賢子の様子をまひろは優しく見守っていました。敦康のことで左大臣の父から苦情を受け、この先も父の言いなりにはなりたくないと悲しむ中宮・藤原彰子(見上愛さん)にまひろは、彰子には弟たちがたくさんいるから彼らと連携してはどうか、と進言しました。彰子は早速、実弟の藤原頼通と藤原教通(姫小松柾さん)と父の妾・明子の子の頼宗と顕信を呼びました。彰子は弟たちに、皆が困ったときは自分ができるだけ力になるから、皆も東宮・敦成のために力を貸して欲しいと語りました。そして「我らは父上(道長)の子であるが、父上を諫めることができるのは我らしかいない。父上のより良き政のためにも、皆で手を携えよう。」と呼びかけ、弟たちも快諾しました。その後、彰子は藤壺から枇杷殿に移り、藤壺には三条天皇の女御の妍子(彰子の妹)が入りました。左大臣・道長の次女の藤原妍子(倉沢杏菜さん)は入内したものの、歳の離れた帝(三条天皇)との生活をつまらなく思っていました。そして夫である帝よりも歳が同じ帝の第一皇子の敦明親王(阿佐辰美さん)との時間が楽しくて、時には敦明を挑発してからかって遊んでいました。しかしこの時はさすがにやり過ぎで、その場に現れた敦明の母の藤原娍子(朝倉あきさん)に制止されました。同じ帝の女御という立場であっても、左大臣を父にもつ妍子は後盾の弱い娍子に対して強気でした。娍子は息子の敦明は悪くないとわかっていても妍子に詫びを入れ、この件を帝の耳に入れて大事にせぬよう懇願していました。また妍子も、娍子との力関係を当然のように考え、反省などありませんでした。(帝に煩わしい思いをさせぬよう常に自分が下がる、娍子のこの賢さと謙虚さがあるから、帝はより娍子が愛おしく思えるのでしょうね。)一方、帝は着々と自分の側近を固めていき、蔵人頭としてまだ日が浅い娍子の弟の藤原通任を参議に取り立てました。そして一つ空いた蔵人頭の地位に、道長の妾・明子の次男の顕信を入れると言いましたが、道長はそれを辞退しました。道長は家全体のことを考えての判断だったのですが、早く出世したかった顕信は、父が蔵人頭のことを断ったと知って深く悲しみ、また自分の息子たちを早く出世させたい母親の明子も、道長の判断に強い怒りと不満を抱きました。程なくして比叡山の僧の慶命が火急の用だと道長を訪れました。慶命によると顕信が出家したとのことで、それを聞いた明子は道長が(政治的に)顕信を殺したと激しく怒り、道長につかみかかって抗議していました。
October 30, 2024
-

大河ドラマ『光る君へ』第40回~「君を置きて」
2024年NHK大河ドラマ 『光る君へ』 の感想です。今回私が興味深く見ていた2つの箇所。それは次の東宮を決めるにあたり帝(一条天皇;塩野瑛久さん)を説得する藤原行成(渡辺大知さん)と、この東宮を決める問題で父で左大臣の藤原道長(柄本佑さん)と対峙する中宮・彰子(見上愛さん)でした。行成の説得の仕方は、説得の見本のようなものでした。相手の主張を一旦は認め、素晴らしい、感動した等の賞賛も入れて受け入れる。でもその後で、じわじわと自分の主張をしていきます。その展開も、過去の天皇の例をあげてこういった事もあったと言い、そうなった理由もつける。「これは天の定めであり、人知が及ばない。」とこうなるのは運命だったと、神がかりなものを相手に思いこませ、そして力関係という現実をつきつける。これはもう、理性的だけど病で気が弱っている帝にはこれでいける!と行成が考えたのでしょう。あるいは行成がとにかく必死で思いついた展開なのか。(逆に、元気で感情的にブチ切れる帝だったら行成も違う作戦を考えたかもしれないので)でも根本は、結局は行成はなんだかんだ言っても道長のことが好きで、道長のために働きたい思いがあるから、知恵がめぐりエネルギーが湧いてくるのでしょうね。そして次の東宮の問題で父・道長と対峙した中宮・彰子。入内前は弟の頼通からは「姉上はぼんやり」と言われ、入内してからも自分はどうあるべきかわからず、帝にも全然振り向いてもらえず、いつも伏目がちでした。それが亡き定子が遺した敦康の小さな愛を得て、やっぱり帝の愛を得ようと突然全身でぶつかっていき、敦康の事も含めて帝の信頼と愛を得て、自信が持てて強くなりました。でもやはりと言うか、今回の父との対峙によって、彰子は愛とは違った形で強くなったように思えます。試練は人を強くするのですね。こちらは、RekiShock(レキショック)先生の情報です。一条天皇が亡くなった頃(1011年6月頃)登場人物の年齢(満年齢) ⇒ ⇒ こちら こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #光る君へ 寛弘8年(1011)中宮・彰子の藤壺に帝(一条天皇)も渡り、まひろ(藤式部;吉高由里子さん)が書く「源氏の物語」を皆で鑑賞していました。それぞれが思うところの感想を述べ合っていると、彰子に育ての親以上の思いを抱く敦康親王(帝の第一皇子;片岡千之助さん)が物語の光る君と自分をまるで重ね合わせるような感想を述べました。それを聞いた左大臣・藤原道長(柄本佑さん)は、娘でもある中宮と敦康が万一面倒なことになったら困ると危惧し、敦康の気持ちが冷めるような感想を述べるのですが、その時に「不実の罪」という言葉を使いました。道長は実は自分も該当者なのに他人事のように言い、また密かに該当者でもあるまひろは思いがけない発言に戸惑いを隠せませんでした。その場にいる者の何人かは実は身に覚えのあるからなのか、皆が急に神妙になってしまって話が途切れてしまいました。でもその時、あかね(和泉式部;泉里香さん)が笑いながら軽く「罪のない恋などつまらない。」と言い、それを受けて赤染衛門(凰稀かなめさん)も「まことに。」笑って返しました。さらに衛門は「人は道険しき恋にこそ燃える。」と話をつなげ、女房たちも笑い、場の空気が明るく収まりました。(ここでこの発言が出るあかね様、衛門様、さすがです!)帝(一条天皇;塩野瑛久さん)が藤壺に渡ってきたある夜、中宮・藤原彰子(見上愛さん)はふと気になっていることを訊ねました。帝はなぜ冬の寒い日も、暖かい物を羽織ったり火取りを使ったりしないのかと。すると帝は「苦しい思いをしている民の心に近づくためだ。民の心を鏡とせねば上には立てぬ。」と言い、彰子は帝は太宗皇帝と同じ名君だと返しました。彰子の言葉を聞いた帝は、彰子が新楽府を読んでいることに気がつきました。帝は彰子がどこまでも自分に沿おうとしてくれていることを愛しく思いました。しかしその後で帝の体調が急変し、自分が傍にいながら今まで帝の体調の変化に気がつかなかった事を彰子は悔み、そして帝の事が心配でたまりませんでした。帝の病状は国の政に関わることなので、道長は大江匡衡(谷口賢志さん)を呼び、帝とこの先のことを占わせました。占いを終えた匡衡は言いにくそうに、それでも言葉を選びながら「世が変わる。崩御の卦が出ている。この卦は醍醐天皇と村上天皇の時と同じ。さらに今年は三合(=大凶)の厄年なので帝の病の平癒はならない。」と答えました。このやりとりを帝は物陰から密かに聞いていて、何かを決意したようでした。道長は公卿たちを集め、帝の譲位に備えることを提案しました。道長の話から帝の病状は重いのだと皆は悟りましたが、藤原実資は帝はまだ若い(回復するかもしれない)のに譲位に備えるとは何事か!と憤りました。道長は自分の政権を支えてくれる藤原公任(町田啓太さん)らを呼びました。4人は現・帝の譲位に際し、道長が自分の孫である敦成親王(娘・彰子の子)を次の東宮にしたい事を、暗にわかっていました。藤原行成(渡辺大知さん)は、次の東宮は帝の第一皇子の敦康親王(亡き中宮・定子の子)であるべきと意見しますが、道長を強く支持する源俊賢(妹・明子が道長の妾;本田大輔さん)は敦康の後見の隆家の家の者はかつては罪人と反論、それでも行成はあまり強引なことはしない方がいいと考えます。藤原斉信(金田哲さん)は、この話を聞いた以上は自分は道長の意に沿うと言い、公任は実資と隆家は自分たちが説得すると協力を申し出ました。そして斉信は行成に(考えが違うのに)無理をするな、自分たちに任せておけと言ってあげてました。道長の話から帝が近いうちに譲位し、いよいよ時代が次に動く事を知った4人は、これから自分たちがやるべき役割をそれぞれが意識していました。ただ道長は「易筮では帝が政務に戻ることはないと出た」としか言わないようにしていたのに、公任はつい「崩御」という言葉を出してしまいました。道長が言霊をはばかってそれを言わなかったのにと公任は行成にたしなめられていましたが、俊賢は「崩御なら一気に話は進む。」と決意を新たにしていました。帝は現・東宮の居貞親王に譲位することを決意しました。心安らかに譲位するためにも、あとは次の東宮を決めておくことだけで、帝は自分の第一皇子であり亡き定子が遺した敦康を東宮にするつもりでした。帝は行成を呼んで自分の意向を左大臣・道長に伝えるよう頼み、行成も最初は敦康を慈しむ帝の強い気持ちに感じ入ったと返答しました。しかしそれからは行成は、清和天皇を例にあげ、さらに道長が重臣にして敦成親王の外戚であり、敦成親王が東宮になるしか道はないと強く訴えました。「天の定めは人知の及ばぬもの。」ーーそして敦康が東宮になることは道長が承知しない(敦康は後盾が弱い)と、敦康と敦成のことは天の力と現世での力によるものだと、行成は「何とぞ」と帝を説得しました。敦康が東宮になっても守る力が弱い現実を悟った帝は、一言「わかった。」と力なく行成に返答しました。帝が敦成を東宮にすることを認めたと確信した行成はすぐさま道長のところに行って「敦成様を東宮にと帝が仰せになった。」と報告しました。道長は安堵し、最初は「敦康が東宮」と反対していたのに、結局は帝の説得という一番難しい仕事をしてくれた行成に深く感謝しました。道長は「行成あっての自分だ。」と思いを伝え、このことの報告に娘の彰子のところに行きました。行成もまた精神力を使い果たしたのか、大きく息を吐いて安堵していました。父・道長から次の東宮が敦康ではなく敦成に決まったと報を受けた中宮・彰子はこの大事を自分に一言も相談なくと怒りを露わにしていました。道長が「これは帝が仰せに。」と言っても彰子は信じず、病で弱っている帝を父が追い詰めたのだと見抜いていました。彰子は幼くして母を亡くした敦康を心から可愛がっていて、帝の思いに沿って敦康を東宮にすることに何ら異論はありませんでした。父は自分を軽んじている、今から帝の考えを変えてもらうと言って彰子が帝のところに行こうとするのを、道長は力ずくで止めました。「政を行うはであ私り、中宮ではない。」ーー立場としては左大臣の父よりも中宮である自分のほうが上であるけど、これまで幾度も困難を乗り越えてきた父の政治的な実力に、彰子はまだまだ敵うことができませんでした。居貞親王は帝と対面するために清涼殿を訪れ、そして帝から自分は譲位するから践祚せよと命を受けました。居貞親王は言葉では帝を案じつつも、その表情には嬉しさが隠せませんでした。ただ次の東宮を敦成にすると言われた時は、自分の子の敦明でないことに面白くないのが少し顔に出ていました。そして寛弘8年(1011)7月、居貞親王は即位して三条天皇となり敦成親王が東宮となりました。道長は中宮と敦成がいる藤壺に行って祝辞と東宮・敦成への忠誠を誓いました。その道長の言葉に敦成の母である中宮・彰子は、「左大臣、東宮様を力の限りお支えせよ。」と力強く返しました。政治的な力は今はとうてい父・道長には及ばないけど、彰子の言葉には以前のような自信のない弱々しさはありませんでした。三条天皇が即位してから間もなく、病が重くなるばかりの一条天皇はいよいよあの世に旅立とうとしていました。僧たちの読経が続く中(極楽浄土へ行くことを願って)剃髪して出家した一条天皇の傍らには彰子がつき、そして御簾の外には公卿たちが一条天皇の様子を見守っていました。一条天皇は最後の力を振り絞って彰子のほうを向いて手を取りにいき、彰子にしか聞こえないようなか細い声で辞世の句を詠みました。そして力尽きて永遠の眠りにつき、彰子が泣きながら何度も「お上、お上…。」と名を呼ぶ声に、周囲の公卿たちは一条天皇の崩御を悟りました。*一条天皇の辞世の句について石山寺さんが解説をされています。 ⇒ ⇒ こちら露の身の 草の宿りに 君を置きて 塵を出でぬる ことをこそ思へさて藤原賢子(まひろの一人娘;南沙良さん)ですが、町に出て市で買い物をした帰りに盗人の集団に襲われましたが、危ういところをたまたま通りがかった双寿丸(伊藤健太郎さん)に助けられました。双寿丸は怪我をして動けない乙丸を背負い、賢子を家まで送ってくれました。家人のいとは身分の低そうな双寿丸を見るなり双寿丸を怪訝そうな目で見ていて、賢子がお礼にと食事をごちそうしていても、食べたら姫様(賢子)のことはもう忘れてくれといった態度でした。でも賢子は今まで自分の周囲にはいなかった感じの双寿丸との会話が、楽しくてしかたがないようでした。そうこうしていると、まひろが御所から宿下がりをして帰ってきて・・・。(この双寿丸は以前、御所に盗賊が入って女官たちが追いはぎに遭ったときに、逃げる一味の中にいた人ですよね。身分が低く、義賊という点でも、直秀と同じような感じがします。)
October 22, 2024
-

大河ドラマ『光る君へ』第39回~「とだえぬ絆」
2024年NHK大河ドラマ 『光る君へ』 の感想です。この回は、主人公・まひろ(藤式部;吉高由里子さん)の弟・藤原惟規(高杉真宙さん)が突然いなくなることによって、私の中でも予想外の感情が湧いた回でした。惟規は藤原道長(柄本佑さん)の義兄の藤原道綱と同様、特別に優秀とかではないけど、周囲を調和して敵を作らず、柔軟で明るい性格で全体の癒し系になっていました。出番もそれほど多くなく圧倒的な存在感はなかったけど、もういなくなるのかと思うと寂しさを感じるのです。現代のふだんの生活でも、こういう人、いますよね。そして惟規の死を、血のつながったまひろや為時以上に悲しんだのが、乳母のいと(信川清順さん)でした。たしかいとは、生まれて間もない我が子を亡くした時に惟規の乳母になった、と(いう設定だと)思ったし、主の為時が無職で家人を雇えない、とにかく金がなくて貧乏だとか、為時が越後の国司となり4年間は帰れないとか、この家に紆余曲折いろいろあったけど、一緒に苦労をしてこの家を支え、惟規に仕え続けました。だからこそ惟規には特別な思いがあるでしょう。でも、ふとですが、もし惟規が突然の病になった時に彼が都にいたら、もしかしたら薬師が早く来て助かったのではないかと思いました。父に同行して越後に行ったのが運命の分かれ道だったのかもしれないし、どのみち助からない重病だったのかもしれないし、どうなのでしょうか。さて、この藤原惟規というお方。彼の死後も子孫が脈々と続き、かなりの歴史上の有名人にも関わっていく人たちが出てきます。 ↓ ↓ (音声が出ます。ご注意を)こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #光る君へ 寛弘6年(1009)晩秋、中宮・彰子は2人目の皇子を出産、在所の土御門殿では多くの公卿たちが集まり、産養の儀式が行われていました。一方、まひろ(藤式部;吉高由里子さん)の家には彰子の父である左大臣・藤原道長から、正月用の酒と米と菓子の他、まひろの娘の賢子の裳着のために高価な祝いの品が届けられていました。織物のあまりの美しさに目を見張る弟・藤原惟規(高杉真宙さん)の乳母のいと(信川清順さん)ですが、その折に惟規が賢子の実の父が左大臣・道長であると言ってしまいました。(いとが惟規に秘密を漏らしていた)この事を初めて知った父・藤原為時(岸谷五朗さん)は、真実を道長に知らせたほうがいいのではと考えました。でもどうすべきか悩んでいたら賢子が帰ってきたので、話は中断となりました。後日、帝(一条天皇)も臨席する宮中の子の日の宴に、まひろの父・為時も左大臣・藤原道長(柄本佑さん)から呼ばれたのですが、道長が賢子の実の父である事が気になって仕方がない為時は、つい道長のほうを何度も見てしまいました。そして途中から退席したとのことで、まひろは父の無礼を詫びました。道長はもう少しまひろと話がしたかったのですが、まひろは娘の賢子の事をまだ道長には知られたくなかったのか、仕事を理由に退室していきました。ある夜、若い頃から道長と共に過ごしてきて、今では道長の政権を支える公卿の藤原公任(町田啓太さん)と藤原斉信(金田哲さん)と藤原行成(渡辺大知さん)、そして道長の妾・明子の兄である源俊賢(本田大輔さん)が集いました。道長の娘・彰子に皇子が2人できたことで斉信は「道長は盤石だ」と言い、でも公任は順番からすればまだ道長の孫は東宮にはなれないと言いました。でも道長が「自分の目の黒いうちに敦成(上の孫)が帝になる姿が見たい。」とつぶやくと4人は少し考え、まず俊賢が道長に協力を申し出ました。話は変わり、道長と長年対立してきた伊周の病がかなり重いことを公任が言うと、道長はまだそのことを把握してないようでした。道長たちを呪詛したことで内裏から遠ざかっていた藤原伊周(三浦翔平さん)は、それ以降ますます病が重くなり、もう命の灯が消えかかっていました。それでも栄耀栄華を極めることができなかった人生をうわごとでもまだ悔やんでいるそんな兄・伊周に弟の藤原隆家(竜星涼さん)、敦康親王(亡き姉・定子の産んだ皇子)の事は自分に任せて安心して黄泉に旅立つよう言いました。伊周は最後の力を振り絞って嫡男の藤原道雅(福崎那由他さん)を呼び、道長に従わぬよう、そして低い官位なら出家せよと命じ、道雅も了承しました。伊周は亡き父母と妹・定子との輝いていた日々を思い浮かべながら、寛弘7年(1010)小雪の舞う1月末に36年の生涯を閉じました。さて、道長の次女の藤原妍子(倉沢杏菜さん)ですが、間もなく東宮・居貞親王の后になることが決まっているのですが、妍子にとっては気の進まない縁談でした。そこで中宮で姉の藤原彰子(見上愛さん)に、やれ東宮は自分には年寄りだとか、東宮にはすでにこよなく愛する娍子がいるとか、愚痴を言いにやってきました。でも愚痴を姉にたしなめられるだけならまだしも、姉の女房にすぎないまひろが横から説教がましく口をはさむので、妍子は気分を害して退室していきました。(でも、RekiShock(レキショック)先生の情報によれば、妍子の気持ちもわかるなあ。妍子はまだ15歳なのに居貞親王は33歳、姉の夫である一条天皇よりも親王のほうが4歳も年上だからね。伊周が亡くなった頃(1010年1月頃)登場人物の年齢(満年齢) ⇒ こちら )妍子が后となった居貞親王(木村達成さん)の屋敷では、妍子の希望でほぼ毎日、宴が開かれていて、その報告を義兄の藤原道綱から聞いた道長も、妍子の夫の居貞親王もさほど気にしてませんでした。宴のときに居貞親王の嫡男の敦明親王(阿佐辰美さん)が見事に舞って歌うのを妍子は陰ながら見つめていて、妍子は同い年の敦明が気になるようでした。ただその敦明は藤原顕光(宮川一朗太さん)の娘の藤原延子(山田愛奈さん)に婿として迎えられ、妍子は何か思うところがあるようでした。ところで敦康親王(片岡千之助さん)ですが、父帝の一条天皇の願いもあって、間もなく元服を迎えることになりました。敦康は母・定子を亡くした幼い頃より中宮の彰子に育てられていて、元服して大人の仲間入りをすると大好きな彰子に今までのように会えなくなるのでずっと延期してもらっていたのですが、いよいよそうはいかなくなりました。彰子のところに挨拶に来た敦康は思いが募ってつい彰子の手を強く握り返してしまったのですが、その現場を道長に見られてしまいました。道長は敦康に声をかけて元服の内容を伝え、そして親王家別当の行成には敦康の元服後はすぐに竹三条宮に移すよう強く申し伝えました。後日、まひろの実家に内裏よりの使者があり、惟規が従五位下に任じられました。惟規には思いもよらなかった出世で、彼の目にはうっすらと喜びの涙がにじんでいましたが、このことを誰よりも喜んだの惟規の乳母だったいとでした。いとは五位が着用する赤い束帯をすでに用意してあると言います。「いつかこういう日が来ると思ってひそかに用意していました。幼き日より私がお育て申し上げた若様だから。」ーーいとと惟規は涙ながらに抱擁し合い、喜びを分かち合っていました。そしてさらに春の除目で、父・為時が越後守に任じられました。為時と惟規は親子で左大臣・道長に挨拶に行き、ご恩に報ずることを誓いました。挨拶の後で惟規は道長に、世話になっている姉のまひろも末永くよろしくお願いしますと意味有り気な挨拶をし、道長も軽く返事をしました。道長は二人にこの後まひろがいる中宮の在所に寄っていけと言い、二人は道長の厚意に甘えまひろのところに顔を出しました。まひろは父・為時には、越後は越前よりも冬の寒さが厳しいから気をつけるよう言葉を贈りましたが、従五位下にしてもらったばかりなのに今は京にいたくないから父を越後まで送っていくという弟に少し呆れていました。11歳になったまひろの娘の藤原賢子(南沙良さん)は裳着を迎え、裳の腰結は叔父にあたる惟規が行いました。賢子は祖父の為時に、今まで育ててもらった礼をあらためて言い、惟規から越後には同行しないのかと訊ねられると、いとたちとこの家を守ると言いました。儀式の後、まひろと惟規は久しぶりに姉弟で思うまま語り合っていました。惟規は姉の裳着の時は父との仲が険悪だったけど今は全然違うことをしみじみと感じ、姉・まひろと賢子もいずれ仲直りするだろうと言いました。そして左大臣・道長の姉への思いもやはり変わらないと感じていて、この先は皆きっとうまくいく、そんな気がする、と優しい笑顔で言い切りました。父・為時に同行して越後に向かった惟規でしたが、越後が近づいたあたりで突然、体が不調になって猛烈な苦しみに襲われました。惟規は越後の国府に担ぎ込まれ、為時は薬師の到着をひたすら待っていましたが、惟規はもう力尽きようとしていました。己の最期を悟った惟規は父に筆と紙を頼み、息子が何かを書き残したがっていると察した父は起きようとする息子の体を支えました。そして惟規は力を振り絞り、思いを託した辞世の句を書いたら命が尽きました。為時から知らされた惟規とのあまりにも突然な永遠の別れに、家の者たちは皆深い悲しみに打ちひしがれていました。特に我が子同様に、否、我が子以上に愛を注いで若様・惟規を育ててきたいとの悲しみは比べようもないほど深く、声をあげてただ泣くばかりでした。
October 16, 2024
-

大河ドラマ『光る君へ』第38回~「まぶしき闇」
2024年NHK大河ドラマ 『光る君へ』 の感想です。この回では私は、帝(一条天皇;塩野瑛久さん)の現・中宮の藤原彰子(見上愛さん)に対してと、亡き中宮・定子に対しての感情や行動の違いが気になりました。帝は亡き定子に対しては、興味の対象や好みが似ていたこともあってか、あるいは初めての女人だったからか、男として本能的に愛おしく思っていたようでした。一方、現・中宮の彰子には、感性は自分と合うわけではないけど、自分と亡き定子の間の子の敦康親王(渡邉櫂くん)を心から大事にしてくれるし、彰子は一生懸命に自分に合わせてくれるので、妻として理性的に愛おしい存在なのかと感じました。でも定子と彰子のこれまでの人生を考えた時。定子は帝からの愛は十分過ぎるほど受けたけど、幼い頃から父には帝を篭絡せよと言われ、中宮となれば父や兄から「早く皇子を」と何度も言われ、時には声を荒げて怒鳴られることもありました。片や彰子は、中宮となってやはり両親は「早く皇子を」と願っていたけど、二人とも外堀を埋めるがごとく、帝が目を止めるよう彰子の周辺をひたすら整え、娘の彰子に対しても、帝を引き寄せられないことを叱ったり嫌味を言ったりはしませんでした。定子は女人としては幸せだったけど娘としては嫌な思いもしてきて、彰子は優しく寛大な両親で娘としては幸せで、でも女人としては幸せをつかむまでに寂しい思いに耐えた、そんな感じがしました。さて今回は意外なキャラクターが出てきました。宮仕えするまひろ(吉高由里子さん)の上司となる、宮の宣旨の小林きな子さんです。月を見て考えを巡らすまひろに自然に話しかけ、まひろの背景や問題などを、自分の人生経験からなんとなく感じて、嫌味のない包容力で思いをまひろに伝えていました。今回のシーンで、宮の宣旨の上司としての株が爆上げしたように思うのですが、いかがでしょうか。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #光る君へ 寛弘6年(1009)、中宮・彰子の藤壺で「源氏の物語」を書きながら仕えるまひろ(藤式部;吉高由里子さん)の元に、かつては親しく交流したききょう(清少納言;ファーストサマーウイカさん)が突然訪ねてきました。ききょうはまひろの書いた物語や作者のまひろ自身を賞賛したり皮肉をこめた批評をしたりと言いたい放題で、まひろも対応に苦慮していました。ききょうは今、かつて自分が一途に仕えた中宮・定子の遺児である脩子内親王の教育係をしていて、まひろのところに来たのは中宮の彰子が養育している定子の遺児の敦康親王のことが気になっていたからでした。でもききょうの思惑とは反対に、中宮・藤原彰子(見上愛さん)は敦康親王が幼くして藤壺に来たときから心から可愛がっていて、敦康親王もまた彰子を姉とも母とも慕っていたし、彰子が産んだ敦成親王のことも可愛がっていました。しかし敦康はもう11歳になっていて、親王家別当の藤原行成から敦康の元服についての話が彰子になされました。元服すると大人の男の仲間入りとなり、大好きな彰子のいる藤壺に自由に出入りできなくなるため、敦康は嫌がっていました。でも彰子は、やがて帝となる敦康の元服を見たいと敦康をなだめていました。そんな折に、敦成と彰子と左大臣・道長(彰子の父)を呪詛する騒動が起こり、帝(一条天皇;塩野瑛久さん)は心を痛めていました。彰子は帝に、自分は敦成の生母だけど次の東宮は敦康と思っている、心は帝と同じであるときっぱりと言い、帝は彰子を愛おしく思うのでした。先日ききょうに言われた様々な事が心に引っかかっていたまひろは、夜空の月を見上げながら、あれこれと考え事をしていました。そこへ藤壺の女房たちを統率する宮の宣旨(小林きな子さん)が来て、まひろに何を思っていたのかと優しく問いました。さらに何のために藤壺にいるのか、物語を書くためなら里でもできるのにここで書くのは生活のためだと思っていた、と考えを伝えました。宮の宣旨の穏やかな問いに、まひろも正直に父も弟も力がない故と言い、さらに宮の宣旨がまひろに子(賢子)とうまくいっていないのかと言った時、まひろはなぜわかるのかと驚きとともに素直に認めました。宮の宣旨は、自分はまひろのような物語は書けないけど、様々な事を見聞きしてそれなりに世のことを学んできたのだとと言いました。今まで気がつかなかったけど、宮の宣旨は周囲の人をよく見て、それなりに理解している人でした。ところで、敦成親王呪詛の騒動が兄・藤原伊周(三浦翔平さん)の周囲の者たちによって引き起こされ、伊周自身は左大臣・道長の恩情で出仕停止でとどまったものの、一体どういうことなのかと気になった藤原隆家(竜星涼さん)は、急ぎ伊周を訪ねました。今は道長を支持する隆家とは反対に、伊周は人生が思い通りにいかないことで今でも道長を強く恨み続け、密かに本当に呪詛を続けていました。隆家が兄を訪ねた時、伊周は呪いに憑りつかれた顔でまさに道長を呪詛している真っ最中で、隆家は慌てて兄をやめさせました。それでも鬼の形相で呪詛をやめない兄を、隆家は絶望的な気持ちで見ていました。一方、左大臣・藤原道長(柄本佑さん)は、娘の彰子が中宮となって皇子を産んだことにより、この先の自分たちはどうあるべきかを言い聞かせるために、嫡男で皇子の叔父でもある藤原頼通(渡邊圭祐さん)を呼びました。道長は頼通に、これから自分たちがなさねばならぬことは何かと問いました。頼通が「朝廷の繁栄と~」とありきたりの事を言うと、道長は「我らがなす事は敦成親王を次の東宮にして、一刻も早く即位させる事」とはっきり言いました。そして「いかなる時も我々を信頼してくれる帝、それは敦成親王だ。我が家の繁栄のためではなく、ゆるぎなき力を持って民のために良き政をすること。その事を胸に刻んで動け。」と頼通に言い聞かせ、頼通も父の命を理解しました。3月4日、臨時の除目が行われ、藤原実資は大納言に、藤原公任(町田啓太さん)と藤原斉信(金田哲さん)権大納言に、藤原行成(渡辺大知さん)は権中納言となり、これは全て道長の思いを反映した人事でした。そしてすでに権中納言であった源俊賢(本田大輔さん)を加え、一条朝の四納言が揃うことになりました。また頼通もこの時にわずか19歳で権中納言となり、頼通はすぐに大納言の実資に挨拶に行き、諸々の教えを乞いたいと伝えました。そう聞いた実資は喜び、では今から早速仕事を教えると意気込んでいました。でも頼通が「今すぐというのは・・」という態度だったので実資は立腹し、頼通を叱って退席しました。さて道長ですが、嫡男・頼道の婿入り先として具平親王の一の姫の隆姫女王にと話しが出ていて、嫡妻の源倫子(黒木華さん)に相談していました。倫子がまず頼道の気持ちをと言うと、道長は「妻は気持ちで決めるものではない。」ときっぱりと言い、道長が自分に対してもそうだったのかと少しがっかりしました。でも「男の行く末は妻で決まる。自分が今日あるのは倫子のおかげだ。隆姫女王も倫子のような妻であることを祈ろう。」と言うと、倫子は安心して笑いました。そして倫子は、子供たちが巣立った後のこととか、年が明けたら威子の裳着だとか、道長との時の流れを感じながら二人で語りあっていました。道長は臨時の除目の時にまひろの父の為時も左少弁に任じていて、長い間仕事がなかった為時は8年ぶりに宮中での仕事を得たことを喜んでいました。道長がまひろの様子を見に藤壺に来たので、まひろは父の任官の礼を伝えました。その折に道長がまひろに娘(実は道長との間の子)は何歳かと訊ね、まひろが娘・賢子は11歳だと言うと、道長はまもなく裳着だと思いを馳せました。裳着の言葉を聞いたまひろは道長に、左大臣として娘の裳着に何か贈ってもらえないかと要望すると、道長はあっさりと了承してくれました。(道長はまひろの娘が自分の子だと気がついているのかどうか、またわからなくなりました。)道長は賢子が裳着を済ませたら藤壺に呼んで宮仕えをさせたらどうかとまひろに提案したのですが、賢子に実の父の存在を知られるのを恐れたまひろは、とっさにあかね(泉里香さん)はどうかと推薦し、あかねは藤壺に入りました。宮の宣旨から「和泉式部」という名を与えられたあかねは新入りであっても堂々と不満を述べて周囲を驚かせましたが、結局はその名を受け入れました。帝が藤壺にお渡りのある日、女房たちは庭で若い公達の頼通らと貝合わせをして遊んでいて、帝と彰子は楽しそうにそれを眺めていました。かつて二人の親王に愛された和泉式部はふだんの何気ない仕草にも色香を漂わせる恋多き女人で、まだ女人の扱いに慣れてなさそうな頼道の隣に座って、頼道の気を引くような仕草を次々とやっていました。和泉式部のやることに頼通はもちろんドキドキ、そして隣にいた義弟の藤原頼宗(道長の妾・明子の嫡男;上村海成さん)も頼通と式部にドキドキしていました。道長が藤壺を訪れて娘の彰子が産んだ孫の敦成親王をお守りをしていたある日、亡き中宮・定子の遺児で彰子が傍に置いて育ててきた敦康親王(渡邉櫂くん)が彰子に甘えている光景が目に入りました。ただその甘え方がじきに元服を迎える男子にしてはやや異様に感じられ、道長はまひろが書いた「源氏の物語」のそれによく似た部分を読み返していました。万一があってはいけないと感じた道長は早速、藤原行成を呼んで陰陽寮に敦康の元服の日取りを決めさせるように言い、日取りが決まったらすぐに帝に奏上して認可をもらうつもりでいました。しかしまだ元服したくない敦康は父の帝に、彰子の第二子出産が済んで藤壺に戻ってくるまでは待って欲しいと訴えていて、帝もそれを認めていました。藤壺に小火があり敦康親王はとりあえず伊周の屋敷に移っていました。敦康は自分の元服を急がせる道長のことを、自分を邪魔にしていると感じていて、そのことを伊周にもらしました。自分の甥でもある敦康を何が何でも守りたい伊周は、病の身をおして道長を訪ね、敦康を帝から引き離さないよう、次の東宮は敦康だと訴えました。重病の伊周は傍から見ても痛々しいほどでした。しかし伊周の道長への恨みは凄まじいもので、自分がこのように落ちぶれたのは全て道長のせいだと罵り、道長が伊周を憐れんで「下がって養生せよ」と言うと、伊周は道長を睨んで呪詛を始めました。そして懐にあった呪詛の紙を辺りに大量にばらまき笑いながら呪詛を続けるので、道長の従者が力ずくで無理やり伊周を退室させました。(呪詛の件では伊周は関係ないとされていたのに、自ら証拠を残していきました。)
October 9, 2024
-

大河ドラマ『光る君へ』第37回~「波紋」
2024年NHK大河ドラマ 『光る君へ』 の感想です。この回では私は、前半の当時の製本作業と、そして宮仕えの仕事が充実して楽しくて仕方がないまひろ(吉高由里子さん)が久しぶりに実家に宿下がりしたものの、そのあまりの浮かれっぷりに父も弟も家人の皆も呆れ、娘の賢子(梨里花さん)は傷ついて怒りが爆発する場面に見入っていました。まひろは賢子のことがふと気になって帰ってきたはずなのに、酒に酔った勢いもあってか、あるいは皆が自分の宮中での土産話を楽しみにしていると思っていたのか、ずーーっと自分のことばかりしゃべり続け、賢子のことを気に掛ける様子はありませんでした。多少興味のある話でも、マシンガントークの人の話を聞き続けるのは疲れると思います。ましてや自分に関心がない母の自慢話を10歳の子が一方的に延々と聞かされても、面白くないですよね。賢子なりに母を理解して、ふだんは質素な暮らしでもそれなりに皆と楽しく暮していたでしょう。なのにまひろの無神経な振る舞いで、賢子は我慢していたことが怒り爆発になりました。これはもう、実家に戻って気が緩み過ぎたまひろの、さらには気を緩められる実家があることへの有難みがわからなかったまひろの落ち度だと思います。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #光る君へ 寛弘5年(1008)秋、帝(一条天皇)の子を懐妊して実家の土御門殿に帰っていた中宮・藤原彰子(見上愛さん)は無事に敦成親王を出産し、しばらくしたら内裏に戻ろうかという時期でした。彰子は母の源倫子(黒木華さん)に、帝への土産をここで作っていきたいと提案し、それは藤式部(まひろ)が書いた物語を美しい冊子にしたいというものでした。娘の彰子の提案で左大臣の藤原道長はすぐに動き、最高級の紙を何種類もたくさん用意して彰子に届けました。ただ彰子があまりにも藤式部を頼りきっていて、そのため藤式部は倫子や他の女房たちに時折り不快感を持たれていました。土御門殿で一斉に冊子づくりが始まりました。各巻に合う紙を選んだら清書は藤原行成をはじめとする何人かの能書家に依頼され、それが仕上がって戻ってくると次は藤式部(まひろ;吉高由里子さん)や宮の宣旨(小林きな子さん)他女房たちによって、さらには中宮・彰子も加わって、冊子を紐で綴じたり表紙をつけたりなどの製本作業が進められていきました。そして皆の頑張りで、源氏の物語の見事な冊子が出来上がりました。冊子が完成し、内裏に戻るまではまだ日があったので、まひろは彰子の許しを得て宿下がりをして実家に戻りました。まひろは彰子から土産として高価な酒や菓子や昆布などの他、白米も俵で持たせてもらい、見たこともない数々の高価な品に実家で仕える者たちは、これが中宮様のお側で仕える人の土産かと誰もが目を丸くしていました。父・藤原為時(岸谷五朗さん)はまひろの働きをありがたく思い、まひろは父に娘の賢子(梨里花さん)の養育をまかせっきりにしていることを詫びました。久しぶりに会った娘の賢子はすっかり背丈も伸び、帰宅した母に挨拶もできるほど成長していたのですが、母に対する態度がどこかよそよそしいものでした。また久々に帰った実家は、まひろの目にはどこかみすぼらしく感じられました。その日はまひろが持ってきた高価な食材で早速ごちそうが作られ、まだ日が明るいうちから延々と身内の皆でのささやかな宴が開かれました。まひろは内裏での暮らしや出来事を土産話にあれやこれやと皆に話し、弟の藤原惟規(高杉真宙さん)も時折り相槌を打っていたし、皆も興味深そうに話に耳を傾けていました。しかし酒が入っているせいか、まひろの話は夜になっても延々と止まることなく続き、ところどころで自慢話も入って、聞いている皆もいいかげん疲れてきたし、特に娘の賢子は母の話にうんざりしていているようでした。まひろは父の為時や惟規にたしなめられても意に介さず、一人で愉快そうに話し続けていました。まひろが実家に帰ってきたのも束の間、翌日にはまひろが傍にいないことを不安に思う彰子から早速、土御門殿に戻ってくるよう通達がありました。為時はまひろの立場を理解していましたが、あっという間に戻っていく母に対して賢子の不満と怒りが爆発しました。何しに帰ってきたの?内裏や土御門殿での暮らしを自慢するため?内裏での贅沢をなぜここで嬉しそうに語るの?と。そして賢子はまひろが嫡妻でないから自分たちが苦労をするのだとも。まひろが、自分は宮仕えをしながら高貴な方々とつながりを持って、いずれ賢子の役に立てたいと思っている、と説明しても母は女房としての仕事が楽しくて仕方がないのだと見抜いている賢子には、まひろの言葉は響きませんでした。やがて彰子は敦成親王を連れて内裏に戻り、彰子の戻りを待ちわびていた敦康親王(渡邉櫂くん)はすぐに藤壺に駆け寄ってきました。中宮・彰子を母とも姉とも慕う敦康は弟・敦成を見て、彰子が自分を可愛がってくれるなら自分も敦成を可愛がると宣言し、彰子ももちろん敦康は大事な敦康だと約束し、二人は微笑み合いました。そうしていると帝(一条天皇;塩野瑛久さん)が藤壺に渡ってきました。彰子は帝への挨拶を済ませた後、実家の土御門殿で皆と作っていた源氏の物語の冊子を帝に献上しました。冊子を手にとった帝はそのあまりの美しさにたいそう感激し、これは彰子が帝のためにしつらえた、彰子が紙を選び製本に彰子も参加したとまひろが説明すると、帝は彰子を愛おしそうに見つめて彰子に喜びを伝えました。*この冊子づくりについての解説が番組の公式HPに出ています。をしへて! 佐多芳彦さん ~彰子が発案! 紫式部も行った『源氏物語』の冊子づくり ⇒ ⇒ こちら まひろが書く源氏の物語をすっかり気に入っている帝は、これを藤壺で読み上げる会を開いてはどうかと提案、後日、藤原公任(町田啓太さん)や藤原斉信(金田哲さん)ら主だった公卿が藤壺に招かれ、会が催されました。物語の中には帝がよく読む『日本紀』も出てきて藤式部(まひろ)はこのような知識もあるのかと斉信や公任は感心し、二人が小声で私語するのを聞いた帝には藤原行成(渡辺大知さん)が当たり障りなく場をつくろっていました。帝は源氏の物語を、女ならではの観点に漢籍の素養も加わりこれまでにない物語であると褒め、このことが人々の評判を呼んで、彰子の藤壺をいっそう華やかなものにしていきました。しかし藤壺の繁栄は、亡き中宮・定子の身内であり、定子が産んだ敦康親王の血縁でもある藤原伊周(三浦翔平さん)らには面白くないことでした。伊周の叔母の高階光子(兵藤公美さん)は、このままでは敦康が左大臣・道長に追いやられてしまうと危惧し、伊周の嫡妻・源幾子(松田るかさん)の兄である源方理(阿部翔平さん)も今の帝は道長に逆らえないと考えていました。幾子は兄に、帝の計らいで伊周の位を戻してもらえた今は騒ぎを起こさぬように言い、伊周も急いては事を仕損じると考えていました。しかし伊周はそう言いつつも、裏では道長への呪詛をひたすら続けていました。ある晩のこと、内裏の藤壺に盗人が押し入り、寝ずの番をしていた女官たちが襲われて衣をはぎ取られるという事件が起こりました。その夜、物語を書いて遅くまで起きていたまひろが女官たちの悲鳴を聞いて駆けつけ、盗人たちは逃げていきました。その報告を聞いた藤原道長(柄本佑さん)はすぐに娘の彰子の元を訪れて安否を確認し、いっそう警護を増やしました。一方、まひろには昨夜のことを訊ね、まひろは彰子が女官たちをいたわって自ら袿を与え、その姿は上に立つ者の威厳と慈悲にあふれていたと道長に伝えました。道長はまひろに、これからも彰子と敦成親王をよろしく頼むと言ったのですが、その折に帝の第一皇子の敦康親王ではなく、彰子が産んだ自分の孫の敦成親王が次の東宮になると、まひろに口を滑らせてしまいました。まひろはもちろん他言しないものの、重大な話を聞くことになりました。年が明けて寛弘6年(1009)1月、帝は伊周に正二位の位を授け、これにより伊周は道長と同じ位で大臣に準ずる地位になりました。伊周は挨拶の中で、自分は帝の第一皇子の敦康親王の(伯父であり)後見であり、道長は第二皇子の後見であることをあらためて強調しました。周囲の公卿たちは、伊周の強気は上に立つ道長のゆとりであろうと評判、一方で道長の政権を支える決意をしている藤原公任は、伊周の弟で今は道長を支持している藤原隆家に、兄の伊周に何か動きがあればすぐに知らせよと命じていました。
October 2, 2024
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- ゴールデンレトリーバー!
- 【まとめました】大型犬の北海道引っ…
- (2024-09-26 07:44:12)
-
-
-

- ☆動物愛護☆
- 🐾「動物界の洗顔名人たち!」🐾
- (2025-01-13 21:36:21)
-
-
-

- クワガタムシ、カブトムシがテーマで…
- パラワンオオヒラタ♂蛹♪(#^.^#)
- (2025-04-27 12:40:51)
-







