[我が良き虫の世かな] カテゴリの記事
全46件 (46件中 1-46件目)
1
-
我が良き虫の世かな ~ クワガタの初夢
ミヤマクワガタは温かい腐葉土に包まれて夢見がてら去年の夏の昆虫大相撲の事を考えていた。西の正横綱でありながら東の正横綱カブトムシに297連勝を許し、連勝ストップは小兵のゲンゴロウに譲り、自分の横綱としての責任や価値について考えていた。 「悔しい。」 その一言だったが、結果は結果だ。受け入れるしかない。 ゲンゴロウごときに負けたショックで戦意を無くしたカブトムシに勝って、今年の夏場所は晴れて東の正横綱だが、今度は堂々とさすがと言われる様な、見事な勝ちっぷりで勝ちたいものだと思った。こうして考えていると、自然と体が動き、気持ちは高ぶり、息遣いが荒くなる。今はまだ冬。こんな事をしていては冬眠には良くないのは分かっている。出来るだけ体力を温存しなければならないのだ。しかし、20年余りカブトムシに独走を許したのは事実だ。昆虫の場合短命なため、年ごとに種族別の代表を決めて戦うのだから、自分ひとりの責任ではないのだが。ミヤマクワガタはいつしかカブトムシとの対決に備えてイメージトレーニングを始めた。がっぷりよつに来たら、右に交わして得意のクワではさみ投げ。突きで来たら下からクワをあてがい、下から差し込みクワすくい。あの角でつりだしに来たら、4本の足を絡めてどうにかしのいで、頃合いを見計って逆に大技クワばさみだ。足を狙って倒しに来たら、カブトムシより重心が低いのを活かして、胸に頭をつけて腰を寄せて一気の寄り倒し。そんな事に構わず、ただやみくもに押し出しに来たら。 来たら・・・・・・・ その時は下に潜って後に出て、このまま反対に突き抜ければゲンゴロウだが、グッと堪えて背中に回り込み送り出しだ。 イメージの中ではいつも東の正横綱のクワガタの長い冬はまだまだ続く。 人間の世界では、もう直ぐ初場所の頃だろう。
2020.12.31
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ 春が来た?
めっきり強くなった日差しの中で蝶のキタテハは舞う。何十年、何百年と受け継いで来たし、これからも受け継いで行く春の風景。花は香りに我が身を託し、目にもまばゆい極彩色で虫達を誘う。これもまた、幾百年も繰り返して来た春の習わしである。春は己を待ちわびる数多の命に優しく囁く、「冬は去った。代わりに温かな風を運んで来た。だからさあ出ておいで。」と。躍動、飛翔、徘徊、虫達はそれぞれの形でそれに応える。春はたゆたう磯の波に似て、ある時は逆巻く波に洗われ、凍える風雨に阻まれながらも、今この場所に安住の場所を求めようとしている。 キタテハは目覚め、花の差し出す蜜の香りに誘われて、巻き取った舌をそこに伸ばす。 「うっ!冷たい!」 キタテハはあまりもの冷たさに今度は本当に目覚めた。 辺りは暗く、相変わらず凍り付くような寒さだ。どうやら寝惚けたらしい。キタテハは落胆のため息を漏らしながら、再び忍耐の冬眠に戻った。
2020.12.27
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ 街は楽しいクリスマス
街は華やかなクリスマスイルミネーションに満ち溢れていた。ショーウィンドウも橋の欄干もタワーもホテルの屋上も光、光、光。赤、青、黄色、様々なランプが自分こそが一番美しく輝いているのだと競い合っていた。 街は賑やかなジングルベルの曲が溢れ返り、デパートもおもちゃ屋もレストランも行き交う宣伝カーさえも、音、音、音。ショーウィンドウは手を引かれた子供達に、「ここにこそ、君達の欲しい物がいっぱいあるんだよ。」と、呼びかけていた。 人はこの日をクリスマスイブと呼ぶ。 そして商店街に沿って並んだ街路樹は、それこそ光と音の一大ページェントだった。 木を二重三重、いや五重六重に、枝は一本一本に巻かれているのではないかと思われるほどのイルミネーションが、煌々と目まぐるしく点滅し、幹に縛り付けられた大音響のスピーカーが、声を限りにクリスマスソング・メドレーをがなり立てる。 街は待ちに待った楽しいクリスマスイブに酔いしれていた。 戯れ行く家族連れも、何やら冗談を言い合いながら黄色い歓声を振り撒く女子高生達も、腕を組み、肩を抱いて今夜のお楽しみをヒソヒソ話し合うカップル達も、それを呼び込む売り子達も、みんな笑顔、笑顔、笑顔。笑顔の洪水である。 しかし、人間達の自分勝手なお祭り騒ぎを、まさに地で行く苦虫をかみつぶしたような表情で、蔑む存在があった。 蛾である。彼の名はスズメガという。 「え?どこにって?そこ、そこの木の幹にしがみついて、完全な木肌模様にカモフラージュして、羽を広げてじっとしている.....彼が何かブツブツ言っています、耳をそば立ててちょっと聴いてみましょう。」 『ちぇっ、何だいこの騒々しさは?来年春まで温かくなるのをひたすら待ち侘び、空腹に堪え、寒さに堪えているこっちの身にもなれって言うんだ。ギラギラ眩しいは、ガチャガチャうるさいのは、堪んねぇぜ。さむいよ~、腹減ったよ~、春はまだか~~~?』 もし彼に歯があるなら、奥歯がガチガチいいそうな寒さの中で、春の香りをその敏感な触覚が捉らえるのをひたすら待ち続けるのであった。
2020.12.24
コメント(5)
-
我が良き虫の世かな ~ ダニ
人々は俺をダニと呼んで、毛嫌いし、軽蔑し、排斥しようとする。俺に言わせれば、俺はただ生きたい様に生き、やりたい事をやり、食いたい物を食ってるだけだ。別によその国に爆弾を落とし、自分たちは奴等に正義を行ったぞと堂々と胸を張ったりはしない。別によその国でまだ可愛い盛りの子供を親の目を盗んでさらい、戦争の道具にさせる事もない。別に善人面をして自分の権限にものを言わせ、談合、癒着、収賄、天下りをしている訳でもない。別に地球にガスを振りまき、1万年の温度変化をほんの100年でやり遂げる様な事も決してしない。別に他の者を気に入らないだけで殺したり、誰でもいいから殺したりする様な事もしてはいない。俺に言わせれば、奴等こそ俺以下だ。そんな俺がいつもの様にいつもの道を歩いていると、奴等は急にやって来て、俺をしょっ引き、この暗く、汚い場所に押し込めやがった。俺はただ生きたい様に生き、やりたい事をやり、食いたい物を食ってるだけだったのに。おれは今ゴミの中で息も絶え絶え、必死に生き延びようともがき苦しんでいる。早く俺をここから出してくれ。この、この、この、この掃除機という地獄から。だから最初に言ったろう。俺はダニだって。
2020.12.20
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ アントンとイブリン(語り継がれるあの日)
アリの国の五代目王ギド・アントンは今、目をクリスマスのローソクの様にキラキラ輝かせる子供たちの視線を浴びながら、この国の建国者アントンとイブリンの冒険を話し終えようとしていた。「アントンは来る日も来る日も国のために働き、働き疲れた者は首をちょん切られて草むらにゴミくずの様に捨てられてしまうアリ社会に疑問を持っていた。そこで危険な疑問を持つ者が増えてきたと危機感を募らせた女王アリの側近は、そんな不穏分子をまとめて箱に詰め川に流してしまった。アントンたちは詰め込まれた箱から抜け出し川を流れる木切れに乗り移ったものの、その木切れは海へと流れ、今度はつらく長い航海となった。そのうちに仲間も一人、二人と命を落とし、諦めかけたとき、この島にたどり着いたのだ。そのとき生き残っていたのが、初代王のアントンとその妃イブリンだった。二人はつらい日々を乗り越え、少しずつ畑を耕し、子孫を残し、やがてそれは増え広がり、今こうしてこの国へと栄えているのだ。だから・・・・」彼が最後の言葉を継ごうとしたしたとき、部屋の隅で子どもが言い争う声がした。「返せよ。それ僕んだ。」「うるさい、僕が先に見つけたんだ。」「でも僕が先に手に取ったんだから僕んだ。」ギド・アントンがそちらを見ると、二人の男の子が小さな飴玉を巡って言い争っていた。親が持たせた飴玉を誰かが一つ落としていたのだろう。「君たち、つまらない争いはやめなさい。私は今、この国の成り立ちについて話しているところなのだよ。」ギド・アントンはここで大きく息をつくと言った。「アントンとイブリンは皆が平等に暮らす幸せな国をめざして二人、二十人、百人、千人と子供を増やして行ってこの国を作り上げたんだ。さっき言いかけた最後の言葉をここで私に言わせてくれるかい?」そこで彼は子どもたちを見回した。彼はニコリと微笑むと最後の言葉を言った。「だから、私たちは皆家族なのだ。」子どもたちの真剣なまなざしが一心に彼に向けられた。その時、一人の子どもが飴玉を取られた男の子に自分の飴玉をひとつ渡した。受け取った子どもは驚いてくれた子どもを見つめた。すると、次から次へと子どもたちはその言い争っていた二人の男の子に、自分の飴玉をひとつずつ交互に渡して行った。やがて二人の男の子は胸に抱えきれないほどの飴玉をもらっていた。二人の男の子は目に涙をいっぱいためてその場にうずくまり、胸いっぱいの飴玉は床にこぼれ落ちた。他の子どもたちも自分たちの飴玉を床の上に落とし、子どもたちの真ん中に大きな飴玉の山が出来た。子どもたちはそこで屈託ない笑い声を上げなら、楽しいひと時を送った。そんな様子をギド・アントンは目を細めて見つめ天に向かってつぶやいた。「アントン、イブリン、わが父母よ。ご覧ください。お二人の子たちはあなた方の心を受け継いで立派に育っています。」
2020.12.17
コメント(4)
-
我が良き虫の世かな ~ アントンとイブリン(国の王)
何の疑問も持たず、ただアリ社会の中で働き詰めに働き、働き通して死ぬと無造作に捨てられる働きアリの一生に疑問を持ったアントンは捕らえられ、危険思想の持ち主として、他のたくさんのアリ達とともに箱に詰められ川に流される。箱を脱出して木切れに乗り移ったアントン達だったが、木切れは川岸にたどり着く事もなく海へと流され、ほとんどのアリは流されたり飢え死にしたりしながら、ようやくたどり着いた無人島ではイブリンというメスのアリとふたりだけになっていた。そしてふたりの新しい生活、新しいアリ社会が始まったのだ。 5代目アントンのギド・アントンが困り果てた顔でアントンの所へやって来た。代々この国の王は元々の名前にアントンを付けて名乗り、女王はイブリンを付けて名乗ったが、彼と2ヶ月前に亡くなった妃は単にアントンとイブリンと呼ばれていた。 「アントンちょっとお話があります。実は山の畑で採れた野菜を隣通しのふたりがそれは自分の畑で採れたのだと言い張り埒があかないのです、聞いてやってくれませんか?」とギド・アントンは言った。アントンはいつもの様ににこにこ微笑みながら、「連れておいで、聞こうじゃないか。」と答えた。ふたりのアリはアントンの前に来るとそれぞれ自分の主張をがなり立て相手の言葉など聞こうともせず、いつまでも平行線で延々と口論が続いた。アントンは相変わらずにこにこしながら聞いていたが、アリのひとりが、「こんな世の中など消えて無くなればいいのだ。」と言った途端アントンの表情がガラッと変わり激しい口調で怒鳴った。「今何と言ったお前?消えて無くなれだと?さっきから聞いていればふたりとも自分の事ばかり言いおって、ああ目障りだ気に食わないからふたりとも海に流してしまえ。」ふたりのアリは青ざめ、ギド・アントンもこの言葉に驚いたが気を取り直すと逆にアントンに食ってかかった。「これはアントンとも思えぬお言葉。気に食わないから海に流してしまえですと?見損ないましたぞ。」ギド・アントンと初代アントンはしばらく険悪な表情で睨み合い、言い争っていたふたりは口論を忘れ、固唾を飲み仲良く並んで成り行きを見守った。するとアントンは突然大笑いを始め、「よいよい、これでよいのだ。みんなが自分の言いたい事を言い、王たる者は相手が誰であろうと言うべき事は敢然と言う。それでよいのだ。これでこそこの国の5代目の王だ。」この言葉に今度は3人とも仲良く唖然とアントンを見つめるのだった。追放されたアリ社会の様にだけはしてはいけないと、この島に着いたときにアントンとイブリンが誓った、「みんなが自由に言い合える世界を作ろう。」という思いはちゃんと守られ、その意思は今の王にもちゃんと受け継がれていた。アントンは満足の眼差しを3人に向けていた。それから1ヶ月後にアントンもイブリンのあとを追うように息を引き取った。アントンの葬式には、最近発明された火を起こす方法で灯された松明に照らされ、長い行列が続いた。社会の一部として何も言えない世界がどれほど不幸な事か、しっかりと伝えられたとしたら、アントンの一生はそれだけでもう何も思い残す事はなかった。
2020.12.13
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ アントンとイブリン(建国の下)
アントンはしばらくうだるような暑さの中じっと荒れた地面を見つめていた。目の先にあるのは固い土。奴隷のようなアリ社会に疑問を持ち、同じような危険思想の持ち主と見なされた他のアリ達と共に追放され箱に詰められ川に流された。箱は川を下り海へ出て苦難の末に小さな小島にたどり着いた。沢山いたアリ達は次々に命を落し、その時残っていたのはイブリンというメスと彼だけになっていた。二人は島に上がりそこで自分達の家族を作り、家族は一族となり、一族は民族、民族は国となりアントンとイブリンはその国の王と王女となっていた。しかし島の環境は厳しく、土地は痩せていた。遠く離れた無人島に生き物も植物も極端に少なく、それぞれが細々と争いながら僅かな食べ物を奪い合っていた。幸いアントンの王国はアリらしい秩序と統率で繁栄してはいたが苦しい国民の生活は相変わらずだった。だがアントンもイブリンも働きアリを単なる道具として個々の考え生き方を認めようとしない旧態依然としたアリ社会に反発して追放された経験から、そんな社会だけにはしたくないと思っていた。アントンは足元に広がる荒涼とした大地に目を落しあることを考えていた。あのくぼみに雨水をため、溝を掘り、水を導きここに植物を植え、その実りで民の飢えを癒す。耕作という知識のないアリ達にとってこれは革新的な考えであった。こうしてアントンとイブリンのもと、アリ達の壮大な挑戦が始まった。倒れるものがあれば代わりに誰かがクワを持つ、飢えるものがあれば自分のわずかな食料を分け与える。しかし夜ともなれば、へとへとに疲れた体ながら星空の下いつか来る理想の生活を熱く語り、楽しく笑う。こうして彼の理想に導かれ遂に農場は完成した。そして初の収穫はまだ十分とは言えないものの確実にアリ達の社会を豊かに変えて行った。大事業を成し終えたアントンは王の地位を後進に譲り、新しい王は代々自分の名前の下にアントンを付けて名乗る様になり、しっかり彼の意志を引き継いで行った。アントンとイブリンは今ではすっかり豊かな農場となった大地を今日も見下ろしながら、手を取り合い微笑みをたたえて余生を送っている。あの下には幾千、幾万のアリそれぞれの生活が営まれているのだ。
2020.12.10
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ アントンとイブリン(不穏分子)
働きアリのアントンはいつもこう思っていた。「何で僕たちは毎日毎日朝から晩まで働き通しに働かなくっちゃならないんだ。夏の間、カンカン照りのお日様の下、同じ道を行ったり来たリ。前を行くアリの匂いをひたすら追って。重たい荷物を口にくわえて、巣穴まで運ぶ。夏が過ぎ、秋は更に忙しくなる。僕の人生って何なんだ?」ビ、ピ、ピ、ピ、ピーーーー!監督官の兵隊アリの笛がけたたましくなった。「おい!そこの働きアリ!そこで何をしている?どこの所属で名前は何だ?」監督官は恐ろしい形相でアントンを睨むと、つかつかと彼の方へ近づいて来た。アントンは押し黙ったまま、その場に立ち尽くしていた。監督官は側まで来るとアントンを見下ろすと、「お前なぜ働かない?働かない奴は首をちょん切って、その辺の草むらに捨ててしまうぞ。分かったか?」アントンは黙ったまま立っていた。監督官の顔は更に険しくなり、詰め寄って来た。「お前何黙って睨み返してるんだ?何か言いたい事でもあるのか?」アントンはゴクッと唾を飲み込み覚悟を決めると一気にこう言った。「何故毎日毎日働かなくっちゃならないんだ。おんなじ事の繰り返し。夏も秋も楽しく歌って踊って、たらふく食べて、好きなだけ寝て、好きなだけ遊べたら、冬に凍え死んでしまっても構わないよ。」これを聞いていた監督官の顔は見る見る青ざめ、ひきつった。「しっ!声がでかい。ちょっとお前こっちに来い。」とアントンは兵隊アリの詰め所に連れて行かれ、報告を受けた女王アリの側近が直ぐさまやって来て尋問が始まった。「このアリですか、問題の働きアリは?」側近は兵隊アリの隊長に尋ねた。隊長は困った様子で、「ええそうなんです。最近こういう考えを持った若者が増え、我々も取締に苦労しています。」隊長は汗を拭き拭き答えた。「どこの所属の者です?」監督官は隊長に聞いた。「第7食料調達部、第12搬送隊です。」隊長は報告した。側近は、「やはりまたあのユニットですか?これで5匹目です。わかりました、あのユニットはまとめて廃棄なさい。」と命じた。隊長は驚く風もなく踵を返して行きかけた。「お待ちなさい。いえ、第7食料調達部全体を廃棄です。」これには隊長も驚いた。側近は続けた。「何千年もの永い間築き上げて来た私たちアリ社会を根底から覆す危険思想です。徹底的に根絶します。女王様には私から、新しい働きアリを増産していただくよう進言します。分かりましたね?」隊長はさすがに少し動揺したが、直ぐに敬礼して立ち去った。間もなく五千匹もの働きアリが、小さな箱に無理矢理押し込まれ、川に流された。ほとんどのアリは何の疑問も抱かず、命じられるままに箱に入り、いつか川底に沈むのを待った。アントンと数匹のアリは必死に箱から抜け出し、そばを通った木切れに乗り移り、木切れが何処か岸に引っ掛かるのを祈った。しかし木切れは川をどんどん下り、岸に乗り移る事も出来ないまま、海へと出てしまった。アントン達数匹は悲嘆にくれ、漂流を続け、その間ある者は飢え死に、ある者は波に飲まれ、ある者は自ら命を絶った。3日後、アントンは揺さぶられ目覚めた。喉が焼ける様だ。それはアントンと共に最後に残った、イブリンというメスだった。「アントン起きて。島よ、島に流れ着いたの。」驚いて起き上がると、確かに小さいが島だった。二匹はその島に降り立つと、どうにか住めそうな事を確かめると見つめ合った。「ここで二人で生きて行こう。」アントンの言葉にイブリンは答えた、「今はまだ二人だけどね?」
2020.12.06
コメント(7)
-
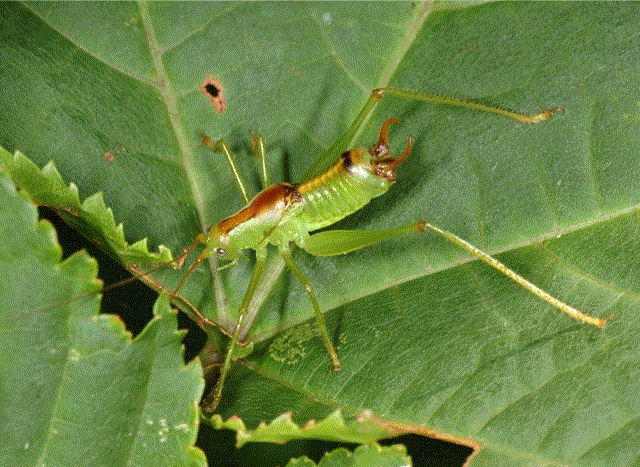
我が良き虫の世かな ~ 寿限無
寿限無と言って思い出すのは、落語でよく知られている小噺の「寿限無」だろう。「寿限無、寿限無、五劫の擦り切きれ、海砂利水魚の、水行末・雲来末・風来末・・・長久命の長助」元気で長生きするように縁起の良い名前を紹介されて、どれがいいか迷った挙句、結局全部繋いでしまったこの長~い名前をすべて書くとそれだけでこの記事が終わってしまうので途中を端折るが、なんとひらがなにして136文字と、とにかく長~いのである。落語では元々、彼(長いので彼とする)が川に落ちて、それを親に知らせに来た子供たちが名前を言っているうちに溺れ死ぬという内容だったが、子供が死ぬのは残酷だと彼に殴られてこぶが出来た子が親に言いつけに来て名前を言っているうちにこぶが引っ込んでしまったなどという話に替えられたバージョンもある。そこで虫さんの長~い名前を調べたらあるブログにこんなのが出ていた。ちなみこのブログで紹介されていた、世界一長~い名前の野球選手は、「ダルビッシュ・セファット・ファリード・有」さんとのこと。イラン系の父親の名前を取ってつけた名前だという。彼(この場合の彼はダルビッシュ有)にはMLBで世界一の投手になってもらいたいと願っている。ハリーポッターの通ったホグワーツ魔法学校のダンブルドア校長の名前も長~い。「アルバス・パーシバル・ウルフリック・ブライアン・ダンブルドア」という。ピッポグリフのバックビークが死刑になる前に、書類にこの名前を署名してポッターたちがバックビークを助け出すまでの時間稼ぎをしたほどだ。さて本題の世界一長~い虫の名前は、「カノウモビックリミトキハニドビックリササキリモドキ」という虫で、標準和名は「スオウササキリモドキ」という。冗談半分に付けたのがきっかけで呼ばれるようになったらしいのだが漢字で書いてみると、「加納もびっくり、元木は二度びっくりササキリモドキ」となるのだが、写真で実物を見てみると合わせてで三度もびっくりするような特異な風貌でもない気がする。「カノウモビックリミトキハニドビックリササキリモドキ」他に長~い虫の名前で、「トゲアリトゲナシトゲトゲ」というのがいる。最初は「トゲトゲ」という虫がいて、「トゲトゲ」棘のない「トゲナシトゲトゲ」が見つかり、「トゲナシトゲトゲ」更に棘のある「トゲアリトゲナシトゲトゲ」が見つかったというのだ。「トゲアリトゲナシトゲトゲ」他にもいる。クロホシテントウゴミムシダマシに似ているが少し違うぞということで、「ニセクロホシテントウゴミムシダマシ」こうなると「お前はテントウムシなのかゴミムシなのかはっきりしろ!」と膝と膝を突き合わせて問いただしたくなる。「ニセクロホシテントウゴミムシダマシ」まあ虫さん本虫は、人間から勝手に名前を付けられているなんてこれっぽっちも自覚はしていないだろうが。まずはこんな長~い名前の虫界の寿限無(幸福が限り無いの意味)たちにびっくり。感想文みたいに長久命(長く久しい命(名))な名前を付けてしまうことに二度びっくり。そんな名前を付けてしまう昆虫学者の水行末・雲来末・風来末(水、雲、風のように果てがない)なセンスに三度びっくりである。
2020.12.03
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ フユシャクご夫婦にインタビュー
「皆様いかがお過しでしょうか?いくら冬とは言え毎日凍える様な寒さですが、お風邪などひかれてはおられませんでしょうか?さて今日のMHK(虫放送協会)、『元気な夫婦』のお時間は、その寒い冬に活動される蛾の仲間フユシャクご夫婦にお越しいただき、並の虫なら凍え死んでいるこの時期になぜこんなにお元気なのか、その秘密をたっぷりとお聞きしたいと思います。」MHKのアナウンサーらしい杓子定規な前口上を並べ立てたテントウムシは、早速夫婦へのインタビューを始めた。「先ずはご主人にずばりお聞きしたいと思います。どうしてこんなに寒い時期を選んで活動されるのでしょうか?」「・・・・・・・」「ざっくばらんで結構です。何かその訳をお聞かせいたたければ。」「・・・・・・・」「少し緊張なさっておられる様ですね。」「・・・・・・・」「では、奥様いかがでしょう?」「・・・・・・・」それまで黙って横で微笑んでいた付き添いの親戚で、成虫で年を越す蝶のルリタテハがそろそろと話し始めた。「フユシャクが寒い冬に活動致しますのは、とりもなおさず怖い鳥やクモやカマキリなどがいないからなのでございます。」アナウンサーはやっと答えが戻って来てほっとしながら相槌を打った。「なるほど、それはなかなか考えましたね。我々テントウムシは臭い体液を出して身を護ろうと致しますが、敵自体がいないのが一番でございますものね?所で奥様にはお羽がございませんが、何かご事情でも?差し支えなければお聞かせいただけますか?」ルリタテハは少し苦笑いしながら皮肉を込めて、「アナウンサーの方なら事前にご存知と思いましたが、フユシャクの女は幼児期のシャクトリムシから大人になっても、羽のない蛾になるのです。」アナウンサーは、「ああ、そうだったんですか?これは大変失礼しました。」と慌てて、「ご主人は奥様のどんな所にお惹かれになったのでしょうか?」と話題を変えた。「・・・・・・・」夫はただ照れるように微笑むだけだった。 「それは、女が放ちますフェロモンに惹かれての事ですわ。」ルリタテハのフォローにアナウンサーは少しうろたえながら、「左様ですか?それはまた...」そこで一息入れて、「ご主人は奥様のフェロモン以外にここに惹かれたというものはございませんか?」「・・・・・・・」「ご夫妻はとても無口な方でございますね?」とアナウンサーがルリタテハに水を向けると彼女は、「もともとシャクトリムシから大人の蛾になったときからフユシャクには口がないのです。冬の間に繁殖して後は死ぬだけですから食べる必要もなく、口はいらないのです。」と言った。テントウムシのアナウンサーはギョッとしてフユシャク夫婦をまじまじと見つめて謝った。「そろそろお時間です。この辺でインタビューは終わりにしたいと存じます。ご夫妻大変申し訳ございませんでした。」「・・・・・・・」
2020.11.29
コメント(7)
-
我が良き虫の世かな ~ ナナホシテントウの寒~い一日
「ううう~。寒~。」ナナホシテントウ虫のてん七親父は口をわななかせ呻いた。「ほんとに今日は一段と冷えるわねぇ?」と、ナナホシテントウ虫のかみさんナナも相槌を打つ。「後どのくらいでお外に出られるの?」と、成虫になったばかりでまだ幼虫気分が抜けないナナホシテントウ虫のナナエが尋ねる。「歳を取るとこの寒さは体に堪えるよ。ところで今は何月だい?」と、ナナホシテントウ虫のさゆり婆さんが聞く。「俺たちゃナナホシテントウ虫だぜ。そんな事わかるわけねえじゃねえか。」と、隣のナナホシテントウ虫のてん蔵爺さんが喚いた。「実は私もさっきから気になってるんだよ。そこに掲示板があるから、ちょこっとこの岩の隙間から覗いてみようかね?」と、ナナホシテントウ虫のこはる叔母さんがもぞもぞ動いた。「こはるさんよ、あまり動き回らない方がいいぞ。」とナナホシテントウ虫のてん七親父が言った途端、ナナホシテントウ虫のこはる叔母さんは寒さで体がかじかんで、岩壁から転げ落ちてしまった。「そら言わんこっちゃない。誰が転んでも無視、無視。俺たちゃナナホシテントウ虫(転倒無視)だ。」 その時、ピューと木枯らしが吹いた。 ナナホシテントウ虫のてん七親父の寒ーいおやじギャグに一同ますます寒い思いをしながら、ナナホシテントウ虫達は岩影に身を寄せ合って、ひたすら啓蟄の日を待ち侘びるのである。
2020.11.26
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ 空蝉姉妹
サブ~、サブ~ 木枯らしの吹きすさぶ林の奥で、風に煽られ小枝は震える。それを支えるクヌギの幹も寒さに堪えかねる様に、木はだを曝していた。その幹の中ほどに2つの蝉の抜け殻が、戻る事のない主を思いやりながらも、よもやま話に花を咲かせていた。 「あーら、あなた土の中にいたときそんな事があったの?」「そうなのよ。その時はびっくりしてもうだめかと思ったわ。だって天敵のモグラが目の前をズリズリ通り過ぎて行くんですもの。息を凝らしてただじっとしているしかなかったわ。」「でもよく見つからずに逃げ延びたわね?」「そうなのよ、運のいい事にそのモグラ大好物のミミズを追いかけていたものだから、知ってか知らずか、見向きもしないで通り過ぎて行ったわ。」「そう?まあ、そのお陰でこうしてここにしがみついていられるわけよね?」「所であなた、私がここに来た時もう抜け殻になっていたけど、いつから?」「ふふふ、知りたい?実はねえ去年の夏からなの。」「えええ!?それはすごいわね?そんなに長く飛ばされず、剥がされる事もなく?」「そうなのよ。モグラから逃げ延びたあなたも相当強運だけど、1年半もここに留まり続けている私もなかなかのものでしょ?」「本当、尊敬しちゃうわ。お姉さんって呼んでいいかしら?」「ええ、構わないわよ。で私はあなたの事、何と呼べばいいの?」「アケミと呼んでくれればいいわ。」「アケミさん、よろしく。」「お姉さん、よろしく。」 こうして、木枯らしも雨も雪も凌ぎながら、空蝉姉妹のおしゃべりは、翌夏、セミ採りに来た子供達の胸のバッチになるまで続いたのだった。
2020.11.22
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ アリばばのきのこ畑(ある春のうららかな日に)
あれから月日は経って... ようやく木枯らしも去り、お日様も申し分なくその温かな光を地上に送り届けられる季節となったある春のうららかな日、アリばばもすっかり衰えた体を震わせて地上へとやって来てお日様を見上げ微笑んだ。彼女は去年の秋まではそんなに地上が好きではなかった。彼女は家の地下にご自慢のキノコ畑を持っており、毎日キノコを食べて何不自由なく暮らしていればそれで良かった。他人が飢えようが、食べ物を探しに出て他の虫に捕らえられ食べられようが、自分には関係ないし、逆に家族との団欒なんて真っ平だし、ましてやわずかな食べ物を分け合って食べて細々と生きていくなんて愚か者のする事だと思っていた。 あの日までは。 あの日飢えた子供の物乞いに根負けして、一切れのキノコを恵んでやったあの日までは。 だがその時まで感じていた寒気を感じなくなり、冷え切っていたのは自分の心だったのだと気付き、冬の忍び寄る凍える外に出ると、彼女の大事なキノコを道行く飢えた虫達に配り始めた。お陰で彼女のご自慢のキノコはほとんど無くなり、どうにか食いつなぎようやく春を迎えたのだった。でも彼女にはキリギリスもカマキリもトンボもみんな1年だけの命という定めを受け入れながら、最期に少しだけ幸せになれたとしたらとても嬉しい事だった。お日様に向かってもう一度にっこり笑うと目をつむり大きく深呼吸した。 数週間後、彼女はまだそこに座っていた。彼女の頭はとうに坂を転げ落ち、草むらの陰でまだ微笑んでいた。そしてお日様の光は彼女の体を優しく包み込んでいた。
2020.11.19
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ アリばばのキノコ畑(友情)
アリの婆さんアリばばは自慢のキノコ畑を彼女の自宅の地下室に栽培していた。しかしこのキノコはすべて自分のものであり、他人に分け与えるなんてとんでもないといつも思っていた。秋も深まり外では北風が木々の枯れ葉をみんな吹き飛ばしてしまう頃、暖かい毛布にくるまってもなぜか寒気がするものの、彼女は今日もキノコを堪能していた。そこへゴミ虫の子供がドアを叩いてキノコを恵んで欲しいと懇願にやって来た。彼女は最初、この子を無下に追いやろうとしたがあまりしつこく物乞いをするので面倒くさくなり僅かなキノコを分けてやるとようやく追い払う事が出来た。ところがその後なぜか体が温かくなり、幸せな気持ちに満ち溢れていた。彼女は気付いた。冷え切っていたのは彼女の心だったのだと。それからの彼女は両腕に有り余るキノコを抱えて家を飛び出し道行く飢えた虫たちにキノコを配り始めた。お陰で彼女のキノコ畑もすっかり採り尽くされ、彼女一人がどうにか春まで持ち堪えられるかどうかという有様になってしまった。そんな冬間近のある日ドアをたたく音がした。彼女がドアを開けてみると一匹のトノサマバッタがみすぼらしい身なりで壁に寄り掛かっていた。彼女はさっそく彼を迎え入れると暖かい暖炉にあたらせ、残り少ないキノコをかき集めると全て彼に与えてしまった。トノサマバッタは彼女の介抱でどうにか元気を取り戻し、少しずつ体力を回復して行った。しかし所詮一年しか生きられないトノサマバッタは再び日に日に衰弱して行ったが、それまでの間アリばばと色々な話をして、笑い合い、時には歌って過ごした数日後、遂に最期の時を迎えた。彼はアリばばに向かってこう告げた。「アリばばさんよ。俺のためにお前さんの大事なキノコをすっかり食べつくしてすまなかったな。あんたのお陰で俺は幸せに旅立つ事が出来るよ。楽しかったぜ。そこで俺の最後の頼みなんだが聞いてくれるかい?」アリばばは何の事だか分からず、でも変わらない笑顔でやさしくうなずいた。「春はまだ遠い。あんたも食料が無くなってこのままでは春を迎える事は出来ないだろう?だから俺が死んだら構わないから、俺を食ってくれ。俺はあんたの中で生きられるならこれ程うれしい事はない。」彼はどうにかそう言い残すと静かに息を引き取った。大粒の涙を湛えたアリばばを残して。
2020.11.15
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ アリばばのきのこ畑(凍える日々)
アリのばあさんアリばばは、仲間達から離れもう何年も独りで暮らしていた。 アリばばには自慢のきのこ畑があった。湿った地下室に横たわる大きな切り株には、柔らかくてとても良い香りのするきのこがびっしりと生えていて、時々それを食べて暮らしていた。 アリばばの口癖は、「あたしゃ誰にも世話にはならないし頼らない。ご覧あたしの自慢のきのこ畑を。これはぜーんぶあたしのもんだ。だから食べることには困らないのさ。」アリのばあさんアリばばはそうやって何年も独りで暮らして来たし、誰にも会いたいとは思わなかった。 そして秋も大分深まった今日も、昼近くにのろのろ起き出して来て、きのこをひと掴み口に押し込むと、大きく背伸びをした。 「うーん、今日もたっぶり寝たし、あたしのきのこもこんなに美味しい。あー気持ちが・・・?」 アリばばはちょっと寒気を感じて押し黙った。 「おや風邪でもひいたのかねぇ?まあ栄養たっぷりのきのこを食べてりゃそのうち治るさ。」 だがいつまで経っても、何日過ぎても一向に良くなるどころか、ますます寒くて堪らない。アリばばは毛布を被ってぶるぶる震えていた。 ある日家の戸を誰かがとんとん叩いた。アリばばはしばらく放っておいたが、いつまでも続くので仕方なく戸を開けた。 戸の外にはみすぼらしいなりのゴミ虫の子供が立っていた。 「アリのおばあさん、僕に何か食べ物を恵んでくれないかい?もう4日も食べてなくてお腹がぺこぺこなんだ。」 アリばばはうさん臭い目で睨むとゴミ虫の子供に、「あんたにやるような物はないよ。おまけに汚らしいし、臭いし、どっかに行っておしまい。」そう言うなり戸をぴしゃりと閉めてしまった。だが戸の外ではいつまでもゴミ虫の子供の泣き叫ぶ声が続いた。 あんまりうるさいものだから、さすがのアリのばあさんも堪らなくなり、きのこを一つ渡してやって、やっと追い払う事が出来た。 アリばばは、ほっとして椅子に座り込んだ。 「おや?」 今まで寒かったのがうその様に、ぽかぼかなのだ。 「どうした事だい。ちっとも寒くないわ。」 アリばばはしばらく考えこうつぶやいた。 「どうやら冷え切ってたのはあたしの心だったみたいだね?」 それからアリばばばあさんは、きのこを両手にいっぱい抱えて表に出ると、冬も近づきたくさんの凍える虫達に配り始めた。 本当に久し振りの心からの笑顔を添えて。
2020.11.12
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ ミノムシ哀歌(エレジー)
ミノムシのマーガレットは物思いに耽っていた。こうしてミノを作り、その身にまとってはや半年、遂に伴侶はやって来なかった。ミノムシのメスは一生をミノの中で芋虫の姿で過ごし、オスが交尾にやって来るのをひたすら待つのである。マーガレットの嘆きはもうお分かりだろう。行かず後家ならぬ、来たらず後家になりそうなのである。ミノの中では美貌も美声も気立ても関係ない。立地とフェロモンと運だけの勝負だというのか?マーガレットは己の不運を嘆きつつ一縷の望みに身を委ねていた。この場所は生きるのには申し分なかった。食料の木の葉は新鮮とは言えないが、いつも十分あり、ミノにくるまっていても底冷えする様な寒さもない。たた難点といえば動き回れる範囲が限られていた。食事ではい回るときいつも何か見えない壁に遮られて、それ以上進めないのだ。いつか限界を知り、その先に行く事など諦めてしまっていたが。今日もいつもと変わらぬ、いつもの今日を迎えていた。いつもと変わらぬ目覚めに、いつもの食事、いつもの散歩にいつもの壁。悲しいいつもを。しかし、いつもの午後の一時をミノの中でいつもの様に過ごしていると、いつもならざる激しい振動が体を襲った。「えっ?どうしたの?どうして?」マーガレットは必死に考えた。しかし、何も思い至らなかった。身を固くしてミノの奥にうずくまっていると、突然冷たい鋭利な物が体に触れた。それはマーガレットの大事なミノを切り裂き、ついにマーガレットは外に引きずり出されてしまった。 「さあみんな。ミノムシを取り出せたかな?取り出したらみんなが切った折り紙の切れ端やビーズの入った箱に入れておこう。どんなになるか何日か観察してスケッチしておいて下さい。」「は~い。」子供達の元気な返事が教室中に響き渡った。
2020.11.08
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ 虫さん川柳 ケッサク20選
1.食うことも 食われることも 虫の道 (詠み人知らず) 2.尻の灯よ 飛び行く先を 照らすべし (ホタル) 3.ともに生き ともに死のうぞ 地の底で (アリ) 4.赤や黄の 花に競いし 我が身かな (チョウ) 5.待ち侘びて 未だ来たらず 今日の飯 (クモ) 6.知るべきや 飛ぶ這う潜る 我の技 (ケラ) 7.砂かけの 悪しき姿を 知るや今 (ウスバカゲロウ) 8.我が子への 糧にしようぞ 血の香り (カ) 9.それ行かん 玉転がしは 糞力 (フンコロガシ)10.メダカ捕らえ 生き血をすすって 虫の仇 (タガメ)11.玉の身を 戯れ遊んで 欲しくない (ダンゴムシ)12.忍び技 我の仕種を 盗み見て (ミズスマシ)13.桑の葉を 絹糸に変えて 衣織る (カイコガ)14.メスを呼ぶ 羽の音人は なぜ愛でる (スズムシ)15.ささやかな庵を結びて彼を待つ (ミノムシ)16.人嫌う ごみ溜め愛しき 我が家なり (ゴミムシ)17.人間よ 来るなら来いと 針磨く (スズメバチ)18.陽光を 浴びんが闇の 永き年 (セミ)19.咲き誇る 香ぐる花園 虫狩り場 (カマキリ)20.生け垣で 細身の体 枝に似て (ナナフシ)
2020.11.05
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ 弁論大会 虫の主張
人間達よ、私は今日この場で我ら虫を代表して、私達に対する不当な中傷に対して断固抗議する。★虫取り子供が網を持って虫を取るのではない。コンビュータ・プログラミングのデバグと言われるプログラムの誤りで仕様通りに動かない箇所を修正したり、除去したりする作業の事である。これは間抜けなプログラマーが我々虫に責任転嫁しているのであり、己の無能さを虫のせいにして、罪をなすりつけようとしているのは明白である。★虫の居所が悪いこれはおそらく寄生虫が体の中をはい回り、その不快さからこういう表現をするのだと私は思う。これは虫という言葉で我々を十把ひとからげで扱い、虫全体に対する中傷に外ならない。★虫歯歯磨きを怠り虫歯菌が歯を侵食し、それにより激しい痛みや歯が抜け落ちる過程の歯をさす。これでは我々があたかも人間の口に入り込み歯を喰い荒らしている様ではないか。しかし、これは自分達の怠慢と不摂生が原因であり不当な表現以外の何物でもない。★虫けら虫けらにも劣る、虫けら同然、虫けら扱い、虫けらの分際で、などと我々を不当に下等扱いし、侮辱する言い回しは明らかに差別用語であり、コンプライアンスに違反する。速やかに謝罪し、以後使用しないと誓う事を要求する。もし『けら』がケラ固有の種を指すのであれば、彼等に成り代わり強く待遇改善を要求するものである。★~の虫これも差別用語に当たる可能性が多分にある。勉強の虫、本の虫、野球の虫など善意に解釈すれば物事に真摯に打ち込む態度とも取れるが、取り様に寄っては変質的にのめり込む、お宅的なニュアンスの引き合いに使われている節もある。万一その使用方法に異義申し立てがあった場合には、速やかに改める事。以上、我々虫からの地位保全および権利擁護に関する改善要求を、ここに表明するものである。- ----------- 我がよき虫の世かな実行委員会会長 17年ゼミ
2020.11.01
コメント(4)
-
我が良き虫の世かな ~ ブルーな虫達
セミは木の汁を吸いながら、残された数日の命を思いブルーな気持ちに沈んでいた。地中での7年間は虫の中では長いとしても、苦節7年の末の一週間だけの我が世の春である。オンブバッタのオスはメスの背中でブルーな気分だった。巨大なメスの背中におまけかアクセサリの様にへばり付く自分の小さな体があまりにもみすぼらしくて。もっと凛々しくて逞しい男でありたかったと。ウスバカゲロウは民家の軒下で、与えられた一日限りの自由なひとときをブルーな気持ちで過ごしていた。地面にすり鉢を穿ち、滑り落ちて来たアリの必死の懇願も意に解さず、ひたすら生き血を啜ったあの頃が懐かしい。彼女が女王なら私は王ではないか。なのに何百という召使いが彼女の世話をし、王の私は所在なげに周りをうろうろ、彼女は百年近く生き、私達王は何世代も入れ代わる。シロアリのオスはブルーな気持ちを訴えた。生まれたばかりのイチジクコバチのオスはイチジクの中でブルーな気持ちでメスを待っていた。手早く交尾を済ますとたった一ヶ月の、幼虫のまま終わる一生にこの世の不合理を歎きながら。かつて散った雄カマキリのブルーな思いが、そよぐ風に流れて消えた。秋、彼は我が子のために我が身を糧にと妻へ差し出したのである。こんな虫達の悲哀に満ちた、ブルーな、ブルーな気持ちを私は今ここに記す。「なにー?」「なにー?」「なにー?」「なにー?」「なにー?」「なにー?」セミからも、オスのオンブバッタからも、ウスバカゲロウからも、シロアリの王からも、イチジクコバチの男の子からも、雄カマキリの魂からも一斉に非難の声が上がった。「あんただけには俺達の事を語って欲しくないよ。あんたはいつもタマムシ色なんだから....」
2020.10.29
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ 虫達の権利
「俺達害虫に生活権を!!」「オー!」「俺達害虫にも生きる権利を!!」「オー!」「私達益虫に保護権を!!」「オー!」「私達益虫に特別保護権益を!!」「オー!」虫達は害虫と益虫に分かれ大規模な抗議デモを行っていた。害虫は食べなければ死んでしまう、生き血を吸わなければ子供の養育義務が果たせない等と生きていく上で必要な行為であり、虫が虫たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する生存権を主張した。益虫は害虫を駆除する農薬散布で自分達の生命まで危険にさらされているとし、特別保護区を設置して優先的に保護される保護権を要求した。害虫の代表はニジュウヤホシテントウ。益虫の代表はモンシロチョウ。両デモ隊はとある農家の前で対峙する事になり、一触即発の事態となった。害虫の代表のニジュウヤホシテントウが前に進み出て、「俺達にも生きる権利がある。喰わなきゃ死んでしまう。お前達益虫どもは俺達害虫を喰ったりして人間に媚びを売る虫社会の裏切り者だ。」益虫のモンシロチョウが反対からやって来て、「私達も食べなければ生きて行けません。蜜を吸うために花に潜り込むだけの者もいます。人間に害をなす事をやめ、生活改善、食料転換を行わないあなたたちのせいで、私達にまで農薬による生命の危険が・・・・・・・?」と言ったとき、モンシロチョウの言葉が止まった。害虫の中に我が子の姿を見つけたのだ。「あなた!そこで何してるの?あなたはこっちでしょ?」モンシロチョウはヒステリックに叫んだ。「でもママ、僕達幼虫はキャベツの葉を食い荒らすから害虫なんだって。」モンシロチョウの子供は、それこそ虫の鳴くような声で言った。「どうやら身内の中に、とんだ厄介者がいるようですな?」ニジュウヤホシテントウは勝ち誇った様に言った。モンシロチョウはしばらく絶句していたが、やがてこう言った。「害虫、益虫は人間の都合で勝手に自分達のために決めた事。本来私達は生活のために食べ、行動をしているのです。私達に善も悪もないし、人間の様に環境を破壊する事は決してありません。そうです、私達は基本的虫権を求めて共に手を携えて断固人間に抗議しましょう。」害虫と益虫のデモ隊の流れは一つの大河となって、人間達の住む町に行進を始めた。
2020.10.25
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ シロアリ女王
長さ10センチ太さ3センチ余りと他のシロアリにに比べて、これが同じ仲間かと思えるほど、巨大な芋虫の様な、ただただ卵を産むだけの工場となったメスのシロアリを人間は女王と呼ぶ。まあ働きアリにかいがいしく食事や排泄の世話をされ、敵が侵入すれば、兵隊アリが自分の命を賭してまで守ろうとする様は、人間の目からすると女王に対する揺るぎない忠誠心に映るのは当然だが。しかし果たして、人間世界の女王の様に尊敬と畏敬の念を持たれる崇高な存在として、シロアリ達が認識しているかは、彼等に聞いてみないことには分からないだろうが、私には女王という呼称よりも、卵を産み、子孫を残すためだけに生かされている奴隷に思えてならない。もっとも、優れた子孫を得るためには優れた個体が必要であり、それが選別されるという一点において女王に値するのかも知れない。中にはオーストラリアのシロアリの女王の様に、100年以上も生きるものさえいるという。虫の中では日本のセミが7年で、アメリカの良く研究テーマになる13年ゼミや17年ゼミなどが虫の中では最も長寿と思っていたが驚きである。100年の間、夫の王やその他の家族は何度も世代交代して、その間に50億個の卵を産むのである。もしあなたがこのシロアリの女王になったとすると、女王としての威厳と尊厳を持って生きることが出来るだろうか?出来る事なら彼女に聞いてみたい気がする。「あなたの楽しみ、生き甲斐、夢は何ですか?」と。私が想像するに、ただ卵を産むという機能だけを持った有機物と成り果てた彼女の視線は定まらず、返事は何も帰っては来ないのではと思う。最後に断っておくが、シロアリとはハチと同じ仲間のアリとは違い、ゴキブリの仲間である。
2020.10.22
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ 肝っ玉母さん
「ねーむれー、ねーむれー。はーはーのーむーねーにー。」ハサミ虫母さんは今日もかいがいしく子供達のお世話をしていた。子供達といってもまだ卵だが。胎教のためにこうして歌いながら、周りのゴミ掃除をし、卵を磨き、お尻の大きなハサミのお手入れに余念がなかった。子供達が生まれて来たらどんなお話をしてあげようかしら。どんな歌を歌ってあげようかしら。すべては子供中心に、子供の事ばかり考えて、その日を待ちわびていた。「明日はいよいよ卵の孵化予定日。私の腕白さんにお転婆さん、明日は安心して出ておいで。私がきっと守るから。」ハサミ虫の肝っ玉母さんは今日も卵達に語りかけながら、熱心にハサミの手入れをしていた。しかしその時、背後から黒い影が広がり、氷で背中をなぞられる様な悪寒と共に殺気を感じた。ハサミ虫母さんは恐る恐る振り返ると、太陽を背にそそり立つオオアリの姿に愕然とした。「よりにもよってこんな大事な時に、しかも卵じゃ呼び集めて、背中におぶって逃げ出すことも出来やしない。いよいよ明日という時に。」ハサミ虫母さんは絶望の溜め息をついた。「いいえ。こんな時こそ戦うの。私のこの自慢の大ハサミで可愛い子供達を守るの。」ハサミ虫母さんそう決心して、卵が見つからない様に移動しながら、オオアリに向かって大ハサミを振りかざした。「オオアリめ、また来たね。今日こそはあんたの頭をこのハサミで切り落として上げるから覚悟するんだね。そんときゃ転がった自分の首の目から出る涙、自分で拭いなよ。」オオアリはニヤリと笑い、「ハサミ虫のおばさん相変わらず威勢がいいじゃねえか。他人の台詞を横取りするんじゃねえぞ。あんたのそのぷりぷりのお肉を今日こそは頂くぜ。まああんたの卵か子供達を差し出せば、助けてやらんとも限らねえけどな。」ハサミ虫母さんはドキッとしながら、オオアリの足元の向こうに見える茂みに目をやり、「まだ出て来るんじゃないよ。じっとしていなよ。」ハサミ虫母さんはそう心の中で語りかけ、更にその場から離れた。やがてハサミ虫母さんとオオアリの激しい戦いが始まった。ハサミ虫がオオアリの首をハサミで狙えば、オオアリはハサミ虫の腹に食らいつこうと、まさに死闘が繰り広げられた。30分後、ハサミ虫のハサミは片方が折れ、オオアリの足が1本切り落とされていた。両者とも荒い息をしながら立ち尽くしていたものの、形勢は圧倒的にオオアリが有利だった。ハサミ虫母さんは傷だらけの体に鞭打って最後の攻撃に出た。猛烈な反撃にオオアリもついに本気になった時、ハサミ虫は突然逃げ出した。しかし完全に怒りまくったオオアリはすかさず追いかけ始めたが、その日はそれっきり2匹とも戻らなかった。よく晴れた翌朝、ハサミ虫母さんの子供達が、誰もいない巣の中でかえり始めた。そして母さんを探し始めた頃、背後から黒い影が近寄って来た。気づかない子供達はまだ母さんを探していた。その時、最後のお寝坊さんが卵から顔を出し、黒い影を見つけて叫んだ。「母さん!」子供達は一斉に振り向き駆け寄って来た。そこにはハサミが片方折れた、ハサミ虫母さんが立っていた。ハサミ虫母さんは優しく言った。「もう大丈夫。オオアリはまいてやったからね。ハサミは1本になっちまったけど、きっとお前達を守ってやるからね。」
2020.10.18
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ 夕焼け小焼けの赤とんぼ
♪夕焼け小焼けの赤とんぼ、負われて見たのはいつの日か....♪「おやおや、こんな所に赤とんぼさんがいるじゃないですか?赤とんぼさん、赤とんぼさん。」しかし、その赤とんぼさん聞こえているのかいないのか、知らんぷりして飛んで行ってしまった。「なんだいあの赤とんぼ。耳が悪いのかお高く留っているのか全然無視しやがって。」と思いつつ振り返ると別の赤とんぼさんがいた。「赤とんぼさん、赤とんぼさん。こんにちは。」しかし、今度の赤とんぼも振り返りもせずにすいすい飛んで行ってしまった。「んもう!今度の赤とんぼも無視しやがって。いくら自分たちは虫だといっても、あいさつされたら会釈するだけでもいいだろうに。ほんと失礼な奴らだ。」「ちょっとちょっと旦那。」こう呼び掛ける声に振り返ると、顔の長い、体も細長いショウリョウバッタさんが草むらから声をかけてきた。「やあこんにちは、ショウリョウバッタさん。あの赤とんぼさんたち一体なんなの。こっちがちゃんと挨拶しているのに、みんな無視して飛んでっちゃって。」「旦那。だめですよそりゃー。だってあいつら赤とんぼじゃないんですから。」「えっ?赤とんぼじゃない?またまたー。体が真っ赤なとんぼが赤とんぼじゃない?」ショウリョウバッタは少し困惑するような表情を浮かべてこう言った。「そもそも旦那。この世の中に赤とんぼと言う虫はいないんですぜ。」私はこのショウリョウバッタの言葉に耳を疑った。「い、い、いない?赤とんぼがいない?でもさっきの歌にも赤とんぼが出てくるじゃないか?」ショウリョウバッタは得たりとばかりの得意な顔をして言った。「あれは赤とんぼじゃなく、アキアカネというとんぼですぜ。」「じゃ赤とんぼって何?」「そりゃね、アキアカネが秋になると赤くなるんでさあ。」「紅葉じゃあるまいし、とんぼも秋になると赤く色づくわけ?でも何故?」「それはね、おっとあっちからまたアキアカネがやってきた。彼女に直接聞いてみておくんなせえ。それじゃアッシはこの辺で....」私はその赤とんぼに呼びかけた。「赤とん....、いやアキアカネさん。こんにちわ。」「あーら、人間さんこんにちは。今日はずいぶん日和が良く、気持ちのいい日ですわね?」「今度はいやに愛想のいいとんぼさんだ事。さっきは赤とんぼさんと声をかけたのがやはりまずかったのかなあ?」「あらごめんなさいね。きっと自分が赤とんぼと人間さんたちに呼ばれているのを知らなかったのね?そうなのよねえ。私たちアキアカネは秋になると体が真っ赤になるんですのよ。」「へえ、そうなんですか?どうしてなんですか?」「それはね、婚姻色と言って『もう十分結婚出来ますよ』って印ですのよ。」「ああ、そうなんですか?」「私も今お相手を探して飛び回っていますの。あらいけない。こんな事をしているとお嫁に行きそびれてしまいますわ。では失礼致します。」と言って、アキアカネレディーは優雅に飛んで行った。私は彼女を見送りながら口ずさんだ。♪夕焼け小焼けのアキアカネ....♪
2020.10.15
コメント(9)
-
我が良き虫の世かな ~ 虫さん三すくみ
三すくみの三は何かご存知だろうか?色々な三すくみがあるのだが、ヘビ→カエル→ナメクジ→ヘビが一般的かと思う。ナメクジ→ヘビは疑問だが昔はナメクジの粘液がヘビを溶かすと信じられていたかららしい。そのほか身近な例ではジャンケンがある。こちらは見事な三すくみである。東南アジアにはゾウ→ヒト→アリ→ゾウがあり、ジャンケンも親指→人差し指→小指→親指なんたそうだ。ゾウ、ヒト、アリは踏み潰すのだが、アリはゾウを食い殺すから強いとなる。この場合のアリは軍隊アリのような大群で進路上にあるものはすべて食い尽くすアリを指すのだろう。しかし、小指が親指より強いという説明が難しく、日本式ジャンケンの方が形そのままの分筋が通ると思う。そこで虫さん三すくみを考えてみた。アブラムシはテントウムシに食べられ、アリはテントウムシを追い払い、アブラムシはアリに守られるから立場はアリより強い。アリはアリ地獄に食べられ、アリ地獄は成虫のウスバカゲロウがいないと生まれなく、ウスバカゲロウはアリに食べられる。ダンゴムシは丸くなってグー、ハサミムシはお尻のハサミがチョキ、クモはいつも足を広げているからパー。虫さん三すくみ、うーんなかなか難しいぞ!!
2020.10.11
コメント(10)
-
我が良き虫の世かな ~ 図々しい奴
電車のベンチシートのど真ん中に一匹のスズメガがどっかりと座っていた。その両脇には男女が座り、女性は無視して携帯を見つめ、男性は珍しそうに携帯で写真を撮っていた。私も乗った時蛾に気付き向かいの席に座り観察していた。ドアが開き乗客が乗り込み、座ろうとして立ちすくみ、別の席へと移る。気持ち悪いのか怖いのか、誰も追い払おうとはしない。余程捕まえ車外に放そうかと思いながら面白さからしばらく見守った。何人の人がギョッとしながら立ち去ったであろう。幾駅も幾駅もこのおそらく無賃乗車客は体長4センチ足らずの小さな体で人ひとり分の席を図々しくも占領していた。やがて一人の男性が乗り込んで来てこの蛾に気付きながらも隣の空いた席に座り、無造作にこの不届き者を手で払った。蛾は床に落ち、這うように飛び、開いたドアから飛び出して行った。もしやこの蛾、酔っ払いおやじの様に眠りこけていたのではあるまいか?いずれにしろ、ここ東京の都会のひとコマではあった。
2020.10.08
コメント(9)
-
我が良き虫の世かな ~ 母を訪ねて3センチ
「日出ずる処の天子、書を没する処の天子に致す。恙無きや云々」これはかの聖徳太子が遣隋使として小野妹子に持たせた国書で、隋の皇帝である煬帝に宛てた外交文書の冒頭の一文であるが、東の国日本と西の国隋を対等な国として交流する事を志したという説から、単に世界情勢に疎かっただけだという説まである。しかし当時の超大国の隋からすると東の小さな島の取るに足らない王から対等に付き合いましょうとは不届き千万な話なのだが、激怒の内容に恐れをなして小野妹子が返事を隠してしまったという説がある。こんな身の程知らずで生意気な事を言う聖徳太子に対して怒り狂うのも大国として見苦しいと思ったのか、こうして倭の国と隋の交流が始まるのである。これこそ聖徳太子が見越した見事な外交手段と言うべきか。ところで最初に紹介した一文の最後の「恙無きや」は文部省唱歌『故郷』の歌詞にも出てくる様に現在も使われている言葉である。この『恙』とはツツガムシの事であるという説がある。当時風土病を媒介する害虫として、つまり「ツツガムシなどいないでしょうね?」と外交文書にも登場するほど軽視すべからざる存在であったのかも知れない。このツツガムシとはどんな虫かと言うと、体長1、2ミリ程度のダニの仲間である。人の血を吸い湿疹かぶれを引き起こすのみならず、ツツガムシ病を撒き散らすとんでもない虫なのである。それはそうとツツガムシのツッチーは先程から、遥か彼方の母を訪ねて複雑に絡み合い迷路となったカーペットの繊維を行きつ戻りつ、大きく回って元に戻ったりしながらさ迷っていた。「母さん、母さんに会いたい。」ツッチーの願いは3次元に絡まり合う合成繊維の密林に虚しく跳ね返りこだまするだけであった。実は直線距離で僅か3センチ先に見果てぬ我が母は食事を求めてうろついていたのだった。ツッチーはひたすら母を求めて旅した揚げ句、あと一歩の所で不気味な地響きと猛烈な暴風に襲われ、必死の抵抗も虚しくついに吹き飛ばされてしまった。渦巻きと他の塵もろとも翻弄されて、更に埃っぽく蒸し暑い所で気を取り戻した彼は、なんと偶然にも同様に吹き飛ばされた、思い焦がれた母との再会を果たすことになった。ひしと抱き合う母と子。これでツッチーの母を訪ねた3センチの旅は終わりを迎えた。ただこの感動のひとこまは、ゴミパックが取り出されて、焼却場へのゴミ出しの日までである事は知る良しもない。「恙無きや。」
2020.10.04
コメント(7)
-
我が良き虫の世かな ~ こおろぎの鎮魂歌
男はこの暮らしを始めて20年に近くなる。俗に言うホームレスである。以前はましな生活を送っていた事もある。地方では大きな部類に入る会社の支店で経理を任されていた。しかし40歳を過ぎたある日、それは突然やって来た。業務上横領彼の罪状である。事が発覚して支店は騒然となったが、社長の一声で不問に伏す代わりに懲戒免職となった。典型的な一族会社であり、支店長を勤める一人息子の経歴に傷が着くのを恐れたためだ。社長にとって幸いな事に、この事実を知る者は、支店の一部のみだったため、それぞれを他の支店の支店長や上級幹部に抜擢して、懐柔を謀り揉み消した。しかしやがてマスコミに知られる事となり、スキャンダルから社長は失脚し、その会社も信用を失墜して、間もなく会社更正法の適用を申請して、事実上の倒産の状態となってしまった。すべてのきっかけとなった彼は、突如職を失い、退職金もなく、妻は家を出て、子供も頼れる親戚もなく、噂は地方ではどこまでも彼を追い詰め、職を求めて大都会東京に出て来た。おりしも世界的不況から職にはありつけず、資金も底を尽き、この川岸のテント生活を始めてもう20年近くになる。男は突然倒れ、食べる物もなく、動く事も、声を出す事も出来ず、ただ生死をさ迷う意識の中に横たわっていた。ホームレス仲間も皆離れた所に住み、彼を訪れる者は週に一度くらいだった。男はこのまま、誰にも看取られずにあの世に行く事になるのだろうと思うと、一抹の淋しさを感じたが、これもひとえに自分の業が成した事。相応しい最期かも知れないと思うと、気持ちも何故か落ち着き、身動きもままならない体におぼろげな意識を委ねていた。するとその時、耳元で一匹のコウロギが鳴き出した。コロコロ、コロコロコロ。その済んだ鳴き声に耳を傾け、昔を思い出した。コロコロ、コロコロコロ。父にせがんでコウロギを捕まえてもらい、毎日餌をやって、コウロギの鳴き声を聞きながら眠った事を。コロコロ、コロコロコロ。あの時のコウロギの声と同じである。コロコロ、コロコロコロ。男は目尻に一筋光を宿すと旅立った。コロコロ、コロコロコロ。コロコロ、コロコロコロ。コロコロ、コロコロコロ。もう聞く者もいなくなったテントの中で、コウロギは相変わらず鳴き続けた。コロコロ、コロコロコロ。
2020.10.01
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ 蜘蛛という商売
「俺も随分長くクモをやっているが、こんなに獲物が来ないのは初めてだ。この空き家に巣くってかれこれ3週間にもなるが一匹の小バエさえ来やしねぇ。あー腹減った。何か喰いてぇー。」と一人愚痴っていたクモは一つの影が近づくのを感じた。「おお、遂に獲物か?」とワクワクして影の方に目をやると、それは頭を覗かせた。暗闇でまだよく見えない。しかしどんどん進んでくる。やがて顔が明るみに出て来た。「ゲゲー!ムカデじゃないか!シッシッあっちに行け!」クモは巣の反対側まで移動してひたすら立ち去るのを待った。ムカデは未練がましく背を伸ばしたものの、クモの巣の上を歩こうとすれば、自分の方が餌になってしまう。やがてあきらめ立ち去った。それから悲しい事に2日間何事もなく過ぎた。あの時ムカデとやり合ってみても良かったかと思い始めていた。逆にやられたにしても、今のひもじさよりもまだマシな気がした。ムカデはあまり好みとは言えないが、これも今のひもじさよりもまだマシな気がした。そんな事を考えていると床で何かが動いた様な気がしたので、息を殺して四つの目でじっと見つめた。確かに何か動いたはずだが。しかし、それっきり何も動かない。また待つしかない。その頃壁一つ隔てた外壁に堂々とした網を張り、その真ん中にどっかり居座るクモがいた。林に近く、軒下には花が咲き乱れ、近くには街灯もある事から、夜も昼も取っ替え引き替え客いや餌食は絶えなかった。「えー?またトンボかよ。どうもトンボはすかすかでうまくない。まあ喰うのには困らないし、運動がてらにはずしてやるか。ほらよ!もう2度と引っ掛かるんじゃねえぞ坊主。」と、壁一つ隔てて反対側に住むクモには到底考えられない毎日を満喫していた。「ビジネスは立地と察知とタッチだ。よい場所で周りの状況を的確に掴み、素早く動いて獲物にタッチだ。昔の様にただ網を広げて待っている時代じゃない。さあ次行くぞ。」と下の通りを営業部長が部下に発破をかけながら、ずんずん進んで行った。
2020.09.27
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ 虫たちの競演
スズムシ君は前から楽しみにしていた昆虫パーティーにやって来た。パーティー会場に入るとクツワムシやミンミンゼミなど賑やかな連中から、アリ、アメンボウと言ったいたって静かな連中までが楽しげに談笑していた。スズムシ君が中に入って行くと、ウマオイのおばさんが一口食べるたびに「うまー美味しい。うまー美味しい。」と言うもんだから、カメムシはふて腐れて「固くて俺、全然かめんし。」と言った。その隣にいたおばさんが、「あらあたし、噛み切りましたわよ。」というので振り向いたら案の定カミキリムシが済まして立っていた。このおやじギャグ三連発を聞いた他の虫達も口々におやじギャグを飛ばし始めて、昆虫パーティーは益々賑やかになって行った。そこに体は小さいが飛び切りの美少女が入って来たのでオス達は急に色めきたち、少女奪え(ショウジョウバエ)と擦り寄ってご機嫌を取り始めたものだから、そこはかとない姿の気品の高いある貴婦人が、えっ?そんな下品な事を?という言葉を囁いていた。よく耳をそばだてて聞いてみると彼女は消え入りそうな声で、「薄バカ下郎。」と罵っていのだ。スズムシ君は大おやじギャグ大会と化した昆虫パーティーにいささかげんなりし始めた。冬にテントウムシのおばさんが忠告を無視して越冬していた岩影から転げ落ち、「言わんこっちゃない、俺達ゃ転倒無視。」とおやじギャグを飛ばして、一同に益々寒い思いをさせたナナホシテントウムシのテン七おやじ(我がよき虫の世かな ~ナナホシテントウの寒~い一日~... )が懲りもせず未だに「俺達ゃ転倒無視。」と一人で受けていたが周りはしらーとしてしまった。しかし、この下らない駄洒落を聞いてもけらけら笑う、そうご名答、ケラのおばさんの陽気な笑い声に昆虫パーティーは再びおやじギャグオンパレードへと戻って行った。普段全く寡黙なナナフシの爺さんまで、「おお!これは七不思議じゃ。」と何が七不思議かさっぱりわからないギャグを言い出す始末。昆虫パーティーは大合唱となった。無論人間達にとってはただの虫がやかましく鳴いている競演に過ぎないのだが。普通おやじギャグと言うと木枯らしが首筋を吹き抜ける様な寒さをもたらすものだが、昆虫パーティーでは次第に熱気を帯びて行った。スズムシ君は会場を抜け出し、風通しの良いひんやりした場所まで来るとぽつりと言った。「暑いのは苦手だよ僕。だからここでしばらく涼むし.....」
2020.09.24
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ 恐るべしミツバチ社会
子供達の歓声が上がり、育児室はもう大変。育児係の働きバチはそれこそハチの巣を突いたような大騒ぎだった。ここはミツバチの巣箱の中。今は真冬で外は凍える寒さだろう。こんな寒さの中に放り出されたら半日も生きていられないだろう。しかし、ミツバチの巣箱の中はすこぶる快適なのだ。なにせ冷暖房完備なのだから。ミツバチの巣箱はミツバチの体温で快適な室温に保たれている。暖房完備のお陰で、こうして子供達を安全に恵まれた環境で育てられるのだ。では夏は?夏は夏で、たくさんの働きバチが巣箱の出入口に陣取り、新鮮で冷たい風を羽を使って送り込んでくれるから、冷房完備となる。ミツバチの巣箱マンションは育児室まである、実に快適な近代マンションなのだ。余談だが、ミツバチの体温の使い方として逆に恐ろしい使い方がある。スズメバチなどが襲って来たら、アメリカンフットボールでディフェンスが一人の敵に対していっせいにギャングタックルを仕掛ける様に、たくさんの蜜蜂がそのスズメバチに寄ってたかって、体温で熱死させてしまうのだ。恐るべしミツバチ社会。
2020.09.20
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ 超虫集合
高いビルは飛べないけれど、1mmたりとも飛べないけれど、75,000気圧の高気圧に耐え、0気圧の真空にも耐え、摂氏150度にも絶対零度(摂氏マイナス273度)にも耐え、人の致死量の12万倍の放射能や電子レンジのマイクロ波照射に耐え、120年の乾燥後に水でよみがえる僅か数ミリのこの体。ある時は落ち葉の間に、ある時は水草に身を任すかと思えば、超深海底にも高山にも住むし、温泉の中でもああいい気持ち。而してその実体は?そう人は私をクマムシと呼ぶ。前後半分に切られれば、頭側から尻尾が、尻尾側から頭が。前後左右4分の1に切られれば、右頭側から左頭、尻尾が、左頭側から右頭、尻尾が、右尻尾側から左尻尾と頭が、左尻尾側から右尻尾と頭が。更に16等分に切られれば、・・・・・ややこしいので止めておく。私の100等分は100人の私となる。3センチに満たないこの体、人は私を切り刻み、加虐の快感に酔いしれる。そんな私を人は、プラナリアと呼ぶ。体長5ミリ前後、脚力には自信あり。並外れて発達したこの太腿を見て欲しい。機能的でありある面機械的でもあるこの美しい太腿。競輪やスピードスケートのトップアスリートでも、文字通り足元にも及ぶまい。もし私が人間並の大きさなら、最高到達点はなんと80~100m。そうだなぁ通天閣に匹敵する高さと言えばいいか?そう、お分かりだね。我輩の名はノミである。
2020.09.17
コメント(5)
-
我が良き虫の世かな ~ スキップ
ムカデは小高い丘の上から下の公園を見下ろしていた。まだ小学校前の幼児達が屈託のない歓声を上げながら走り回っていた。鬼ごっこに砂遊び、ボール投げにブランコ。子供達の笑顔、笑顔、笑顔。笑顔で満ち溢れていた。ムカデはそんな様子を伺いながら、頬えましくも羨ましくもあった。ふと公園に続く小道に目を向けると、ひとりの女の子がスキップしながら楽しそうにやって来る所だった。ムカデはその子のスキップを見ると無性に自分もやってみたくなった。右ちょん、左ちょん、右ちょん、左ちょん。楽しげで軽やかなステップ。右、左、右、左、・・・元来跳ねる事の出来ないムカデは、交互に片方ずつすべての足を振り上げるのみで、相撲取りの四股よろしく、とてもスキップと呼べるものではなかった。「ううん、こうかな?」ムカデは奇数番目と偶数番目に分けて足の上げ下ろしをやってみた。しかし、これだけ足があると頭の中がごちゃごちゃになり、自分でも訳が分からなくなりそうだった。これでは人間のムカデ競争を見て笑う事など出来ない。2本ずつ3本ずつ上げる事も試したが更に本数を考えるだけで、更に混乱してしまった。ムカデは暫く考え、足を自分の真ん中から前後のグループに分け、更に前後のグループを左右に分け、前後のグループで左右を互い違いに出す事にした。やってみると、とても軽やかとは言い難いが、それでも何となくリズミカルで楽しい気分になった。右前、左後ちょん、左前、右後ちょん、右前、左後ちょん、左前、右後ちょん、・・・ムカデはだんだん楽しくなり、人間なら鼻歌でも歌いたい気分で小高い丘の草むらを歩き回るのだった。もしもこれを人間が見たら、目をむいて驚いた事だろう。
2020.09.13
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ 自然の摂理
暖かな日差しが照り付け、少し暑ささえ感じる秋の昼下がり、にこにこ幼稚園のなかよし花壇では、蝶が残った花の中を盛んに往きかい、その花の奥に秘められた甘い蜜を一心に貪っていた。そしてひときわ大きな真っ赤な花に吸い寄せられる様に、一ひらの蝶が近付いた時、鋭い鎌が一閃された。哀れな蝶はたった今我が身に起こった不幸が何なのかを確かめる様に見回し、自由を奪った物から逃れるべくもがいた。しかし、それは鋼の強さでびくともしない。薄れ行く意識の中で、自分を掴む物、そう鎌の向こうに見える小さな三角形の顔を見た。三角形の両角に鋭い眼光を宿す目を持つその顔はそっと語りかけた。「すまねえな。俺も喰わなきゃ生きて行けないんだ。その代わりと言っちゃ何だが、この花に来たやつだけいただく事に決めているんだ。おまえ達も甘い蜜を吸わなきゃ生きて行けないのだからな。」蝶は仕方がないと悟り、鎌に身を委ねた。こうして自然の摂理は満たされた。この花壇の主と恐れられる、大カマキリは鎌に残った獲物の残滓を嘗め取りながら、元いた花の影へと戻っていった。花壇の片隅で起きた悲劇の事など知らなげに、いつもの一日は過ぎて行った。秋も深まって来た頃、なかよし花壇の花もほとんど枯れてしまい、例の大きく真っ赤な花もしょぼくれた花びらを脇に垂らして傾いていた。ここの主の大カマキリは、花にとって代わる様な真っ赤な夕日が作る長い長い影の先に映る自分の影を見つめながら、長かった夏の間この花を訪れ、自分のために逝って行った者達の事を思い返していた。今では食べる物もめっきり減って、己の命を保つのに汲々とする有様である。そんな思いを巡らしながらただぼんやりしていると、やがて夕日に引き伸ばされた影にもう一つの影が近づいた。なかよし花壇の主の称号に違わない、ずっしりと大きな体になった大カマキリは更に大きな影に振り向いた。その影は夕日を背にそっと彼に告げた。「あんた、そろそろ時間だよ。」大カマキリは相変わらず鋭い眼光を留めたまま振り向いてうなずいた。「そうか、わかった。」こうして彼もまた自然の摂理に従った。
2020.09.10
コメント(9)
-
我が良き虫の世かな ~ 男の季節
ツンツン、ツンツン。アリがお尻をつっつくとアブラムシはお尻を上げてお尻の先から蜜を出してやった。「さあ召し上がれ。大事な大事な用心棒さん。」この間ナナホシテントウ虫の襲撃があったときも、果敢に追い払い、わずか4匹の娘と2匹の孫娘が犠牲になっただけですんだのだし。「あっ、そこのいかしたアリのお兄さん、あの辺りに娘達がたくさんいるわよ。その辺りは孫娘達だから、いまいち蜜の出が悪いかも知れなくってよ。」グランドマザーは手際よくアリに娘達を割り当てながら、アリのお食事タイムを切り盛りしていた。「どう?私の娘達が出す蜜は格別だろう?もっとも娘や孫娘と言っても、私たち女だけで生んで来た遺伝子が同じ子供、いや私自身の様なものだけどね。」グランドマザーが満足そうに見渡していると、「お婆様、私もそろそろ子供を産もうかと思うの。」やっと一人前のアブラムシに成長した孫娘がやって来てこう言った。グランドマザーはにっこり笑って、「まあ、もうあなたもそんな年頃になったのね?頑張って元気な私を産んでおくれ、このオマセさん。」やがてその子は元気な男の子を産んだ。男の子?それを見てグランドマザーは感慨深げにつぶやいた。「夏も終わりもう秋。そろそろ男を産む季節だねえ。」こうして何度も女達は『私』だけを産んで来た。アブラムシ達は時期が来ると、自分達で男を調達し、交配し単一の遺伝子による種の衰退を防いでいるのだ。グランドマザーは生まれたばかりの男の子を覗き込み、「まあなんて可愛い子かしら。私の夫にしようかしら。」と目を細めた。「生まれてからずっと、未婚の母だったけど、そろそろ身を固める潮時かしら。」グランドマザーはなまめかしい視線を送りながら囁いた。「ねえあなた、私の事オリーブって呼んでくださる?」
2020.09.06
コメント(4)
-
我が良き虫の世かな ~ 大きな赤い花
野原に大きくて真っ赤な花が咲いていた。真っ赤な花は真っ赤な花びらの真ん中に黄色い花粉のクッキーとあまーい、あまい蜜の壷を置いて、虫達が遊びに来てくれるのをいつも楽しみに待っていた。そして今日も、「花さん、花さん今日もとってもおきれいね。今日もご馳走になっていいかしら?」と蝶々さんがやって来た。花は嬉しくて、「どうぞ、どうぞ。沢山用意してありますから、お好きなだけ召し上がれ。」と明るい声で言った。今度は蜜バチ君が、「花さん、花さん今日もとってもいい香り。またおいしい花粉のクッキーいただいてもいいかな?」とやって来た。赤い花はまたまた嬉しくて、「あら蜜バチ君こんにちわ。遠慮なく沢山召し上がれ。帰りにはいつもの様に、花粉のクッキーをお土産にどうぞ。」と温かく迎えた。それからコガネ虫さんも、テントウ虫さんもやって来て、みんなでペチャクチャおしゃべりや笑い声で楽しく過ごしたが、やがてみんなはしゃべり疲れて、うとうとお昼寝が始まった。大きな赤い花は優しい歌声で、歌ってあげた。夕方になると虫達はそれぞれのねぐらに帰って行った。蜜バチ君も花粉のクッキーのお土産を足にたくさんくっつけて、巣にいる仲間達の所に戻って行った。大きな赤い花はとっても幸せな気持ちで、また夜の内に明日も虫達にご馳走する花粉のクッキーと甘い蜜をせっせと作り始めた。ところが、その晩急に嵐がやって来て、赤い花は風に引き裂かれ、花粉のクッキーも甘い蜜も激しい雨に打たれて流されてしまった。やっと朝が来て嵐も去った後、そこには花びらはほとんどなくなり、クッキーのお皿も蜜の壷もなくした花の哀れな姿があった。立っているのが精一杯だった。花はもう虫達と楽しく歌ったり笑ったり出来ないと思うと、悲しくて悲しくていつまでも泣いていた。泣いて泣いて泣き疲れた頃、ふと呼ばれる声に気付いた。「花さん、花さん悲しまないで。今日は僕達ハチからプレゼントだよ。」と沢山の蜜バチがやって来て、口から出すロウで花の周りを塗り固め、花びらを作ってくれた。「花さん、花さん悲しまないで。今日は私達からのお礼です。」と言って蝶々達が、ハチ達が作ったロウの上に羽の粉を少しずつふりかけて、色鮮やかな花びらが出来上がった。花は喜んでお礼を言ったが、すぐに、「でももうみなさんに花粉のクッキーも甘い蜜もご馳走出来ないんです」と泣き始めてしまった。そこにコガネ虫達が、「なーに、俺達仲間で木の汁をたくさん集めて来たぜ。花さんの蜜ほどうまくねえかも知れないけど、またみんなで食べて、しゃべって、歌おうぜ。」とやって来た。こうして大きな赤い花の周りはいつも虫達が集まり、自分達で持ち寄った蜜やクッキーを食べながら、賑やかな一時を過ごす様になり、そこにはいつも大きな赤い花の一際高い笑い声が響き渡っていた。
2020.09.03
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ ビートル将軍
「ビートル将軍、第3要塞が突破されました。地下シェルターに退避願います。」カブト虫のビートル将軍は目をつむり、瞑想するかの様に佇んでいた。「いや私は結構。君達こそ退避してくれたまえ。今までよく尽くしてくれた。礼を言う。『ありがとう』私は死んで行った者達の元に留まる。」「将軍・・・・・・」それはまだ数時間前だった。人間どもが大挙して押し寄せ、虫達の家を踏みにじり、ひっくり返し、女子供も容赦なく連れ去り、あらん限りの破壊の爪痕を残し、今最後の砦に迫ろうとしていた。中でも悲惨を極めたのがブロックや石や腐葉土を寝ぐらとするダンゴ虫達だ。彼等は危険が迫ると丸まって身を守るしか術を持たない。反撃するなどまるで出来ない者達だ。逃げ足も遅く、ミミズの様に地下に潜る事もできない。人間達は虫達が食料としていた草も、それこそねこそぎ略奪して行く。ほとんどの虫達はただ逃げ惑うのみだった。だが若干ではあるが抵抗を試みる者もいた。「サンダーホーネット第5中隊、ブン太少佐が敵の右腕に毒針を命中。敵は退去しました。」指令本部は一斉に歓喜に満ちた。「しかし、毒針は少佐の内臓ごと脱落。ブン太少佐は戦死されました。」「うん、彼を大佐にニ階級特進せよ。奴は鼻っ柱が強く、時には樹液をめぐり争った事もあるが、残念だ。」ビートル将軍はうなだれた。「ムカデ戦車隊の百郎隊長は、敵の指先に後一歩の所まで迫るも、発見され長靴の下で圧死。」「あいつと私はまだ地中で幼少の頃からの付き合いだったが、腹が減っていないときは、物静かな男だった。」「将軍、報告します。ただいま野バラのロージーさんが、敵の指先に彼女の棘で一矢を報いた模様。」ビートル将軍は一瞬表情を緩め、「民間人である彼女のけなげな反撃に、尊敬と称賛の意を表したい。」と言ったが伝令は、「しかし彼女は強制撤去されました。」と続けた。それを聞き将軍の瞳は悲しみに満ち溢れ、椅子に突っ伏してしまったのだった。やがて一人となったビートル将軍は、去って行った者達の事に思いを巡らせていたその時、いきなり天井が引きはがされ、夕日の赤い日差しがなだれ込んで来た。その夜、町の公民館では今日の合同草苅の慰労会が開かれていた。世話役の自治会長が、「泰造さんは蜂に刺されたらしいけど大丈夫かい?」と聞いた。泰造さんは、「なーにあんなもん、ションベン引っ掛けときゃなんでもねえよ、会長。」と得意げに笑って、うまそうにビールをあおった。「さすがは年の甲。」と自治会長も笑いながらビールをつぎ足した。その横では、子供達が紐で繋いだ大きな栓抜きを一生懸命引っ張る、かつては将軍と呼ばれたカブト虫が一匹。
2020.08.30
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ 蚊の不満
蚊はとても不満だった。何がって自分の呼び名が。だって蚊だぜ。そうただの『カ』だけだからだ。もっと名前の付けようがあると思うのだが。例えば、羽が二枚しかないから『フタハネ虫』とか、体が細いから『ホソミ虫』とか、独特の甲高い羽音から『ウナリ虫』とか、薮によく住んでいるから『ヤブ虫』とかちょっと考えればいくらでもありそうなものなのにただの『カ』だけだなんて、何とも理不尽だし、名付け方が余りにもいい加減だと思うのだ。我が子の幼虫期には『ボウフラ』という立派な名前がある。幼虫期で他に名前を持っているのは、トンボの『ヤゴ』とか、ウスバカゲロウの『アリジゴク』などそんなに多くはない。しかもボウフラの場合、蛹期には『オニボウフラ』という勇ましい名前まで付けてもらっているのに、『オニボウフラ』から羽化するとただの『カ』とはどういう事だ?同じ様な不満を鳥の『ウ』も漏らしていると聞いた事がある。おまけにあちらは、人の話をよく確かめもせずに信じて、後から馬鹿を見る事を゛鵜呑み゛にすると完全にアホ扱いだ。それより少しはマシとは言っても、考えれば考えるほど蚊は情けないやら悔しいやら悲しいやら。だから蚊は人間の血を吸って復讐してやろうと思ったのだ。
2020.08.27
コメント(7)
-
我が良き虫の世かな ~ 華と咲く虫
地上に飛び立ち僅か1週間しか生きられないセミは、実は地中で7年間も幼虫時代を過ごす、虫の中では長寿な生き物なのだという事をご存知だろう?アメリカでは、更に13年周期と17周期の13年ゼミと17年ゼミがいて、この周期性の謎が科学者の間で盛んに論議されている程だ。先日アメリカのあるアイスクリーム屋がセミ入りアイスを出したところ予想に反して大ヒット。しかし当局から発売禁止命令であえなく消えたという話題もあった。シロアリの女王アリは100年以上生きるものもいるらしいが、これは別格としてもやはり長寿なのだ。セミの幼虫が7年も生きると言うと、「でも暗い地中の中ででしょ?」とか「お日様を1週間しか見られないんだよ。」という反論が返ってくる。だが人間の感覚で虫の世界を推ってはならない。地中にいるのが不幸なら、暗闇にいるのが不幸なら、ケラやミミズは悲劇の主人公、ロミオとジュリエットどころではないではないか。勿論そんな事はない。彼等はそこに好んで住んでいるのであり、それが幸せなのだ。もうすぐ夏。地中ではセミの幼虫達の卒業式が開かれていた。「送辞。6年生の皆さん。長い間僕たちの優しいお兄さんお姉さんとして、遊んでくれたり、教えてくれたり、励ましてくれだり、注意をしてくれたりして、幼稚園から7年間本当にありがとうございました。・・・・・・・」 :式は続いて、 :「卒業式もそろそろ終りです。それでは6年生の皆さん一人一人から答辞をいただきたいと思います。」「在校生の皆さん、私たちは間もなく旅立ちます。皆さんと過ごした7年間とても楽しかったです。」「僕はきっと素晴らしいお嫁さんを見つけて卵を産んでもらいたいと思います。」「私は大きくて丈夫な卵を産みます。」「僕は大きな音で思い切り鳴きたいと思います。」「僕も大きな声で負けないように頑張ります。」 :最後にメソメソ泣き虫のミンミンが残った、 :「私はもっとここにいたかった・・・」と、消え入りそうな声で話し始めたが最後に、「後一週間しか生きられないと思うと悲しいし寂しいけど、これが今までのご褒美と思って一週間を思う存分楽しみたいと思います。」とはっきりした大きな声で締めくくった。会場から一際大きな拍手と歓声が沸き上がった。奇しくもミンミンが言ったように、地上で一週間しか生きられない事をセミ達は悲観しているばかりではなく、最後のひとときをパッと花開かせる、そう、7年間の光跡を残し、最後に大輪の花を咲かせる花火の様な虫なのだと私は思うのだ。 :式はようやく終わり、 :一匹また一匹、背中がむず痒くなると地上へ出て行った。
2020.08.23
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ ゾウリムシ君の優雅なお食事
「マー君、汚いでしょ。そんな所に手を浸けちゃ。」マー君は顔を曇らせると指先の木の葉の船を見送った。「そんなドブ川で遊ばないで、さあ家に帰って手を洗って。マー君の好きなシュークリーム買ってきたわよ。」お母さんは買い物帰りの玄関先からマー君に声をかけ家の中に入って行った。マー君もシュークリームと聞けば木の葉の船などもうどうでもいい。ニコッと笑うと元気にお家へと走り出した。その頃そのドブ川ではゾウリムシ君が、今日もおいしいランチに舌鼓を打っていた。「うまい。実にうまい。このバクテリアはいつ喰っても実にうまい。正に珍味中の珍味。グルメの俺でさえつい唸ってしまうくらいだ。」ゾウリムシ君はたくさんのせん毛をせわしなく動かしながら、久し振りに見つけた超レアなバクテリアを取り囲み、取り込んで行った。「あー喰った喰った。この川は栄養付加が高く、バクテリア類も多く、こんな特急グルメにもありつけるって訳だ。幸せな気分だぜ。」ゾウリムシ君、ゾウリムシに出来る範囲でせん毛を伸ばして背伸びをした。その時、何やら毒々しい液体が流れて来た。妙な匂いもする。気分が悪くなりそうだ。暫くその液体はゾウリムシ君の周りを淀み、ようやく去って行った。しかしゾウリムシ君の繊細なお肌はまだピリピリしており、あの状態が続けば、命にかかわったかも知れない。「マー君ダメでしょ。水道出しっ放しよ。」「あっ、いけない。」マー君は慌てて洗面所に戻り、今石鹸でゴシゴシ洗った綺麗な手で蛇口を閉めると、食卓テーブルにすっ飛んで行った。「ワー、おいしそうなシュークリーム。いたたきまーす。」
2020.08.20
コメント(8)
-
我が良き虫の世かな ~ 黒いクモ
大きなイエグモが薄暗い下水路を歩いていた。今までいた家で殺されかけたのを辛うじて逃れて来たところだった。何をしたわけでもなくただ気味が悪いという理由だけでだ。彼は大いに憤慨していた。「俺が何をしたって言うんだ?世間一般にイエクモはゴキブリなどを捕ってくれる益虫だって言われているのに、あの家の奴ら何にも分かっちゃいねえ。」クモは思い出すたびにはらわたが煮え繰り返る思いで側溝を伝い歩いていた。その時突然声がした。「ねえパパ見てあそこ黒いクモ。」女の子の声だ。クモはしまった見つかったと一瞬立ち止まった。間もなく父親の声が聞こえた。「ああホントだ。やな感じだな。」クモはこの言葉にドキリとした。人間の父親というものは子供特に娘の前では頼もしい存在であろうと、何をするか分からない事が往々にしてある。クモはこんな所に長居は無用と猛ダッシュを始めた途端再び父親の声がした。「かなり動きが速いな。」クモはドキリとして再び立ち止まった。「いかん、追跡監視されている。」クモはこのまま止まっていれば溝の壁に溶け込んでしまえるかの様にじっといていた。「ねえパパどうする?」娘が言うとすぐに父親の声が返って来た。「どうするって・・・・」『パパが叩き殺してやるよ。』という言葉が返って来るものとクモは覚悟した。「残念だけど今日はプールは諦めて帰ろう。もうすぐ大雨が来るぞ。」父親が言うと娘は「チェーッ!」と言いながら二人は帰って行った。「何だ!?黒いクモって空の黒い雨雲の事かよ?まぎらわしい脅かすんじゃねえ。」と毒づきながらクモもその場をそそくさと去って行った。
2020.08.16
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ 大いなる野望
スズメガと呼ばれる大型の蛾の幼虫もまたその大きさは並ではない。男性の人差し指くらいは裕にあるだろう。彼もやはりその大きな体を木の枝に横たえ、朝から一心不乱に葉っぱを食べていた。彼には大いなる野望があった。それは、『他のどのオスよりも大きく、立派で、色艶のある羽を持ち、メス達の注目を集め、その中の類い稀な美貌のメスに見初められ、結ばれ、真珠の様な卵を葉っぱに溢れんばかりに生み付けてもらう』事だ。そのために彼は今朝から食べ続けているし、いつもの様に深夜まで食べ続けるのだ。彼はいつか彼の子供達が彼と交配相手の素晴らしい遺伝特性を引き継いで、夜の空を飛び回るのを想像し、恍惚感に浸りながらなおもひたすら食べ続けた。やっと梅雨も開け夏真っ盛り。日差しの暑さに辟易しながら通りすがった得意先回りのサラリーマンは、今月もトップセールスになり出世一番乗りを目指していた。吹き出る汗をぐしょぐしょのハンカチで拭き拭き、彼を見上げ、「イモムシはいいよな、ただ食べてればいいんだから。」と呟きながら足早に通り過ぎて行った。
2020.08.13
コメント(4)
-
我が良き虫の世かな ~ 展覧会の招待状
森の奥である昆虫画家の個人展覧会があり、沢山の虫に招待状が届いた。しかしその招待状の出品者名をめぐって一騒動が起きた。作品の絵は前衛的な色使いの幾何学的な背景の真ん中に、精緻に描かれた超写実的な花の絵を描き、抽象絵画と写実絵画の融合が見事に織り成された画風で虫達を魅了した。しかしその招待状の画家名の所が、印刷の汚れで蛾(が)か蚊(か)かよく分からなくなっていた。蛾の仲間は、こんな前衛的な絵を描けるのは我々蛾族しか有り得ないと、蚊の仲間は、こんな繊細な絵を描けるのは我々蚊族にしか出来ないと、互いに主張し合った。蛾の仲間は、蚊にはこんな美しい花は描けまい。せいぜい血の滴る牛肉位しか描けないだろうとせせら笑った。蚊の仲間は、蛾にはこんな前衛的な色使いの幾何学模様は無理だろう。せいぜい自分の羽の模様を描き写す位の独創性しかないだろうとやり返した。他の虫達も、蛾と蚊のとんだ中傷合戦にうなづいたり、眉をひそめたりしたが、確かに絵画の出来自体は素晴らしいとしか言いようがなかった。そこで幼虫時代から数えると虫歴7年のクマゼミ親分が一肌脱いでこう提案した。「まあまあ蛾さんも蚊さんも、ここはワシに免じて下駄を預けてはくれねえかい?ワシワシ」これには蛾も蚊も、クマゼミ親分の言うからにはと一旦引き下がる事になった。そこでクマゼミ親分は招待状の印刷元であるシロアリ印刷店に出掛けて、シロアリ爺さんに尋ねる事にした。シロアリ爺さんは暗い作業場のくたびれた椅子に座り、分厚い眼鏡の底からクマゼミ親分を見つめて、すまなそうに言った。「すまねえクマゼミ親分。最近は一段と目も耳も遠くなっちまってなあ。なんだって?」クマゼミ親分は先程から辛抱強く、個展の招待状を見せたり、大きな声で何度も繰り返して聞くのだが埒があかない。堅気にはめったに取り乱さないクマゼミ親分も、遂に切れてついつい大声で怒鳴った。「ワシワシワシワシ、あのなあ爺さんよく聞けワシワシワシワシ、この招待状のなあワシワシワシワシ、ワシが聞いているのはなあワシワシワシワシ、こう言う事だワシワシワシワシ!」クマゼミ親分は招待状を振りかざし、「ワシワシワシワシ、この招待状の『画家が、蛾が画家か?蚊が画家か?』てえ事だ!!」哀れなシロアリ爺さんは訳が分からず、「が?か?が?か?・・・」と繰り返し、目をパチクリするだけだった。
2020.08.09
コメント(6)
-
我が良き虫の世かな ~ 昆虫大相撲
昆虫大相撲本場所がまた賑々しく開催される。とは言ってもすべての虫が揃うのは夏真っ盛りの7月の初場所兼夏場所兼本場所の年一回なのだが。東の横綱はもう25年も代々カブトムシが務めていた。なんと297連勝中である。西の横綱はミヤマクワガタ。木の上では自慢のクワを使って互角に渡り合えるのだが、平地の土俵となると勝手が悪く、全勝対決で後一歩の所まで行った事もあるが、もう何十年も勝てていない。東の正大関は大カミキリムシ。格下には部類の強さを発揮するのだが、圧倒的な強さの2横綱には歯が立たない。西の正大関は小兵ながらカナプンが務めていた。相撲となると甲虫類がなんと言っても強く、カナプンも甲虫類特有の力と体重と盤石の擦り足で断然有利だった。東の張出し大関はバッタ類ながら類い稀な体力を持つクツワムシ。更にトノサマバッタ、キリギリスの両関脇にスズメバチ、タガメの小結達が続く。水棲昆虫のタガメは水の中ではカブトムシにも負けない強さなのだが、地上だと踏ん張る力と息が続かないためどうしても不利だ。同じ水棲昆虫のゲンゴロウは前頭十五枚目、今場所負け越せば幕内陥落の可能性もあった。だから必死だ。ここまで5勝7敗と後がなく、しかもどういう訳か今日は横綱カブトムシとの対戦だ。ゲンゴロウは色々策を張り巡らしていたものの、これと言っていい案も浮かばず、控え席で結びの一番を緊張しながら待っていた。ゲンゴロウは今まで策を巡らしながらどうにかここまでやって来た。しかし横綱戦となると何をやっても無駄に思えた。立行司は去年までのスズムシが余りにも迫力がないという事で、今年からミンミンゼミに代わった。呼出しがかかり、いよいよ本日結びの一番である。桟敷席の客も審判もムシHKのアナウンサーも解説のタマムシ親方も横綱もゲンゴロウ本人も番狂わせが起こるなどとは思ってもいなかった。ゲンゴロウは緊張ともう後がないという悲壮感から、がくがくしながら土俵に上がった。「どうしよう、どうしよう。」そればかり考えていた。ここで断っておくが、元々四つん這い、いや六つん這いの昆虫大相撲にはひっくり反るか押し出されるか、吊りだされる以外負けはない。余裕の横綱とそわそわのゲンゴロウでは結果は明らか。新聞記者は翌朝の記事を書き始め、観客は千秋楽の前人未踏の300連勝達成の話しに花を咲かせ、審判の何人かは審判席で居眠りしていた。いよいよ軍配が反った。ゲンゴロウは土俵の端で蹲踞(そんきょ)の姿勢から猛然とカブトムシに向かって走り出し、あわやがっぷり六つの寸前にUターンして元いた土俵の端に駆け戻った。こんな小細工など気にする風でもなく横綱はにやにやしながら、のしのしと前進して来た。場内も大爆笑である。ゲンゴロウは土俵際から行き場を失い再びUターンし、横綱に向けてもう一度突進した時それは起こった。なんとカブトムシの6本の足の間を擦り抜け、ゲンゴロウは横綱の後ろに飛び出してしまい、そのまま土俵の反対側にすっ飛んでしまった。これには場内も更に大爆笑。がしかし次の瞬間驚愕のどよめきに満ちていた。ミンミンゼミの行司の軍配はゲンゴロウへ。新聞記者は茫然、観客は唖然、審判は愕然。行司だけが毅然と立ち、そのまま止まれず進み続けたカブトムシの足がゲンゴロウよりも一瞬早く土俵を割るのをしっかり見定めていた。こうしてゲンゴロウは一躍新聞トップを飾り、カブトムシはショックで千秋楽の横綱対決に破れ、26年振りにミヤマクワガタが東横綱となった。もっとも結局ゲンゴロウは負け越し、十両転落となってしまったのだが。
2020.08.06
コメント(4)
-
我が良き虫の世かな ~ 昆虫大相撲
昆虫大相撲本場所がまた賑々しく開催される。とは言ってもすべての虫が揃うのは夏真っ盛りの7月の初場所兼夏場所兼本場所の年一回なのだが。東の横綱はもう25年も代々カブトムシが務めていた。なんと297連勝中である。西の横綱はミヤマクワガタ。木の上では自慢のクワを使って互角に渡り合えるのだが、平地の土俵となると勝手が悪く、全勝対決で後一歩の所まで行った事もあるが、もう何十年も勝てていない。東の正大関は大カミキリムシ。格下には部類の強さを発揮するのだが、圧倒的な強さの2横綱には歯が立たない。西の正大関は小兵ながらカナプンが務めていた。相撲となると甲虫類がなんと言っても強く、カナプンも甲虫類特有の力と体重と盤石の擦り足で断然有利だった。東の張出し大関はバッタ類ながら類い稀な体力を持つクツワムシ。更にトノサマバッタ、キリギリスの両関脇にスズメバチ、タガメの小結達が続く。水棲昆虫のタガメは水の中ではカブトムシにも負けない強さなのだが、地上だと踏ん張る力と息が続かないためどうしても不利だ。同じ水棲昆虫のゲンゴロウは前頭十五枚目、今場所負け越せば幕内陥落の可能性もあった。だから必死だ。ここまで5勝7敗と後がなく、しかもどういう訳か今日は横綱カブトムシとの対戦だ。ゲンゴロウは色々策を張り巡らしていたものの、これと言っていい案も浮かばず、控え席で結びの一番を緊張しながら待っていた。ゲンゴロウは今まで策を巡らしながらどうにかここまでやって来た。しかし横綱戦となると何をやっても無駄に思えた。立行司は去年までのスズムシが余りにも迫力がないという事で、今年からミンミンゼミに代わった。呼出しがかかり、いよいよ本日結びの一番である。桟敷席の客も審判もムシHKのアナウンサーも解説のタマムシ親方も横綱もゲンゴロウ本人も番狂わせが起こるなどとは思ってもいなかった。ゲンゴロウは緊張ともう後がないという悲壮感から、がくがくしながら土俵に上がった。「どうしよう、どうしよう。」そればかり考えていた。ここで断っておくが、元々四つん這い、いや六つん這いの昆虫大相撲にはひっくり反るか押し出されるか、吊りだされる以外負けはない。余裕の横綱とそわそわのゲンゴロウでは結果は明らか。新聞記者は翌朝の記事を書き始め、観客は千秋楽の前人未踏の300連勝達成の話しに花を咲かせ、審判の何人かは審判席で居眠りしていた。いよいよ軍配が反った。ゲンゴロウは土俵の端で蹲踞(そんきょ)の姿勢から猛然とカブトムシに向かって走り出し、あわやがっぷり六つの寸前にUターンして元いた土俵の端に駆け戻った。こんな小細工など気にする風でもなく横綱はにやにやしながら、のしのしと前進して来た。場内も大爆笑である。ゲンゴロウは土俵際から行き場を失い再びUターンし、横綱に向けてもう一度突進した時それは起こった。なんとカブトムシの6本の足の間を擦り抜け、ゲンゴロウは横綱の後ろに飛び出してしまい、そのまま土俵の反対側にすっ飛んでしまった。これには場内も更に大爆笑。がしかし次の瞬間驚愕のどよめきに満ちていた。ミンミンゼミの行司の軍配はゲンゴロウへ。新聞記者は茫然、観客は唖然、審判は愕然。行司だけが毅然と立ち、そのまま止まれず進み続けたカブトムシの足がゲンゴロウよりも一瞬早く土俵を割るのをしっかり見定めていた。こうしてゲンゴロウは一躍新聞トップを飾り、カブトムシはショックで千秋楽の横綱対決に破れ、26年振りにミヤマクワガタが東横綱となった。もっとも結局ゲンゴロウは負け越し、十両転落となってしまったのだが。
2020.08.06
コメント(3)
-
我が良き虫の世かな ~ お散歩ロード
「三猫珍道中」は第一話で10回の話であることを書いていましたが、唐突に終わってしまった感があるようなコメントが多かったです。忘れてしまった四百年前の計画を、益比というとぼけた仙人のもとに八人の仙人が集まりこれから百年の歳月をかけて思い出そうという話になり、五百年の「壮大なる計画」になったという落ちでした。これは「ニャン騒、シャーとミー八犬伝」で、道節と毛野に伝言しに行く途中の三猫の道中を描いたスピンオフで、さすがにこれを何か月も続けるわけにはいきません。続編も構想はありますが、それまで旧作で特に私が好きなシリーズ「我が良き虫の世かな」を再掲載します。実は8年前くらいに自費出版した時、出版するうえでブログにあるのはまずいので削除してくれと出版社から言われたものです。今回の話は、このシリーズでも一番好きな話しで、この話だけは削除せずに残しておいたものです。悲しい最後ですが、誰も悪くない。みんな自然に生きているだけなんだという事を伝えたい作品です。2019.06.17我が良き虫の世かな ~ お散歩ロードケムシ君はいつもになく上機嫌で、いつも葉っぱをご馳走になっているくぬぎの木からとなりの木へと、小さな大移動をしていた。道をはさんでほんの10メートル程なのだが、彼にとっては大移動なのだ。「今度のくぬぎの木は葉っぱがいっぱいあって、柔らかく、とってもおいしそうだぞ。」ここを散歩する人間が時々するように、口笛でも吹きたい気分だ。もちろん毛虫でなければ。・・・・・小学校2年生のユミちゃんは、大好きなお父さんと手をつなぎ、今日は100点だった算数のテストのご褒美に、近くのアイスクリーム屋さんで、やっぱり大好きなアイスクリームを買ってもらいに、いつもの公園のお散歩ロードを時々スキップしながら歩いていた。くぬぎや松が日陰をつくって、ひんやりとしてとってもいい気持ちだ。「ユミ?どんなアイスクリームが食べたいんだい?」「私ねえ、三段重ねの三色アイスクリーム。前から一度食べたかったの。」「ああ、この間広告に出てたやつだな?」お父さんもにこにこしながら言った。・・・・・『新しいくぬぎさんの所に行ったらちゃんとご挨拶して、いっぱい葉っぱをご馳走になろう。』そう考えるとケムシ君はますますウキウキしながら、道の真ん中に差し掛かった。・・・・・ユミちゃんは大きな三段の三色アイスクリームを食べている所を思い浮かべながら、「ユミももう2年生だから一人で全部食べられるよ。ね、いいでしょ?」ユミちゃんはお散歩ロードの真ん中でお父さんに振り向きながら、ぴょんと前に飛び出した。」ブチッ不気味な音が辺り一面に響き渡った。もちろん虫の世界だけの事だが。・・・・・「しようがないなあ。」お父さんもユミちゃんもにこにこしながら、また手をつなぎお散歩ロードを歩き始めた。・・・・・そこには新しい葉っぱへの思いが微かに漂い、それもやがて草木の息吹に吸い込まれ、さわやかなそよ風が渡っていった。
2020.08.03
コメント(6)
-
お散歩ロード
ケムシ君はいつもになく上機嫌で、いつも葉っぱをご馳走になっているくぬぎの木からとなりの木へと、小さな大移動をしていた。道をはさんでほんの10メートル程なのだが、彼にとっては大移動なのだ。「今度のくぬぎの木は葉っぱがいっぱいあって、柔らかく、とってもおいしそうだぞ。」ここを散歩する人間が時々するように、口笛でも吹きたい気分だ。もちろん毛虫でなければ。 ・・・・・ 小学校2年生のユミちゃんは、大好きなお父さんと手をつなぎ、今日は100点だった算数のテストのご褒美に、近くのアイスクリーム屋さんで、やっぱり大好きなアイスクリームを買ってもらいに、いつもの公園のお散歩ロードを時々スキップしながら歩いていた。くぬぎや松が日陰をつくって、ひんやりとしてとってもいい気持ちだ。「ユミ?どんなアイスクリームが食べたいんだい?」「私ねえ、三段重ねの三色アイスクリーム。前から一度食べたかったの。」「ああ、この間広告に出てたやつだな?」お父さんもにこにこしながら言った。 ・・・・・ 『新しいくぬぎさんの所に行ったらちゃんとご挨拶して、いっぱい葉っぱをご馳走になろう。』そう考えるとケムシ君はますますウキウキしながら、道の真ん中に差し掛かった。 ・・・・・ ユミちゃんは大きな三段の三色アイスクリームを食べている所を思い浮かべながら、「ユミももう2年生だから一人で全部食べられるよ。ね、いいでしょ?」ユミちゃんはお散歩ロードの真ん中でお父さんに振り向きながら、ぴょんと前に飛び出した。」 ブチッ 不気味な音が辺り一面に響き渡った。もちろん虫の世界だけの事だが。 ・・・・・ 「しようがないなあ。」お父さんもユミちゃんもにこにこしながら、また手をつなぎお散歩ロードを歩き始めた。 ・・・・・ そこには新しい葉っぱへの思いが微かに漂い、それもやがて草木の息吹に吸い込まれ、さわやかなそよ風が渡っていった。
2019.06.17
コメント(4)
全46件 (46件中 1-46件目)
1










