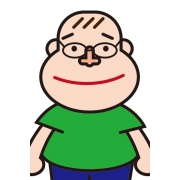PR
X
カレンダー
2024.06
2024.05
2024.04
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02
2024.02
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 子規と漱石
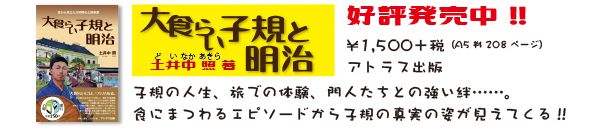
幼い頃から、子規も漱石も寄席が好きでした。
幼い子規は、松山の大街道にあった「遠山席」とも「改良座」とも称した寄席に掛けられる軍談(講談)に夢中になりました。当時、松山で人気を集めていたのは軍談師の燕柳でした。柳原極堂著『友人子規』には、燕柳は「大阪風の講釈ぶりで大きな張扇で机をバタバタ叩きながら威勢よく盛んな調子」だったとあります。
明治11(1878)年、子規と親戚の三並良(はじめ)は、親に無断で親戚に金を借り、寄席に潜りこみました。そのことが発覚して家の戸を閉められ、閉め出されたこともありました。
上京してからも子規は、友人たちと連れ立って寄席に出かけました。木戸銭の捻出に借金や質屋を利用したこともあります。「白梅亭」は神田連雀町、「立花亭」は日本橋通石町にあり、猿楽町の下宿からも近かったためでした。
当時は「娘義太夫」がブームとなっていて、書生たちは「堂摺連」を結成して、奇声を発しました。名前の通り、サワリの部分で「どうするどうする」と囃したて、拍手喝采するのですが、子規たちもそれに倣ってはしゃぎました。
南方熊楠は、大学予備門で同級だった子規や秋山真之が大流行していた奥州仙台節を習っていると記しています。子規は、『筆まかせ』で三遊亭円朝を文章の手本とするようにと記しています。円朝は、本名が出淵次郎吉で、前田備前守に仕えた江戸留守居役を祖父に持つといいます。伊予国出淵庄を領していたという噂もあり、子規はこれを誇っていたのでしょうか。

漱石は、『僕の昔』で「 何分兄等が揃って遊び好きだから、自然と僕も落語や講釈なんぞが好きになってしまったのだよ
」といい、明治41年9月号の「ホトトギス」掲載の『正岡子規』には、「 忘れていたが、彼と僕と交際し始めたも一つの原因は、二人で寄席の話をした時、先生も大に寄席通を以て任じて居る。ところが僕も寄席のことを知っていたので、話すに足るとでも思ったのであろう、それから大いに近よって来た
」とあるように、漱石も子規も寄席が好きでした。
漱石の贔屓は柳家小さんで、小説『三四郎』の中で「 小さんは天才である。あんな芸術家は滅多にでるものじゃない。……彼と時を同じうして生きている我々は大変な仕合せである。今から少し前に生れても小さんは聞けない。少し後れても同様だ
」と絶賛しています。
子規と漱石は、幼い頃からの寄席通いが共通し、その縁でさらに親しくなっていきました。
余はこの頃、井林氏とともに寄席に遊ぶことしげく、寄席は白梅亭か立花亭を常とす。しかれども懐中の黄衣公子意にまかせざること多ければ、あるいは松木氏のもとに至り、あるいは豊島氏のもとに至り、多少を借りきたりてこれをイラッシャイという門口に投ずることしばしばなれども、未だかつて後にその人に返済したることなし。必ずうたてき人やとうとまれけん。また、人をして余らの道楽心を満足せしむることは、度々できることにあらざれば、時として井林氏は着物を質に置き、その金にて落語家の一笑を買うたることもありたり。寄席につとめたりというべし。
(『筆まかせ』「寄席」)
(明治) 二十一年の頃には、君と僕とは土曜日の夜ごとに落語を聞きに寄席へ出かけた。落語家の手腕を比較して番付さえ作った。君は落語を哲学的に評論するというて、大分書かれたものもあった。
(大谷是空『正岡子規君』)
落語か。落語はすきで、よく牛込の肴町の和良店へ聞きにでかけたもんだ。僕はどちらかといえば子供の時分には講釈がすきで、東京中の講釈の寄席はたいてい聞きに回った。なにぶん兄らがそろって遊び好きだから、自然と僕も落語や講釈なんぞが好きになってしまったのだ。落語家で思い出したが、僕の故家からもう少し穴八幡のほうへ行くと、右側に松本順という人の邸があった。あの人は僕の子供の時分には時の軍医総監ではぶりがきいてなかなかいばったものだった。円遊やその他の落語家がたくさん出入りしておった。
(夏目漱石 僕の昔)
松山の今は銀座通りと呼ばれる大街道に、今は残っていないが寄席があって、それに軍談(講談のこと)があった。燕柳という男のが、我々には面白かった。彼は真田三代記が得意で、大坂冬の陣、夏の陣を読んでいた。彼は家康がきらいで、幸村にめちゃめちゃにやられる光景を、ものも鮮かに演じたり、家康が六文銭の旗を見ると、腰をぬかして、彦左「またぬけた」などいう辺りを面白おかしく述べ立てるので、我々は夢中になっていた。……景浦の夜学に行く晩に、子規と寄席の前を通って、昨晩の続きが聴きたくて仕方がなくなった。代金は一人前全部で五、六厘だったと記憶するが、その頃私どもには小使いというものが特別に渡されなかったので、一文だって金銭は所有していなかったが、それでも何かの残りが、誰かの袂に四、五厘はあった。もう五、六厘あれば、入れるのだった。相談の結果、子規の親類が近所にあるので、彼がそこへ借りに行って難なく借りてきて、一緒に講談を聴いて、いつもの通り、通学から帰ったつもりにしてくると家の大戸がしまっていて、開かない。いくらたたいても何の返事もない。変だが悪事露見したのかと思っていると、子規が飛んできて、どうした、お前も入られんのかという。運命は同じなのだ。どんどんたたいていると、母の声がして『今夜はもう開けてやらん、夜学へ行くといって寄席へ行くものなんかは入らさんぞな』という。その中に子規のお母さんが見にきてくれて、升も入らすから幸さんもお入れといってくれたので、やっと門が開いた。どうして露見したかというと、その晩おり悪しく雨が降り出したので、子規の母と私の母とが雨傘と下駄を持って、景浦先生のところまで行ったのであったが、今夜は二人とも来ないといわれ、それではてっきり、燕柳を聴きに行ったと図星をさされ、双方の母たちが相談して門をしめて入れなかったのだ。
(三並良『子規の少年時代』)
いそがしき手習のひまに長々しき御返事、態々御つかわし被下候段、御芳志の程ありい(洋語にあらず)、かく迄御懇篤なる君様を何しに冷淡の冷笑のとそしり申すべきや。まじめの御弁護にていたみ入りて穴へも入りたき心地ぞし侍る程に、一時のたわ言と水に流し給へ。七面倒な文章論かかずともよきに、そこがそれ人間の浅ましき。終に余計なことをならべて君にまた攻撃せられて大閉口、何事も餅が言わする雑言過言と御許しあれ。
当年の正月は不相変雑煮を食い、寝てくらし候。寄席へは五六回程参り、かるたは二返取り候。一日神田の小川亭と申にて鶴蝶と申女義太夫を聞き、女子にでもかかる掘り出し物あるやと愚兄と共に大感心。そこで愚兄、余に云う様「芸がよいと顔迄よく見える」と。その当否は君の御批判を願います。
米山は当時夢中に禅に凝り、当休暇中も鎌倉へ修行に罷越したり。山川は不相変学校へは出でこず、過日十時頃一寸訪問せしに未だ褥中にありて、煙車を吸い、それより起きて月琴を一曲弾て聞かせたり。いつもいつものん気なるが、心は憂欝病にかからんとする最中也。これも貴兄の判断を仰ぐ。兎角この頃は学校でも吾党の子が少ないから、何となく物淋しく面白くなし。可成早く御帰りお帰り。もう仙人もあきがきた時分だろうから、一寸已めにしてこの夏にまた仙人になり給え。云々
別紙文章論今一度貴覧を煩はす云々
埋塵道人拝
四国仙人 梧下
七草集、四日大尽、水戸紀行、その他の雑録を貴兄の文章と也。文章でなしと仰せらるれば失敬御免可被下候。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[子規と漱石] カテゴリの最新記事
-
子規とアート(番外)/漱石と模倣 2020.05.30
-
愚陀仏庵と久保より江 2019.07.16
-
子規の『画』と漱石の『子規の画』 2019.01.26
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.