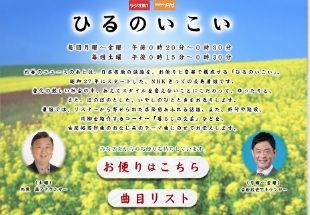PR
X
Free Space
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(0)映画 Cinema
(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube
(268)TVラジオ番組 television & radio programs
(375)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad
(148)外国語学習 Studying Foreign Language
(67)花 Flowers
(329)グルメ Gourmet
(204)介護 Nursery Care
(20)中高年の資格取得Qualification for middle
(15)散歩 Taking a walk
(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life
(121)フィットネスクラブ Fitness Club
(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath
(10)旅行 Travel
(88)読書 Reading
(54)健康 Health
(44)絵画 Picture
(25)Japanese TV Drama with English
(2)季節
(32)災害
(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス
(88)リンク修正、内容追加
(180)政治
(156)宗教
(121)写真
(27)グリーティング
(45)人生
(19)科学
(17)ダイエット
(7)少子・高齢化社会
(11)生き物 creatures
(5)月と星空
(26)不動産
(2)演劇
(1)Comments
Freepage List
テーマ: 仏教について思うこと(1038)
カテゴリ: 宗教
今週末京都の比叡山に不滅の法灯を見に行く予定です。延暦寺について、下調べしていて、前から気になっていた千日回峰行に行き当たりました。
2回も達成された酒井 雄哉師大阿闍梨のユーチューブを観ていて厳しい行に驚きました。酒井大阿闍梨については若いころ、新婚間もない奥さまが自殺されたり、人生でいろいろ経験されて比叡山に入られたのをTVで観た記憶があります。著作の一日一生が面白そうでしたが、アマゾンンのキンドルアンリミテッド読み放題の別の本を借りてみました。
また、千日回峰行について、成功率を調べましたがネットでは見当たりませんでした。本当に自害した人がいるのかどうかもわかりませんでした。ヤフー知恵袋の回答を見るとそんなに歴史のある行事でもない書き込みがあったり、昔は千日回峰行者が夜な夜な京都の街に繰り出していたとの書き込みもありました。ガチンコでやると本当に死人が出そうな行事なので、チャリティ番組のマラソンみたいな番組を盛り上げる演出みたいなものがあるのかどうかも気になりました。個人的には一日の千日回峰行を終えたお坊さんと祇園の街に繰り出して、冷えたビールでいっぱいというほうが、人間味があって好きです。
1日80kmも何日も歩いたり、不眠不休で飲まず食わずでお経を何日も唱えるのは不可能に近いと思います。延暦寺のお坊さんの中でトップクラスの厳しい修行に耐えられたお坊さんを、不滅の法灯と一緒に、延暦寺の象徴としてアピールする行事と考えると、しっくりきますが、真相はどうなんでしょうか。
また、親鸞聖人はかつて比叡山で厳しい修行を行いましたが、悟りを開くことが出来ず山を下りられました。千日回峰行という激しい修行によらなくても、たとえばある勉強やスポーツを究めたりすると何か見えてくることがありますが、それで代替できそうにも思います。
■参考リンク
Wikipedia:千日回峰行 (比叡山)
千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)とは、滋賀県と京都府にまたがる比叡山山内で行われる、天台宗の回峰行の一つである。満行者は「北嶺大先達大行満大阿闍梨」と称される。
「千日」と言われるが実際に歩む日数は「975日」である。「悟りを得るためではなく、悟りに近づくために課していただく[1]」ことを理解するための行である。
概要
行者の服装(1954年7月発行の国際文化情報社「国際文化画報」より)
この行に入るためには、先達から受戒を受けて作法と所作を学んだのちに、「初百日満行」入り、その後7年の間、1 - 3年目は1年間に連続100日、4 - 5年目は1年間に連続200日、行を為す[2]。
無動寺で勤行のあと、深夜2時に出発する。真言を唱えながら東塔、西塔、横川、日吉大社と260箇所で礼拝しながら、約30キロメートル (km) を平均6時間で巡拝する。
途中で行を続けられなくなったときは自害する。そのための「死出紐」と、降魔の剣(短剣)、三途の川の渡り賃である六文銭、埋葬料10万円を常時携行する。
未開の蓮華の葉をかたどった笠をかぶり、白装束、草鞋履きで行う。
堂入り
無動寺明王堂
5年700日を満行すると、最も過酷とされる「堂入り」が行われる。
行者は入堂前に生前葬となる「生き葬式」を執り行い、無動寺明王堂で足かけ9日[3]かけて断食・断水・断眠・断臥の4無行に入る。堂入り中は明王堂に五色の幔幕が張られ、行者は不動明王の真言を唱え続ける。毎晩、深夜2時に堂を出て、近くの閼伽井で閼伽水を汲み、堂内の不動明王にこれを供えなければならない。水を汲みに出る以外は、堂中で10万回真言を唱え続ける[4]。
堂入りを満了して「堂さがり」すると、行者は生身の不動明王ともいわれる阿闍梨となり、信者達の合掌で迎えられる。これを機に行者は自分のための自利行から、衆生救済の利他行に入る。
6年目はこれまでの行程に京都の赤山禅院への往復が加わり、1日約60kmの行程を100日続ける。
7年目は200日行い、はじめの100日は全行程84kmの京都大回りで、後半100日は比叡山中30kmの行程に戻る。
満行後
満行者で、無動寺谷明王堂の輪番職にある者は、その後2 - 3年以内に、米・麦・粟・豆・稗の五穀と塩・果物・海草類を100日間摂取しない「五穀断ち」ののちに、自ら発願して7日間の断食と断水で火炙り地獄とも俗称される「十万枚大護摩供」を行う。
満行者は京都御所に土足参内し、加持祈祷を行う。京都御所内は土足厳禁だが満行者のみ許される。回峰行を創始した相応和尚が草鞋履きで参内したところ文徳天皇の女御の病気が快癒したから[5]であるとも、清和天皇の后の病気平癒祈祷で草履履きのまま参内したから[6]とも伝聞される。
回峰行初百日を終えた後に立候補し、先達会議で認められた者が行に入る。
“現代の生き仏”が死の3日前に語った「最期の言葉」がん2014/03/12 16:00筆者:朝日新聞出版・友澤和子Area.dot
Wikipedia:酒井雄哉
酒井 雄哉(さかい ゆうさい、1926年(大正15年)9月5日 - 2013年(平成25年)9月23日 )は、天台宗の僧侶。比叡山延暦寺の千日回峰行を2度満行した行者として知られる。天台宗北嶺大行満大阿闍梨、大僧正、比叡山一山 飯室谷不動堂長寿院住職を務めた。
経歴
経歴
誕生
1926年(大正15年)、大阪市玉造で、10人兄弟の長男として生まれる。5歳の時、一家で東京へ移る。旧制麻布中学を受験するも失敗し、1941年(昭和16年)、慶應義塾商業学校(慶應義塾大学の夜間商業学校)に入学、同校卒。落第生で卒業が危ぶまれたため、担任教員に、軍隊入隊を勧められる。当時は入隊と引き換えに卒業が認められる制度があった。
入隊
1944年(昭和19年)、熊本県人吉の予科練に入隊。そこで半年間の訓練を受けた後、宮崎県の宮崎海軍航空隊(後の松島海軍航空隊、陸上攻撃機)所属を経て、鹿児島県の鹿屋飛行場に移る。同僚が特別攻撃隊員として、次々と戦死していく中、鹿屋飛行場も連日のように米軍機による空襲を受ける。ある日、訓練の最中に米軍の機銃掃射による猛攻撃を受け、逃げ損ねるが、田んぼの溝に落ち、奇跡的に助かる。少し前まで元気だった優秀な仲間が命を失い、自身は生き残った体験から、世の無常を味わう。
戦後
戦後は、法政大学の図書館職員となり、その働きぶりが評価され、大学の教授から、法政大学入学を勧められる。自身もその気になり、法政大学受験を決意。願書を出すため、出身校である慶應義塾商業学校の成績証明書を取りに行くも、不安になり、中を見ると、品行が良くないなど、ろくなことが書かれていないことに愕然とし、受験を断念。同時に職場も放棄してしまう。
その後、父親が始めたラーメン屋を手伝い、繁盛したものの、約5年で火事で廃業。次に、父親と株売買の代理店を始めるが、スターリン暴落による大損害で、借金取りに追われる始末。その後も、そば屋の店員、菓子屋のセールスマンなど、職を転々とする。
33歳の時、従妹と結婚するが、新婚早々、妻が大阪の実家に帰ってしまう。連れ戻そうと迎えに行くも、しばらくして妻がガス自殺を遂げる。わずか2ヶ月の結婚生活だった。以後、抜け殻のような生活を送る。
比叡山へ
ある日、叔母と比叡山を訪ねたことがきっかけとなり、折に触れて通うようになる。1965年(昭和40年)、39歳のとき出家、得度。ここが最後の砦と自覚し、十代、二十代の若者に混じり、天台宗学の理論と実践を学ぶ。叡山学院を首席で卒業。天台座主賞も受賞する。千日回峰行に挑む前には、明治時代に死者が出て以来、中断していた荒行で知られる常行三昧も達成している。
千日回峰行
1973年(昭和48年)より千日回峰行を開始し、1980年(昭和55年)10月に満行した。この行の様子は1979年(昭和54年)1月5日、NHK特集『行~比叡山・千日回峰~』で放送された。
しかし酒井はこれに満足せず、半年後に2度目の千日回峰行に入った。そして、1987年(昭和62年)7月、60歳という最高齢で2度目の満行を達成した。2度の千日回峰行を達成した者は、1000年を越える比叡山の歴史の中でも3人しかいない。
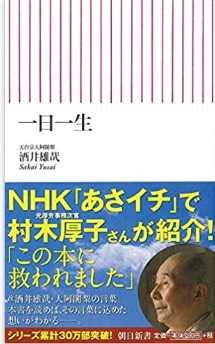
一日一生 (朝日新書) 新書 – 2008/10/10天台宗大阿闍梨 酒井 雄哉 (著)
第一章 「一日一生」
・一日が一生、と思って生きる
・身の丈に合ったことを毎日くるくる繰り返す
・仏さんは、人生を見通している
・足が疲れたなら、肩で歩けばいい
・ありのままの自分としかっと向き合い続ける
・人からすごいと思われなくたっていいんだよ
・「一日」を中心に生きる
・人は毎日、新しい気持ちで出会える
第二章 「道」
・生き残ったのは、生き「残された」ということ
・長い長い引き揚げの旅が教えてくれたこと
・同じことを、ぐるぐるぐるぐる繰り返している
・どんな目にあったとしても
・人の心には闇がある
・ある日突然、妻は逝ってしまった
・人生の出会いはある日突然やってくる
・仏が見せた夜叉の顔
・自分は何のために生まれてきたのか、なにするべきか問い続ける
・その答えを、一生考え続けなさい
第三章 「行」
・衣を染める朝露も、いつしか琵琶湖にそそぐ
・歩くことが、きっと何かを教えてくれる
・知りたいと思ったら、実践すること
・仏さんが教えてくれた親子の情愛
・息を吸って、吐く。呼吸の大切さ
・仏はいったいどこにいるのか
・身の回りに宝がたくさんある
・学ぶこと、実践することは両輪
・ゆっくりと、時間をかけて分かっていくことがある
第四章 「命」
・ほっこち温かな祖父母のぬくもり
・大きな父の背中におぶわれた冬の日
・子供はおぶったりおぶわれたりして育つ
・夜店で母が隠した父の姿
・心と心が繋がっていた父と母
・東京大空襲の時に鹿児島で見た夢
・死を目前とした兄と弟 ・一生懸命生きる背中を子供に見せる
・命が尽きれば死んで、他の命を支えるんだよ
第五章 「調和」
・桜は、精いっぱい咲いている
・人は自然の中で生き、生かされている
・重い荷物を負う中国の子供たちにみた「大志」
・心のありようはいろいろなものに作用される
・本当は同じものを見ているのかもしれない
・まだ、たったの三万日しか生きていないんだなあ
親鸞聖人・比叡山での難行── 煩悩との闘い
ヤフー知恵袋:lst********さん
2015/10/21 12:37
大峯千日回峰行
挫折したら自害しなきゃなんないって、2015年の現在でも決められてるんですか?
国も許可してるんですか?
あと、堂入りって9日間飲まず食わずの無睡らしいですが、監視役いるんですか?
監視役は目の前で食っちゃ寝してるんですか?
ベストアンサー
このベストアンサーは投票で選ばれました
adv********さん
2015/10/21 17:31
さすがに自害に関しては認められないでしょう。平成に入ってこの儀式を無事に全行程達成した方のインタビュー記事を見たことがありますが現代では象徴的な物になってるみたいです。堂入りに関しては1日一回程確認の方が見回りに来る見たいですがそれ以外は独りきりのようです。神聖な修行の場ですから目前で飲食なんてしたら関係者から叩き出されるかと。
只、堂入り含む修行の場にドクターストップをかける医者はいないみたいですので堂入りの最中や巡礼の途中の山道でバッタリ倒れて見つかった時には手遅れと言う事態は十分にあり得るみたいです。そのような事態になった場合に法律的には危険を侵して行く冒険家みたいな扱いになるのでは。
ヤフー知恵袋:取りあえーずさん2015/10/21 17:16千日回峰について、失敗した時は自害しなければならないとの事ですが、過去に自害された人が居るのでしょうか?お分かりでしたら教えてください。
※Wikiでは成功者47名との事ですが、失敗した人についての記載が皆無でした。失礼な言い方になりますが、全員成功ということでは、ちょっと何か裏があるのかと疑りが沸いてしまいます。
ps.私はよく比叡山に登るのですが、横川に行った時に、浄土真宗の開祖・親鸞聖人を始めて知りました。諸説ありますが、彼は、九歳から二十九歳まで二十年間、その千日回峰行よりも、さらに厳しい「大曼の難行」に、全身全霊打ち込みましたが、結局は魂の開放には至らず、厳しい修行では悟りを開くことは出来ないと、結果、比叡山を降りたのを知っていますので、千日回峰についても、興味は持っています。
ベストアンサー
( =^ω^=)さん
2015/10/21 19:09
千日回峰は比叡山の伝統的な行ではなく
十二年籠山制度とは別の修行でした。
国家資格のお坊さんとは違って身分に関係なく
だれでも千日回峰行をできたそうです。
昔は結構乱れていて夜な夜な修行僧が京都まで遊びに行ったり
行方知れずになった人もいたそうです。
千日回峰が十二年籠山制度に組み入れられたのは
戦後になってからなんだそうです。
ヤフー知恵袋:mou********さん2015/10/21 16:22比叡山延暦寺の千日回峰行の「堂入り」は今年13人目の成功とのことですが、失敗した人がいるということですよね?何人ぐらい失敗されているのかどのように失敗して、どうなったのか失敗するときは自決しなくてはならないと聞いてますが、本当でしょうか?
ベストアンサー
このベストアンサーは投票で選ばれました
bit********さん
2015/10/22 9:17
商業大相撲の行司と同じです。あいつらは行司差し違えをしたら腰の刀で自害すべきなんですが、差し違いはしょっちゅうあっても、いまだに誰一人、行司が自害した話は皆無です。
2回も達成された酒井 雄哉師大阿闍梨のユーチューブを観ていて厳しい行に驚きました。酒井大阿闍梨については若いころ、新婚間もない奥さまが自殺されたり、人生でいろいろ経験されて比叡山に入られたのをTVで観た記憶があります。著作の一日一生が面白そうでしたが、アマゾンンのキンドルアンリミテッド読み放題の別の本を借りてみました。
また、千日回峰行について、成功率を調べましたがネットでは見当たりませんでした。本当に自害した人がいるのかどうかもわかりませんでした。ヤフー知恵袋の回答を見るとそんなに歴史のある行事でもない書き込みがあったり、昔は千日回峰行者が夜な夜な京都の街に繰り出していたとの書き込みもありました。ガチンコでやると本当に死人が出そうな行事なので、チャリティ番組のマラソンみたいな番組を盛り上げる演出みたいなものがあるのかどうかも気になりました。個人的には一日の千日回峰行を終えたお坊さんと祇園の街に繰り出して、冷えたビールでいっぱいというほうが、人間味があって好きです。
1日80kmも何日も歩いたり、不眠不休で飲まず食わずでお経を何日も唱えるのは不可能に近いと思います。延暦寺のお坊さんの中でトップクラスの厳しい修行に耐えられたお坊さんを、不滅の法灯と一緒に、延暦寺の象徴としてアピールする行事と考えると、しっくりきますが、真相はどうなんでしょうか。
また、親鸞聖人はかつて比叡山で厳しい修行を行いましたが、悟りを開くことが出来ず山を下りられました。千日回峰行という激しい修行によらなくても、たとえばある勉強やスポーツを究めたりすると何か見えてくることがありますが、それで代替できそうにも思います。
■参考リンク
Wikipedia:千日回峰行 (比叡山)
千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)とは、滋賀県と京都府にまたがる比叡山山内で行われる、天台宗の回峰行の一つである。満行者は「北嶺大先達大行満大阿闍梨」と称される。
「千日」と言われるが実際に歩む日数は「975日」である。「悟りを得るためではなく、悟りに近づくために課していただく[1]」ことを理解するための行である。
概要
行者の服装(1954年7月発行の国際文化情報社「国際文化画報」より)
この行に入るためには、先達から受戒を受けて作法と所作を学んだのちに、「初百日満行」入り、その後7年の間、1 - 3年目は1年間に連続100日、4 - 5年目は1年間に連続200日、行を為す[2]。
無動寺で勤行のあと、深夜2時に出発する。真言を唱えながら東塔、西塔、横川、日吉大社と260箇所で礼拝しながら、約30キロメートル (km) を平均6時間で巡拝する。
途中で行を続けられなくなったときは自害する。そのための「死出紐」と、降魔の剣(短剣)、三途の川の渡り賃である六文銭、埋葬料10万円を常時携行する。
未開の蓮華の葉をかたどった笠をかぶり、白装束、草鞋履きで行う。
堂入り
無動寺明王堂
5年700日を満行すると、最も過酷とされる「堂入り」が行われる。
行者は入堂前に生前葬となる「生き葬式」を執り行い、無動寺明王堂で足かけ9日[3]かけて断食・断水・断眠・断臥の4無行に入る。堂入り中は明王堂に五色の幔幕が張られ、行者は不動明王の真言を唱え続ける。毎晩、深夜2時に堂を出て、近くの閼伽井で閼伽水を汲み、堂内の不動明王にこれを供えなければならない。水を汲みに出る以外は、堂中で10万回真言を唱え続ける[4]。
堂入りを満了して「堂さがり」すると、行者は生身の不動明王ともいわれる阿闍梨となり、信者達の合掌で迎えられる。これを機に行者は自分のための自利行から、衆生救済の利他行に入る。
6年目はこれまでの行程に京都の赤山禅院への往復が加わり、1日約60kmの行程を100日続ける。
7年目は200日行い、はじめの100日は全行程84kmの京都大回りで、後半100日は比叡山中30kmの行程に戻る。
満行後
満行者で、無動寺谷明王堂の輪番職にある者は、その後2 - 3年以内に、米・麦・粟・豆・稗の五穀と塩・果物・海草類を100日間摂取しない「五穀断ち」ののちに、自ら発願して7日間の断食と断水で火炙り地獄とも俗称される「十万枚大護摩供」を行う。
満行者は京都御所に土足参内し、加持祈祷を行う。京都御所内は土足厳禁だが満行者のみ許される。回峰行を創始した相応和尚が草鞋履きで参内したところ文徳天皇の女御の病気が快癒したから[5]であるとも、清和天皇の后の病気平癒祈祷で草履履きのまま参内したから[6]とも伝聞される。
回峰行初百日を終えた後に立候補し、先達会議で認められた者が行に入る。
“現代の生き仏”が死の3日前に語った「最期の言葉」がん2014/03/12 16:00筆者:朝日新聞出版・友澤和子Area.dot
Wikipedia:酒井雄哉
酒井 雄哉(さかい ゆうさい、1926年(大正15年)9月5日 - 2013年(平成25年)9月23日 )は、天台宗の僧侶。比叡山延暦寺の千日回峰行を2度満行した行者として知られる。天台宗北嶺大行満大阿闍梨、大僧正、比叡山一山 飯室谷不動堂長寿院住職を務めた。
経歴
経歴
誕生
1926年(大正15年)、大阪市玉造で、10人兄弟の長男として生まれる。5歳の時、一家で東京へ移る。旧制麻布中学を受験するも失敗し、1941年(昭和16年)、慶應義塾商業学校(慶應義塾大学の夜間商業学校)に入学、同校卒。落第生で卒業が危ぶまれたため、担任教員に、軍隊入隊を勧められる。当時は入隊と引き換えに卒業が認められる制度があった。
入隊
1944年(昭和19年)、熊本県人吉の予科練に入隊。そこで半年間の訓練を受けた後、宮崎県の宮崎海軍航空隊(後の松島海軍航空隊、陸上攻撃機)所属を経て、鹿児島県の鹿屋飛行場に移る。同僚が特別攻撃隊員として、次々と戦死していく中、鹿屋飛行場も連日のように米軍機による空襲を受ける。ある日、訓練の最中に米軍の機銃掃射による猛攻撃を受け、逃げ損ねるが、田んぼの溝に落ち、奇跡的に助かる。少し前まで元気だった優秀な仲間が命を失い、自身は生き残った体験から、世の無常を味わう。
戦後
戦後は、法政大学の図書館職員となり、その働きぶりが評価され、大学の教授から、法政大学入学を勧められる。自身もその気になり、法政大学受験を決意。願書を出すため、出身校である慶應義塾商業学校の成績証明書を取りに行くも、不安になり、中を見ると、品行が良くないなど、ろくなことが書かれていないことに愕然とし、受験を断念。同時に職場も放棄してしまう。
その後、父親が始めたラーメン屋を手伝い、繁盛したものの、約5年で火事で廃業。次に、父親と株売買の代理店を始めるが、スターリン暴落による大損害で、借金取りに追われる始末。その後も、そば屋の店員、菓子屋のセールスマンなど、職を転々とする。
33歳の時、従妹と結婚するが、新婚早々、妻が大阪の実家に帰ってしまう。連れ戻そうと迎えに行くも、しばらくして妻がガス自殺を遂げる。わずか2ヶ月の結婚生活だった。以後、抜け殻のような生活を送る。
比叡山へ
ある日、叔母と比叡山を訪ねたことがきっかけとなり、折に触れて通うようになる。1965年(昭和40年)、39歳のとき出家、得度。ここが最後の砦と自覚し、十代、二十代の若者に混じり、天台宗学の理論と実践を学ぶ。叡山学院を首席で卒業。天台座主賞も受賞する。千日回峰行に挑む前には、明治時代に死者が出て以来、中断していた荒行で知られる常行三昧も達成している。
千日回峰行
1973年(昭和48年)より千日回峰行を開始し、1980年(昭和55年)10月に満行した。この行の様子は1979年(昭和54年)1月5日、NHK特集『行~比叡山・千日回峰~』で放送された。
しかし酒井はこれに満足せず、半年後に2度目の千日回峰行に入った。そして、1987年(昭和62年)7月、60歳という最高齢で2度目の満行を達成した。2度の千日回峰行を達成した者は、1000年を越える比叡山の歴史の中でも3人しかいない。
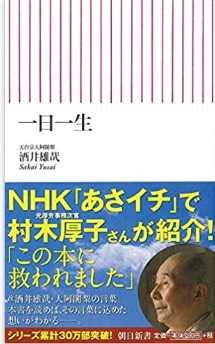
一日一生 (朝日新書) 新書 – 2008/10/10天台宗大阿闍梨 酒井 雄哉 (著)
第一章 「一日一生」
・一日が一生、と思って生きる
・身の丈に合ったことを毎日くるくる繰り返す
・仏さんは、人生を見通している
・足が疲れたなら、肩で歩けばいい
・ありのままの自分としかっと向き合い続ける
・人からすごいと思われなくたっていいんだよ
・「一日」を中心に生きる
・人は毎日、新しい気持ちで出会える
第二章 「道」
・生き残ったのは、生き「残された」ということ
・長い長い引き揚げの旅が教えてくれたこと
・同じことを、ぐるぐるぐるぐる繰り返している
・どんな目にあったとしても
・人の心には闇がある
・ある日突然、妻は逝ってしまった
・人生の出会いはある日突然やってくる
・仏が見せた夜叉の顔
・自分は何のために生まれてきたのか、なにするべきか問い続ける
・その答えを、一生考え続けなさい
第三章 「行」
・衣を染める朝露も、いつしか琵琶湖にそそぐ
・歩くことが、きっと何かを教えてくれる
・知りたいと思ったら、実践すること
・仏さんが教えてくれた親子の情愛
・息を吸って、吐く。呼吸の大切さ
・仏はいったいどこにいるのか
・身の回りに宝がたくさんある
・学ぶこと、実践することは両輪
・ゆっくりと、時間をかけて分かっていくことがある
第四章 「命」
・ほっこち温かな祖父母のぬくもり
・大きな父の背中におぶわれた冬の日
・子供はおぶったりおぶわれたりして育つ
・夜店で母が隠した父の姿
・心と心が繋がっていた父と母
・東京大空襲の時に鹿児島で見た夢
・死を目前とした兄と弟 ・一生懸命生きる背中を子供に見せる
・命が尽きれば死んで、他の命を支えるんだよ
第五章 「調和」
・桜は、精いっぱい咲いている
・人は自然の中で生き、生かされている
・重い荷物を負う中国の子供たちにみた「大志」
・心のありようはいろいろなものに作用される
・本当は同じものを見ているのかもしれない
・まだ、たったの三万日しか生きていないんだなあ
親鸞聖人・比叡山での難行── 煩悩との闘い
ヤフー知恵袋:lst********さん
2015/10/21 12:37
大峯千日回峰行
挫折したら自害しなきゃなんないって、2015年の現在でも決められてるんですか?
国も許可してるんですか?
あと、堂入りって9日間飲まず食わずの無睡らしいですが、監視役いるんですか?
監視役は目の前で食っちゃ寝してるんですか?
ベストアンサー
このベストアンサーは投票で選ばれました
adv********さん
2015/10/21 17:31
さすがに自害に関しては認められないでしょう。平成に入ってこの儀式を無事に全行程達成した方のインタビュー記事を見たことがありますが現代では象徴的な物になってるみたいです。堂入りに関しては1日一回程確認の方が見回りに来る見たいですがそれ以外は独りきりのようです。神聖な修行の場ですから目前で飲食なんてしたら関係者から叩き出されるかと。
只、堂入り含む修行の場にドクターストップをかける医者はいないみたいですので堂入りの最中や巡礼の途中の山道でバッタリ倒れて見つかった時には手遅れと言う事態は十分にあり得るみたいです。そのような事態になった場合に法律的には危険を侵して行く冒険家みたいな扱いになるのでは。
ヤフー知恵袋:取りあえーずさん2015/10/21 17:16千日回峰について、失敗した時は自害しなければならないとの事ですが、過去に自害された人が居るのでしょうか?お分かりでしたら教えてください。
※Wikiでは成功者47名との事ですが、失敗した人についての記載が皆無でした。失礼な言い方になりますが、全員成功ということでは、ちょっと何か裏があるのかと疑りが沸いてしまいます。
ps.私はよく比叡山に登るのですが、横川に行った時に、浄土真宗の開祖・親鸞聖人を始めて知りました。諸説ありますが、彼は、九歳から二十九歳まで二十年間、その千日回峰行よりも、さらに厳しい「大曼の難行」に、全身全霊打ち込みましたが、結局は魂の開放には至らず、厳しい修行では悟りを開くことは出来ないと、結果、比叡山を降りたのを知っていますので、千日回峰についても、興味は持っています。
ベストアンサー
( =^ω^=)さん
2015/10/21 19:09
千日回峰は比叡山の伝統的な行ではなく
十二年籠山制度とは別の修行でした。
国家資格のお坊さんとは違って身分に関係なく
だれでも千日回峰行をできたそうです。
昔は結構乱れていて夜な夜な修行僧が京都まで遊びに行ったり
行方知れずになった人もいたそうです。
千日回峰が十二年籠山制度に組み入れられたのは
戦後になってからなんだそうです。
ヤフー知恵袋:mou********さん2015/10/21 16:22比叡山延暦寺の千日回峰行の「堂入り」は今年13人目の成功とのことですが、失敗した人がいるということですよね?何人ぐらい失敗されているのかどのように失敗して、どうなったのか失敗するときは自決しなくてはならないと聞いてますが、本当でしょうか?
ベストアンサー
このベストアンサーは投票で選ばれました
bit********さん
2015/10/22 9:17
商業大相撲の行司と同じです。あいつらは行司差し違えをしたら腰の刀で自害すべきなんですが、差し違いはしょっちゅうあっても、いまだに誰一人、行司が自害した話は皆無です。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2022.06.26 08:36:45
[宗教] カテゴリの最新記事
-
2024.6西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.06.01
-
2024.5清正公寺の掲示板:人身は持ちがた… 2024.05.01
-
2024.4 西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.04.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.