第五話 サンガララの戦(3)

【 第五話 サンガララの戦(3) 】
インカ軍本営の一隅では、スペイン軍の攻撃によって負傷した多くの兵たちが、懸命な手当てを受けていた。
手当てを担当している者の殆どは女性たちで、戦場には出ずとも、彼女たちもまた、インカ軍を背後で強力に支えていたのである。
そして、その中にはコイユールの姿もあった。
敵の銃器や鈍器によって負傷した兵たちの怪我の状態は様々で、中には、瀕死の重態の者もいる。
コイユールは、他の者たちが目をそむけたくなるような酷い傷でも、決して避けず、丁寧に拭いて清め、薬草を配合して塗布し、優しく布で巻いて仕上げた。
必然的に、負傷の状態の重い兵士たちを中心に診る結果になっていた。
とはいえ、代替医療としての自然療法は行えても、所詮は一介の農民にすぎぬコイユールには医療行為などはできようはずがなく、治療はしかるべき従軍医が行った。
インカ軍では複数の従軍医が働いていたが、ビルカパサの連隊に所属する従軍医は特にその腕が冴えており、トゥパク・アマルの側近たちからの信頼も厚かった。
この従軍医は、義勇兵として志願して参戦した者で、もともと村の小さな診療所を開業していたクリオーリョ(当地生まれのスペイン人)の村医者であったが、実際、その腕はなかなか優れていた。
年齢的にはそろそろ初老にさしかかり、落ち着いた、温厚な雰囲気の持ち主である。
それにしても、このサンガララの戦いでの負傷者の状態は、いつにも増して、ひどく酷いものだった。
手当てをしながら、コイユールの中に不安が募ってくる。
合戦がインカ軍の勝利に終わったということは聞いていたが、負傷兵の状態を見るにつれ、その戦闘がいかに激しいものであったかは容易に想像できた。
コイユールは、義勇兵たちの噂で、常にアンドレスが戦線の最前線で戦っていることを知っていた。
それがどれほど危険なことなのか、実際の戦場を知らぬコイユールには推測するしかなかったが、それでも、その身の危険さは手に取るように想像できる。
負傷兵が運び込まれる度に、彼女は心臓が止まる思いで、そちらを振り向いた。
まさか、アンドレスが…――と、運び込まれる兵たちの治療をしながらも、気が気ではない。
せめて命が無事であることだけでもマルセラに確認したかったが、今は正式な隊長補佐でもある彼女は任務で忙しく、コイユールのところに顔を見せにくる暇などなかった。
コイユールから、思わず深い溜め息が漏れる。

その時、高貴な身なりをした一人のインカ族の初老の男が、従軍医のもとに急ぎ足で近づいた。
コイユールには知る由もなかったが、その人物は、あのトゥパク・アマルの老練の重臣、ベルムデスであった。
ベルムデスはやや緊迫した面持ちで従軍医に何か話すと、「かたじけないが、急ぎ、頼む。」と言い残し、また早足で引き返していった。
従軍医は診ていた兵士の治療を手早く終えると、素早く自分の治療道具を荷にまとめ、それから、暫し周囲をキョロキョロ見回してからコイユールの方に声をかけた。
「コイユール、私と一緒に来てくれないか。」
不意のことにコイユールは驚いて、目を見開いたまま、ちょうど兵の包帯を巻き終わったその手を止める。
普段のコイユールの働きぶりを知っている従軍医は、まじめな顔で彼女の目を見ながら言う。
「トゥパク・アマル様の側近のお方が、お二人も、緊急に治療が必要らしい。
すぐに連隊長の天幕まで行かねばならぬ。
手伝っておくれ。」
トゥパク・アマルの側近と聞いて、コイユールの心臓は本当に止まりそうになった。
「誰ですか?!
誰が、怪我をされたのですか?!
どんな怪我なのです?!」
普段はどちらかと言えば控えめなコイユールの尋常ではない様子に、従軍医はやや驚いた様子で、「怪我とも誰とも、そこまではまだ聞いていないが、行けばわかるだろう。とにかく、緊急を要するようだ。」と、既に歩み出しながら答える。
コイユールは、ただもう心配で、自分が助手として選ばれたということなど吹き飛んだまま、その眼差しには、もはや鋭いほどの険しさを滲ませて、それこそ従軍医を追い立てんばかりの勢いで歩みはじめた。
従軍医は、殆ど急(せ)き立てられるようになりながら、小走りで進む。
そんな二人を包み込むように、既に日の暮れた空からは、白い精霊のような雪が再び地に舞い降りはじめた。

二人は白い息を吐きながら、トゥパク・アマルら側近たちの天幕が張られている界隈に近づいていく。
周辺では、幾多の精鋭のインカ兵たちが、どこにも増して厳しい警護の目を光らせている。
従軍医が「治療に来たのですが。」と言うと、兵たちは待ち侘びたとばかりに、「こちらに!」と早足で案内してくれた。
まもなく、通されたのは、ビルカパサの天幕だった。
天幕が近づくにつれ、あまりの心配と不安のあまり、コイユールの心臓は張り裂けんばかりに、いっそう激しく鳴り響いた。
そして、心の中で、祈り続けていた。
どうか、どうか、アンドレスでは、ありませんように…――!!
もちろん、トゥパク・アマルの側近の誰一人とて、負傷などしてほしくはないはずだったが、今のコイユールは完全にアンドレスへの心配で頭が占められてしまっていた。
天幕の入り口に従軍医が近づくと、「さあ、はやく、中へ!!」と、勢いよく天幕が内側から開かれた。
そう言いながら天幕の内部から姿を見せたのは、アンドレスだった。
「!!」
二人の目が完全に合う。
突然、アンドレスを目の前にして、コイユールは足から力が抜けていくのを感じた。
今は、偶然の再会への驚きよりも、むしろ、アンドレスの無事な姿に、ただもうあまりの安堵で、彼女はその場にしゃがみこみそうなほどだった。
一方、アンドレスもまた、天幕の入り口の布を持ち上げたまま、完全に固まっていた。
コイユールの姿に釘付けられた目が離せない。
「…――コイユール、なぜ…?!」
思わず、聞こえないほどの擦れた声でアンドレスが呟く。
その時、コイユールもハッと我に返った。
そして、アンドレスのすぐ傍にいる自分の状況に気付き、はじかれたように、その瞳を見開く。

その瞬間、二人は、呆然と、それから、揺れるような眼差しで、しっかりとお互いを見つめた。
かつてと変わらぬ互いのその瞳の色に、二人の時間は完全に歩みを止める。
たちまち、二人の意識は、時空を越えて、あの懐かしい日々に二人を引き戻す。
そして、敢えて表面には出さずに心に深く沈めていたはずの、あの二人の絆を、今、再び目の前につきつけ、輝かせる。
「コイユール、手伝っておくれ!」
従軍医の緊迫した声に、コイユールは現実に引き戻された。
アンドレスも我に返り、入り口を開き、コイユールを中に通した。
震えるような足取りで、コイユールはアンドレスのすぐ直近を通り過ぎる。
そして、ともかくも、コイユールは従軍医のすぐ隣に控えた。
天幕の中では、意識の朦朧としたビルカパサが、苦痛に顔を歪めながら、右腕を押さえて横たわっていた。
それは、あの戦闘開始時に、己の体を張ってトゥパク・アマルを守った時の、あの大砲がかすめた際の傷であった。
ビルカパサはこれほどの重傷を負いながらも、あの数時間にも及ぶ激闘の中を、しかも並外れた働きぶりによって敵を討ち取り続けたのだった。
さらには、戦闘後の処理の間も、トゥパク・アマルを助けて働き続けた。
しかし、日没と共に、ついに力尽きて倒れたのだ。
天幕の中には、なんとトゥパク・アマルやディエゴもおり、ビルカパサの様子をひどく心配そうに見守っている。
アンドレスは天幕の中に戻ると、集団から少し離れたところに立った。
思わず息を詰め、微かに震える指を握り締める。
負傷による血生臭いにおいの充満する天幕の中だというのに、コイユールがいるというだけで、その場の空気が優しく柔らかく感じられてしまう。
従軍医は、トゥパク・アマルらを前にして、かなり緊張した様子ではあったが、それでもビルカパサの傷口の手当てを慎重に進めていった。
彼の指示のもと、コイユールも丁寧に血を拭い、傷口を拭き清めていく。
そして、指示通りに、薬草を調合する。
アンドレスの存在を近くに感じると手元が狂いそうで、彼女は必死で為すべきことに集中しようと努めた。
アンドレスもまた、もはや胸の高鳴りを止められぬまま、しかし、彼もまた精一杯に平静を装っていた。
「ビルカパサの怪我の様子は、どのようであろうか。」
トゥパク・アマルが、深く案ずる眼差しで従軍医に問う。
「はい。」と、従軍医はひどくかしこまってトゥパク・アマルに深々と礼を払い、そして、とても緊張の滲む声で、しかし、しっかりと答える。
「幸い、ビルカパサ様の傷はそれほど深くはありません。
ただ、傷を負ってから時間も経っており、お体へのご負担がかなりきております。
今宵は高熱になるやもしれません。」
そう言うと、恭しい手つきで、指示をしてコイユールに調合させた薬草を掲げた。
「こちらの薬を、お飲みいただいてください。
高熱に効きましょう。
お怪我の方は、定期的にお薬を塗布しに参ります。
時間はかかりますが、徐々に回復いたしましょう。」
この有能な従軍医の言葉に、トゥパク・アマルもディエゴも、そして、アンドレスも深い安堵の表情になった。
「ご苦労であった。」と、トゥパク・アマルが深く礼を払った声で言う。
従軍医が再び深々と頭を下げ、同じく、コイユールも深く頭を下げた。
従軍医の後に従い、コイユールはアンドレスの方に大いに気持ちだけ残しながら、しかし、天幕を後にするしかなかった。
アンドレスもどうすることもできぬまま、ただその瞳だけで、去っていくコイユールの後ろ姿を必死に追う。

緊張感の余韻を滲ませながら、従軍医はもと来た道を戻りはじめ、コイユールもそれに続いた。
すると、その後を、ディエゴが急ぎ追ってきた。
従軍医が振り返ると、「もう一人診てほしいのだ。」と言って、ディエゴは別の天幕へと二人を連れていった。
中に入ると、もう一人のトゥパク・アマルの側近、フランシスコがぐったりと横になっている。
どうやら、そこはフランシスコの天幕のようだった。
フランシスコは眠っているのか気を失っているのか、いずれにしろ、意識のないまま、額から多量の油汗を流して身を横たえている。
呼吸も苦しげで、肩を激しく上下させている。
やはり、天幕の中にはトゥパク・アマルが既に来ていて、心配そうにフランシスコの傍に身を屈めていた。
従軍医が急いで全身状態を調べるが、はっきりとした外傷が見当たらない。
「いつからです?」と問いかける従軍医に、「さきほど、天幕に戻られてから、突然状態がおかしくなられたのだ。」と、ディエゴが答える。
「ひどく熱が出て、呼吸も浅くなっておりますが、さしたる外傷も見当たりません。」と、従軍医もやや困惑気味の表情で、改めて、フランシスコを診察する。
それから、従軍医は暫し考え深気に目を細めた後、「ある種の精神的なショック状態かもしれません。だとすれば、ゆっくりと心と体を休められれば、徐々に回復いたしましょう。いずれにしろ、経過を診させていただかなければ、何とも言えません。」と、慎重な口調で言う。
ディエゴは、「精神的なショック状態?!」と、思わず唖然とした様子で目を見張る。
しかし、トゥパク・アマルは静かな眼差しで、「あの戦闘は凄まじかった。そのようなことも有り得よう。」と、いたわるようにフランシスコの方を見た。
トゥパク・アマルは改めて従軍医の労をねぎらい、従軍医も恭しく礼を払う。
そのまま従軍医はコイユールを伴って、今度こそ本当に側近たちの天幕を後にした。
従軍医と共に、再び、負傷兵の治療場へと戻ったコイユールではあったが、今しがたの突然のアンドレスとの再会に、その心はすっかりここにあらずの状態になっていた。
三年以上前に会って以来、この反乱がはじまってからは、同じ陣営にいながらも彼女の前には全く姿を現さぬアンドレスの真意は、コイユールには推察することしかできなかった。
歳月が経ち、もはや自分のことなど忘れてしまったのか、あるいは、彼の立場や責任の重さ故に、安易な行動をとれぬためなのか…。
しかし、先ほどの、アンドレスの目の色は、そして、あの時の瞬間に覚えた感覚は、コイユールの心に熱い波紋を投げかけずにはいられなかった。
いや、アンドレスの真意は、結局は、今も、わかりはしない。
アンドレスの自分に対する感情がどうであるか、ということよりも、むしろ、コイユールは、己のアンドレスに対する感情の強さを、再び、真正面から突きつけられた思いに憑かれていたのだった。
アンドレスがインカ軍で重要な位置にあり、彼なりに懸命にその責を果たそうとしていることを認識していた彼女は、彼が存分に力を発揮できるように決して邪魔はすまいと、そして、自分も自分なりにインカのために精一杯のことをしていくのみだと、心を既に整理していたはずだった。
だというのに、偶然、アンドレスを間近に目にしただけで、これほどに心が動揺し、胸苦しいのは、どうしたことだろう…――!!
(私、本当は、アンドレスのこと…全然、気持ちの整理なんて、ついていないのでは?)
自問自答しながら、無意識に深い溜息が漏れる。

ふと気付くと、すっかり上の空になっていた自分の手は、全く誤った薬草の配合をしているではないか。
(いけない…しっかりしないと!!)
すっかり慌てて薬草を配合し直しているコイユールに、やはり負傷兵の看護に当たるインカ族の女性が、心配そうに視線を向けた。
「コイユール、少し休んだ方がいいわ。
ここは、私が見ているから、ね。」
と、優しい笑顔で促してくれる。
コイユールは申し訳なさそうに瞳を揺らしたが、しかし、とても仕事が手につく状態でないのは、自分が一番よくわかっていた。
「ありがとう…。
それじゃ、ちょっと…外の空気でも吸ってこようかしら。」
「行ってらっしゃい。」
再び相手の優しい笑顔に背中を押され、コイユールも微笑み返し、「それじゃ…。」と、治療場を出ていった。
治療場を出ると、既に、雪のやんだ夜の野営場のそこかしこからは、兵たちが炊き出しをしているのだろう、煮炊きされた食物のにおいが漂ってくる。
そんな空気の中を歩んでいると、ふと、祖母のいる故郷が無性に懐かしく思い起こされてきた。
「お婆ちゃん…どうしているかしら…。」
しかし、たちまち故郷の連想の中から祖母の姿は消えゆき、やはり、そこに現われ出(い)でてくるのは、まだ少年だった懐かしくも愛しいアンドレスの姿ばかりであった。
いっそう切ない思いで胸が締めつけられる。
コイユールは、記憶を吹き飛ばすように、思い切り頭を振った。
そして、険しい目で前方を見据えながら、意識的にアンドレスのことは考えまいとしながら、当ても無くただ野営地を歩みはじめた。

力無く歩むコイユールの足は、結局は向かう場所など無く、いつの間にか自分の属するビルカパサの連隊が天幕を張る界隈へと戻ってきていた。
そのまま所在無く歩いていると、5~6名の馴染みの兵たちが天幕の片隅で円陣を組み、笑顔になったり、時に深刻な表情になったりしながら、談笑している様子が目に入る。
コイユールも、ふらりと、そちらの集団の方に足が向く。
その円陣の中心に陣取っているのは相変わらずあの黒人青年ジェロニモで、彼はやや興奮気味になりながら、周囲の兵たちに何やら夢中で説明している。
「それが、ホントに、すごかったのサ!!
いや…いつも、全く、驚くばかりなんだけどね。
だけど、今日は特に凄まじかった!!
馬に乗ったり、下りたりしながらサ、蒼く光るようなサーベルを振り翳し、次々と敵をなぎ倒していくんだ。
いや…本当に、人間ワザとは思えない…ちょっと、あれを間近で見たら、ゾッとするくらい…だぜ、全く…!!」
恍惚とした表情で身振りを交えて語るジェロニモを、周りの兵たちも顔を輝かせながら、あるいは、やや慄きの眼差しで、固唾を呑んで聞いている。
「いやあ、ジェロニモの話を聞くと、俺も見てみたいって、いつも思うんだけどな…。
だがなあ…、実際、あの戦場じゃあ、とてもそんな…見てる余裕なんてないねえ、俺には。」
周りで聞いていた男たちが、溜息混じりに言う。
ジェロニモも頷き、そして、相変わらず興奮を滲ませた声で言う。
「ああ、俺もはじめはそうだった。
だけど、あの姿を見ると、なんだか勇気が湧くっていうか、やる気になるんだ!!
だから、つい、探して見ちまうのサ!!」
周囲の男たちが、再び、眩しそうな眼差しで頷き返す。
一方、ジェロニモは、やや声のトーンを落として、深刻な表情になった。
「だけど…いつも、最前線に立って、あんなに派手に振舞っていちゃあ、幾ら命があっても、足りないっても思うぜ。
まあ…余計なお世話には違いないが、心配になる時もある。
何でもありの戦場じゃあ、目立つ奴ほど狙われるのが常だ。
ましてや、あたりには、鉄砲の弾がガンガン飛んでるんだし、ナ。
まだお若いのに、難儀に思えてしまことさえある…。
あのおかたが命を落とされるなんてことになったら、それは勿体無いって…、はは…いや、余計なお世話だろうけど、つい、思っちまうんだよナ。」
「そ…それって、誰のこと…?」
「…――え?!」
不意に背後から女性の声がして、ジェロニモや他の兵たちが振り返った先には、いつの間にそこにいたのか、コイユールの立ち竦(すく)む姿があった。
「なんだ、驚いた!コイユールか。戻ったの?」と、声をかけるジェロニモの視線の先で、しかし、コイユールは完全に顔色を無くし、強張った表情でこちらを凝視している。
そのただならぬ様子は、ジェロニモのみならず、そこにいた他の兵たちにもハッキリとわかるほどで、皆、驚いたように互いに目配せし合う。
一方、当のコイユールはそんな周囲の様子など全く目に入らぬ様子で、「今、話していた人って、誰のこと?!まさか…!!」と、殆ど睨みつけるがごとくの険しい目になってジェロニモに詰め寄った。
やや訝しげな目になりながらも、ジェロニモがありのままに応える。
「ああ、今のは、アンドレス様のことだよ。
コイユールは知らないかもしれないが、インカ軍の最年少の連隊長さ。」
「アンドレス!!…やっぱり…!!」
「『アンドレス』…?!」
いきなりコイユールが連隊長の一人を呼び捨てにしたのには、周りの方が驚いて目を見張る。
「あ…いえ…アンドレス…様…。」
さすがに冷ややかに注がれる周りの空気に我に返ったコイユールが訂正するものの、皆、興ざめした表情になると、「そろそろ寝るか…。」と、その場を立ち去りはじめる。
「あ…ああ、おやすみ!」
そう皆に返事を送るジェロニモの、そのすぐ脇までコイユールは再び詰め寄った。
「もっと詳しく教えて、ジェロニモ。
アンドレス様の戦場でのご様子は…?!
そんなに危ないことをしているの?!」
睨んでいるのか、泣きそうなのか分らぬ表情でしつこく詰めてくるコイユールに、ジェロニモは、ますます不審の表情になる。
「今、話した通りサ。
俺が見たのは、それだけだ。
それより、何なんだ?
コイユール、まさか、アンドレス様と知り合いか何か?
そういやあ、君はマルセラ様とも知り合いだったし、ナ。」
やや皮相なジェロニモの目つきと口調に、コイユールは言葉を呑む。
言葉に詰まったように固まってしまったコイユールに、ジェロニモは真正面から向き直った。
「そうなのか、コイユール?!
まさか…本当に、アンドレス様と知り合いなのか?!」
「いえ…まさか、そんな…。」
「それじゃあ、ナゼ、そんなに気にする?」
口ごもるコイユールに、今度は逆にジェロニモが詰めた。
「今更、隠し事なんて、水臭いナ。」
「それは…。
ただ、知りたくて…。」
下を向いてしまったコイユールに、ジェロニモはじっと視線を注ぐ。
コイユールの握り締めた華奢な指が、明らかに震えている。
ジェロニモは一つ深く溜息をつくと、いつもの落ち着いた声に戻って言った。
「アンドレス様の敵を倒す腕はスゴイよ。
俺には、人間ワザとは思えない。
だけど、最前線で、あんなことを続けていたら…命の保障はできないだろう。
それだけは、言える。」
再び顔を上げて愕然とした表情で喰い入るように己を見据えるコイユールの目の色を確かめると、ジェロニモは真顔で「やっぱり、そうか…知り合いなのか…。」と、独り言のように呟く。
そして、さっと視線をそらすと、全てを吹き飛ばすように大きく伸びをした。
「ああ~!!
それにしても、今日は良く戦ったナぁ。」
そう言って己の天幕の方に向き直り、去りかけて、もう一度、ジェロニモが振り返る。
「アンドレス様には、立派な馬も、恐ろしく良く切れるサーベルもある。
それに比べて、俺たち義勇兵は、斧や棍棒がせいぜいだ。
…――こっちだって、死ぬか生きるかの瀬戸際なんだぜ。」
その口調は、本人も驚くほどに深刻だった。
コイユールは胸を突かれたように、固まったまま、完全に動けなくなっている。
一方、そこまで言ってしまってから、ジェロニモは急に我に返ったように慌てた表情になると、コイユールに再び向き直った。
そして、今しがたの自分の発言を打ち消すように、いつもの冗談めかした笑顔をつくる。
「…ったくぅ、コイユールが、あんまり深刻な顔してるから、俺にまで移ったじゃないかぁ!
ホラホラ、コイユール、なんだかよくわかんないけど、元気だせって!!
なんなら、また、ここで一緒に踊る?」
「ジェロニモ…。」
コイユールも懸命に笑顔をつくろうとするが、顔の筋肉が固まってしまったように動かない。
そんな彼女から視線をはずしたジェロニモの横顔には、ふと寂しげな色がよぎる。
「事情は知らないケドさ、それにしたって…、あ~あ、コイユールも、やっぱアンドレス様かぁ…。
ちぇっ、やっぱ、カッコイイもんナ~!!」
愕然とした目の色のコイユールに、「ああ!!もう、冗談だって!!そこで突っ込んでくれないと~!」と、ジェロニモは笑顔をつくるが、彼のその表情もどこかいつもと違って無理がある。
そして、ついに観念したように、ポツリと言う。
「本当はサ、少しは、喜んでほしかったナ…こうして、俺が生きて戻ったこと。」
(あ…それは…もちろん…――!!)
コイユールが声にならない言葉を必死に搾り出そうとしている間に、ジェロニモはふっと溜息をつくと、「おやすみ。」と小さく笑って自分の寝所に向かって足早に去っていった。
後には、さらに胸を突かれたような表情のコイユールだけが残された。

その夜、アンドレスとコイユールは、野営場のそれぞれ別の場所から、同じ月を見ていた。
先ほどまで降りしきっていた雪も、まるで嘘のように、今、空は澄み渡り、初夏の星座が輝いている。
標高の高いアンデスの地では、手に届くほどの近さに、無数の星々を感じることができる。
コイユールは治療場へ戻る足が止まったまま、震えるような瞳で、白々とした光を地に注ぎ続ける月を、そして、星々を見つめていた。
先刻のジェロニモとのやり取り、そして、トゥパク・アマルの側近たちの負傷の姿、次々と治療場へ運び込まれる負傷兵たちの悲惨な状態が、生々しく脳裏に飛来しては、嘔気を伴うほどの激しく不穏な感情を巻き起こした。
彼女は、ついに、草の上に小さく胃液を吐いてしまうほどだった。
(アンドレス…もし…今日…その身に何か起こっていたとしたら…、あるいは、この先、万一、命を…失うようなことになったら…――!!)
コイユールは、再び、草の上にうつ伏して吐いた。
(もし、アンドレスがいなくなったら…この世界からいなくなったら…?!)
足元の地面が崩れていくような錯覚に襲われる。
コイユールはひどく思いつめた目で、朦朧としながらも立ち上がった。
すぐさまアンドレスのもとに走り、もう戦うのをやめてほしいと訴えなければいけない!
少なくとも、前線で先陣切って戦うなどという危険きわまりない行為は、すぐにもやめさせなければいけない!!
彼女は、本気でそう思った。
本当に、自分の足に力が入っているのがわかる。
しかし、次の瞬間には、彼女は再び草の上に崩れるようにしゃがみこんだ。
再び、嘔気が突き上げる。
(そんなことできるわけがない…!)
アンドレスとて危険を承知の上で、己の意志で、命を懸けてやっていることなのだ。
インカの民の復権という、この二百年以上の間、この地の人々がずっと切望してきたその崇高な目的のために、全身全霊を懸けているのだから。
(でも、死んでほしくない、アンドレスに死んでほしくない…――!!)
コイユールは混乱した頭を両手で抱えこむようにして、震えながら草の上にうずくまった。
そして、アンドレスもまた、人気(ひとけ)の無い、いつもの素振りの練習場所で、粛々と白く輝く月を見上げていた。
あの修羅場のような戦闘が数時間前には展開していたなどまるで信じられぬほどに、美しく清らかな初夏の星たちが煌いている。
手の中にあるサーベルも、先ほど慎重に血糊を拭き取ったために、今は何事もなかったように月明かりを反射して濡れたように輝いている。
しかし、彼には、いつもと変わらぬ風情で清い光を放つそのサーベルが、どこかひどく白々しく思われた。
あれほど残虐に次々と人を切り刻み、唯一つの命を奪い去り、獰猛な魔物のごとくに、おびただしい生き血を吸ったくせに…――!!
まるで汚れたものを振り払うかのように、アンドレスは思わずサーベルを地に放り出した。
そのサーベルを握って素振りをする気になどには到底なれず、彼は皮相な気分で足元の地面に目を落とした。
本当に、これで正しい方向に進んでいるのだろうか。
己の為していることは、これで正しいのだろうか?
思わず両手で頭を押さえこむ。
熱くなった頭の中で、戦場の血みどろの情景が渦巻くように甦る。
己の刃にかかって死んでいく人々の悲痛なあの表情、あの絶叫、命あるものが息絶えていく瞬間、血の生臭いにおい…己の手で残虐な苦痛を与え、絶命させた無数の命――アンドレスもまた、突き上げる嘔気に苛(さいな)まれて、口元を押さえた。
背筋に、ひどい悪寒が走る。
急速に体温が下がるのを感じ、彼は思わず両肩を腕で押さえた。
「コイユール…。」
朦朧とした意識の中で、擦れた声でその名を呼ぶ。
俺のやっていることは、正しいか?
コイユール…俺のやっていることは正しいか?
教えてほしい、コイユール、君に…――。
「会いたい…。」
殆ど声にならぬ声で小さく呟き、アンドレスもまた、身を震わせるようにして草の上にうずくまった。
それからどれくらい時間が経っただろうか。
アンドレスはゆっくり身を起こし、先ほど放り出したサーベルを苦々しい気分で拾い上げた。
そして、心の中で己に毒づいた。
自分の為した所業をサーベルのせいにするなどと、何と愚かなこと。
すべては己の意志で行ったことだというのに。
そう、すべての責任は、自分自身にあるのだ。
アンドレスはやや引きつった表情のまま、天幕の方に戻っていった。

彼は自分の天幕に戻る前に、フランシスコの天幕に立ち寄った。
原因不明の高熱と呼吸困難に苦しんでいるその様子が、とても案じられた。
先刻、フランシスコの病状を尋ねたアンドレスに叔父のディエゴは、「精神的なショック状態らしい。」と、怪訝(けげん)そうな表情で応えていた。
あの勇猛果敢な猛将ディエゴには、激しい戦闘場面の体験によって精神的に参ってしまうなどとは、全く想像すらつかぬ別世界に違いなかった。
しかし、アンドレスは、たまたま己の場合は身体症状には表れていないだけで、その精神的な衝撃は同様であり、フランシスコの心境がとても良くわかる気がした。
アンドレスが訪れると、フランシスコは、天幕の周囲をトゥパク・アマルの精兵たちに護られながら、一人、天幕奥で身を横たえていた。
まだ大量の油汗を滲ませ、呼吸も不規則ではあったが、意識は戻っているようだ。
アンドレスがそっと近づくと、フランシスコもそちらに顔を向けた。
ひょろりとして普段から神経質そうでさえある繊細なその面持ちが、今宵はいつにも増して弱々しく悲痛に見える。
アンドレスはそんなフランシスコの表情にいっそうの悲愴感を覚えながら、深く頭を下げて礼を払った。
フランシスコも力無く、瞳で頷き返す。
「フランシスコ殿、お加減はいかがですか?」
アンドレスが、慎重に尋ねる。
「アンドレス…、このような見苦しいところを見せて、情けなく思うよ。」
そう言ってフランシスコは皮相な笑みを微かに浮かべ、「戦闘のショックによるものだなどと…。」と、苦しげに言う。
フランシスコの寝台の傍らに跪きながら、アンドレスは首を横に振った。
「いいえ、俺とて、同じ思いなのです。
むしろ、フランシスコ殿のようにお苦しみになるのは、人として自然な感情であると思います。
あれだけの壮絶な戦闘だったのです。
まるで…、まるで相手を、襲ってくる化け物か何かのように、切っては捨て、切っては捨て…!
人の命をそんなふうに…いくら敵だからって…!
あんな酷い所業を為しておいて、何も感じない方がどうかしているってもんです!!」
フランシスコを励ましているつもりが、次第に己の方が興奮しはじめ、その声さえ震えてきたのを感じて、アンドレスはハッと口をつぐんだ。
フランシスコは、無言で、そんな彼に視線を注いでいる。
いきなり本音を吐露してしまった決まり悪さから、アンドレスは思わず視線をそらした。
無意識にサーベルの鞘を握り締める。
今は魂の抜けたようなそのサーベルは、ただ冷たく、固い感触だけを彼の指に返してくる。
フランシスコはそんなアンドレスの様子に静かに目を細め、そっと微笑んだ。
「ありがとう、アンドレス。
そんなふうに言ってくれるのは、そなただけだ。」
「いえ…、そんな…。」
フランシスコの、この繊細で静かな雰囲気に、あのトゥパク・アマルも安らぎを覚えるのだろう、とアンドレスは改めて感じる。
実際、トゥパク・アマルは、フランシスコが倒れてから、あの重症を負っているビルカパサに対するのと同様の深い案じようを見せていた。
「トゥパク・アマル様も、とても心配しておられました。
フランシスコ殿の意識が戻られぬ間も、先ほどまで、ずっとこちらの天幕の中にお見舞いにいらしていたのですよ。」
そんなアンドレスの言葉に、フランシスコはかえって苦しげな表情になった。
気のせいか、油汗がいっそう噴出しはじめ、呼吸も荒くなってきたように見える。
アンドレスは心配になって、身を乗り出した。
「フランシスコ殿、大丈夫ですか?
何か、とてもお辛そうに見えます。
お苦しければ、すぐに医者を呼びますが…。」
「いや、いいのだ。」と、アンドレスを制し、フランシスコは苦渋に満ちた表情のまま、「トゥパク・アマル様には、全く、ご迷惑ばかりおかけしてしまって、わたしは身の置き所のない心境なのだよ。」と呟くように言う。
「え…?!」と、フランシスコの言葉に、アンドレスは息を呑む。
「キスピカンチ郡の代官カブレラを追跡した時も、結局、わたしは捕えることができなかった。
その挙句、あの代官がクスコに逃げ込んだがために、クスコに反乱のことが知られてしまったのだ。
あれほど、トゥパク・アマル様やミカエラ様が、情報の漏れぬように細心の注意を払っていらしたというのに…。」
そう言って、フランシスコは深い溜息を漏らした。
寝台に横たわるフランシスコのその横顔は、ひどい苦々しさを湛え、皮相に歪んでいく。
(フランシスコ殿…お一人で、そんな思いを抱えていらしたなんて…!!)
アンドレスはいたたまれぬ思いに激しく貫かれ、思わず身を乗り出した。
「あれは、フランシスコ殿のせいではありません!
追いかけても間に合わぬほどに、カブレラは早々に逃走していたのです。
トゥパク・アマル様とて、決して、フランシスコ殿を悪くなど思ってはおりません。」
アンドレスの眼差しは真剣で、全くの本心からの言葉であることがわかる。
フランシスコは静かに微笑み、しかし、すぐに苦しげな眼差しに戻って言う。
「トゥパク・アマル様は、表面にお気持ちは表さぬお方だ。
ご本心では、何を考えているかなぞ、わかるまい。
それに、他の側近の者たちがどう思っていることか…。
皆、口には出さぬだけで、きっと心の中では、わたしを責め、苛立っているに違いあるまい。」
「フランシスコ殿…!!」
アンドレスは言葉に詰まった。
他の側近の者とて、あなたを責めるような気持ちなど決してもってはおりません、と言いたかった。
しかし、フランシスコのひどく思いつめた、そして、既に壁で隔てられたような目の色に、今、安易な言葉がけは、かえってこの心に傷を負った人物の内面を閉ざさせてしまうように思われた。
暫し、重苦しい沈黙が流れた後、地を這うような低い声でフランシスコが言う。
「アンドレス、そなたは、インカ族ばかりの側近の中では、唯一、わたしと同じ混血児…。
わたしと同様に、半分は、あの憎きスペイン人の血が混ざっている…そなたなら、わたしの気持ちも少しはわかるであろう。
我々は、所詮、半端者なのだ。
最終的には、インカの民にも、スペイン人にも、なりきれぬ。
どっちに転ぼうとも、周囲の者たちとて、結局は、我々を本当には受けいれまいよ。」
そう言って、フランシスコはじっとアンドレスを見つめて、また続ける。
「一体何のために、戦うのか…こんな思いをしてまで…。」
「そんな…フランシスコ殿…。
待ってください。
何を仰っているのか…。」
己は完全にインカの人間だと信じてきたアンドレスにとって、フランシスコの言葉は、ひどい混乱を抱かせた。
しかも、フランシスコの、そのあまりに苦しげな目には、何かに憑かれたような、不安定な色が揺れている。
アンドレスはやや身を硬めながら、その目の色に圧(お)されるように微かに後退った。
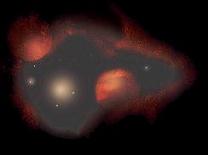
一方、ひるみはじめたアンドレスの様子を見抜くように、フランシスコは僅かに笑う。
「アンドレス、聞いてくれるか。」
「いえ…ちょっと待ってください。」
混乱しはじめたアンドレスが、己の指で額を押さえているのを認めると、フランシスコは、さらに意味ありげに声をたてずに笑う。
そして、アンドレスの制するのも構わず、むしろ、その混乱を煽るように、低い声で諭すように話しはじめた。
「アンドレス、聞いてくれ。
わたしは、キスピカンチ郡の代官を逃してしまった汚名を注ぎたくて、今回のサンガララでは力を奮いたかった。
だが、実際には、あの恐ろしい戦場でわたしは身が竦んでしまったのだよ。
わたしは、あの戦場で逃げ続けた。
ふふ…そんなことは、トゥパク・アマル様には言えないが…。」
そう言って、フランシスコは皮相に鼻で自嘲する。
アンドレスは、額を押さえている指の間から、驚愕の目でフランシスコを見据えた。
「え…?
な、何を…言い出すのです。」
愕然としているアンドレスに視線を注ぎ続けたまま、まるで囁きかけるようにフランシスコが続ける。
「今日、あの戦場で、わたしは、自分が生き残るのに必死だった。
そなたが苦悩するようなことは…敵を切るなど、そんな余裕はわたしには無かった。
…わたしは、ただひたすら逃げ続けたのだよ。
あの酷い戦闘のどさくさに、味方の中に身を潜ませ、敵の刃を逃れて、必死に…。
そう…味方さえ、盾にしたさ。
そうでもしなければ、わたしは今頃、死んでいた。
そして、やっとのことで生き延びた。
…本当に怖かったのだ。
怖くて、怖くて…その挙句が、このざまだ。」
天幕の中に点る蝋燭の灯りに浮き上がるフランシスコの横顔は、今や不気味に歪み、苦悶そのものだった。
滲んだ額の無数の油汗が、その粒の一つ一つにまで蝋燭の炎を映し出す。

そして、再び、苦々しく自嘲した後、アンドレスを見つめ、ふっと微笑んだ。
「アンドレス、そなたは勇敢で、心根も、姿も、美しい。
トゥパク・アマル様の覚えもめでたい。
実に、羨ましいよ。」
「…!!」
瞬間、アンドレスは反射的に身を固めた。
一方、フランシスコは、完全に表情を失っているアンドレスを斜めに見上げ、再び声をたてずに笑う。
今、呆然と見開かれたアンドレスの瞳の中で、フランシスコのその微笑みは何かひどく不可解な色を放って見えた。
喉元に何かがつまったようにアンドレスは息苦しさを覚え、やっとのことでゴクリと唾を呑む。
辺りの空気が、まるで水底のように冷え冷えと感じられた。
己の目と耳を疑うように、アンドレスは瞬きをして、頭を振る。
そして、再び、息を殺してフランシスコを見た。
しかし、フランシスコの眼差しは、これまで彼が知っているフランシスコとは明らかに異なる、底知れぬ異様な、何か背筋を凍らすような色味を発した微笑みを相変わらず湛えたまま、じっとアンドレスを見つめている。
アンドレスは混乱の極みに達したままに、しかし、その混乱の糸を解こうと、フランシスコの方に身を乗り出して必死に声を絞り出す。
「フランシスコ殿…待ってください…。
え…?
戦場で、あなたは…。
あ、今、何と…。」
しかし、混乱した頭では、どこから何を聞いていいのかさえわからない。

一方、フランシスコは不意に真顔になる。
「トゥパク・アマル様に、このことを話すか?
アンドレス。」
「…!」
グッと言葉を呑み込んだまま硬直しているアンドレスを見上げるフランスコの表情は、今、完全に笑みをひそめ、みるみる固く強張っていく。
「このようなことをトゥパク・アマル様や他の側近たちに知られたら、わたしの立場も信用も完全になくなる。
アンドレス…そなたを見込んで打ち明けたのだ。
わかるね…これは、そなたとわたしだけの秘密だ。」
「しかし…これからも戦(いくさ)は続くのですよ…。
お一人で抱えられるよりも、本当のことを打ち明け、フランシスコ殿のお心の負担が少なくなるよう、トゥパク・アマル様とも相談をされる方がよいのでは…。」
混乱から抜けきれぬままの表情で、しかし、アンドレスは精一杯の穏やかな声で諭すように語りかける。
しかし、フランシスコは、「だめだ!!絶対に、話さないでくれ。」と鋭く制すると、懇願するような目の色に変わり、「後生だ、アンドレス…。これ以上、生き恥を晒せようか…わたしの気持ちをわかっておくれ。」とすがるように言う。
「フランシスコ殿…。」
「頼む…アンドレス…。」
「…。」
ついにアンドレスは、観念したように頷いた。
「わかりました…。
俺の胸の内にしまいましょう。」
フランシスコは大きく息をつくと、深い安堵の表情になった。
それから、再び、声をたてずに意味ありげに笑う。
「そなたは、本当に、いい子だね…、アンドレス。」
息を詰めて身を固めるアンドレスの方に、フランシスコが、その痩せた片腕をゆっくり伸ばす。
そして、不意に、その細く長い指でアンドレスの頬を包み、それから、まるで愛撫するようにその手を動かすと、そのまま指でアンドレスの唇に触れた。
「…!!」
「トゥパク・アマル様の寵愛を受けている秘密兵器が、そなたなのだよ、アンドレス。
だが、まだ、あまりに若い…いや、青い、というべきか。」
アンドレスは、はじかれたように後方に飛び退った。
そして、もはや完全に言葉を失ったまま目を白黒させ、殆ど無意識的に一礼すると、逃れるようにその場を離れた。
走るようにして、その天幕を出る。
(何だったんだ、今のは…――?!)
彼は、あまりに酷い悪夢を見た後のような激しい不穏な念に憑かれ、自分の天幕に急ぎ足で引き返した。
「ああ…、今日は、いろいろなことがありすぎた…!!」
そして、完全に混乱した額を激しく押さえこんだまま、己の天幕の中に、まるで目に見えぬ何者かから逃れ去るように駆け込んだ。
◆◇◆ここまでお読みくださり、誠にありがとうございました。続きは、フリーページ 第五話 サンガララの戦(4) をご覧ください。◆◇◆
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- これは一気読みしました ブリット・…
- (2024-11-27 00:00:27)
-
-
-

- 読書備忘録
- 信長の原理 垣根 涼介
- (2024-11-25 22:57:45)
-
-
-
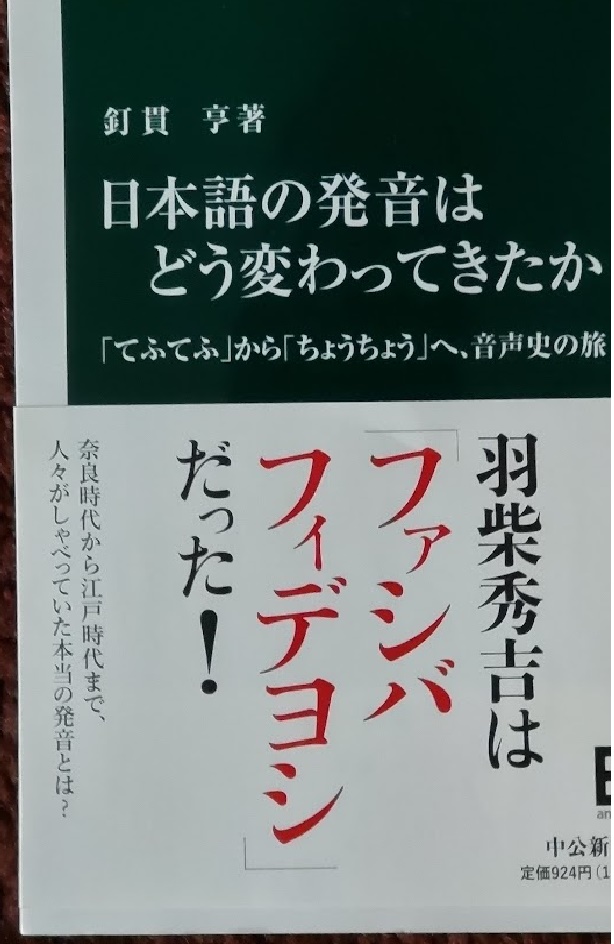
- 最近、読んだ本を教えて!
- 分かります タイムマシンがなくてもね
- (2024-11-26 09:02:54)
-
© Rakuten Group, Inc.


