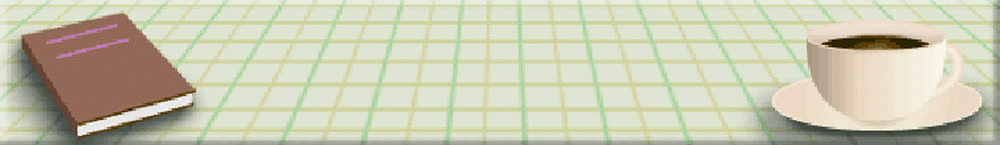PR
2024年11月
2024年10月
2024年08月
カテゴリ
空白
(216)妙に知(明日)の日記
(1580)新・知だらけの学習塾
(564)新・営業リーダーのための「めんどうかい」
(358)完全版シナリオ「ビリーの挑戦」
(261)知育タンスの引き出し
(317)営業の「質を測るものさし」あります
(104)のほほんのほんの本
(386)乱知タイム
(71)国内「あ」の著者
(24)国内「い」の著者
(28)国内「う」の著者
(11)国内「え」の著者
(5)国内「お」の著者
(21)国内「か」の著者
(21)国内「き」の著者
(9)国内「く・け」の著者
(14)国内「こ」の著者
(18)国内「さ」の著者
(17)国内「し」の著者
(27)国内「すせそ」の著者
(8)国内「た」の著者
(23)国内「ち・つ」の著者
(10)国内「て・と」の著者
(14)国内「な」の著者
(16)国内「にぬね」の著者
(5)国内「の」の著者
(6)国内「は」の著者B
(13)国内「ひ」の著者B
(12)国内「ふ・へ」の著者A
(10)国内「ほ」の著者A
(7)国内「ま」の著者A
(16)国内「み」の著者
(22)国内「む」の著者
(15)国内「め・も」の著者
(10)国内「や」の著者
(14)国内「ゆ」の著者
(3)国内「よ」の著者
(10)国内「ら・わ」行の著者
(4)海外「ア」行の著者
(28)海外「カ」行の著者
(28)サ行の著作者(海外)の書評
(23)タ行の著作者(海外)の書評
(25)ナ行の著作者(海外)の書評
(1)ハ行の著作者(海外)の書評
(27)マ行の著作者(海外)の書評
(12)ヤ行の著作者(海外)の書評
(1)ラ・ワ行の著作者(海外)の書評
(10)営業マン必読小説:どん底塾の3人
(56)笑話の時代
(19)「ビリーの挑戦」第2部・伝説のSSTプロジェクトに挑む
(124)知だらけの学習塾
(105)銀塾・知だらけの学習塾
(116)雑文倉庫
(44)キーワードサーチ
コメント新着
サイド自由欄
■川端康成『雪国』(新潮文庫)

◎名詞に注意してじっくりと読む
『雪国』の冒頭は、あまりにも有名な文章です。
――国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。(本文冒頭より)
だれもがこのフレーズまでは、そらんじていえることでしょう。国境、長いトンネル、雪国、夜の底、信号所、汽車……。川端康成は短いフレーズのなかに、幻想的な名詞を重ねて「冒頭」部分をきわだたせています。
長いトンネル(清水トンネル)を抜けて、黒い塊は水上町から湯沢町(雪国)へと入ります。トンネルを抜けたところに、信号所があります。重い連結音を響かせ、汽車は止まります。冒頭のつづきを引用してみます。
――向側の座席から娘が立って来て、島村の前のガラス窓を落とした。雪の冷気が流れこんだ。娘は窓いっぱいに乗り出して、遠くへ叫ぶように、/「駅長さあん。」/明りをさげてゆっくり雪を踏んで来た男は、襟巻きで鼻の上まで包み、耳に帽子の毛皮を垂れていた。(本文冒頭のつづき)
向側の座席、娘(葉子)、島村、ガラス窓、駅長……。さり気なく、今度も名詞を並べています。しかし冒頭の3句とは、まったく意味合いの異なる羅列です。この点が、川端康成の作品の巧みさだと思います。
「向側」とは、ボックス席の前という位置関係ではありません。やがて明らかになりますが、油を塗りたくった黒ずんだ通路の向こうを指しています。「娘」は葉子という名前です。葉子の前の席には、病気らしい男が横たわっています。「島村」は、葉子を観察しているだけの存在にすぎません。
昔の汽車は、窓を開けて駅弁を買うことができました。川端康成は巧みに、窓ガラスを鏡に変化させます。私はこの小道具に、うなってしまいました。「駅長」は、葉子の弟の存在を、確認させるだけの道具だてとなっています。
世の中に出回っている「あらすじ本」には、肝心な部分が欠落しています。川端康成の作品に、「あらすじ」はなじみません。名詞に留意して、じっくりと読み進めてもらいたいと思うからです。
『伊豆の踊子』(集英社文庫)と『雪国』(新潮文庫)を熟読してみて、私はある法則を発見しました。いまを必死に生きる女性(前者では踊子、後者は駒子または葉子)と、いまをもてあましている主人公(前者は私・一高生、後者は島村)との対比です。
『雪国』ではその対比が、鮮やかに描かれています。汽車に乗り合わせた島村は、暗くなった窓外を見ています。そこに葉子の顔が映ります。葉子のぼんやりとした顔には、外の灯りが重なります。これが『雪国』の、象徴的な場面です。川端康成は登場人物の心象を、たよりない淡い情景に重ねてみせる名手なのです。
川端康成は『伊豆の踊子』(1926年=大正15年)年で、文壇に名をなしました。その後、『雪国』(1935年=昭和10年)を上梓するまでに、約10年の歳月を費やしています。当時の文壇は、「プロレタリア文学」が勢力をきわめていました。また谷崎潤一郎や永井荷風といった「既存作家」の活動も活発でした。川端康成や横光利一が唱える「新感覚派」は片身の狭い思いをしていました。
川端康成は、プロレタリア文学を嫌っていました。代表的なプロレタリア文学作品(※印)をならべてみます。川端康成の代表的な作品年譜を併記しますので、くらべてみてください。また川端康成は、外国文学から技法などを寸借する潮流のなかに、埋没しつつある自身に気づいていました。
【1926(大正15)年】
○川端康成『伊豆の踊子』(新潮文庫)
※葉山嘉樹『海に生くる人』(岩波文庫)
【1929(昭和4)年】
○川端康成『浅草紅団』(講談社文芸文庫)
※小林多喜二『蟹工船』(新潮文庫)
※徳永直『太陽のない街』(岩波文庫)
【1933(昭和8)年】
〇川端康成『禽獣』(新潮文庫『伊豆の踊子』所収)
【1935(昭和10)年】
○川端康成『雪国』(新潮文庫)
※中野重治『村の家』(講談社文芸文庫)
【1942(昭和17)年】
○川端康成『名人』(新潮文庫)
プロレタリア文学隆盛のなかで、川端康成は独自の道を歩きつづけます。その後プロレタリア文学は衰退するのですが、近年小林多喜二『蟹工船』が爆発的に売れました。きっと川端康成は、苦い顔をしていることでしょう。
◎モダニズムからの脱皮
吉本隆明の著作は難解です。大学時代は背伸びをして読みましたが、社会人になってからは手にすることはありません。ただし1冊だけ、たいへんお世話になっている著作があります。2001年に毎日新聞社から刊行された『日本近代文学の名作』(現・新潮文庫)です。夏目漱石『こころ』、太宰治『斜陽』などとならんで、『雪国』もとりあげられています。非常にわかりやすいブックナビで、重宝しております。
――『雪国』はモダニズム的な作品(補:『浅草紅団』講談社文芸文庫などのこと)から日本の古典主義的な美意識に連なる作品へと転換していく最初の優れた小説として位置づけられる。『雪国』を契機にして、川端はモダニズムから脱し、長編作家としての個性を発揮していった。それは戦後の長編『山の音』や『古都』(ともに新潮文庫)へとつながっていく。(吉本隆明『日本近代文学の名作』新潮文庫、P75)
「モダニズム文学」についての説明は、ドナルド・キーンにゆだねることにします。
――モダニズム文学は、単なる近代的な文学とは違って、作者が意識的に作品の中にそれとわかる非伝統的な要素をとり入れようとしているのが特色である。(ドナルド・キーン『日本文学史・近代現代篇4』中公文庫、P8)
『雪国』は川端康成作品の分水嶺だった、と吉本隆明はいっています。その点について川端康成自身は、つぎのように語っています。これもドナルド・キーンの著作からの借りものです。
――通俗小説に筆を染め始めたこの時期に、川端は、純文学の敵は岩波文庫の赤帯(外国文学の翻訳)だという発言をしている。純文学すなわち大衆の嗜好に迎合しない文学の領域でヨーロッパの大作家に対抗するのがいかに困難かを、川端は感じたのであろう。(ドナルド・キーン『日本文学史・近代現代篇4』中公文庫、P233)
川端康成は決然とプロレタリア文学に背をむけ、押し寄せる外国文学を踏みにじります。そして生まれたのが『雪国』だったのです。ところが川端康成の意図は、安部公房には通じていません。安部は『雪国』から、岩波文庫赤帯に近い匂いを感じているのです。ドナルド・キーンと安部公房の対談の一部を紹介します。「川端康成の小説は非常に日本的だと思います」(補:話題の対象は『雪国』です)というドナルド・キーンにたいして、安部公房はつぎのように反論しています。
――恋愛を描いた日本の現代文学の傑作に至っては、志賀直哉氏の「暗夜行路」の或る部分と川端康成氏の「雪国」が頭に浮かぶ位なものである。(吉田健一:『文学人生案内』講談社文芸文庫)
いずれにしても激動の昭和初期の文壇で、川端康成は独自の美的世界をつらぬきとおしたといえます。赤いプロレタリア文学の嵐と、赤帯に影響された文学の波とに揺られ、川端文学はひっそりと船出した白い小舟に似ていました。
(山本藤光:2012.10.12初稿、2014.09.30改稿)
-
門田隆将『死の淵を見た男』(角川文庫) 2020年04月30日
-
川越宗一『熱源』(文藝春秋) 2020年02月23日
-
角野栄子『魔女の宅急便』(全6巻、角川文… 2018年12月08日