-
1

春を探して スズメノエンドウ カラスノエンドウ
最強の寒波が猛威を振るっている昨今そんな最中、春を探してみました。植物たちは負けずに咲き出していました。
2025/02/15
閲覧総数 57
-
2

筑波山で出会った花 ヤマアジサイ シモツケ他
梅雨の晴れ間に出かけた筑波山思いのほか、木の花にも出会えました。ヤマアジサイ(山紫陽花)ヤブムラサキ(藪紫)ビロードのような手触りの葉っぱですヤブムラサキ花の周りは毛むくじゃらムラサキシキブ(紫式部)シモツケ(下野)ツルアリドオシ(蔓蟻通し)仲良くこのこたちだけが咲いていました。実になるときは合体しちゃいます。コアジサイ(小紫陽花)線香花火のように弾けてきれいウツギ(空木)ウツギ蜜を求めて蝶さんたちがたくさん飛んでいましたが撮れず・・・でしたイワガラミ(岩絡み)ツルアジサイ(蔓紫陽花)に似ているけど、花びらのような装飾花は1枚サカキ(榊)筑波山神社の境内に咲いていました。モミジイチゴ(紅葉苺)キイチゴといわれているおいしい苺ですモミジイチゴヤマウグイスカグラ(山鶯神楽)一つだけ残っていた実気が付かなかったけど、PCに取り込んだら毛がいっぱいヤマウグイスカグラでした。ニワトコ(接骨木)の赤い実去年まで住んでいた佐倉市には、キミノニワトコ(黄実の接骨木)がありました。ミヤマシキミ(深山樒)シキミといっても、仏さまのシキミとは全然違ってます。別名 億両ですが ??? なんでかな???トンボさんがたくさん飛んでいました。(完)
2020/07/04
閲覧総数 448
-
3

この花に逢いたくて 千葉市内でセツブンソウ
1ケ月ほど前に花友さんから情報をいただいて、植栽のセリバオウレンを見に行きましたが、今回は、セツブンソウの情報をいただきました。もちろん、千葉に自生地はありません、植栽です。セツブンソウは石灰岩を好む植物ですので、土には石灰がすき込んであるようで、それでも咲くのですね。毎年のように自生地に見に行っていましたが、今年はコロナ感染拡大で緊急事態宣言で遠出ができません。セツブンソウに出会えて感動しました。セツブンソウ(節分草)
2021/02/09
閲覧総数 992
-
4

春の筑波山で出会った花たち1
今更ですが、載せそびれた花たちです。ヤマブキソウ(山吹草)ツルキンバイ(蔓金梅)ワチガイソウ(輪違草)ワチガイソウトウゴクサバノオ(東国鯖の尾)花と実実の形が鯖に似ているからが由来トウゴクサバノオトウゴクサバノオチゴユリ(稚児百合)ツクバキンモンソウ(筑波金紋草)クリンユキフデ(九輪雪筆)クリンユキフデクリンユキフデタガネソウ(鏨草)タガネソウツクバネソウ(衝羽根草)ツクバネソウウスバサイシン(薄葉細辛)ニリンソウ(二輪草)ニリンソウ(二輪草)ミミガタテンナンショウ(耳形天南星)マルバコンロンソウ(丸葉崑崙草)ミヤマハコベ(深山繫縷)ユキザワ(雪笹)ユキザサオドリコソウ(踊子草)スミレ(菫)マンジョリカノジスミレ(野路菫)?フモトスミレ(麓菫)フモトスミレフモトスミレツボスミレ(坪菫)アケボノスミレ(曙菫)アケボノスミレアケボノスミレ
2023/05/26
閲覧総数 177
-
5

春を探して 菜の花
河津桜のツボミが膨らんできました。
2025/02/14
閲覧総数 57
-
6

鋸山 地獄の階段歩き 最終章
日帰りでひっぱりすぎの鋸山、今日は最終章になりそうです。。。お付き合いくださいね~保田海岸の遠望です。晴れてたけど、風が強くてイマイチで、霞んじゃってるけど・・・右のほうに見える小さな島は、先月孫達と遊覧船で巡った島鋸山山行記(1)鋸山山行記(2)車力道の分岐を過ぎたところからが、はじめて歩くコースです。小さなアップダウンを繰り返し、いよいよ最後の「絶壁階段」を登って尾根にあがります。。これが階段極めつけ・・凄い、さすが「絶壁階段」というだけのことはあり・・最初は関東ふれあいの道特有?の丸太を2段に重ねた階段で、次に段差の深い石階段、ここが整備されて階段に手すりがついてるけど、なかったらこわいよ、四つんばいで?ふうふういいながら、登りきったところが、山頂と展望台の分岐点、「地球が丸く見える展望台」へ風が強く、ガスって遠望はできないものの、向かい側には、あの「地獄のぞき」の展望台がみえます。コンクリートの建物はロープウェー山頂駅、茶色く見えるのが、「地獄のぞき」の展望台いつか鋸山の山頂へ行ってみたいなって、向こうの展望台から眺めていたんだなと・・こちらの展望台からみる初めての景色に感激!お天気がよかったら、、富士山も見えるんだけど・・・「里見八犬伝」の舞台になった「富山」もきれいな山容を見せてくれてます。6人ぐらいのグループが登ってきました。きょう唯一、出会った人達でした。しばらく休憩して、いよいよ山頂を目指します。 雑木の中の小さなアップダウンを繰り返し、やっぱり階段・・・ NTTのパラボナアンテナや千葉テレビの送信所を越えてそのまた、先を越えたところが山頂です。 一等三角点の山頂(標高329.5m)です。展望のないほんの小さな広場になっていてベンチが一つ置いてありました。。 はじめての山頂 ちょっと早めのお昼にしました。今回はSさんが全部用意してきてくれました。いつものお返しだよって・・・いつもはガスとコーヒー、味噌汁など持つhimekyonですが、亀足で迷惑かけちゃ悪いかなといったんザックに入れたものを置いてきちゃいました。ごちそうさまでした~まあ、あとは下山だけですので、ちょっとのんびりです。。。。しかし、風が強かった・・・・いよいよ下山開始 またまた階段だ~これがけっこう長い、、、右側の展望が開けていて、海を眺めたり、鋸山ダムの展望を見ながら、尾根道のアップダウンを繰り返して、杉の植林地の中へ下りてくると林道口に到着、無事に下山しました。ところがです。ここからが長いんです。保田駅まで、1時間15分、逆コースじゃ、登山口まで行くのに疲れて、登るのが嫌になっちゃうかも・・・ この林道を延々と歩きました。山を歩く距離よりも林道歩きが長かった 鋸山ダム 館山道をくぐると保田の集落が見えてきます今日一日歩いたスカイラインを眺めて感無量駅についたら、タイミングよく、ばんやの無料バスがあり、ばんやの湯に入って汗を流してから、Sさんたちと別れて、5/13の日記に書いた、息子達と合流して帰途につきました。念願の新コース、ほぼ90%は階段だったけど・・・交通の便の悪い千葉の山としては、駅から駅に歩けて、低山ながら楽しい山歩きができるコースでした。前日に、クライミングの先輩に話したら、以前はおもしろかったけど、整備されちゃっておもしろくなくなっちゃったよって・・・もっとスリルがあったのかな、、でもでも楽しく歩けましたよ。。。千葉もなかなかいいとこあるじゃん!!でも、マムシにヒルは願い下げだね、やっぱり秋~春先までが千葉の山かもね今度はどこへ行きましょうかね。。。。人気blogランキングへ ←押していただけたらうれしいです
2007/05/19
閲覧総数 891
-
7

初登りは山中湖村 石割山
天候不良で、暮れのどたん場にキャンセルした山小屋泊の山行キャンセルの電話をしたらオーナーさんが台風並みの風、身の安全が大事ですからまた別の機会においでください。とおっしゃってくださいました。急遽、何度かお世話になっている山中湖畔の民宿が取れて無事に年越しができました。登り納めは山中湖村の鉄砲木ノ頭へ初登りは同じく山中湖村の石割山へ宿のおせち料理をおいしくいただき、車で登山口まで送っていただきました。石割山山頂(1412m)9年ぶり、4回目の石割山です。9年前は岩手県の山友さんと大晦日に本栖湖にテント泊して、元旦に竜ヶ岳に登りダイヤモンド富士を仰ぎ見て、その足で山中湖のペンションに泊まり1月2日に石割山に登りました。石割神社登山口赤い鳥居をくぐってスタートですしかし・・・403段の石段が待っていました。ここが一番の難所です・・・20段づつ足を変えながらゆっくりゆっくり登ります。登りきってあずまやで一息入れていたら20歳ぐらいの息子さんと登ってきたおかあさんこんなきついのにまだ先があるの、帰ろうかもう階段はありません、地図ではあと25分って書いてありますよそれならがんばろうかって歩いていきました(^^♪この壁は何だろう沢があるわけではないけど右奥を登ると石割神社のご神木 カツラの木今まで知らなかったけど、このカツラの木の後ろから湧き出している水が桂川の源流だそうな・・名前もこのカツラの木から取ったとのこと石割神社に到着ご神体の岩の割れ目が石の字に似ているからがいわれ天岩戸伝説といえば 宮崎県高千穂にある天岩戸と教えられてきたけれど(行きました)この石割神社が天岩戸伝説の地とのこと。この岩の裏側が縦に割れていて3回回ると願いが叶うとのいわれがあります。入口幅60センチの割れ目ここを時計回りに3回通ります。上から滴り落ちる水滴は眼病を治すとか(雨が降らずカラカラ)お参り済ませて山頂へ急登を20分で到着です。山頂からの富士山だいぶ雲が湧いてきています。南アルプスもくっきり南アルプスの百名山は聖岳と光岳は登りそこなったけど登った山が見えている~赤石岳と東岳(悪沢岳)かな間ノ岳と北岳かな鳳凰三山と甲斐駒ヶ岳かな石割山ハイキングコース入口バス停以前は石割山山頂から大平山ハイキングコースまで歩いたこともあったけど今回は石割山山頂をピストンして平野へ下山しました。このあとバスで移動して最後の目的地元旦の沈むダイヤモンド富士へ
2025/01/03
閲覧総数 128
-
8

今日は観光かな・・
今日のお出かけは・・・16000歩の観光だったかな奇跡のローカル線デハ801昭和25年生まれ一つ年下だね(^^♪経営危機を救った「ぬれ煎餅」赤、緑、青の袋は食べたことがあるけど「ひ志お」は初めて癖になるおいしさ、あっというまに10枚完食これは現地かネットでないと買えない・・こっちの方向からは初めてだもっとも早い初日の出が見られるんだって昔、昔、初日の出ツアーでこの地を訪れていたなぁ今年の大漁を願っての大漁旗江戸時代前期 和歌山から移り住んで水揚げ日本2位の漁港の基礎を築き上げた人の碑亀の子さまという祠漁師の網にかかったウミガメを海に返してあげるそうな実際にあった悲しい物語のよう・・この地にも義経伝説が・・昔は島になっていたらしい、義経の兵士がここに隠れたんだってこれも義経伝説義経に置きざりにされた愛犬が7日7晩鳴き続けて8日目に岩になっちゃったんだって屏風のような断崖あそこまで行くつもりだったけど・・・疲れた~( ;∀;)もしかして岩海苔?大きな伊勢海老・・ブランド海老「銚子黒潮海老」というそうな海老小屋があったけど「準備中」食べたかったな 残念!でも高そう・・開いてるお店発見開店したばかりみたい・・というか移転してきたばかりで以前からやっていたそうな満席で常連さんが多かったよくテレビで紹介されているそうで 相席になった女性もテレビで「〇川憲〇」がでていたので隣町からやってきたという隣のご夫婦は利根川を渡って茨城からきたそうな刺身と煮魚定食マグロ、ヒラメ、ヤリイカの刺身とブリカマの煮魚おいしゅうございました(^_-)-☆
2025/01/04
閲覧総数 117
-
9

山の会 山梨県大月市 扇山
月2回の例会予定は大月市の雁ヶ腹摺山でしたが、前日ネット検索していたら「林道冬季閉鎖」となっていて別の登山口があるのかなと幹事からのコース案内を見たら同じコース幹事にメールしたら、計画段階では冬季閉鎖の情報はなかったとのことでしたが、手前のバス停から登山口までは11キロとても歩くのは無理ということで今朝、大月駅に集合した段階で扇山に変更しました。中央高速道談合坂サービスエリアの向かいに見える扇の形をした山で大月市が制定した富岳秀麗十二景に選定されていて山頂から富士山が見えます。昨日まで3月ごろの陽気だったのが、今朝は寒さが戻り、山の天気はマイナス気温、曇り空で歩き始めは寒かったものの、勾配のある登り一辺倒の登山道で汗をかきました。登山口の駐車場から扇山山頂がみえました。登山口大久保のコルの水場山の神社奥宮つつじ群生地分岐百蔵山分岐やっと稜線にでました。尾根道10分で山頂です。扇山山頂(標高1138m)この間から富士山が見えるはず・・・山頂でランチ後に同じ道を下山
2025/01/25
閲覧総数 102
-
10

早春の栃木・星野のフクジュソウ
2月20日に出かけた栃木・星野のセツブンソウ自生地にはフクジュソウも咲いていました。Facebookのお友達・菊池つとむさんから情報をいただいて、植栽ですが、別の場所でも群生を見ることができました。植栽ですが、畑の持ち主の方が丹精込めて育て群生させたものです。柿の木の下や梅の木の下に一面に咲いています。背後にみえる山並みは栃木三峰山、2005年3月に登っています。野生のフクジュソウ
2020/03/03
閲覧総数 328
-
11

山の会 湯河原・幕山~南郷山 出会った花たち
山の会はのん兵衛仲間の会で花などまったく興味のない人たち大好きな花を見つけてもゆっくり見る時間なし、写真に撮る時間もなし・・ボケボケのスマホ写真ですが、忘備録としてUPします。ハンショウヅル(半鐘蔓)下向きに咲く花の形が半鐘に似ているからオオバウマノスズクサ(大葉馬の鈴草)食草を求めてジャコウアゲハがたくさん飛んでいました。ジガバチソウ(似我蜂草)?それともクモキリソウ(雲霧草)?花芽が少しだけ上がってきているうわ~蘭がある・・・感激でした。ジュウニヒトエ(十二単)?コバノタツナミソウ(小葉の立浪草)コナスビ(小茄子)ボケボケですマムシグサ(蝮草)の仲間ナツトウダイ(夏燈台)オオナルコユリ(大鳴子百合)?ボケボケですニガナ(苦菜)フタリシズカ(二人静)ウワバミソウ(蟒蛇草)/別名 ミズもしかしてヒメウワバミソウ(姫蟒蛇草)?ミヤマキケマン(深山黄華鬘)ピンボケコバノタツナミソウ(小葉の立浪草)蕾畑の中にアマリリスマルバウツギ(丸葉空木)ハコネウツギ(箱根空木)?ピンボケニシキウツギ(二色空木)?ミツバウツギ(三つ葉空木)コゴメウツギ(小米空木)ピンボケクサイチゴ(草苺)サルトリイバラ(猿捕茨)ピンボケニワトコ(接骨木)ヤマツツジ(山躑躅)ボケボケ花の形からロウヤガキ(老爺柿)?ミカン(蜜柑)畑の花花が大きいので温州ミカンではなく夏蜜柑系かな・・ ワラビを一握りいただいてきました。一晩あく抜きをしておひたしに
2024/05/15
閲覧総数 338
-
12

東京近郊にも春の女神・ギフチョウ!!
人気blogランキングへ ←押していただけたらうれしいです(@_@) 1年に一度、この時期に飛ぶ蝶・ギフチョウをを春の女神といいます。4月から週休2日になり、連休の初日、ギフチョウを見に行ってきました。東京の近くにもギフチョウが生息する・・・去年この山に登って看板を見て知りました。先週・役場の観光課に電話すると、飛び始めていますが、短い期間だから来週いっぱいでしょうとのこと。連休2日目出掛ける予定が入っているけれど、何が何でもこの日しかない・・・・ 前日は、日記の更新で2時半に寝て、4時半起き2時間の睡眠で出発しました。目的地の駅に降りると同時にバスがでてしまい、次は2時間後・・・・どうしよう・・・平日はだれもいない、タクシーはいくらかかるのかな・・おそるおそる聞いてみると2300円ぐらいという2時間待ちとどっちを取るか、これはタクシーでしょう・・・登山口脇の家のおばさんが、先行の男性と話をしていましたが、男性が歩き出したあと、話をすると、男性はギフチョウのことは知らないで、歩きに来たという。この家の庭には、野草がたくさんあり、今朝見知らぬ人が、掘り返していたという。一声掛けてくれれば譲ってあげるものを・・・だまって取っていこうとする、ひどいことをするものだと怒っていました。昨日、一昨日の天気とは打って変わって、朝から晴れて風もなく暖かいというよりは、歩いていると汗がでるくらいの暖かさでした。これなら「ギフチョウ」がみられるかも・・・はやる気持ちを抑えながら歩く足元には、すみれやシュンランやヒトリシズカが咲いていて、急いでいてもやっぱり写真を撮ってしまうヒメです。なかなか前に進みません。中腹までくると「アゲハチョウ」みたいな蝶が1頭舞いながら近づいてきました、もしかして・・・「わー、ギフチョウ・・・」急いでカメラを構えるけれど速くてとてもとても・・・ こんなに速かったら、写真なんて無理かもしれない・・・まあ、みられただけでも満足だわ・・・花の写真を撮りながら歩いていると、一人の男性が下りてきて、聞いてみると山頂には大勢の人がカメラを構えているという、蝶も何頭かいるけれど、気温が上がってきて、動きが活発になり思うように写真が撮れないよと、あわてたhimekyonhは走り出し、ハアハアゼイゼイ・・・山頂に着きました。います、います。立派な一眼レフカメラを構えた人たちが15.6人・・・ ギフチョウはどこ、どこ、どこ???あせるhimekyonに、親切な男性が少し待てばメスがとまるからと、ギフチョウの習性を教えてくれました。きました、きました。でもなかなかとまってくれませんあ、とまった、と思ったら、オスが近づき、飛んでしまいます。1頭のメスにオスが3頭、4頭と乱舞する。もう、蝶の楽園といった感じ、同じ仲間の蝶を一度にこんなにたくさんみたのははじめてかもしれない。とにかくすごい、すごいと興奮してしまいました。もう10年以上、毎年来ているという男性はすごいです。デジカメの被写界深度を固定して、飛び回る蝶を連写、連写・・・数打ちゃ当たるだよ・・・って笑ってました。 ギフチョウはアゲハチョウ科・日本固有種ギフチョウとヒメギフチョウの2種長野県を境に東西(南北)に棲み分けています。西(南)がギフチョウ、東(北)がヒメギフチョウ・棲み分けラインをルードルフィアラインと呼ばれているギフチョウの食草が「カンアオイ」ヒメギフチョウは「ウスバサイシン」 食草:○○○カンアオイ::地域によって「タマノ」とか「コシノ」の名前が付きますこの地はギフチョウの東限とされています。以前はこの一帯の山にも生息していたそうですが、開発がすすみ、ゴルフ場ができて、次々と消滅し、今はここだけになり、県の天然記念物に指定されています。ギフチョウの写真というと、カタクリに止まっている写真をよく目にしますが、この地はカタクリはないそうです。ギフチョウの幼虫の食草「カンアオイ」類は、絶滅危惧種になっているものが多い、食草がなくなるということはギフチョウも・・・12/6の日記の「アサキマダラ」も見てみてくださいね。 ここをクリックしてね人気blogランキングへ ←押していただけたらうれしいです(@_@)
2006/04/05
閲覧総数 897
-
13

青春18きっぷの旅 木曽路・上松 赤沢自然休養林 レンゲショウマ
旅の4日目 路線バスで赤沢自然休養林へ午後から列車移動のため、2時間弱の滞在森林鉄道に乗り往復してバリアフリーの「ふれあいの道」をバスの時間まで時計を見ながら歩いてみました。レンゲショウマ(蓮華升麻)この時期に、このお花に出会えて感激??葉っぱに切れ込みがない・・ツリガネニンジン(釣鐘人参)ツリガネニンジンハクサンフウロ(白山風露)ヨツバヒヨドリ(四葉鵯)白い花だったのでハナチダケサシ(花乳茸刺)かな?ノリウツギ(糊空木)シロモジ(白文字)の葉っぱ関東にはクロモジ(黒文字)はありますが、シロモジは本州中部から九州に生育します。マルバノキ(丸葉の木)早くも紅葉しています。夏の終わりから紅葉する木なのだそうです。花は紅葉の時期に咲くそうです。森林鉄道を往復、時間が限られているため、車いすの人も歩ける「ふれあいの路」コースを時計を見ながら行けるところまで行き、戻りました。
2019/09/07
閲覧総数 286
-
14

45年ぶりの入院
今日は雲ひとつない青空❗ というのに、今、囚われの身です。 ここは、大学病院の病棟 次男のお産以来45年ぶりの入院です。 といっても、白内障の手術なのですぐに退院予定ですが、、 白内障といえば、日帰り入院が主流の簡単な手術のようですが、こちらの病院は、日帰りだと付き添いが必要でそれができないと入院になります。息子夫婦に頼めば付き添ってくれるとは思いますが、仕事をしているのに右目、左目と2回も頼むのは、、と入院を選びました。1泊2日かと思ったら、前日からの入院で2泊3日です。 そんなわけで明日手術なので、今日、入院しました。 しかし、やることが何もない、退屈です。 それとPCが動かなくて、日曜日に息子の使っていないPCを付け替えてもらいましたが、Windows8、1から10に変わり、使い勝手がわからす悪戦苦闘しています。 画像が大きすぎて縮小しないとブログに貼り付けできませんが、ソフトをダウンロードしていないのと貼り付けた画像をブログ内の前後に移動することができないでいます、しばらくはスマホからの更新になりそうです。が、スマホに保存している画像がありません。しばらくはブログはお休みになるかもです。
2019/11/12
閲覧総数 1099
-
15

早春の佐倉の里山 生き物と春の恵み・ふきのとう
3月9日胃カメラ検査の帰り道バスで移動して里山に寄り道してみました。早春というよりは春といった感じでした。暖かい日差しに生き物たちも出てきました。早くも孵ったニホンアカガエルのおたまじゃくしニホンアカガエル、ヤマアカガエルは早春の寒いときに卵を産み、再び冬眠するという水中昆虫や蛇などの天敵が活動する前におたまじゃくしが成長するように早く産むのだそうニホンアカガエルの卵塊オタマジャクシが孵って崩れてしまってます。水田などの浅い水辺に丸い卵塊を産むニホンアカガエルこの卵塊を探してみたけど全然見当たらないーと思ったらかわいらしいオタマジャクシがたくさん泳いでいました。てんとう虫発見ナナホシテントウムシさんのようバッタさんみっけカマキリ(蟷螂)の卵ベニシジミ(紅蜆)モンシロチョウ(紋白蝶)藪の中をガサゴソ動いていたからシロハラかな?と思ったら、ツグミさんでした。ほかに雉の声、ドラミングの音(コゲラ)かな?春の恵み フキノトウ(蕗の薹)春になると一度は口にしたいフキノトウのてんぷら、今年は新型コロナウィルスの影響でおでかけもままならず、あきらめていましたが、12月まで住んでいた佐倉市の病院への帰りに里山へ寄り道開ききってはいましたが、摘み残しが少しだけあったのでいただいちゃいました。今回は、少しの量だったので、フライパンで少量の油で揚げたら焦げちゃって失敗の巻それでもほろっと苦みのあるフキノトウのてんぷらをいただくことができました。満足~おまけは、プランター菜園の春菊むくどりさんは好きではないようで何度も胡麻和えに、今回はかき揚げにしました。
2020/03/11
閲覧総数 342
-
16

道端に咲く花 ナガミヒナゲシと 園芸種のポピー ハナビシソウ
千葉市に転居してきて4ケ月お出かけへのアクセスがよくなり、今年こそはお出かけするぞ~と意気込んでいたのもつかの間新型コロナウィルスが猛威を振るい、緊急事態宣言がでて外出自粛要請、相次ぐイベント中止で大好きな山の花に逢いに行くこともできません。命あってこそですから、いまはじっと我慢の時道端に咲く花を追いかけています。ナガミヒナゲシ(長実雛罌粟 長実雛芥子)地中海沿岸の原産果実が長いことが名前の由来ナガミヒナゲシの果実※※※※※※園芸種ポピー/ヒナゲシ(雛芥子・雛芥子)/アイスランドポピーヨーロッパ南部原産ポピーの実※※※※※※ハナビシソウ(花菱草)/カリフォルニアポピー北アメリカ原産
2020/05/02
閲覧総数 1363
-
17

日本の野生蘭 ミヤマウズラ
逢えそうで逢えなかったミヤマウズラ2年ぶりかなミヤマウズラ(深山鶉)飛んでいる鳥の羽根のような子豚の鼻のような俺たちひょうきん族~?
2020/09/07
閲覧総数 256
-
18

新幹線車窓からの富士山
富士山大好きhimekyonです昨日のお出かけは、東京駅から熱海駅まで新幹線移動大好きな富士山に出会えました。関西方面への新幹線は進行方向右側の窓側日曜日ながらコロナの影響か、発車10分ほど前の切符購入でも空席ありでした。でも富士山がよく見えるのは、もう少し先の新富士駅から静岡駅あたりまででしょうが昨日は熱海駅で乗り換えだったので残念ですが
2020/10/26
閲覧総数 183
-
19

梅雨の最中の北岳で出会った花 エゾサカネラン キソチドリ ヒメムヨウラン コフタバラン他
梅雨の時期、北岳のみに咲くキタダケソウに出会うために登った北岳ほかにもたくさんの花に出会え、感激の3日間でした。梅雨の最中の北岳 この花に逢いたくて キタダケソウ梅雨の最中の北岳で出会った花 ミヤマハナシノブ タカネグンナイフウロ他エゾサカネラン(蝦夷逆根蘭)根が上に向かって逆さまに生えているように見えるからだそうですがみることはできません。菌従属栄養植物:光合成をしないので葉緑素を持たず、菌と共生して菌から栄養をもらっている蘭の仲間ですエゾサカネランは全体に毛がない母種で、全体に毛があるのが変種のサカネランだそうです。エゾサカネランヒメムヨウラン(姫無葉蘭)菌従属栄養植物で光合成をしないため葉がありません。盛りが過ぎて茎が折れてしまってます。蘭の仲間です。コフタバラン(小二葉蘭)花がピンボケ蘭の仲間です。キソチドリ(木曽千鳥)蘭の仲間です。キソチドリキソチドリハクサンチドリ(白山千鳥)蘭の仲間ですハクサンチドリギンリョウソウ(銀竜草)菌従属栄養植物こちらは蘭ではありませんが、葉緑素を持たない植物です。別名:ユウレイソウキバナノヤマオダマキ(黄花の山苧環)キバナノヤマオダマキ山頂付近には淡い紫色のミヤマオダマキ(深山苧環)の蕾があったのに撮り忘れクリンユキフデ(九輪雪筆)はほぼ咲き終わりクルマバソウ(車葉草)ゴゼンタチバナ(御前橘)タニギキョウ(谷桔梗)サンリンソウ(三輪草)ツマトリソウ(褄取草)マイヅルソウ(舞鶴草)ミヤマカラマツ(深山唐松)ヒロハコンロンソウ(広葉崑崙草)ミヤマバイケイソウ(深山梅ケイ草)ミヤマバイケイソウミヤマバイケイソウヤグルマソウ(矢車草)カニコウモリ(蟹蝙蝠)ハリブキ(針蕗)クロクモソウ(黒雲草)キバナノコマノツメ(黄花の駒の爪)スミレなのにスミレの名前がついていませんヤマガラシ(山芥子)/ミヤマガラシ(深山芥子)ミヤマキンポウゲ(深山金鳳花)シナノキンバイ(信濃金梅)ミヤマキンバイ(深山金梅)ミヤマキンバイ(深山金梅)とチョウノスケソウ(長之助草)ハクサンイチゲ(白山一花)タカネヤハズハハコ(高嶺矢筈母子)のつぼみハハコヨモギ(母子蓬)花芽はまだのようハハコヨモギコイワカガミ(小岩鏡)イワベンケイ(岩弁慶)ブーケのようなイワベンケイイワベンケイとハクサンイチゲミネズオウ(峰蘇芳)のつぼみレンゲイワヤナギ(蓮華岩柳)レンゲイワヤナギキバナシャクナゲ(黄花石楠花)キバナシャクナゲミヤマハナゴケ(深山花苔)?一面真っ白なことろもありました。苔の名がついていますが、地衣類(藻類と菌類の共生体)でサルオガセと同じ仲間ミネザクラ(峰桜)最後の花ウラシロナナカマド(裏白七竈)タカネナナカマド(高嶺七竃)コマガタケスグリ(駒ヶ岳酸塊)コマガタケスグリの花オガラバナ(麻幹花・苧殻花)/別名 ホザキカエデ(穂咲楓)材が柔らかいので麻幹(麻の皮を剥いだ茎)にたとえたことによる穂状に咲く楓はこの1種だけバイカウツギ(梅花空木)バイカウツギツルツゲ(蔓柘植)雨が降ってカメラをしまっていて撮っていない花もありましたがたくさんのお花に出会えました。ライチョウさんには出会えなかったけどイワヒバリに出会えました。イワヒバリ(岩雲雀)
2021/07/10
閲覧総数 1191
-
20

似てるかな? マメヅタラン マメヅタ ムギラン
花の時期ではありませんが・・マメヅタラン(豆蔦蘭)ラン科マメヅタラン属マメヅタランムギラン(麦蘭)ラン科マメヅタラン属ムギランマメヅタ(豆蔦)シダ植物マメヅタマメヅタ
2022/12/13
閲覧総数 1100
-
21

白馬八方で出会った花 ミヤマママコナ ミヤマダイモンジソウ ミヤマアズマギク ミヤマシシウド ミヤマコゴメグサ
2泊3日の花旅たくさんの花に出会えました。ミヤマコゴメグサ(深山小米草)ハマウツボ科ミヤマママコナ(深山飯子菜)ゴマノハグサ科からハマウツボ科に変更花びらにある斑紋が米粒のような形からが由来の深山に咲く半寄生植物ミヤマダイモンジソウ(深山大文字草)ミヤマアズマギク(深山東菊)ミヤマシシウド(深山猪独活)
2023/07/25
閲覧総数 296
-
22

山の会 房総・鋸山
今回は地元千葉県房総・鋸山記録的な寒波襲来の中の山歩きでもやっぱり房総は暖かいのかなあまり寒さを感じずに歩けました。詳細は後日JR内房線の車窓からの富士山下からのみる獄のぞき石切場跡山頂手前の展望台からの富士山
2025/02/08
閲覧総数 107
-
23

ミニ尾瀬 葦毛湿原はマクロの世界・・
シラタマホシクサを見に行った葦毛湿原はマクロの世界でした。かわいいシラタマホシクサに見とれていたhimekyonですが、その根元になにやら小さな黄色いお花が咲いています。なんだろう・・・よく見ると、そうか、これがミミカキグサかもしれない。よくよく見ると紫色の花も咲いている。そういえばミミカキグサは何種類かあると聞いていた。ミミカキグサ(耳掻草)タヌキモ科タヌキモ属花のあとの実が耳掻きに似ているから葦毛湿原では、日本に4種類あるミミカキグサの全部がみられる。バス停で降りたのは、おじさんとおばさんの二人連れとhimekyonだけ、雨が降り出して合羽を着ながら会話を聞いていると、おばさんのほうは東京から2日前にも来たようで、かなりお花に詳しそう。狭い湿原の中を歩いていると、何度も2人連れとすれ違う、思い切って声を掛けてみる。「教えてください」というと「ミミカキグサ」は4種類あって、この湿原には4種類ともあるという。3種類はわかったけど、あと1つはわからないんですよ。と言ったら、その場所まで案内してくれました。でも、見つからなくて・・・そのあと、保護の会の方に出会って、最後の1つのミミカキグサを教えてもらったのでした。その場所はおばさんが教えてくれたところ、まず、肉眼ではみえない、小さな小さなお花でした。ミミカキグサは食虫植物、タヌキモ科には、葉で補虫するムシトリスミレ属と、補虫嚢て補虫するタヌキモ属があり、ミミカキグサは地下茎に補虫嚢をつけて、水中の虫を取るタヌキモ属湧き水が流れ、貧栄養の場所でしか生育しないため、開発され湧き水が枯れれば消えてしまう。ミミカキグサは絶滅危惧種になっている。ヒメミミカキグサ(姫耳掻草)高さ1~2センチ、花の大きさ2~3ミリ虫眼鏡でやっと確認できる大きさでした。ヒメミミカキグサあまりにも小さいので、拡大してみました。ムラサキミミカキグサ(紫耳掻草)3~4ミリの花をつけるミミカキグサ、ホザキノミミカキグサは貧栄養の湧き水の流れに生えるが、ムラサキミミカキグサは、泥の堆積した場所やミズゴケの上を好むというムラサキミミカキグサ木道が膝の高さぐらいにあって、小さなお花を撮るのは大変、雨も降っていて、ザックも降ろせないで、それでも夢中になって撮っていたら3人組のおじさん、おばさんがすれ違い、「何を撮ってるんですか?」「ミミカキグサ」ですよ「えっ?それなんですか?」「よくみてください。黄色いのと紫色の花があるでしょう」「あ、ほんとだ、毎年見に来てるけど、知らなかったわ、」早速、受け売りの花の説明をしてあげたら、びっくりして、喜んで・・・「シラタマホシクサ」これだけがお花ではなかったんですよ。ホザキノミミカキグサ(穂咲の耳掻草)花序が穂状に見えるためホザキノミミカキグサこの種はとってもユニークな顔をしていますちょっとお猿さんに似てませんか??ホザキノミミカキグサ何に見えますか?ホザキノミミカキグサ初めてみるお花ばかりの葦毛湿原に感激のhimekyonでした。他にもお花が咲いていましたが、また別の機会にUPしたいと思います。今日(14日)の夜、鳥取へ出発です。4日間とも雨マーク、お天気に見放されたhimekyonですが、今回は雨でも、中止するわけにいきません。あくまでもメインは講習会ですからね(笑)大山登山、鳥取砂丘は天候次第ということで・・行ってきます。更新、ブログご訪問、お休みさせていただきます。帰ってからまたお邪魔します。よろしくで~す。人気blogランキングへ ←押していただけたらうれしいです
2006/09/14
閲覧総数 111
-
24

春の奥多摩・御岳山奥の院~大岳山へ スミレ色々
2ヶ月も前になってしまいました。季節はずれなんか載せて・・・なんて思うことでしょうでも折角撮ったお花たち、陽の目をみないとかわいそう~4月24日と5月8日、ブログ友hiroさんと、奥多摩・御岳山奥の院から大岳山を歩きました。お花が大好きなhiroさん、怖いもの知らずでhimekyonの心配をよそに、軽装で歩きます。1回2回ならともかく1年続いたわけでして、そろそろステップを踏んでいただかないとと思いまして、さすがに6月の入笠山のあと、このままでは一緒に歩けませんと宣言してしまいました。山野草に嵌っているhiroさん、だんだんエスカレートして、「山」の域に今回の奥の院~大岳山も岩場や鎖場がある山なのです。「イワウチワがみたい、大岳山に登りたい」himekyonのきついことばに耳をかたむけてくれまして・・復活することになりましたが・・・承知の上で誘っているわけで、何かあったら、誘った側にも問題ありですし、その何かがあってからでは遅いですからね、そんなわけで、いまさらですが春の奥多摩・御岳山のお花からヒカゲスミレ(日陰菫)山はすっかり夏の装いになっていますが、4月の下旬はまだまだ菫の季節でもありました初めてみるスミレなんだろう?図鑑をみてもネットで検索してもわかりません検索サイトに問い合わせてみると一人の方は、ゲンジスミレ、もう一人の方はヒカゲスミレではとビジターセンターに画像を送ってみていただきましたこれだけはっきりと筋が入ったのはみたことがありませんが「ヒカゲスミレ」だと思いますとの回答をいただきました。高尾山で発見された「タカオスミレ」は、「ヒカゲスミレ」の変種なのですがちょっと想像がつきませんhimekyonも、ゲンジスミレをみたいと思っていたので一瞬、小躍りしてしまいそうなほど感激のすみれでした。図鑑ではゲンジスミレの特徴は、見つからず、でもヒカゲスミレとは思いもよりませんでしたこれほどきれいな色のスミレは見たことがないので感激です(なんにでもすぐ感激のhimekyonです)エイザンスミレ(叡山菫)菫の同定は難しいのですが、この菫の葉っぱは特徴がありますのでわかりますエイザンスミレエイザンスミレの一番よい時期だったのでかわいい花が次から次と何枚も何枚も撮ってしまいましたエイザンスミレエイザンスミレエイザンスミレエイザンスミレこんな風に同じものばかり載せているので、字数制限などで先に進まないのかもですねエイザンスミレは特徴があって、すぐにわかりましたが、これから載せるスミレは同定できなくて間違っているものもあると思います。ご指導ください、お願いいたしますタチツボスミレ(立坪菫)この花はあちこちでみられました。ごく普通にみられるすみれですね立坪菫タチツボスミレスミレに詳しい方でしたら、同じタチツボスミレでもすぐにここが違うよと同定できると思うのですが、himekyonはみんなタチツボスミレですアカフタチツボスミレ(赤斑立坪菫)?わずかに葉っぱに赤い筋が入っています。もっと濃い筋のもありましたコタチツボスミレ(小立坪菫)?小さな株もありましたコタチツボスミレ?岩の割れ目からも小さなスミレがコタチツボスミレ?マルバスミレ(丸葉菫)マルバスミレヒナスミレ(雛菫)?もしかして咲き残りかな??ヒナスミレ?ナガバノスミレサイシン(長葉の菫細辛)ナガバノスミレサイシンオカスミレ(丘菫)orアカネスミレ(茜菫)オカスミレに見えるけど、葉っぱだけを撮りそこない毛がないようにみえるのでオカスミレかな?同定できないスミレですビジターセンターに問い合わせするのを忘れました
2012/06/29
閲覧総数 306
-
25

久々の高尾山 ツルニンジンとツルギキョウ
10月9日朝起きたら晴れ~体調は戻ってきているし、出遅れだけど、やっぱり高尾でしょう~JR高尾駅に着いたのが11時、この時間だと、いつもなら高尾山口まで行ってケーブルカーのはず何を血迷ったか、バスで日影まで行き、小仏城山~高尾山へなんてとんでもないことを・・・歩きだしてから・日が暮れるのが早くなっているから、やっぱり無理!途中から逆沢作業道?からもみじ台へ登ることにしました。もみじ台下まで登り、歩いてるいていると 通りすがりのおじ様がジイソブが咲いているよと2カ所も教えてくれました。ツルニンジン(蔓人参)/ジイソブ別な場所で今度はおばさまが教えてくれました。同じジイソブだけど、花の中が少し色が濃い花でした。花が終わって実になってきたところ下山途中もしかしてまだツルギキョウの咲き残りがあるのではと探しながら降りました。ツルギキョウ(蔓桔梗)もう少し立つと、暗赤色に色づいてきます。
2019/10/15
閲覧総数 390
-
26

この花に逢いたくて センブリ4種の4 ソナレセンブリ
今年はセンブリ4種のうち、最後の1種は無理かと思っていましたが、今日、4年ぶりに出逢えましたので、センブリ3種を4種に変更しました。センブリ イヌセンブリ ムラサキセンブリソナレセンブリ(磯馴千振)環境省絶滅危惧1A類(CR)CR:ごく近い将来において野生の絶滅の危険性の高いものごく限られた海岸の湿った岩場に咲くソナレセンブリ海岸特有の厚ぼったい葉ハマボッスの葉に似た感じでセンブリという感じには見えませんが4年前、花友さんたちと探しに出かけて、見ることができました。その後、行きたいと思っていましたが一人で行くには、ちょっと危険なところもあるので行きそびれていましたが、思い切って逢いに行ってきました。センブリの仲間には、高山に咲くセンブリ、北海道に咲くセンブリがあります。タカネセンブリ、ハッポウタカネセンブリ、ヒメセンブリエゾタカネセンブリ、チシマセンブリこの種の中で、今の体力で逢いに行けそうなのは、ハッポウタカネセンブリだけ来年は、逢いに行ってみたいなと思います。
2020/10/25
閲覧総数 1093
-
27

日本の野生蘭 エビネ
純粋な野生ではありませんが・・・咲きだしていました。
2023/03/31
閲覧総数 440
-
28

岩手の山友さんと埼玉県の宝登山へ
23年前、岩手山で知り合った山友さんが上京してきたので、行きたいと言っていた埼玉県な宝登山に登ってきました。詳細は後日に
2025/02/16
閲覧総数 44
-
29

初登りは高尾山から小仏城山 おめでたい植物
毎年、出かけていた年末年始、今回は仕事で1月3日の1日だけが休みでした。去年は不本意な山登り、今年こそは復活したいと 思いを新たにとはいいながら、夜はバイトで遠出ができません。・・で、大好きな高尾山になりました。稲荷山コースから山頂を目指し、小仏城山まで足をのばし、帰りに薬王院で初詣 この冬2回目のシモバシラ 登山道には、お正月にふさわしく、めでたい万両と十両が赤い実をつけていました。 マンリョウ(万両) ヤブコウジ(藪柑子)/ジュウリョウ(十両) 高尾山には、マンリョウ(万両)とジュウリョウ(十両)は自生していますが、 センリョウ(千両)とヒャクリョウ(百両)/カラタチバナ(唐橘)、アリドオシ(蟻通し)/イチリョウ(一両)は 高尾では見たことがありません。(あるのかな???) そんなことを思いながら歩いていたら 猿園の入口前で山野草を販売していました。 やっぱりおめでたいお正月だからでしょうか、万両、千両、百両、十両、一両揃い踏みでした。 センリョウ(千両) カラタチバナ(唐橘)/ヒャクリョウ(百両) アリドオシ(蟻通し)/イチリョウ(一両) 赤い実は付いていませんでした。 (1年中、千両、万両が有り通しという縁起物で主に関西で使われるようです) 2012年のブログに縁起物の植物としてUPしていますが、 今も時々ご覧いただいているようでうれしい限りです。
2017/01/05
閲覧総数 329
-
30

日本の野生蘭 セッコク(植栽)三度
もうとっくに終わっていると思っていたセッコクがお出かけした先で咲いていました。正確にいうとこのセッコクは野生種ではありません。 人の手によって木につけられたものが育ったものです。 今は身近に見られるものはほとんどが植栽されたものではないでしょうか。 ケーブルカー駅のセッコク(植栽) 杉の木のセッコク(自生)セッコク(石斛) 淡いピンク色のセッコクは見たことがありますが はっきりとしたピンク色のセッコクは初めて見ました。 ほぼ終わりの一般的なセッコク こちらも樹木につけられたもので自生ではありません。
2017/06/26
閲覧総数 375
-
31

高尾の春 ハナネコノメとコチャルメルソウ
高尾山の春といえば、このお花・ハナネコノメ早春の裏高尾で一番先に見つけるお花はハナネコノメなじみのない名前・・と思う方もいると思います。いつも3月になると高尾山へ行かなくっちゃって思うhimekyonです。もうあの花は咲き出しているかな今年も元気に咲いていてくれるかなもしかして終わっちゃったかな、なくなってはいないだろうか・今年は暖冬というか異常気象・・全体に2週間くらい咲き出すのが早いというもしかして、ハナネコノメはもう終わっているのでは・・不安になりながら、行って見ました満開でした。間に合ってよかったまた今年もかわいいハナネコノメに出会うことができました。かわいいでしょう・・お花はほんの1センチくらいの小さな小さなお花です。咲きはじめは赤い葯がアクセントになっている先客が2人いました、ひとりは地元のおばさん、新聞に出ていたのでみにきたんだってはじめてのお花に感激、近所の人に教えて、また明日、一緒に来るという地元でも知らないのに、千葉に住んでいてどうして知っているんですか?って聞かれたけど・・やっぱりお花が好きだからかな・・このお花は?あれは?聞かれるとうれしくなってついつい教えちゃうhimekyon、おせっかいなhimekyonです・・もう一人は本格的に写真を撮っている男性あとからおばさんに聞いたら、プロのカメラマンで「アライさん」とかもしかして、山渓によく写真を載せているあの「新井和也」さんだったのかな?なんでもたくさん花の写真は撮っているけど、ハナネコノメはまだ撮っていなかったんだってあまりに真剣に撮っていたので声をかけられずにいたけど、失敗したぁー撮り方を教えてもらいたかったなぁーって図々しい??撮った写真は何に載せるんだろう、どんなハナネコノメが撮れているんだろう、見てみたいなぁーヨゴレネコノメハナネコノメとは大違いこちらもネコノメソウなんですよ葉っぱの色がなんとなく薄汚れた感じだから・・・って名前をつけたかた、失礼ですよね、なにもそんな名前をつけなくても・・ってなにかいい名前はないかしら・・この花も真ん中にある花が赤くてかわいいんですよあっ、なんでネコノメソウかって??咲き終わって種子になった形が猫の目のように見えるんですよ、それでネコノメソウネコノメソウ(猫の目草)ユキノシタ科ネコノメソウ属 こちらはコチャルメルソウなんでコチャルメルソウ?種子の形がむかしの夜鳴きそばやの「チャルメラ」に似ているんですよそうそう、○星食品のインスタントラーメンにチャルメラってあるでしょうたしかおじさんがチャルメラ吹いていたと思ったけど・・・PCで拡大してみましたほんとにユニークな形をしていますよね。むかしのウーパールーパーに似ていません??でもほんと自然って不思議ですよね。どうしてこんな形の花があるんだろう種を保存するにかなった形になるとはいうけれど・・この花をみつけると・・あった、あったとひとり、ニヤニヤしてしまうhimekyon川のほとりにうずくまって・・ちょっとあやしいおばさんですコチャルメルソウ(小哨吶草)ユキノシタ科チャルメルソウ属東京都心から約1時間で高尾山の登山口に着く自然が減少している郊外に今も残る自然の宝庫高尾山、今、6月の開通を目指して圏央道のジャンクションの工事が急ピッチで進められている。完成すると、次は高尾山の下を貫通させるトンネル工事がはじまるという道路ができることにより、利便性は出てくると思うできるだけ、生態系を壊す工事はしないでほしいこの地域だけでない、世界規模で生態系を守らなければならないと思いますスミレも咲き出しました。いずれUPできたらと思ってます。人気blogランキングへ ←押していただけたらうれしいです
2007/03/10
閲覧総数 253
-
32

春を告げる雪虫・・セッケイカワゲラ
北八ツのお天気がうそのよう・・・(T_T) 白馬岳 人気blogランキングへ ←押していただけたらうれしいです(@_@) セッケイカワゲラスノーシューで落倉高原・浅間山山頂の雪の上で見つけた小さな虫は「セッケイカワゲラ」春を告げる「雪虫」白馬にこの虫がでると春がくるという。「セッケイカワゲラ」は1840年に鈴木牧之氏の「北越雪譜」という本の「雪中の虫」の中に「雪蛆」として登場するらしい。雪虫の仲間は、トビムシ類、カワゲラ類、ユスリカ類、トビケラ類、ガガンボ類セッケイカワゲラは体長が約10mmで、全体が黒色で翅のないカワゲラである幼虫は渓流に棲むというが、成虫は羽がなく飛べないのにこの930mの山頂にどうやってやってくるのだろうか、不思議な虫である。「雪虫」というと、冬の訪れを告げる白いフワフワした虫と思っていたのですが・・・春を告げる「雪虫」もいたのですね。雪の上にも小さな発見がたくさんありました。 残業続きでスノーシューの続きがなかなか書けません。人気blogランキングへ ←押していただけたらうれしいです(@_@)
2006/03/12
閲覧総数 321
-
33

この花に出会い旅 白いカタクリ
5年ぶりにキスミレに逢いたくて遠征した先で思わぬカタクリの白花に出会うことができました。それも同じ場所に違ったものが3株教えていただかなければわからなかったことに感激!カタクリ(片栗)白花種通常みられるカタクリ 花びらに紫色のWの斑紋があります。花びらに薄い紫色のWの斑紋黄色いWの斑紋があるカタクリWの斑紋のないカタクリ下を向いて咲くカタクリ、花の中を撮るのも難しい花です。斑紋の色まで気がつきませんでした。黄色黄色黄色黄色斑紋なし斑紋なし斑紋無し斑紋なし斑紋なし斑紋なし薄紫の斑紋薄紫の斑紋別の場所ではほとんど白い花が何株もありました。普通のカタクリ
2018/04/01
閲覧総数 200
-
34

幸福の木とベンジャミン 花と実
久しぶりに花の話題が続きます山野草が好きなhimekyonですが、今日のお花は観葉植物2月1日、お花を目当てに出かけものの成田の近く、地元ということもあって布団を干して出かけたために、9時に出かけて3時には帰ってきました休みとなると出かけしているので、美容院もなかなか行くことができません今日は行けそうと電話予約して夕方から行ってきました2ケ月ぶりの美容院カットをしてもらいながら、鏡に映る観葉植物を見ていたらどうも花が咲いているような・・・珍しいでしょう幸福の木に花が咲いたのよ匂いをかいでみて強烈な甘い香りがするでしょう今は1本だけど2本同時に咲いた時には朝、出勤してくると部屋中がむせ返るように臭っていたのよ昼間開いて夜には花が閉じちゃうのよ珍しいのかと思ってネットで検索したら、咲いたっていう書き込みがたくさんあったわよこのたくさん実がなってるのは何?ベンジャミンよえっ、ベンジャミンて実がなるの?花ってどんなだったの?花はみたことないわよ、気がついたら実がついてたものえー、だってこんなにいっぱい実が付いてるよ不思議ね~帰ってからネットで調べたらイチヂクの仲間で花の軸が肥大化したものを花嚢といい、その内側に無数の花をつけるのを隠頭花序というそうですいちぢくと同じで実の中に花が咲くのでみえないわけですそういわれてみると実の形もどことなくイチヂクの膨らんだ先のかたちに似ているかもよく花が咲くと枯れると言われるけど去年も咲いたけど元気なのよって写真がボケボケだったけど、日々草も夏から枯れることなく、次々と花を咲かせているそうなお店は一面ガラス張りで、朝日がタップリ入るからいいのかもね
2013/02/04
閲覧総数 1027
-
35

房総の早春 自生に出会えたコセリバオウレン
再登場のコセリバオウレンですが、こちらは自生ですまさか、4日後に自生にあえるなんて思ってもみなかったのですが・・もう大感激の1日になりました2月1日に見に行った植栽のコセリバオウレンこの地にあるということは、房総にはまだ自生があるはず・・・もしかして、あの場所なら・・・自生にこだわるhimekyonです5日の昨日、電車3本乗り換えてさらにバスに乗り換えること3時間地元といえ、流石に布団を干して出かける距離ではありません・・・コセリバオウレン自生のつぼみですあまりにも小さくて踏み潰しそうになりましたあまりにも小さくて、ピントが合わず、みんなピントが甘いです腕が悪いのを棚に上げています(>_<)ところどころにポツポツと咲き出していましたが聞くところによると以前は群生していたそうだけどかなり少なくなっているとか雌しべのある株は1株のみでしたこの日は驚くべきことが・・去年、高尾で知り合ったト○吉さんにアケボノシュスランの地を案内していただいた時にご一緒されたMさんに偶然にも再会しましたやっぱり、花好きが考えることは同じなのでしょうか(*_*)デカレンズを肩がけして歩いてきた女性から何を撮ってます?鳥撮りですか?あらっ、あの時のーーって大きなマスクをしていて顔がわかりませんト○吉さんといっしょだったMです探し物はもう一つ一緒に探しましたが、まだ蕾もありません地元の方なので、車で近くを案内していただいて別れましたその後himekyonは山の中を散策ここで目的の花をみつけましたまたまた思わせぶりですが・・出勤時間です、また後日に続く
2013/02/06
閲覧総数 179
-
36

青春18切符で九州一周ひとり旅日記15 旅は道づれ 一期一会の出会い
年末年始の長い休暇を利用して、各駅停車で九州へ旅も4日目を迎えました。3日目の夕方、鹿児島の旧友と別れて、JR日豊本線を乗り継いで宮崎県延岡に着きました。今回の旅は、どうやったら九州を一周できるかで悩んで、出発の前日まで一部の宿が決まりませんでした。ネットで予約が完了したものの、果たして各駅停車でたどりつけるのだろうか鹿児島の友達と28日の午後の待ち合わせが確定していたので、それに合わせて人吉の一部だけは特急を利用しました。その後をどうするかで悩んだ結果が延岡泊、宮崎県延岡と大分県佐伯の区間は普通列車は1日3往復のみ、上りは朝6時11分、次は10時間後の16時55分と19時35分だけ、1本乗り遅れたら身動きがとれなくなります。とりあえずは先に進んでおかないと、宮崎の観光もいくつか行ってみたいところはあったけど、過去2回ツアーで行っているので今回はパスしました。(一応JR肥薩線の真幸駅は宮崎県ですからほんの20分ほど観光したことになりますか?)乗り遅れたら大変と、少し早めに宿をでました。旅行者は雰囲気でわかるもので、それとわかる男性がいましたが、なかに地元の子ではなさそうな若い女性がいました。同じ宿ではなかったようだけど、列車に乗り込んでお互いに挨拶をかわして、隣通しに腰掛けることにしました。やはり青春18切符を利用で山口県萩からやってきた女の子昨日は、鹿児島市内見物をして、今日は別府で温泉三昧水族館が好きで別府にも水族館があるので楽しみだそうです。おとなしいお嬢さんと思ったら、結構大胆で、思い立って仕事が終わってから台湾へ行きおいしいものを食べて日帰りで帰ってきたこともあるとか旅の話をしていると話がつきません。九州は、夜明けが遅く7時になってもまだ暗いです 佐伯に着くころにようやく明るくなってきました。佐伯駅 佐伯出身の富永一郎氏の漫画があちこちにありました最近見かけませんが、懐かしい漫画のキャラクターです大胆かつ行動派の女の子Kさん許可なく載せちゃいましたので小さくしましたごめんなさい太陽が昇る寸前です時間がなく、太陽は撮っていません山が赤く染まり、佐伯を後にします約30分ほど待って、大分方面の列車がきました。himekyonは、夕べ急遽決めた臼杵に途中下車します。お互いに名前だけをかわしてお別れです前回の山陰旅行では、萩は行きそびれました、一度訪れたことのある素敵な街、また行ってみたいと思います電話番号を聞きそびれちゃったから、連絡が取れないですね。その時まで、お勤めしていれば訪ねていこうかな?2時間ほどの短い旅の道ずれだったけど、旅の話がつきない楽しいひと時を過ごすことができましたこんな出会い旅、いいですね。無事に帰宅されて、おうちで新年を迎えられたとのこと、コメントをいただきました。これからもたくさん、旅をしてくださいねまた機会があったらお会いしましょうね楽しかったですよ、ありがとう
2014/01/22
閲覧総数 291
-
37

印西の初夏 野ウサギ見つけた
5月23日用事があって出かけたあと、久しぶりに印西を歩いてみました。いつもとは違う場所を歩いてみることにしました道路を歩いていると動くものがえっ、うさぎさん?コンパクトデジカメしか持っていなくて太陽がまぶしくて液晶画面が見えない、写るかなぁ・・・冬の雪原を歩くと一番多くみられるのが、兎の足跡ですが本物を見るのは2度目2年前、木曽御嶽山へ登ったあと、開田高原に1泊夕方ペンションの周りを散歩していた時にみましたその時は、夕方で薄暗い林の中、逃げ足が速くてかろうじて、写真に撮ることができましたが今回は、ほとんど動かなくて、草を食べていました。草を食べているところです目が真ん丸で耳がピンと立って、かわいい~5分も10分も見ていたような気がしてましたが撮影した時間をみたらたった1分間のできごとでしたが感激の時間でした。
2014/06/10
閲覧総数 168
-
38

秩父・奥武蔵を歩く(4)松枝の座禅草
3月のはじめになると「春の訪れ」のニュースになる座禅草 座禅草:サトイモ科で水芭蕉と同じ仲間ですお坊さんが座禅を組んでいるようにみえるから 西武秩父線正丸駅から1時間50分ほど歩いた松枝地区に座禅草自生地があります 沢沿いの少し湿った杉林の中に咲きます臭いをかぐと嫌な匂いがするそうですが・・・(かいだことはありません) こちらの座禅草は青みがかったのが多いです。 梅や桜のような華やかさはないけれど・・ 水芭蕉のような清楚な感じはしないけれど・・ユニークでちょっと気になる座禅草です。。。 人気blogランキングへ
2006/02/12
閲覧総数 347
-
39

佐倉・志津の歴史めぐり 天御中主神社(志津城址) 上志津八幡神社
佐倉市に住んで5年になります。江戸時代11万石の城下町だった佐倉の街歩きはしたことがありましたが、2月中旬に歩いた隣町・臼井歴史めぐり」は、江戸時代よりも古い歴史の町だったことを知りました。歴史めぐりで、臼井氏と志津氏の関連を知り、志津の歴史にも触れてみようと歩いてみました。駅から5分ほどのところに住んでいながら、この町をほとんど歩いたことがなかったのですが駅の反対側に志津の町は広がっていたことがわかりました。天御中主神社((あめのみなかぬしじんじゃ)北極星・北斗七星を神とした妙見信仰で下総地方を治めた千葉氏の氏神さま志津の町は宅地開発が進み、城址の面影は薄れていますが、千葉氏の一族、臼井氏中興の祖・臼井興胤の叔父志津次郎胤氏の居城ではないかと言われています。志津次郎胤氏は、兄の臼井祐胤から若竹丸(後の臼井興胤)の後見を託されたが、若竹丸を殺して臼井城を奪おうとしたが失敗元服して足利尊氏の元で功績を残して、臼井に戻った臼井興胤に従えず滅ぼされたとされています。 鉄骨の覆い屋で囲われている社殿社殿の側面に彫られているものは「高砂」で鶴と亀 翁と媼が彫られています。樹齢600年以上の保存樹林途中に墓地がありましたが、ほとんどが志津家の墓志津氏の子孫なのでしょうね。大きな邸宅もありました。近所の方の話だと駅前のほとんどの土地が志津家所有だったとか他に豊田家、中村家もこの地の旧家のようです。立派な長屋門の家、武家屋敷門ともいい、この家は、佐倉藩の藩士で道場を開いていたそうです。西福寺真言宗豊山派千手院(佐倉市井野)の末寺だそうで明治初期、井野小学校が開校した地でもあるそうです。本堂秩父講中碑出羽三山講中碑 子安講中弘化の年号が刻まれていますので、江戸時代1840年代のもののようです。鷲宮神社八幡神社の前にあった小さな社上志津八幡神社1626年創建の上志津の氏神様 トタンの覆い屋に囲われた社殿藁葺きの社殿壁面の彫刻は、作成時には彩色が施されていたそうです。祭神・応神天皇を抱く神功皇后や天の岩戸に隠れた天照大神の神話などが彫られているとか確認してみたがどれがどれか判別できませんでした。伏見稲荷神社京都神社奉行所から開設の許可を取って建立したものだそうです。参道にはお狐さんが4体のお出迎え旧家の裏の高台にあり、その家が守っているそうです。保存樹林の椎の大木は樹齢300年以上たっているそうです。18代続く旧家だそうです。2月中旬でしたので、古い土蔵の裏庭には紅梅が満開でした。お社が3ケ所見えましたが、どこから入ってよいのかわからず大きな屋敷をひとまわりしてもわからず、個人のお宅のような門扉を開けて入ってみました。どうもこの旧家のお屋敷の中の稲荷神社だったようです。石垣に囲まれた大きな屋敷だったので、ここが志津城址かなと思いましたが違っていました。石垣の上には、サルトリイバラ(猿捕茨)の大株が垂れ下がっています。秋には真っ赤に色づいていたことでしょう藪椿が咲いていました。
2016/03/15
閲覧総数 4012
-
40

この花に逢いたくて カワラノギク(鬼怒川水系)
一昨年、カワラノギクの存在を知り、去年、初めて出会うことができました。関東の三水系と静岡の一部のみに咲くカワラノギク多摩川水系、相模川水系、鬼怒川水系の河原の石がごろごろしたところに生育します。河川開発や改修、上流にダムが建設されて洪水がなくなり、河原には帰化植物などが蔓延り、 生育環境が悪化して年々数を減らして、環境省の絶滅危惧1B類(EN)に指定されています。去年は、多摩川へ2日かけて探しに行き、出会うことができました。今年は相模川水系を探す予定でいましたが、 偶然に鬼怒川水系の場所を知ることができてこちらを先に訪れてみました。夕方近くなっていたのと、時期的には10月のほうがよいようでほぼ終わりかけでした。 カワラノギク(河原野菊) 高原山が近くに見えました。 石がごろごろしているところに生育します。 全体に薄紫色をしていますが、白い花もありました。 カワラニガナ(河原苦菜) 中部地方の河川流域に生育する苦菜 カワラノギクと同じように上流のダム建設や河川開発、改修で生育環境が減少して 環境省の絶滅危惧2類(VU) ※数字はアラビア数字が使用不可のためカワラハハコ(河原母子) 河原の石がごろごろしたところに地下茎を伸ばして群生する ほぼ終盤でドライフラワーのようになっていました。 ベニシジミ(紅小灰蝶)を撮っていて 家に帰ってPCに入れたら、もう1頭シジミチョウが写っていました。 もしかしてシルビアシジミ? この地はシルビアシジミの生息地です。 裏翅をみると大和小灰蝶かも・・・??
2017/11/07
閲覧総数 498
-
41

季節を間違えていませんか?柳の芽吹き ヒサカキの花
返り咲き、狂い咲きという言葉がありますが・・初冬のこの時期に木全体が芽吹いていたり、花が咲いたりするのはなんと言えば・・・ヤナギ(柳)の芽吹き3mほど離れたところに、もう1本ありますが、そちらは芽吹いていませんでした。ヒサカキ(柃)の雄花本来は3月から4月に咲きます。訂正なんたんさんからコメントをいただきました。ハマヒサカキ(浜柃)とのことでした。図鑑を見てみましたら花の時期は11月から12月、葉っぱの形からなるほどでした。海岸に生育するそうですが、千葉県は海のある県、海から離れた当地の生垣でも生育するのですね。他にも間違いがありましたらぜひ教えていただけたらと思います。またわからないものもたくさんありますのでよろしくお願いいたします。なんたんさん、ありがとうございました。別の場所でヒサカキの実本来、この時期は熟した黒い実がたくさんついています。※ 題名から変えてしまうとわからなくなってしまいますので本文中の名前を訂正しました。
2017/12/11
閲覧総数 270
-
42

初登りは高尾山~陣馬山縦走3 縦走1
混雑で山頂付近が入山規制というアクシデント(想定すべきでした)でにっちもさっちも行かず、薬王院で1時間半も足止めをくってしまいましたが、とりあえずは山頂へたどり着きました。すでに陽は高く「紅富士」は撮れませんでしたが、初冨士を拝み、高尾山を後にして陣馬山縦走スタートです。高尾山頂からの初冨士高尾山山頂~の富士山に見送られて一丁平まで歩きました。ここで朝食です。久しぶりにバーナーを持参しましたが1時間遅れのスタートだったので、テルモスでトン汁とおにぎりをお正月は山頂でお節とお雑煮なんて思っていましたが、今回は縦走なのでやめて正解休憩後は期待していたシモバシラしかし、あまりにも気温が高すぎてほとんどありません。朝9時台で融けかけています。というか昨日融けきれなかったのがそのままのじょうたいというのかな氷だからマイナスにならないとダメ本当に気温に左右されますね。小仏城山富士山の左側に雲が湧きだしています。小仏城山から高尾山遠望小仏城山から都心遠望スカイツリーがうっすらと横浜ランドマークタワー今年の初鳥撮りはホオジロ(頬白)拡大したらカシラダカのような頭してる残念!枝被り小仏峠展望台から宝永山付近にも雲が湧いてきました。小仏峠いつもの狸の家族+うさぎさん恒例のhimekyonも影自撮り(UPに堪えられる歳ではありませんので)タチツボスミレ(立ち坪菫)今年の初花撮りノイバラ(野茨)の実ノイバラの実は赤くて小さいのですがこれは暗赤色で実も大きい種類がわかりません。景信山へもう一息全然写真を撮っていませんでした。景信山山頂去年は、花友さんと小仏バス停から景信山~高尾山を歩きました。その時に気がついたのですが、りっぱな山頂標柱になっています。景信山山頂からの富士山左側はすっかり雲に覆われてしまいました。マンリョウ(万両)お正月の縁起物です。さてここからは久しぶりのコースです。高尾山を1時間遅れでスタートしたので、景信山に着いてから時間によっては縦走を断念しなければと考えていましたが、11時鈍足亀足なhimekyonの足でもなんとか明るいうちには下山できそうと出発です。たしか、平成13年の元旦は、高尾山~陣馬山まで縦走していると思います。この時の画像を間違って消去してしまったので、全く残っていません。平成15年の元旦も縦走しようとしましたが、元旦に雪が降り、景信山に着くころは降り積もった雪で縦走を断念しましたので、元旦の縦走は17年ぶりということになります。平成20年1月中旬に積雪の中、山友S夫妻と陣馬山~景信山を歩いていますがいずれにしてもロングコースは久しぶりです。景信山から先は、巻道があって、楽して歩けるようになっています。左が巻道というかこっちのほうがしっかりしています。最初は意識して撮っていなかったので距離がわかりませんでしたがすでに小仏峠から3.1キロ歩いていて陣馬山まで4.2キロ高尾山から6キロ歩いています。(高尾山~陣馬山まで10キロ5時間といわれています)小さなピークがいくつもありますが、ピークごとにほぼ巻道があります。この尾根の北側の北高尾山陵は巻道なしのピークをなぞって歩くため、結構しんどいです。尾根道も広々として歩きやすいです。陣馬山へ3.5キロになりました。♪山、巻き巻き、山、巻き巻き 巻いて蒔いて歩こ♪左が巻道ですコウヤボウキ(高野箒)の果穂伐採された跡どんなだったか覚えていませんが、10数年前は樹林帯だったってことですね、今、高尾山はあちらこちらで伐採作業をしています。正面に見えるのが陣馬山?ぐるっと回るからまだまだってこと?縁起物のジュウリョウ(十両)/ヤブコウジ(藪柑子)初昆虫撮りもしかしてツチハンミョウ(土斑猫)の仲間?としたら、毒があって触ると水ぶくれになるとか底沢峠2回ほど降りて美女谷温泉に入ったことがありました。今はやっているのかな?明王峠もっと近かったような気がしていましたが、意外と時間がかかりました。JR相模湖駅から歩いて登ったことがありました。明王峠からの富士山左側はすっかり雲の中陣馬山まであと1.8キロここまで来ればもう少し頑張ろう~ツルウメモドキ(蔓梅擬)の実登山道に赤い種が沢山落ちていたので見上げると実がなっています。望遠で覗いてみると赤い種はみんな食べられて殻だけが残っていました。奈良子峠左へ降りればJR藤野駅へ右へ降りれば陣馬高原下バス停へ奈良子峠からは藤野駅へ降りたことはありません。バス停へは降りたことがありました。ススキの枯れた茎に大きなカマキリの卵陣馬山山頂へあと100mやっと着きました。続く
2018/01/04
閲覧総数 277
-
43

この花に逢いたくて(18年) ヤマシャクヤクとベニバナヤマシャクヤク
花の命は短くて・・・仕事をしていると「この日」という時に行くことができず、早すぎたり、遅かったり・・残念ながら今年はきれいに開いた花に出会うことができませんでした。でも出会えただけでも感激です。ベニバナヤマシャクヤクは、ヤマシャクヤクの開花から約1ヶ月あとに咲きます。ヤマシャクヤク(山芍薬)環境省絶滅危惧2類(VU)ベニバナヤマシャクヤク(紅花山芍薬)絶滅危惧1B類(EN)このヤマシャクヤクは6年前別の場所で出会った時の画像です。このベニバナヤマシャクヤクは3年前、別の場所で出会ったときの画像です。
2018/05/25
閲覧総数 488
-
44

この花に逢いたくて(18年) リンネソウ
何年も逢いたかった花、久々の出会いです。1週間前に登った「誕生日登山・根子岳」で、のんびりと花の写真を撮りながら歩いていたら、別の登山口から登ってきた2人の女性から「リンネソウが咲いていましたよ」これは見に行かなければ・・・今回パスする予定だった山の方へどんどん下っていきました。教えてもらったのはこんな感じのところだけど、小さな花見つかるかな・・・目を凝らして探してみるとあった~しかし、残念!今回はマクロレンズを持参していませんでした。リンネソウ 別名/メオトバナ(夫婦花)エゾアリドオシ(蝦夷蟻通)植物分類学の基礎を築いた植物学者カール・フォン・リンネが好きな花だったことから学名に自らの名前をつけたとのことです。茎の高さは10センチにも満たなくて花の大きさも10mmほどこんなに小さくても草の花ではなく木の花です。1本の茎に分かれて2つの花をつけることから別名がメオトバナですが普通にリンネソウですね。初めての出会いは18年前に登った白馬岳その後、八ヶ岳でも出会っているはずだけど画像がみつかりません。亜高山帯から高山帯に咲く花を7年前に入笠山で見つけたときは驚きました。入笠山も亜高山ですが、手軽に登れる山なので思いもよらない出会いでした。小さくて下向きに咲くので花の中まで撮ることができません。終わりかけでしたが、7年ぶりの出会いです。気にいっているんだけど、残念、1輪は咲き終わっていました。これはまだまさ蕾がいっぱい
2018/07/18
閲覧総数 283
-
45

地元佐倉で花探し ハゴロモモ
花友さんから、地元にバイカモが咲くんですよとお聞きして湧き水の清流があるのかな?その後、バイカモではなくハゴロモモと判明したとのこと、バイカモに似ているってどんな花だろう見に行ってみました。スイレン(睡蓮)が咲く堀ハゴロモモ(羽衣藻)/別名フサジュンサイ北アメリカ原産の水草金魚や熱帯魚の水槽に入れる水草が野生化したもので繁殖力が旺盛で在来の水生植物が生育できなくなってしまっているために要注意外来植物に指定されています。たしかにバイカモに似ていますね。夏になると細い楕円形の葉を水面にだして葉の脇から花を咲かせます。、花弁は6枚バイカモの花弁は5枚ヒシ(菱)の間から咲いていたので、菱の花が咲きだしたかなと思ったけどヒシの花びらは4枚、花びらが6枚あるので、同じくハゴロモモの花のようヒシの花にも見えるけど・・キツネノマゴ(狐の孫)ヤブミョウガ(藪茗荷)カラスウリ(烏瓜)の花夜咲く花だけど準備しているのかな?それとも咲き終わって萎んだ状態?(ネムノキ(合歓の木)が咲き残っていた。オニグルミ(鬼胡桃)の実ギンナン(銀杏)の実※※※※※※久しぶりのチョウトンボ(蝶蜻蛉)縄張り意識が強くてちょっと止まるとすぐに別のチョウトンボがくるのでなかなかじっと止まってくれない池の上を飛んでいたら木の枝に止まってくれた。大きなトンボといえば、オニヤンマしか知らない・・・花友さん、情報ありがとうございました。
2018/07/27
閲覧総数 830
-
46

高尾の冬 アサギマダラチョウのサナギ
海を渡って2000キロも旅する蝶々高尾には、アサギマダラチョウの幼虫の食草になるキジョランが多く生育しています。先日、キジョランの種をUPしたばかりですが、今日はアサギマダラです。幼虫は何度か見つけたことがありましたが、今回は蛹を見つけることができました。アサギマダラ(浅葱斑)のサナギnet検索すると冬は幼虫で過ごすと載っていますがまちがいなくアサギマダラのサナギです。以前から探していたのに見つからなくてやっとであえました。あのきれいな蝶々がこの中にいると思うと大感激でした。冬を越せるのか心配ですが、蝶になって大空を優雅に飛んで南の国へ渡ってほしいです。以前撮ったアサギマダラの幼虫の食事キジョランは毒ですが、その毒を体に取り入れることで成蝶になって天敵から守ることができるそうです。 アサギマダラのオス雄は後ろ翅に黒い斑紋ヒヨドリバナ系の蜜を吸うことにより生殖機能ができます。アサギマダラのメス
2018/12/25
閲覧総数 740
-
47
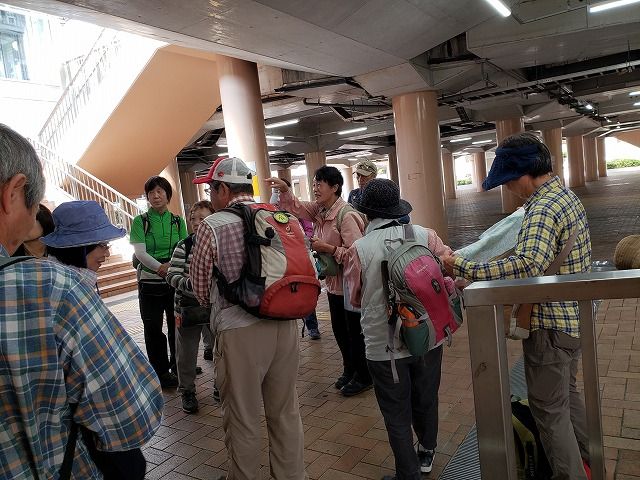
かたばみ会ウォーク「歴史あふれる小山から相原を歩こう」
赤い帽子ウォーク主宰のO氏と同じク○ブツーリズムでの添乗のお仕事をされていたSさん、以前、O氏と山歩きをしていたとき、何度かご一緒したことがありました。その後は年賀状のやり取りだけになっていましたが、O氏のウォーキングの会で再会しました。添乗の仕事を定年で辞めてから、ご自分でウォーキングの会と山の会を立ち上げて活動されているとか、お誘いいただいてウォーキングは公休日と同じなので参加させていただくことになりました。山の会は公休日と合わないので残念ながら参加できません。(スマホの画像です)多摩境駅ー札次神社―小山白山公園ー田端環状積石遺構ー小山田端自然公園ー宝泉寺ー日枝神社ー三つ目山公園・久保ケ谷戸横穴墓ー昼食ー蚕種石ー清水寺ー青木家屋敷―相原駅5月20日京王線多摩境駅からスタートです。平成3年にできた駅で、東京都と神奈川県の境、多摩ニュータウンの境、近くに境川が流れていることから「多摩境駅」の名が付いたそうな札次神社(ふだつぎ)。蚕種石多摩地域は昔は養蚕が盛んだったことから養蚕と子孫繁栄を願って繭の形をした石が祀られている。八十八夜のころになると、石が緑色になるので、その色を見て、蚕を孵化させる準備に入る言い伝えがあるそうな(苔が緑色になるのではとのこと)町田市相原町には「蚕種石」という地域名が残っていそうなヤマザクラ(山桜)とシラカシ(白樫)は町田市銘木100選小山白山公園ー写真なし縄文時代中期から後期の住居跡が67軒発見されたところ日本最大の古墳時代粘土採掘群が発見された場所田畑環状積石遺構縄文時代後期ごろに造られた古代の岸の場(祭祀場)と考えられている。昭和46年東京都の史跡に指定冬至の日、丹沢・蛭が岳の山頂に太陽が沈むそうです。、昔の人はどんな道具でこの石を加工したのか不思議です。何のために?テイカカズラ(定家蔓)
2019/06/06
閲覧総数 123
-
48

青春18きっぷの旅 伊吹山の花 「イブキ」の名前がつく花
8月11日~12日に登った伊吹山で出会った花たち花の名山伊吹山の歴史は古く、織田信長の時代、ポルトガルの宣教師が許可を得て、伊吹山に薬草園を開いたと言われていますが、位置は今も不明とか、ヨーロッパ原産の植物が5種類確認されているそうで薬草園の名残と見られているそうです。京都大学には伊吹山の植物の標本が1700種保存されているそうですが、確認されているのは1300種類だとか、鹿の食害や環境の変化などで減っているそうです。「イブキ」の名の付く花イブキシダ、オオイブキシダ、イブキ、イブキトラノオ、イブキレイジンソウ、イブキトリカブト、イブキハタザオ、イブキシモツケ、ホソバノイブキシモツケ、イブキフウロ、イブキタイゲキ、イブキスミレ、イブキセントウソウ、イブキボウフウ、ハマノイブキボウフウ、イブキゼリ、イブキジャコウソウ、イブキコゴメグサ、イブキクガイソウ、コイブキアザミ、イブキアザミ、イブキタンポポ、イブキカモジグサ、イブキトボシガラ、イブキヌカボ、イブキソモソモ、イブキザサ。その中でも、イブキレイジンソウ、イブキコゴメグサ、コイブキアザミ、イブキタンポポは、伊吹山の特産種だとか。今回、夜間登山者のための仮眠所(売店)に泊まりましたがオーナーさんと思った男性は、伊吹山に魅せられて兵庫県から40年通っている方で先代のオーナーさんの時から、忙しいときは頼まれて手伝いをしているそうです。地元では、県の希少植物の調査をしたり、高校生の生物部顧問などをしているそうでhimekyonが花好きとわかり、たくさんの話をしてくれました。朝も仮眠者の出発を見送った後、大急ぎで東遊歩道、西遊歩道を案内していただきました。イブキジャコウソウ(伊吹麝香草)草ではなく、矮性低木ですコイブキアザミ(小伊吹薊)まだ蕾イブキトラノオ(伊吹虎の尾)イブキトラノオイブキトリカブト(伊吹鳥兜)イブキトラノオイブキトラノオイブキセントウソウ(伊吹仙洞草)花は終わっていました。イブキゼリモドキ(伊吹芹擬)だったかな?イブキフウロ(伊吹風露)掲載済みですが・・イブキボウフウ(伊吹防風)イブキシモツケ(伊吹下野)は撮り忘れました。もしかして イブキガラシ(伊吹芥子)の咲き残り??イブキガラシは、上記の27種に入っていないけど伊吹山の固有種らしいです。イブキタンポポ(伊吹蒲公英)??多分違うと思うけど・・・登山道の真ん中に咲いていたので、(セイヨウタンポポ西洋蒲公英)だとは思うけど花の裏側を見たら、萼片が反り返っていなかったのと、上に見える花の終わったものにも反り返った萼片がみあたらない・・・
2019/08/27
閲覧総数 771
-
49

会津駒ヶ岳で出会った花 ハクサンコザクラ
花の名山会津駒ヶ岳たくさんの花に出会えました。ハクサンコザクラ(白山小桜)白いハクサンコザクラもありました。
2019/09/13
閲覧総数 461
-
50

新幹線車窓からの富士山
昨日は、群馬県水上町最奥の大幽洞窟(おおゆうどうくつ)へスノーシューで氷筍見学へ行ってきました。久々の新幹線乗車、関東平野部はピーカンの天気富士山もバッチリ!と見えました。高崎の手前から見えた浅間山日本百名山・浅間山日本百名山・両神山荒船山クレヨンしんちゃんの作者が亡くなった山(右の垂直の艫岩から転落したらしいです)
2020/02/03
閲覧総数 601










