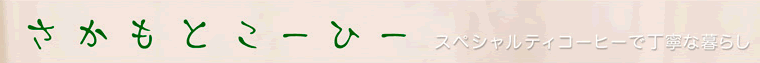カテゴリ: コーヒーの焙煎を考える
さて、「コーヒーの焙煎を考える(26)」は
「味のしくみ」から、
*香りをつくる物質(香りの正体)乾熱調理
「糖類のカラメル化」「脂肪の加熱と香り」ときて、
今回は、
「メラノイジン」です。
先日、近所の常連さんが来られた時、
農学部だったそうで…
この辺の内容は学生時代を思い出すそうです。
もっとも、
ここで書いているような基本的なレベルとは違って、
複雑な化学反応ばかりで、大層難しかったようです。
そんな「アミノカルボニル反応」に進んでいきます。
これは糖類とタンパク質がともに存在するとき、
150℃以上に加熱されるとおこる化学反応です。
これによってできる物質は「メラノイジン」とよばれ、
きつね色でよい香りがします。
このメラノイジンは、たくさんの種類からなる一連の
物質の総称だそうです。
焼いたときにできるメラノイジンは実に種類が多く、
まだ科学的には未知の部分が多いそうです。
それは、材料のタンパク質やアミノ酸の種類はたいへん
多いのと、
ちょっとした温度のかかり方の違いで別の物質が
できるといったことなどが関連しているからと
思われるそうです。
魚の照り焼き、うなぎの蒲焼き、
ステーキ、ケーキ等々の焼く時の香りは
みなメラノイジンの香りだそうです。
小麦粉をただといてフライパンで焼いても、
白っぽくてきれいな色には焼けません。
小麦粉に卵だけ、あるいは砂糖だけ加えて
焙いても、色はあまりきれいではありません。
ところが、小麦粉に砂糖よ卵を混ぜて焼くと
実にきれいな、こんがりとした色に焼き上がり、
よい香りも生まれます。
これは、タンパク質と糖分が加わって加熱され
アミノカルボニル反応がおこり、メラノイジンが
できたからです。
糖類やアミノ酸、あるいはタンパク質も各種の
食品に含まれています。
たいていの食品は焼く事でこのメラノイジンができ、
おいしさにプラスされます。
なお、このアミノカルボニル反応も
200℃以上になると炭化して焦げてしまい、
成分がタンパク質から成るために、
毛糸を焼いたときのような焦げた嫌なにおいが
でてきます。
そんなこんなで、
次回は「よいおこげ」をつくる条件に進みます。
「味のしくみ」から、
*香りをつくる物質(香りの正体)乾熱調理
「糖類のカラメル化」「脂肪の加熱と香り」ときて、
今回は、
「メラノイジン」です。
先日、近所の常連さんが来られた時、
農学部だったそうで…
この辺の内容は学生時代を思い出すそうです。
もっとも、
ここで書いているような基本的なレベルとは違って、
複雑な化学反応ばかりで、大層難しかったようです。
そんな「アミノカルボニル反応」に進んでいきます。
これは糖類とタンパク質がともに存在するとき、
150℃以上に加熱されるとおこる化学反応です。
これによってできる物質は「メラノイジン」とよばれ、
きつね色でよい香りがします。
このメラノイジンは、たくさんの種類からなる一連の
物質の総称だそうです。
焼いたときにできるメラノイジンは実に種類が多く、
まだ科学的には未知の部分が多いそうです。
それは、材料のタンパク質やアミノ酸の種類はたいへん
多いのと、
ちょっとした温度のかかり方の違いで別の物質が
できるといったことなどが関連しているからと
思われるそうです。
魚の照り焼き、うなぎの蒲焼き、
ステーキ、ケーキ等々の焼く時の香りは
みなメラノイジンの香りだそうです。
小麦粉をただといてフライパンで焼いても、
白っぽくてきれいな色には焼けません。
小麦粉に卵だけ、あるいは砂糖だけ加えて
焙いても、色はあまりきれいではありません。
ところが、小麦粉に砂糖よ卵を混ぜて焼くと
実にきれいな、こんがりとした色に焼き上がり、
よい香りも生まれます。
これは、タンパク質と糖分が加わって加熱され
アミノカルボニル反応がおこり、メラノイジンが
できたからです。
糖類やアミノ酸、あるいはタンパク質も各種の
食品に含まれています。
たいていの食品は焼く事でこのメラノイジンができ、
おいしさにプラスされます。
なお、このアミノカルボニル反応も
200℃以上になると炭化して焦げてしまい、
成分がタンパク質から成るために、
毛糸を焼いたときのような焦げた嫌なにおいが
でてきます。
そんなこんなで、
次回は「よいおこげ」をつくる条件に進みます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[コーヒーの焙煎を考える] カテゴリの最新記事
-
プロのつぶやき1105「さかもとこーひーの… 2021.05.02
-
プロのつぶやき1104「スペシャルティコー… 2021.04.25
-
プロのつぶやき1076「さかもとこーひーの… 2020.10.11
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(128)スペシャルティコーヒー
(1414)ニカラグア・エルサルバドル産地巡り
(9)美味しい暮らし
(279)コーヒーのコク研究
(49)コーヒーの焙煎を考える
(61)さかもとこーひー、5つのこだわり
(11)フードペアリングの方程式
(56)僕の好きな紅茶
(34)サンプリング倶楽部21
(23)コーヒービジネスを考える
(77)Comments
© Rakuten Group, Inc.