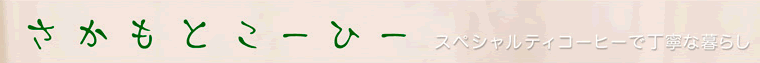プロのつぶやき877「プロ向け焙煎トレーニング」
12月に入って…仕事に食事会と、毎日が猛スピードで駆け抜けていってます。このところ昼間は暖かな日差しですが…流石に朝は冷え込んで…朝は歩いて通ってますので手袋とマフラーするようになりました。
前回の「プロ向けブレンド練習」についていくつも感想頂いたので…あーそういうのも書いた方が良いのかと、引き続き 「プロ向け焙煎トレーニング」を書いてみたいと思います。
毎年何人かから焙煎指導の依頼がありますが…今年は夏前と秋から焙煎指導している店があって…暮れになって開店1年位の店の方から焙煎指導依頼のメールがきました。色々な焙煎セミナーに参加したんだけれども、どうも自分の焙煎機に落とし込めないと悩んでいるそうです。
とりあえず、さかもとこーひーの焙煎やこーひーがその方のイメージと違っていたら意味無いので…さかもとこーひーは飲んだことがあるか聞いて…以前1回あるそうでしたが、とりあえずもう一度気になる豆を飲んでもらいました。それで、気にいって頂き…とくに、ケニア・ガツゥブとグアテマラ・エルインヘルト・パカマラが気にいったそうで…まぁ、同業者らしい印象だと思いました。
さかもとこーひーの焙煎の方法は…焙煎初期に一旦温度が下がりきりますが…それを「ボトムポイントとか中点」とか業界では言いますが…低すぎず高すぎずの温度を見つけます…「表面焼け」と言ってますが…何度以上になると「表面焼け」して辛味が出たり、水分抜けが悪くなったりする原因になり、そうなったら後では取り返せないので、この温度を最初のポイントにしています。
日本のスペシャルティコーヒーの店でかなり多くみかける味わいで…薄い「表面焼け」だと分かりづらいので、厄介です。辛味までいかなくても、熱いうちは香りが印象的であっても、冷えてから滑らかさや甘さ、余韻の心地よさに欠けているコーヒーの多くがこの表面焼けに原因があるように思ってます。
次は水分抜き工程からロースティング工程、最後に煎り止めのロースティングポイントになります。それと排気のバランスも大切です。
それぞれの工程を過不足の無いカロリーを与えるという考え方で…基準の温度と温度を何分何秒で進行するのか、その許される誤差、範囲はどの位なのかを見つけていきます。過不足が無いと何で決めるかというとカッピングで決める訳です。
まぁ、手法は色々あって良いのですが…ようはオーケーだすのはその人の味覚なんだと言うのがポイントです。味わうためのものですから…最終的に味わって決めるわけです。どんなに詳しいデータを揃えても、化学的な理論があっても…人が味わい、美味しいと感じるものですから…何を美味しいと感じるのかがゴールになります。
どのような理論があっても、焙煎機の違いがあっても…何を美味しいとするのか、何を美味しいと感じるのか、そのレベルで美味しさのレベルも決まってしまうのが厄介です。自分の店の味は…結局は最後に自分の味覚で判断するしか無いのです。
美味しさと言っても、好みはあるし、個人差はあるし、個人でもブレがあるし…ほんと、とらえどころが無いのですが、そこから逃げないで時間をかけて味覚を磨くしかありません。それを、美味しさは科学的で無いと逃げると永遠に美味しさにたどり着けないと思ってます。
確かに、不特定多数相手の美味しさと特定少数向けの美味しさには違いがありますので厄介ですが…スペシャルティコーヒーの美味しさは特定少数なカスタマー向けの美味しさが相応しいと思ってますので…自店の常連さん向けの美味しさならたどり着けると思ってます。
そして、その為には、最後はカッピングのレベルがポイントと言う事です…それも、インポーターや生産者のカッピングスキル以外に、ロースターとしてのカッピングスキルが重要だと思います。
インポーターや生産者には最終的なお客さん、カスタマーがいませんので…素材のカッピングは出来ても、その店の商品のカッピングはできません。不特定多数相手のカッピングは出来ても、特定少数のカスタマー向けのカッピングは無理です。スペシャルティコーヒーなのに、消費者と書いてあるととっても違和感を感じます。
自店のお客さんのお好み、しかもある程度多様なお好みをイメージすることもカッピングする上でとても大切なことです。
今年は飲食関係の知人の誘いで…都内の1つ星レストラン2軒に行きました。素材も勿論素晴らしい、調理の技術も素晴らしい…しかし、こちらに訴えかけるような魅力、心震えるような魅力に欠けているように感じました。
先日都内の伝統的フランス菓子店の焼き菓子を頂きました。僕は25年位前に行ったことがあって、その時の印象を憶えているのですが…やはり今回も同じで、感心しませんでした。特に今回は焼きが甘く粉を焼いた魅力が弱く…さらに不快な焦げ味もあり残念でした。
今年は博多のフランス菓子16区のダックワーズやショソンポム、ブルーベリーパイ、マロンパイと食べましたが…ひとつひとつどんな美味しさを伝えたいか明確に伝わってきました。サンク・オ・ピエの料理やデザートもその伝えたいイメージが押し寄せてきます。
勿論、みなさんお好みがありますので…難しいところですが…焙煎もそのようなイメージがあり、素材があり、焙煎があるということです。
北欧オスロやコペンハーゲンの豆を頂きカッピングしましたが…素晴らしいケニアがありました…素材も焙煎も素晴らしいものでした…少し甘さの印象が弱く、その辺がさかもとこーひーのイメージと違いましたが、それもオスロの気候や水で味わうと又違ってくるかもしれません。もうひとつケニアで、焙煎は素晴らしいのですが、酸が少し重く、さかもとこーひーでは使わないレベルの豆もありました。他の何店舗かの豆は…焙煎になっていないレベルで残念でした。
これも、お互いの味覚がマッチしているからなんでしょうね…焙煎の話しなんですが、結局は味覚のレベルアップをしないと焙煎もレベルアップしないという話しになりました。
さかもとこーひーは「部屋中にひろがる香りと後味の美味しさ」を大切にしています。
-
プロのつぶやき1105「さかもとこーひーの… 2021.05.02
-
プロのつぶやき1104「スペシャルティコー… 2021.04.25
-
プロのつぶやき1076「さかもとこーひーの… 2020.10.11
PR
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(128)スペシャルティコーヒー
(1414)ニカラグア・エルサルバドル産地巡り
(9)美味しい暮らし
(279)コーヒーのコク研究
(49)コーヒーの焙煎を考える
(61)さかもとこーひー、5つのこだわり
(11)フードペアリングの方程式
(56)僕の好きな紅茶
(34)サンプリング倶楽部21
(23)コーヒービジネスを考える
(77)Comments