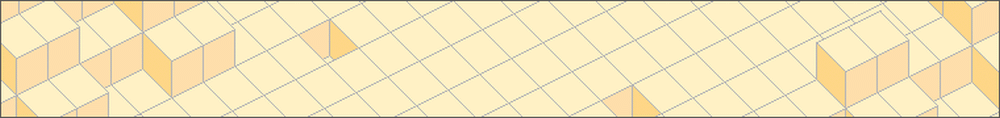前回の続き。
パ・リーグの一番の話題は、48年度から、
- 2シーズン制
を採用したことである。観客数が結成以来、セ・リーグにおよばないパ・リーグが打ち出した新機軸の興業方法であった。
プロ野球で初めての制度ではなかった。戦前に2年続けて施行したことがあった。昭和12年と13年の両年は2シーズン制であった。
(『野球百年』より)
■ちなみに、この1973年(昭和48年)の前期優勝は、監督就任4年目の野村克也率いる南海ホークス。後期優勝は阪急ブレーブス(監督は西本幸雄)。そして、この両チームがプレーオフを戦い、南海がパ・リーグを制した(3勝2敗)。
金田正一
監督である。この金田は、前期(7月11日)の対日拓ホーム・フライヤーズ12回戦に、5万3千人の観客を呼び神宮球場を満員にしたのだ。パ・リーグの試合で5万台の観客が集まったの史上2度目だったという(1度目は尾崎行雄が入団した年の神宮球場、尾崎人気で観客が集まった)。
大和球士さんはいう。
「超満員にさせたのは、2シーズン制にあらずして、
-タレント監督金田
の功績であった。新監督金田は、お客様を大切にした。プロ野球が始まって以来、こんなにスタンドのお客を丁重にもてなした監督はいなかった。選手をひきつれてグラウンドに入るやいなや、スタンドに向かって帽子をぬいで頭をさげた。・・・ロッテはフランチャイズ球場をもたない悲しさ、神宮、後楽園、さらには仙台球場まで足を伸ばしたが、遠い仙台でも、金田の奮励努力のかいあって固定ファンを獲得した。それはロッテファンというより、金田ファンの固定客2万人だった」。
この年、ロッテと太平洋ライオンズの遺恨試合も始まった。とはいっても、太平洋の中村長芳オーナー、稲尾和久監督、そして金田監督が合意して始めた人気拡大のための出来レースだったことが、後になって発覚した。やたらとルールにうるさい現代の視点で見るととんでもないことだけど、当時は「やんちゃが過ぎた」程度のことだったかもしれない。
※ロッテと太平洋の遺恨試合、詳しくは こちら
へ。
■また73年は、パ・リーグの2チームの経営母体が変わった年でもある。
東映フライヤーズは日拓ホームフライヤーズになった、母体は日拓ホーム会社。そして西鉄ライオンズが太平洋クラブライオンズになった。 「西日本鉄道は、例の”黒い霧事件”に厭気がさしてチームを売り」
(大和球士さん)、それを買ったのが太平洋クラブだった。
この年の監督は、日拓が(前期)田村謙次郎、(後期)土橋正幸。太平洋が稲尾和久。
※下の写真は、日拓ホームフライヤーズの7色のユニフォーム。この派手なユニフォームは当時、話題を集めた。いや、決していい意味ではなく・・・。

-
【1890(明治23)年】インブリ―事件が生ん… 2025.02.08
-
【1903年】早慶の初顔合わせの日。 2025.02.06
-
【1901年】東京専門学校(後の早大)に野… 2025.01.29
PR
Keyword Search
Calendar
【東京六大学2025秋】開幕カード。慶應、7点差を追いつき、同点引き分けに。
【東京六大学2025春】東京大学vs.横浜高校の歴史的一戦
【1890(明治23)年】インブリ―事件が生んだ『精神野球』
【1903年】早慶の初顔合わせの日。
【1901年】東京専門学校(後の早大)に野球部が誕生
【東京六大学1931春】八十川ボーク事件
【甲子園1927春】珍事?大阪代表校ゼロは92年ぶり。調べてたどりついた小川正太郎、そして八十川ボーク事件
【東都2024秋入替戦(1部2部)】第1戦は、東洋大がサヨナラ本塁打で先勝!
【甲子園2024夏】大社、31年ぶりのベスト8へ。昭和6年夏は映画『KANO』の題材となった中京商ー嘉義農林の決勝戦があった大会
Comments