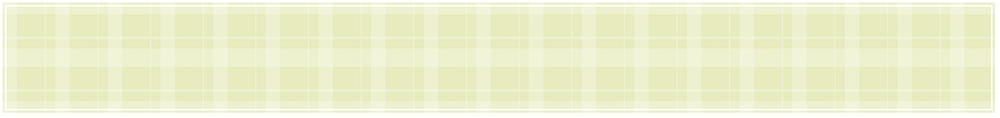2007年02月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-

『女中っ子』 由起しげ子
瀬戸内寂聴と山田詠美の『いま聞きたい いま話したい』に出てきた由起しげ子という人(昭和24年 第1回芥川賞受賞『本の話』)の本を読みたくなって、図書館を検索。何冊か出てきたが、『女中っ子』という大変刺激的な(?)タイトルを発見。しかも児童書の棚にあるらしい(?)ますます刺激的(笑) 『女中っ子』目的の書架を覗いて、一瞬仰天。40年前の我が家の本棚が時を越えて復元された・・・。私を含む4人の子供たちに、父が買い与えてくれた子供向けの本の数々が脳裏に浮かぶ。赤いカバーの、偕成社ジュニア版日本文学名作選。(あー懐かしい)『女中っ子』はその中の一冊だった。二段組、漢字にはふり仮名がついているが、今の本から見れば字体も読みづらい。昔の子供って、こんなのを平気で読んでいたんだねー。というか、こんな本が子供向きとして当たり前だったのか・・・。内容も現代の感覚から見れば、とうてい子供向きではない(!)遠い寒村から、口減らしのために女中として働きに出てきた女の子は、お屋敷の3人の子供のうち、疎んじられている次男を見て、死んだ弟を思い出し、陰に日向にその子をかばい、ただ一人の味方となる。母の病気のため帰省した女中を追って、次男は一人で汽車に乗り迎えにゆく。心配した両親は後を追って、女中の田舎まで迎えに行き、長年の確執が消えて次男は他の2人の子と同様に愛されるようになった。女中は、次男が汚した母のコートを、叱られては可哀相なので隠しておいたが或るとき見つかってしまい、説明しないために暇を出される。最後の別れに、次男に会いに学校へ行くが、出てきた次男は、「女中っ子と言われるから、学校へ来るなよ」・・・悲哀な話だが、当時(昭和30年作)映画化もされて、著者の一番の傑作と言われたらしい。私が子供の頃、女中ということばはまだあったが、「女中さん」と、さん付けで使っていたような気がする。この本の他の短篇も、今では大人向きだ。ジュニア版日本名作文学選の品揃えじたいが、そのまま「新潮文庫の100冊」になっても遜色ないと思える。図書館には他に、(児童向け)江戸川乱歩選集、アルセーヌルパン選集、コナンドイル選集なども揃っていて、ほんとうに懐かしかった。図鑑シリーズも懐かしい。植物図鑑・昆虫図鑑・動物図鑑。子供の頃が甦る。「本ばかり読んでないで勉強しなさい!」しかし、本を読んでいれば国語の成績はそう悪くないはずだ
2007.02.28
コメント(6)
-

『逢わばや見ばや』 (完結篇)出久根達郎
出久根達郎の新刊が出ている。しかも、独立して古書店を開業してからのことが書かれているとあっては、(あ、読みたい!)すぐに図書館へ行って借りてきた。古本屋は天職であると信じていた。昭和48年、高円寺に自分の店を構えた。本から薫る、時代のにおいを伝えたくて古書にずっと携わってきた。戦後日本の姿を眺めながら。―長編自伝小説、ついに完結。 (楽天ブックスより)ぬくもりのある、ほのぼのとしたエッセイだ。開業後知り合ったお客さん、古本を売りに来る廃品回収の人たち、ひとりひとりを愛すべき知人として、心をこめて細やかに描く。少し変った人、小ずるいところのあるような人でも、著者の筆によると、すべて忘れられぬ隣人、自分を成長させてくれた掛替えのない人たちとしてキャラ立ちさせる。読んでいて安らぎがある。むかし、こういう時代があった。誠実に生きることが最上のことという、真心をみんな持っていた。そういう雰囲気をしみじみと偲ばせてくれる。著者の描くものには、この本に限らず、悪人は出てこない。謙虚で温かい人柄なのだろうと思う。読売新聞の身の上相談の回答者もされていて、いつも読んでいるが、一番親身で現実的な答え方をしていると思っている。古本屋さんをされているときに一度行ってみたかった。今は無き、「芳雅堂書店」読むたびにそう思えてならない。
2007.02.24
コメント(2)
-

『無銭優雅』 山田詠美
中年になって初めて本当の恋に巡りあえた。この人と出会う為に随分遠回りもした。だからこそ、本当のオトコイが出来る恋は中央線でしろ!人生の後半に始めたオトコイ(大人の恋!?)に勤しむ、42歳の慈雨と栄。「心中する前の気持ちで、これからは付き合っていかないか……」2人は今、死という代物に、世界で一番身勝手な価値を与えている。いつか死ぬのは知っていた。けれど、死ぬまでは生きているのだ。ささやかな日々の積み重ねが、こすり合わされて灯をともし、その人の生涯を照らす(略) -楽天ブックスよりーひどい風邪をひいて、夜になると熱が出て咳が出て苦しかった。しかしその間も本だけは平常的に読もうとする、哀れな本好きのサガ久しぶりに手にした山田詠美、物語の舞台と私の居住地が同じという単純な興味から。文頭の文章を読めば、なに(っ)山田詠美の描く中年の恋、遠回りの末の本当の恋 しかも中央線(笑)そりゃ~ちょっと読みたいじゃないの~・・・モクモクと繁殖する好奇心、欲張りな本好きのサガ恋する男女に年齢はない。と言っても、私より10才近く若い人の恋愛ものがたりなので微笑ましい(わかるよわかるよ) それでいて、不自然な場面、突っ込みたい箇所は一つもない、完熟した小説だった。著者の恋愛観が描かれていると思って読めば、恋愛道の修羅を経たのちに味わう洒脱さもあり、(著者が)良い恋愛をしてきたんだな。と思わせる。何よりも、著者でなければ書けない文体が光っている。「大学で学んだことは今の私には使えない」「使えないもの持ってるって、贅沢じゃないか」「この恋を人生の後半から始められたのは、とてつもない幸運だと思う。終わりは、死だ、と思い込める」さらに、21の小説の一部分がところどころに挿入されていて、小説に深みを与えていた。有名な小説ばかりなのだが、私が見ないでもわかったのは遠藤周作『わたしが・棄てた・女』 だけだった中年すぎての温い恋愛をゆるく描いているように見せかけて、力作だろう。父親の死が出てくるのも著者の重ねた歳月を偲ばせて感慨があった。次は「風味絶佳」を読みたい。
2007.02.19
コメント(12)
-

たまには新書にも注目!
気になる本が新書版だったので、図書館ではめったに見ない新書の棚を探す。お目当てはあったが、パラパラしていま一つなので止め、その周辺に、何だか面白そうな本が幾つもあった。(あら面白そう~、あら、こんなのいつ出たの?、あっ、これも!)と、薄くて軽いのを良いことに、パッパと手にとり借りる借りる。 『明治人ものがたり』森田誠吾 ・「陸仁天皇の恋」 明治天皇の浮気が新聞に載る(!)皇后ご立腹(!!)ホントのこと。 ・森銑三を描いた「学歴のない学歴」 私の興味のある文筆家 ・森茉莉と幸田文の対比を描く、「マリとあや」『魚河岸ものがたり』の著者が描く明治の人物像。もっと読みたい~。『大江戸曲者伝・太平の巻』 野口武彦『 〃 ・幕末の巻』 〃 歴史上の大事件から、無名の庶民が引き起こす市井の出来事まで、 面白おかしく書き連ねる人物誌。 《歴史の素顔はゴシップに宿る》 カバー裏書 途中まで読んでいるが、なかなか面白いし、一篇が短いので楽。『昭和の墓碑銘』 週間新潮編集部編 時代を担った物故者の生涯を振り返る。正史では窺えぬ「生きた昭和史」以上が新書版。字が大きくて読みやすくなっている。『無銭優雅』 山田詠美 新刊。先日書店で見てリクエストしておいた。 この著者の本は久しぶり、読まぬうちから期待(しようかしまいか)『いま聞きたい いま話したい』 瀬戸内寂聴・聞き手山田詠美 文庫で買おうと思ったが、内容は同じらしいので買わずにすまそー(笑)『不適応症候群』 江波戸哲夫 ストレスに悩むビジネスマンのクリニック。彼らに向き合う医師と院長。 (シリアスな伊良部先生?) 企業社会に生きる人びとの癒しを描く連作短編集。小説現代も借りてあるんだっけ~、ガンバレ本の虫
2007.02.14
コメント(4)
-

『秋の森の奇跡』 林真理子
図書館の順番がようやく廻ってきた、『秋の森の奇跡』 林真理子。著者お得意の、愛に悩むセレブな女性を描いて、そこそこ面白かった。それプラス介護問題というので、話題作らしかったが、やっぱり主題は恋愛。家具店の店長で働く四十路の人妻、娘は私立の小学生、夫は一流私立の教師でハンサム。束縛されるわけでなく、妻の仕事にはとても理解を示す。娘にも問題は無い。でも何故か、友人の紹介で知り合った、タイプでもない男性に引っ張られて浮気してしまう。そうして結局は遊ばれたことを知り傷つく・・・あるパーティーの会話では、夫に浮気されていると思い、また傷つくが問い質さない。同時期に、母が呆け始めていることを知り、施設に入れることを拒んで兄と口論になり、夫と別居して母と生活するが、母が呆けていることをより認識する。心細さに、仕事で知り合った男性をたより、やがてそれは恋になる嘘を付いて出かけデート中に、母が徘徊して肺炎を起こす。病院で目覚めた母は、娘を見て「あなたは、どなたですか?」そして母は施設へ・・・。一気に読んでしまったが、何となく(お手軽だねー)だって主人公は美人でモテるんだよ。それにキャリァウーマンでもあるし、家庭も恵まれている。そんな女は、少しくらい誘われたってやすやすと落ちないはずだよ?まして好きなタイプでもないのにさ。遊びで割り切って浮気するということなら、モテる女でもするだろう。この立場の女性がこんなに純情とは思えない私。もっとプライドあるんじゃないの?このなかで「母に精神的にしがみつく気持ち」というのは、かなり理解できる。今の私の心境にも遠からず、著者にもそんな気持ちがあるのだろう。(・・・『本を読む女』のモデルは著者の母との記憶がある。好きな小説)後から出てきた男はまじめでよかった。かなり男らしい男だ。だから(?)幾ら好きあってもHしないで終わって欲しかったわ(残念)その方が余韻が広がるしぃ(笑)同性同年代として、30年以上テンションを落とさず書き続けることには感心するし、根強い読者が多いことも頷ける。新刊発売と同時に、図書館のリクエストは数十人待ちにもなるのだ。次は50代以上の読者を想定して書いた小説を読ませて欲しいなー(等身大ってやつ)
2007.02.11
コメント(6)
-

『一所懸命』・『きつねのはなし』
『きつねのはなし』森見登美彦(えっ、こんなのも書けるの?) 「太陽の塔」「夜は短し歩けよ乙女」とは趣の違う、オカルトっぽい短編集。(へぇ~)と感心しながら読んでいくけれど、何となく妖しげなまま終わるものばかり。(もう少し書けば面白くなるのに!)と思わせたものもあるが、それで終わるのが良さなのか・・・?著者の作風の幅を感じさせる一冊ではあるが、やっぱり個性豊かな大学生が登場する《青春ユーモアファンタジー》のほうが好きあとは「四畳半神話大系」も読んでみなくては。 『一所懸命』岩井三四二「難儀でござる」に続く、時代小説短編集。どの話も、下級武士の生活を現代の庶民的視線で捉えていて、(うふふ、なるほどね)それなりに面白味はあるが、「難儀でござる」には及ばなかった。・・・今月になって、まだ3冊しか読んでいない。読むペースがすごく落ちていて、自分でもイラつく気がするが原因は目の悪さ(老眼)なのだ。あ~ん哀しい
2007.02.07
コメント(2)
-

最近買った本・図書館の本
☆最近買った本 『さよならを言うまえに』太宰治 『作家たちが読んだ芥川龍之介』別冊宝島太宰にそんな題名の小説あったかな と思うでしょ。《人生のことば292章》という、太宰文学の抜粋・編成本です。一瞬の懐かしさに買っちゃいました。パラパラ捲って、いいなと思った文章―「生活とは何ですか」「わびしさを堪える事です」 (かすかな声)より今年に入ってから買った本は、まだ一冊も読んでないけど書店へ行けば、買わないで帰りたくない。☆図書館の本 『きつねのはなし』森見登美彦 『世間の辻』澤田ふじ子こちらは確実に読む本(返却期限があるからね)他に小説新潮1月号。群像2006年10月号(創刊60周年記念号)も~本に飢えることの無い幸福・・・
2007.02.03
コメント(4)
-

『10歳の放浪記』 上条さなえ
若いとき読んだ、林芙美子の『放浪記』に、強烈な印象を受けてから30年余り以後の読書傾向に大きな影響を与えた1冊でもあった。今もって『放浪』という言葉には、青春の日のあこがれが甦る。いま思えば笑えるが、当時気に入った言葉では他に「吟遊詩人」「刹那」「堕天使」などがあった。・・・どんな人間になりたかったのやら(ファイナルファンタジーの世界のひと?)そんな気持ちで手にした、『10歳の放浪記』 上条さなえ昭和35年、父とふたり、池袋のドヤ街でその日暮らしをしていた著者を支えてくれたのは、街で出会った人たちだった。パチンコ屋のお兄さん、やくざのお兄さん、床屋のお姉さん…ふつうの人々がやさしかった時代を生きた、10歳の女の子の記録。 【目次】椎名町/大塚/狭山貯水池/鮫洲/滝野川/高尾山/九十九里村根津八重垣町/池袋/秋津/房総へ (楽天ブックスより)昭和30年代後半になってもまだ、貧しさのために母や姉と離れ、父とホームレス生活をして、1年間通学できなかった女の子がいたことに胸を突かれる。貧乏のために親戚を転々とし、施設にも入り、それでもくじけず、夢を忘れず勉強して、教員、童話作家、児童館館長を経て、埼玉県の教育委員長になった経歴。父母亡き現在、一番苦しかったあの時代を書くことで救われたい、楽になりたい。あの時代があったから精神的に強くなった。子供たちに愛を勇気を伝えたい~。著者は現在56歳だが、当時の子供の目線、心境を実に緻密に描きだしていて感動した。もう一つの《三丁目の夕日》がここにある。
2007.02.01
コメント(2)
全8件 (8件中 1-8件目)
1