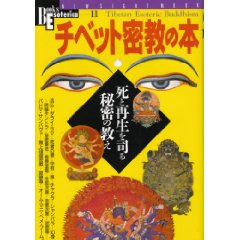
「チベット密教の本」
<2>
死と再生を司る秘密の教え
学習研究社 1994/12 ムックその他 227p
初読時 には、キーワード「アガルタ」を追いかけるだけで、特段にこの本全体に興味があるわけではなかった。レーリッヒやブラバッキーなどの西洋神秘主義的関心ごとの後追いをしていただけだった。ところが、 「裸形のチベット」 においても、 「増補 チベット密教」 においても、「挿図が豊富で入門書としては適している」との紹介があり、再読してみることに。
「ゲルク派版 チベット死者の書」 をめくった時に、同じ出版社であるし、デザインの色調が似ているなぁ、と思って、この本を思い出していたのだが、実際に読んでみると、「生起次第」や「究竟次第」の修行過程のダイジェストがあり、よりくわしくは「ゲルク派版」をよむようにとの指示があったりする。私のセンスとしては、瞑想をこのようなこまかいプロセスと見ることは好みではないのだが、こと「密教」という限りにおいて、ことはかなりの込み入った話になっているようだ。
この本の出版が1994/12。実際にこの本が話題になってしかりべき頃にあの忌まわしい 事件 がおきたのであったのだから、この本にとってはやや不幸であったというべきだろう。私もこの本をどういう経緯で購入したのか、すっかり忘れているが、実際に「密教」の世界に入る、というよりは、いかにして「密教」の世界に「入らないか」という理由づけにすら使われてしまったのではなかっただろうか。
しかし、2008年の現在、たしかに挿図もかなり豊富で、私のような「密教」門外漢の「入門書」としては最適のようだ。出版から14年が経過しているが、古くない。むしろ、時間が経過していい味だしている、と言ってもいいかもしれない。時代(というか私自身)がようやくこの本を読める段階になったというべきか。
この本には、西洋神秘主義の案内ばかりではなく、巻末に「チベット密教ブックガイド」がついている。すでに当ブログでも読みすすめてきた本がだいぶあるが、この時代から現在まで、それほど読むべき重要書というものが変化しているわけではないようだ。「曼荼羅やチベット密教美術などを知りたい方に」という項目が目新しいが、今の私は、まだ「曼荼羅やチベット密教美術」を知りたいという要求が大きくはない。しかし、全体像を知るうえにおいて、このブックガイドを利用して、ひととおり目を通しておくのも悪くはない。
非常に多くの姿で表される観自在のうちで、チベット、ネパールで最もポピュラーなのが六字世自在(観自在)だ。「六字」とはチベットや中国でも非常に有名な真言、「オーム・マニ・パドメ(ペメ)・フーム」(オーム、宝珠と蓮華よ、幸いなれ)の6つの音節を指す。
p203「観自在」
オーム・
マ
ニ
・
パド
メ
(ペメ)
・フーム
-
仏教が好き! 2008.10.23
-
男一代菩薩道 インド仏教の頂点に立つ日… 2008.10.23 コメント(4)
-
21世紀のブディストマガジン「ジッポウ」 2008.10.22
PR
Freepage List
Category
目次
(6)22番目のカテゴリー
(49)バック・ヤード
(108)osho@spiritual.earth
(108)mandala-integral
(108)agarta-david
(108)スピノザ
(108)環境心理学
(108)アンソロポロジー
(108)スピリット・オブ・エクスタシー
(108)マーケットプレイス
(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2
(108)チェロキー
(108)シンギュラリタリアン
(108)レムリア
(108)2nd ライフ
(108)ブッダ達の心理学1.0
(108)マルチチュード
(108)シンギュラリティ
(108)アガルタ
(108)ネットワーク社会と未来
(108)地球人スピリット
(108)ブログ・ジャーナリズム
(108)Comments




