<1>より続く

「密教的生活のすすめ」
<2>
正木晃 2007/11 幻冬舎 新書 198p
著者作品 一覧を見ると 、 「空海をめぐる人物日本密教史」 2008/10、 「宗像大社・古代祭祀の原風景」 2008/08、 「『なぞり書き』心に響く禅のことば108」 2007/06、などが近著としてあり、なぁ~んだ、チベット密教専門家ではないのだ、とちょっと残念な気分にならないのでもない。もちろん、日本密教にも、神道にも、禅にも、関心がないわけではない。時間があれば、正木おっかけを開始しないでもないが、当ブログは、すでに大団円に向って走り始めている。ここはグッと押さえて、そろそろ正木ワールド卒業に向って歩きださなければならない。
玄侑宗久の 「禅的生活」 と対をなすかのような「密教的生活」という言葉だが、この言葉はちょっと珍しいのではないだろうか。ひょっとするとこの本において初めて出てきた造語なのかもしれない。「密教」という概念と、「生活」という概念、ほぼ対極にあるような言葉でありながら、その二律背反的な言葉が一つになるところに、新しい概念を生み出す妙というものがあるのだろう。
禅であっても、ZENであっても、たとえば平田精耕 「禅語辞典」 のようにすでに現代人には読むことすらできない漢字熟語ワールドにひきこもって悟りすましてしまったり、 「OSHO ZEN TAROT」 のように、まるで墨絵の世界から総天然色世界に飛び出してしまったら、これらもまた「生活」という概念から遠く離れてしまっているようでもあり、いやいや「生活」にあらたな意味を吹き込む、新しい意欲的な試みだ、と思い直さないでもない。
ええい、それではどっちなのだ。「密教的生活」は是か非か? どっちなのだ。あえて言おう。「密教的生活」などありえない。「密教生活」はあるかもしれないが、「密教『的』生活」はあり得ないのではないか。「禅生活」はあっても「禅『的』生活」はなさそう、という直感とほぼ同じ意味あいで、そう思う。少なくとも、当ブログの主テーマにはならないだろう。
密教とは、正木「的」に言えば、プロフェッショナルな世界だ。プロにしか許されない世界なのだ。ところが、この本は、読者はアマチュアであるということを前提として書かれている。であるがゆえに、「密教『的』世界」ということになってしまう。サッカー少年がJ1リーグの選手になることを夢見ているような、自らをどこか一歩ひいて考えているような、劣等感を感じる。
ところが、密教の主目的は即身成仏、この身で仏になることを目指すものだ。その点において、密教を学び始めるということはすべてプロフェッショナルになることが目的なのであり、アマチュアで終わってしまったら、それは「密教的」に考えれば、それは失敗であった、という結論になってしまうのではないか。
問題を本質にもどそう。つまり、当ブログは「密教」という言葉を重視していない。「密教」という言葉は、職業的宗教家たちによって、自らの商売を業界化するために編み出された言葉だ。一般人が「密教」という言葉を多用することは、論理矛盾に陥るのではないか。
サッカーファンがJ1の試合を「観戦」することは、まぁ、ありえることだろう。しかし、「密教」ファンが、「密教」プロを崇拝する、ということは、あっていいのだろうか。メタボで悩む中年が、驚異的なダイエットに成功したモデルにうっとりしていても、どうしようもない。自らがダイエットしなければ、「ダイエット」という概念自体無意味だ。
つまり、「人間」にはアマチュアもプロフェッショナルもないのではないか。いや、人生を積極的に生きようとするなら、人間は、自らの方法によって、全員あらゆる人がプロフェショナルな「人間」にならなければならないのだ。アマチュアであることはゆるされない。
「生活」という言葉は、どこか「アマチュア」を連想させる。プロフェッショナルという言葉は、「生活」という世界から遠く離れていった「夢」の世界のようなイメージがある。しかし・・・・。密教とは、夢と生活を一つにしてしまうことだ。密教的生活という造語は、意欲的な意図から生まれて言葉であろうが、そこにある矛盾がどこまでも、ひびを入れてくる。
密教的生活ではなくて、タントラライフのほうがすっきりする。密教という言葉は、いまや日本のローカルな言葉に堕してしまっているのでないか。そして、旧態依然とした守旧派がまた千年の惰眠に戻ってしまうことを許してしまっているのではないか。
この本を読みながら、そんなことを考えていた。
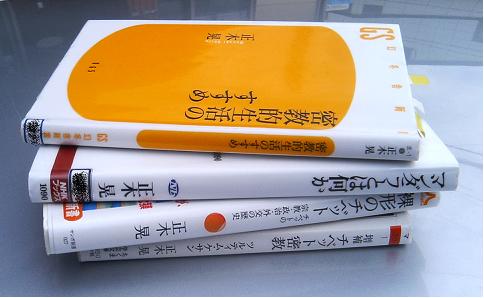
-
トランスパーソナル心理療法入門 <2> … 2009.01.14
-
エスリンとアメリカの覚醒<6> ラジニー… 2009.01.13 コメント(2)
-
「維摩経」 長尾雅人訳 <1> 2009.01.12
PR
Freepage List
Category
目次
(6)22番目のカテゴリー
(49)バック・ヤード
(108)osho@spiritual.earth
(108)mandala-integral
(108)agarta-david
(108)スピノザ
(108)環境心理学
(108)アンソロポロジー
(108)スピリット・オブ・エクスタシー
(108)マーケットプレイス
(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2
(108)チェロキー
(108)シンギュラリタリアン
(108)レムリア
(108)2nd ライフ
(108)ブッダ達の心理学1.0
(108)マルチチュード
(108)シンギュラリティ
(108)アガルタ
(108)ネットワーク社会と未来
(108)地球人スピリット
(108)ブログ・ジャーナリズム
(108)Comments




