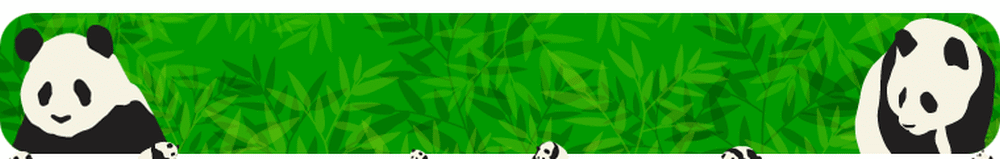PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: いたづらにむつかしい刑法
 以前の日記
以前の日記
ここで(たぶん)と留保して書いたのは、
まず、「とあるブログ」とされてどのブログのことか特定されておらず、リンクも張られていないという形式的な理由からです。
また、そのブログの批判の骨子は、『リーガルクエスト刑法各論』は「法科大学院生向けの教科書・基本書」であるにもかかわらず、「とあるブログ」が、単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証がなされておらず不十分などと批判しているのは妥当でない、というものなんですが、
私の日記では、論証が「不十分」なんて書いたことはなく、論証が「なされていない」と書きました。ましてや、単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証が必要だなどといったこともありません。「論証が0だ」と言ったのであって、「論証が1しかないが10書くべきである」なんて言っていないということです。
また私は、その記述には論証がないと言っただけで、そのブログに書かれているように、その記述が「執筆者の意見・立論であると捉えたうえで」その執筆者を批判する、なんてことはしていません(「樋口範雄先生」に対する身も蓋もない 物言い と対比してみてください)。
このように、内容的にみても、私のブログに書いてあることと全然対応していないので、私のブログと似たような別のブログがあって、そっちに対する批判なのかもしれないなあと思ったというのが実質的な理由です。
ただ、「下位基準云々」てところにも触れられているので、さすがにまあ私のブログのことなんだろうなと思うわけです。
○
いくら法科大学院生向けの教科書だからといって、論証が無くてもいいってことにはならないでしょう。判例の結論をそのままなぞるだけの本であれば話は別ですが。
単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証は不要だと批判しながら、じゃあ教科書レベルの論証として何が書いてあるの、ってことには触れられていません。やはり、教科書レベルの論証さえ不要だというつもりでしょうか。
単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証が現に存在するのであれば、教科書では教科書レベルの論証にとどまっていてもいいんですが、私の少ない読書量の範囲では、単著・モノグラフィーで「直接性・不法性」が必要な理由を詳細・厳密に述べたものを見かけたことがありません。あるとしても、せいぜい事例からの「帰納的」な理由付けだけじゃないですか(この辺は私の勉強不足に起因する問題です)。
「不法性」に関して、条文上は「財産上不法『の』利益を得」とされていて「財産上不法『に』利益を得」とはなっていません。
文言解釈からすれば、あくまで財産自体に不法性が備わっていることを要求しているのであって、財産の取得の仕方が不法かどうかは問題としていない、ということになるのでしょう。
なので、不法性が必要なのは「条文に書いてあるから」というのは、正しい解釈論ではないでしょう。文言解釈+αではじめて財産の取得の仕方に不法性が要求されるという結論がでてくるわけです。
教科書レベルでは、文言解釈で押し切ってしまえばいいってことになるんでしょうか。
また、「直接性」に関しては、総論における「因果関係論」と関係があるのか別建ての概念なのかもはっきりしませんが、これも法科大学院生レベルの教科書では、総論と各論を関連づけて書く必要はないってことでしょうか。
○
ここからは、なぜ、彼/彼女が、私がブログに書いた<論証がない>を、<記述箇所を執筆者の意見・立論と捉えた上で、これに対し単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証がなされておらず不十分と批判している>などと、曲解してしまったのかを考えてみます(私としては、上に書いた反論のための反論みたいなものより、こういうことを考える方が好みです)。
<教科書であっても、単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証が必要である>
<執筆者の主張でない記述に対しても、当人が書いた以上執筆者の主張だと捉えて批判してよい>
なんて主張は、誰がどう考えてもおかしいですよね。
私がそのような主張をしていないにもかかわらず、なぜ、そのように主張していると曲解した上で批判してしまっているのか、その理由を考えてみたいのですが、
この方の他のエントリーを見る限り、とても私では書けないようなしっかりした論述がなされていますので、決して読解力がないとかそういうわけではなさそうです。
他のエントリーの雰囲気からも感じられることですが、小林憲太郎先生のことが大変大好きなんでしょう。そうしたところ、大好きな小林先生の著作にケチをつけてる奴がいると。
ここから先が二通りに分かれると思うのですが、
1 こいつをどうにか批判してやりたい。「論証がない」に対しては「論証がある」と反論するしかないけども、論証がないのは事実だ。このままでは批判できなくなってしまう。そこで、誰もが明らかに間違いだと分かるような見解に仕立て上げてしまおう、そうすればいくらでも批判できるぞ。直リンを貼らなければ、自分のブログを読んでいる人には実際の主張を見られないで済むし。
2 1の思考過程を、意図せず無意識におこなってしまった。
なぜ2のような可能性がありうるかというと、彼/彼女が小林先生のことを大好きだからです。大好きな先生にケチをつけている奴を見ると、正しく言葉を読み込まないまま反射的に批判してしまうと。
私は、別に彼/彼女のことを批判しているのではなくって(他のエントリーを見れば、私よりも断然賢い方であることが分かります)、なぜ曲解しているのかが不思議で、その理由を考えてみたかっただけです。
○
もう一つ触れたい記述があって、それは、突然「ポストモダン」なんて単語がでてくるところです。
<その人に対する批判はその人の見解に対してすべきである>
<教科書には単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証は不要である>
<文脈にあった批判をすべきである>
なんて、極めて普通の主張の、どのへんがポストモダンなの?と思わず突っ込みを入れたくなっちゃいます。が、私がいいたいのはそういう普通の突っ込みではありません(ポストモダンの定義とか、私にはどうでもいいことですし)。
この記述がおもしろいと私が感じるところは、記述の大部分が小林先生を擁護するための論述に費やされているにもかかわらず、「このような私の考えは、ポストモダン的すぎるだろうか」なんて、突然自分のことに触れ出すという点です。
このポストモダンに関するくだりは、ごっそり無くなっても何の問題もないですよね。なのに、なぜこんな記述がでてきたのかってことを考えてみたくなるんですが、これには二通りの可能性があるんじゃないかと。
1 一つは、「小林先生を守ってあげる」だけではあまりにも自分というものを見失っていると感じたので、自尊心を回復するために「私の考えはポストモダンだ」と言ってみたと。
この場合、自尊心が回復できればいいわけだから、そこに入る言葉は「ポストモダン」じゃなくってもいいことになります(取替え自由であるせいで、逆に、いまいちかみ合ってない「ポストモダン」を持ってきてしまった?)。ただ、彼/彼女にとっては、自分の考えがポストモダンだということが、一番自尊心を回復させやすい言葉だったんでしょう。
2 もう一つは、彼/彼女が、小林先生のことをポストモダニストだと捉えていて、単に先生を遠くから援護するだけでなく、「私も先生と同じポストモダニストなんですよ」と近づいていってみたと。
2と考えたほうが、全体の姿勢が一貫していて美しいと感じますがどうでしょう。
○
ちなみに、 別のエントリー で書いたので読まれていらっしゃらないのかもしれませんが、相続事例で財産の取得に「不法性がない」というあてはめをしているのは間違っている、と指摘したことに対しては、この方は何の反論もしていません。さすがにこれに対してはフォローできなかったんでしょうか。
彼/彼女の言い方からすれば、これも単に誰かの学説の「あてはめ」をただ引用しているだけだということになりますかね。でもさすがに、間違ったことを「ただ」引用しちゃまずいでしょ。
これもまあ、「相続欠格であることがばれずに相続したこと」は刑法上は「不法な」利益移転と評価されない(という見解がある)、だけどそんな細かいことは教科書に書かなくてもよく、不法でないという結論だけ書いておけばいい、なんて「教科書だから」の抗弁を畳み掛けられちゃったら、私はもう何も言えません。
○
以上書いたことは、大部分が私の創作にかかる「物語」に基づいた記述ですので、まあ、的はずれなんでしょう。
ただ、あくまでも「書かれていること」から、その背後にある「書かれていないこと」を推測しているのであって、「書かれていること」に反することを「書かれていること」だと主張する、という誤りは犯していないつもりです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年08月08日 22時43分06秒 コメントを書く
[いたづらにむつかしい刑法] カテゴリの最新記事
-
精神分析する自分を精神分析する-自己言… 2007年08月10日
-
これは総論ではないのか。 2007年05月18日
-
それは理由ではない-法律書とフィクション 2007年05月13日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.