第六話 牙城クスコ(8)

【 第六話 牙城クスコ(8) 】
トゥパク・アマルは固唾を呑み、鋭くフィゲロアを観察した。
フィゲロアの目はひどくすわり、激しい混乱に混濁を深めながら、その焦点さえも危うくなっている。
今、フィゲロアの脳裏には、あのモスコーソ司祭の言葉がキンキンと響き渡っていた。
『フィゲロア殿、忠良なる神の御前の子羊よ、本当にそなただけが頼りじゃ。
この国の神聖なるキリスト教を悉く血と火で汚すあの謀反人トゥパク・アマルから、この国を、そして、このか弱き牧者を守っておくれ!!』
そして、あの植民地巡察官アレッチェの言葉が、ドロドロとした赤黒いイメージと共に、ひどい大音響で耳元にこだまする。
『トゥパク・アマルに思うようにさせてはならぬ。
あの男は、再び「インカ皇帝」として君臨し、独裁政治を敷こうとしている。
そなたがそれを防ぐのだ!!』
さらには、眼前の先刻のトゥパク・アマルの言葉が…――。
『インカの地の民としての誇り、その身に深く宿る魂は、決して、いかなる民族にも劣るものではない。
我々の中には、まだそれが生きている。
今こそ、本来の我々自身を取り戻す時なのだ。
今こそ、スペインの植民地体制から独立するのだ。
この国を我々自身の手に取り戻すのだ!!』
フィゲロアの頭の中で、3人の言葉が激しく嵐のように渦巻いた。
「うわああああ!!」
いきなり狂ったような叫び声を上げるフィゲロアを鋭く見据えるトゥパク・アマルの目の中で、その褐色の敵将の呼吸はひどく荒々しくなっている。
フィゲロアは、肩を激しく上下させながら、血走った眼(まなこ)でその危険な半月刀を握り締め、にじり寄るように、確実に迫り来る。
トゥパク・アマルは、敵を刺激せぬよう、慎重に椅子から立ち上がった。
そして、すぐに次の動作に移れるように、僧衣の裾を素早く整える。
彼は、相手を深い混乱に貶めてしまったことを申し訳無くさえ思うと共に、事態がまずい方向になった、と感じる。
常軌を逸した相手との話し合いは、これ以上は無理だった。
もはや、話し合いはこれまでか…――!
まだ話がついていないだけに、トゥパク・アマルの中に苦々しい思いが渦を巻く。
しかしながら、この事態に至っては、ともかくも、この場を安全に逃れることが最優先であった。
ぬめるような不気味な光を放つ巨大な三日月型の刃を構えながら、ジリジリと間合いを詰めてくるフィゲロアを、彼は鋭く見据えた。
さすがに武勇に秀でた敵将だけあって、この状況下にあっても、刃を構えるその姿勢に隙が無い。
一方、まだ術後の傷の癒えぬトゥパク・アマルの左腕は、今は完全に通常の機能を失っている。
トゥパク・アマルの横顔に、ついに一筋の汗が流れた。
よもや、ここまでか…!!――彼の中に、そんな念が突き上げる。
武器を持参していないトゥパク・アマルは、しかし、それでも、右手で敵の襲撃に構えの姿勢を取った。
その動作に触発されたがごとく、今や常軌を逸した眼のフィゲロアが、全く戦場と違わぬ勢いで、半月刀をトゥパク・アマル目掛けて激しく振り下ろす。
「トゥパク・アマル、覚悟!!」
ビョウッと、不気味な音が空(くう)に響く…――!!
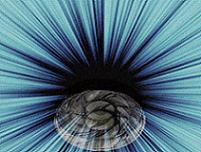
だが、確実に仕留めたと思ったはずのフィゲロアには、手応えが伝わってこない。
「!!?」
一方、完全に間一髪のところで俊敏に身を翻して刀をかわしたトゥパク・アマルが、次の瞬間には、その僧衣の裾が裂けるほどの凄まじい勢いで己の足を蹴り上げた。
そして、そのままフィゲロアの足を激しく薙(な)ぎ払う。
鉄棍のように固く鍛えられたトゥパク・アマルの足払いを受け、同じく鍛えられているはずのフィゲロアの足は、しかし、強烈な衝撃に大きく傾いた。
この時にはすっかり冷静さを失っていたフィゲロアは、そのまま大きくバランスを崩し、前方へ前のめりになった。
その一瞬に、トゥパク・アマルはフィゲロアの背後に照準を合わせ、頭頂の急所に右肘(ひじ)を鋭く打ち落とす。
たちまち褐色の敵将は気絶して床に崩れた。
彼の手から、半月刀が鋭い金属音を立てて床に転がり落ちる。
「フィゲロア殿、すまぬ…。」
そう言い残すと、トゥパク・アマルは素早く頭からベール代わりの布を被り直し、何事もなかったかのようにその部屋を出ると、門前で見張る衛兵たちに軽く会釈をしてそこを通り過ぎた。
そして、素早い身のこなしでフィゲロアの屋敷から遠ざかると、ロレンソの待つクスコの夜の繁華街の方にその姿を消し去った。
深夜遅くに、ロレンソに伴われてインカ軍に帰還したトゥパク・アマルの姿を見て、側近たちはもとよりインカ軍の兵たちは皆、深い安堵に包まれた。
「トゥパク・アマル様、よくぞご無事で!!」
あの勇猛なディエゴも、あまりに深い安堵の念から、この時ばかりは殆ど泣き出さぬばかりの面持ちである。
感情を統制することにかけては他に類を見ないあのビルカパサさえ、「トゥパク・アマル様、本当に良かった…。」と、思わず、その目が潤んでいたほどであった。
そんな側近や兵たちの心を映し出すかのように、先刻までどんよりと曇っていた空も、嘘のように今はスッキリと晴れ渡り、明るい月がインカ軍の陣営を照らし出している。
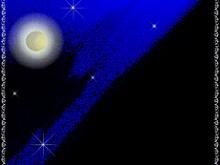
側近や兵たちに、包み込むようなあの眼差しを返しながら、「皆の者には、ひどく心配をかけた。かたじけないことであった。」と、トゥパク・アマルが深く礼を払う。
それから、彼はロレンソに改めて視線を注ぎ、「そなたの導き、誠に的確であった。深く礼を申すぞ。」と、クスコに辿り着いた時と同様に丁寧に礼を送った。
ロレンソはとても恭しく頭を垂れ、「わたしは、ただ単に道案内をしたのみ。そのような身に余る御言葉、勿体(もったい)のうございます。」と、真に深く恐縮している。
そんなトゥパク・アマルとロレンソを、今、アンドレスもまた、深い安堵と敬意の眼差しで見守っていた。
(トゥパク・アマル様、ロレンソ、無事に戻られて、本当に、本当に良かった…!!)
アンドレスの揺れるような眼差しを受けて、トゥパク・アマルもそれに応えるように穏やかな微笑みを返す。
アンドレスはそのトゥパク・アマルの視線に深く感じ入りながらも、しかし、次の瞬間、胸に何かが突き刺さるような激しい感覚に憑かれ、無意識にその目をそらした。
トゥパク・アマルは、そのようなアンドレスの様子を見逃さない。
彼はすっと目を細めて、真っ直ぐアンドレスに視線を注ぎ続ける。
アンドレスは、その視線に耐えかねるように、大柄なディエゴの陰に、まるで逃げ込むように身を隠した。
突然、己の傍に身を翻してきたアンドレスを、当のディエゴはやや鬱陶しそうに、その太い腕で軽く払うようにして、再び、トゥパク・アマルの方に向き直る。
「それで、フィゲロア殿との話し合いはどうなられましたか?
トゥパク・アマル様。」
トゥパク・アマルはまだアンドレスの方向を見ていたが、ゆっくりディエゴの方に視線を戻して、「少々、面倒な方向になった。」と、彼はありのままの経過を説明した。
「そうでしたか…。」と、側近たちは、やや肩を落として溜息をつく。
そんな彼らにトゥパク・アマルは落ち着いた声で、「案ずるな。」と言いながら、全員の方を丁寧に見渡した。
「あの者ならば、必ず、わかってくれる時がこよう。
それまで、我々も辛抱だ。」
トゥパク・アマルは静かにそう言った後、今度は力強いゆるぎない声に変わって、「この後も、今は『敵』といえども、褐色兵たちに決して刃を向けてはならぬ。そのことだけは、しかと肝に銘じよ。」と言う。
皆、「はっ!!」と、深く頭を下げて、恭順を示した。
トゥパク・アマルは、再び、深く頷いた。
それから、一応、その晩は散会となり、各人は己の天幕に戻っていった。
他の側近たちに紛れながら、いつになく素早くトゥパク・アマルの元を立ち去ろうとするアンドレスを、トゥパク・アマルが静かに呼び止める。
「アンドレス。」
アンドレスは、ギクリとした横顔で、しかし、足を止めざるをえない。
普段は、トゥパク・アマルの前であろうと、敬意を払いつつも、その態度は堂々としているアンドレスには珍しく、今はおずおずと視線を漂わせるその姿に、トゥパク・アマルは「何かあったのか?」と問うてくる。
「いえ…。」と、視線を微妙にはずしたまま、アンドレスは「今宵はこれにて失礼いたします。」と、最後にビルカパサが出て行くタイミングを逃すまいとするように出口に踏み出しかけた。
「待ちなさい。」と、トゥパク・アマルがはっきりとした声で呼び止める。
ビルカパサも、ちらりとこちらに視線を投げたが、トゥパク・アマルが「そなたは、行って構わない。」という視線を送ると、ビルカパサは恭しく一礼をして、そのまま天幕を後にした。
トゥパク・アマルの元に一人残されたアンドレスは、不安定に瞳を揺らしながら、しかしながら、この期に及んでは、ともかくも平静な表情を装おうと無理に笑顔をつくろうとする。
「フランシスコ殿のこと、そなたも気にかけていたようだが…。」
トゥパク・アマルのその言葉に、いきなり直球を投げつけられたような感覚に襲われ、アンドレスの不自然な笑顔は、いっそう引きつった。
「やはり、何かあったのだな。」と、トゥパク・アマルは低く言うと、貫くような目でアンドレスの瞳の奥を覗いた。
「何があったのか、申してみよ。」
トゥパク・アマルの視線は鋭いものではあったが、同時に、包み込むような包容力に溢れてもいる。
アンドレスは、その喉元まで、フランシスコとの一連の出来事が、そして、交わしたやり取りが出かかるが、しかし、それと共に、フランシスコの涙に歪んだあのあまりに悲痛な表情が脳裏に激しく甦る。
フランシスコの常軌を逸した行動や言動の背後にあるものは、――トゥパク・アマルに嫌われたくない、見捨てられたくない!!…――その一点に尽きるのだと、今、アンドレスには痛いほど分かっていた。
(もし全てを話したら…トゥパク・アマル様は、フランシスコ殿のことを、どう思われるだろうか…?!)
アンドレスは、トゥパク・アマルの射し込むような眼差しに釘付けられながら、固唾を呑んだ。
(トゥパク・アマル様なら、すべてを呑んで理解してくださるだろうか…?
だけど…、フランシスコ殿は、これまでの事で既に酷い羞恥心に苛まれておられるのだ。
この上、それに追い討ちをかけるようにして、今のあの状態をトゥパク・アマル様に知られようものなら、それこそフランシスコ殿には耐え難いことなのでは…?!)
アンドレスは改めて、常に正義心に貫かれているトゥパク・アマルの澱みない瞳の奥を見据えた。
真理をどこまでも追究し、不正や曲がったことには、ひどく厳しい側面を持つ眼前の人物に、今のフランシスコのありのままの姿を伝えることは、最悪の場合、フランシスコが一番恐れている事態を招くことにもなりかねぬのではないか、と、アンドレスの頭はめまぐるしく回り続ける。
そのようなアンドレスを諭すような口調で、「フランシスコ殿と何かあったのだな?真実を申してみよ。」と、相変わらず何事にも妙に察しのよいトゥパク・アマルが再び言う。
アンドレスはカラカラに乾いた喉から搾り出すように、「何も…何も、ありません。」と、応えた。
トゥパク・アマルの前で生まれて初めて、ついに偽りを語った彼の心臓は、今や早鐘のように激しく打ちはじめる。
「アンドレス…。」
トゥパク・アマルは、まるで全てを察しているがごとくに、意味深げに目を細めた。
「わたしに、偽りを告げるのか…。」と、その目は語っているかのようにアンドレスには思えてくる。
そのような思いで見上げるトゥパク・アマルの目は、恐ろしく冷ややかに、厳しく見える。
アンドレスは、己の背筋に寒気が走るのを感じた。
そのようなトゥパク・アマルの目を慄きの混ざった心境で見上げながら、今、アンドレスには、フランシスコが恐れと惑いの渦に呑まれた心境をどこか察することができた。
トゥパク・アマルの視線に耐えられず、アンドレスは思わず目をそらした。
「すいません…。」
無意識に、アンドレスの口元から、小さくそんな言葉が漏れる。
「何故、謝る?」
「いえ…。」
アンドレスは目を合わせられぬまま、深く頭を垂れた。
「今宵は、これで失礼いたします。」
そのまま天幕の出口に向かうアンドレスに、トゥパク・アマルはその目を細めたまま言う。
「明日、フランシスコ殿を見舞いたいと思う。
そなたも共に来なさい。」
アンドレスは、はじかれたようにトゥパク・アマルの方を振り向いた。
「で、でも…!!
フランシスコ殿はお加減が悪く、今はどなたともお会いにはならぬご様子です!!」
どこか必死の体(てい)でそのように語るアンドレスを、トゥパク・アマルは細めた目でじっと見つめながら、「構わぬ。明日、参る。」ときっぱりとした口調で言う。
アンドレスは己の目元が明らかに引きつるのを感じながら、もはや、たとえ小さなことでもトゥパク・アマルが言い出したことを訂正することは不可能であることを知っている彼は、朦朧とした感覚に襲われながら、礼を払うことさえ忘れたまま、その場を後にした。
ところで、かのコイユールは、その頃、どうなっていたであろうか。
その夜も、彼女は、相変わらず徹夜で負傷兵たちの治療に当たりながらも、ひどく考え深げな目になっていた。
彼女は、トゥパク・アマルへの施術中に見てしまった、まるで彼の最期を、そして、インカの滅亡を予見するがごとくの呪わしき光景に、今も心を固く縛られたままでいた。
己の見てしまったものが単なる幻覚であることを心底祈る思いと、しかし、一方で、それは真に天が指し示した何らかの啓示であったのではあるまいか、との強い思いとに、激しく引き裂かれていた。
最初は、その忌まわしきヴィジョンをひたすら恐れ慄き、それから目をそむけていた彼女であったが、時の経過と共に、僅かずつながらも、その恐怖の対象を真っ直ぐに見つめてみようとする勇気を振り絞るようになっていた。
(もし、敢えて、天がお示しくださったのであれば…それは、天がトゥパク・アマル様をお助けになろうとしているからでは?
命の危険があるから細心の注意を払えと、あるいは、何か策を講じよと、天が警告してくださったのではないかしら…――?!)
そのような考えに至ると、コイユールは、もはや己の心の内にただ悶々とその予見を留めていることに、何か、ひどく違和感と焦燥感を覚えるのであった。
確かに、トゥパク・アマルは、決して他言してはならぬ、と言っていた。
当然ながら、コイユールはその言いつけを完全に守り、決して、誰にも言いなどしなかった。
トゥパク・アマルが他言を禁じた意味は、彼女にはよく汲み取れた。
そのような呪わしい予言は、どれほど確証の乏しいものであったとしても、兵を、民衆を、大いなる不安と混乱と恐怖に陥れる危険性があまりにも大きかった。
ましてや、このような不安定な戦況下では、それは尚更のことであろう。
流言となって尾ひれがついて広まり、果ては、敵の情報操作に利用される危険さえあるのだ。
(トゥパク・アマル様は、そのお心に、お一人で呑みこんでおられるのだ…。
というか、あのお方なら、このような幻覚まがいの不確かなものなど、そもそもお気に留めることなど無いのかもしれないけれど…。)
でも!!…――と、コイユールは、その華奢な褐色の手をギュッと握り締めた。
(できるだけのことは、しておきたい!
しておかないと、いけない!!)
コイユールは意を決した表情で、きっぱりと前方を見据えた。
その心の中に、はっきりとアンドレスの姿を思い描いて。
(あの時、見えたものを、アンドレスに話そう!
アンドレスなら、きっと、真剣に受け留めてくれる。
トゥパク・アマル様をお傍で、しっかり守ってくれる…――!!)
コイユールはすっくと立ち上がった。
そして、ついに彼女は、アンドレスの天幕がある方角に向かって歩みはじめた。
微かに足の震えるのを感じながらも、しっかりと大地を踏みしめながら、一歩、一歩、着実に。

トゥパク・アマルの側近たちの天幕のありかは、義勇兵たちも皆、知らされていたから、コイユールも自然とその位置は知っていた。
やがてアンドレスの天幕が近づくにつれて、コイユールの胸の鼓動は、己の耳にもはっきり聞こえてくるほど高鳴った。
あまりの緊張と、高揚感から、だんだん頭がぼうっとしてくる。
(アンドレス…。)
もうすぐアンドレスに会うのだ――会えるのだ…ああ、本当に何年ぶりかしら…――そう思うと、愛しさと、切ない感情の高まりから、一体、何のためにそちらに向かっているのかさえ分からなくなってくる。
あまりの感情の高ぶりから、その目には涙さえも浮かんできた。
コイユールは頭を振って、「しっかり…!」と、声に出して自分を叱咤する。
そして、細い指先で、溢れる涙をぬぐった。
その時、月明かりの下を、トゥパク・アマルの天幕の方向から、彼の天幕の方に戻ってくるアンドレスらしき人影の姿がコイユールの目に飛び込んだ。
(え?!
まさか、アンドレス?!)
コイユールは心臓が止まる思いで息を呑み、しかし、夜闇の中で、じっと目を凝らす。
幸い、明るい月に照らされて、それが確かにアンドレスだとわかると、殆ど無意識のうちに、さっと木陰に姿を隠した。
(アンドレスだわ!!
なんてタイミングがいいのだろう。
今なら…衛兵の目もはばからず、アンドレスに声をかけられる…!)
激しく高鳴る胸を押さえながら、意を決して飛び出すチャンスをうかがうように、コイユールは大木の陰から身を乗り出した。
一方、アンドレスは、深く思いに耽った目をして、まるで心ここにあらずという足取りで歩み来る。
まさしく、今、彼の心と頭の中は、今晩のフランシスコとの出来事と、そして、明日、フランシスコを強引にも見舞うと言ったトゥパク・アマルのことで、完全に占められていたのだった。
コイユールが見守る中、アンドレスは、ひどく思いつめた表情のまま、己の天幕すら通り過ぎ、彼女が身を隠す大木の前をも、ただ呆然と通り過ぎていった。
(…――アンドレス…!!)
これほど直近を通り過ぎながらも、自分の気配に欠片(かけら)も気付くことのないアンドレスの様子に、コイユールは全身から力が抜けていくのを感じた。
一方、当のアンドレスは、天幕も、コイユールの隠れる大木も、はるかに通り越してから、やっと、はたと我に返ったように慌てて己の天幕の方に引き返しはじめた。
コイユールは揺れるような眼差しで、再び自分の直近を通り過ぎていく彼の横顔を見つめた。
彼女の瞳の中で、すっかり肩を落としたアンドレスは、重々しい悩みを抱え込んでいるように、とても苦しげに、辛そうに、映る。
(ああ…アンドレス…!!)
コイユールは、目の前の愛しい人の名を、ただ心の中で呼びかけるしかできなかった。
それから、音をたてぬよう、深く溜息をつく。

あのように煩悶しているアンドレスに、これ以上、負担をかけるようなことを言えようか…――。
むしろ、その身に、その心に背負っているものを、少しでも肩代わりしたいくらいの気持ちになってしまう。
コイユールは再び涙の溢れるのを今はぬぐうことも忘れて、おぼつかぬ足取りで天幕の中に消えていくアンドレスの後姿を最後まで見届けると、彼女もまた深く肩を落とし、ふらつく足取りで治療場へと戻っていった。
一方、コイユールの来訪など露とも知らぬアンドレスは、その晩、ついに一睡もできぬまま日の出の時を迎えた。
彼は後頭部に鈍痛を覚えながら、どうにも落ち着かぬ心境で己の天幕を出た。
夏の早朝の白々とした空が見える。
彼の天幕の入り口付近で警護に当たっている兵たちが、早々とその姿を見せた自分たちの若き隊長アンドレスに、深い礼を払って挨拶を送ってくる。
「アンドレス様、おはやいですね。」
アンドレスは力ない笑顔で、「おはよう。いつもご苦労様。」と言うと、ふらりと天幕を後にした。
いかなる時でも大抵は晴れ晴れとした笑顔を絶やさぬ通常のアンドレスの様子とは異なるその風情に、兵たちは心配そうな視線でその後姿を見送った。
まだ早朝のまどろみの中にある陣営の中を朦朧とした頭を抱えるようにして歩むアンドレスの足は、無意識のうちにフランシスコの天幕に向かう。
勤務交替をしたのであろう、昨晩とは別の衛兵が、その天幕の入り口で警護に当たっていた。
アンドレスは意を決したように、衛兵の傍に近づく。
やはり衛兵は恭しく深い礼を払って、アンドレスの方に頭を下げる。
「アンドレス様、おはようございます。」
アンドレスも深く礼を払って、「おはよう、ご苦労様。」とその労をねぎらった。
「フランシスコ殿は、まだお休みだろうね。」
「…はい。」
そう返事をしながらも、サッと視線をそらす衛兵の目を覗くようにして、アンドレスは言う。
「フランシスコ殿に、どうしてもお伝えしたいことがあるのだ。
フランシスコ殿とお会いすることはできないだろうか。」
衛兵は視線を泳がせながら、「フランシスコ様は、今は、どなた様ともお会いになられぬと仰っておりまして…。」と、昨夜の衛兵と同じことを言う。
アンドレスは深刻な表情で、相手を見据えた。
「わかっているが、そこを何とか、取り次いでほしいのだ。
とても火急の用件だから、と、お伝えしてほしい。
トゥパク・アマル様のことで…と!」
「トゥパク・アマル」の一言に、まるでそこにトゥパク・アマルがいるかのごとくに、急に緊張した面持ちで居住まいを正した衛兵は、「わ、わかりました!と…とにかく、聞くだけ聞いて参ります…!!」と慌てて天幕の中に姿を消した。

アンドレスは思いつめた眼差しで、じっとフランシスコの天幕の入り口を見据えて待った。
彼とて、その本心は、昨夜のフランシスコの異様な言動と、そして、まるで常軌を逸した行動に、まだ全く気持ちの整理をつけられずにいた。
できることなら、暫くの間、顔を合わせることは極力避けたい心境ではあったが、事態の急を要することを思えば、そのようなことは言ってはいられなかった。
(フランシスコ殿は、昨夜はひどく酔っていらしたのだ。
その上、俺が、お心をえぐるようなことばかり申し上げたから…、あの温和なフランシスコ殿も、さすがに箍がはずれてしまったのだろう…。
それで、あのようなことを…――。)
自分にそう言い聞かせることで、アンドレスは、何とかして己を納得させようとした。
しかし、どれほど振り払おうとしても、昨夜のフランシスコの泥酔し切ったあの尋常ならざる様子と、その彼から投げつけられた言葉の数々は、今もアンドレスの脳裏に生々しくこびりついたままぬぐえなかった。
『おまえがトゥパク・アマル様のおそばに来てから、すべてが狂ってきたのだ。』
『アンドレス…おまえが、わたしをここまで追い込んだ…。
二度と、おまえの顔など見たくはない…――!』
『トゥパク・アマル様に誰よりも大事にされているおまえに、わたしの何がわかるというのだ。
おまえのような、常に安全な位置にいて、庇護され、穢(けが)れを知りませんと言わんばかりの奴を見ていると、全てを破壊してやりたくなる…!!』
そして、それらの容赦無い言葉の数々と共に、あの時、いきなり顎を掴まれた際の、その喰い込むようなフランシスコの指と爪の感触、さらには、フランシスコの顔面に強引に引き寄せられた際の覆いかぶさるような酒の臭いと、そして、震撼とも、嫌悪とも、何とも形容し難い異様な感覚…――それらを思い出した瞬間、アンドレスの胸に激しい嘔気が突き上げた。
「ウッ…――!」
彼は思わず身を屈(かが)めて、咄嗟に己の口を右手で押さえた。
しかし、彼は全てを振り払うように幾度も頭を振ると、決然とした表情で前方を見据えた。
そして、己を叱咤するように、心の中で言い放つ。
(今、すべきことに集中するのだ、アンドレス!
フランシスコ殿の、あのような状態のままをトゥパク・アマル様にお見せすることはできない…――!!)
相変わらず苦渋と困惑を滲ませた表情の衛兵が、今回は昨夜とは異なり、素早くアンドレスの元に戻ってきた。
「アンドレス様、どうぞ中へお入りください、とのことでございます。」
フランシスコからの言葉を恭しく伝える衛兵に、アンドレスは目を見開いた。
「本当に?
本当に、俺が中に入ってもいいと?
フランシスコ殿が、そう仰っているのか?!」
「はい、アンドレス様。
トゥパク・アマル様のことで、と、お伝え申し上げましたら、中へ通してほしいと…。
さあ、どうぞ中へ!」
「ありがとう!!」と力を込めて礼を述べ、アンドレスは決意を秘めた眼差しで入り口の垂れ布をまくった。
中に入ると、相変わらず酒瓶の中に埋もれるようにして、朦朧としたままテーブルに座しているフランシスコの姿があった。
(一晩中、飲んでいたのだろうか?!)
アンドレスの胸は、再び悲痛な思いでいっぱいになる。
今、彼に向けられるフランシスコの眼には、昨晩同様の憎悪が漲ってはいたが、「トゥパク・アマル様が、何と言っておられるのだ?」と尋ねてくるその表情は、深い慄きと恐れに満ちている。
その目つきは、今や憎しみの対象であるはずのアンドレスにさえも、激しく救いを求めんとするがごとくの、喰い入るような必死の様相を呈していた。
アンドレスは、フランシスコの傍に跪いた。
そして、言葉を選ぶようにしながら、慎重に言う。
「フランシスコ殿、どうか落ち着いてお聞きください。
今日、トゥパク・アマル様が、ここにお見舞いに来られます。」
フランシスコは、すっかり黄色くなったその眼を、突如、カッと見開いた。
そして、いきなりヒステリックな声で叫ぶように言う。
「トゥパク・アマル様が…ここに…?!
ア…アンドレス…まさか…!!
そなた…話したのだな?!
トゥパク・アマル様に、わたしの、この滅茶苦茶な状態を…そなた、話したのだな!!」
フランシスコの激しい剣幕に、アンドレスは急いで首を振る。
「いいえ、フランシスコ殿!!
俺は、まだ何もトゥパク・アマル様に申し上げてはおりません。
ですが、トゥパク・アマル様は、ご心配されているのです。
どうしてもお見舞いしたいと…。」
フランシスコのいきり立った顔は、今度はすっかり泣きそうに変り、その憔悴しきった顔面が今やピクピクと痙攣をはじめている。
見るからに呼吸が乱れだし、あのジットリとした油汗が額に噴出する。
再び身体症状を呈しはじめたフランシスコの怯えを取り除くように、アンドレスはできる限りの柔らかい声で語りかけた。
「大丈夫です。
まだ、今なら時間はあります。
急いで、この天幕を片付け、身を清められ、トゥパク・アマル様のご来訪に備えましょう。」
真摯な優しい瞳で見つめるアンドレスの目の中で、フランシスコはすっかり震え上がった弱々しい表情を浮かべたまま呆然と放心している。
アンドレスは、さらに声を和らげて囁くように繰り返す。
「フランシスコ殿…、突然のことに驚かれるのは無理もありません。
でも、今から準備すれば、まだ十分、間に合います。
大丈夫…!
俺が、何もかも手はずを整えますから。
だから、心配しないで、さあ…お立ちになって…。」
フランシスコは、もはや、他に手立て無しと思ったのか、今にも泣き出しそうなその目線を不安定に泳がせながらも、力無く頷いた。
アンドレスは相手を安心させようとして微笑みを絶やさぬまま、頷き返す。
(よかった…!
とりあえずは、フランシスコ殿に話が通じた…!!)
まずは、安堵し、しかし、天幕内部を見渡すと、すぐにアンドレスの表情は曇った。
そして、小さく呟く。
「まず、この無数の酒瓶を何とかしないと…。」
この戦乱の最中に、よくぞここまで掻き集めたと思われるほどの何十本にも及ぶ酒の空き瓶が、所狭しとばかりに散乱している。
恐らく、負傷兵たちのためにトゥパク・アマルが特別に取り寄せた貴重な酒類を、倉庫から無断で持ち出したのに相違なかった。
アルコールは本来は薬の一種であり、適量の使用により、程よく脳に作用し、身体的苦痛を緩和するのみならず、精神的にも気力を回復する役割を果たしてくれる。
生死を彷徨う負傷兵にとっては、命綱にもなりうる珍重なもののはずである。
そのようなものに手を付けたと知れたら、いくら相手がフランシスコであろうと、さすがのトゥパク・アマルも黙ってはいまいと思われた。
アンドレスは額に手を当てたまま難しい表情で、考え込んだ。
まさか、これほどの酒瓶を陣営内のどこかに捨てるわけにもいかないし…、とはいえ、この天幕の中に隠す場所も無い。
(やむを得まい…!)
アンドレスは意を決した目で、フランシスコを見た。
「この酒瓶を、一旦、俺の天幕に運びましょう。
処理の仕方は、後で考えればよいのだから。」
フランシスコは、驚愕したようにその眼を大きく見開いた。
「しかし!!
アンドレス…そのようなことをして、万一にも、そなたの天幕で酒瓶の山なぞ見つかろうものなら、そなたが酷い罪に問われよう…!」
己の身を案じているかのようなフランシスコの言葉に、アンドレスは素直に微笑んだ。
「ご案じくださり、ありがとうございます。
大丈夫です。
少なくとも、今日、トゥパク・アマル様や側近の誰かが俺の天幕に来る予定はありません。
それより、ここを急いで片付けましょう。
さあ!」
そう言って、床に身を屈め、俊敏な手つきで酒瓶を集めはじめたアンドレスを、フランシスコはまだ驚きを引き摺ったままの表情で呆然と見つめている。
「アンドレス…そなた、何故…何故だ…?
あれほど酷くそなたのことを罵ったわたしに、何故、そこまでする…?!」
アンドレスは酒瓶を集める手を動かし続けたまま、フランシスコの方に顔だけ上げて、笑顔を見せた。
「フランシスコ殿のお気持ち、何となく分かるのです…。
多分、俺たちは、どこか似ているのです。」
「そなたと、わたしが…?」
相変わらず驚いたように己を見下ろすフランシスコに、再び、柔らかな笑顔を返して、「さあ、ともかく、急いで一緒に酒瓶を集めてください。その後、俺は見つからぬように瓶を運び出しますから、その間にフランシスコ殿は水場で御身を清めてきてください。それから、ここの空気も入れ換えねば…。」と言いながら、アンドレスはテキパキと作業を進めていく。
すっかり酔いの回ったおぼつかぬ手つきではあるが、フランシスコも、今は素直にアンドレスの指示に従っている。
自分の方に背を向けながらも、黙々と酒瓶を集めはじめたフランシスコの様子に、アンドレスは心の中の冷たい塊がゆっくり溶け出すのを感じた。
彼はフランシスコの後姿に、いつもの優しい微笑みを送り続ける。
…――そんなアンドレスの目の届かぬ角度で、フランシスコの横顔に密かな策謀の色が浮かんでいるとも知らずに。

次第に日が昇り、白んでいた空がいっそう明るくなってくる。
アンドレスは集めた酒瓶を麻袋に押し込み、天幕の内部を整えると、改めて、見違えるようにスッキリとした全体を見渡した。
「こんな感じなら、もう大丈夫ですね。」
そう言って笑顔を送るアンドレスに、フランシスコも微かに笑顔を見せた。
弱々しい笑顔ではあったが、久しぶりに見るフランシスコの笑顔を、アンドレスは眩しそうに見つめた。
それから、「それでは、俺はこの瓶を自分の天幕に運んでしまいますので、フランシスコ殿は水場にいかれて御身を清めてきてください。お召し物も新しい物を。」と言いながら、天幕の入り口の垂れ布を開いた。
そして、垂れ布を開いたままの状態になるように、布の端を器用に結わえて止めた。
早朝の爽やかな涼風が、天幕の中に流れ込む。
「こうして、新鮮な空気を流しておけば、だいぶ酒の臭いもとれましょう。
さあ、はやく。」
アンドレスに促されるようにして、フランシスコは急ぎ着替えの準備を整えて、天幕の出口に向かう。
相変わらず、優しい笑みを湛えながら見守るアンドレスの方を、フランシスコはおずおずと振り返った。
そして、躊躇(ためら)いがちに、しかし、心を込めた声で言う。
「そなたは、本当に心根の美しい者なのだな。」
そのフランシスコの台詞に、アンドレスは、瞬間、先日来(せんじつらい)のやりとりを思い出し、ビクリと身を固める。
そんなアンドレスの様子に、フランシスコは慌てて言葉を継ぎ足すように続けた。
「いや…、決して、悪い意味で言ったのではないのだ。
助かったよ。
ありがとう、アンドレス。」
そう言って、再び小さく笑った。
「いえ…、俺の方こそ、ありがとうございます。
フランシスコ殿…!」
「何故、そなたが礼を言うのだ…?」という目でフランシスコがこちらを見たが、「さあ、早く行ってきてください。」と、アンドレスに促され、そのままフランシスコは実に久々に天幕の外に出ていった。
(あんなに憎く思われていた俺の言葉を聞き入れてくださり、ありがとうございます!
フランシスコ殿…!!)
フランシスコの後姿を見送りながら、アンドレスは心の中で深く礼の言葉を述べた。
そして、そのまま、今度は真剣な顔になる。
(このまま、トゥパク・アマル様とフランシスコ殿との間の信頼関係が元に戻れば、他の側近たちとも、また以前のような良い形に戻れるかもしれない。
いや、実際は、フランシスコ殿が、お一人で疑心暗鬼になられているだけなのだ。
だから、フランシスコ殿のお気持ちの中の疑いを何とか晴らしたい。
そのためには、今日、トゥパク・アマル様が、以前と変わらずフランスシスコ殿に接してくださることが肝要。
何とか、このまま上手く事が運びますように…――。)
アンドレスは祈るような気持ちでそんなふうに思いながら、己の天幕に運ぶため、空の酒瓶で膨れ上がった重い麻袋を持ち上げた。

やがて夏の午前の陽光が降り注ぎはじめた頃、フランシスコの天幕でトゥパク・アマルを迎える準備を完了したアンドレスは、「それでは、これからトゥパク・アマル様のところに行って参ります。」と、フランシスコに笑顔を向けた。
身を清め、こざっぱりとしたフランシスコは、しかし、トゥパク・アマルの来訪が迫っていることに再び怯えの色を強く滲ませ、力なく寝台に横たわっている。
そんな彼に、「大丈夫です。」と、アンドレスは安心させるように優しく微笑み、それから、噛み締めるように、「トゥパク・アマル様は、本当に今でも、フランシスコ殿のことをとても大事に思っていらっしゃるのですから。お信じください。」と言う。
そして、もう一度、相手の瞳に深く頷き返し、アンドレスはトゥパク・アマルの天幕に向かった。
まだ午前の早い時間ではあったが、空気の薄い高地の盛夏の日差しは、既に肌をじりじりと焦がすほどに強い。
トゥパク・アマルの天幕に近づくにつれ、しかしながら、アンドレスの心にも次第に緊張の色が広がる。
アンドレスなりに己の信ずるところに従った行動であるとはいえ、トゥパク・アマルの目を誤魔化すための行いであることには相違なかった。
彼の心の奥底が、にわかにざわめく。
(いや、こうするしかなかった…。
これでよかったのだ!!)
己を叱咤するように心の中できっぱりと言ってから、意を決した表情でトゥパク・アマルの天幕に足を踏み入れた。
既に、アンドレスの来訪を待っていたらしきトゥパク・アマルは、「それでは、参ろうか。」と淡々とした声で応じる。
「はい。」と畏まるアンドレスを見下ろすトゥパク・アマルの感情の見えない目は、どこか探るように鋭い。
アンドレスは心の中で固唾を呑んだ。
フランシスコを見舞うために、アンドレスを連れ立って颯爽と陣営を歩むトゥパク・アマルに、そして、アンドレスに、すれ違うインカ兵たちが次々と深く頭を垂れて礼を払う。
そして、また、二人から少し離れたところで警護しながら歩むビルカパサにも、兵たちは恭しく頭を下げる。
トゥパク・アマルの重臣ビルカパサは、常に控えめに主人への恭順を示し、その命さえ投げ打って行動してはいたが、実際のところ、彼は貴族の中でもかなり高位の身分に属する者だったのだ。
かくして、もともとトゥパク・アマルの天幕に近いフランシスコの天幕には、ほどなく着いてしまう。
アンドレスの胸の鼓動は、押さえようにも、どうにも速まるばかりだった。
だが、表情に出さぬよう、懸命に平静を装う。
一方、トゥパク・アマルはフランシスコの天幕から少し離れたところで足を止めた。
その辺りからは、遥かに連なる長大なアンデス山脈を背景に、雄大に流れるビルカマユ川が眼下に広々と見渡せる。
フランシスコの天幕の方にすっかり気をとられているアンドレスに、トゥパク・アマルが呼びかけた。
「アンドレス、来てごらん。」
アンドレスはハッとして、振り向き、慌ててそちらに向かう。
トゥパク・アマルは夏の陽光に輝く山脈の方に真っ直ぐ顔を向け、眩しそうに、そして、その自然美を慈しむように目を細めた。
アンドレスも、その眼差しにつられるように、眼前に展開する雄大な光景に視線を向けた。

緑の香り立つような爽やかな風が吹きぬけていく。
短い夏を謳歌するように緑に燃える遥かなるアンデス山脈は、夏の午前の、瑞々しくも力強い太陽の光を受けて、湧き立つようなエネルギーを彼方の大地まで解き放っているように見える。
一方、眼下に広がるビルカマユ川の深い藍色の水面では、夏の眩い陽光を反射して、幾重もの繊細な波紋が光を宿しながらキラキラと煌いている。
そして、彼方の宇宙空間までが透けて見えるほどに蒼く澄み切った上空には、一羽のコンドルが悠然とその大きく逞しい翼を広げ、宙を切るように鋭く、力強く、滑らかに、そして、優美に舞い飛んでいる。
トゥパク・アマルの漆黒の長髪が風に舞い、その傍らでは、その背丈も風貌もすっかり逞しく成長し、どこかトゥパク・アマルに似てきたアンドレスが、まるで吸い込まれるように雄大なパノラマに見入っている。
爽やかな風に吹かれながら高台に立つ二人の上に、透明な黄金色の陽光が煌々と降り注ぐ。
少し離れたところから二人を見守るビルカパサの目には、まるで二人が年の近い父親と息子、あるいは、兄と弟のごとくに見える。
ビルカパサは、その眩しさに、思わず目を瞬かせた。
暫し、コンドルの飛翔を視線で追っていたトゥパク・アマルが、不意に言う。
「この後、いかなることがあろうとも、わたしは、常にそなたたちと共にあるであろう。
あのコンドルのように。」
アンドレスは、驚いたようにトゥパク・アマルを見上げた。
眩げにコンドルを見つめるトゥパク・アマルの、いつもと変わらぬ精悍な横顔が彼の目に映る。
「え?
トゥパク・アマル様?」
己の方に釘付けられたように見入るアンドレスの方に視線を移し、トゥパク・アマルは微かに目を細めた。
(トゥパク・アマル様、何を言っているのです?
何のことです?!)
トゥパク・アマルの言葉の意味を察するのを恐れるかのように、そして、その言葉を掻き消そうとするように、アンドレスの揺れる瞳はトゥパク・アマルの顔を見据える。
そんなアンドレスの方を黙って眺め渡しながら、今、彼を見下ろすトゥパク・アマルの面持ちに、何かとても感慨深げな色が浮かんでいく。
「それにしても…アンドレス。
こうして改めて見ると、そなたは、そなたの父にとても似てきたようだ。
そう…だな、姿も、その性格も。」
そう言って、包み込むような、慈しむような眼差しで、そっと微笑んだ。
(え…――?!)
突然、亡き父のことに触れられ、アンドレスは、無意識のうちに、その美しい彫像のような目を大きく見開く。
アンドレスの父親は、彼が6歳になる頃には、既に他界していた。
スペイン渡来の神父であったこと、事故で亡くなったらしいことを聞かされてはいたが、そんな父のことを聞こうとすると母があまりに悲しそうな顔をするために、アンドレスは父のことを詳しく聞けぬままに生育してきた。
それでも、幼き日、その大きな胸に包み込むようにして慈しんでくれた父の温もりの記憶は、その感覚として、アンドレスの中にずっと残っていた。
(父上…!!)
思わず、瞳を潤ませそうになるアンドレスを、トゥパク・アマルは全く実の兄か何かのごとくに見守っている。
「アンドレス、そなたの父は確かにスペイン人ではあった。
だが、そなたの父が、我々インカのために、その身を捧げていたことを、そなたは知っているか?」
「え!?
…いえ!!」
驚きと興奮の表情で身を乗り出してくるアンドレスに、トゥパク・アマルは深く頷く。
「いずれ時がくれば、そなたも知ることになるであろう。
アンドレス、そなたの父を、わたしは誇りに思っている。」
「…――!!」
アンドレスは恍惚としたまま、完全に言葉を失っている。
そんな彼の方に真正面から向き直り、トゥパク・アマルは改めて目を細めた。

「そなたも、そなたの父のごとくに、この悠久のインカの地を、その民を、守り抜くに足る者として相応しく、さらに成長しなければならないよ。
アンドレス。」
そう言って、トゥパク・アマルは、もう一度アンドレスに向かって、はっきりと微笑んだ。
アンドレスの鼓動がドキンと、強く脈打った。
急激に熱いものが体の奥底から込み上げてくる感覚を覚える。
頬を紅潮させながら己を見上げるアンドレスの逞しく成長した肩を、やはり逞しい褐色の手で軽く叩くと、トゥパク・アマルは今までとは少し趣の異なる意味ありげな笑みを浮かべ、「では、フランシスコ殿のところへ参ろうか。」と、歩みはじめた。
◆◇◆ここまでお読みくださり、誠にありがとうございました。続きは、フリーページ 第六話 牙城クスコ(9) をご覧ください。◆◇◆
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- duta89 link daftar terbaik dengan …
- (2024-09-11 01:49:11)
-
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『「死んでみろ」と言われたので死に…
- (2024-12-01 00:00:20)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- バーバラ・H・ローゼンワイン/リッ…
- (2024-11-30 22:57:12)
-
© Rakuten Group, Inc.


