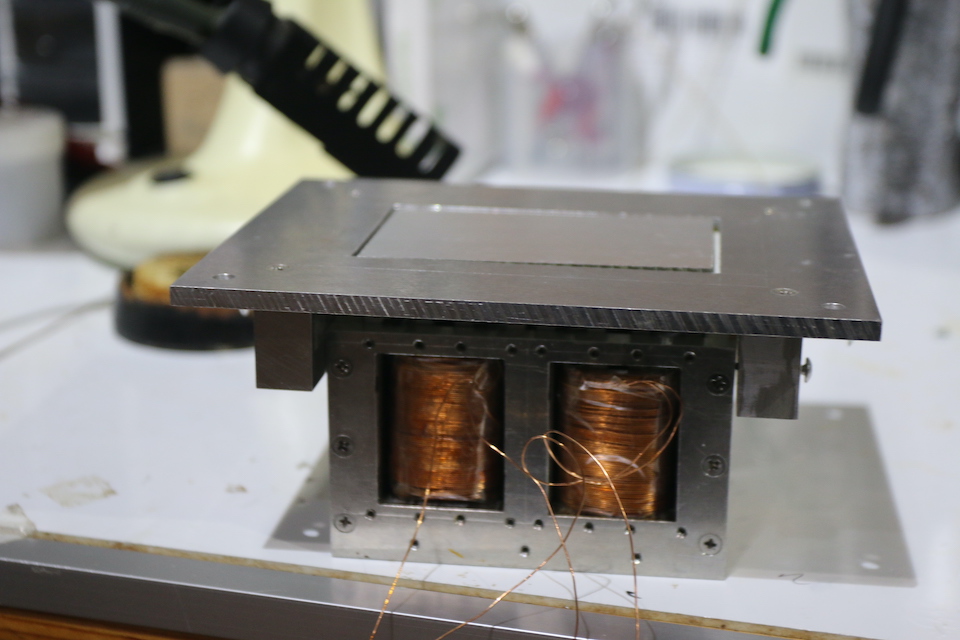2024年12月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
アルバム『NINE HALF』(その2)
河合奈保子さんのアルバム『NINE HALF』について書いていたところ、やや中途半端なところで終わってしまったので、引き続きこのアルバムについて少しばかり書いておきたいと思います。『NINE HALF』は、河合奈保子さんのアルバムの中では個人的にもっとも「再生回数」の多い作品の一つで、もはや何度聴いているかわかりませんが、繰り返し聴いても飽きがこない良作です。もちろんその理由としては、プロデューサーを務めたウンベルト・ガティカをはじめとするスタッフ陣の良質な音作りに加えて、参加しているミュージシャンたちの力量によるところが大きいことは言うまでもありません。ですが本作はそれだけでなく、シンガーとしての奈保子さんのひとつの集大成というか、完成形とも言える面があり、翌年のアルバム『Scarlet』から本格的に自作曲に取り組んでいく奈保子さんにとって、ミュージシャンとしての道のりにおける「第二期」から「第三期」へのターニングポイントとして相応しいものです。本作で訳詞を担当した売野雅勇さんは、既述のとおりボーカリストとしての河合奈保子さんの才能を非常に高く評価していましたが、『週刊現代』の企画「熱討スタジアム」(売野さん、嘉門達夫さんと下隆浩さんによる鼎談)の中では以下のようにコメントされています。アイドルの曲ってアイドル本人が前に出すぎて、音楽が後ろに引っ込んでしまうものなんです、宿命的に。だから日常生活の中で普通に聴くのは難しい。だけど、奈保子ちゃんは違う。音楽として聴けるんですよ。きっと、彼女は歌うことが心の底から好きだったんじゃないかな。※上記はJR120XEさんのブログに掲載されている記事から引用させていただきましたこの売野さんの発言は、特に『NINE HALF』について言及したものというわけではありませんが、私からすると、奈保子さんの曲が「音楽として聴ける」という特徴は『NINE HALF』において非常によく表れているように感じられます。売野さんが企画面を担当した『さよなら物語』に『STARDUST GARDEN』という、コンセプト性の高い二つのアルバムを経て幅を広げた表現力が、『NINE HALF』では純粋に「音楽性」として発揮されていることが、そのような印象につながっているのかもしれません。付け加えると、『DAYDREAM COAST』から『NINE HALF』まで、シングルA面曲をひとつも含まないという楽曲構成(『NINE HALF』にはシングルB面の「白い影 ONLY IN MY DREAM」を収録)は、アルバムを「音楽」として聴かせるという観点から考えるた場合に、プラスの面があると思います。つまり、これらのアルバムの中には華やかな衣装を着てシングル曲をステージで歌う「アイドル・河合奈保子」ではなく、あくまで「シンガー・河合奈保子」だけが表現されている、ということです。もちろん、だからといって「アイドル・河合奈保子」の魅力を否定するものではありません。ただ、アイドルであってなくても、テレビ番組やコンサートで歌う姿から「歌うことが心の底から好きだ」と聴く人に思わせるパッションがこれほど溢れている人は珍しいのではないかと思います。もう一つ『NINE HALF』における歌唱面での特徴としては、『DAYDREAM COAST』から積極的に取り入れるようになったヘッドボイスによる表現を、より洗練された形で聴くことができるという点があげられます。特に「星になるまで NIGHT AFTER NIGHT」や「砂の記号 HAPPY EVER AFTER」でのスキャットはたいへん美しく、かつそれぞれ異なる魅力があります。また、いずれの曲でもミックス領域からヘッドボイスへの移行が自然で、かつ強度を保ったまま歌われていますが、こうした歌い方は『Scarlet』以降の作品、たとえば「ハーフムーン・セレナーデ」の中にも活かされていると見て差支えないでしょう。ただ、『NINE HALF』において奈保子さんの歌は(スタジオでのレコーディングなので当然といえば当然ですが)、時に情熱的かつパワフル、時にソフトで抒情的になることはあっても、あくまでコントロールされ、バンドやバッキングボーカルと調和を保っていますが、「ハーフムーン・セレナーデ」の場合、スタジオ録音の音源ですら歌に込められた感情の幅が尋常でないところが違いと言えるでしょう。これがライブになると完全に振り切れており、まさしく魂が燃焼するような歌唱になっているのですが、『NINE HALF』に収録された「NIGHT AFTER NIGHT」にも同じような面があり、アルバムに収録されたレコーディングとNHK『ヤングスタジオ101』での歌唱(『河合奈保子プレミアムコレクション』に収録)にはそれほど大きな違いはないのですが、88年よみうりランドEASTでの「NIGHT AFTER NIGHT」後半は完全に別世界となっており(じっさいスキャットがまったく異なるのではありますが)、聴く者を圧倒する絶唱となっています。というわけで、結局何が言いたいかという話ですが、『NINE HALF』が何度でも聴けるアルバムであるのは、その音楽的な完成度の高さ、コントロールされた美しさゆえである一方で、ライブミュージシャンとしての奈保子さんの本質は、そのコントロールを突き破ってしまうほどのエモーションであり、それこそが私を捉えて離さないものではないかと感じるのもまた事実なのです。<参考文献>週刊現代2019年3月30日号|JR120XEのブログ|Fifty Bellが聞こえる・・・ - みんカラ
2024.12.03
コメント(0)
-
イエスのアルバム『ヘヴン&アース』
『トーマト』に『90125』と、なぜかイエス「らしくない」アルバムを取り上げて来たので、引き続きその路線で2014年のアルバム『ヘブン&アース(HEAVEN & EARTH)』を紹介します。このアルバムはイエスの21枚目のスタジオ・アルバムであり、バンド結成からただ一人、すべての作品に参加してきた柱石とも言えるベーシストであるクリス・スクワイヤの遺作となりました(2015年6月27日逝去)。80年代以降のイエスの作品は評価の分かれるものが少なくありませんが、本作もその例にもれず、というか、基本的に評判は芳しくない部類に入るでしょう。この記事を書いている時点でアマゾンのレビュー平均は3.8点(評価数641)となっており、いずれも4.7点の『こわれもの』や『危機』とは大きな差があります。不評の理由はいくつか考えられますが、少なくともその一つは長らくメインボーカルを務めたジョン・アンダーソンの不在でしょう。といっても、彼が参加した最後のアルバムは2001年の『マグニフィケイション(Magnification)』で、その後2008年にイエスの結成40周年を記念したツアーを前に急性呼吸不全によりジョンは長期休養を余儀なくされました。その間、ボーカルにべノワ・デイヴィッドを迎えたイエスは2011年に10年ぶりの新作『フライ・フロム・ヒア』をリリースしますが、そのべノワも病気のため脱退し、後任として加入したのが現在もイエスのリードボーカルを務める「もう一人のジョン」ことジョン・デイヴィソンです。彼は「危機」をはじめ、かなりのハイトーンが要求されるイエスの代表曲を歌えるだけの広い音域の持ち主ですが、アンダーソンに比べるとかなりソフトな声質のため、アンダーソンに比べると「弱い」と感じる人が少なくないようです。ただ、これまでアンダーソンの「代理」を務めたトレヴァー・ホーン(『ドラマ』)やべノワ・デイヴィッド(『フライ・フロム・ヒア』)が「ちょっとアンダーソンっぽい」という評価にとどまったのに対し、デイヴィソンはアンダーソンとは明確に異なる個性の持ち主で、かつアンダーソンの音楽に対するリスペクトも持っており、結成40年を超えたイエスが、イエスとしての音楽性を保ちつつ新たな方向性に踏み出すにはむしろ好適の人材だったという見方もできます。12歳の頃からイエスのファンだったというデイヴィソンは、「ラウンドアバウト」というイエスのトリビュート・バンドなどで活動していましたが、アメリカのプログレ・バンドであるグラス・ハマーにスカウトされます。グラス・ハマーもイエスの影響を強く受けたバンドで、特にデイヴィソンが参加して制作された『イフ』はその傾向が強く表れていると言われますが、その後、他ならぬイエス自体に加入することになるとはデイヴィソン自身も思いもよらないことだったのではないでしょうか。彼とイエスの間を橋渡ししたのは、実はフー・ファイターのドラマーとして有名なテイラー・ホーキンスでした。ジョン・デイヴィソンとテイラー・ホーキンスは幼少期に家が近所で親しく、ともに音楽を志す間柄であったということです。一方でテイラーとイエスのベーシストであるクリス・スクワイヤの間にも親交があり、2012年にツアーを前にべノワ・デイヴィッドが病気離脱を余儀なくされた際、テイラーの仲介でクリスがジョン・デイヴィソンにコンタクトしたことで彼の加入に繋がったといいます。『ヘヴン&アース』はほとんどの曲にデイヴィソンの名前がクレジットされており、彼のカラーが前面に出た作品と見てよいでしょう。評判が芳しくない原因のもう一つはおそらくこの点にあり、たとえばアルバム冒頭、ミドルテンポの「Believe Again」はイエスにしてはかなり穏やかな、ヒーリング系と言ってもよいサウンドで、プログレ的な「尖った」楽曲を期待する向きには物足りないかもしれません。ドラマーとしてはかなり高齢となり、健康上の問題も抱えていたアラン・ホワイトの演奏がかなり軽めになっているのはやむを得ないとして、スティーヴ・ハウのギターやクリスのベースも控え目です。エイジアでは個性を強く出すキーボードのジェフ・ダウンズも、イエスでは脇役に徹する傾向がありますー彼の場合も、個性強すぎ(笑)のリック・ウェイクマンと常に比べられてしまうという面がありますが…とはいえ『ヘヴン&アース』は、メンバーの大半が60代半ばとなったバンドが年齢相応に大人しくなったことだけを示すものではありません。「Light Of The Ages」や、アルバム最後に収められた「Subway Walls」には、「成熟したプログレ」とでも呼びたくなる味わいがあります。前者はイエスにしては珍しいマイナー調の曲ですが、スティーヴのトレードマークでもあるスティール・ギターに加えて、クリスのベースが時にメロディアスな動きを見せながらしっかりと全体を支えています。後者は変拍子や転調を織り交ぜたもっともプログレ的な楽曲で、各パートに見せ場がありますが、中間部では特にクリスのベースが渋い輝きを見せています。曲の最後のパートは7拍子でDマイナー(ニ短調)の荘重な音楽となり、デイヴィソンの "Trance end" というロングトーンが印象的に流れます。Dマイナーはクラシックの交響曲ではある種特別な意味付けを与えられるキーであり、たとえばショスタコーヴィチの交響曲第五番や、19世紀ドイツの大作曲家ブルックナーの最後の交響曲第九番、そしてベートーヴェンの有名な交響曲第九番などがニ短調で作られています(ちなみに河合奈保子さんの自作曲で言うと「十六夜物語」や「緋の少女」がニ短調、非自作曲ではたとえば筒美京平さんの「エスカレーション」がニ短調)。アルバムの4曲目、イエスとしては珍しい3連バラードである「To Ascrnd」は、やはりソフトで美しいメロディーで、それだけに古参のイエスファンにとっては「ぬるい」と感じられるかもしれませんが、コーラスを付けているのがクリスであることもあり、彼の最後のアルバムに収録された曲としてとりわけ印象深い曲です。ただ一人バンド結成時からのメンバーとして、イエスを守り続けてきたクリス・スクワイヤは2015年に急性骨髄性白血病のために惜しくも亡くなりましたが、彼の遺志は、90年代からイエスと関わってきたビリー・シャーウッドという理想的な人材に受け継がれました。ジョン・デイヴィソンの加入から10年以上が経ち、その後クリスに続いてアラン・ホワイトも2022年に他界したため、1970年代からのメンバーはスティーヴ・ハウのみとなっていますが、結成から50年を超えたイエスは、いわゆる5大バンドの中で唯一新作をリリースし、活動を継続しています。「もう一つのイエス」として活動を始めるかに見えたAWR(アンダーソン・ウェイクマン・ラヴィン)が、結局アルバムをリリースしないまま解散したことも考えれば、ジョン・デイヴィソンの加入は正しい道だったと見るべきでしょう。<参考文献>Martin Popoff "Time And A Word The Yes story”Yes Singer Jon Davison Discusses New Album 'Heaven & Earth' And All Things Prog-Rock [INTERVIEW] | IBTimes
2024.12.02
コメント(0)
-
アルバム『NINE HALF』
1984年~85年にかけてのいくつかの楽曲に触れつつ、the Gentle Wind に脱線したりもしてちょっと時期が前後しましたが、ここでようやく(?)アルバム『9 1/2 NINE HALF』について紹介したいと思います。「9 1/2」の表記は本来の字体と異なるのですが、フォント的に表記できないので(私がやり方を知らないだけかもしれませんが)以降は『NINE HALF』とのみ表記します。『NINE HALF』は、河合奈保子さんの12枚目のオリジナルアルバムとして1985年12月12日にリリースされた、海外レコーディング第二弾となる作品です。LPと並行してミュージック・ビデオも制作され、同日に『9 1/2 <ナイン・ハーフ> Fantastic Journey』として発売されました。こちらは抜粋版が「PURE MOMENTS」ボックスに収録されています。また、ピーター・ベケットのカヴァーであるシングル「THROUGH THE WINDOW~月に降る雪~」も同日リリースとなりました。SACD盤にボーナストラックとして収録された「THROUGH THE WINDOW」と「砂の記号」のロングバージョンは、ミュージック・ビデオに使用されたものです。アルバム『NINE HALF』はオリコンチャートでは10位にとどまり、3位まで上がった『DAYDREAM COAST』に比べると順位を落としていますが、アルバムとしての完成度や歌唱の成熟度という面では、奈保子さんの数あるオリジナルアルバムの中でも屈指の出来といってよいかと思います。『さよなら物語』や『ブックエンド』も同様ですが、奈保子さんのアルバムは売上やチャート順位と作品としての仕上がりが必ずしも一致しないものが少なくありません。といっても、もちろん『DAYDREAM COAST』が十分魅力的なアルバムであることを否定するものではありませんが…さて、初の海外レコーディングとなった『DAYDREAM COAST』ではL.A.の大物ミュージシャンが多数参加していましたが、この『NINE HALF』でも引き続きデイヴィッド・フォスター、マイケル・ランドウ(G)にTOTOのマイク・ポーカロ(B)といった面々が参加しているのに加えて、TOTOのボーカル(兼ギタリスト)であるスティーブ・ルカサーが「FINDING EACH OTHER」のデュエットで参加しています。ドラムは『DAYDREAM COAST』のレコーディングでは"JR" ことジョン・ロビンソンとTOTOのジェフ・ポーカロの二人が参加していましたが、『NINE HALF』はジョン・ロビンソンが全曲を担当しているようです。ちなみに彼は "USA for Africa" によるチャリティー・シングルとして有名な「We Are the World」のドラムを担当した人物でもあります。アルバム全体のプロデュースは『DAYDREAM COAST』でもエンジニアとして参加していたウンベルト・ガティカが担当しており、詞・曲はトム・キーン(Key)やマイケル・ランドウら複数のメンバーがクレジットされています。アレンジについては基本的にトム・キーンとウンベルト・ガティカの二人が手がけていますが、「FINDING EACH OTHER」のみデイヴィッド・フォスターが担当しています。ちなみにアルバムのクレジットによると、この曲で彼はすべての楽器を演奏しているとのことです。また、訳詞は全曲売野雅勇さんとなっています。ところで、「WHAT COMES AROUND GOES AROUND」について書いた中で、河合奈保子さんは「日本語」でロックを歌えたことについて強調したわけですが、それは『DAYDREAM COAST』の場合、曲調としてはロックでありつつ、歌詞がほぼ日本語になっていたことを踏まえての記述でした。これに対して、『NINE HALF』では英語の歌詞が多くなっており、「FINDING EACH OTHER」のように全曲が英語、つまり原詞のままで歌われる曲もあります。『Naoko Premium』のブックレットに掲載されている「奈保子しんぶん」Vol. 32の記事によると、デイヴィッド・フォスターの秘書で奈保子さんと同年齢だったスーザンという女性に発音の特訓を受けたエピソードが語られています(なお、アルバムのクレジットでは "ENGLISH INSTRUCTOR" として "LUCA BERCOVICHI" という記載があります)。特訓の甲斐あってか、"R" の発音に苦労した「TURN IT UP(トワイライト・クルーズ)」での発音も自然で、本作に関しては「奈保子さんの英語の発音が上達した」ことがポイントとして挙げられることがあるようですが、それは確かにその通りではあっても、個人的にはあまり重要ではないかなと思っています。同じ英語でもアメリカとイギリスとインドではまったく発音が異なるわけで、日本人の歌手が「日本風の英語」で歌ったとしても、それは表現として何も問題はないはずです。むしろ、英語(というか、じっさいは「アメリカ語」)の発音が巧みであることを日本人歌手の「力量」として評価するのはちょっと軸がずれているように感じられます。ただ、本作の場合現地のミュージシャンと共演しているわけで、特に「FINDING EACH OTHER」でスティーブ・ルカサーとのデュエットをハイレベルで完成させるためには英語のトレーニングは確かに必要だったでしょうし、「風の花びら(THERE'S NOT MANY LEFT)」のようなかなりの「早回し」をこなすのにも役に立ったという想像はできます。ファンの方々には言わずもがなですが、河合奈保子さんは現在オーストラリアに在住されています。オーストラリアの英語もまた、USやUKとは発音が異なる面があるようですから、『NINE HALF』の楽曲をいま奈保子さんが歌ったら、オーストラリア風の発音になるのでは、などと妄想したりしています。<参考文献>『Naoko Premium』ブックレット「奈保子しんぶん」Vol. 32(1985年10月)
2024.12.01
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1