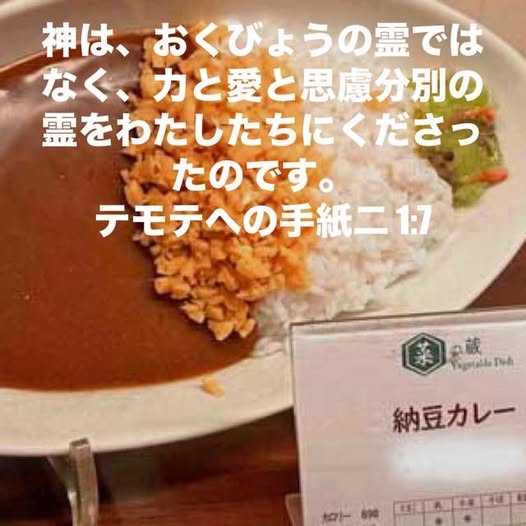沖縄料理チャンプルー
| ■■■ | 沖縄料理チャンプルー | ■■■ |
沖縄伝統料理は、医食同源の思想を中国から受けていて、沖縄方言では食べ物を「クスイムシ」(薬になる体にいいご飯)とか、「ヌチグスイ」(命の薬)とも呼び、長寿食として有名。
沖縄の野菜料理のチャンプルーとは琉球語で「混ぜこぜにした」というような意味があり、沖縄独特の固い豆腐を中心にした炒め物である。ただし豆腐や野菜に限らず、様々な材料を一緒にして炒めたものでもある。
その料理の チャンプルー に似ていることから沖縄文化を「チャンプルー文化」と呼ぶこともある。
その訳は、沖縄が古くから中国文化の影響を受けてきたのち、江戸時代には影で薩摩藩に支配された。明治以降は日本政府による統治され、戦後はアメリカ軍による統治を経験する。
いろいろの文化と接することで常に影響を受け続けてきているが、それらを柔軟に受け入れ、独自に生み出した沖縄の文化を、この料理のチャンプルーに似ていることから「チャンプルー文化」という。
ところで、チャンプルーに使われる材料は多彩。一般的なタマナ(キャベツ)、ニンジン、マーミナ(モヤシ)などの他にゴーヤー、パパイヤなど独特のものもある。

風味のある沖縄独特の豆腐に、豚肉、またはSPAMなどのポークランチョンミートやツナ、それに卵、麩などが材料。
独特の風味を持ち炒めても崩れにくい沖縄の豆腐を使用することが本土の野菜炒めとの大きな違いである。 だだし、豆腐を使用しないチャンプルーもある。固く茹でた素麺とニラやネギなど少しの野菜のみを炒めるソーミンチャンプルーなどだ。
言葉としての意味からは、豆腐を用いないものはチャンプルーとは呼ばない習慣もある。
だから、「ソーミンプットルー」または「ソーミンタシヤー」と呼ぶべきであると言う。
沖縄独特の豆腐が手にはいらない場合には、木綿豆腐を代わりに念入りに水切りして代替としたり、厚揚げを使うこともある。
絹ごし豆腐は、きめが細かくて水切りができないため、炒めた際にグズグズに崩れてしまうので適さない。
素材を順に炒めていき、豆腐やポークなどの味に加えて、塩や醤油、好みで胡椒などで味付けする。砂糖を入れて少し甘く仕上げみたり、鰹節を最後に風味付けに混ぜ合わせることもある。
多彩なチャンプルーのバリエーションを、主な材料の名を付けて「○○チャンプルー」と呼んでいる。
◆ゴーヤーチャンプルー

代表的なチャンプルーで、ゴーヤーを含めた野菜、豆腐などを材料としたのが、 ゴーヤーチャンプルー 。
◆マーミナーチャンプルーモヤシであるマーミナー(豆菜)で、モヤシ中心のチャンプルー。他の野菜が少量であったり、豆腐やポーク等を含まないので「マーミナーチャンプルー」という場合が多い。
◆タマナーチャンプルーキャベツのことをタマナー(玉菜)といい、キャベツ中心のチャンプルー。「タマナーチャンプルー」という場合、他の野菜が少量であったり、豆腐やポーク等を含まないことが多い。
◆パパヤーチャンプルー青い状態で生で食べられるようになる前の、青いパパイヤを使う。これを千切りにしてからあく抜きし、チャンプルーにしたものをいう。
◆ナーベーラーチャンプルーヘチマのことをいうナーベーラーを使い、青い状態のヘチマを豆腐やポークなどと炒める。また、水分が多くて、煮物状になることからチャンプルーと言わないで「ナーベーラーンブシー」とも呼ぶ。
◆野菜チャンプルー野菜、豆腐、ポークなどを材料としたチャンプルー。モヤシ・シイタケ・ニンジンなど野菜の種類が多くて、中心となる野菜がないというより、あまりに色々なチャンプルーの特色を混ぜてしまったものというが、「野菜チャンプルー」。 多彩な野菜類から大量の水分が出てきて、これらが醤油や肉汁とまざって、独特の風味がある。
◆豆腐チャンプルーチャンプルーの中でもその名の通り、豆腐を主役として、他の野菜やポーク等があまり無いもの。
◆ポークチャンプルー豚肉やツナなどではなく、ポークランチョンミートを使ったチャンプルー。
◆フーチャンプルー
フーと呼ばれる麩を使う。沖縄で常用されるいる車麩を水や卵液に浸し、野菜などとともに炒める。フーイリチーと呼ばれることもある。
炒め物の中でも昆布や中身(豚の臓物)等の炒め煮は「 イリチー
」と呼ぶ。
◆ソーミンチャンプルー素麺であるソーミンのチャンプルー。固めに茹でたソーミンを使い、少量の油に、ニラやネギなど少量の薬味野菜と先に炒めておいたポークやツナなどと一緒に炒める。
【楽天トラベル】情報
航空券とホテルがセットになった「ANA・JAL楽パック」が誕生!
■日程や発着空港の条件などを入れるだけで、航空券やホテルの空席・空室確認ができます。さらにリアルタイム予約も。なにより航空券とホテルを自由に組み合わせられることが一番の魅力です。
>> あなただけの自由な旅を…