木地師について
<木地師について>図書館で「漆・柿渋と木工」というわりと地味な本を手にしたのだが…
これだ、これだ♪木地師が載っているし、民俗学と木工がダブルで語られるとは、ドングリ・ワールドなんですね。
それと『脊梁山脈』を読む前に、木地師について勉強しておこうとも思うわけです。
・柳田国男の故郷七十年
・漆・柿渋と木工
・木と漆(民芸の教科書3)
・木地師の里
<柳田国男の故郷七十年>
図書館で『柳田国男の故郷七十年』という本を手にしたが・・・・
この本は柳田国男入門には最適とのこと。
兵庫県民なら、なおさらやで・・・ということで借りたわけです。
まず、大使のツボともいえる木地屋のあたりを見てみます。
p118~120
<木地屋のこと>
ふるくから山奥の原始林地帯に入って、木地の材料を求め、これを加工していろいろの木器を造って里に出していた木地屋の生活には、われわれとして研究すべきものがたくさん含まれている。
小倉とか小椋、大蔵など、オグラという言葉は、私は山上の「小暗き所」という意味だろうと思うが、こういう苗字や地名は、大体において、この木地屋に由縁があると見られる。
近江の君ヶ畑や蛭谷などを心の故郷としたこれら同業の人々は、近江、伊賀、伊勢はもちろん、北陸にも東海にも東北にも、また中国から西国の果ての九州の島々にも、いたるところその足跡を残している。
田中長嶺の書いたものとして世に知られる「小野宮御偉績考」なども、木地屋についての問題を扱い、遠く南北朝の時代にも遡ろうとする面白い試みであるが、何分にもその基になるものが全部近江蛭谷に伝わる作りごとから出発しているので、信用いたしかねるのである。
本の出来た年代にしても、私がこの事柄をいい出したときよりは、やっと十年ぐらいしかさかのぼれないのである。収録されている古文書の写しなども、太閤時代の長束正家という人に関するものなどは、本物らしいが、他はどうも疑わしいものが多い。
しかし木地屋そのものは、なかなか興味のある問題をもっている。播州西部の谷間でも話にきくし、但馬、丹波、越前あたりにかけても、その拡がりが認められる。
全国の木地屋の総元締と伝えられてきた近江の木地屋も、愛知郡の蛭谷や君ヶ畑、犬上郡の大君ヶ畑など、それぞれの系統があったらしい。しかもここでは寛政、享和のころにはすでに木地の材料がなくなって、ただ諸国に散らばっている木地屋を糾合するだけであった。木地屋の系統といえば、私は面白いことから近江と地方とのつながりを知ったことがある。
明治40年前後私が内閣の役人をしていたころ、賞勲局に横田香苗という人がいた。彦根藩士で、名家の出で、学者でもあった。もと警視庁の捜査係をしていたこともある。他のことではあまり冗談も言わない人だったが、この人の話に、維新前、今の日比谷に彦根藩の邸があって、そこに一人、近江犬上郡大君ヶ畑の木地屋に関係のある者がいた。いつも道楽をして金が足りなくなると、箱根の木地屋に行って僅かだけれど借りて来たというのである。つまり箱根の木地屋が大君ヶ畑の系統であったからという話であった。
箱根の木地屋は一時寄木細工などをしていたが、やがてこれでは手数がかかるので、それも廃れてしまった。明治になって、山林を自由に伐ることができなくなった木地屋は、大体二つに分かれてしまったようである。
まず少し有能の士は里に降りて来て木地の卸し売りをし、方々と連絡をとって大規模な生産や供給をした。次に能力の乏しい方は、コケシなどを造るようになったのではなかろうかと考えている。
私は近ごろまた木地屋のことに興味をもち出したのは、民族の国内移動ということを調べるのに、この山間を漂泊した木地屋などは最もよい例だと思うからである。
<木地屋のこと>
ふるくから山奥の原始林地帯に入って、木地の材料を求め、これを加工していろいろの木器を造って里に出していた木地屋の生活には、われわれとして研究すべきものがたくさん含まれている。
小倉とか小椋、大蔵など、オグラという言葉は、私は山上の「小暗き所」という意味だろうと思うが、こういう苗字や地名は、大体において、この木地屋に由縁があると見られる。
近江の君ヶ畑や蛭谷などを心の故郷としたこれら同業の人々は、近江、伊賀、伊勢はもちろん、北陸にも東海にも東北にも、また中国から西国の果ての九州の島々にも、いたるところその足跡を残している。
田中長嶺の書いたものとして世に知られる「小野宮御偉績考」なども、木地屋についての問題を扱い、遠く南北朝の時代にも遡ろうとする面白い試みであるが、何分にもその基になるものが全部近江蛭谷に伝わる作りごとから出発しているので、信用いたしかねるのである。
本の出来た年代にしても、私がこの事柄をいい出したときよりは、やっと十年ぐらいしかさかのぼれないのである。収録されている古文書の写しなども、太閤時代の長束正家という人に関するものなどは、本物らしいが、他はどうも疑わしいものが多い。
しかし木地屋そのものは、なかなか興味のある問題をもっている。播州西部の谷間でも話にきくし、但馬、丹波、越前あたりにかけても、その拡がりが認められる。
全国の木地屋の総元締と伝えられてきた近江の木地屋も、愛知郡の蛭谷や君ヶ畑、犬上郡の大君ヶ畑など、それぞれの系統があったらしい。しかもここでは寛政、享和のころにはすでに木地の材料がなくなって、ただ諸国に散らばっている木地屋を糾合するだけであった。木地屋の系統といえば、私は面白いことから近江と地方とのつながりを知ったことがある。
明治40年前後私が内閣の役人をしていたころ、賞勲局に横田香苗という人がいた。彦根藩士で、名家の出で、学者でもあった。もと警視庁の捜査係をしていたこともある。他のことではあまり冗談も言わない人だったが、この人の話に、維新前、今の日比谷に彦根藩の邸があって、そこに一人、近江犬上郡大君ヶ畑の木地屋に関係のある者がいた。いつも道楽をして金が足りなくなると、箱根の木地屋に行って僅かだけれど借りて来たというのである。つまり箱根の木地屋が大君ヶ畑の系統であったからという話であった。
箱根の木地屋は一時寄木細工などをしていたが、やがてこれでは手数がかかるので、それも廃れてしまった。明治になって、山林を自由に伐ることができなくなった木地屋は、大体二つに分かれてしまったようである。
まず少し有能の士は里に降りて来て木地の卸し売りをし、方々と連絡をとって大規模な生産や供給をした。次に能力の乏しい方は、コケシなどを造るようになったのではなかろうかと考えている。
私は近ごろまた木地屋のことに興味をもち出したのは、民族の国内移動ということを調べるのに、この山間を漂泊した木地屋などは最もよい例だと思うからである。
木地屋ということば使いからして、柳田先生の上から目線が表れていて気になるところです。(目の付けどころはいいだけに、惜しまれます)
先日、竹中大工道具館の企画展「木地屋 小椋榮一の仕事」で「木地屋集落と移住ルート」を観たのだが・・・・
営々と移動した庶民の活力または悲哀に感じいったのです。
 木地屋集落と移住ルート
木地屋集落と移住ルート【柳田国男の故郷七十年】

石井正己編、PHP研究所、2014年刊
<「BOOK」データベース>より
小林秀雄も絶賛の隠れた名著・柳田国男の口承自伝を読みやすく最編集して復刊。
【目次】
故郷を離れたころ/私の生家/布川時代/辻川の話/文学の思い出・交遊録/私の学問
<読む前の大使寸評>
この本は柳田国男入門には最適とのこと。
兵庫県民なら、なおさらやで・・・ということで借りたわけです。
rakuten 柳田国男の故郷七十年
【漆・柿渋と木工】
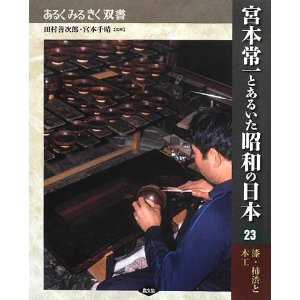
田村善次郎監修、農山漁村文化協会、2012年刊
<「BOOK」データベース>より
阿波半田の塗師、宮城県鳴子の漆かき、越前大野の木地屋と塗師、各地の柿渋屋、南会津の太鼓屋など、伝統工芸を受継いできた人々を訪ねる。
<読む前の大使寸評>
これだ、これだ♪木地師が載っているし、民俗学と木工が語られるとは、大使のツボを突いているわけです。
全国で五ヶ所の民俗学的フィールドワークが紹介されているが、いずれも昭和52年から61年までのレポートであり、これらが産業として今も残っているか、やや不安を覚えるのです。
Amazon 漆・柿渋と木工
木地師はいろんな職人集団のなかでも最も上流側で、下請けにあまんじていたようです。
<木地屋のくらし:須藤護> よりp173~174
木地屋の生活の場も仕事場も山であった。古くは家族ともども年間通しての山暮らしであったが、越前地方では次第に里村や大野市に降り、春から秋までの雪の降らない間だけ山に入るようになったようである。スエさん夫婦も結婚した当初は、冬期間も山を降りなかったというから、大正時代の後期ごろまでは山から山へ渡り歩く木地屋の姿があったとみられる。
さて、越前地方の木地業はかなり早くから分業が成立していたようである。深い山に入って仕事をする職人は先山師とアラガタを挽く木地屋であった。先山師は原木を倒し、円筒形の木片をつくる職人、それを足踏みロクロを使ってアラガタをつくる職人を木地屋といった。アラガタは漆器の産地である河和田や山中に送られて、さらに仕上げをする。この作業をする職人もまた木地屋であった。
先山師の仕事は原木であるトチやケヤキの大木をヨキとノコギリで伐採することから始まる。まず木を倒す方向を見定めて、ヨキグチをあける。ヨキグチというのは倒したい方向にヨキで木の側面をえぐり取ることで、木の芯までヨキが入ると、今度はその背後からノコギリで挽いて見定めた方向に木を倒す。倒した木は3尺の長さに玉切りをして、切断面に椀の大きさに合わせて円を描く。これが椀の直径にあたるが、このときアガタ(芯の赤味)は、はずして木取りをしなければならない。次に円と円との間のいらない部分に溝を掘るようにヨキで削り取り、玉切りした木から円筒状のトボ(丸太)を取り出す。これをヒを掘るという。
ここまでの作業は原木の伐採現場で行い、トボを背負って作業小屋まで運ぶ。夫婦で入っている先山師は、男がトボをつくり、運ぶのは主に女の役目であったという。
そして作業小屋の中でダイギリとよばれるノコギリで椀や鉢の高さに合わせて挽き、円盤状の木片をつくる。これを枚切りといい、木取りの方法はタテキドリである。この枚切りも夫婦で行う場合が多かった。そして枚切りしたものを木地小屋に運び、それからが木地屋の仕事になる。
木地屋の仕事はロクロ挽きである。枚切りした木片をロクロにかけ、まず内側を挽き、次に木片をひっくりかえして外側を挽く。そして最後にコウダイの内部を挽いて大体の椀の形にする。これをアラガタといい、アラガタは1ヶ月ほど煙乾燥した後に、河和田や山中に送られる。

<越前の木地屋の歴史:須藤護> よりp180
元亀3年の文書は、当時木地ものを扱う職人として、板物木地の職人と、椀などの丸物木地をつくる職人、そして塗物をする職人が分化していたことを示している。引物師とあるものは挽物師の意とみるのが自然であるが、轆轤師も挽物師も、ロクロを使って丸物をつくる職人ということになるので、あるいは膳や箱物をつくる指物師のことであったかもしれない。
また永禄と天正の文書では、轆轤師と塗物師とが一つの職業集団を形成していたことを暗示している。これから、漆器の産地とまではいわないにしても、漆器を生産する小規模な職業集団が、越前の地に成立していたことが考えられる。それらの地は、「越前州今南東郡吉河、鞍谷、大同丸保」であろう。今日の鞍安川の谷口にある味真野町がその中心地であったとみられる。さらに、年代は明らかではないが、その北の今立町粟田部、河和田町片山なども、古い漆器の産地であったことが知られている。これらの地で生産された漆器が、府中(武生市)、一条谷などに出されていたのではないだろうか。
また、これらの職業集団では、古くは轆轤師の頭が主導権を握っていたと思われるが、轆轤師よりも先に塗師屋が書かれている文書をみると、次第に塗師の力が大きくなっていったことを感ずる。漆器は木地よりも漆のかけ方によって、製品の良し悪しが決定される。したがって漆器の仕上げをする塗師、そして顧客により近いところにいる塗師の力が、轆轤師よりも大きくなっていくことは当然のなりゆきであろう。近世に入って各地に漆器産地が成立し、塗師の力が強くなっていくのだが、その前段階の過程が、これらの文書の中に現れているように思える。それは、主に木地を売りものにしていたであろう中世の轆轤師が、近世の塗師の下請業としての「木地屋」、もしくは「木地師」へと変貌をとげていく過程でもあったように思える。
大使が車で帰省するときは吉野川沿いの徳島自動車道を通るが、吉野川SAの手前に半田町があることさえ知らなかったのです。
この半田町がかつては「半田塗」として知られた漆器の大産地だったようです。
<木地椀が消える:姫田道子> よりp19~20
「半田塗という名称は明治時代、小学校の地理の教科書にも収録されていたから、日本中に知られていた。特に郷土の人々には、日常の食生活にかかすことができない膳、椀中心の生活必要品であったから、半田漆器の名は非常に親しみ深いものであった」
これは竹内さんが見せてくれた昭和40年2月の徳島新聞の記事です。ところが竹内さんの仕事場には、膳などはあっても椀は見ることが出来ません。私はそれが気になりました。どうしてお椀がないのかしら。竹内さんのお話では、椀をつくっていたのは、専ら敷地屋という半田では唯一の漆器問屋だったらしい。そして半田周辺の山や、半田の町なかに住んでいた木地師たちがつくった椀木地は、すべてその敷地屋に納められていたといいます。独占でした。また明治20年代の記録では、逢坂には40軒の塗師屋がありましたが、そのうちのほとんどが、敷地屋の賃仕事をしていたといいます。たぶん半田のお椀の大多数は、そういう家々によってつくられたのでしょう。
「峠庵から逢坂見れば、朝も早よから椀みがき」
「食うや食わずの椀みがき」
と替歌にして唄われていた歌があるとも聞きました。
一階の書斎の戸棚に、わずかに1、2個ずつの白木地と錆下地をした椀がありました。竹内さん父子の手によって、仕残されたものではなさそうでした。竹内さんのお話では、お父さんの年代になってからは、山に住んでロクロを挽く木地師たちが、半田に見切りをつけて山を去って行ったといいます。山からの椀木地の供給が絶えた後は、里に蓄積された椀木地を頼りに、里に住む仕上げロクロ師が細々と椀づくりをつづけたようですが、その仕上げロクロ師も転業してゆき、角物専門指物大工の檜木地類に変わっていったようでした。
最後まで漆椀をつくっていたのは、敷地屋の下請けの塗師屋で、椀は椀、膳は膳とそれぞれ専業でやっていたようです。素地と漆と道具を敷地屋から預かり、賃仕事として敷地屋に納めます。ところが大正15年に敷地屋が廃業してからは、そのまま椀の木地も漆も道具も下請職人のものになりました。そしてしばらくは、下請け職人が自ら塗って売るという時代がつづき、やがて手持ちの漆もなくなり、木地もなくなり、半田の椀づくりは、じりじりなくなって行ったようでした。
これはひとつの例ですが、美原安夫さんという人の家では、御自分は役場に勤めながらも、家には職人を入れて御自分も昭和23年まで塗り、そして31年までには漆器類は売り尽し、大量に残った塗ってない椀木地など、若干の木地類を記念に残してあるだけで、他は全部風呂の焚き木にしてしまったとおっしゃるのでした。
<木地の道:姫田道子> よりp26~31
車で降り立ったところは、中屋といわれる山の中腹で陽が当たり、上を見上げると更に高い尾根がとりまいています。
「あそこは蔭の名、おそくまで雪が残るところ。馬越から蔭の嶺へと尾根伝いに東祖谷山の道に通じています。昔、木地師と問屋を往復する中持人が、この下のあの道を登り、そして尾根へと歩いてゆく」
と竹内さんは説明して下さると、折りしも指をさした下の道を、長い杖を持って郵便配達人が、段々畑の柔らかな畦道を確実な足どりで登ってきました。平坦地から海抜700メートルの高さまで点在する半田町の農家をつなぐ道は、郵便配達人が通る道であり、かつては木地師の作る椀の荒挽を運ぶ人達の生活の道でもあったのです。
東祖谷山村の落合までは、直線距離で25キロ、尾根道を登り降りすると40キロ。陽の高い春から秋にかけては、泊まらずに往復してしまう中持人もいたとか。さすがにプロです。ですが信じられないほどの早さです。しかも肩で担う天秤棒に振り分け荷物で13貫(約50キロ)という重量があり、いくつも難所があったのに町から塩、米、麦、味噌、醤油、衣料、菓子類までも持ってゆき、そして半田の里にむけての帰り道は木地師が作った木地類を持ち帰ります。運搬の駄賃をもらう専門職でした。おそくまで雪の残る陰の人々に、中持人が多かったと聞き、私は想いました。そこに住む人々は彼らの点在する家々の背後の尾根に上り、南の尾根へと続く落合までの道を歩みつづけて行ったのでしょう。
また半田から南東の剣山の麓近くの村、一宇村葛籠までは、峠を越え尾根道をゆき渓谷ぞいの道を歩いて25キロ。竹内さんはここで昔、木地師をしていた小椋忠左ヱ門さん夫妻をさがし当てました。51年の1月と51年の秋に二度訪れております。おそらく阿波の山でこの方ひとりが半田漆器と敷地屋とに、かかわりあいを持った最後の木地師ではないかと思われます。
竹内さんは小椋さん夫妻から、
「半田から一宇方面には、定まった中持人が来ていて、敷地屋から木地小屋までを上げ荷といった。来た日は一泊して疲れを取り、翌朝早く木地類を持って出発した。草履は一足余分に腰につけてきている。持ち帰る木地類は品物によっては数量も重さも違うが、菓子皿の場合だったら一荷400枚が定数であった、重さも12,3貫(約50キロ)であった。
冬の山は寒さが厳しく、その上とても寂しい。正月前は半田からやってくる中持人をまだか、まだかと待っていた。(問屋との清算の取引は盆と正月の年2回)」と、お聞きしたと云う。
小椋さん達は木地師文書など8点を持っていて、黒漆の縦長の合せ箱に納められ、箱の表には菊の紋と御倫旨の字が金蒔絵でかかれてあった。自分たちは山の8合目以上は、自由に伐採してよいと言い、また実際に山持ち人から、山を静めるために山へ入ってほしいと頼まれたりもする。1ケ所に3年か5年で、あたりの原木を伐り尽して移動し、忠左ヱ門さんは東祖谷から一宇の九日谷に入り、最終は、葛籠在所に定住。戦時中になって山の地にくわしいからと、営林署の山廻りをしたそうです。
木地の仕事は、秋に木を倒して玉取り(木からヨキで椀の荒型をとり出す)して放置する。冬になって1メートルほどの雪をかき分け小屋に運び入れロクロ挽きをした。
そのほか、木地師仲間との交流、年中行事、山神、道具に行われる祭事など、竹内さんは興味が尽きない話をしてくださいました。
大使は柿渋の効用を知らない世代であるが、私より一回り?上の世代の山崎さんが、その効用を説いています。
<うす暗し土蔵の隅の渋甕に:山崎禅雄> よりp156~158
私は柿渋をとった体験がない。ただ使った覚えはある。ただ使った覚えはある。わが故里の家には、子供のころには、確かに土蔵のそばのうす暗い隅に小さい渋甕があった。網目の破れたソウケ(ショウケ)や米揚げザルは、反古紙を幾重にも貼り、柿渋を刷いて補強された張り子があったし、なにかと渋紙を使っていたように思う。渋甕に柿渋が入っていたということは、近所の農家からもらっていたにちがいないのだが…。
私が渋甕をあけるのは、川の魚つりに使う釣り糸を染めるときであった。当時は、まだナイロン糸の時代ではなくて、テグスの他に木綿や麻糸を使っていた。とくに延縄は木綿糸で、夏の川遊びに欠かせなかったし、その糸は柿渋で染めて使うものであったからだ。なぜ、鼻をつままないと蓋をあけられない、あの臭い柿渋で糸を染めなくてはならないのか理由もよくわからず、ただ漁のうまい人は皆そうしているから私もまねたに過ぎなかった。
だいたいに、渋というとあまりよいイメージがない。渋い柿は、口からはき出さないといけないし、渋面にあうと用心しなくてはならない。そして渋さが味わえるのは人生経験を重ねた上のことらしい。
渋の正体というのは、これだけ化学の進んだ今日でも、わかりにくいもののようだ。百科事典の渋の項をみると、詳しくは「タンニン」の項をみよとある。タンニンの項をみると、よほど日ごろ化学に親しんでいる人でないと、何のことやらわからない渋い説明がしてある。
要するに、タンニンといおうが、渋といおうが、またジュウ質といおうが、その本体なり作用の仕組みはヤブの中であり、正確に化学分子式で示し得ないことが多いようである。このわけのわからない、つまり複合的な有機物を昔の人は「渋」といい、近ごろは西洋風に「タンニン」とよんでいるにすぎない。
食べものとしてみると、渋は邪魔物で、強い渋をもつ柿などは、それを抜くのに苦労してきたのだ。しかし反面、この口には邪魔物の渋・タンニンを世界中の人々が、それぞれの身近な植物からとり出して様々に使ってきたことも確かで、現に多用されている。
しかし、日本で「渋」といったとき、私たちがすぐ思うのは、口にしては柿の渋味、目には柿渋染めの茶系の色ではあるまいか。
ただ、柿渋染めの紙や糸布をみることの少なくなった現在、この色合いが日常の色でなくなってきている。渋紙が家庭から消えていったのは近ごろのことだが、柿渋染めの衣が少なくなったのはもっと昔で、藍染めの木綿が日常着になってからである。そして日本人の「渋い色」という言葉に、あでやかな色に対する雅趣のある地味な色というニュアンスがでてきて、渋好みは必ずしも茶系の色とは限らなくなった。
柿渋で糸や布を染めるということは、色をつけるということばかりではなく、根本のところには、繊維を強くし、腐食を防ごうとする目的があったのではないか。渋染めの中には、珍しい色を発色させる意図もあるが、柿渋染めは、色というより、繊維の強化の意味が強いと思われる。これは紙においても、木器や木材においても同様である。
<浦人よ魚獲る網の染め渋は:山崎禅雄> よりp159
柿渋は、だいたいどこでも8月の盆すぎのころに近郷の小粒の青柿をのせて叩きつぶす。そして木綿布で果汁をしぼって渋をとり甕に入れて保存しておいたのである。
明治43年、農務省水産局によって編纂された『日本水産捕採誌』の網コの項をみると、網漁が全国的に盛んになり、大型化する当時の日本で使用された網の原料は、麻糸、カラムシ、藁、葛糸、木綿糸であって、絹糸などはごく特殊な漁法にのみ使われ、テグスは釣り糸にこそ使うが網にはほとんど用いなかったようで、最も多用されたものは麻糸と、明治10年以降になって普及してゆく木綿糸であった。この魚網や釣り糸は必ずといってよいくらい渋染めにして使っている。これは同書の「網の保存法」に詳しい。それをみいると、魚網は柿渋で染めるだけでなく、全国的にみると、種々の樹木の渋が使われているのである。槲(かしわ)・楢・栗・椎・橡(くぬぎ)の樹皮を乾かし、大釜で煮出してとった渋が多く、他に樺・ブナ・ハリノマキ・ヤマモモ・ノグルミなどの樹皮や根も煮出して使っている。こうした樹皮からとる渋で一番多く使われていたのが槲である。
柿渋については ここ に載せています。
<木と漆(民芸の教科書3)>
図書館で『木と漆(民芸の教科書3)』という本を手にしたが、木地師が載っているやんけ♪
・・・ということで借りたのです。
目下のところ、木地師とかWOOD JOB!(ウッジョブ)が大使の関心事なんです。
徳島の「半田塗」は廃れたが・・・
この本を読むと、東北や北陸など木工品産業は曲がりなりにも健在のようですね。
各地の木工品について読み進めたが、北陸の状況について紹介します。
<山中木地挽物> よりp108~109
石川県にある漆器の産地にはそれぞれに特徴がある。「塗りの輪島」「蒔絵の金沢」そして「木地の山中」だ。「木地の山中」については県内にとどまらず、本書の取材を続けるなかで、各産地やつくり手からもずいぶんと耳にした。川連や会津、輪島などの大産地にも当然木地師はいるものの、数をこなすためには山中の木地に頼らざるをえない部分があるそうなのだ。
いまや全国の漆器、とくに椀などの挽物の生産地といっても過言ではない山中だが、ここにいたったことについては大きくふたつの理由が考えられる。
ひとつは、産地としての成り立ちだ。山中は安土桃山時代の天正年間に、越前の国から山伝いに入ってきた木地師の集団が、山中温泉の真砂という集落に住みついたことが起源といわれる。江戸時代中期に木地挽物の技術が伝達されて以降は、とくに挽物の産地として大きく発展を遂げていった。
<木地生産協同組合を設立し、漆器用木地の一大産地へ>
そしてもうひとつは産地として、「木地の山中」の伝統をさらに推し進めたことだ。それが、木地屋が協同で出資して始まったという「山中漆器木地生産協同組合」の設立だ。こちらでは、それまで各々の木地屋でおこなっていた原木の仕入れから、「粗取り」と呼ばれる半製品の状態に加工するまでの作業が一括しておこなわれる。
工場に入ると、ケヤキ、トチなどの樹種別、寸法別に大まかに加工された椀がうず高く積まれており、その奥では機械音が響き、4名の従業員が黙々と粗取りの作業をおこなっていた。それらを木地屋が購入し、注文に応じて製品の仕上げて、山中および全国の塗師や漆芸家へと出荷していくというしくみだ。
原木の仕入れ、粗取りというもっとも手間にかかる工程を組合でまとめて請負うことにより、木地師の作業の効率は飛躍的に向上し、全国から寄せられる大量注文にも対応できるようになった。それが原木の大量仕入れによるさらなるコストの削減を促すという好循環を生み出した。
現在の組合長で、木地師でもある中出利成さんは、「全国の漆器の椀もののほとんどは、山中でつくられたと思ってもらってもいい」と胸を張る。原木の仕入れは月に一度、中出さんと職員が岐阜の原木市場へ足を運び、ケヤキやトチ、ミズメなどを購入するそうだ。これが木地となり、全国へ出荷されていくということを考えると、中出さんたちの役割は大きい。
漆器と聞くと、塗りのこと、あるいは漆のことに目が行きがちだ。しかし、うつわの使い勝手の大部分を決めるのはそのかたち。ところが近現代の漆の世界では、そこがなおざりにされてきた感は否めない。結果として、全国の漆器産地には塗師があふれ、木地師の数は減ってしまった。その現状に山中は目をつけ、全国の木地の生産地として確固たる地位を築いた。また近年は中国などへの指導もおこなっていると聞く。活力を失っている漆器の産地も少なくないなか、歴史を重んじ、強みを理解した山中の試みは注目に値する。
塗りの種類もいろいろあって、この本では9種類の塗りが載っています。。
大使の好みは、木目の見える拭漆(摺漆)なんだけど・・・

その拭漆を売りにしている小田原漆器を読んでみます。
<ケヤキの木目を活かした堅牢で美しい木地> よりp75
室町時代中期に興り、北条氏により発展。江戸時代には地理的にも近い江戸で実用漆器として多用された小田原漆器。その背景には、一番に箱根山系の豊富な木材、また北条氏康が武具に漆を塗るために招いた多数の塗師の存在や、かつて相模漆が産出されたことなどが挙げられる。
特筆すべきは、漆器の産地のなかでは石川の山中漆器と同じく、木地挽きの技術の高さで知られることだ。
(中略)
戦後の最盛期には300人の木地師、100人の塗師を擁していた小田原漆器も、現在職人の数は往時の10分の1以下となり、漆器屋もわずか2軒に。余談だが、通常漆器の産地では、塗師が木地師を下請け的にあつかい、漆器の販売も塗師が手がけることがほとんどだ。しかし、小田原では逆で、取材で訪れた大川木工所もその名の通り、木地の制作がメインなのだが、店を構えている。このように塗師よりも木地師の立場が強いのも、木地挽きに端を発する小田原漆器ならではの他産地にはない特色である。
出迎えてくれたのは、3代目の大川肇さん。小田原漆器の特徴について、次のように語ってくれた。
「素朴というか、田舎風というか・・・。木の息づかいが感じられるものです。ケヤキの木目を活かすのに、生漆を何度も摺り込む技法(摺漆)を用います。盆などの平物は板目、椀などの深さのあるものは柾目で取ります。うつわの種類としては椀や盆が中心です。私が工房に入った30数年前は全盛期で、箱根や湯河原などの温泉旅館向けの茶びつや菓子盆、縁の立ち上がりが低い独特な形の『仁取盆』などがよく売れました。」
【木と漆(民芸の教科書3)】

萩原健太郎著、グラフィック社、2012年刊
<内容紹介>より
“木の文化"といわれる日本の暮らしを支えてきた木の道具たち。伝統的な木工品、漆工品をいまも守り続ける全国23カ所のつくり手たちをレポート。
木のある暮らしの魅力を再認識できる一冊。
産地を訪ねて、大館曲げわっぱ(秋田県)/樺細工(秋田県)/川連漆器(秋田県)/岩手の桶(岩手県)/鳴子漆器(宮城県)/会津塗(福島県)/小田原漆器(神奈川県)/木曾漆器(長野県)/松本民芸家具(長野県)/飛騨春慶(岐阜県)/庄川挽物木地(富山県)/輪島塗(石川県)/山中木地挽物(石川県)/若狭塗箸(福井県)/大塔坪杓子(奈良県)/郷原漆器(岡山県)ほか
【久野恵一】
手仕事フォーラム代表。地域手仕事文化研究所主宰。もやい工藝店主。1947年生まれ。武蔵野美術大学在学中に民俗学者・宮本常一に師事。松本民藝家具の創始者・池田三四郎との出会いをきっかけに民藝の世界へ。大学卒業後、仲間5人と「もやい工藝」をはじめ、その後独立。北鎌倉を経て現在の鎌倉市佐助に店舗を構える。40年にわたり1年の3分の2は手仕事の産地をめぐり、買いつけや調査、職人をプロデュースする活動を続けてきた。2011年まで日本民藝協会の常任理事を務め、現代の民藝運動と積極的に関わる。
<読む前の大使寸評>
“木の文化"とかWOOD JOB!(ウッジョブ)が大使のこだわりでおます。
amazon 木と漆(民芸の教科書3)
「琵琶湖の風物詩」というサイトに《木地師の里》が載っていたので紹介します。
琵琶湖の風物詩 より
《木地師の里》
とち、ぶな、けやきなどの木を伐り 椀や盆、こけし、こまなどの木地を作る職人のことを木地師と言い 轆轤(ロクロ)師、杓子師、塗物師、引物師を木地業の四職と言った。 殆どの木地師は人里離れた深山に入って職を営みながら生活し、その山に良材がなくなれば新しい土地へ移住する漂泊の生涯を送る。 その活動の足跡は全国各地に見られる。
このような木地師発祥の地が近江路の湖東地区、神崎郡永源寺町の小椋谷と呼ばれる所で、今も 「蛭谷」と「君ヶ畑」という集落がある。
今回は蛭谷にある「木地師資料館」を訪ね、この伝統文化を守り伝承努力をしておられる小椋正美氏にお話を伺った。
近江路随一の紅葉の名所としても知られる臨済宗永源寺派の大本山永源寺を過ぎ、永源寺ダムを越えて 更に30分ほど北東方向へ車で走った山中、鈴鹿山系の山々に抱かれた山間に小椋谷はある。
【全国木地師の支配・支援・保護】
蛭谷の「筒井公文所」や君ヶ畑の「高松御所」は、全国に分散した木地師たちをすべて自らの氏子と称して保護したため 江戸時代には全国最大の木地師支配組織が確立することになった。 両支配所は諸国の木地師に「山への立ち入り 原木の切り出しは自由という許可証」や「諸国の関所を自由に通行できる往来手形」を発行するなどの特権が与えられており、それによって木地師の特権を保護した。
お墨付きと称する朱雀天皇や正親町天皇の綸旨(天皇の仰せを受け蔵人所が発行)をはじめ、時の為政者(足利尊氏、織田信長、豊臣秀吉など)の許可状の写しが下付され、木地師たちは安心して活動することが出来た。
両支配所は氏子として木地師の身元を確認し、氏子かり料・初穂料・奉加金などを集め、氏子には神札・お墨付きなどを配布しながら各地を巡回した。
この廻国のことを蛭谷では「氏子駈(うじこかり)」、君ヶ畑では「氏子狩」と言い、その記録が 「氏子駈帳」 「氏子狩帳」 である。 県指定文化財で前者が32冊、後者が53冊現存し 両地区で数万戸の木地師名が記帳されている。
 木地師資料館
木地師資料館【 木地師資料館 】
筒井神社境内にある普通の民家風の建物が「木地師資料館」。 全国から寄贈されたロクロを使った伝統ある木地製品をはじめ木地師の伝統と文化を伝える古文書の数々が展示されている。
1100年以上遡る朱雀天皇、正親町天皇の綸旨や信長、秀吉の許可書の現物がこの山奥の資料館に保存されているのを目の当たりにして驚きを感じる。
またここでは 手挽きロクロの原型も見ることが出来る。 このロクロは秋田の有名なこけし工人、小椋久太郎氏の父久四郎翁が愛用された現物である。
日本木地師学界HP
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- パク・ヨンハくん!
- HappyBirthday ヨンハ 2024
- (2024-08-12 11:19:59)
-
-
-

- 華より美しい男~イ・ジュンギ~
- 10月の準彼ンダー&台北公演の画像続…
- (2024-10-01 14:52:47)
-
-
-

- おすすめ映画
- クレヨンしんちゃん/嵐を呼ぶ栄光の…
- (2024-11-14 14:40:04)
-
© Rakuten Group, Inc.



