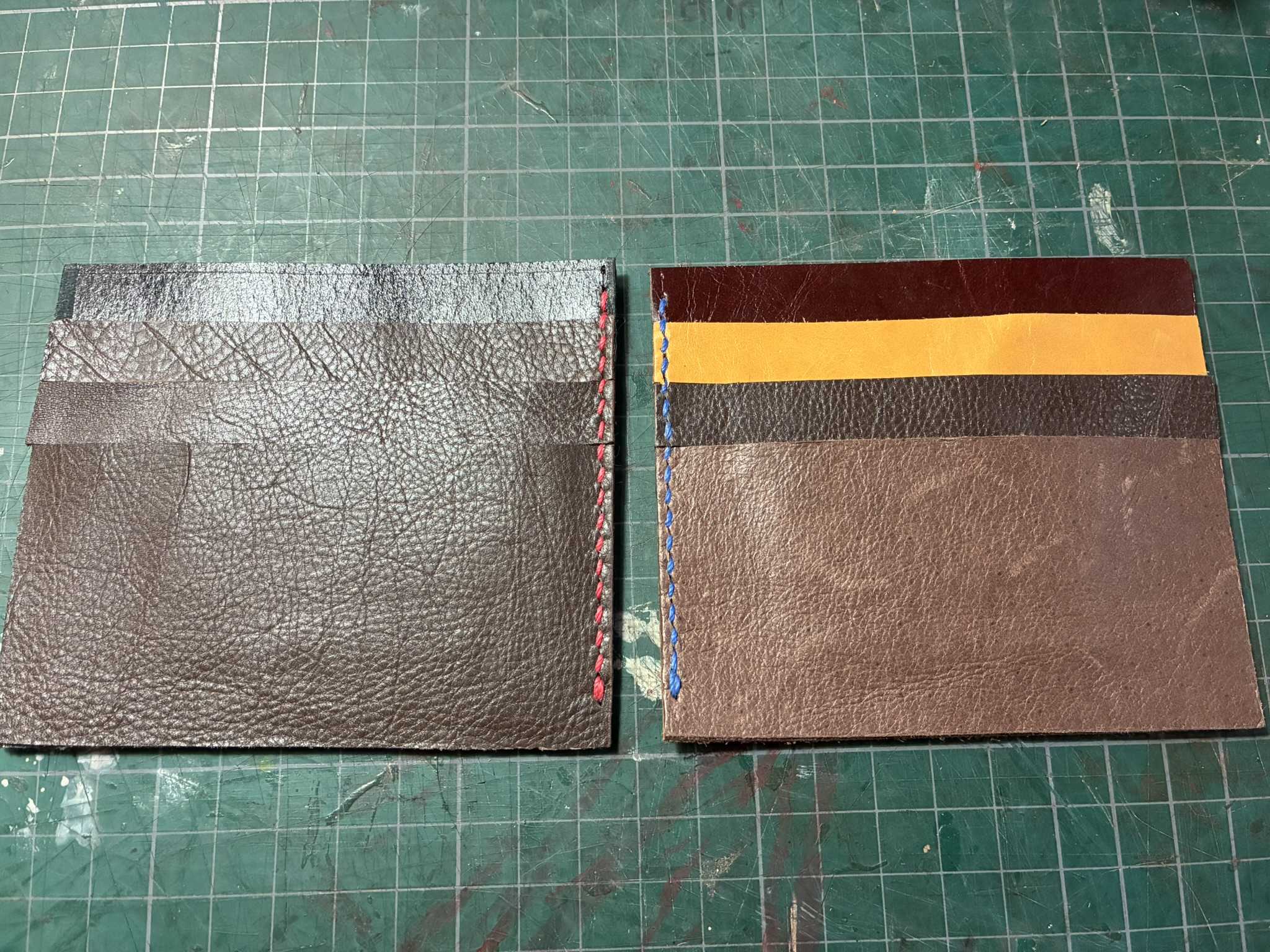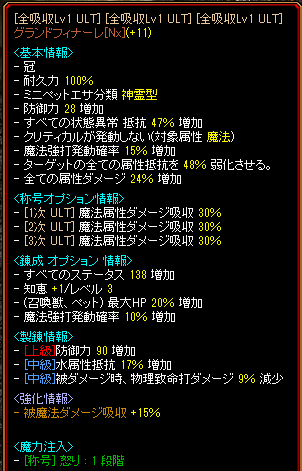2017年01月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
「笑い」はがんに効く?
「笑い」はがんに効く? 実証実験、吉本や松竹も協力へ「笑い」が、がんに効くかどうかは、別にして、健康に良いことは間違いないと思います。笑って過ごしているとき、一番、感じるのは、唾液の状態です。気分が良いときは、水のような唾液が、ほどよく、口の中にあります。嫌なとき、ストレスを感じているときは、口の中が乾いていたり、あるいは、粘っこい唾液になります。確か、医学的に、この唾液の差は、免疫力の差として出ていたと思います。これを考えると、がんにも、ある程度は効果があると思います。プラシーボ効果(思い込み)でも、病気が改善することがあるのですから。もし、効果がないとしても、笑って過ごすことに、損はありません。
2017.01.29
コメント(0)
-
シェーバーを処分 バッテリーを外す
日立のロータリーシェーバーを処分しました。2008年の製造で、バッテリーは使い始めて、1年ほどでだめになり、それ以後、ACケーブルを繋いで使ってきました。最近、電源スイッチを押しても、動かないことが多くなり、使用をあきらめました。シェーバーを処分するには、バッテリーを外す必要があります。インターネットで、取扱説明書を調べ、分解して、バッテリーを取り出しました。バッテリーはリサイクルへ。本体は、不燃ゴミへ。
2017.01.24
コメント(0)
-
本家HPを更新
本家HP「不思議な物」を更新しました。今回は、X68000のキーボードをUSBに繋ぐです。Debianで、コンパイル、書き込み環境を完結させたかったのですが、linuxのFLIPのバージョンが古く、対象のマイコンに対応していませんでした。結局、コンパイルは、Debian、書き込みは、Windowsになりました。キーの割り付けも、期待通りにでき、後は、反応しないキーを修理すれば完成です。
2017.01.23
コメント(0)
-

X68000のキーボードを、USBで接続する 2
X68000のキーボードを、USB接続に変換する機器を製作しています。昨日の続きマイコンに合うケースを、100円ショップで探してきました。100円玉を収納するケースの大きさが、ちょうど良い感じでした。加工は、ケーブルを通すための穴を空けるだけで済みました。ただし、昨日は、基板にピンを立てていましたが、それでは、ケースに収まらないため、ケーブルの配線は、基板に直接、はんだ付けしました。キーボードの入力テストは、ThinkPad X200sで行いました。このパソコンは、英語キーボードにしています。ここに、日本語キーボードを繋いで、テストするために、ソフトを使いました。キーボード切り替えツール Proこれを使うと、ノートパソコンの英語キーボードで入力を行いつつ、USB接続の日本語キーボードから入力することができます。ポイントは、どちらも、刻印通りに入力できることです。キーボードを2つ繋いだのは、X68000のキーボードが、正常に動かないときに、パソコンを操作するためのキーボードが必要なためです。入力を試してみると、予想通り、反応の悪いキーが、いくつもありました。ほとんどのキーは、10数回も繰り返し押せば回復しましたが、5、6個のキーは入力できませんでした。これは、後で、直そうと思います。問題は、キーボードが、ANSIタイプになっていることでした。通常の日本語キーボードは、JISタイプです。これは、主に、スペースキーの左右のキーの役割が異なります。ANSIでは、ALTキーなどですが、JISでは無変換キーなどになります。ソースを眺めてみると、JIS配列のマトリックスが用意されていたため、どこかのフラグを修正するだけで、JISになると思います。今時のキーボードに慣れている(ブラインドタッチ)と、刻印通りに打てることよりも、今のキーボードと同じ位置で打てることの方が便利です。特に、X68000のキーボードのCTRLキーの位置は、Aの左にあり、これは、今のキーボードの位置とは異なります。慣れている左下のキーに、CTRLは割り当てたいと考えています。また、普段から、キーボードの割り当ては、少し変更して使っています。私は、英語キーボードを愛用していますが、日本語への切り替えキーは、通常、ALT+~です。2つのキーを押すのは不便なので、Capsを切り替えキーに割り当てています。Capsの位置は、どんなキーボードでも同じなので、キーボードが替わっても、違和感なく、入力することができます。キーボードのキーの割り当ては、通常、OSの設定変更が必要ですが、せっかく、キーボード側で対応できるのですから、キーボード側でやってしまいたいと思います。そうなると、JIS配列のマトリックスに、修正が必要になります。日本語キーボードには、不慣れなため、どのキーに、どの機能を割り当てると使いやすくなるのか、検討中です。また、再度、プログラムのコンパイル、書き込みが必要になることから、開発環境を新たに作ることにしました。Debianの64ビットで行おうとしましたが、FLIPのプログラムは、X86用だったことから、32ビットで、開発環境を構築します。完成への道のりは、まだ、長い。
2017.01.22
コメント(0)
-

X68000のキーボードを、USBで接続する
X68000のキーボードを、USB接続に変換する機器を製作しています。製作が終わったら、あらためて記事をまとめる予定ですから、今回は、だらだらと、経緯を書いていきます。用意したマイコンは、ダ・ヴィンチ32Uです。主に、ADBのキーボード(昔のapple)をUSBに変換する記事で使われていて知りました。ADBのキーボードも持っていますので、これを繋げるために調べていましたが、その中に、x68用のファイルを見つけ、これでいけるのではないかと方針を変えました。ADBのキーボードは、変換器で変換しただけでは使いにくく、使いやすくするためにはハードウェアの改造が必要で、しかもでかいため、たぶん、変換器を作っても使わないと思い、X68000のキーボードにしました。昔、ADBのキーボードのテンキー部分をカットした顛末を書いていますので、興味のある方は、どうぞ(笑)Apple Extended Keyboard2 テンキーカット完成X68000のキーボードを使う理由は、日本語キーボードだからです。英語キーボードは、上記のテンキーカットを筆頭に、何台か改造して所有していますが、日本語キーボードは、未改造の物しか持っていません(笑)ひとつぐらいは、気持ちよくタイプできる日本語キーボードが欲しいと思いました。変換器の制作で、一番、参考になったのは、こちらのページです。https://geekhack.org/index.php?topic=29060.0分かる人なら、このページだけで作れると思います。さて、用意したダ・ヴィンチ32Uは、Arduinoに対応していない方です。Arduino版は、面倒があるらしく、避けました。USBミニのケーブルも、同時に購入しました。ソフトは、・tmk_keyboard 変換プログラム・FLIP・(WinAVR)らしい最初、先日、用意した、Raspberry Piの環境で開発することを考えました。FLIPをインストールしましたが、起動しません。共有ライブラリファイルがないというエラーが出ました。cpuの問題かもしれません。共有ライブラリを、CPUに最適化してコンパイルした物が用意できれば、なんとかなったかもしれませんが、Raspberry Piでの開発をあきらめ、windowsに変更しました。Windowsでは、FLIPは、素直に動きました。次に、WinAVRをインストールしました。ここまでは、順調でした。しかし、コンパイルすると、エラーが出て、コンパイルできません。調べてみると、WinAVRは古く、toolchainを使うらしいとわかり、toolchainを試しましたが、こちらも、別の場所でエラーが発生し、コンパイルできません。開発環境のIDEも、インストールしてみましたが、時間が、やたらと掛かっただけで、無駄足でした。Raspberry Piに戻り、こちらで、$ sudo apt install gcc-avr avr-libcとして、コンパイル環境を整えました。こちらでは、無事に、コンパイルできました。ここで、パッケージという手があったと、$ sudo apt install flipを実行しましたが、入ったソフトは、全く関係のないソフトでした(笑)Raspberry Piでは、コンパイルできて、.hexファイルが出来る。しかし、マイコンに書き込めない。Windowsでは、コンパイルできない。でも、マイコンには書き込める。そこで、Raspberry Piでコンパイルしたファイルを、Windowsへコピーし、windowsでマイコンに書き込みました。成功!マイコンをパソコンに繋いでみました。順調なら、USBの接続音が聞こえ、デバイスマネージャーに、キーボードの項目が増えるはずですが、増えませんでした。なにか、おかしい。そう思いつつも、キーボード側の配線を行うことにしました。資料の配線は、コンピュータ側の資料のため、キーボードの端子を見るときは、左右が逆になります。この点に注意して、配線を行いました。嫌な予感は的中し、動きません。そもそも、ジャンクのキーボード。壊れているのかもしれないと、分解して、配線をチェックしました。こちらの、X68000のキーボード配線図を参考に、配線をチェックしました。http://galapagosstore.com/resource/browser/v21/index.html#sample=true&cid=289902&pid=sh&url=http%3A%2F%2Fgalapagosstore.com%2Fweb%2Fdispatch%3FPR%3D332448%26PT%3DBUY_NOW%26cp%3DdmzYHbRZK_m7HabxgVS-e2go4WNaslQNM_7RGKwEyjPg7dMiczk0aRMwEW-6gaQMT2m4e7srzeGJTiLnoNqujMepRdaKZrRnZrbQVjbEVzUEDmq9pQgvW3BUVGVl6llu5zykfOkvu-xt0fB_0zyCiQ%3D%3D&title=%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%20X68000%20CZ%2d634C%2FCZ%2d644C問題なさそうでした。X68000のキーボードは、シリアル通信のため、Rs232cに接続して、データが送られているか確認してみることにしました。データが送られてこない。あきらめようかと思いました。念のため、tmk_keyboardのソースを眺めてみることにしました。シリアル通信を、USBに流すだけのプログラムですから、時間を掛ければ作ることはできます。でも、そこまで、手間を掛けたくない。そう思っていると、ひとつの項目を見つけました。MCU = atmega32u2atmega32u2ではなく、atmega32u4ですから、書き換えて、MCU = atmega32u4コンパイル。windowsへコピー。マイコンへ書き込み。書き込んだ、直後は、キーボードとして認識してくれませんでした。一度、抜いて、刺し直し。「ピコ!」キーボードとして認識しました。喜んで、キーボードを押してみました。しかし、何も起こりません。やけになって、キーボードを、ガチャガチャと打っていると、入力が入ってきました。メカニカルキーボードは使わないと、キーを押しても入力されなくなることがある。まして、10年以上、放置されたキーボードですから、ほとんどのキーが反応しなくても、おかしくない。ほぼ、完成しました。後は、・マイコンをカバーに入れること。・キーの接触を改善すること。この2点を行えば、完成です。
2017.01.21
コメント(0)
-

X68000のキーボード
X68000のキーボードこれを、Windowsで使えないかと挑戦しています。変換器を購入すれば解決することですが、arduinoを勉強しているため、変換器を作っています。コンパイルや書き込みの環境を整えるだけで、少々、手間取りました。さらに、プログラムを書き込んだ後、期待通りに動かず、悩んでいるところです。無事に動けば、経緯を公開する予定です。X68000のキーボードは、5Vを繋いだだけでは、LEDランプが点灯しないのでしょうか。そもそも、ジャンク品のキーボードで挑戦しているのが間違いかも。最悪の場合、マトリックススキャン、マルチプレクサなどの低レベルの部分から作り直すことになるかもしれません。
2017.01.20
コメント(0)
-

ArduinoをRaspberry Piで開発
Arduino開発環境をRaspberry Piに構築しました。写真の通り、とても、コンパクトです。さすがに、パソコン(VMware内のDebian)に比べ、Raspberry Piでのコンパイルは遅くなりますが、今のところ、それほど問題ではありません。Arduinoでのハードウェア制作に失敗して、万が一、開発マシンが壊れたとしても、Raspberry Piなら、それほど、痛くありませんから安心です。今日のところは、ハードウェアは期待通りに動きませんでした。Arduinoが、正規ではなく互換機のためなのか、接続したハードウェアに問題があるのか、単に、電力不足なのか、ソフトの問題か、原因究明中です。期待通りに動かないとき、やはり、互換機ではなく、正規のArduino Unoを購入しておけば、問題の切り分けができたのにと、後悔しています。GHEO SA Arduino Uno R3
2017.01.17
コメント(0)
-
Arduino開発環境をRaspberry Piに
Arduino開発環境をRaspberry Piに構築しました。数日前、VMwareの仮想マシンにDebianをセットアップして開発環境を構築しました。これで、勉強を進めようと思いましたが、万が一、USBポートに繋いだArduinoの影響で、パソコンが壊れると困ると思い、Raspberry Piを試してみることにしました。Raspberry Piの便利なところは、OSを構築し、そのSDカードのイメージを保存しておけば、いつでも、保存時の状態に戻せることです。これは、VMwareを使う利点と同じです。環境の構築は簡単でしたが、その前に、apt-getで、OSを最新状態にするのに時間が掛かってしまいました。最も、Windowsの更新に比べれば、早いものでしたが。さて、IDEのインストールについて前回、Debianでは、Debianのパッケージを使いましたが、今回は、www.arduino.ccから、最新版をダウンロードしました。ダウンロードファイルをダブルクリックで、アーカイバのXarchiverが立ち上がり、展開しました。コンソールで、arduino-x.x.x フォルダを、/optに移動。install.shをダブルクリックで、インストールが終わりました。
2017.01.15
コメント(0)
-

Nationalのシェーバーのバッテリーを交換
Nationalのシェーバーのバッテリーを交換しました。Panasonicではなく、Nationalですから、新しい物に買い換えた方が良いのではと言われそうです。自分でも、そう思い、今まで、2個のシェーバーを購入しました。1つ目の日立のロータリーは、そり味は良いものの、あごの下が剃れず、Nationalのシェーバーと併用することになりました。しばらく経ち、さすがに、買い換えだろうと、2つ目としてPanasonicのシェーバーを購入しました。しかし、これが剃れません。新製品の新品なのに、古いシェーバーより、だめでした。これは、予備として、仕事場に置いています。どちらも、バッテリーは、すぐに、だめになり、ACケーブルを繋いで使っています。一方のNationalのシェーバーは、古いのに、元気で、バッテリーも問題ありませんでした。しかし、さすがに、今年の冬、モーターの音から劣化を感じるようになりました。買い換えも考えましたが、これまで、2回、失望していますから、どうしようかと考えていたところ、楽天で、バッテリーを売っているのを見つけました。【在庫あり!】ナショナルパナソニックシェーバーES8001、ES8035、ES8068、ES8900、ES8930、ES8921、ES8980、ES8950、ES8067用の蓄電池★1個【NationalPanasonic ES8068L2507N】※1台の交換に必要な分だけセットになっています。試しに、交換してみて、だめだったら、新しいのを買おうと思い、とりあえず、バッテリーを購入してみました。交換作業は、取扱説明書を見て行いたいところでしたが、さすがに、古すぎて、ネットにはありませんでした。ねじを外すだけだろうと思い、トライ。まず、刃を外しました。次に、底の部分のネジと、刃の側のネジを外しました。きわぞりの機構部分へのプラスティックの連結部品を外しました。これは、少し強引に、きわぞりのパーツを外し加減に広げて、取り外しました。次に、金属の板を外しました。これで、中の物が、するりと出てきました。バッテリーを新品と交換し、位置ずれ防止のシールを貼りました。後は、逆に、組み立てましたが、プラスティックの連結部品の取り付けには苦労しました。充電し、電源を入れてみると、「おぉ!」。元気な頃の音に戻りました。これなら、替え刃を交換すれば、まだ、数年、使えそうです。
2017.01.13
コメント(0)
-
Arduino 開発環境の構築
私は、開発環境は、パソコンにそのまま構築するのではなく、VMwareを用いて、仮想OSをインストールし、その中に、開発環境を構築しています。こうしておけば、パソコンを新しくした場合、仮想マシンをコピーすれば、すぐに利用することができます。問題は、Windows10の場合で、これは、コピーしてもライセンスの関係で動いてくれません。同じパソコン内で、仮想マシンをコピーしても動かなくなります。(今は、大丈夫でしょうか?)最近は、この関係で、仮想マシンは、Linuxを使うことが多くなっています。今回も、Debianで、開発環境を構築します。Debianならば、ラズベリーパイで、Arduinoの開発を行うことも可能かもしれませんから。Debianは、jessieを使いました。開発ツール(IDE)のインストール$ sudo apt install arduinoこれで済みました。最初、ポートが選べず、考え込みましたが、一度、ログアウトし、ログインし直すことで解決しました。後は、USBケーブルで、arduino uno(互換)をつなぐと動きました。フォントの表示が、いまひとつだったため、.arduino/preference.txtを編集し、editor.antialias=trueeditor.font=TakaoExGothic,plain,12に修正して、使い始めました。Takaoフォントは、パッケージをインストールしました。最近は、Windowsより、Linux系の方が楽です(笑)
2017.01.10
コメント(0)
-

Arduinoをはじめよう
「Arduinoをはじめよう」という本を読みながら、勉強を始めました。Arduinoをはじめよう第3版 [ マッシモ・バンジ ]本は、以前から持っていましたが、今回、Arduinoのキットを購入し、実際に動かしてみようと思っています。キットは、様々なメーカーから出ています。下記のキットが、一番、無難に思いましたが、パーツが豊富だった、互換機のキットを購入しました。スイッチサイエンス Arduinoをはじめようキットまずは、開発ツール(IDE)のインストールのための準備を行っています。開発は、VMwareのゲストOSで行うことにしています。ゲストOSを使うと、一度、セットアップした開発環境を、別のパソコンに容易に移すことができて便利です。OSは、Windowsが無難ですが、別のパソコンに移すことを考えると、windows8.1になります。Windows10は、他のパソコンに移動させるとライセンスの関係で動作しません。できれば、Debianで開発環境を構築できないかと考えています。しばらく、Arduinoの話題が続くと思います。
2017.01.09
コメント(0)
-
電気料をお得に支払う
電気料金をクレジットカードで支払えるようになったため、どれだけ、得になるかを調べてみました。楽天クレジットカードの場合、ポイント還元率が1%です。一方、口座振替の場合、割引が適応されますが、その適応が除外されると、年間648円負担増になります。つまり、年間の支払額が、64,800円を超えていなければ、損をすることになります。この金額を超えていたため、クレジットカード引き落としにする方が得をする計算になりましたが、クレジットカードでの支払いは行わないことにしました。それほど金額に違いがないこともありますが、クレジットカードの有効期限が切れたら、再び、申し込み手続きが必要になる面倒さを嫌いました。
2017.01.08
コメント(0)
-
携帯電話が充電できない
ドコモの携帯電話 P-01G を使っています。いつものように、充電台に設置して、しばらくすると充電が終わっていました。かなり、早く終わったため、不審に思って開いてみると、充電に関して、エラーが発生していました。エラーの内容は、バッテリーが、低温、または、高温になったため、充電を中止したとのこと。おそらく、低温の方でしょう。部屋の温度が、10度を下回ることが珍しくない季節。電子機器の、特に、バッテリーが不調を訴えてきます。メーカーには、もう少し低温に対して耐性のある製品を作ってもらいたいです。
2017.01.06
コメント(0)
-
初夢はいつ?
今の時期に思うのは、初夢とは、いつ見る夢なのか。以前は、2日の夜、3日のかけての夢だと思っていました。最近は、1日の夜、2日にかけてなのでしょうか。正解は分かりませんが、いずれにしても、あまり、意味がない(笑)あいまいなものに一喜一憂するより、確かな物を得たいです。
2017.01.02
コメント(0)
全14件 (14件中 1-14件目)
1