全5875件 (5875件中 1-50件目)
-
教育について(105)自由化が鍵
《「人生の初期に集中し過ぎた学校教育の肥大化」の原因として、「新卒一括採用などの雇用慣行をもつ日本的経営が発展し、そこでは職業生活への入り口いかんが大きな意味をもつ」(第1部第5節の)ようになったことが挙げられている…これはたしかにお役所文書としては新しい指摘である。日本の産業の成功が、学校教育に歪(ひず)みを強制しているというかねてからの私の主張を認めてもらったような気さえしてくる。しかし、ここまで言うのなら、経済の成功因が同時に教育の荒廃因であり、原因は1つだとはっきり言うべきだし、さらに日本的経営に代表される集団社会から、より個人の労働原理に立脚した資格社会、ライセンス社会に向かっていくための法改正等の具体的措置に踏み込んで行くべきであったであろう》(西尾幹二『教育を掴む 論争的討議の中から』(洋泉社)、p. 19) 日本社会は、「落ち零(こぼ)れ」を許さない。先頭集団からの落ち零れは、出世競争からの脱落を意味し、中間集団からの落ち零れは、平凡だが安心できる人生からの落伍(らくご)を意味する。問題は、日本社会は落後した人達の再挑戦を認めないということだ。人生は「一本道」で、一度道を踏み外せば、元には戻れない。 このような単線の人生行路は、日本社会が欧米に追い付き追い越すことを目標としていた時代の名残(なごり)である。が、欧米に追い付き、新たな目標が未だ定まらない時代において求められるのは、様々な環境に対応できる多様な人生行路であるべきだ。 それは、必ずしも「集団」から「個人」へ重心を移すということではない。日本が得意とする「協働」型社会を手放す必要はない。が、これからの時代において、何が評価され、何が必要となるのかが見えない中で、過去に成功した、一点集中、一点突破型の手法は最早通用しないということだけははっきりしている。 戦後日本は、戦時体制に懲(こ)りて「個人」を尊重するという話になった。が、個人を尊重するということと、個人を甘やかすということは同じではない。自由には責任が伴わねばならない。が、戦後日本は、個人を甘やかし、責任感のない個人を生むだけになってしまった。このような個人に社会を牽引できるはずもなく、ただ社会に「自分勝手」が巻き散らすだけとなってしまった。個人の自由が拡大することに反対するわけではない。が、日本人には、個人よりも集団を重んじる方が性に合っているのではないかと思うだけである。 行き先の定まらぬ時代において大事なのは、個人であろうと集団であろうと、目標を固定化しないということだ。如何なる時代が来ようとも、柔軟に対応できる社会が求められるのであり、そのためには、「自由化」が鍵となるということだ。
2024.12.09
コメント(0)
-
教育について(104)教養を軽んずる勿(なか)れ
《教育というと日本では空想めいた甘いイメージばかりで、人間性の暗い側面や社会の発展に逆行する価値に権利を与えるというような考えがそもそもテーマにならない。死への心構えにも、悪の魅力にも、正面から目を向けない。つまり教育は人間性の半分に目をつぶっている。これでは「死ぬ覚悟があるか」という邪教の教祖の端的な問いに抵抗できない》(西尾幹二『教育を掴む 論争的討議の中から』(洋泉社)、p. 3) が、学校における集団教育において、西尾氏の言うような人間性の暗部と向き合うことは無謀と言うしかない。善悪の基準が定まっていない若者に、〈悪の魅力〉など持ち出せば、混乱を来し、収拾がつかなくなってしまうであろうことは容易に想像される。それが、個人ではなく集団であれば尚更(なおさら)だ。 そういうことに対し、一切の免疫を持たずに大人になることは、出来れば避けたいのは山々だ。が、だからといって、安易に「悪」を持ち出して、収拾がつかなくなってしまっては藪蛇でしかない。《加えて、最近の大学改革では一般教育が追放される方向にあり、理科系の大学生にこそ必要な文科系の知性の育成が削られていく一方である。自閉的な今の若者に必要なのは、社会救済への問いではない。それはよく誤解される点である。環境問題も、消費文明の反省も、欲望の滅却も、今の若者にはどれもとおりのいい、心地よい言葉にすぎない。たいせつなのは何を求めるにせよ、歴史の評価に耐える尺度、「真贋(しんがん)」というもう1つの尺度があることを教えることではないか》(同、pp. 3f) 高度成長期の日本人は、物質的豊かさを求め、直(ひた)走ってきた。それは、精神的なものを疎(おろそ)かにしてきたということの裏返しである。その結果、我々は、「実利」に目敏(めざと)く、実用に供しないものを軽視することが習い性(ならいせい)となってしまった。 学生は、実利に結び付くものには飛び付く一方で、「教養」(culture)といった実利に結び付かぬものには見向きもしない。が、利益と直結しないにしても、「教養」は、間接的に利益を得るのに役立っている。それどころか、目の前の利益に汲々としている人間は、長い目で見たより大きな利益をみすみす失ってしまっているということに気が付かない、などと私が言ったところで何の説得力もないのであるが、単に物質的なものだけでなく精神的なものも含めて総合的に考えれば、必ずや教養がある人の方が遥かに「豊かな」人生を送ることが出来るはずだ。
2024.12.08
コメント(0)
-

教育について(103)若者のやる気を殺ぐ既定路線
《今の若者の大半が無気力で、自分に閉じこもり、社会的メッセージを欠いているのはなぜだろうか。オウム真理教に入信した高学歴者の問題は特別なケースではなく、明日どの若者をも襲う目の前の問題である》(西尾幹二『教育を掴む 論争的討議の中から』(洋泉社)、p. 1) 社会には「既定路線」というものがあり、それから食み出たものは、「異端」と見做されてしまう。だから今の若者は、型に嵌ったことしか出来ない「囚(とら)われの身」となってしまっている、詰まり、「自由」がないということだ。《教育に関する限り現代はすでに全体主義体制で、「主体の自由」はない。すべてを計量化し物量化する思考。数と凡庸への屈服。統計学ではじき出された偏差値という科学的数字は、「あなたの未来はわかってしまった」という公的宣言である。これは受験の失敗者を不幸にする制度だから非人間的なのではない。受験の成功者を知らぬ間に無意志、無感動にする点にこそ最大の問題がある。偏差値で未来が決められた有利な人生は、若者にとって生きるに値しない人生だからである。教育が、失敗や過誤を含む生の可能性の量り難い部分に大きく門戸を開いておく余裕を失って、すでに久しい》(同) 教育もまた然(しか)り。既定路線から食み出ることは許されない。この画一的教育が、若者の「やる気」を喪失させていることは今更言うまでもないことだろう。その路線が時代に合ったものであればまだしも、時代は大きく転換しようとしているのだから、教育もまた変更を余儀なくされているに違いない。 が、時代は混迷の中にある。詰まり、これからの時代はこうなるなどという、信じるに値する「予言」などない。だから、様々な環境の変化に対応できるように教育も多様化しなければならない。それが「教育の自由化」ということの意味である。《たとえば、有力大学同士の点数優等生獲得競争が野放しにされている「自由」に、日本の教育がいま必死に考えなければならない課題の1つがあるのではないか。日本の大学は「入口」だけが重視され、入試は無意味な記憶力競争となり、大学の「序列」は明治以来の順序で固定したままで、学問の活性化にとってたいせつな大学間競争を阻害している。同時に高校以下の教育に深刻な圧力を及ぼし、それがついに小学生をも過当競争にまきこむ危険水域を越えている、と第14期中教審で指摘されたほどである。日本の大学だけが、他の国に例のないピラミッド型の多層的序列構造を形づくり、一部の大学に点数優等生が集中する「寡占状態」をなすすべなく放置してきた。この構造は高校以下にも波及している。全国的に序列上位の学校が下位へ向け点数の高い受験生を獲得する自由度が放任されている弱肉強食の法則の貫徹は、他の業種、他の業界にみられない完璧な閉鎖状態を呈し、子どもの世界に理不尽な不自由を強いている。一方の自由は明らかに他方の自由を侵害している。最近は憲法の「信教の自由」の戦後風の扱い方が疑問視されだした時代だが、教育界のこの種の自由も同様なわが国の病理の1つである》(同、p. 2)
2024.12.07
コメント(0)
-
教育について(102)教育の自由化の裏読み
《これまで均質の労働者の「和」によって、すなわち団栗(ドングリ)の背比べによって大量生産システムを成功させてきた日本の企業は、知らず知らずに異能の人間を排除していた。しかし、今や中進国に追われている日本の産業は、今後はいっそう知識集約型産業に転身していく必要がある。そのためには、異能の人間を救い出し、育て、その独創力を活用しなくてはならないであろう。学校教育もまた、巨人=天才を産み出すような、画一性や平等主義を排した環境に自らを改めて行かなくてはならない》(西尾幹二『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 168) 成程、これからは、〈異能の人間〉を大切にしなければならない。だから、これまでのような〈異能の人間〉を抑え込んだり、排除したりするようなことは慎まねばならない。が、それを一足飛びに〈異能の人間を救い出し、育て、その独創力を活用しなくてはならない〉とまで言うと言いすぎであろうと思われる。 〈異能の人間〉を排除しないとは、画一的な教育を改めるということであり、教育の自由化ということである。が、〈異能の人間〉を育てるとまで言うと、そのことが目的化され、逆に不自由な教育になりかねないのである。詰まり、教育の自由化とは、「画一からの自由」であって、それを飛び越えて新たな「画一」を生むような「設計主義」的なやり方ではないということだ。《(3)は「自由化」論者がこれまでロを緘(かん)して決して言わなかった、隠された最も重要な動機である。彼らは「学校選択の自由」を義務教育段階にまで求めていた。今度の答申でもまだ義務教育にかかわる許認可や規制の見直しの項目を残している(第2部8の(1))。この意味する処(ところ)は、私立の小中学校を自由に多数作らせる(塾を公認学校にする等も含む)。そして余裕のある親は子弟をそこへどんどん入れれば良いではないか。公立小中学校が質的低下を来しても構わない。階層分化が激しくなっても構わない。国民の統合が毀損してもいっこう構わない。これの狙いとする処は、誰にも一目瞭然と思うが、教育予算の公費削減である。義務教育の公費を大幅に余裕のある親に肩代りさせることである。一口でいえば行革路線であって、中曽根内閣が行財政改革の一環として教育改革を企てていた本当の狙いはこの一点にあったのではないか》(同、p. 169)という話の根拠は何か。根拠を示さなければ只の西尾氏の邪推にしかならない。 また、教育の自由化が副次的に教育予算の削減にもなるという話と、教育予算を削減するために教育を自由化しようとするのでは意味合いがまったく異なってくる。教育の自由化論者が、口を緘さなければならないとすれば、後者の話となるが、なんともせせこましい話だ。本当に中曽根首相(当時)はそんなせこいことを考えていたのだろうか。
2024.12.06
コメント(0)
-
教育について(101)教育の自由化論が出て来た背景
西尾氏は、教育の自由化論が出て来た背景には、経済界が将来の日本に危機感を抱いているからだと推察する。《まず青年層に熱気(aspiration)がなくなってきたことだ。与えられたこと以外しない青年が多い。やる気の喪失、モチべーション(興味を起こさせること)の消滅が、やがて日本経済の成長の鈍化につながるだろう、との怖れが発生した。財界人からみると今の子供はどうしようもない。いったい学校の教師は何をしているのか、と苛々(いらいら)して見ている。企業同士の活溌な競争によって日本経済は成功した筈(はず)だ。あの遣り方(やりかた)を学校に適用すべきである、と彼らは考える。ぼやぼやしている教師、たるんでいる学校をなくせば、子供たちのやる気は取り戻せるだろう、と》(西尾幹二『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 167) が、青年のモチべーションの喪失はいわば世界的傾向であって、日本だけの問題ではないと西尾氏は言う。《精神的権威が消滅し神秘が不在となり人間が無感動となった現代の地球文明の状況と、切っても切り離せない。視野が鎖(とざ)されていたとき人間は強かった。情報の拡大が地球を透明にしていくこの時代に、情熱の高揚は難しい》(同、p. 168) 青年に活力が失われているというのはその通りだろうし、このことに対する西尾氏の哲学的な意見に異を唱える気もない。が、経済界は、西尾氏が推察するような危機感を抱いているのだろうか。経済界は、むしろ教育は入社してから自分たちが行うから、大学で変な色を付けないで欲しいという姿勢だったはずだ。にもかかわらず、今度は教育を改革せよというのでは、あまりにも勝手すぎるだろう。だとすれば、教育の自由化の話は、経済界から出て来たとは考えにくいということだ。《これまで均質の労働者の「和」によって、すなわち団栗(ドングリ)の背比べによって大量生産システムを成功させてきた日本の企業は、知らず知らずに異能の人間を排除していた。しかし、今や中進国に追われている日本の産業は、今後はいっそう知識集約型産業に転身していく必要がある》(同) 正解のある時代から、正解のない時代へと時代が移り変わろうとしているのであるから、次代を担う若者に求められる能力も自ずと異なってくる。例えば、正解のある時代は、〈和〉こそが重要であったが、正解のない時代には、むしろ〈和〉から食(は)み出ることが必要となり重要となる。だから、教育も変わらなければならないというのはその通りである。
2024.12.05
コメント(0)
-
教育について(100)対症療法
《戦後、進学の量的拡大だけを自画自讃してきた文部行政も、この点に強い懐疑と改革意図を抱いたことはなかった。欧米の学問や技術をコピーしていた久しい期間、日本の大学や研究機関でも、組織からはみ出た異能の才の、ある種の貴族的遊戯精神を尊重する気風は存在しなかった。これなくして、独創的発見も、学問の其の発展も望めないのだが、学校や大学は非難される通り、「ドングリ」に順番をつけることしかなし得ないで来た。そして自動的にその順番の上位の者が特権を享受する不毛の構造に、怨嗟(えんさ)の声だけでなく、近年では能率と創造の見地からも疑問の声が上ったのである。 それが教育改革の原点であったはずだ》(西尾幹二『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 151) 日本は、集団から食(は)み出ることを許さない非寛容な社会ということなのか。日本人は、農耕民族であるから、集団主義的気質が有ると言われればそうだとも思われる。が、過ぎたるは及ばざるが如(ごと)しで、集団主義に過ぎ、個人の自由が抑圧されては、集団が不活性に陥ってしまうに違いない。それではその集団は生き残れない。《答申の第2部が抽象的なお題目の羅列、第2部が委員の力量を越えた大風呂敷の開帳に終わり、教育改革のあの原点は何処へ行ってしまったのかと私は不思議に思う。私が理解している原点とは、「ドングリ」の背比べに代る異色異能な人材の育成、世界に寄与できる独創的な才能の発掘、といった方向が1つある。次いで、後期中等教育までがほぼ義務となっている現状の中で、学校は抑圧機構と化し、閉塞感と不公平感が急速に拡がっている。受験競争、いじめ、校内暴力に代表される病理現象の打開が、求められているもう1つの方向である》(同、p. 155) 西尾氏は、問題に対し直接働き掛ける方途を考えておられるのに対し、私は、間接的に対応すべきだと考える。その理由は、そもそも何がどう問題なのかを見抜けるほど優れた洞察力が私にはないし、見抜けたとしても、その対策がどのような副作用を生じるのかが分からないからである。譬えて言えば、副作用が出るかもしれない薬で治そうとするよりも体質改善こそ考えるべきなのではないかという立場である。詰まり、個々の問題に対処しようとするのではなく、教育環境こそ改めるべきだという立場である。《前者が長期的ヴィジョンを要する、息の長い国民性の変化の中で徐々に達成されるべき目的なら、後者は対症療法をさえ要する緊急課題である。前者の目的の性急な推進は、往々にして後者の病理を拡大し、それに復讐されて、前者の目的達成さえじつは覚束(おぼつか)なくなる、ということを私は今までに幾度も書いてきた。外見的に相反しているこの2方向の病理はじつは同一の原因に発しているものの、後者の現実は前者の理想より、全包囲的作用を及ぼす威力を持っているからである。いつの時代にも理想より現実が強い。「個性の重視」はたしかに2方向の解決のどちらにも通じる、運用いかんで有効な理念には違いないのだが、残念ながら現段階では単なるスローガンの域を出ない》(同) 私が言っているのは、時間の掛け方の問題ではないのだが、恐らく私のような曖昧な改革案では、〈スローガンの域〉にも達さないと一蹴(いっしゅう)されてしまうのであろう。
2024.12.04
コメント(0)
-
教育について(99)日本型「和」の社会
《1975年頃から今日までに、何かと教育の病理が取沙汰され、政治問題化して来たのは、学校教育と社会運営の効率とがうまく噛み合わず、軋(きし)みが生じて来たからに相違ない。個人にとっては教育が抑圧機構として意識され、閉塞感と不公平感が激増した。日本型「和」の社会とは適度な無駄を許容する点において一見人間的に見えるのだが、じつは個性やロマン的情熱をじわじわと吸い取って、人間を小型化し、勇気を阻喪(そそう)させる独特な効率化社会である。特殊な才能を持つ人間、異能の人間を排除してしまう社会でもある。日本の学校組織はただひたすらそれに奉仕する機関にすぎなかった》(西尾幹二『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、pp. 150f) 日本型「和」の社会は、〈個性やロマン的情熱をじわじわと吸い取って、人間を小型化し、勇気を阻喪させる〉と言うのだが、果たしてそうか。有子曰。礼之用。和為貴。先王之道斯為美。小大由之。有所不行。知和而和。不以礼節之。亦不可行也。【学而第一】(有子曰く、礼の用は和を以て貴しとなす。先王の道斯れを美となし、小大之による。行はれざる所あり。和を知つて和するも、礼を以て之れを節せざれば亦行ふべからざる也。) 茲(ここ)に有子が曰(い)はるゝ「礼」とは、普通の言葉に於ける「礼」と其意味を異にし、頗(すこぶ)る広い意義の礼を指したもので、そのうちには礼記(らいき)にある礼を総(すべ)て含んでるものと見るべきである。随(したが)つて、この句にある「礼」の一字中には周の刑制のことも亦(また)含蓄(がんちく)せられてあるのだが、礼の精神が和にあるのを忘れては礼が礼にならず、却(かえっ)て之がお互に疎隔(そかく)する原因になつてしまふものである。刑の根本なぞに於(おい)ても、和を以(もっ)て精神とし、之を執(と)り行ふことにせねばならぬものである。然(しか)し又、和が余りに過ぎると互に狎(な)れて却て不和となり、世の中の秩序を紊(みだ)すことにもなるから、そこは礼を以て之を節して参らねばならぬもので中庸を得たるところに真の和が在るのである。― 澁澤榮一 デジタル版「実験論語処世談」(2):12. 礼と和とは如何 詰まり、「礼」と「和」は、一方に偏することなく平衡することこそが重要だということである。 仮に、西尾氏の言うような「和」の弊害が見られるとすれば、それはむしろ戦前までの文化を否定する戦後日本が「和を以て尊しと為す」文化を破壊し、「平和主義」に侵(おか)されてしまったことによるものではないかと私には思われるのだ。
2024.12.03
コメント(0)
-

教育について(98)官僚支配
《官僚制化は、(正常な、歴史的にも正常であると証明される傾向からいえば)身分的平準化をおこなうのであるが、逆に、どのような社会的平準化も、官僚制化を促進することになる。それは、行政手段や行政権力の専有による身分的支配者を排除し、また、財産があるために「名誉職的」ないしは「兼職的」な行政にあずかる資格のある官職保持者を、「平等」の見地から排除することによっておこなわれる。このような官僚制化は、すすみゆく「大衆民主制」にいつもつきまとう影なのである》(マックス・ウェーバー『権力と支配』(講談社学術文庫)濱島朗訳、p. 50) 官僚主義と平等主義は、ある意味、表裏一体のものなのだ。敗戦後、フランス革命に倣(なら)って、「平等」という観念が日本に導入された。平等が絶対ということになると、「自由」は生きられない。詰まり、平等主義社会においては、自由は制限され抑圧されるということだ。《近代国家において支配が現実に力を発揮するのは、議会の演説でもなく、君主の宣言でもない。日常生活における行政の執行が現実の力なのであるから、この支配は、必然約・不可避的に、文武の官僚の掌握するとなる》(マックス・ウェーバー「新秩序ドイツの議会と政府」中村貞二・山田高生訳:『世界の大思想29 ウェーバー 政治・社会論集』(河出書房新社)、p. 319) 近代化された国家において、国家を支配するのは「官僚」だということだ。《中世以来の資本主義への進歩といわれるものが経済の近代化を見定める一義的な尺度であるのと同様に、官僚制への進歩、すなわち任命・俸給(ほうきゅう)・恩給・昇進・専門的訓練と分業・明確な権限・文書主義・上下の階層的秩序などに基づく官僚制への進歩というものが、君主制国家であれ、民主制国家であれ、およそ国家の近代化を見定める一義的な尺度なのである》(同) 尚(なお)、「文書主義」という訳語が独り歩きしているしているが、原語Aktenmäßigkeitとは「文書の正確性」ということだ。Grundsatz der AktenmäßigkeitUnter dem Grundsatz der Aktenmäßigkeit (auch: Grundsatz der Schriftlichkeit) versteht man ein klassisches Prinzip einer Bürokratie, demzufolge Stand und Entwicklung eines Vorganges bzw. einer Angelegenheit stets aus den Akten (elektronisch oder in Papierform geführt) hervorgehen müssen. Der Grundsatz der Aktenmäßigkeit soll insb. die Kontrollierbarkeit der Verwaltungstätigkeit sicherstellen.― https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-grundsatz-der-aktenmaessigkeit.html文書の正確性の原則文書の正確性の原則 (書面の原則ともいう) は、古典的官僚主義の原則であり、これによれば、過程や事項の状況と展開は、常に(電子または紙の形式で保持される)文書に示されなければなりません。記録の正確性の原則は、特に管理活動を確実に監視できるようにすることを目的としています。《絶対主義国家とまったく同様に、民主政体もまた、任命される官吏(かんり)のために、封建的・家産的・都市貴族的.その他名誉職的にあるいは世襲的に、職務を行なう名望家行政を排除していく。任命された官吏が、われわれのあらゆる日常的な要求や苦情について、決定を下すようになる》(ウェーバー、同) 平等主義は、観念的「正義」を御旗(みはた)にして、文化伝統を破壊していく側面がある。そして官僚が国家を支配することになるのだ。
2024.12.02
コメント(0)
-

教育について(97)日本の官僚主義化
《日本は中流階級の社会だといわれるが、戦後も40年経つと中流の中の階層化が進み、社会全体の構造分化がいわば固定してくる》(西尾幹二「なぜ第一次答申は無内容に終わったか」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 150) 〈中流の中の階層化〉などどこにあると言うのか。成程、富裕層の子供は、教育に掛けるお金の余裕があるので、お金を掛けて一流の大学に入る。つまり、金持ちの子供は金持ちになるという富裕層の固定化現象が進んでいる。が、中流層の人達にはそのようなものはない。ただの西尾氏の妄想だ。《これは別言すれば、個人にとって上昇移動が止まり、どう努力しても越えられない壁を知って、やる気をなくしてしまう青年が殖えてくるということでもある》(同) 〈どう努力しても越えられない壁〉って何だ。学歴社会にそんなものはない。有りもしない壁の存在を知って、やる気をなくす青年など勿論いない。《受験管理が徹底して、偏差値がいくつならこの程度の学校へ行けと各人の序列が外から定められる傾向と並行して、国家社会全体の官僚主義化、余計者の排除、効率一点ばりのいわゆる管理社会の完成度が進む》(同) マックス・ウェーバーは言う。《官僚制的行政は、知識による支配を意味する。これこそは、官僚制に特有な合理的根本特徴なのである。専門知識に由来する強大な権力的地位にとどまらず、官僚制(または、それを利用する首長)は、職務上の知識、すなわち、職務上の交渉をつうじて獲得されるか、「文書に精通した」実務知識によって、その勢力をさらにいっそう増大させようとする傾向がある。「職務上の秘密」――その専門知識にたいする関係は、技術的知識にたいする商業経営上の秘密に、ほぼ匹敵する――という概念は、唯一のといえないまでも、とにかく官僚制に特有な概念であるが、それは、このような勢力をえようとする努力に由来するのである》(マックス・ウェーバー『権力と支配』(講談社学術文庫)濱嶋朗訳、p. 48) 官僚主義とは、〈知識による支配〉ということだから、成績上位の学生たちは、将来支配者になることを夢見て、知識を詰め込むことに血道を上げてきたのだ。日本の官僚制と知識詰込み教育は、その軌(き)を一(いつ)にしているのだ。《知識、つまり、専門知識や実務知識の点で、官僚制よりもまさっているのは、自己の利害にかんする範囲内では、おおむね、私的な営利に利害関係をもつ人、したがって、資本主義的企業者だけであるにすぎない。かれこそは、官僚制的・合理的な知識の支配の不可避性にたいして、実際上(すくなくとも相対的に)免疫性をもった唯一の機関なのである。それ以外の人びとは、すべて、大量成員団体のなかでは、官僚制的な支配に従属することを余儀なくされるのであって、それはちょうど、財貨の大量生産において、没主観的な精密機械の支配に従属することを余儀なくされるのと、まったくことなるところはない》(同、pp. 48f)
2024.12.01
コメント(0)
-
教育について(96)学歴主義の人材採用を改めることが必須
《西尾 非常に難しいのは、学校間「格差」と偏差値支配の発生原因はもっと根が深く、歴史的背景があり、社会全体の画一化の代替作用という意味合いがあると考えられることです。日本では古くから人種や言語が1つであるし、明治以来単線型教育制度が近代化の成功に大きな役割を果たしました。また、戦後は農地改革で地主階級がなくなり、華族制度も撤廃してしまったために、おそるべき画一的な社会になりました。その分だけ学校に微妙な差別の構造が入ってきたと思います。つまり学校間「格差」は身分差別の代償行為です。企業だけでなく、社会全体がダイナミックな多様性をはらんだ構造にならない限り、子どもの側に競争が押しつけられるこのスタイルを変えることは、ちょっと難しいんじゃないかと思うんですが》(西尾幹二『教育を掴む』(洋泉社)、p. 44)という西尾氏の「格差」の分析には直接触れず、天谷氏は次のように返した。私も西尾氏の分析にはかなり偏見めいたものを感じるので、天谷氏のこの態度は賢明であったと思う。西尾氏の分析を否定したところで、建設的な議論になろうとは思えないからである。《天谷 企業が変わるかということについては、私はそれほど悲観的じゃないんですね。企業は、世の中の変化に対する適応を誤れば自分の生き死ににかかわることをよく知っております。だから、これから企業が人間を採用する場合に、もっと個性を尊重して、一芸に秀でた者とか、あるいは伝統、常識、既成概念からはずれたような者に価値を認める方向に、変わって行くと思っていますね》(同、pp. 44f) 私も天谷氏の楽観論に賛同したいところではあるが、が、果たして企業は世の中の変化に柔軟に対応できるのか、正直不安な面もある。1つは政府の甘やかしにある。自由社会においては、経営がうまく行かない企業は自助努力によって立て直しを図るのが筋である。が、日本の企業は、すぐ政府を頼ろうとする。また、政府も、大企業が潰れては社会に失業者が溢(あふ)れてしまうからと、例えば、エコロジーに託(かこ)けて、やれ「エコカー減税」だの「エコポイント」だのと、斜陽産業に安易に税金を突っ込み勝ちである。これでは企業の本質的新陳代謝は図(はか)れない。 GDP(国民総生産)が、シナに抜かれ、ドイツに抜かれ、さらにはインドに抜かれ、世界第5位に転落せんとしているのは、根本的には日本企業の自助努力不足であろう。世界に置いて行かれないようにするには、企業がこれまでの成功体験に胡坐(あぐら)をかくのではなく、「物づくり」から「価値づくり」への転換を円滑(seamless)に行うべく、学歴主義の人材採用を改めることもまた必須なのではないかと思われる。
2024.11.30
コメント(0)
-
教育について(95)設計主義的改革
《西尾 天谷さんは抜本的見直しをなさるとおっしゃるけれども、この抜本的という言葉が、私には非常に幻想的に聞こえる。もし抜本的にお直しになるとするなら、臨教審は法的な強制力を企業サイドに発揮できるとでもお考えになっているのでしょうか。天谷 企業の人事方針に対して法的強制力をもって政府が干渉するなどということはまったくできないし、するべきではないと思います。西尾 では、抜本的という言葉をなぜ用いたのですか。できもしないことをあたかも目ざましくできるかのようにいうのは無責任ではありませんか。天谷 我々にできることは、企業なり大学なりの意識が少しずつ変わるように呼びかけるというだけなんですね。抜本的というのは、「大幅に変えてくれ」という要望を言っているだけです。第一部会は総論的な部分をやる役割で、それをどの程度具体化できるかは、第三部会とか第四部会の各論で検討してもらわなきゃいけない。いくら検討したところで、独裁的政府じゃありませんから、政府のできることには限度があります。しかし、権限がないから黙っているのでは社会の変革はありませんから、政府としてはこういう方向にいってくださいと企業やジャーナリズムに呼びかけ、世論もそういう呼びかけをする。それによって企業もだんだん軌道を修正していく。それが民主主義社会の物事の進み方でしょう》(西尾幹二『教育を掴む』(洋泉社)、pp. 41f) 〈抜本的見直し〉という言葉には、絶対的に見直さなければならないという意味もなければ、強制的にでも見直させるという意味合いもない。どうして西尾氏がこのように天谷氏に絡むのかが分からない。私は、抜本的に見直すべきだという提言自体に問題があるとは思わない。また、法的強制力をもって政府が企業に干渉すべきでない、臨教審に出来ることは、〈企業なり大学なりの意識が少しずつ変わるように呼びかけるというだけ〉という天谷氏の応答も妥当である。問題は、その後である。 天谷氏は、〈権限がないから黙っているのでは社会の変革はありません〉と言う。が、このような考え方は、設計主義的である。成程、強制力はない。が、方向性は示すというのは、知の過信のように思われるのだ。 社会変革は、誰かが作った工程表に基づいて行われるものなのか。社会が変わるということと、社会を変えるということは同じではない。だから、私は、〈政府としてはこういう方向にいってくださいと企業やジャーナリズムに呼びかけ、世論もそういう呼びかけをする〉というようなやり方には賛同できない。 呼び掛けに応じて〈企業もだんだん軌道を修正していく〉というのは、自由主義の考え方とは相容(あいい)れない。〈それが民主主義社会の物事の進み方〉というのは、社会主義的考え方でしかない。
2024.11.29
コメント(0)
-
教育について(94)「知価革命」の時代
《天野 企業は採用の基準を変えなければならないと思います。かつての帝国陸軍や帝国海軍では、陸軍大学や海軍兵学校での成績の序列が一生を支配しました。徹底した学歴主義を採っていました。戦後の日本は学歴主義を引き継いで、大企業の人事部は今にいたるまで人事判断の尺度を大学に依存してきたわけです。これに対応して、日本の大学は大企業の下請けになり、「ドングリ」に順番をつけることが任務みたいになってしまった。過去はそれでよかったかもしれないけど、今後は企業も大学とともに、まずそこを直していかなければいけない》(西尾幹二『教育を掴む』(洋泉社)、pp. 40f) 自由主義的に言えば、企業は、これまでのような学歴主義の人事採用を改めなければ、時代に遅れ、衰退するだろうということだ。端的な例は、「白物家電」と呼ばれるものである。これまではテレビならテレビ、冷蔵庫なら冷蔵庫を作ればよかった。が、それらは一定家庭に行き渡ってしまった。 これからは、単なるテレビでは駄目で、テレビにどのような機能が付いているのかが問われる時代になったということだ。堺屋太一流に言えば、「知価革命の時代」なのだ。物自体の価値よりも、物に付属する価値、すなわち「付加価値」こそが重要となったということだ。 従来のように、出来るだけ多くの知識を詰め込み、これを再生することは、あまり意味がなく、感性や発想が問われる時代となったのだ。教育も時代と共に変わらなければならない。「頭が良い」人作りから、「感受性」が豊かで、「創造性」の高い人材をいかに作り出すのかが問われるようになったということだ。《西尾 天谷さんは朝日新聞の2月17日(1985年)の欄で「小中学校にいかない子どもがいたっていいではないか」というお話をなさっています。原理的には私も共感します。しかしきちんとした経歴を要求するのも企業社会なんですね。現に日本の企業では、30歳で大学を卒業した者を大学卒として認めないという非常におかしな慣行があります。欧米社会では、25から30歳で大学を卒業した者が大学卒の3分の1ぐらいいます。つまり自由な青年の企業外活動を企業が尊重するという態度があるんですね。このように上部構造が緩むことによって、小学校での自由なスタイルの生きかたも可能になるのです。企業社会が改まらなければ、小学校・中学校の「自由化」だってできません。ところが今の日本の企業には、採用して自社の好みの人材に育てるので、外からよけいな知識を持ってきた人間は邪魔だ、という意識があまりにも強い》(同、p. 41) 果たして学歴重視の大企業が変わらない限り、教育改革も進まないのか、あるいは、進めるべきではないのか。が、大企業に入ることが「勝ち組」という時代はそろそろ幕を閉じるのではないか。「付加価値」は、企業規模の制約を受けにくい。お金を掛ければ高付加価値が生み出せるというわけではない。また、必ずしも高学歴を有(も)った人材が、「知価革命」の時代を切り拓いていくわけでもない。
2024.11.28
コメント(0)
-

教育について(93)社会転換による教育転換の必要
ここからは、『中央公論』(1985年4月号)紙上の西尾幹二氏と天野直弘氏の対談を検討しよう。《西尾 小・中学に落第も飛び級もない能力平等主義は私もうっとうしいと思いますが、しかしこれは企業の側の年功序列を尊重し労働者の心情的一体化を図るという構造と表裏の関係にある》(西尾幹二・天野直弘「対談 未来志向か、現実主義か」:西尾幹二『教育を掴む 論争的討議の中から』(洋泉社)、p. 36) この西尾氏の指摘は重要であろう。日本の義務教育には「落第」はない。日本のように、学校への入学、学校からの卒業、会社への就職と年齢が一致するような中で、「落第」させることは、それだけで社会から落ち零(こぼ)れることを意味する。だから簡単に落第させるわけにはいかないのだ。逆に「飛び級」させるのも、年齢と学年の関係がずれるので、その後の社会の受け皿の用意が整っておらず、社会から厄介者扱いされかねないのである。詰まり、「落第」や「飛び級」といったものを行うためには、社会全体の受け入れ態勢の変更が必要となる。また、根本的に、日本社会全体が「年功序列」的な考え方を脱却することが望まれるということになるが、これがなかなかどうして難しい。《天谷 私は今までの画一主義的教育は、20世紀後半における日本の経済復興に非常に大きな貢献をしたという評価をしています。日本がキャッチアップしなければならない段階におきましては、画一均質な教育を受けた労働者を学校が大量に生産し供給することを企業は歓迎しておった。TQCが非常にうまくいったことは、日本の労働者が均質な教育を受け、均質な能力を持っておったということと密接に相関しています》(同、p. 40)※TQC=Total Quality Control(全社的品質管理) このように天谷氏は、欧米に追い付け追い越せの時代においては、画一的で均質的な教育はそれなりに有効であったと評価する。《天谷 今日の大問題は20世紀の成功が、21世紀の成功につながるのであろうかということです。「失敗は成功のもと」というが、逆に成功は失敗のもととなりやすい。そこを日本の企業は深く考えて、戦略を変えていかなければならない》(同) 「驕る平家は久しからず」という抽象的な戒(いまし)めも大事なのだが、具体的に言えば、欧米を模範とした遣り方では今後は成り立たないという認識が必要だということだ。社会は、農耕の時代から工業の時代を経て情報の時代へと重心を移して来た。換言すれば、物質的豊かさが飽和し、新たな時代が到来するであろうことを予感させるのだ。《「知価」が重要な役割を果すような社会――「知価社会」は、工業社会の延長上にある「高度社会」などではなく、工業社会とは全く別の「新社会」なのである。 今、この1980年代に、日本で、そして世界の先進諸国(とりわけアメリカ)で起っている変革は、単なる技術革新でもなければ、一時的な流行でもない。それは、産業革命以来200年振りに人類が迎えた「新社会」を生み出す大変革、いわば「知価革命」なのである》(堺屋太一『「知価革命」 工業社会が終わる 知価社会が始まる』(PHP)、p. 222)
2024.11.27
コメント(0)
-
教育について(92)平等は思考停止の呪文
《文部省は戦後、雲霞(うんか)のように増殖しつづける縦並びの競争の惹(ひ)き起こす恐しい結果について、完全に予測を誤り、「平等」という美名の下に、進学率急上昇の動きにただただ迎合してきた》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 121) 「平等」など美名でも何ともない。「平等」は、人々の思考を停止させるただの呪文だ。平等であろうとすれば、秀でたものは刈り取られ、出る杭は打たれ、結果、社会の推進力が失われていく。日本の教育もまさにそうだ。《文部行政の無方針拡大政策こそ、今日の教育荒廃をもたらした最大の原因であると、敢えて私は書き添えておくが、しかし学校数を殖やし、あらゆる大学.高校を互いに同資格とする平等主義に加担してきた点では、日教組も経済界も等しく共同責任があり、文部省だけを責めるわけにもいかない。経済の高度成長は、教育の大衆化路線、すなわち平等主義のこの果てしなき単一競争のお蔭を蒙(こおむ)っているからである。国民もまた進学率上昇路線を支持していたのである》(同) 明治以降の日本の教育が欧米に追い付け追い越せの1点突破を図った画一主義と、戦後日本に顕著な、マルクス主義的平等主義は、分けて考えるべきだろう。画一主義は、時代の役目を終えた。が、社会に平等主義が蔓延(はびこ)っている限り、画一的教育は改まらない。問題は、戦後日本を蝕(むしば)む平等主義に如何にして風穴を開けるのかということだ。《日本企業の強さをなす要因が、個性や癖の少い均質な労働者の組織内協調を前提とした競争によると考えられるとすれば、まさにこれこそ、職業高校よりも普通高校へと殺到し、またどんなユニークな私立大学をも縦並びの一直線上に位置づけてしまう相互同一化感情の強さと、基底を共通にしていると言わなくてはならない》(同) 時代は、「重厚長大」から「軽薄短小」へと移っていく。人材に求められる能力も、「決められたことを決められた通りに行う」ことから、「如何に工夫するか」が問われることとなる。言うまでもないが、〈工夫〉とは自己満足ではない。対象に受け入れられてこその〈工夫〉である。そこには対象認識能力が必要であり、如何にすれば対象の評価が得られるのかを考えなければならないという意味で高度な能力が必要となる。詰まり、これからの時代は、「物」そのものよりも「価値」を如何に生み出すかが問われるようになるだろうということだ。だからこそ教育が画一的であっては困るのだ。《経済と教育とは戦後日本においては双生児である。前者は成績のいい優等生で、つい兄貴面をしたがるが、弟が不良でなくなったら一番困るのは兄貴の方である》(同)
2024.11.26
コメント(0)
-
教育について(91)教育の脱画一化は時代の要請
《日本の教育組織が明治5年の学制公布以来、単線型であったからこういう帰結を招いたのだろうか。それとも、もともと日本人の相互同一化感情(コンフォーミティ)が強いために、単線型教育制度――武士の子も町人の子も一緒に教育し、士族のための特別学校を作らなかった単線型の持つ開放性が、日本の近代化推進に役立った、という別の面もある――が、欧州諸国と違って、19世紀後半にしごくあっさりと創られてしまったのだろうか》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 120) 日本の教育が画一的になったのは、欧米に植民地化されないように、いかにして富国強兵するかが唯一最大の課題だったからである。《それは鶏が先か卵が先かの問題であって一概には言えない。が、いずれにしても、他人と同じ存在であろうとする日本人の競争心理(ないしは競争回避心理)は、平等が進めば進むほど、横に広がって価値の多様化をもたらすのではなく、同一路線に縦に並んで競い合う結果、「格差」をますます大きくするという傾向がある。戦後において高校や大学の数が殖えれば殖えるほど、学校間の「格差」が広がり競争が激化するという、経済の需要供給の関係では説明のつかない事態を招いたのも、この特殊な日本的競争の力学が作用している結果である》(同) 1980年代には、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と呼ばれるまでの経済大国となり、「欧米に追い付け追い越せ」という目標は一旦達成された。次代の日本に求められるのは、世界を先導する形で、自ら課題を設定し、答えを出すことであろう。そのためには、これまでのような画一的教育では用を足さないのだ。 これからの世の中で何が大事なのか、何が必要なのかについて、確かなことは誰にも分からない。だから、様々な環境の変化に対応できるように、教育は多様化されるべきなのである。努力したが無駄だったということもあり得るだろう。が、そのような無駄を引き受ける覚悟が世界の先進国たる日本に必要なのではないか。 勿論、誰かを先に行かせて、結果を見て方向性を決めるということは可能である。問題は、そのようなやり方を世界はどう見るかということである。日本に、先進国としての矜持(きょうじ)があるのなら、たとえ無駄になろうとも、世界の指導者としての責務を果たすべきではないか。無駄なことはしないという後ろ向きな国を、果たして世界は指導者として認めるだろうか。 が、無駄のすべてが無駄なのではない。実際に社会の役に立たなくとも、その努力は決して無駄ではない。無駄な努力も、必ずどこかで生きてくるに違いないということだ。
2024.11.25
コメント(0)
-
教育について(90)競争社会と非競争社会
《私は競争を大人の社会が避け、子供に押しつけていると言ったけれど、じつは心理的微妙さに即してみるなら、子供たちも本当は競争しているとは言えないのではないだろうか。そういうもう1つの問題があるのだ。高校進学率94パーセント、4年制大学の数461校という現実をよく考えてみて頂きたい。本当に勉強したいから進学するのではもはやあるまい。他人より抜きん出るためではなく、他人と同じような資格を得たいがために進学熱が高まっているのが一椴的な実情だが、そもそも他人と同じような存在でありたいと思うのは競争心理では決してなく、むしろ競争回避心理である。高校卒あるいは大学卒という「属性」を外されることを怖れ、言い換えれば「個人」の競争を避け、高校卒もしくは大学卒という集団性の内部に身を隠し安心したいがために、学校へ、学校へと殺到し、その揚句、学校を激しい競争の舞台にするというばかげた逆の事態を招いてしまったのである》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、pp. 119f) 高校へ進学できるかどうかは、社会から「落ち零(こぼ)れる」かどうかの第一関門だという日本人独特の集団心理が強いということなのだろう。が、落ち零れないように、集団に付いて行こうとすることを「競争」とは呼べないだろう。上位校目指して競争している受験生はごく一部であり、大半は落ち零れないように周りを見ながら最低限の努力を欠かさないだけである。《他人と違う存在であろうとする競争は共存共栄を可能にするが、他人と同じ存在であろうとする競争は、序列化した同一路線上での優勝劣敗の可能性をしか残さない》(同、p. 120) 前者は、因果関係が逆であろう。他人と違う存在であろうとする競争が共存共栄を可能にするのではなく、個々バラバラであっても共存共栄できる社会だからこそ、個人間競争も可能となるということなのではないだろうか。日本のような集団社会では、集団の輪を搔き乱すような行動は慎まねばならないから、個人間の競争は避けられる。詰まり、社会構造が先に在って、競争が行われるかどうかが決まるということだ。 一方、後者の〈他人と同じ存在であろうとする競争〉は「競争」ではない。集団社会の日本にも、集団から上に抜け出ようとする「競争」は存在するが、例外的なものである(だからこそこの競争は激化するのではあるが)。 また、西尾氏は、恐らく「学歴」のことを指して、〈序列化した同一路線上での優勝劣敗〉と言っておられるのだろう。が、「一億総中流」とまで呼ばれた非競争社会日本には、基本的に「優勝劣敗」のような考え方はない。それは、集団から抜け出たエリート層に顕著な問題だと思われる。
2024.11.24
コメント(0)
-

教育について(89)和と競争
《もし仮りに、日本人が他人と違う存在になろうとして競争し合う性格が強ければ、微妙な差別であるとはいえ、それが豊かな多様性に発展することがあり得たろう。農業高校に行くことは劣等感にならず、ユニークな私立大学は序列の外に立つことで繁昌しただろう。なぜ、今農業高校は底辺高校と言われるようになり、早稲田や慶応はますます東大に構造的に似た官僚輩出型の大学になっていくのだろうか。私は「画一性」という言葉は陳腐なのでもう使いたくないけれども、まさに画一性こそ教育の病理の行き着いた帰結であり、困り果てた今日の学校の姿である》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 119) 教育の画一性の問題は、主として義務教育のものであり、農業高校や大学とは論点が異なる。小中学校は、通学区域が定められており、通学する学校を選択する余地は基本的にない。そのため、学校ごとの格差があってはならないために、施設も教育課程も同一のものでなければならない。このため「画一的」とならざるを得ないのだ。一方、高校や大学には通学区域という制約がない。したがって、他の学校と中身を揃える必要がない。詰まり、画一的である必要がない。 高校や大学における画一性の問題があるとすれば、日本を覆う「平等主義」によるものだと思われる。戦後日本人は、「平等」こそが絶対的だと刷り込まれているので、半ば自動的に「格差」を悪と見做し、「競争」を忌避する思考回路が出来上がってしまっているのだ。 また、聖徳太子の「17条の憲法」に、1に曰(い)わく、和を以(も)って貴(とうと)しとなし、とあるので、和を乱す行為は御法度(ごはっと)とばかりに、競争を否定するものもいるだろう。が、これは誤解であって、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。と続くように、太子は、「反抗しないようにせよ」と言っているだけである。競争は反抗ではない。 出典とされる『論語』も競争を否定していないどころか、和を過剰に求めることの非を説いている。有子曰(い)はく、礼の用は和を貴しとなす、先王の道、これを美となす。小大之に由る。行はれざる所あり、和を知って和すとも、礼を以(もっ)て之を節せざれば、亦(また)行はるべからざるなり。― 学而第1(礼は貴賤(きせん)長幼等の秩序を定めて、その性質が厳格なものであるけれども、みな自然の理から出たものであるから、これを行う場合に従容(しょうよう)として迫らず、極めて和順(わじゅん)であるのが貴いのである。これが先王の道なる礼の美たる所以(ゆえん)であって、天下後世(こうせい)小事も大事もみなこの礼によって行わないことはないのである。このようにしても行われない所があるが、それはいたずらに和の貴いことを知って専ら和を求めても、礼をもって程よく節制することを忘れるなら礼の本体を失うから秩序が乱れて小事も大事もまた行われることができないのである)― 宇野哲人『論語新釈』(講談社学術文庫)、pp. 28f
2024.11.23
コメント(0)
-
教育について(88)働かなくなった日本
《欧米社会では大学生にも競争があり、社会人にも競争がある反面、高校生以下の児童生徒たちは一般に競争からは解放されている。年齢的に上へ行ってなお幾度も競争し合う挑戦の機会に恵まれるのであるから、子供のときは大いにのんびりしていることが許されるのである。ところが日本では、大学に入るまでが競争で、大学生になるともう競争が弱まり、社会人はすでに違った原理でしか競争しなくなる。言い換えれば、大学生以上の大人の社会の全体が赤裸々な個人競争を避けるために、人生の競争の儀式を、18歳と15歳の子供たちに押しつけている。しかも最近では12歳へと段々年齢的に下の層へ押しつける圧力を強めているのではないか》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 118) バブル崩壊前の日本人は、(異論は大いにあり得ようが)、大学入試までは知識競争に明け暮れ、大学で一旦中休みし、企業に入ってからは再び、企業戦士として我武者羅(がむしゃら)に働いてきた、という印象が強い。が、バブル崩壊後は、ワーク・ライフ・バランスだの、近年は「働き方改革」だのと競争を回避するような大人社会が出来つつある。が、そんなことを言っている間に、世界は日本に追い付き、追い越して行くだろう。実際、かつての米国に次ぐGDP世界第2位の経済大国に上り詰めた日本は、チュウゴクにもドイツにも抜かれ、近い将来インドにも抜かれると予測されている。 また、子供社会も、従来型の知識詰込みを忌避し、ゆとり教育だのアクティブラーニングだのと教育現場は半ば教育関係者の「実験場」と化してしまっている。一体日本の教育は何を目指しているのだろうか。《大人の社会が競争を避ける分だけ、子供の世界が競争を肩代りして、それが高校以上の学校に関して、学校と学校の問の「格差」という微妙な差別を全国一帯に普及させたのが、今日の日本の教育の病理の基本をなしている。 企業社会人が教育問題は自分には責任がない、自分は災いの原因をなしていない、と嘯(うそぶ)いてはいられない筈(はず)である》(同、pp. 118f) 西尾氏は、何をもって大人が競争を回避したことで、その皺寄せが子供に行ったと考えているのだろうか。大人が競争を回避する傾向が見られるのは確かであるが、子供の教育の世界でもかつて「受験地獄」などと呼ばれたような過酷な状況は影を潜(ひそ)めた。詰まり、大人も子供も日本全国が「働かなくなった」のが本当のところではないか。それは日本が豊かになったことが大きいのであろうが、明治以降欧米に追い付け追い越せでやってきたのが、欧米に追い付いてしまい、目標を見失ったこともまた大きな要因であろうと思われる。
2024.11.22
コメント(0)
-
教育について(87)学校世界における差別の構造
《イギリス社会なら上流階級から労働者階級の下まで細分化された微妙な差別の体系があるのに、日本では明治維新以後の能力主義の尊重の結果、学校の世界にそれが移し変えられ、受験生たちの肩に覆い被(おおいかぶ)さって来たと解釈できる。政治や経済の一般社会が画一化し無差別化した分だけ、学校の世界がそのいわば代償として、差別の構造を肩代りしたのだ》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 114) ラーレンドルフの言う〈微妙な差別〉とは、英国における「自生的秩序」(ハイエク)を構成する要素とも考えられる。詰まり、長い歴史の積み重ねの中で創られ、その意味で、「公正」と呼ぶに値し得る差異化である。したがって、日本の教育に見られる、西尾氏が言うところの〈差別の構造〉と英国の〈微妙な差別〉を同列に語ることは出来ないだろう。《アメリカ社会になら人種や所得による明確な仕切りがある。だから進学率が高くなっても、日本のような同一路線上の競争は起こらない。一般にヨーロッパの他の諸国には、イギリスほどではないにしても、まだ階級間の仕切りが残っている。だから進学率は高くならない。これらの諸国に対し日本は社会の中に仕切りを失った結果、学校の「格差」とか「序列」とかが、仕切りの代用をなして来た》(同) 確かに、日本には「階級」という仕切りはない。その意味で、日本は稀に見る「平等社会」を実現していると言えるのだろう。が、平等社会といえども、様々な「格差」は存在する。地域格差もあれば、所得格差もある。教育においても同様である。が、日本の教育に〈差別〉と呼べるような〈仕切り〉はない。成績によって序列化されはするものの、それは〈差別〉でもなんでもない。《しかしここで注意しなければならないのは、学校に忍び込んだこの「仕切り」は、フランスやドイツの教育組織のように、国民を高級管理層と民衆、知識階層と民衆という風に明確に2分極化する方向には作用しなかった。勿論日本にも指導層とそうでない層の漠たる区別はあるのだけれど、両者の関係は曖昧に連続している。いつでも交代可能である。それだけにまた、1本の太い「仕切り」があるのではなく、細分化された何本もの「仕切り」が段をなして、微妙な差別の体系を形成しているのである》(同) 〈交代可能な仕切り〉は〈差別〉ではない。容易に交代を許さないからこその〈差別〉なのだ。《今日の日本の政治的無風状態と経済世界の小市民的自己満足状態は、ほかでもない、学校教育に災いをもたらしているこの差別の体系に裏側から守られ、支えられている。あるいは、少くとも、両者は相互補完的な密接な関係にあって、前者の安定と成功は、後者の犠牲と悲劇の上に成り立っているという外はない》(同、p. 115) 西尾氏は、「校内暴力」や「青少年非行」を念頭に置き、学校における〈微妙な差別〉が学校教育の災いを引き起こしていると言っているのだとすれば、それは見当違いと言うしかない。
2024.11.21
コメント(0)
-

教育について(86)知識・見識・胆識
安岡正篤(やすおか・まさひろ)氏は、「知識より見識が必要だ」と言う。《知識と見識は似ておるようですが、これは全く違います。知識というものは、薄っぺらな大脳皮質の作用だけで得られます。学校へ入って講義を聞いておるだけでも、あるいは参考書を読むだけでも得ることができます。しかし、これは人間の信念とか行動力にはなりません。知識というものにもっと根本的なもの、もっと権威のあるものが加わりませんと、知識というものも役に立ちません。それは何かと言えば見識であります》(安岡正篤『活眼 活学』(PHP文庫)、p. 43) 〈見識〉があってこその〈知識〉であって、ただ〈知識〉があるだけでは役に立たない。詰まり、〈学歴〉は〈能力〉の大凡(おおよそ)の目安にはなっても、学歴だけで物事を成し遂げる力は測れないということだ。《ある1つの問題についても、いろいろの知識を持った人が解答をします。しかし、それはあくまでも知識であります。しかし事に当たってこれを解決しようという時に、こうしよう、こうでなければならぬという判断は、人格、体験、あるいはそこから得た悟り等が内容となって出て参ります。これが見識であります。知識と見識とはこのように違うものです》(同、pp. 43f) 知識とは既知の結論である。が、我々が直面する課題にはこのように定まった結論はない。詰まり、知識だけでは太刀打ちできないということだ。課題に向き合い、弛(たゆ)まぬ努力によって、未知の「結論」を自らの力を総動員して導かねばならない。その際、必要となるのが〈見識〉というものなのである。《ところが、見識というものはそういう意味で難しいものですけれども、この見識だけではまだ駄目で、反対がどうしてもあります。つまり見識が高ければ高いほど、低俗な人間は反対するでしょう。そこでこれを実行するためには、いろいろの反対、妨害等を断々乎として排し実行する知識・見識を胆識と申します。つまり決断力・実行力を持った知識あるいは見識が胆識であります。これがないと、せっかく良い見識を持っておっても優柔不断に終わります》(同、p. 44) 反対派を生み出すのが民主主義というものであるから、これに打ち勝つことが物事を実現するには必要となる。また、世論を説得するという地道な作業も不可欠である。そこで必要となるのが安岡氏の言う「胆識」である。《また、平生どういう理想を持っているか、ただ漫然と過ごすのではなく、1つの理想あるいは目標を持っている、これを志を持つといいます。しかしそれは、一時的では駄目でありまして、永続性がなければなりませんので、これを操という言葉で表現いたします。また仕事をするに当たっては、きびきびした締めくくりも必要でありまして、これを節といい、前述の操と合わせて、節操という熟語ができております。つまり単なる知識人あるいは事務家では駄目でありまして、胆識があり、節操のある人物が出てこなければ、この難局は救われません》(同)
2024.11.20
コメント(0)
-

教育について(85)能力主義と学歴主義は別
《イギリス社会なら上流階級から労働者階級の下まで細分化された微妙な差別の体系があるのに、日本では明治維新以後の能力主義の尊重の結果、学校の世界にそれが移し変えられ、受験生たちの肩に覆い被(おおいかぶ)さって来たと解釈できる》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 114) 明治以降の日本を「能力主義」と言うのは如何(いかが)なものか。 渡部昇一氏は、「早熟秀才序列を崩せ」と言う。《明治維新の動乱期が終わり、世間が落ち着いてくると、日本では早熟度によって出世コースが決まるシステムができあがってしまった。今ではそれがさらに極端になって、幼稚園にまで「お受験」なるものがあると言うが、有名な小学校や中学校の入学試験に合格するのは要するに早熟な子であって、そうではない子どもは出世コースからはじき出されるというのが近代以降の日本なのである。 そしてその「お受験」の頂点にあるのが、言うまでもない、官僚のキャリア制度である。 東大法学部を優秀な成績で卒業し、国家公務員I種の試験を優秀な成績でパスする。それはたしかに頭のよさの証明であろう。しかし、それは単にその人物が早熟であるということを示しているにすぎないことが多いのだ。 早熟な人間があとあとまで優秀である保証はどこにもない。そのことはすでに孔子の時代からわかっていたことで、『論語』にも「苗ニシテ秀デザル者アリ。秀デテ実ラザル者アリ」と記されている。苗の段階、つまり若いころに優秀であっても、その後の実りがよくない人もあれば、反対に苗のころにはパッとしなくても、たわわな実をつける例もある。若いころの評価で人間はわからないと、あの孔子ですら嘆息しているのである。 しかるに、日本の教育制度においては、苗の時代にその人の将来がすべて決まるという仕組みになっている。これが問題でなくて何であろうか》(渡部昇一『日本の生き筋 かくてこの国は甦る』(致知出版社)、pp. 57f) 先ず、西尾氏の言う能力主義とは、所謂(いわゆる)学歴主義に他ならない。が、人間の能力は、学力試験だけで測ることが出来ないことは言うまでもない。能力とは、もっと総合的なものであり、「知情意」(知性・感情・意志)すべてを総合して考えるべきものだろう。知性が備わっているかどうかは学歴から一定の判断を下せよう。が、だからといって、物事を成し遂げられるかは別の問題だということだ。
2024.11.19
コメント(0)
-
教育について(84)受験生の危機意識
《日本の教育は画一化していると盛んに言われるわけだけれど、社会の方が氏素姓(うじすじょう)とか、出身階層とかを余り問題にしなくなってきて、その分だけ画一化している反面、学校は偏差値であれ、就職率であれ、基準は何であろうと、ともかく細かく自他を弁別し合う意識を精妙に研ぎ澄まして来た結果、必ずしも画一化とはいえない局面がいくらもあるのである》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 113) 公教育は、営利目的ではないので、人気があろうとなかろうと、画一的に同じ内容をただ提供すればそれでよいのであるが、企業はそうはいかない。企業は、生き残り競争に勝たねばならないから、能力の高い人材を獲得しなければならない。ここに「格差」が生じるのは当然である。また、大学入試は、就職の前哨戦的なものであるから、ここにも当然受験偏差値という「格差」が生じるのである。 このように「格差」が生じているのは、教育ではなく、謂わば「教育後」の部分である。詰まり、教育自体はやはり画一的であると言うべきであろうと思われる。《受験生の心理ひとつを考えてみてもいい。まだ若い年齢の彼らが、鎬(しのぎ)を削って僅(わず)かの点差を競り合うのは、大人になって企業や官庁に入ってからの早い昇格を願ってのことだとは必ずしも言えまい。若いときには誰しもそんな事は余り気にしていないものだ》(同) 成程(なるほど)、受験生が鎬を削るのは、受験生自身が将来の高い目標を掲げてのことだとは考えにくいだろう。が、受験生は、ただ自分の意思で受験競争しているのではない。親をはじめとして周りにいる人達が期待するからこそ、それに応えなければならないのだ。東大の価値が分かるのは、子供ではなく親の方であって、子供が東大を目指すとすれば、それは親が子供に東大を目指させているからである。《そうではなく、僅かな差が心理的社会的に拡大されて決定的な差になる特殊な競争心理に彼らは苛(さいな)まれているのである。ことに高学歴競争においては、経済競争とはまったく別の動機が働いている。すなわち、入学試験に失敗すれば、ただ学校競争に失敗したという程度にとどまらず、人生全般に関わる自分の能力をかなり限定して考えなければならない、という自己催眠が彼らを動かしているのである。自分の生涯にわたる人間としての能力が問われているのだ、との危機意識が受験生心理の根底にある》(同、pp. 113f) 中学受験、高校受験、大学受験で事情は異なるだろうことは前にも書いた(参照:(78)競争と競争回避)。西尾氏の言うような〈危機意識〉は、エリート層にはあるのかもしれないが、大半の受験生にはそこまで切迫したものはないのではないか。
2024.11.18
コメント(0)
-

教育について(83)微妙な差別
《われわれの国では、ある程度の近代化の達成に、われわれがふと気がついたときには、国内の文化意識はすでにひどく均質化しており、あの微妙な差別とそれに基づく心理的安定や風俗の妙味を失って、国民こぞって気ぜわしい成金人間と無風流人士になり果てていたのである》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 102) 〈あの微妙な差別〉とは、次のダ―レンドルフの著作に出てくる言葉である。《アダム・スミスが表現した、いまでも記憶に新しい言葉である労働の微妙な差別は、それ以上に微妙な社会的地位や所属による差別となり、この差別プロセスから生じる身分の1つ1つは、それなりのシンポルやルール、そしてとりわけ他との境界線を持っているのである。他の国々が大きな重複したカテゴリーの社会となり、それが1つの中心的な価値観で支配されているとき、イギリスは微妙な差別の社会にとどまった》(ラルフ・ダーレンドルフ『なぜ英国は「失敗」したか?』(TBSブリタニカ)天野亮一訳、p. 74) 道徳、慣習、礼儀作法といったものは、それに遵(したが)う人と遵わない人とを分け、区別する。当然、そのことで人は差異化される。これもまた「差別」であるが、平等主義はこのような差別をも攻撃することになるだろう。その攻撃は、道徳、慣習、礼儀作法にも及び、日本の文化が傷付けられることとなる。戦後日本が平等を絶対視することによって、文化破壊が進行したということだ。《そして、じつはここからが私の今一番強調したい点なのだが、社会生活の中に微妙な差別が消えてなくなった結果、すなわち画一化が進行した結果――それがまた日本経済の成功や政治の無風状態の主たる原因となっているに相違ないのではあるが――代りに、教育意識の中に微妙な差別の構造が微妙なままに移し変えられたのである》(西尾、同) ダ―レンドルフの言う英国における階級に伴う「微妙な差別」は、差し詰め日本では、学歴に伴う「微妙な差別」ということになるという西尾氏の見立てなのであろう。成程(なるほど)、今や日本には「階級」というものは無い。代わりに、日本人を区別するものとして「学歴」というものが存在する。大卒、高卒、中卒という区別があり、さらに細かく、東大卒、法大卒といった区別がある。 が、英国の階級には、歴史伝統的に育まれた規範があるのにたいし、日本の学歴にはそのようなものはない。英国には「高貴なる者の義務」(noblesse oblige)があるが、日本にはない。詰まり、日本の学歴は、優れて表層的なものだということだ。それが故、日本の学歴は、人の差別感情に結び付き易い性質のものではないかと推察される。《近代日本は社会の中から人間を識別するあらゆる目じるしを追放しつづけてきた特異な平等国家ではあるが、究極的には区別とか差別とかなしでは、人間集団はまとまりを維持していくことが出来ないものとみえる…慶大経済学部と一橋大学との違いなどについて、一般の日本人は誰も説明が出来ないが、一方を好む人は他方に合格してもがっかりしたりするのである。そういう微妙な差別が上から下まで、大学から高校まで全国規模で張りめぐらされているのが「格差」という化物であり、それは人が言うほどに明確な序列を形成せず、専門ごとにあるいは地域ごとに、まさしく微妙に形づくられ、かつ運用されているとみていい》(同、pp. 112f)
2024.11.17
コメント(0)
-
教育について(82)「学歴=能力」にあらず
《かりに画一性を打破せんと、主張される通りに小中学の通学区域を撤廃したり、民間の塾を公認したりしてみたら――進学率のいい小中学校に越境しないでも入れるというわけで親も子も喜んで殺到し、12歳の受験戦争が全国規模でひろがる、という新たな今以上の画一性に見舞われることにもなり兼ねないのだ。私は第1部会の「審議メモ」と香山私案を読んで、そこに現実の困難性が――あるいは、日本の教育の学んでいる病理の手に負えない実体が――少しも滲(にじ)み出ていない、単なるスローガンの空しさを覚えた》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 102)と言うのは杞憂(きゆう)であるというか、大事なことが抜け落ちている。今は、東大を頂点とする競争一択しかないが、これからの時代は、価値が多様化し、知識を詰め込んで東大に合格したからといって、社会で活躍できるわけではない。したがって、競争の道筋が多様化することになって、西尾氏が危惧するような受験戦争など(過渡期は別として)起こらないに違いない。《日本の社会、とりわけ戦後社会が画一的であるのは、この種の微妙な差別をことごとく押し流そうとする大きな力が働いてきた結果である。人種・言語・風土の単一性という古代以来の日本本来の文化のあり方もそこに与(あずか)って力があったと思うが、例の「追いつき型近代化」の急速な要請が何といっても一番強くこの差別止揚の傾向に拍車を掛けてきた。明治の元勲の孫たちがしばしば週刊誌などで好ましくない風評を立てられるのを読む度(たび)に、私は日本では名誉ある家系のプレスティージ(名声)がわずか3代つづかない流動社会なのだなと合点(がてん)する》(同、pp. 111f) 単一性は自然なものだが、画一性は人工的なものである。画一的教育も富国強兵なる時代の要請によって人工的に作られたものだ。が、同時にその裏には、社会主義思想の影響もある。今や時代が画一的教育を要請することはない。したがって、問題となるのは社会主義思想の方である。社会主義は「平等」を求める。だから、この問題は、如何に平等主義を改めるのかということに帰着する。《親の出自・地位・財産よりも、学歴が官庁や企業に迎えられるパスポートになる比率が日本において高いのは、明治以来官民あげての「追いつき型近代化」の要請が「1つの中心的な価値観」となって、日本を闇雲(やみくも)に駆り立てて来た帰結と考えられる。国家が列強同士の相剋(そうこく)の谷間に埋没し兼ねない緊張が百余年もつづいた間、指導者として旧大名の息子たちに頼るのでは到底国を維持できず、生存本能からも、能力主義を尊重しないわけには行かなかったのであろう》(同、p. 112) が、「学力=能力」ではない。高学歴の人間が必ずしも「能力」が高いわけではない。例えば、学歴エリート将校が判断を誤ったのが、大東亜・太平洋戦争であった。 日本は、学歴主義ではあっても、それは必ずしも「能力主義」を意味しない。そこを間違えてはならない。
2024.11.16
コメント(0)
-
教育について(81)生き残り競争
西尾氏は、次のように反論する。《「審議メモ」に示された宣言内容は、すべて結構ずくめで、私とて異論はない。単なる言葉の呼び掛けによって、物事がこの通りに実現されるなら、何も言うことはないのだ。教育における「画一性」が「多様性」になり、「閉鎖性」が「開放性」になり、「非国際性」が「国際性」になることを望んでいない国民なんか1人もいない》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 101) が、例えば、画一性が悪で、多様性が善というような単純な二元論で物事を考えることは疑問だ。「欧米に追い付け追い越せ」の時代には有効だった画一的教育は、欧米に追い付いた今、その役目を終え、これからの何が正解なのかが分からない時代において、視野を広げ、様々な課題に取り組むことがダーウィン的「生き残り競争」を勝ち抜くためには必須である。であれば、教育を多様化することは時代の必然と言える。 が、それは取り組む課題が多様化するということであって、教育に関する価値観まで多様化し、ある意味、「破壊」することを意味するものではない。昨今の「多様性」の話には、既存の価値観を破壊し、自分たちが理想とする「妄想世界」に引き込もうとする輩(やから)も少なくないから注意が必要である。 多様化しなければならないのは必然なのだとしても、何でもかんでも多様化すればよいというような乱暴な話ではなく、何をどう多様化するのかということが重要となる。だから、渡部昇一氏は、塾を公認することで「蟻の一穴(いっけつ)」とし、画一化から多様化への緩やかな移行を図(はか)ろうと提案されているのである。 既存の画一化された学校でよければそれでよし。塾で勉強したければそれもよし。そこに、徐々に「競争」が生まれ、自分が受けたい教育が提供されるところを選択する自由も次第に保障さていくということだ。《しかし平和主義を唱えていれば平和が維持できるとは決まっていないように、画一性の打破をロにしていれば画一的でなくなるというものではないだろう。それどころか、個性尊重とか、画一性打破とか、昔から百万遍も言われて来た決まり文句を用いることは、冒頭にも述べた通り、そのこと自体が画一的で、個性のない所業と言わざるを得まい》(同、pp. 101f) 教育の画一性は、平和主義とは問題の構造が異なるので同列に扱うべきではないだろう。戦争には相手があるので、幾ら平和主義を唱えても、そのことで戦争を回避することは出来ない。詰まり、平和主義を唱えることは賢明な選択とは言えないということだ。一方、教育の自由化は、画一的教育を打破しなければ達成できない。日本の教育の成否が、競争することによって教育を活性化することにかかっているのだとすれば、画一的教育を打破することを訴えることは当然のことだ。
2024.11.15
コメント(0)
-
教育について(80)画一主義だけが問題なのか
〈過度の学歴社会意識や偏差値偏重の受験競争、校内暴力、青少年非行などにみられる教育荒廃は、画一主義と硬直化がもたらした病理現象である〉という結論にも疑問符が付く。これらは、〈画一主義〉が齎(もたら)したものと即座に断定できるようなものではない。 例えば、日本人が「学歴」を重んじてきたのは、画一化の問題ではなく、文化の問題と言うべきだろう。ここには、日本人特有の「公正観」がある。学歴は、誰の目にも明らかなものである。この公明正大な尺度で、人材の能力を事前判断するのである。勿論、東大を出たからと言って優秀とは限らない。が、「欧米に追い付け追い越せ」の時代には非常に有効な尺度であったことは否めないであろう。 が、欧米に追い付いた今、求められるのは知識量や演算速度、すなわち、「頭の良さ」ではない。21世紀という先の見えない時代に求められるのは、自ら課題を設定し、倦(う)むことなくこの課題に取り組み、何某(なにがし)かの「解答」を導き出すことである。そこで重要になるのは、「発想力」であり「想像力」である。 こういった能力は、「学歴」で判断できないものである。当然、教育内容も、「知識」の量や質ではなく、「発想」や「想像」を重んじるものに変化せざるを得なくなるに違いない。 〈校内暴力〉や〈青少年非行〉も、〈画一主義〉が生み出したというよりも、高度経済成長によって、家庭環境が大きく変化したことが最大の要因ではないだろうか。さらに、家庭や地域共同体の教育力の低下も大きいだろう。見方を変えれば、精神面を軽んじた物質的豊かさの追求の問題とも言える。いずれにせよ、画一主義が問題であるなら、青少年は暴力的ではなく虚無的になるはずである。《ここにいう「個性主義」とは臨教審第1部会の新造語であるが、その定義は「個人の尊厳、個性の尊重、自由、自律、自己責任の原則の確立」である。 このような観点から、同メモは、①官公庁・企業の採用基準の抜本的見直し、学歴・官学偏重の是正②大学院教育、基礎研究の整備充実③大学設置基準、許認可条件の見直しなどによる画一性の排除、個性化の推進④共通一次試験を含めた各種試験制度の改革⑤ゆとりと国際化の観点も踏まえた9月新学年制の検討⑥高校、専修学校など後期中等教育機関の連携と高等教育への接続の研究⑦単位制の見直し、中高一貫教育の推進など高校教育の多様化、入試制度の改善⑧義務教育段階においても、過度の画一化を戒め、少なくとも学校選択について配慮する⑨乳幼児保育に始まる生涯教育システムの確立、教育機関の地域社会への開放、家庭・学校・職場・地域社会を結ぶ教育ネットワーク形成の検討⑩国・都道府県教育委員会・市町村教育委員会の役割分担の明確化、特に市町村教委の権限と責任の再確立 ――など、10項目の具体的方策を例示し、各部会での検討を要請した》(香山健一『自由のための教育改革』(PHP)、p. 76)
2024.11.14
コメント(0)
-

教育について(79)臨教審第1部会「基本認識」
香山健一氏は、「臨時教育審議会」(臨教審)第1部会について、次のように書く。《昭和59年9月5日の初会合以来、約半年間に、臨時教育審議会は12回の総会、延べ約60回の部会、100有余の教育関係諸団体等からの「教育改革提案ヒアリング」、福岡、福島、香川での地区公聴会を開き、21世紀のための教育改革について、精力的な審議、検討を続けてきた。 この間、第1部会は、審議会としては前例のない3日間の合宿集中審議を行い、 ①21世紀社会と教育への要請、②教育の目標、③教育改革の方向について、最初の基本的な合意形成を行った。 第1部会の総意として確認された「合宿集中審議メモ」(2月11日)は、「明治、大正、昭和の日本の追いつき型近代化は、成功のうちにその百余年の歴史的役割を終えた。同時に世界、人類も、近代工業社会から21世紀の高度情報社会への文明史的転換期を迎えている。模倣と物量と画一の時代は終わった。創造力と質の充実と個性の発揮が新たな時代の要請である。教育はこの要請にこたえなければならない。過度の学歴社会意識や偏差値偏重の受験競争、校内暴力、青少年非行などにみられる教育荒廃は、画一主義と硬直化がもたらした病理現象であることを認識し、これまでの画一性、閉鎖性、非国際性を打破し、多様性、開放性、国際性を実現する抜本的改革を進めなければならない」 という基本認識に立って、「画一主義から個性主義への、大胆かつ細心の移行、改革」こそ今次教育改革の基本方向でなければならないということを打ち出した》(香山健一『自由のための教育改革』(PHP)、p. 75) 果たしてこれは、「基本認識」と呼べるようなものなのか。叩き台としての一意見と言うのなら分かる。が、これが認識の基本だなどと言われては黙っていられない。 香山氏は、〈明治、大正、昭和の日本の追いつき型近代化〉は成功だったと言う。成程(なるほど)、大東亜・太平洋戦争の敗北があったにせよ、1980年代には、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と呼ばれるまでの大国となったのだから、成功だったと言えなくもない。が、それは物質的側面に限ったものである。詰まり、先進国に追い付いたと言えるのは、物質的側面においてであって、そこには精神的側面における評価がすっぽり抜け落ちてしまっている。 戦後日本は経済復興のために、精神的なものを等閑(なおざり)にした。GHQが敷いた路線そのまま、戦前までの日本を否定し、日本本来の文化伝統を粗末にし続けてきたということだ。このように平衡を欠いた豊かさを、「成功」という一語で括(くく)ることには、とても賛成できないということだ。
2024.11.13
コメント(0)
-
教育について(78)競争とその回避
《他人より抜きん出るためではなく、他人と同じような資格を得たいがために高校、大学の進学熱が高まっているのが今日の実情であるが、そもそも他人と同じような存在でありたいと思うのは競争心理では決してなく、むしろ競争回避心理である》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、pp. 96f) 中学受験、高校受験、大学受験、それぞれ受験心理は異なると思われる。中学受験は、1流大学に進もうとする「上流心理」が働いた熾烈(しれつ)な競争であり、高校受験は、せめて高校だけは出ておかないとという「反下流心理」が働いた、落ち零れの回避であり、大学受験は、将来、良い就職先と収入が得られるように、出来るだけ優秀な学校に入ろうとする「上流心理」から、まだ就職はしたくないという「モラトリアム(猶予)心理」や、見栄や世間体から、どこでもいいから大学と名の付くところへ行きたいという「反下流心理」まで幅広い。大学への進学率が高まっていることと、大学への進学熱が高まっていることは必ずしも同じではない。《高校卒あるいは大学卒という「属性」を外されることを恐れ、言い換えれば個人の競争を避け、高校卒もしくは大学卒という集団性の内部に身を隠し安心したいがために、学校へ、学校へと殺到し、その揚げ句、学校を激しい競争の舞台にするというはかげた逆の事態を招いてしまった》(同、p. 97) 当時は、受験競争が過熱したことを「受験地獄」などと称し、否定的な見方がなされることもあったが、受験のために競争することが悪いわけではない。あくまでも程度の問題であり、受験競争が地獄であるかのように言い、競争自体を否定してしまっては、学力低下を招くであろうことは必至である。《経済人や政治家は競争は人間に活力を与えると素朴に信じているが、競争を逃げたいために競争に陥るという逆説的状況がここにはある。そして、一流企業に入るために一流大学に進もうとする世の風潮は、じつはこの競争回避心理に支えられているのである。日本の企業間競争は確かにすさまじいが、ビジネスマンや技術者が企業から企業を渡り歩く欧米型の「個人」の労働原理は日本には存在しない。日本人がいい学歴を身につけたがるのは、個人の競争を避け、企業という集団内部に身を隠し安心したいがために外ならない。逆にいえば企業社会人の全体が赤裸々な個人競争を避けるために、人生の競争のすべてを高校三年生に押しつけているのではないだろうか》(同) 無事企業に就職したとて、競争を回避できたわけではない。個人の「出世競争」もあれば、組織が社運を賭けた「企業間競争」もある。たとえ一流企業に入社できたとしても、競争しないような人材ばかりになってしまえば、その企業は早晩衰退するに違いない。
2024.11.12
コメント(0)
-
教育について(77)初等中等教育改革と高等教育改革の違い
《日本の大学機構が中曽根首相と「臨教審」の力で本当に「自由化」され、ドイツやアメリカの大学のように公平でオープンな競争状態を保つことが出来るようになるのなら、これほど歓迎すべきことはないであろう。その限りでなら私は、首相の好む「学校、教師の側に競争を」を是認する。ところが「京都座会」の提言にもはっきり述べられている通り、何を勘違いしたか、「学校、教師の側の競争」を取り入れるのは大学ではなく、むしろ「初等・中等教育」が予定されているのである》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、pp. 94f) 初等中等教育改革、すなわち、小中高校改革と、高等教育改革、すなわち、大学改革とは分けて考えるべきだと思われる。大学改革は、教育全体に関わる改革となるから大事(おおごと)である。一方、小中高校改革、特に、義務教育改革は部分的改革に留まるから改革の手を付け易い。また、大学改革に取り組むには、小中高校にも影響が及ぶので、10年、20年単位で事を進める必要があるが、義務教育改革は、このような制約がほとんどない。 また、小中高改革の味噌は、「平等主義」、言い換えれば、「官僚支配」に風穴を開けることであるのに対し、大学改革は、「自ら課題を見付け、答えを出す」人材が必要となった「時代の要請」である。《いわく、誰でも自由に小中学校を作れるようにせよ、塾を公認すべし、通学区域を撤廃せよ、飛び級を認めよ、先生になれる資格を緩めよ、等々。この中にも聞くべき意見は皆無ではないが、上部構造が閉ざされ、大学の序列が動かない現状で――序列に大流動化を起こす明確な見通しもないまま――下部構造に競争の原理を大幅に取り入れたら、一体どういうことが起こるであろう。常識ある日本人になら誰にでも分り切ったことが起こる。すなわちエリート小学校・中学校が全国各所に出現し、受験競争が年齢的に果てしなく下へさがって日本人の心身に破壊的荒廃をもたらすであろう》(同、p. 95) 私は、初等中等教育に競争原理を導入しても、「エリート小中学校」が出来て、受験競争がさらに低年齢化し、子供たちの精神を荒廃させることにはならないと思う。仮に登山道が1本しかなければ、競争は激化するかもしれない。が、初等中等教育の多様化は、山の頂上に辿り着くのに色々な道があり、当然そこには長所・短所があり、どの道を選択するのかは自由だから、皆がエリート小中学校に押し寄せて、精神を擦切らせるようなことはないのではないかと考えるからである。 否、登るべき山の頂上には今は東大しかないのであるが、初等中等教育改革の後には、高等教育改革が控えており、登る山は東大とは限らないという時代が近い将来やって来る、否、来なければならないのである。※余談だが、マルクス用語と違う意味で「上部構造」「下部構造」と言うのは混乱を来(きた)すから、普通に「高等教育」「初等中等教育」と言うべきだろう。
2024.11.11
コメント(0)
-
教育について(76)西尾幹二氏に哀悼の誠を込めて
話を西尾氏の著作に戻そう。《教育の自由化をめぐって「臨教審」内部で論議が交わされて以後、競争という言葉が新しい脚光を浴びるようになった。今までは生徒が競争を強いられるばかりで、学校、教師の側に正しい競争がなく、生徒に学校や教師を選択する自由が与えられていないことに、公教育が画一化する原因があった、というのである》(西尾幹二「『競争』概念の再考」:『日本の教育 智恵と矛盾』(中央公論社)、p. 93) 成程(なるほど)、生徒に学校や教師を選択する自由はない。また、公教育は画一化されている。が、生徒に学校および教師を選択する自由が与えられていないから公教育が画一化しているわけではない。 生徒や親に学校や教師を選択する自由がないのも、公教育が画一化しているのも、その根っこには「平等思想」がある。平等が絶対的であるから、教育における選択の自由もないし、教育自体画一化するのである。したがって、教育改革の成否は、如何に「平等信仰」を崩せるかにかかっていると言っても過言ではない。が、それを崩すのは殊の外(ことのほか)大変である。 学校選択の自由が認められても、学校に選べるだけの違いがなければ意味がない。詰まり、学校施設や教育内容に学校ごとの特色を認める必要があるということだ。平等の箍(たが)が外れれば、学校が多様化し、知育に特化した学校、徳育を重んじる学校、体育に力を入れる学校のように特色豊かな学校が登場し、自分に合った学校を選べるようにもなろう。が、平等教の信者たちは、学校の自由は、学校間格差を生み、それを認めれば、自分だけが貧乏くじを引くのではないかと恐れ、差別だと非難し、平等を叫ぶことになるのだろう。《今度の「教育の自由化」論議の要点に、「競争」概念の新しい見直しがあることはほぼ間違いないであろう。 「学校、教師の側にも競争を」というこの新しいキャッチフレーズを、「大学、大学教授の側にも競争を」という風に限定して考えることが許されるなら、私は大賛成である。日本の教育組織の最大の癌(がん)は、組織の上部構造の競争、すなわち大学間競争が今までなかったことに尽きるからである》(同、pp. 93f) 大学に競争がないことが問題であることは事実である。だから、私は、大学の「入り口を広く、出口を狭く」することを提案し続けているのである。その意味は、大学生にしっかり勉強や研究をさせるということであり、そのためには、大学の指導者たちも自分の研究だけに力を入れるのではなく、学生の指導にも尽力するということである。《明治時代に国家的要請から、国際的に1流の構成を持つ東京帝国大学を1校だけつくるのが精一杯で、後から出来た6帝大は永らく講座が整わないままだった。私立大学は予算と人材において官立大学に太刀打ち出来なかった。欧米に追いつけという後発工業国の当時の無理が、現在に至るまでずっと尾をひいている》(同、p. 94)※本ブログで、西尾幹二著『日本の教育 智恵と矛盾』を取り上げ、検討している最中(さなか)、西尾氏が逝去されました。ここに謹んでお悔やみ申し上げます。
2024.11.10
コメント(0)
-
教育について(75)社会に必要なのは「平等」ではなく「活力」
《すべての人間が同じになる「平等」をこの世にもたらそうなどということは、絶対に無理なことである。社会にデコポコがあることによってこそ活力が生まれ、それが貧乏な人の自由の保障にもなる。しかも今は、どの国も物質的に生産過剰だから、セーフティー・ネットが完備されている。飢えず、凍えず、雨風を避けることのできる生活は、みんなに保障されていて、最低限の医療も受けることができるのである。 だから、ものは考えようで、セーフティー・ネットに引っ掛かって、そこで満足するというのなら、それも気楽でいいのではないだろうか。生活そのものはセーフティー・ネットに引っ掛かっている状態であっても、高尚な短歌や俳句を詠むこともできるし、図書館にこもって万巻の書を読むことだってできる。つまらない仕事に就いて年中アクセクしているよりも、そのように過ごしたほうが人生としては充実しているという人がいてもいいのである。 あるいは、そうしてしばらくの間休んで、また闘いを求めて敢然と社会に出ていくということもできる。金持ちの多い社会には、仕事はいっぱいあり、掃除をするだけでも食べていくことができるのである》(渡部昇一『国民の教育』(産経新聞社)、pp. 363f) ここで注意すべきは、「金持ちが多い」という結果ではなく、多くの金持ちを生む社会構造が重要だということであろう。金持ちが多いということは、社会が活性化しているということである。活性化した社会には、社会から落ち零れた人達を抱える余力がある。だから如何に社会を活性化させるのかが政治の第一義とならねばならない。 平等は、社会の活力を奪う。社会の活力が奪われれば、救える人も救えない。だから、社会の第一義が平等であることなど有り得ないのである。《不平等の国のほうが実際はむしろ暮らしやすい。不平等社会といわれるアメリカでも、たとえば高校でちょっとすぐれた成績を挙げることができれば、グラント(奨学金その他)は必ず出るといってよい。金のない日本からの留学生でも学位を取得した例を、私の周囲でも何人か知っている。 それに、平等国の権力者というのはソ連の秘密警察などが示すように、ものすごく怖い存在である。ところが、不平等国の場合は、何かよほど悪いことでもしないかぎり、少しも怖くはない。法律に触れるようなことはしないで、自分のチャンスを見つけ、それを生かしていけばよいのである》(同、p. 364) 〈不平等の国〉とは、「活力ある国」ということだ。「活力」は、必然的に「格差」を生じる。が、「格差」が生まれながらも、国全体としては「豊か」になる。国全体が豊かになれば、「安全網」(safety net)も充実する。平等な国よりも、誰もが圧倒的に暮らし易いということだ。
2024.11.09
コメント(0)
-
教育について(74)「地獄への道は善意で舗装されている」
《ああ、「地獄への道は善意によって舗装されている」ということは、あまりにも真実である。そして人間にとって、最も危険なことは、たしかに、善意によって(言いかえれば約束することによって)後退するということにほかならない》(キルケゴール「愛のわざ」:『キルケゴール著作集第15巻』(白水社)武藤一雄・芦津丈夫共訳、pp. 158f) 「善意によって舗装された道は、地獄への道」であるかもしれないから注意せよということだ。「善意」を疑うなどということは、人の道に外れると人は思い勝ちだ。が、そもそも「善意」とは何なのか。例えば、戦後日本人は、「平等は絶対善」であると思い込んでいる、否、思い込まされている。そこに「悪」の入り込む余地はない。「平等」は絶対である。だから、すべての不平等は排除されなければならない。そう思って平等教の信者は、人間社会を破壊していくのである。《それがほんとうに後退であるということを発見することは、非常に困難なことである。しかも、それが後退であることに変わりはない。善意をもって彼はほかならぬ善きものに面(おもて)を向けていた。しかも、善意をもちながら、彼は善きものに向かって前進はしないで、善きものに背を向けて後退するのである。新しい志をいだくたびに、彼は一歩前に踏み出すように見える。ところが実際は、同じところに踏みとどまっていることすらできないで、現に一歩後退しているのである》(同、p. 159)《挫折した意志、みたされない約束は、不満と意志阻喪(そそう)の後味を残し、おそらく彼をしてやがてふたたびより熱烈な志をいだかせることになるであろう。しかもそれはただいっそう大きな意気消沈を残すにすぎないのである。酒飲みが、酔い痴れたいためにたえずますます強い刺激を必要とするように、善意をいだくという情熱にとりつかれた人は、いよいよ大きな刺激を必要とし、しかもそれによって後退するのである》(同) 「絶対善の平等」は、現実を捨象(しゃしょう)した観念でしかない。現実社会で「平等」を追求すれば、社会そのものを傷付けることとなる。「平等」を追求すればするほど、社会の傷は深く大きくなる。この傷の痛みをなくそうとするなら、社会から痛みの感覚を奪うしかない。それは、社会から活力を奪うということである。《わたしたちは「否」をいった息子を称賛するつもりではない。そうではなくて、「主よ、参ります」と言うことが、いかに危険であるかということを、福音書から学びたいと思うだけである。約束というものは、行動に対する関係においては悪魔の取換児(とりかえこ)みたいなものである》※取換児:ヨーロッパの伝承で、人間の子どもがひそかに連れ去られたとき、その子のかわりに置き去りにされるフェアリー・エルフ・トロールなどの子のことを指す。《約束するには、充分な注意を払わねばならぬ。子供がたったいま生まれたばかりの瞬間、そして母親の喜びが絶頂であるとき、おそらくはただ喜びのあまり、彼女の注意がなおざりになっているその瞬間に、悪魔がやってきて、子供の代わりに悪魔の取換児をすりかえるのである》(同)《同様に、人がいよいよ行動しはじめなければならないという大切な、しかしそのゆえにまた危険な醜聞(しゅうぶん)に、悪魔がやってきて、実際に行動を開始することをうっちゃらかさせて、それを悪魔の取換児に相当する「約束」とすりかえるのである。実際、いかに多くの人が、こういったやり方で欺(あざむ)かれ、魔法に魅入(みい)られたことであろうか!》(同) 「平等」という観念も、「悪魔の取換児」に違いない。この美しい観念は、地獄への「水先案内人」なのかもしれない。そう疑ってみることが必要だ。
2024.11.08
コメント(0)
-
教育について(73)平等という約束
《現世的なものとは瞬間的なもののことであり、約束するということは、その瞬間には、きわめて立派に見えるものである。そうであるからこそ、永遠性は約束に対して不信の念をいだく。なぜなら、永遠性はおよそあらゆる瞬間的なものに対して不信をいだくからである》(キルケゴール「愛のわざ」:『キルケゴール著作集第15巻』(白水社)武藤一雄・芦津丈夫共訳、p. 158) 難解な哲学的論考を抽象的なまま理解するのは難しいので、具体的な〈約束〉として「平等」について考えてみよう。「人は生まれながらにして皆平等である」。なんと美しい言葉であろう。多くの人がそう思っているようである。が、現実は、人は生まれながらにして皆「不平等」である。だから、人はそんな社会が間違っていると思ってしまう。が、間違っているのは社会ではなく、「人は生まれながらにして皆平等である」という命題の方である。 人は生まれながらにして平等ではない。すなわち、平等は不自然だということだ。平等は、観念の世界の中だけで通用する「妄想(もうそう)」でしかない。この妄想に囚(とら)われて、現実も平等でなければならないと思うのは非現実的であり、不自然であり、理に反している。にもかかわらず、現実を平等にしようとすれば、無理が生じる。例えば、「革命」によって不平等な社会を破壊しても、平等な社会は得られず、新たな不平等な社会が登場するだけである。 だからといって、どんな「格差」も容認しなければならない、すべての「差別」を受け入れよと言いたいわけではない。「格差」や「差別」があるからといって、のべつ幕無しにこれを否定するのは誤りだということである。「格差」や「差別」の中には、人間活動を通して必然的に生じるものもある。これをすべて否定してしまっては、人間活動自体を否定することになりかねないということだ。 大事なことは、「峻別(しゅんべつ)」することである。自然な「格差」か、不自然な「格差」か、容認できる「差別」か、容認できない「差別」か、見極める必要があるということである。ここで求められるのは、「公正」か否かということであろう。「それは公正なのか」と問うことが重要だということである。《かりに2人の兄弟のどちらも出かけることをせず、したがってまた父親の意志を果たさなかったと考えてみよう。その場合でも、「否」といった弟のほうが、自分の不従順に気づくということに、より近かっただけにまだしも父親の意志を果たすことに対してたえずそれだけ近かったと言える。「否」は何ひとつかくしだてをしない。それに対して「しかり」は、容易に錯覚となり、自己欺瞞(ぎまん)となる。そしてそういった錯覚と自己欺瞞は、おそらくは、あらゆる困難のなかでも克服するに最も困難なものなのである》(同)
2024.11.07
コメント(0)
-
教育について(72)平等という地獄
《渡部 さて、そうやって国家社会主義になった日本は昭和20年8月15日、敗戦を迎えます。 では、その敗戦によって日本から国家社会主義がなくなったか。なくなっていません。総量規制に象徴されるように、いまだに価格統制をやろうという官僚が支配しているのです。 その大きな理由は、マッカーサー司令部が日本を占領統治するうえで、日本の官僚組織をそのまま活用しようと考えたからです。日本軍は解体されましたが、日本の官僚組織は解体されなかった》(谷沢永一・渡部昇一『誰が国賊か』(ビジネス社)、p. 124)※総量規制:1990(平成2)年3月27日に「不動産融資総量規制」という一通の通達が、大蔵省銀行局長・土田正顕の名で全国の金融機関に発せられ、これを契機としてバブルは崩壊した。 詰まり、戦時にかこつけて敷かれた社会主義体制が敗戦後も温存されてしまったということだ。《しかも、みすみす日本を敗戦の淵に追いやっておきながら、日本の官僚はちっとも反省しなかった。統制経済は官僚にとって最も住み心地のいいシステムなんです。なにしろ、産業のあらゆる面に口が出せるのですから、これほど彼らにとって気持ちのいい話はない。 だから、戦前から今日に至るまで、西側陣営に属しながらも、日本はずっと国家社会主義をやってきたわけです》(同)☆《悪魔が見るからに恐ろしげな顔をしてつねに邪悪なことを説いているのならば、大きな問題は起こらない。悪魔がこの世のものとは思えないほど端正な顔だちで甘い言葉を口にするからこそ、人々は誘惑され、地獄に堕ちるのである》(渡部昇一『国民の教育』(産経新聞社)、p. 354) 恐ろしい顔で邪悪なことを説く、誰の目にもそれと分かる悪魔は「安物の悪魔」でしかない。端正な顔立ちで甘言を弄(ろう)し、人々を地獄へと導く悪魔こそが「本物の悪魔」なのである。《20世紀の悪魔もとても甘美で魅惑的な言説を弄してきた。そして、その芯(しん)になった言葉こそが「平等」だった。「平等」という言葉の響きはとても美しく、それはいつの間にか基本的な人権の平等ではなく、現象的な平等に変わった。経済や社会において「平等」が実現されなければならないということで、私有財産が否定され、相続権が廃止され、さらに貧富の差をなくすために、生産手段・流通手段さえも国有化しなければならないというように進んでいったのである》(同) 頑張っても頑張らなくても「平等」な社会は、「地獄」だ。頑張っても、頑張らない者と受け取る報酬が同じではやり切れない。否、それどころか、頑張る人は、平等な社会を搔き乱す「反逆者」と見做されて、批判の的となる。結果として、誰も頑張らなくなる社会、それが「平等社会」というものなのだ。これが「地獄」でなくて何なのか。
2024.11.06
コメント(0)
-
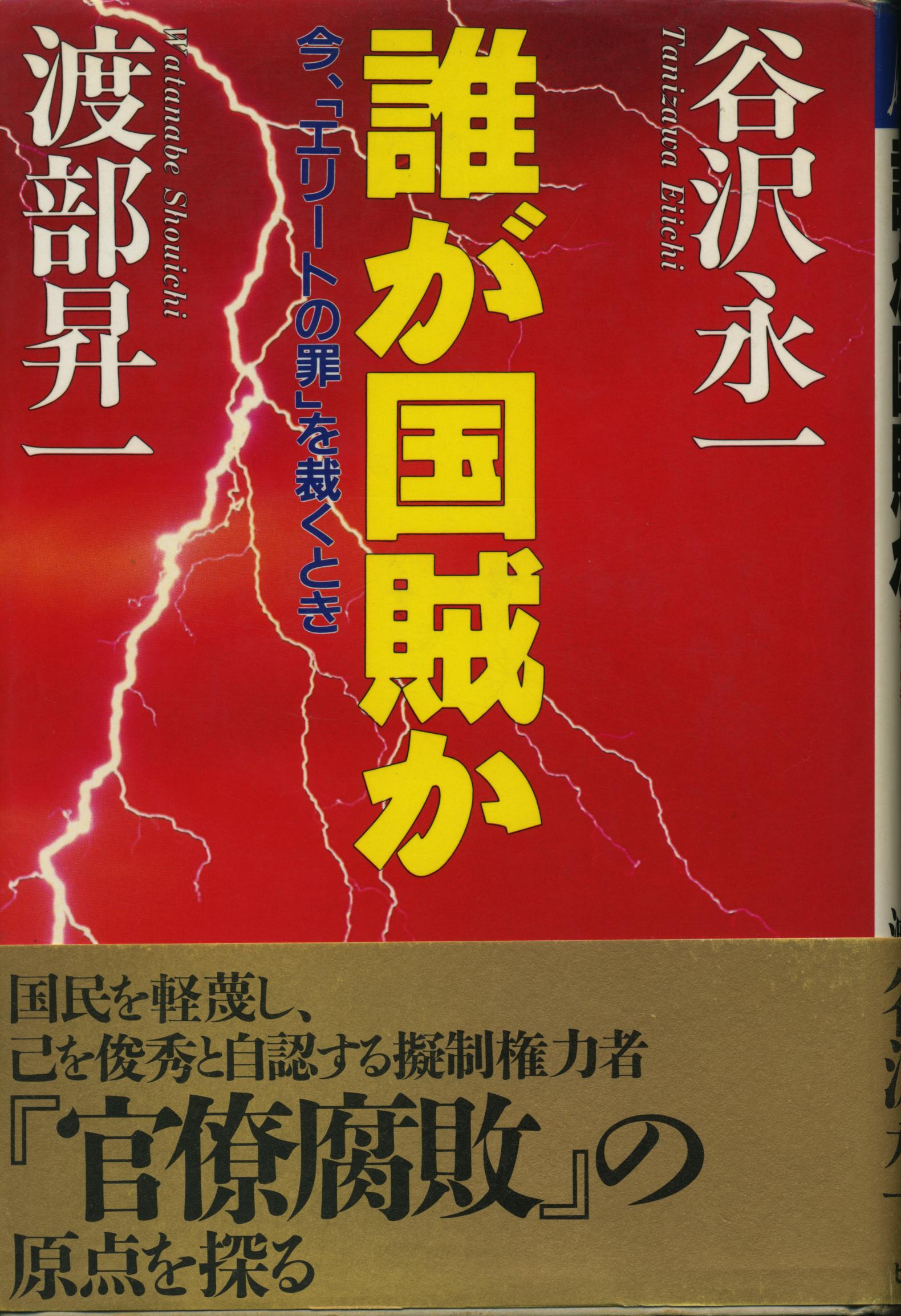
教育について(71)戦前にあった義務教育を受けない自由
《近代教育制度が始まった明治のころには、教育の選択権が親にあることは、誰から教えられなくても皆よく理解していた。江戸時代、子どもの通う寺子屋や塾を決めるのは親であり、幕府や藩ではなかった。そのときの感覚が生きていたから、教育の主体は親であるということを誰もが疑わなかったのである。 もちろん小学校がたった1つしかない村や町は珍しくなかった。現実問題として親が教育の選択権を行使したくとも、なかなか許されないということはあったであろう。だが、それでも戦前の日本の義務教育のほうが、今日よりもずっと選択の自由があったことは間違いない》(渡部昇一『国民の教育』(産経新聞社)、pp. 16f) が、問題は、「教育の選択権」の所在がどこにあるかなのか。仮に、今、親や子供に「選択の自由」があったとしても、どこの学校を選んでも大差ないのであれば、選択権の持ち腐れである。 やはり根本問題は、公教育は平等に提供されないといけないという「平等主義の呪縛」にある。平等主義が改められない限り、選択肢のない選択権にしかならない。 「選択の自由」がないのは「社会主義」である。《大戦突入前の日本は、すでに社会主義国家であった――こう言うと驚かれる方も多いかもしれません。大戦突入前の日本はファシストが支配して、共産主義を弾圧したんだというのが「戦後の歴史観」だからです。しかし、実際にはそんなものではありません。 大戦突入前の日本は、多くの面でナチス・ドイツの真似をしたのですが、価格統制もまた、ナチスに倣ったことの1つでした。 そのヒトラーの率いるナチスという党名は略称で、では正式名称は何かと言えば「国家社会主義ドイツ労働者党」なのです。つまりナチスというものの正体は「国家社会主義」なのです。 このナチスの思想を日本でもやろうとしたのが、大戦前の軍人であり、官僚でした。つまり、大戦に突入する前のナチス・ドイツも日本も、スターリンのソ連と同じように社会主義だったのです》(谷沢永一・渡部昇一『誰が国賊か』(ビジネス社)、pp. 121f)
2024.11.05
コメント(0)
-
教育について(70)求められるのは「平等」ではなく「公正」
自由には、英国的自由と大陸的自由の2つの自由があり、敗戦後持ち込まれたのは後者の大陸的自由であった。 本来、自由と平等は、相反するものである。自由を追求すれば、格差が広がり不平等になる。一方、平等を追求すれば、活動が制限され不自由になる。だから、自由と平等を共に追求することは矛盾なのである。それでも、自由と平等が成立するのは、ここで言う「自由」が、平等を追求するために限定された「自由」だからである。だとすれば、戦後日本において、平等とは反対の方向性を持つ「選択の自由」が認められるわけがないのも無理はないのだ。 「選択の自由」を認めるためには、戦後日本を覆う「平等主義」を打破しなければならない。「自由」と平衡しなければならないのは、「平等」ではなく「公正」である。「平等主義」に囲われた「自由」ではなく、「公正」と「自由」が均衡し、平衡する社会を目指すべきなのである。「頑張った者が報われる」活力ある社会が求められるのであり、そのための自由は、尊重されて然(しか)りだということだ。《明治5(1872)年の学制頒布(はんぷ)によって、日本は義務教育制度を本格的に導入することになった。19世紀後半のこの時期に、日本が義務教育を取り入れたことは世界的に見てもけっして遅くはない。むしろ明治の日本は、当時としては先進的な教育制度を採用したのであり、その質も優れていたといえる。 明治政府の教育改革が成功したのには大きな理由があった。当時の日本人がすでに教育の価値や意味をよく理解していたという事実である。江戸時代の日本には至るところに寺子屋があって、町人や農民でも読み書き算盤を学ぶことの大事さを知っていた。江戸時代の識字率は、当時の世界においても群を抜いた高さであったといわれている。 たとえ政府が大きな権力を持っていたとしても、義務教育が定着するかどうかは別の問題である。発展途上国のように、かたちだけは義務教育制度が導入されていても、その実を挙げていない国は今でも多い。経済が未発達な国では、子どもは貴重な労働資源であると考えられているからである。たとえ立派な学校を建てて法律を整備しても、親は学校に行かせて読み書きを覚えさせるよりも、家や田畑で子どもを働かせようとする。 その点、日本人は江戸時代から教育の価値、知識の価値を知っていたから、かなりスムーズに義務教育が定着したといえる》(渡部昇一『国民の教育』(産経新聞社)、p. 16) が、「欧米にお附け追い越せ」式の教育が上手く行ったのは、「義務教育制度」のお陰というよりも、日本人の高い教育意識にあったと言うべきだろう。詰まり、今の義務教育制度に拘(こだわ)る必要はまったくないのだ。
2024.11.04
コメント(0)
-
教育について(69)英国の伝統と大陸の伝統
Most of liberalism's adherents would also profess a belief in individual freedom of action and in some sort of equality of all men, but closer examination shows that this agreement was in part only verbal since the key terms 'freedom' and 'equality' were used with somewhat different meanings. While to the older British tradition the freedom of the individual in the sense of a protection by law against all arbitrary coercion was the chief value, in the Continental tradition the demand for the self determination of each group concerning its form of government occupied the highest place. This led to an early association and almost identification of the Continental movement with the movement for democracy, which is concerned with a different problem from that which was the chief concern of the liberal tradition of the British type. -- F. A. Hayek, Liberalism: Introduction 1. The different concepts of liberalism《自由主義信奉者のほとんどが、個人の行動の自由とすべての人間のある種の平等の考えも公言していたが、よくよく考えてみると、「自由」と「平等」という重要な言葉が多少異なる意味で使われていたために、この一致はある程度言葉上のものに過ぎなかった。かつての英国の伝統では、すべての恣意(しい)的な強制から法によって守られるという意味での個人の自由が最大の価値であったのに対し、大陸の伝統では、政府の形態に関し各集団が自己決定することを要求することが最高位を占めていた。このため、大陸の運動は、英国型の自由主義の伝統が主に関心をもつ問題とは異なった問題に関心をもつデモクラシー運動と早くから結び付けられ、ほとんど同一視されるようになったのである》― F・A・ハイエク『自由主義』:序 1. 自由主義の様々な概念 During the period of their formation these ideas, which in the nineteenth century came to be known as liberalism, were not yet described by that name. The adjective 'liberal' gradually assumed its political connotation during the later part of the eighteenth century when it was used in such occasional phrases as when Adam Smith wrote of 'the liberal plan of equality, liberty, and justice'. As the name of a political movement liberalism appears, however, only at the beginning of the next century, first when in 1812 it was used by the Spanish party of Liberales, and a little later when it was adopted as a party name in France. In Britain it came to be so used only after the Whigs and the Radicals joined in a single party which from the early 1840s came to be known as the Liberal Party. Since the Radicals were inspired largely by what we have described as the Continental tradition, even the English Liberal Party at the time of its greatest influence was based on a fusion of the two traditions mentioned. – Ibid.《19世紀に自由主義として知られるようになったこれらの思想が形成された時期には、まだそのような名称で呼ばれてはいなかった。「自由」という形容詞は、徐々に政治的な意味合いを持つようになり、18世紀後半には、アダム・スミスが「平等、自由、正義の自由な計画」と書いた時のような特別な目的のための言い回しが用いられた。しかしながら、次世紀の初めになってはじめて、自由主義という政治活動の名称が登場し、1812年にスペインの政党リベラレスが使用したのが最初で、少し遅れてフランスで政党名として採用されたのである。イギリスでは、ホイッグ党と急進党が1840年代初頭から自由党として知られるようになった単一政党に合流して初めてそう呼ばれるようになった。急進派は、主に大陸の伝統としてこれまで述べてきたものに端を発していたので、最も影響力のあった頃のイギリス自由党でさえ基礎に置いていたのは、前述の2つの伝統が融合されたものであった》― 同In view of these facts it would be misleading to claim the term 'liberal' exclusively for either of the two distinct traditions. They have occasionally been referred to as the 'English', 'classical' or 'evolutionary', and as the 'Continental' or 'constructivistic' types respectively. In the following historical survey both types will be considered, but as only the first has developed a definite political doctrine, the later systematic exposition will have to concentrate on it. – Ibid.《このような事実を鑑(かんが)みれば、「自由」という用語を2つの異なる伝統のいずれかに限定して主張することは、誤解を招くことになるだろう。両者は時に応じ、それぞれ「英国型」、「古典型」、「進化型」、「大陸型」、「設計主義型」と呼ばれてきたのである》― 同
2024.11.03
コメント(0)
-
教育について(68)設計主義的自由主義
The one tradition, much older than the name 'liberalism', traces back to classical antiquity and took its modern form during the late seventeenth and the eighteenth centuries as the political doctrines of the English Whigs. It provided the model of political institutions which most of the European nineteenth century liberalism followed. It was the individual liberty which a 'government under the law' had secured to the citizens of Great Britain which inspired the movement for liberty in the countries of the Continent in which absolutism had destroyed most of the medieval liberties which had been largely preserved in Britain. --F. A. Hayek, Liberalism: Introduction 1. The different concepts of liberalism《前者の伝統は、「自由主義」という呼称よりもずっと古く、古典古代にまで遡(さかのぼ)り、17世紀後半から18世紀にかけて、英国ホイッグ党の政治方針として近代的な形と成った。それは、大半の19世紀欧州自由主義が模範とした政治制度のモデルとなった。英国では大部分が維持されていた中世の自由の大半を、絶対主義によって破壊された大陸諸国において、自由を求める運動を鼓舞したのは、「法の下の政府」が英国国民に保障した個人の自由であった》 ― F・A・ハイエク『自由主義』:序 1. 自由主義の様々な概念These institutions were, however, interpreted on the Continent in the light of a philosophical tradition very different from the evolutionary conceptions predominant in Britain, namely of it rationalist or constructivistic view which demanded a deliberate reconstruction of the whole of society in accordance with principles of reason. This approach derived from the new rationalist philosophy developed above all by René Descartes (but also by Thomas Hobbes in Britain) and gained its greatest influence in the eighteenth century through the philosophers of the French Enlightenment. Voltaire and J. J. Rousseau were the two most influential figures of the intellectual movement that culminated in the French Revolution and from which the Continental or constructivistic type of liberalism derives. – Ibid.《しかしながら、これらの制度は、大陸では、英国で優勢だった進化論的概念とはまったく異なった哲学の伝統、すなわち、理性の原理に従って社会全体を意図的に再構築することを要求する合理主義的ないしは設計主義的な考え方に照らして解釈された。この方法は、取り分け、ルネ・デカルト(さらに英国のトマス・ホッブズ)によって発展した新しい合理主義哲学に由来し、18世紀にはフランス啓蒙思想の哲学者たちによって最も大きな影響力を得た。ヴォルテールとJ・J・ルソーは、フランス革命に結実し、大陸主義的ないしは設計主義的な自由主義形態が派生した知的運動の中で最も影響力のあった2人であった》― 同The core of this movement, unlike the British tradition, was not so much a definite political doctrine as a general mental attitude, a demand for an emancipation from all prejudice and all beliefs which could not be rationally justified, and for an escape from the authority of 'priests and kings'. Its best expression is probably B. de Spinoza's statement that 'he is a free man who lives according to the dictates of reason alone'. – Ibid.《この運動の核心は、英国の伝統とは異なり、明確な政治政策というよりもむしろ一般的な精神的態度、すなわち、すべての先入観や合理的に正当化できないすべての信念からの解放、「司祭や王」の権威からの脱却を求めるものであった。その最も優れた表現が、恐らくB・ド・スピノザの「ただ理性が命ずるがまま生きる人は自由である」という言葉であろう》― 同These two strands of thought which provided the chief ingredients of what in the nineteenth century came to be called liberalism were on a few essential postulates, such as freedom of thought, of speech, and of the press, in sufficient agreement to create a common opposition to conservative and authoritarian views and therefore to appear as part of a common movement. – Ibid 《19世紀に自由主義と呼ばれるようになったものを構成する主な要素を規定するこれら2つの思想は、思想の自由、言論の自由、報道の自由といった幾つかの本質的公準において一致し、保守的で権威主義的な見解に共に反対したので、共同活動の一部であるかのように見えたのである》― 同
2024.11.02
コメント(0)
-
教育について(67)義務教育とは何か
《にもかかわらず、こうしたことについて、疑問や不審の声を上げる人が少ないのはなぜなのか。理由はさまざま考えられるだろうが、なんといっても大きいのは小・中学校の教育が「義務教育」と称されていることにあるのではないか。すなわち、小・中学校の教育は義務なのだから、選択の自由がなくても仕方がないという印象が強いために、誰もそれを疑問に思わないのである。 しかし、義務教育とは本来、「親が子どもに教育を施す義務」のことであって、国や政府が指定した学校に義務的に通わせるということではない。学校に通わせなくても十分な教育を与えられるのであれば、それはそれで「親の義務」を果たしたことになるはずなのだ》(渡部昇一『国民の教育』(産経新聞社)、p. 15) まずは、「義務教育」とは何かという問題がある。成程(なるほど)、日本国憲法は、第26条2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。と、子供に教育を受けさせる義務を親に負わせている。が、だからといって、子供たちは、選択の自由なく、否応なく決められた学校に通わなければならないということにはならない。義務教育とは、親が子供に教育を受けさせる義務があるというだけのことであって、行政が予め割り振った学校に通い、行政が定めた教育内容を履修しなければならないというような話ではない。自分が通いたい学校に通う自由は、憲法と何ら矛盾しない。 義務教育が画一的であるのはそれが義務なのだから仕方がないと思ってしまうのは、憲法の所為(せい)というよりも、戦後日本を覆う思想上の問題であろうと思われる。戦後日本人は、フランス革命よろしく、「自由」と「平等」は絶対的であると未だに刷り込まれている。 が、ここで注意すべきは、人権宣言における「自由」と、上に述べてきた「選択の自由」における「自由」とでは、自由の概念が異なっているということだ。The term〔=liberalism〕 is now used with a variety of meanings which have little in common beyond describing an openness to new ideas, including some which are directly opposed to those which are originally designated by it during the nineteenth and the earlier parts of the twentieth centuries. What will alone be considered here is that broad stream of political ideals which during that period under the name of liberalism operated as one of the most influential intellectual forces guiding developments in western and central Europe. This movement derives, however, from two distinct sources, and the two traditions to which they gave rise, though generally mixed to various degrees, coexisted only in an uneasy partnership and must be clearly distinguished if the development of the liberal movement is to be understood. -- F. A. Hayek, Liberalism: Introduction 1. The different concepts of liberalism《〔自由主義〕という用語は今や、19世紀から20世紀初頭にかけて元々それが明示した意味とは正反対の意味も含め、新しい思想に対し開かれていることを表す以外共通点がほとんどない様々な意味で用いられるようになった。ここで考察されるのは、リベラリズムの名の下に、西欧と中欧の発展を導く最も影響力のある知的勢力の1つとして作動した政治思想の幅広い流れだけである。しかしながら、この運動は、2つの異なる端(たん)に発し、それらが生み出した2つの伝統は、一般的には様々な程度混在していたとはいえ、不安定な結び付きの中で共存していたに過ぎず、自由主義運動の発展を理解するためには、明確に区別されなければならない》― F・A・ハイエク『自由主義』:序 1. 自由主義の様々な概念
2024.11.01
コメント(0)
-
教育について(66)日本の教育は社会主義的
《とはいえ、金がかからず、しかも安全度の高い教育改革案がなくもない。たとえば、これは年来の私の持論でもあるが、今、塾と呼ばれているものをすべて公認し、現行の正式の学校との区別を撤廃するというものである》(渡部昇一『国民の教育』(産経新聞社)、p. 14) 塾を公教育機関として公認するという渡部氏の教育改革案に私も賛成する。そのことによって、画一化され、身動きが取れなくなった公教育に風穴を空けようということである。《そのことを述べる前に、まず次のことを強調しておきたい。 それは、教育においては教育を受ける側の選択権が、何よりも尊重されなければならないという事実である。幼いころにおいては親の選択権、長じては親と当人の選択権が尊重されるべきであるというのが教育の鉄則である》(同、pp. 14f) 現在の公教育、特に義務教育には、「選択の自由」がない。通学区域が設定され、決められた小中学校にしか通えない。そのため、児童生徒に不公平があってはならないということで、どの学校も一律同じ教育環境、教育内容が提供されないといけないということで、身動きがとれなくなってしまっているのだ。どこかの学校が抜け駆けし、良い教育を提供しようものなら、教育の平等に反するものとして総スカンを食らうことになる。かくして、どこも同じの画一的教育が提供されることになるのである。《ところが今の教育制度では、その選択権はほとんど尊重されていない。 なるほど大都市には私立学校があり、多少の選択の余地はある。しかし、日本の大部分の地区には公立学校しかないのが現状である。そうした地方に住む人にとっては、割り当てられた公立学校に子弟を進ませるしかない。「教育の権利」という言葉が最近はよく使われるようだが、大多数の日本人にとっては義務教育レベルの「教育の権利」は有名無実になっているわけである》(同、p. 15) 「自由」があるとは、選択できるということである。が、日本の義務教育には選択権がない。だとすれば、日本の義務教育には自由がないということになる。詰まり、日本の義務教育は、自由主義ではなく社会主義的政策でしかないということだ。《これは戦時中の配給制度と似ている。配給制度の下では、A町内のB地区の人は、たとえば魚を買うとき、特定のCという魚屋からしか魚を買えなかった。今の学校制度も、地区によって義務教育の子どもの通う学校は決められている。「寄留(きりゅう)」という便宜手段が用いられ、学区城の適用も緩和され、狭い範囲での学校選択も最近ではようやく実現され始めるようになったが、子どもの通う学校を行政が決めるということは、戦時統制経済の時代に、魚を買う店を指定されていたのと同じ構造なのである》(同)
2024.10.31
コメント(0)
-
教育について(65)教育改革の方向性
《さすがに最近では、そうした杓子定規(しゃくしじょうぎ)な対応は人道にもとるという声もあり、学校長の裁量で、不登校の子どもにも卒業資格を与えることが許されるようになったという。 しかし、それはあくまでも便宜的、緊急避難的な措置にすぎない。大検のように制度化されたものではなく、悪く言えば「ごまかし卒業」である。そのようなかたちで卒業免状を与えられても、当の生徒も親も後ろめたい気持ちしか残らないのではなかろうか。 日本の学校教育、ことに義務教育が限界に来ているという事実は、最近になってわかったことではない。万単位に子どもたちが不登校になり、中途退学をしている現実は、何年も前からあったことだ。昭和59(1984)年、中曾根内閣が設置した臨教審(臨時教育審議会)でこの間題は論じられているから、それから数えてもすでに17年以上年月がたっている。 こうした状況に対して、これまで何か抜本的な対応策が1つでも行われたであろうか。その答えは言うまでもない。少なくとも公的な場においては抜本的な制度改革案はつくられなかったし、それどころか真剣に討議さえされていないのが現実である。かくして、事態は悪化の一途をたどって今日に至っている》(渡部昇一『国民の教育』(産経新聞社)、pp. 13f) 見方を変えれば、「欧米に追い付け追い越せ」を目標とした教育が、欧米に追い付いた今、目標喪失し、右往左往してしまっているということだ。何事であれ、上手く行っているときは、粗(あら)の存在は問題にならない。が、一度(ひとたび)推進力が失われれば、粗が気になって仕方がなくなるのだ。 が、教育目標が喪失された中で、不登校児童の問題を幾ら考えても、ただの弥縫策(びほうさく)にしかならないだろう。矢張り、「欧米に追い付け追い越せ」という目標に代わる新たな教育目標を設定することが先になければならない。 欧米が作った「答え」を鵜呑みにする時代は終わり、日本が自ら問題を設定し、「答え」を創り出すことが求められているということだ。 少し具体的に言えば、これまでのようなコツコツ真面目に働けばよいという時代から、労働人口減少も相俟(あいま)って、高い付加価値を生み出す産業構造への転換が求められている。そのためには、「知識」よりも「発想」や「知恵」といったものが尊重される教育というものが必要となってくるのではないかということだ。《このような状況を抜本的に変え、学校教育を根底から救う道はあるのかというと、そこにはおのずから制限がある。あまりにドラスティック(=極端)な改革で、莫大な予算を必要とするものは非現実的であり、あまりに革新的な内容であるためにどんな弊害が起こるか予想がつかないようなことをやってはならない。教育においては軽はずみな「実験」は許されない。何か問題が現れた場合、その直接の被害を受けるのは当の子どもたちだからである》(同、p. 14)
2024.10.30
コメント(0)
-
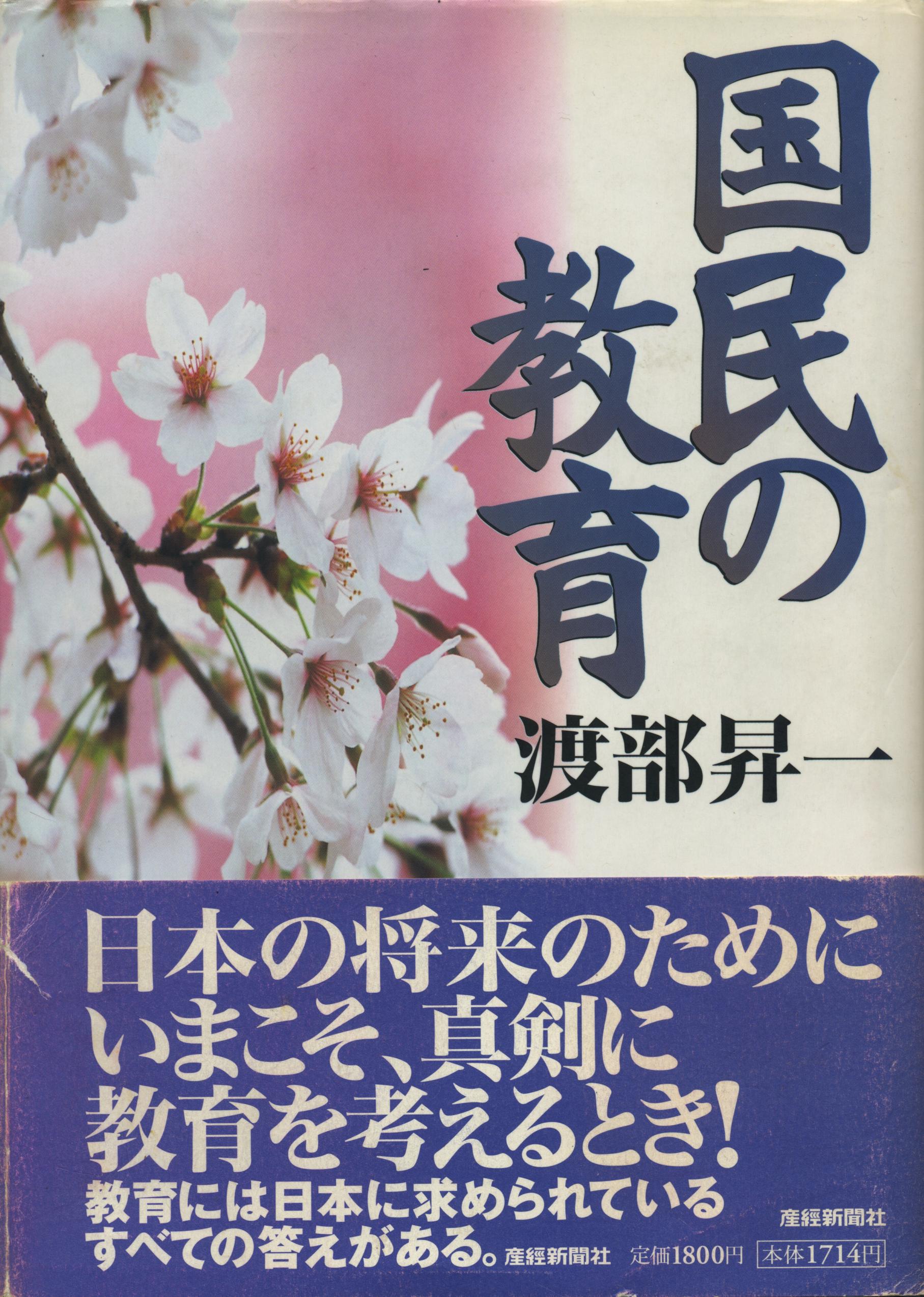
教育について(64)増え続ける不登校児童生徒
《平成12年度中に30日以上欠席した不登校の児童・生徒の数が、日本全国の小・中学校で約13万4千人にも達していたことが、平成13年5月の文部科学省の調査でわかった。これは、前年度より約4千300人も増加していて、最多を更新するものだ。小学校では279人に1人、中学校では38人に1人の割合で不登校の子どもたちが存在することになる》(渡部昇一『国民の教育』(産経新聞社)、p. 12) 最新の令和4年度の調査では、小・中学校の不登校児童生徒数は、全体の生徒数が減少しているにもかかわらず、約29万9千件に倍増している。《小・中学校で不登校の児童・生徒の数が10万人を突破したのは、平成10年のことであったが、それからわずか2年の間に3万人、率にすれば3割強も増加していたというわけである。高校を中退している生徒の数も、平成10年度でやはり10万人近くに達していたが、これも13万人以上にまで膨れあがっているかもしれない。 ひと口に13万というが、これは定員500人の学校に換算すれば、260校分に当たる。つまり、今の日本では260校分の小・中学生が不登校になり、同じく260校分の高校生が中途退学しているということになる。 小・中・高合わせて520校分の生徒が「消えている」という一事をもってしても、日本の学校教育がすでに破綻(はたん)しかかっていることは明らかであろう。にもかかわらず、こうした事態に対して、日本の文部科学省は文字どおり手をこまねいているだけである》(同、pp. 12f) が、私には、文科省は手を拱(こまね)きすらしてしないように思われる。「どこ吹く風」なのだ。文科官僚にとって気になるのは、教育現場の問題ではなく、「天下り」先の方であろう。したがって、生徒数が減少しようが、大学の数は一向に減らない。また、公教育では対応しきれない教育改革によって、入試がお金の掛かるものとなり、私的教育機関が潤う結果となってしまってもいる。《中途退学した高校生に対しては、大検、つまり大学入学資格検定という制度があるからまだ救いがある。大検の資格を得れば、高校を中退しても、また最初から高校に入らずとも、大学に進むことができるからである。 ところが、義務教育を標榜する小・中学校ではそうはいかない。義務教育には、大検に相当する検定試験はない。だから原則論をふりかざせば、学校に行きたくない子どもや行きたくとも行けない子どもは義務教育未修了者となり、上の学校に進学する道を塞(ふさ)がれることになってしまう》(同、p. 13)
2024.10.29
コメント(0)
-
教育について(63)「水平化の鎌」を捨てよ
《以上教育改革論を概観してわかることは、いずれも教育改革の必要性については認めていても、教育荒廃がどこにあって、どこにその原因があるかということになると、少しも一致していない。そうである限り、教育改革は急いでやるべきではない》(加藤寛「教育荒廃の根源にあるもの」:世界を考える京都座会編『学校教育活性化のための7つの提言』(PHP研究所)、p. 57) が、一方で、このまま画一的な教育を続けていては、日本の将来は危うい。 問題は、戦後日本を覆っている「平等思想」にある。公教育は、平等に提供されなければならないという枠の中で、ああでもない、こうでもないと弄(いじく)ったところで、何の解決にもならないということだ。 教育の自由化を成功させるには、同時に、戦後日本の平等主義を改めることから始めなければならない。優れたものを刈り取ろうとする「水平化の鋭い鎌」(キルケゴール)を捨てなければならない。そして、「真の自由」を取り戻さなければならない。《かつて〔昭和〕46年答申としてだされた中教審答申が尊重されているときくが、冒頭に指摘したようにそれは当然でもある。ちょうど46年、ニクソン・ショックで象徴的にいわれたように、日本経済の工業化がついにアメリカに影郷を与えるまでになったことであり、45年万博の成功によってそれが確認された時期であったからである。 しかし、高度成長に酔っていた日本は、転換の時代を必ずしも意識していなかった。他の多くの改革案とともに46年答申もついに消滅してしまった。 もし、その時からいくつかの実験・検討をしておけば、今頃はまさに教育改革への方針を明確に打ちだせたであろう》(同、pp. 57f) 教育改革が結局立ち消えになってしまうのは、平等主義が根本に存在するからである。教育が画一的となって、活力が失われてしまっているのは平等主義の所為(せい)である。平等主義がある限り、日本の教育の再生はない。《今なし得ることは、大きな改革ではなく、以上、5つの教育改革論の根源にある問題を、1つでもよいから風穴をあけてみることであろう。ではそれは何であろうか. 第1は教科書問題であったが、それはつまるところ、教師がどのように教科書を利用するかということにすぎない。教師の教育問題である。 第2はエリート選抜の問題であったが、それは敗者復活の弾力化で対応できる。学校の多角化である。 第3は幼児教育の問題だが、これは、学校教育の補完である。 第4は道徳教育の復活だが、これも教師そのものである。 第5は公教育問題だが、「官主私従」の考え方を改めることである。 こうしてみると、この5つの教育改革論に共通している根源の問題は、学校間の競争がすすむ状況を作りだせば教師の意欲が高まり、それが教師の研修効果を高め、子供たちが教師を尊敬していく途(みち)だということである。 そのためには、高等教育はすでに学校間の競争がすすんでいるから、とりあえずは、小・中学校の競争をいかにすすめるかであろう。それには、学区制を自由化する措置を講じ、公立間の競争、公立・私立の競争を可能にすることである。 それによって、義務教育制がもたらしやすい、囚(とら)われた生徒の状態を変化させるし、年齢主義を課程主義に変えていくことにもつながっている。こうして蟻穴(ぎけつ)からすすめていくのが妥当なのではあるまいか》(同、pp. 58f)
2024.10.28
コメント(0)
-
教育について(62)教育の本旨
《教育の本旨は、ただ知識を増やすことにあるのではなくて、人が人であるための共通の規範を学ぶことにある。 学窓(がくそう)を去った人たちが、何年かしてしばしば述懐することは、自分が学校教育で学んだ知識の内容ではなく、いろいろな友だちとの交際であり、先生たちの人生訓であることが多い。やはりそれは教育というものが単なる知識の追求ではないということを示している。 家庭においてはもちろんであるが、学校においても社会のルールとして守るべき基本を考え、社会人として生きていくための共通の規範教育に何故、今の学校は臆病なのだろうか》(加藤寛「教育荒廃の根源にあるもの」:世界を考える京都座会編『学校教育活性化のための7つの提言』(PHP研究所)、p. 56) 私なら、教育の本旨すなわち真の目的を、〈共通の規範〉に限定せず、「日本人としての共通性を高めること」とでも言うだろうか。日本人として最低身に付けておかねばならないことを学ぶということである。知識的なこともあれば、道徳的なこともあろう。言葉を学び、文化や歴史を学ぶ。そして、日本社会を成り立たせている、目には見えないが確(しか)と存在する「法」(law)を学ぶということだ。そうした共通の基盤の上に、社会の自由は機能する。《“抜本的な改革”という言葉がしばしば使われているけれども、教育改革は非常に多くの問題を含んでいる。したがって抜本的な教育改革というものはあり得ないのだということを、まず認識することが、教育改革の原点であり、教育側の自由化・競争化こそが本来の姿である》(同) フリードマンは言う。《われわれは、競争原理を導入しさえすれば、学校教育はアメリカの全階層に開かれ、教育の質も大幅に改善されると確信している。 残念ながら、先の見通しはよくない。政治家の反応をみると、現状維持を求めているのがよくわかる。国民が抗議をするたびに、教育関係機関からはいろいろな報告書が出されてきた。だが、どれもこれも、レーガン大統領の教育諮問委員会の報告書と似たり寄ったりだ。つまり、現行制度の構造は是認し、教育委員会や校長や教員に、今までと違うことをもっとうまいやり方で行えと強要しているだけにすぎない。そのうえ、教育制度の改善には何と費用がかかることかといって、お涙頂戴の茶番を演じてさえいる。 真の改革は、これとは全く別物である。私立学校の中には、教育の質は公立よりずっとよく、費用も半分以下ですむところも多い。学校教育についても、民間市場でやれる仕事を政府がやると2倍の費用がかかるという一般法則が当てはまるわけだ。肝心かなめの問題は.教育費をつり上げることではなく、消費者、つまり学生と親を王様の座に戻すことなのである》(ミルトン・フリードマン『奇跡の選択 自由経済をはばむものは何か』(三笠書房)加藤寛監訳、pp. 264f)
2024.10.27
コメント(0)
-
教育について(61)教育の突然変異も必要
《上級学校においても同様で、選抜試験を常に知識に頼ることは好ましくない。各学校が自由に入試方法を工夫し、それぞれの適性に応じた選抜の仕方が考えられるべきである。 たとえば信州大学では1つの科目が優秀な成績であれば.ほかの科目がたとえ零点であっても採用するという、独特な入試方法をとっているが、こうしたやり方も1つの方法であろう。いろいろな工夫が、いま子供たちが持っている単一な勉強の仕方が教育だというような考え方を、次第に是正することになるだろう》(加藤寛「教育荒廃の根源にあるもの」:世界を考える京都座会編『学校教育活性化のための7つの提言』(PHP研究所)、p. 55) 「大学は、入学は広く、卒業は狭く、に改革すべし」が私の持論である。大学独自の教育課程に必要な条件を満たしていれば、広く入学を許可し、必要な単位を取得できなければ、卒業証書を授与しないという厳格さが求められる。詰まり、しっかり勉強し研究に励まない学生は卒業させないという形への変革が必要だということだ。《一方では、そんな教育改革はあまりにも秩序がなさすぎるのではないか、教育というもののシステムがこわれてしまうのではないか、という危惧を抱く人が出てくるかもしれない。 しかし、それは工業化の過程で歪(ひず)みが生じた教育システムを改革するために不可欠なことであって、根強い学歴信仰や、あるいは社会がもっている学歴偏重と相まって、是正していかなければならないものなのである》(同、pp. 55f)The opening up of new markets, foreign or domestic, and the organizational development from the craft shop and factory to such concerns as U.S. Steel illustrate the same process of industrial mutation—if I may use that biological term—that incessantly revolutionizes the economic structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one. This process of Creative Destruction is the essential fact about capitalism. It is what capitalism consists in and what every capitalist concern has got to live in. – Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism & Democracy, Part II: VII. The Process of Creative Destruction(国内外の新市場の開拓や、手芸用品の店や工場からU.S.スチールのような企業へ組織が発展することは、(生物学的用語を使わせてもらえば)産業の突然変異と同じ過程を示している。この創造的破壊の過程こそが、資本主義についての本質的な事実である。それこそが資本主義であり、あらゆる資本主義企業が生きなければならないものなのだ)―ヨーゼフ・A・シュンペーター『資本主義・社会主義・民主主義』:第2部:第7章 創造的破壊の過程 シュンペーターの顰(ひそみ)に倣うなら、今の教育改革にも「突然変異」が必要なのではないかということだ。勿論、進化論的な意味での「突然変異」とは、人工的に起こすようなものではないから、同一に語れないのだけれども、学校選択の自由を認める教育改革があまりにも突飛であるとの心配には及ばない、進化には、時として「突飛」と思われることもまた必要になるということを確認できれば、それでよい。
2024.10.26
コメント(0)
-
教育について(60)義務教育は小学校だけで十分
《現在の教育の内容からすれば、小学校6年間で最低教育水準は、十分に確保できる》(加藤寛「教育荒廃の根源にあるもの」:世界を考える京都座会編『学校教育活性化のための7つの提言』(PHP研究所)、p. 54) そう考えるのなら、義務教育は小学校だけでよいということになる。勿論、最低水準をどう考えるのかという問題もあるが、仮に義務教育を小学校だけで終えることになれば、中学校以上の教育はもっと柔軟なものとなり得るということだ。《さらにいえば、語学教育などはむしろ小学校から始めるべきで、これをいま中学校から始めていることが、かえって子供たちの意欲を殺(そ)いでしまっている》(同) 私は、この意見には反対である。少なくとも小学校は義務教育であり、日本人に必要な最低限の知徳体を身に付けることが最優先でなければならない。また、日本人に必要なのは、従来の日本式の英語教育であって、日本では使い様(よう)のない実践英語ではない。文法中心の日本式英語教育は、英語を学習する中で日本語を磨くものであり、この作業を欠けば、国語力の低下に繋がるに違いない。 今後、人口減少社会にあって、日本人に必要なのは高い国語力であって、日常的に英語を話すことのない日本社会において、英会話力を義務教育化することは要らぬお世話と言うべきだ。《そういう意味で、中学校の義務教育制は廃止する方向へもっていくべきであろうが、しかしそれも一律に行う必要はない。ある学校は義務教育を5年で終り、あるいは6年で終り、あとは中学校へ行っても行かなくても自由であるとか、米国のように義務教育は2年間だけで、あとはほかの学校へ行って勉強するというような考え方もあり得る。むしろ自由に適性に応じた教育をすることが望ましい》(同、p. 55) 地域によっては、中学校や高校も義務化する自由があってもよいように思うが、全国的には、義務教育は小学校だけとすべきだろう。中学校を義務教育から外すことを危険視する人達もいるだろうが、今でも義務教育ではない高校へ97%超の生徒が進学しているのであるから、中学校を義務教育から外したからといって、中学へ進学しなくなるとは考えにくい。が、進学せず、家業を継ぐなどして就職したとしても、それはそれで問題はないだろう。実際、中学校で習うようなことを必要としない職業は少なくない。《たとえばバイオリニストとして有名な辻久子さんなどは、小学校へはほとんど通わずに、英才教育を受け、世界的なバイオリニストになったことはよく知られているが、このような例は日木でもほかにたくさんある。つまり、このように能力を備えているものが、特殊な教育によってその才能を伸ばしていくことこそが、真の教育なのである》(同)
2024.10.25
コメント(0)
-
教育について(59)集団教育
《学校選択の自由が保障されるような学校教育を考えていけば、よく議論の対象とされる6・3制の問題も、それほど大きな問題ではないことに気づくだろう。 義務教育というものが、小学校ぐらいではある程度必要であっても、しかし必ずしも学校を経なくても一定の教育水準を達成することは不可能ではない。 たとえば年齢によってその共通知識と能力を認定するような学力認定制度があって、それに合格さえすれば義務教育はそれで終了したという形にしていけば、あえて魅力のない学校に縛られなくても教育を受けることは可能である》(加藤寛「教育荒廃の根源にあるもの」:世界を考える京都座会編『学校教育活性化のための7つの提言』(PHP研究所)、pp. 53f) 小学校6年、中学校3年の義務教育は、社会人に必要な知識・道徳・身体を身に付けるための最低保証なのであって、例えば、中学卒業認定試験に合格できるのであれば、必ずしも公的教育機関に通わなくてもよい、というような柔軟な考え方はできないのかということだ。 日本は、基本的に「集団社会」であるから、集団の中で教育を受けることが望ましい。が、一方で、一旦集団から外れれば生きていけないような社会であってもならないだろう。 日本の強みは、平均的な教育力の高さにあり、それを束ねた組織力こそが日本の「生き筋」であろうと思われる。翻(ひるがえ)って、その組織にも、かつての松下幸之助、盛田昭夫、本田宗一郎のような優れた指導者が必要だ。が、優れた指導者は、平均的教育からは生まれない。また、芸術家や科学者といった人々も、平均的教育とは無縁のものであろう。こういった人達は、本来「集団教育」には馴染まない。《このようにいうと、すぐ、学校に通わせなければ集団行動のできない反社会的な子供が増えるのではないかという批判が出てくるけれども、決してそのようなことは一般的ではない》(同、p. 54) 集団に馴染まない人間は「反社会的」とまで言うのは偏見が過ぎる。組織の頂点に立つ指導者は常に孤独であるが、だからといって「反社会的」ということにはならないだろう。また、個人の才能に依存する職業の人達を「反社会的」と言って爪弾(つまはじ)きにするのも非寛容に過ぎる。《もし学校に通わずに認定試験によって教育水準を認めてもらう制度ができたとしても、そういう方法でやってやろうというだけの自信のある親、あるいは子供がどれだけいるだろうか。 米国などでは.その点でかなり自由な教育が行われているが、それでも学校に通わずに教育を受けている子供は、1割か2割程度しかいないという統計がある。したがってそのような自由が認められたとしても、子供たちが学校を経ないで学習するということはまず考えられない。 しかし、学校に行かなくても義務教育制度の教育ぐらいはできるということであれは、無理をしてまで学校に行くことはないだろう。子供たちを9年間も義務教育で締る理由は全くない》(同、p. 54) 集団教育を受けるのが基本中の基本ではあるとしても、集団教育に馴染めない人達に集団教育を無理強いしないことも、多様性ある柔軟な社会を構成構築するためには必要なのではないだろうか。
2024.10.24
コメント(0)
-
教育について(58)平等信仰をいかに打ち破るのかが鍵
《どの方法をとるにせよ、学校教育への政府の財源には変わりがない。子供のあるなしや、子供の学校が私立か公立かを問わず、すべての国民が政府の教育費をまかなうために納税義務を負う点も、現在と変わりない。ただ、子供の通学校を決めるのは政府の官僚ではなく、親自身であるという点が決定的に違う。つまり、どの学校の資金を増やし、どの学校は減らすかを決めるのも、親自身である。また、私立学校を選ぶ親は.税金と授業料という形で教育費を二重払いしないでもすむ。 その結果、教職員は、本当のお客様である生徒の要望に答えざるをえなくなる。「お客様は神様です」とは、まさに競争市場特有のスローガンなのだ。授業料クーポンは、このスローガンを学校教育に適用したものである》(ミルトン・フリードマン『奇跡の選択 自由経済をはばむものは何か』(三笠書房)加藤寛監訳、pp. 252f) 「クーポン制」は、学校選択の自由を有効たらしめるための手段である。したがって、そもそも学校選択の自由がなければ「絵に描いた餅」にしかならない。 学校を自由に選択するためには、教育はどの学校も平等に提供されねばならないという平等信仰の呪縛をまず解かねばならない。が、これは殊の外(ことのほか)難しそうである。学校によって教育内容が異なるのは、「差別」であると言い出す人が出てくることは容易に予想される。 戦後日本人は、平等は「絶対善」だと思い込み、信じているから、この人達を説得することはほとんど不可能ではないか。また、少なからず共産社会に移行することを望む人達(共産主義シンパ)もいるであろうから、「自由」を拡大することなど論外だと言う声も少なくないに違いないのだ。《公立よりいい学校はどこかと、死に物狂いで探す親が多い実情をみれば、クーポン制のよさにも納得がいこう。 必死で学校を探した結果、カトリックを信じてもいないのに、子供をカトリックの教区学校へ適わせる親が増えている。なぜなら、教区学校はカトリック教会が多額の財政補助をしているので、ふつうの親でもあまり負担がかからない唯一の私立学校だからだ。また、私立の授業料のべらぼうな高さにもかかわらず、通学者の比率が増えているのをみても、親たちがどれだけ学校選びに夢中かがわかる》(同、p. 253) 仮に平等の呪縛が解け、画一的な学校が解放され、それぞれの学校が独自の運営を出来るようになれば、学校選択の自由も意味のあるものとなるし、「クーポン制」がこの自由を有効たらしめることになるであろう。だとすれば、平等信仰を如何に打ち破るのかがこの問題の鍵となるということだ。
2024.10.23
コメント(0)
-
教育について(57)「クーポン制」
《いま学校選択の主たる理由は経済的な理由である。とくにそれは親たちに共通した考え方になっている。しかし経済的な理由によって私学か国公立かを選択することは.聞達いではないだろうか。学校選択の自由を拡大するためには、私学であろうと国公立であろうと、同じ選択でなければならない》(加藤寛「教育荒廃の根源にあるもの」:世界を考える京都座会編『学校教育活性化のための7つの提言』(PHP研究所)、p. 51) が、大きくは受験偏差値にしか大学が特色がない段階で、学校選択の自由の拡大だけを言っても虚しい。学校選択の自由を有効たらしめるためには、大学改革が先に、あるいは、少なくも同時進行でなされなければならない。《その選択の条件を等しくするための試みは、私学教育費減税もその1つだし、いまや国公立大学を廃止して、すべて独立の法人にするのも一法である。そうなることによって初めて国公立も教育の独立を守ることができるし、私学という言葉も必要がなくなってくる。国公立、私学はすべて1つになり、ただ学校法人としてのみ存在する》(同) 国公立大学、私立大学が同じ基準で競争し競合するのであれば、国公立か私立かにこだわる必要はない。考え方としては分かるが、国公立大学を廃止するというのは極論過ぎる。《そして子供たちに対しては、政府が奨学金を与えることによって学校の選択をさせるべきである。そうすれば経済的な理由によって学校を区別する必要もなくなってくる。かねてからクーポン側を強化せよという考え方が多くの専門家によって主張されているのだから、こうした考え方は決して異常な考え方ではないはずである。要するに私学と国公立の区別をなくすことによって、学校選択の自由は拡大されていくだろう》(同、pp. 51f) ここでフリードマンの言う「クーポン制」について見ておこう。《われわれはすでに、「授業料クーポン」計画を提案している。これは、親に子供の学校を自由に選べるようにする一方、資金負担の方法は現行どおりとするものだ。 授業料クーポン側が導入されれば、州や地方自治体が公立学校に出している助成金は、授業料クーポンという形で親が受け取るようになる。このクーポンは学校教育のためにだけ使える。クーポンの使用は公立、私立を問わないが、公立学校の財源はこのクーポンだけとする、というのがいちばん簡単なやり方だ。ほかに、公立学校はクーポンだけでなく、州や地方自治体からじかに助成金を受け取ってもよいとする方法がある。あるいは、クーポンは私立学校でのみ使えるとしてもよい》(ミルトン・フリードマン『奇跡の選択 自由経済をはばむものは何か』(三笠書房)加藤寛監訳、p. 252)
2024.10.22
コメント(0)
-
教育について(56)私学助成金
《こうした議論に対して、ただちに出てくる反論は、私学が政府から助成金をもらっていること自体がおかしいのではないか、むしろ私学のほうこそ官に依存しようとしているのではないか、という議論である。 しかし、これは工業化時代を脱して.次の新しい時代へ変わる過渡的な現象であると考えるべきである。そもそも助成金の問題は、まだ十分に多様な学校の設立の自由が認められていないときに、国公立の能力だけでは急増する進学者を受け入れることができなかったために、国公立に代って私学が引き受けたという結果から生まれてきたものである》(加藤寛「教育荒廃の根源にあるもの」:世界を考える京都座会編『学校教育活性化のための7つの提言』(PHP研究所)、pp. 50f) 国公立、私立にかかわらず、大学生の教育費を国家が負担するということであれば、問題にするような話ではないだろう。大学に補助金を出すと考えるから、どうして国が私立大学を補助するのか、それは、憲法に抵触するのではないかとの懸念がもたれるのだ。第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 「私学助成金」に関しては、基本的に合憲と考えてよいと思われるけれども、違憲とする学説もあり、すっきりしない。《私学教育は,重大な国民的関心事であるという意味で「公的」だ,といえなくはない。しかしながら,私学教育が重要だから89条の制約を軽く考えていいというわけはない。論者によっては,89条の制約は26条の教育を受ける権利によって解除されている,と論ずるものもある。が,89条の法意に留意したとき,教育を受ける権利を実効的とする助成方法にも限界があることにわれわれは気づくべきだ。89条違反の疑義を生ぜず,しかも26条のために公費を支出するやり方は,現行の私学助成のほかにも存在する。それは,親または子どもに対して直接に助成することだ。そうすれば,89条違反の問題は生じないばかりか,親子の側には選択の機会が増え,学校側は生徒子供をより多く獲得しようと競争し,国家の補助金は最も有効に活用されるだろう。現行の私学助成は,学校が努力をしなくても資金を獲得できる制度であって,かえって教育を受ける権利を阻害している》(阪本昌成『憲法I 国制クラシック【第2版】』(有斐閣)、pp. 254f) この意見は、フリードマンの「クーポン制」に通ずるものだ。《したがって、初めから私学が官に依存したわけではない。ただ私学の理念に立てば、たとえ政府からの助成金があったとしても、私学はあくまでも学問の独立を主張し、教育の独立を主張することに上って行政の支配を脱するようにしなければならない。それは教育基本法においても明確にうたわれているところである。もとより学校選択の自由を拡大していくためにも、私学がいつまでも、そのような状況に甘んじていることは許されない》(加藤、同、p. 51)
2024.10.21
コメント(0)
全5875件 (5875件中 1-50件目)
-
-

- みんなのレビュー
- レポ☆カリカリ 堅い 豆 パスタスナッ…
- (2024-12-10 06:00:08)
-
-
-

- 楽天写真館
- 10 日 ( 火曜日 ) の日記 寒い …
- (2024-12-10 05:14:26)
-
-
-

- 避難所
- 【ぼくらの国会・第855回】ニュー…
- (2024-12-09 22:02:13)
-








