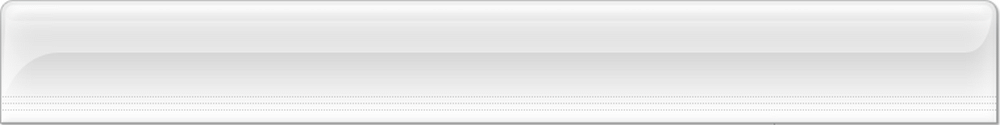PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
Freepage List
November , 2025
October , 2025
September , 2025
October , 2025
September , 2025
August , 2025
July , 2025
July , 2025
Comments
カテゴリ: 歴史全般
■「その時歴史は動いた『源義経 栄光と悲劇の旅路』」批判-その4
番組では義経が壇の浦合戦に際して平家方の武将に働きかけ、河野水軍、熊野水軍、田口水軍を寝返らせたとしていた。これは歴史に関して無知であり、平家物語も吾妻鏡も見ていないことを自白する間違いである。
河野氏は平家勢力の真っ只中で、頼朝の旗揚げに時を置かず反平家の旗を掲げ、幾多の困難に遭いながら義経が来るまで支え切ったことは、歴史書を見れば直ぐ判ることである。それを壇の浦合戦の時に平家から寝返ったとは、どこから出て来る戯言か理解に苦しむ。
熊野水軍にしても同様で、河野氏と同日に熊野水軍も屋島にはせ参じている。これも壇の浦合戦の時に寝返ったのではない。阿波の田口氏は確かに壇の浦合戦の際に寝返り、そのため平家の作戦が源氏方に筒抜けになってしまった。いずれも平家物語、吾妻鏡に記されていることである。
戦後、田口氏は源氏勝利に貢献したにも拘わらず、旧主を裏切ったとして処刑されている。一方河野氏は功績を高く評価され、西国武士で河野氏のみ重く用いられ、守護に準じる立場を認められた。河野氏の処遇は田口氏の処遇とは対極の位置にある。両者の差は何か。NHKはこの点についても認識を新たにすることが必要である。
■「その時歴史は動いた『源義経 栄光と悲劇の旅路』」批判-その5
番組では屋島合戦についても重要なな事実を無視ないしは見逃している。平家物語と吾妻鏡に記されていることを抜き出して見よう。(平は平家物語、吾は吾妻鏡)
元歴2年2月18日 義経荒れる海を渡り、阿波に上陸(平・吾)
義経平家五千のうち田内勢三千が河野氏討伐のため遠征中であることを知る(平)
20日 義経屋島を攻撃(平)
21日 平家讃岐國志度道場に篭る(平・吾)
熊野別当湛増二百余艘、源氏に加はる(平・吾)
河野四郎通信、一千余騎の軍兵を率いて源氏に加はる(平)
河野四郎道信、粧三十艘之兵舩、參加(吾)
田内左衛門降る(平・吾)
22日 梶原景時以下源氏勢屋島到着(平・吾)
この記述から義経が屋島を攻めた時、平家方は田内(でんない)左衛門則良以下三千が河野通信討伐のため不在で、屋島は極めて手薄であり、田内勢は遂に合戦に間に合わなかったこと、義経は手薄な屋島を攻めたこと、河野・熊野両軍とも同日に参陣していること、などが判る。これを仔細に検討すると、重要な問題が浮かんで来る。番組で何故この記述に目を向けなかったのか理解し難い。そもそもこの記述だけからも、河野・熊野両軍は壇の浦合戦の時に平家方から寝返ったのでないことは明白である。NHKはこの点をどう説明するのか。
更に上記の記述から幾つかの疑問が生じる。河野・熊野両軍とも屋島までの所要日数を考えると、義経の阿波上陸前に領国を出発していることになる。これは何故か。両軍とも単独で平家を攻める積りでやって来たのか。また同じ日に到着したのは偶然か。田内勢も同日に屋島に帰着しているが、これも偶然か。
以下これらを検討して見よう。
■「その時歴史は動いた『源義経 栄光と悲劇の旅路』」批判-その6
義経の阿波上陸を知らず、単独で平家と戦う力のない両者が、同じ日に到着したのは何故か。それは義経・通信・湛増の間で練り上げた約束だったと考えるしかないであろう。つまり、源氏・河野水軍・熊野水軍の三者が21日に屋島で合流する。これが義経の作戦だったのではなかろうか。
ところが運悪く直前に台風に襲われ、源氏の舟が多数損傷し、約束の日に間に合わない事態となった。河野・熊野水軍は既に出発しているはず故、手を拱いていては源氏が約束を違えたことになり、作戦全体が崩壊する。その緊急事態を打開するため、義経は行ける者だけで急行し、21日に屋島で合流しようとしたのではなかろうか。平家物語などが伝えるように、僅か150騎で荒れる海を強行突破して阿波に上陸したのは、このような事情によると考えられる。
では僅か150騎で勝算はあったのか。ここで注目されるのは、田内左衛門則良率いる三千が河野氏討伐に向かい、屋島が手薄だったと言う記述である。平家物語では、義経は上陸後屋島の兵力を尋ねたところ、田内勢三千が河野氏討伐に遠征し、屋島に残るのは凡そ二千、そのうち千ほどはあちこちに分散配置され、屋島には千もいるかどうかと言う答えを得たことを記している。この記述は吾妻鏡にはない。
この記述は本当か。義経は事前に屋島が手薄なのを知っていたのではないか。平家は天皇以下守らねばならない大切な人々を抱えている。戦闘になった場合これは大変な重荷で、その警護に多くの将兵を割かねばならない。その結果屋島に千ほどの兵力があっても、防衛口の一つ一つの兵力は少なく、実際の戦闘場面での兵力は互角となる。義経は平家方兵力の実態を知っていればこそ、僅か150騎でも行きさえすれば何とでもなると渡海を強行したのではなかったか。平家物語が記すように、敵状を知らずに飛び出したのなら、それは蛮勇に過ぎない。一の谷合戦でも綿密な作戦で平家本陣を一気に壊滅させた名将義経なればこそ、敵方兵力の状況を知るが故に採り得た、臨機応変の決断であったと考えるのが至当であろう。(続く)
■「その時歴史は動いた『源義経 栄光と悲劇の旅路』」批判-その7
平家物語は通信がめ召しても来なかったから討伐軍を派遣したと記している。四国の武士達で屋島に行かなかったのは河野氏だけではない。それなのに何故河野氏だけを、しかも平家物語によると、屋島の総兵力の6割もの大軍を動員しているが、何故そこまでして討たねばならなかったのか。これには余程の事情があった筈である。
河野氏の史書「水里玄義」や「予陽河野家譜」などに田内勢との合戦が記されているので、それらを参照すると、平家を烏帽子親とする平家の御家人高市氏を通信が攻め、高市氏の鴛小山城(現伊予市)を陥とし、屋島から発向してきた田内勢を比志城(現大洲城)に迎え撃ち、5日間の激戦の末に撃退したと言う。なお、比志城の合戦の前に通信の伯父福良新三郎通豊が途中で田内勢迎え討って戦死している。この記述は通信が高市氏を攻めたので、田内勢が救援に来て、それと通信が戦ったかのように見える。ところが高市氏を攻めたのが1月16日、通豊の討死が22日、比志城の戦いが25日から5日間と記されている。これから勘定すると、田内勢は鴛小山城が攻められる前に既に出発していたことになり、河野氏を討伐を決意させた何かが、これ以前に起きていたはずである。
当時高市氏は国府(今の今治市)の近くの高市郷と伊予市と、所領を二箇所持っていた。これ以降は全くの推測であるが、通信は高市郷を先に攻めたのではなかろうか。高市氏は平家の御家人であるので見捨てるわけに行かず、更に通信に国府一帯を抑えられては芸予諸島も河野水軍に支配される惧れもある。この事態は平家にとっては脅威であり、放置するわけに行かない。そこで脅威の元凶である河野通信の討伐を決意したのではなかろうか。
河野氏側から考えると、高市氏を攻め国府一帯を抑えようとすれば当然平家が通信を討とうとすることは予想できる筈であり、現に田内勢三千が発向して来た。先に述べたように河野氏が単独で平家と戦う力は無いにも拘わらず、このような危険を冒すにはそれなりの狙いと収拾策が無ければならない。それは義経と示し合わせた陽動作戦であり、うまく平家軍が出て来たらその隙に義経が屋島を攻めると言う作戦だった可能性が浮かんで来る。
このように考えると屋島が手薄だったのは偶然ではなく、義経が仕組んだ作戦に平家方がまんまと引っ掛かったことになる。そして義経が僅かな兵力で荒れる海を強行渡海したのは、折角うまく運んでいた作戦が、仕上げの段階で嵐により台無しになるのを救うための非常手段であったことになる。
■「その時歴史は動いた『源義経 栄光と悲劇の旅路』」批判-その8
平家物語も吾妻鏡も伊予における合戦について何も記していないが、田内左衛門尉が屋島への帰還に際し、討ち取った首を先に送り、首実検をしたとの記述があるので、伊予において相当な合戦があったことは事実と見て間違いない。
この記述で疑問に思うのは、首実権が2月19日で、義経の攻撃が始まった日であるが、平家方は義経が迫っているのをまだ気が付いていないのか、田内勢の帰還を急ぐよう指令した形跡が窺えないことである。結局田内勢は合戦に間に合わず、21日に戻りはしたものの屋島は既に陥落した後で、義経の命を受けた伊勢三郎の口車に騙されて降伏してしまった。平家方の状況把握力と情報収集力の弱さをここでも感じる。
このように見て行くと、河野通信は何らかの陽動作戦で平家軍を屋島から引き出し、義経の屋島攻撃に際してその平家軍を最後まで屋島から分断しておく役割を果たしたと言える。つまり、義経が勝てる状況を作り出したのは通信であり、義経勝利の陰の演出者が通信であった。戦後河野氏が功績を高く評価され、西国武士の中でただ一人守護に準じる地位を与えられたのは、屋島合戦における貢献によるものではなかったか。
■「その時歴史は動いた『源義経 栄光と悲劇の旅路』」批判-その9
以上述べたように河野氏は壇の浦合戦の時寝返ったのではなく、最初から旗色鮮明に反平氏で戦い、源氏の勝利に大きく貢献した。先に紹介した屋島合戦に関する平家物語や吾妻鏡の記述に気が付かないのか無視したのか知らないが、天下のNHKが教養番組である「その時歴史は動いた」の中で、史実と全く違うことを平気で語る無神経さに憤りを感じる。その責任は重い。宮尾登美子氏も歴史を見る目を持っていないと断ぜざるを得ない。
吉川英治氏は「新平家物語」の中で、通信から田内勢が出て来たとの連絡を受け、でかしたと誉めそやしたと書いていると聞く。平家物語・吾妻鏡の記述から肝腎なポイントにきちんと注目している証拠であり、流石と言うべきである。
述べたいことはまだあるが、屋島合戦に関する私見はここで一先ず終わりとする。
番組では義経が壇の浦合戦に際して平家方の武将に働きかけ、河野水軍、熊野水軍、田口水軍を寝返らせたとしていた。これは歴史に関して無知であり、平家物語も吾妻鏡も見ていないことを自白する間違いである。
河野氏は平家勢力の真っ只中で、頼朝の旗揚げに時を置かず反平家の旗を掲げ、幾多の困難に遭いながら義経が来るまで支え切ったことは、歴史書を見れば直ぐ判ることである。それを壇の浦合戦の時に平家から寝返ったとは、どこから出て来る戯言か理解に苦しむ。
熊野水軍にしても同様で、河野氏と同日に熊野水軍も屋島にはせ参じている。これも壇の浦合戦の時に寝返ったのではない。阿波の田口氏は確かに壇の浦合戦の際に寝返り、そのため平家の作戦が源氏方に筒抜けになってしまった。いずれも平家物語、吾妻鏡に記されていることである。
戦後、田口氏は源氏勝利に貢献したにも拘わらず、旧主を裏切ったとして処刑されている。一方河野氏は功績を高く評価され、西国武士で河野氏のみ重く用いられ、守護に準じる立場を認められた。河野氏の処遇は田口氏の処遇とは対極の位置にある。両者の差は何か。NHKはこの点についても認識を新たにすることが必要である。
■「その時歴史は動いた『源義経 栄光と悲劇の旅路』」批判-その5
番組では屋島合戦についても重要なな事実を無視ないしは見逃している。平家物語と吾妻鏡に記されていることを抜き出して見よう。(平は平家物語、吾は吾妻鏡)
元歴2年2月18日 義経荒れる海を渡り、阿波に上陸(平・吾)
義経平家五千のうち田内勢三千が河野氏討伐のため遠征中であることを知る(平)
20日 義経屋島を攻撃(平)
21日 平家讃岐國志度道場に篭る(平・吾)
熊野別当湛増二百余艘、源氏に加はる(平・吾)
河野四郎通信、一千余騎の軍兵を率いて源氏に加はる(平)
河野四郎道信、粧三十艘之兵舩、參加(吾)
田内左衛門降る(平・吾)
22日 梶原景時以下源氏勢屋島到着(平・吾)
この記述から義経が屋島を攻めた時、平家方は田内(でんない)左衛門則良以下三千が河野通信討伐のため不在で、屋島は極めて手薄であり、田内勢は遂に合戦に間に合わなかったこと、義経は手薄な屋島を攻めたこと、河野・熊野両軍とも同日に参陣していること、などが判る。これを仔細に検討すると、重要な問題が浮かんで来る。番組で何故この記述に目を向けなかったのか理解し難い。そもそもこの記述だけからも、河野・熊野両軍は壇の浦合戦の時に平家方から寝返ったのでないことは明白である。NHKはこの点をどう説明するのか。
更に上記の記述から幾つかの疑問が生じる。河野・熊野両軍とも屋島までの所要日数を考えると、義経の阿波上陸前に領国を出発していることになる。これは何故か。両軍とも単独で平家を攻める積りでやって来たのか。また同じ日に到着したのは偶然か。田内勢も同日に屋島に帰着しているが、これも偶然か。
以下これらを検討して見よう。
■「その時歴史は動いた『源義経 栄光と悲劇の旅路』」批判-その6
義経の阿波上陸を知らず、単独で平家と戦う力のない両者が、同じ日に到着したのは何故か。それは義経・通信・湛増の間で練り上げた約束だったと考えるしかないであろう。つまり、源氏・河野水軍・熊野水軍の三者が21日に屋島で合流する。これが義経の作戦だったのではなかろうか。
ところが運悪く直前に台風に襲われ、源氏の舟が多数損傷し、約束の日に間に合わない事態となった。河野・熊野水軍は既に出発しているはず故、手を拱いていては源氏が約束を違えたことになり、作戦全体が崩壊する。その緊急事態を打開するため、義経は行ける者だけで急行し、21日に屋島で合流しようとしたのではなかろうか。平家物語などが伝えるように、僅か150騎で荒れる海を強行突破して阿波に上陸したのは、このような事情によると考えられる。
では僅か150騎で勝算はあったのか。ここで注目されるのは、田内左衛門則良率いる三千が河野氏討伐に向かい、屋島が手薄だったと言う記述である。平家物語では、義経は上陸後屋島の兵力を尋ねたところ、田内勢三千が河野氏討伐に遠征し、屋島に残るのは凡そ二千、そのうち千ほどはあちこちに分散配置され、屋島には千もいるかどうかと言う答えを得たことを記している。この記述は吾妻鏡にはない。
この記述は本当か。義経は事前に屋島が手薄なのを知っていたのではないか。平家は天皇以下守らねばならない大切な人々を抱えている。戦闘になった場合これは大変な重荷で、その警護に多くの将兵を割かねばならない。その結果屋島に千ほどの兵力があっても、防衛口の一つ一つの兵力は少なく、実際の戦闘場面での兵力は互角となる。義経は平家方兵力の実態を知っていればこそ、僅か150騎でも行きさえすれば何とでもなると渡海を強行したのではなかったか。平家物語が記すように、敵状を知らずに飛び出したのなら、それは蛮勇に過ぎない。一の谷合戦でも綿密な作戦で平家本陣を一気に壊滅させた名将義経なればこそ、敵方兵力の状況を知るが故に採り得た、臨機応変の決断であったと考えるのが至当であろう。(続く)
■「その時歴史は動いた『源義経 栄光と悲劇の旅路』」批判-その7
平家物語は通信がめ召しても来なかったから討伐軍を派遣したと記している。四国の武士達で屋島に行かなかったのは河野氏だけではない。それなのに何故河野氏だけを、しかも平家物語によると、屋島の総兵力の6割もの大軍を動員しているが、何故そこまでして討たねばならなかったのか。これには余程の事情があった筈である。
河野氏の史書「水里玄義」や「予陽河野家譜」などに田内勢との合戦が記されているので、それらを参照すると、平家を烏帽子親とする平家の御家人高市氏を通信が攻め、高市氏の鴛小山城(現伊予市)を陥とし、屋島から発向してきた田内勢を比志城(現大洲城)に迎え撃ち、5日間の激戦の末に撃退したと言う。なお、比志城の合戦の前に通信の伯父福良新三郎通豊が途中で田内勢迎え討って戦死している。この記述は通信が高市氏を攻めたので、田内勢が救援に来て、それと通信が戦ったかのように見える。ところが高市氏を攻めたのが1月16日、通豊の討死が22日、比志城の戦いが25日から5日間と記されている。これから勘定すると、田内勢は鴛小山城が攻められる前に既に出発していたことになり、河野氏を討伐を決意させた何かが、これ以前に起きていたはずである。
当時高市氏は国府(今の今治市)の近くの高市郷と伊予市と、所領を二箇所持っていた。これ以降は全くの推測であるが、通信は高市郷を先に攻めたのではなかろうか。高市氏は平家の御家人であるので見捨てるわけに行かず、更に通信に国府一帯を抑えられては芸予諸島も河野水軍に支配される惧れもある。この事態は平家にとっては脅威であり、放置するわけに行かない。そこで脅威の元凶である河野通信の討伐を決意したのではなかろうか。
河野氏側から考えると、高市氏を攻め国府一帯を抑えようとすれば当然平家が通信を討とうとすることは予想できる筈であり、現に田内勢三千が発向して来た。先に述べたように河野氏が単独で平家と戦う力は無いにも拘わらず、このような危険を冒すにはそれなりの狙いと収拾策が無ければならない。それは義経と示し合わせた陽動作戦であり、うまく平家軍が出て来たらその隙に義経が屋島を攻めると言う作戦だった可能性が浮かんで来る。
このように考えると屋島が手薄だったのは偶然ではなく、義経が仕組んだ作戦に平家方がまんまと引っ掛かったことになる。そして義経が僅かな兵力で荒れる海を強行渡海したのは、折角うまく運んでいた作戦が、仕上げの段階で嵐により台無しになるのを救うための非常手段であったことになる。
■「その時歴史は動いた『源義経 栄光と悲劇の旅路』」批判-その8
平家物語も吾妻鏡も伊予における合戦について何も記していないが、田内左衛門尉が屋島への帰還に際し、討ち取った首を先に送り、首実検をしたとの記述があるので、伊予において相当な合戦があったことは事実と見て間違いない。
この記述で疑問に思うのは、首実権が2月19日で、義経の攻撃が始まった日であるが、平家方は義経が迫っているのをまだ気が付いていないのか、田内勢の帰還を急ぐよう指令した形跡が窺えないことである。結局田内勢は合戦に間に合わず、21日に戻りはしたものの屋島は既に陥落した後で、義経の命を受けた伊勢三郎の口車に騙されて降伏してしまった。平家方の状況把握力と情報収集力の弱さをここでも感じる。
このように見て行くと、河野通信は何らかの陽動作戦で平家軍を屋島から引き出し、義経の屋島攻撃に際してその平家軍を最後まで屋島から分断しておく役割を果たしたと言える。つまり、義経が勝てる状況を作り出したのは通信であり、義経勝利の陰の演出者が通信であった。戦後河野氏が功績を高く評価され、西国武士の中でただ一人守護に準じる地位を与えられたのは、屋島合戦における貢献によるものではなかったか。
■「その時歴史は動いた『源義経 栄光と悲劇の旅路』」批判-その9
以上述べたように河野氏は壇の浦合戦の時寝返ったのではなく、最初から旗色鮮明に反平氏で戦い、源氏の勝利に大きく貢献した。先に紹介した屋島合戦に関する平家物語や吾妻鏡の記述に気が付かないのか無視したのか知らないが、天下のNHKが教養番組である「その時歴史は動いた」の中で、史実と全く違うことを平気で語る無神経さに憤りを感じる。その責任は重い。宮尾登美子氏も歴史を見る目を持っていないと断ぜざるを得ない。
吉川英治氏は「新平家物語」の中で、通信から田内勢が出て来たとの連絡を受け、でかしたと誉めそやしたと書いていると聞く。平家物語・吾妻鏡の記述から肝腎なポイントにきちんと注目している証拠であり、流石と言うべきである。
述べたいことはまだあるが、屋島合戦に関する私見はここで一先ず終わりとする。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[ 歴史全般] カテゴリの最新記事
-
[歴史]漢委奴国王印の委奴とは November 4, 2009
-
中世美濃と尾張の境界(2) August 23, 2006 コメント(1)
-
中世美濃と尾張の境界(1) August 23, 2006 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.