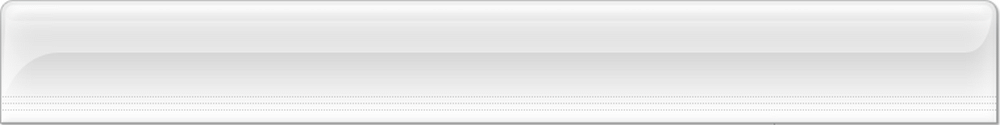PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
Freepage List
November , 2025
October , 2025
September , 2025
October , 2025
September , 2025
August , 2025
July , 2025
July , 2025
Comments
カテゴリ: 歴史全般
■屋島合戦に勝った義経の気持ち
屋島合戦について平家物語・吾妻鏡と河野氏関係の史書とを付き合わせた結果、前者が黙して語らぬ部分を後者が矛盾無く補い、屋島合戦の全体像が見えた気がしている。子供の頃、源平盛衰記の屋島合戦を読んだ時、たった150騎でどうやって勝ったのか不思議でならなかったのを今でも覚えている。その疑問を漸く解き明かしてすっきりした気分になった。
だが、ふと嵐に襲われなかったらどうなっていたかと考えた時。義経の苦い気持ちに思い至った。作戦がすんでのところで破綻する危機を切り抜けて勝利を得たが、もし作戦が順調に進んだら、それこそ完全勝利だったのではないか。それを逃がし、義経にとっては悔いの残る勝利だったのではなかったか。
予定通り2月21日に源氏・河野・熊野の全軍が屋島で合流していたら、恐らくは屋島を陸海から完全に包囲したであろう。田内勢は分断されたまま故、屋島は極めて手薄である。従って平家方は戦っても勝ち目は無く、海にも源氏方の兵船がひしめいて逃れることも出来ず、義経は天皇も三種の神器も取り戻し、完全勝利を収めたであろう。実際には嵐のため予定が狂い、勝つには勝ったが平家を海に逃がしてしまった。それ故義経にしてみれば、会心の勝利にはほど遠く、大いに悔いの残る勝利では無かったかと推察する。
嵐のお陰で平家はなお生き延び、最終決戦の場が残されることになったが、これは滅び行く平家への天の哀れみだったかも知れない。かくして源平の無敗のエース義経と知盛の最初にして最後の決戦が、壇の浦で行われることとなった。
■河野通信と源範頼に共通する役割
屋島合戦においても壇の浦の合戦でも河野通信の華々しい活躍は伝えられていない。それにも拘わらず戦後河野通信の貢献は高く評価されたことは先に述べた通りである。通信の果たした役割は、屋島合戦に際して、源氏が勝つ状況を作り出したことにあったと考えるのが至当と思う。壇の浦合戦の最後の場面で阿波水軍田口氏の寝返りが勝敗を左右したが、寝返りの原因は、屋島で義経の軍門に下った嫡子田内左衛門尉の身の上を田口氏が案じてのことと言われるが、これも通信の一連の作戦行動の結果である。このように考えると屋島・壇の浦合戦共に、通信は合戦で目立つ活躍は伝わっていないが、合戦の勝因を作ったことが大きな貢献であった。
屋島合戦勝利の陰の演出者が通信だったと考えると、源範頼の役割が似たものであったように映る。範頼は源氏の本隊を率いて各地を転戦し、これに対し平家方は常にエース知盛が相対し、範頼は苦戦の連続であった。そのため義経の華々しい活躍と比較すると範頼は如何にも見劣りし、凡将のように見られている。屋島合戦の時も知盛は範頼に相対していて屋島にいなかった。このように範頼が知盛を引き付け、その隙を義経が衝いたと見ると、範頼は源平の戦い全般にわたって、屋島合戦における通信の役割を演じたことになる。
範頼は一般に思われているような凡将だったのだろうか。本当は常に知盛が立ち向かわねばならぬ程の武将だったのではなかったか。そうだったとすると範頼は損な役割を演じ続けたことになる。範頼の実像はどうだったのか、検討し直す必要がありそうに思う。
義経と言う武将とその戦法について、義経は奇襲が得意、背後から攻める、と言う言葉をしばしば耳にする。これは一の谷合戦と屋島合戦の時の義経の戦法を評している言葉である。
一の谷合戦の逆落としは、平家側から見れば予想もしなかった所から攻められたので確かに奇襲であったろう。だが仔細に眺めれば、義経は相手方の一番の弱点、守備の盲点を見付け、そこから一番効果の大きい攻撃目標である敵本陣を衝いたのであって、非常に合理的な戦法と言うべきである。この攻撃を成功させるため、配下の全軍をもって平家の防衛線を攻撃して、敵の注意をそちらに釘付けにしている。
この作戦を背後を衝いたと見るのはどうも腑に落ちない。平家は義経軍が進撃して来る方に向かって防衛線を敷いている。それを背後から攻めたと見るのは理解に苦しむ。背後を衝いたとは防衛線の後ろから攻めたことを言う。この場合、海から攻めたなら、平家は背後から攻められたことになる。
屋島合戦における義経の攻撃を奇襲とか背後から攻めたと見るのは、より理解し難い。義経は阿波に上陸してから小さな戦闘を行っている。その義経の動きが屋島に伝わらなかったとするなら、平家の情報連絡能力の弱さに呆れる。これを奇襲と感じるのは、敵状把握能力の欠如と言うほかはない。更に、これを背後からの攻撃と見るのは、正面とは海側とする通念でもあるのだろうか。屋島の防衛線は陸側に対しても敷かれていた筈である。それを何故背後を衝いたと見るのか理解出来ない。
屋島合戦における平家軍の戦い方は誠に不様である。もし知盛が屋島にいたら、兵力で遥かに劣る義経は勝てなかったかも知れない。尤も義経は知盛がいない平家軍の脆さまで計算し、知盛不在の時期を選んだとも考えられる。知盛不在が義経勝利の一つの要因であったとするなら、その状況を作り出したのは範頼であることに、もっと注目する必要が有るように思う。
屋島合戦について平家物語・吾妻鏡と河野氏関係の史書とを付き合わせた結果、前者が黙して語らぬ部分を後者が矛盾無く補い、屋島合戦の全体像が見えた気がしている。子供の頃、源平盛衰記の屋島合戦を読んだ時、たった150騎でどうやって勝ったのか不思議でならなかったのを今でも覚えている。その疑問を漸く解き明かしてすっきりした気分になった。
だが、ふと嵐に襲われなかったらどうなっていたかと考えた時。義経の苦い気持ちに思い至った。作戦がすんでのところで破綻する危機を切り抜けて勝利を得たが、もし作戦が順調に進んだら、それこそ完全勝利だったのではないか。それを逃がし、義経にとっては悔いの残る勝利だったのではなかったか。
予定通り2月21日に源氏・河野・熊野の全軍が屋島で合流していたら、恐らくは屋島を陸海から完全に包囲したであろう。田内勢は分断されたまま故、屋島は極めて手薄である。従って平家方は戦っても勝ち目は無く、海にも源氏方の兵船がひしめいて逃れることも出来ず、義経は天皇も三種の神器も取り戻し、完全勝利を収めたであろう。実際には嵐のため予定が狂い、勝つには勝ったが平家を海に逃がしてしまった。それ故義経にしてみれば、会心の勝利にはほど遠く、大いに悔いの残る勝利では無かったかと推察する。
嵐のお陰で平家はなお生き延び、最終決戦の場が残されることになったが、これは滅び行く平家への天の哀れみだったかも知れない。かくして源平の無敗のエース義経と知盛の最初にして最後の決戦が、壇の浦で行われることとなった。
■河野通信と源範頼に共通する役割
屋島合戦においても壇の浦の合戦でも河野通信の華々しい活躍は伝えられていない。それにも拘わらず戦後河野通信の貢献は高く評価されたことは先に述べた通りである。通信の果たした役割は、屋島合戦に際して、源氏が勝つ状況を作り出したことにあったと考えるのが至当と思う。壇の浦合戦の最後の場面で阿波水軍田口氏の寝返りが勝敗を左右したが、寝返りの原因は、屋島で義経の軍門に下った嫡子田内左衛門尉の身の上を田口氏が案じてのことと言われるが、これも通信の一連の作戦行動の結果である。このように考えると屋島・壇の浦合戦共に、通信は合戦で目立つ活躍は伝わっていないが、合戦の勝因を作ったことが大きな貢献であった。
屋島合戦勝利の陰の演出者が通信だったと考えると、源範頼の役割が似たものであったように映る。範頼は源氏の本隊を率いて各地を転戦し、これに対し平家方は常にエース知盛が相対し、範頼は苦戦の連続であった。そのため義経の華々しい活躍と比較すると範頼は如何にも見劣りし、凡将のように見られている。屋島合戦の時も知盛は範頼に相対していて屋島にいなかった。このように範頼が知盛を引き付け、その隙を義経が衝いたと見ると、範頼は源平の戦い全般にわたって、屋島合戦における通信の役割を演じたことになる。
範頼は一般に思われているような凡将だったのだろうか。本当は常に知盛が立ち向かわねばならぬ程の武将だったのではなかったか。そうだったとすると範頼は損な役割を演じ続けたことになる。範頼の実像はどうだったのか、検討し直す必要がありそうに思う。
義経と言う武将とその戦法について、義経は奇襲が得意、背後から攻める、と言う言葉をしばしば耳にする。これは一の谷合戦と屋島合戦の時の義経の戦法を評している言葉である。
一の谷合戦の逆落としは、平家側から見れば予想もしなかった所から攻められたので確かに奇襲であったろう。だが仔細に眺めれば、義経は相手方の一番の弱点、守備の盲点を見付け、そこから一番効果の大きい攻撃目標である敵本陣を衝いたのであって、非常に合理的な戦法と言うべきである。この攻撃を成功させるため、配下の全軍をもって平家の防衛線を攻撃して、敵の注意をそちらに釘付けにしている。
この作戦を背後を衝いたと見るのはどうも腑に落ちない。平家は義経軍が進撃して来る方に向かって防衛線を敷いている。それを背後から攻めたと見るのは理解に苦しむ。背後を衝いたとは防衛線の後ろから攻めたことを言う。この場合、海から攻めたなら、平家は背後から攻められたことになる。
屋島合戦における義経の攻撃を奇襲とか背後から攻めたと見るのは、より理解し難い。義経は阿波に上陸してから小さな戦闘を行っている。その義経の動きが屋島に伝わらなかったとするなら、平家の情報連絡能力の弱さに呆れる。これを奇襲と感じるのは、敵状把握能力の欠如と言うほかはない。更に、これを背後からの攻撃と見るのは、正面とは海側とする通念でもあるのだろうか。屋島の防衛線は陸側に対しても敷かれていた筈である。それを何故背後を衝いたと見るのか理解出来ない。
屋島合戦における平家軍の戦い方は誠に不様である。もし知盛が屋島にいたら、兵力で遥かに劣る義経は勝てなかったかも知れない。尤も義経は知盛がいない平家軍の脆さまで計算し、知盛不在の時期を選んだとも考えられる。知盛不在が義経勝利の一つの要因であったとするなら、その状況を作り出したのは範頼であることに、もっと注目する必要が有るように思う。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[ 歴史全般] カテゴリの最新記事
-
[歴史]漢委奴国王印の委奴とは November 4, 2009
-
中世美濃と尾張の境界(2) August 23, 2006 コメント(1)
-
中世美濃と尾張の境界(1) August 23, 2006 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.