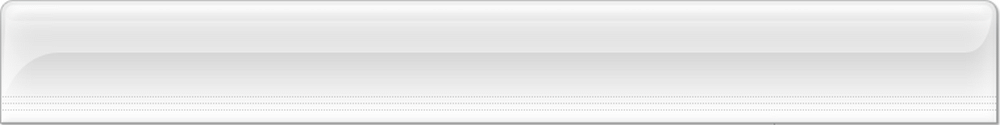PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
Freepage List
November , 2025
October , 2025
September , 2025
October , 2025
September , 2025
August , 2025
July , 2025
July , 2025
Comments
カテゴリ: 伊豫の今と昔の資料と考察
第1回シンポジウム「河野氏と湯築城をとりまく諸問題」
開催の趣旨:文献史学と考古学の研究者によって、遺跡を媒介として伊予の中世史について共通の課題を設定し、互いの方法を持ち寄って研究、交流し、総合的に伊予の中世史を論じていく。
報告者:川岡勉教授、西尾和美教授(文献史学)。 中野良一氏、柴田圭子氏、松村さを里氏(考古学)
全体の纏めは後日行うこととして、ここでは中野良一氏の瓦に関する見解について記す。
1.瓦の紋様
長曽我部氏の岡豊城で出土した瓦と同笵ではないが同文。紋様の寸法は一致しているが、瓦全体の大きさや厚さは異なる。両者の紋様はシャープさが異なる。岡豊城の瓦の紋様はシャープで、版木が新しいことを示す。湯築城のそれは、かなり使い込まれた版木で造られたものである。同文であることは、同じ工人によって作られたものである。ただし、両者の硬さは異なるので、焼いた窯は異なる。これは出来上がったものを運んだのではなく、別々の地域で焼いたことを意味する。
(注:資料に同文、同笵とあるのでその字を使ったが、同文は同紋、同笵は同版と同義か?)
2.長曽我部氏の技術の伝播
3.湯築城で岡豊城と同文の瓦が出土したことは、長曽我部氏の影響があったことを示す。
4.出土した場所は大手門を入って左側から南に伸びる溝で、纏めて埋まっていた。
この問題提起に対し、日和佐氏(愛媛)、松田氏(高知)らからそれぞれ見解が示された。
A.中野氏が示した紋様の瓦が出土するのは、岡豊城、中村城と湯築城だけである。長曽我部氏が侵攻した城全部に存在するものではない。
B.畝状竪掘は長曽我部氏の技術と言うよりは、高岡郡の技術である。長曽我部氏には複数の軍団があり、高岡勢が侵攻した跡に畝状竪掘が残されているが、その他の軍団が進んだ地域には無い。
C.縄張りは地勢と強く関係する。地勢との関係で見なければならぬ。湯築城の東北部の切り欠きも地勢の関係である。
D.畝状竪掘は最初新潟で見つかり、全国にある。毛利氏にもある。これの伝播経路は一つではなく、複数の経路を考える必要がある。
まだ色々とあったと思うが、記憶に残った中の主なものを記した。この発表と討論を聞いての感想を記す。
ア.岡豊城の出土瓦と同文の瓦が出土したことは、長曽我部氏と河野氏の間に何らかの関係があった可能性を示唆するものではあるが、長曽我部氏が湯築城を陥としたことを意味すると見るのは短絡的に過ぎるのではないか。
イ.以前、長曽我部軍の進攻年月日を整理したことがあるが、湯築城近くまで来たとき、秀長軍が四国に上陸し、湯築城を攻める間は無かったと感じた。
ウ.川岡先生は長曽我部軍が攻めたことがはっきりしている城に関しては、戦闘を示す一次史料が存在するが、湯築城での戦闘を示す史料が見当たらないことを指摘していらっしゃる。当時湯築城には小早川氏の家臣が常駐していたので、ここで戦闘があれば、小早川氏、或いは毛利氏の文書に記録が残る筈だが、それも無いとのこと。
オ.瓦が捨てられていた溝は、湯築城が現役の間は常時使用されていたものである。その溝に埋めたと言うことは溝が不要となったことを意味し、その時期は湯築城が廃城となった後でなければならない。
カ.今回問題となっている瓦と同文或いは同笵瓦は他の地域には存在しないのか。存在するなら、そちらとの関係も考慮しなければならない。
以上記したように、結論を出すにはまだ資料不足である。ここで言えるのは、湯築城から岡豊城の出土瓦と同じ紋様を持つ瓦が出土したこと、文献史学の立場から長曽我部軍が湯築城を陥とした、或いは湯築城で戦ったことを示す史料が現時点では見つかっていないと言うことで、結論は今後の研究を待たねばならない。結論は出ないが非常に面白い内容であった。
開催の趣旨:文献史学と考古学の研究者によって、遺跡を媒介として伊予の中世史について共通の課題を設定し、互いの方法を持ち寄って研究、交流し、総合的に伊予の中世史を論じていく。
報告者:川岡勉教授、西尾和美教授(文献史学)。 中野良一氏、柴田圭子氏、松村さを里氏(考古学)
全体の纏めは後日行うこととして、ここでは中野良一氏の瓦に関する見解について記す。
1.瓦の紋様
長曽我部氏の岡豊城で出土した瓦と同笵ではないが同文。紋様の寸法は一致しているが、瓦全体の大きさや厚さは異なる。両者の紋様はシャープさが異なる。岡豊城の瓦の紋様はシャープで、版木が新しいことを示す。湯築城のそれは、かなり使い込まれた版木で造られたものである。同文であることは、同じ工人によって作られたものである。ただし、両者の硬さは異なるので、焼いた窯は異なる。これは出来上がったものを運んだのではなく、別々の地域で焼いたことを意味する。
(注:資料に同文、同笵とあるのでその字を使ったが、同文は同紋、同笵は同版と同義か?)
2.長曽我部氏の技術の伝播
3.湯築城で岡豊城と同文の瓦が出土したことは、長曽我部氏の影響があったことを示す。
4.出土した場所は大手門を入って左側から南に伸びる溝で、纏めて埋まっていた。
この問題提起に対し、日和佐氏(愛媛)、松田氏(高知)らからそれぞれ見解が示された。
A.中野氏が示した紋様の瓦が出土するのは、岡豊城、中村城と湯築城だけである。長曽我部氏が侵攻した城全部に存在するものではない。
B.畝状竪掘は長曽我部氏の技術と言うよりは、高岡郡の技術である。長曽我部氏には複数の軍団があり、高岡勢が侵攻した跡に畝状竪掘が残されているが、その他の軍団が進んだ地域には無い。
C.縄張りは地勢と強く関係する。地勢との関係で見なければならぬ。湯築城の東北部の切り欠きも地勢の関係である。
D.畝状竪掘は最初新潟で見つかり、全国にある。毛利氏にもある。これの伝播経路は一つではなく、複数の経路を考える必要がある。
まだ色々とあったと思うが、記憶に残った中の主なものを記した。この発表と討論を聞いての感想を記す。
ア.岡豊城の出土瓦と同文の瓦が出土したことは、長曽我部氏と河野氏の間に何らかの関係があった可能性を示唆するものではあるが、長曽我部氏が湯築城を陥としたことを意味すると見るのは短絡的に過ぎるのではないか。
イ.以前、長曽我部軍の進攻年月日を整理したことがあるが、湯築城近くまで来たとき、秀長軍が四国に上陸し、湯築城を攻める間は無かったと感じた。
ウ.川岡先生は長曽我部軍が攻めたことがはっきりしている城に関しては、戦闘を示す一次史料が存在するが、湯築城での戦闘を示す史料が見当たらないことを指摘していらっしゃる。当時湯築城には小早川氏の家臣が常駐していたので、ここで戦闘があれば、小早川氏、或いは毛利氏の文書に記録が残る筈だが、それも無いとのこと。
オ.瓦が捨てられていた溝は、湯築城が現役の間は常時使用されていたものである。その溝に埋めたと言うことは溝が不要となったことを意味し、その時期は湯築城が廃城となった後でなければならない。
カ.今回問題となっている瓦と同文或いは同笵瓦は他の地域には存在しないのか。存在するなら、そちらとの関係も考慮しなければならない。
以上記したように、結論を出すにはまだ資料不足である。ここで言えるのは、湯築城から岡豊城の出土瓦と同じ紋様を持つ瓦が出土したこと、文献史学の立場から長曽我部軍が湯築城を陥とした、或いは湯築城で戦ったことを示す史料が現時点では見つかっていないと言うことで、結論は今後の研究を待たねばならない。結論は出ないが非常に面白い内容であった。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[伊豫の今と昔の資料と考察] カテゴリの最新記事
-
[歴史]元親は四国統一できずの記事 June 10, 2010 コメント(6)
-
[歴史]湯築城資料館で開催中の企画展「道… November 18, 2009
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.