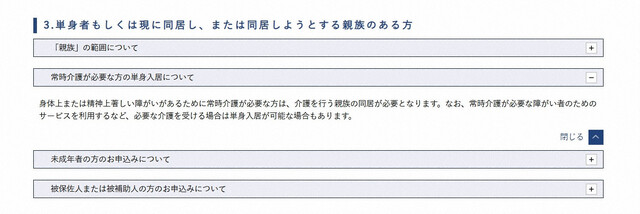-
1

「自衛隊に入ろう」 高田渡、 「戦争小唄」 泉谷しげる
今日、毎日新聞の一面に「最後の外交努力」という見出しを見つけて、この歌が浮かんできた。毎日新聞というのは、マスコミの中ではもっともリベラルだと僕は思っている。リベラルだから部数を伸ばすことが難しく苦労している。その毎日新聞でさえも、戦争に結びつく行動を「努力」と表現してしまう。何かいいことをしているのではないかと錯覚させる。この「努力」は、殺す側の努力であって、殺される側にとってはして欲しくない「努力」であって、「努力」を無条件にいいことだと思い込んでいる多くの日本人を誤解させることになりそうな気がしていやな気分になった。僕のように「努力」が嫌いな人間は、こういう嘘に対しては、思いっきり皮肉っぽくそれをほめあげて馬鹿にするという、こういう歌を歌いたくなってくる。この歌はどちらも30年以上も前の歌じゃないかと思えるようなものだが、この歌に歌われている状況はほとんど変わりがないみたいだ。大まじめに正義を振りかざす殺す側を笑い飛ばしてやりたいものだ。高田渡の歌は、勘違いした自衛隊関係者が、自衛隊の宣伝の歌にしようとしたくらい、自衛隊をほめあげているのだが、そのほめあげているところをよく考えると、そんなことしかほめるところがないのかと、そう思えてくる歌だ。スポーツをやりたい人、鉄砲や戦車や飛行機に興味がある人、学歴や年齢も問わないということだから、そういう人材は大歓迎ですよ、というセリフを勘違いしたのか、自衛隊員の募集に使えると思ったんだろうか。でも、よく考えてみると、あまり深く考えない、体さえ丈夫だったら、戦争というゲームのいい駒になる、という呼びかけに聞こえるんだけれどな。平和を守るために武器が必要で、アメリカに頼らなければならないんだというのはまさに今の状況と同じだ。30年以上この状況は変わらずに来たわけだ。でも、これが嘘だというのをどうしたら多くの日本人が理解するようになるのかな。アメリカの歴史を見たら、「アラモの砦」なんかで象徴されるように、大義名分を作るためなら、平気で自国民でさえ犠牲にする国なのに、そんな国が本当に守ってくれると本気で信じているんだろうか。アラモの砦というのは、先住民族を皆殺しにするための大義名分を作りたいために、わざと孤立させて、先住民族に襲わせて、先に彼らに皆殺しにさせたところだ。彼らが先にやったのだから、どれだけ残酷なことをしてもいいのだという理由付けのためにやった。それ以上に残酷なことは、日常的にやっていたにもかかわらず、最後の仕上げには、そういう演出を行ったわけだ。安保条約というのは、アメリカの利益がある限りで日本を守るという安全保障条約に過ぎないのに、それがなければ日本は安全でないと思い込んでいる日本人はたくさんいる。だから、日本は安保条約がある限り自立した外交が出来ないでいるんだと思う。アメリカの利益にならないことをしたら、守ってもらうことが出来ないからだ。実際には、アメリカぐらいテロにねらわれている国はないのだから、日本にとって戦争という可能性が限りなくなくなってきた現在という時は、むしろアメリカにべったりすり寄っていることで生じるテロの危険の方が大きくなるんじゃないかとも思ったりする。この歌の時代と一つ違うのは、この時代は「悪いソ連や中国をやっつけましょう」ということだったけれど、それがアフガニスタンやイラクに変わってしまっただけなのかな。でもこれはひどい変わり方だ。ソ連や中国なら、一応の驚異は、嘘の中でも本当らしさがあったけれども、アフガニスタンやイラクは、アメリカにとっては全然驚異でもなんでもないのに。戦闘能力からいったら、プロレスの世界チャンピオンが、なんの優れた運動能力を持たない男と戦うようなものだ。もう一つの「戦争小唄」は、戦争の楽しさを歌い上げる歌で、戦争の好きな人間は、みんなこういう人間なんだよということを教えてくれる痛快な歌だ。まともな思考力と、人の心を感じることの出来る人間だったら、戦争を好きになれるはずがないと確信させてくれる歌だ。この歌では、「待ちに待った戦争」が始まったことを喜び、国が認めた戦争だから、みんなで殺そうと呼びかけている。欲求不満のやつや、ストレスを解消したいやつには、一番だと勧めている。次のセリフは、絶対に放送に載ることはないだろうな。 いくら殺しても 大丈夫 何を盗んでも 平気さ やればやるほど ほめられる 鼻血だしだし それすすめ戦争というのは、最悪のモラルが出てくるところだ。どんな大義名分があっても、それはほとんどが嘘であるから、その場にいる人間のモラルは最低のものになる。すべての暴力の中で、やむを得ないと理解出来るのは正当防衛の時のみで、それも正当であるという証明は非常に難しい。先制攻撃の暴力に正義があると考えるのは、侵略者の勝手な殺す論理だ。僕が知っている限りでは、モラルの高かった軍隊は、毛沢東の八路軍と、ホー・チ・ミンのベトナムの解放戦線だ。いずれも侵略者に対する抵抗の軍隊だった。このような軍隊でない限り、モラルの高い軍隊は存在しないと思う。ましてや、侵略軍であるアメリカ軍が、どれだけひどいことをするかは、予想するのさえ怒りがわいてくるくらいだ。もしアメリカが戦争を仕掛けるならば、それは、悪魔のようにののしっていたイラクの軍隊を抵抗軍にし、モラルを高めるという皮肉な結果をもたらしてしまうだろう。アメリカのやっていることは侵略であり、最悪の弱いものいじめにしか映らない。まっとうな意見のフランスを世界の人々が支持し、応援することを願っている。
2003.03.15
閲覧総数 465
-
2

「たどり着いたらいつも雨降り」 吉田拓郎
このところラブソングばかり続いたので、今日はそうでないのを選んでみた。この歌は、モップスのバージョンの方が好きだという人がいるかもしれない。僕の復刻盤は、とりあえず拓郎のものしかないので、拓郎を聞きながら日記を書いている。若い頃は、人生は疲れ果てることばかりで、いつも土砂降りの中を歩いているようなものだと思っていた。たまに晴れ間が見えてきても、それはつかの間の嵐の前の静けさとでも言おうか、いつまでもほっとしていられるような感じはしなかった。人生は、自分の希望したとおりには行かないで、挫折と失望の連続のような感じがした。こんな若い頃の気分にぴったりだったのが、不条理の哲学の実存主義だった。生きるということは自分の自由にならない。かなりの部分運命的なものが支配している。それなら、死ぬことくらい自分の自由に出来るだろうかなどということを考えていたこともある。生きることに価値を見いだせないなら、死ぬ瞬間くらいは、満足できる時と所が欲しいものだと思っていた。そんな気分には、この歌の歌詞はぴったりの雰囲気を持っているのに、拓郎の歌声は決して、ここでピリオドを打ってしまえというような気分にはならない不思議さを持っていた。特別応援してくれている訳じゃないのに、「まあ、ちょっと待ってみろよ、人生なんてそんなものかもしれないぜ」と呼びかけているような感じがしてきた。年を重ねてくると、ある種のあきらめというか悟りのようなものが芽生えてくる。運命を受け入れてもいいじゃないか、というような感じだろうか。疲れ果てていたら休めばいい。土砂降りだったら、雨がやむまで寝ていようか、という感じだ。人生はそんなことの繰り返しかもしれない。でも、だからおもしろいのかもしれない。雨が全然降っていなかったら、その時が人生のピリオドの時なのかもしれない。今この曲を聴くと、そんな思いが浮かんできた。
2002.09.11
閲覧総数 333
-
3

運動における弁証法的矛盾
三浦つとむさんは、『弁証法はどういう科学か』(講談社現代新書)の中で、ヘーゲルは「ゼノンの詭弁(パラドックス)」に正しい解答を与えたとして、次のヘーゲルの言葉を引用して運動における矛盾の説明をしている。「この矛盾はあちこちに見受けられる単なる変則とみなすべきでなく、むしろその本質的規定において否定的なるもの、あらゆる自己運動の原理であって、この自己運動は、矛盾の示現以外のどこにも存しない。外的な感性的運動そのものはその直接的定在である。あるものが運動するのは、それが今ここにあり、他の瞬間にはあそこにあるためばかりでなく、同一の瞬間にここにあるとともにここにはなく、同じ場所に存在するとともに存在しないためでもある。人は古代の弁証法論者とともに、彼らが運動の中に指摘した矛盾を認めなければならないが、これは、運動はそれゆえに存在しない、ということにはならない。むしろ反対に、運動は存在する矛盾そのものである、ということになるのだ。」(ヘーゲル『大論理学』)三浦さんがゼノンのパラドックスを「詭弁」と呼んでいるのは、そこに矛盾が表現されているからで、その言説が間違っている・あるいはでたらめだということから「詭弁」と語っているのではないだろうと思う。むしろ、現実の運動の持っている矛盾を指摘した言葉として論理的な重要性を持っているからこそそれはパラドックスという呼ばれ方をしているのだと思う。運動における矛盾に関しては、僕は板倉聖宣さんが語っていたように、それは運動そのものの属性として観測されるのではなく、運動を論理的に表現しようとするときに、表現の中に入り込んでしまうものとして捉えたほうがいいと思っている。矛盾というのは、論理的に考えれば、肯定表現と否定表現とが両立してしまうことを指す。肯定判断と否定判断とがともに正しくなるような現象は、厳密に考えればあり得ない。もしそのようなものが現実に存在してしまえば、論理法則は根底から崩れてしまい、人間は論理的にものを考えることが出来なくなってしまう。論理的に正しいというのは、たまたま現実がそうなっていたからであって、現実がそうなっていない時は、論理といえども正しくないのだとされてしまう。そうなれば、論理的判断によって正しいという結論を導くことは、人間にとっては信頼のおける判断ではなくなってしまう。すべての真理の判断は現実にあるのであって、形式論理の真理性が形式にあるというのは間違いだと考えるなら、僕の主張とは相容れなくなるのだが、僕は現実を超えた観点から、形式論理の真理性を論じることが出来ると思っているので、現実の中に矛盾を直接見出すことは出来ないと思っている。もし、現実の中に矛盾を取り出すことが出来るなら、それは形式論理の法則を否定しなければならなくなることにつながってしまうと思う。そして、それは考えるということの枠組みをなくしてしまうことを意味するだろうと思う。ある笑い話にこんなものがあった。プロ野球の試合を実際に観戦した人がいて、彼はその観戦した試合についてはどちらのチームが勝ったかを確かに言うことが出来た。それは彼が実際にその試合を見ていたからで、経験したからこそ真理が言える(分かる)という判断だった。しかし、彼に他の球場でやっている試合の結果を、そのスコアを教えて聞いたところ、「それは明日の新聞を見なければ分からない」という答えだったというものだ。普通は、スコアを聞いて点数が多いほうが勝ったと判断するのだが、彼は、経験したことを信じるだけで論理的判断をしないので、経験的事実が書かれている新聞を見なければ勝敗の結果がわからないという判断をするのだ。それが笑い話になるというのは、実は誰もが論理的判断が正しいと分かっているからで、その試合を見ていなくても、あるいは見ている人の報告を聞かなくても、スコアさえ分かれば勝敗は判断できるというのが、論理的な判断になる。点数が多いほうが勝つというルールがあれば、そこから論理的にどのチームが勝ったかが結論される。勝ったと同時に勝っていないというチームは現実にはあり得ない。実際のプロ野球では、試合は1対0で勝ったけれども、相手のミスで1点を取っただけで完全に相手投手に押さえられていた時は、「試合に勝って、勝負に負けた」などという言われ方をするときがある。こんな時は、勝ったと同時に勝っていない(負けた)と言えるわけだが、これは、実際の試合でそのような結果が出ているのではなく、勝ち負けというのをどのような観点から見るかということの違いから、論理の中に矛盾したような表現が入り込んでくることを意味する。これこそが弁証法的矛盾であるというのが板倉さんの指摘であり、僕もそう思う。運動における矛盾も、僕は現実の運動が矛盾していると見るのではなく、現実の運動を論理的に記述しようとすると矛盾した表現が入り込んでこざるをえないような観点があるという捉え方が正しいと思っている。そしてその観点は、実は運動を記述するときに大きな有効性を持っているので、運動の分析において弁証法が役立つことが出てくるのだと思う。ヘーゲルが運動そのものを矛盾と呼んだことを差し引いて、それが運動の表現に関わることだと考えて、運動の記述を考察してみたいと思う。運動の記述において、たとえば物理的な位置の移動に関する運動を記述するときのことを考えてみると、一定の時間にどれだけの変位を持ったかという記述をする限りでは、そこに矛盾した表現は入り込んでこない。一定の時間の幅を持って運動する物体を観察するなら、それが今はここにあってしばらく後にはあそこに行ったというような記述が出来る。この一定の幅の時間をどんどん短くしていくことを考える。これはどんなに短くして0に近づけようとも、それが一定の幅を持っているのであれば、「今はここにあってしばらく後にはあそこに行った」という記述になり、そこには矛盾は生じてこない。しかしこれを究極的な値である0にしてしまうとそこに矛盾した表現が生じてくる。一定の時間の幅があれば、どんなに短い時間であろうともそこに変位というものを観察することが出来るのが運動である。一定の時間の中で変位がなかったら、その物体は運動しているとは言えなくなるだろう。ところが、時間0の世界では、時間が0であることによって、そこには変位を観察(計算)することが出来なくなる。時間0の世界では物質は静止している(変位が0)と考えざるを得ない。これは論理的な要請となる。時間0の世界を考察の中にいればなければ運動における矛盾は生じないだろうと思われる。しかし、この時間0は、運動の分析においてはどうしても避けられない現象のようにも思われる。なぜなら、我々が観察できるのは、たとえ一定の時間の幅の存在する対象の姿であろうとも、視覚的映像としては瞬間を写したと受け取るしかない静止画像ではないかと思うからだ。もし我々が、静止画像ではない運動の画像を認識しようとすれば、それは手ぶれをして取ったような写真と同じように、何かぼんやりとボケた画像が見えるだけだろう。そこでは位置の確定が出来なくなる。位置の確定が出来るようにはっきりと写った写真にしたければ、一定の幅を持ったというシャッタースピードを誤差として受け取って、そのピントの合った写真画像は瞬間を写したものだと考えることになるだろう。我々が運動を正確に捉えようと思えば、そこに静止を持ってこざるを得ないというのが論理的な要請ではないかと思う。だから、運動を論理で表現しようとすれば、そこに矛盾したような表現が入り込むことが必然になるのではないだろうか。数学における微分という考え方は、運動の記述を極限という概念を使って表現しようとするものだ。この極限では、0であって0でないというような矛盾したと思える表現が生じてくる。極限は限りなく近づくのであるから0ではないんじゃないかと感じる人もいるだろう。確かに、それが「限りなく近づく」という運動を表現しているあいだは、それは決して0にはならない。しかし、微分の計算を行うときには、その計算において瞬間という1点における係数を計算する必要が出てくる。そのときには、限りなく近づくのではなく、極限値と一致する0の世界を設定しなければ計算が出来なくなる。微分係数というのは、微分可能な関数のグラフの1点における傾き(接線の傾き)を与える。もし、この傾きを計算するときに、1点しかないのであれば、1点を通過する直線は無数に存在するので、傾きは一つには決まらない。しかし、それが微分可能なグラフであれば、その1点の周りに無数の連続な点が存在し、その点で運動しているという捉え方で、その点における微分係数が決定する。1点では微分係数は決定しないが、その点における極限を考えれば微分係数は決定する。1点を通る直線は無数に存在するが、それが運動をする通過点の1点であれば、微分係数の傾きを持った直線は1つに決定する。1つであって1つではないという矛盾した表現が、そのグラフで表現される運動の様子を決定する。これは、その矛盾を排除してしまえば、各点における観察をしなければ運動の経過を決定出来ないことになる。つまり、経験しなければ結果としての運動について何も記述できないということになる。経験せずとも、その運動について何らかの言及が出来るようにするためには、運動を論理で捉える必要がある。論理的記述に成功すれば、経験していないことでも論理的帰結としてその運動に対して正しい記述をすることが出来る。だからこそ論理によって運動を捉えることには大きな意味がある。だが、論理的な記述をしようとすればそこに矛盾したような表現が入り込む。これこそがゼノンが素朴な直感で指摘したことだろう。ヘーゲルはその素朴な直感を、現実の属性として捉えてしまったのではないかと思われる。それが観念論者として批判される部分なのだろう。正しくは、表現の中に矛盾が生じると捉えることが大事なのではないかと思う。運動が矛盾である。運動の中に静止を見るというのは、そこに瞬間という時間0の状態を見て、それを記述するからではないかと思う。そして、それこそが運動を正確に記述することになるというところが、弁証法の有用性の不思議なところなのだろう。
2008.01.25
閲覧総数 18
-
4

陸山会事件判決の論理的分析 6
判決要旨には政治資金収支報告書の虚偽記入について大久保被告の関与を語るところがある。ここにも僕は違和感を感じる。そこでは、「収支報告書に新政研及び未来研からの寄附であるとの虚偽の記載をすることを承知の上で、同人らをしてその旨の記載をさせ、提出させていたことが認められる。したがって、陸山会の収支報告書についての虚偽記入につき、被告人大久保の故意は優に認められる。」「被告人大久保は、本件各寄附が新政研及び未来研からのものであることを内容とする第4区総支部の収支報告書が提出させることになると承知の上で、それに至る各作業をさせ、これを提出させていたことが認められる。したがって、第4区総支部の収支報告書についての虚偽記入につき、被告人大久保の故意は優に認められる。」と書かれている。虚偽記入について、大久保被告がそれを承知の上で書かせていたという「共謀」の証明を述べているように見える。この証明が、どうも論理的にすっきりしない。この証明には、この結論を論理的に導く前提が必要だ。それは、新政研及び未来研という二つの政治団体がダミーであり、しかも大久保被告がそれを認識していたということだ。この前提がなければ上の結論は出てこない。収支報告書には新政研及び未来研の寄付は記載されているから、記載漏れではない。この記載が虚偽であるという告発だ。つまり正当な寄付ではないということだ。これは証明された事実なのか、ということにどうしても違和感が残る。確かに西松建設そのものの裁判においては、西松建設という会社がその政治団体がダミーであることを認めている。だが、西松建設が認めているからといって、それが事実になるのだろうか。裁判というのは事実を明らかにするところではなく、事実ではなくても会社にとって有利と判断すればそれで手を打つということもあり得る。西松建設は、郷原さんによれば全面降伏したと指摘されていた。そのような会社のいうことをそのまま信じられるのだろうか。大久保被告が関係した西松建設事件では、どういうわけか、この政治団体のダミー性が裁判で争われていたのに、その判決を迎えることなく終わってしまっている。どうしてなのか?それはダミー性を否定する証言が現れてきたからだ。もちろん、その証言によってダミー性という事実が否定されたわけではないが、そのような証言の元では、大久保被告がダミー性を認識していたということが証明できなくなる。それで裁判は、訴因変更を経て、より証明できる可能性の高いものにシフトしていった。そのような経過を見ると、どうしてもこの判決要旨の言葉には違和感を感じる。弁護人の主張を退ける判決要旨の論理も、両政治団体がダミーであり、献金そのものが不正であることを自明の前提としている。そして、それを大久保被告が承知していることも前提としている。だがそれが証明されたようには僕には思えない。いったいどうやって証明されたのだろうか。唯一の根拠は、西松建設本社の裁判で、西松建設側が認めたということだけなのではないか。この構造はえん罪の構造にも似ているように感じる。えん罪でよくあるパターンは、本来の主犯格の人間が、自らの罪を軽く見せるために、主犯格の人間をでっち上げるものだ。他人の証言で主犯にされた人間は、当然のことながらそれを否定する。しかし、罪を認めて観念した人間がすべてを話した、という前提でそれが事実のように扱われると、やってもいないことをやったようにされてしまう。確かなのは、あいつが言ったという証言だけだ。しかし、その証言の中身が正しいかどうかは評価が難しい。疑われた人間にアリバイがなかったらさらに難しくなる。西松建設は、本当に両政治団体をダミーとして作ったのかどうか。ダミーというほどではなく、会社に関係する人間が働きかけることで、会社の印象を良くしようと考えた程度ではないのか。西松建設側は、本当の犯罪行為は裏金をつくったと言うことの方だったようだ。その裏金をどこに使ったかが明らかになっていれば、それこそが本当の犯罪になっただろう。こちらの犯罪は言い逃れが出来ない種類のものだったので、裁判を早く終わらせたかった西松建設は全面降伏したというのが事実ではないのか。その裏金が直接小沢事務所に入っているのなら、それで事件化できただろう。しかし、それがなかったので、新政研及び未来研という二つの政治団体の寄付が裏金だとにらんで大久保被告の逮捕をしたのだと思う。だがそれは証明できなかった。大久保被告の裁判で出てきたのは、両団体には実体と呼べるものがあり、しかも個人の金で運営されていて、形の上では西松建設そのものの金が入っていたのではないということだった。つまり裏金が流れていたわけではないのだ。会員に対して上乗せされた給料が、献金目的だったというような解釈もされていたが、もしそうであっても、そのような会社内部の状況を大久保被告が知るはずもないので、本当にそうであっても、それはよほどのことがない限り分からないようなものになっていただろう。このような疑念がたくさんありながら、西松建設事件に関して裁判所がこうもはっきり言い切るには、やはり論理的根拠が怪しい。こんな怪しい論理を、どうして裁判所は言い切らなければならないのか。どうしても有罪にしなければならない理由があるからだと憶測するしかない。あらゆる前提を考慮して、そこから論理を導いているのではなく、結論を導きたいことに合わせて、ご都合主義的に前提を選び、都合の悪い前提は捨てているように、論理のデタラメさを感じる。そこが違和感を覚える最大の要素だ。
2011.10.22
閲覧総数 20
-
5

「あなたの心に」 中山千夏
今日も気ままに<うたまっぷ>を検索していたらこの歌にぶつかった。僕は、図書館にあった歌謡曲のオムニバス盤をいくつか借りたんだけれど、この歌もたまたまその中の一つに入っていた。僕がまだテレビっ子だった頃に中山千夏はちょっとしたアイドルだった。お嫁さんをやるシリーズか何かがあって、毎週見ていたように覚えている。そのアイドル時代の可愛い歌がこの歌で、中山千夏自身が作詞をしている。若い頃に作った詞だから、それほど深い意味があるわけじゃないけれど、実に微笑ましい純な気持ちを感じる詞だと思う。愛する人の心に、風や空や海を見るのは、あの頃の女の子にはとても共感できる気持ちだっただろう。今はどうなんだろう。「私一人で」という気持ちがかわいいと思う。そして だって いつも あなたは 笑って いるだけ そして 私を 抱きしめるだけここのところは、あの頃の男の子だった者たちに共感できる雰囲気だと思った。何もしゃべらないで、ただ笑っているだけで、抱きしめるだけだったらいいね。今だったら、僕はかなり饒舌になったけれど、若い頃は思っていることを表現するだけの言葉を知らなかったから困ったものだ。中山千夏は、いわゆる美人タイプではなかったけれど、あれだけ絶大な人気があった理由が今はよく分かる気がする。ああいう可愛さが男は好きなんだと思う。その後国会議員になったりしたけれど、他のタレント議員とは一線を画していたように感じた。中山千夏は、自分の言葉で語れる人だと思った。僕は本多勝一のファンなので、本多勝一が編集委員をしている「週刊金曜日」を創刊号から定期購読している。そこにも中山千夏は寄稿していた。ステキに年を重ねていることが分かる。若い頃魅力を感じた人が、美しい年の取り方をしているのを見るのはとても嬉しいことだなと思う。
2003.01.09
閲覧総数 1511
-
6

小沢裁判二審判決の論理的考察 2 判決文の合理性を考察する その1
二審判決の要旨については、http://k1fighter2.web.fc2.com/Enzai/OzawaSaiban/kosoKikyaku121112.htm「小沢一郎さん控訴審判決要旨 東京高裁・小川正持裁判長 2012年11月12日」と言うページに書かれているものが見やすくて、読むのに便利だ。判決文そのものは法律的な文章なので非常に読みにくい。どの言葉がどこにかかるのかを、文法的な知識をもとに読解しなければ全く訳の分からない文章に見えてしまう。それを考察するのに役に立つような工夫がこのページではなされているので、判決に関心のある人はこれを読んで考えるといいだろうと思う。僕は論理的側面としての合理性に関心があるので、ここに書かれていることが合理的であるという面を引き出せるような読み方をしてみようと思う。陸山会事件の全容を論理的に考察すれば、これが全く犯罪とは呼べないような事実を無理矢理犯罪に結びつけたためにデタラメなものになったと言うことが分かる。まず確認したいのは、原判決(一審判決)に何が書かれていたかだがそれは指定弁護士の控訴趣意書にも次のように記されている。<事実認定>原判決は 陸山会の平成 16年分及び平成17年分の収支報告書に本件公訴事実どおりの虚偽記入及び記載すべき事項の不記載があることを指摘している。 石川知裕に故意が認められる部分 ・平成16年分の収支報告書における本件4億円の収入並びに本件土地の取得及び取得費の支出に係る虚偽記入・不記載 池田光智に故意が認められる部分 ・平成17年分の収支報告書における本件土地の取得及び取得費の支出こ係る虚偽記入 被告人(小沢一郎)に関する事実の部分 ・石川らから本件4億円を簿外処理すること ・本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に記載せず ・平成17年分の収支報告書に記載すること以上の3点にについて報告を受けこれを了承した、しかし次のこと ・本件4億円の簿外処理や本件土地公表の先送りが違法とされる根拠となる具体的事情については、石川らにおいて、被告人に報告してその了承を受けることをしなかった。「違法とされる根拠となる具体的事情」を小沢さんは知らなかった。<事実に対する解釈> 虚偽性の認識に関する可能性の指摘 ・本件4億円の簿外処理や本件土地公表の先送りが違法とされる根拠となる具体的事情を認識していなかった可能性があり ・本件4億円を借入金として収入計上する必要性 ・本件土地の取得等を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり ・平成17年分の収支報告書に同年中のものとして計上すべきでないことの3点を認識していなかった可能性を否定できないこの解釈をもとに「被告人(小沢一郎)を無罪とした」。控訴趣意書では、この「無罪」という判決に異議を唱えてそれに反論している。その論拠は次のようなものだ。被告人(小沢一郎)の認識 ・本件4億円を借入金として収入計上する必要性 ・本件土地の取得等を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり ・平成17年分の収支報告書に計上すべきでないことの3点を認識していたから、原判決は本件4億円の簿外処理及び本件土地公表の先送りに係る被告人の故意及び石川らとの共謀が認められないとする点において事実誤認をしており、この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであって、原判決は破棄されなければならない、と主張している。控訴趣意書では、「3点を認識していた」とそれが事実であるかのように断定しているがその証明は書かれていない。出来ていないのではないか。一審判決では「認識していなかった可能性を否定できない」と指摘されている。一方は「認識していた」と断定し、もう一方は「認識していなかった可能性を否定できない」と「可能性」について言及している。この違いをどう理解すればいいか?この指定弁護士の主張は、後に判決によって否定されるのだが、これは論理的に言えば、指定弁護士の証明というのは、可能性をすべて否定しなければならないからだと考えられる。可能性が一つでも残れば、それは「認識していた」と断定は出来ないのだ。判決は事実を吟味して、小沢さんに虚偽性の認識がなかった可能性を指摘している。これはその可能性を否定しなければ、虚偽性を認識していたという指摘が成立しないからだ。これは、虚偽性の認識を直接証明する証拠がないからだ。直接証明できないので、間接的に証明するしかない。つまりすべての可能性を否定することによって、直接証明できないことを証明することが出来るという、論理での場合分けの考え方がここにはある。二審判決が、一審の判断が妥当であると判断し、指定弁護士の主張を退けているのは、可能性をすべて否定するという点での証明が弱いという指摘からだ。疑いだけでは有罪には出来ないというごく当たり前の判断がここで話されているのを感じる。だからこそ判決の方に合理性があると感じる。控訴趣意書のもう一つの主張の「審理不尽」についても判決では一蹴されている。この論理も明快だ。指定弁護士の主張は次のようなものだ。原判決が被告人の故意及び石川らとの共謀が認められない根拠として認定したことすなわち、 ・被告人が本件売買契約の決済全体が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があること ・被告人が、本件定期預金は本件4億円を原資として設定され被告人のために確保されるものなので、本件4億円を借入金として収入計上する必要がないと認識していた可能性があることの2点については、原審の審理過程において、被告人及び弁護人は一切主張しておらず、争点になっていなかった、だから原審裁判所がこの点を争点と考えていたのであれば、当事者に確認して争点化を図るか、自ら被告人に質問しその真偽を確認すべきであったが、原審裁判所はそれをしなかった。これが「審理不尽」だという主張だ。争点化して審理すべきだという考えだ。判決は、この指摘に対して、可能性の話は指定弁護士の証明が弱いために出てきた話であり、その可能性を積極的に証明すべきという流れの中で出てきたものではないと反論している。つまり、指定弁護士は、その可能性を否定しなければ自らの主張の証明は出来ないのであって、むしろ可能性を否定すべき責任は指定弁護士の方にある。被告人および弁護人がそれを争点化する必要はないのだ。判決はそれを指摘しているだけなのである。審理が足りないのではなく、証明が足りないのだ。後の文章を読んでいくと、指定弁護士が一審で指摘されたような証明の弱さを二審で強めたのではなく、事実は、むしろ一審が認めたものでさえもその論理的正当性が弱いと言うことを指摘している。それが郷原さんが指摘するもので、小沢さんの虚偽認識という「犯意」だけではなく、石川元秘書の虚偽認識の方も証明が弱いという指摘をしている。この二審判決は、控訴を退けたと言うだけではなく、一審の誤りも指摘して、この起訴自体が非論理的なデタラメであることを指摘している。後は、細かい点においてどのように事実を解釈していっているかというような合理性についても注目して考察していこうと思う。
2012.11.17
閲覧総数 11