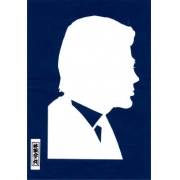【粗筋】
塩原角右衛門の女房・おせいにおかめという妹がいたが、これが家来の岸田右内といい仲になり妊娠する。二人は駆落ちをして江戸へ出、娘・おえいが生まれる。この娘が7歳になる頃、右内はすっかり落ちぶれて猟師になった主人と再会する。角右衛門は仕官の話があるので、支度金の50両を工面してと頼む。
右内は思案にくれながら歩くうちに、百姓が馬を売る話をしているのを聞きつける。相手の男が手付けに1両を預けたが、まだ7、80両は持っている様子。思い詰まった右内がこの男に50両を貸してくれるよう頼むが、相手はこれを盗人だと思い込んで助けを呼ぶ。聞きつけた角右衛門が駆け付けると、盗人が相手を押さえつけていると思い込み、とっさに鉄砲で撃ったが、倒れたのは何と右内ではないか。右内はいまわの際まで金を主人に貸してくれるように言って息耐える。相手の男と話してみると、この男も塩原角右衛門という同姓同名、同じ一族であった。百姓の角右衛門は右内の心にうたれ、相手の角右衛門の息子を養子とし、その支度金として50両を渡すことにした。この子は多助という名で、今買われたばかりの、「青」と名付けられた馬と一緒に育っていく。
多助を養子にした角右衛門が女を救ったが、これが右内の家内・おかめで、娘と共に夫を追ってきたが、悪人にだまされて母娘別れ別れになってしまったのだ。角右衛門はおかめを預かり、周囲の世話で後妻に迎えることになった。宝暦10年2月4日、たまたま江戸に出ていた角右衛門は、火事の中で自害しようとした娘を救う。これが悪人にさわられた娘のおえい。13年ぶりに母娘が巡り会うが、角右衛門はこの火事の苦労から体調を崩し、多助とおえいを夫婦にして死んでしまう。
35日の墓参りの日、おえいはならず者に襲われるが、原丹治という侍に救われる。この丹治と母親のおかめがいい仲になり、丹治の息子・丹三郎とおえいが関係するようになってしまう。多助がいては二組とも表立っては会えない。庄屋の娘への恋文をでっち上げて追い出そうとして失敗、今度は罠に掛けて原親子が闇討ちにするよう手はずを整えた。
多助は隣村へ出掛けたが、帰り道、どうしたことか馬の青が一歩も進まなくなった。友人の円次郎が通り掛かり、彼が引くと青は進む。そこで荷物を取り替えて、多助が円次郎の品物を家に届け、円次郎が青を家まで運ぶことにする。このため円次郎が殺され、青は独りで家に戻った。何も知らず帰ってきた多助は、翌日になって円次郎の死を知り、このままでは自分が危ういのを確信する。十五夜の晩に荷を届けた代金を懐に、江戸へ逃げようと、沼田原の物見の松に青をつなぎ、別れを惜しむ。話を聞いて心が通じたものか、馬の目に涙があふれる。
「あァ、青ッ……わりゃァ泣いてくれたかァ……ありがてえ……」
行こうとすると、草鞋の切れ緒を馬が前足で抑え、肩をくッとくわえて放すまいとする。
「青ッ、とめるんじゃァねえ……とめるんじゃァねえッ……それじゃァおらァ行かれねえェ……達者でいろよッ」
これを振り切って、城下までの三里の道を夢中で駆け降り、さて、これから江戸へ参ります。
【成立】
三遊亭圓朝が怪談噺のネタを求めている時に、柴田是真という画家から逸話を紹介された話を膨らませたもの。三代で塩原家がつぶれたという話で、聞いた途端に駕籠をあつらえ、取材に出かけたという。しかし、いざ噺を始めると怪談噺はどこへやら、勤倹貯蓄を旨とし、仇に報ゆるに徳を以てするという、立身出世美談になってしまった。これはもちろん、この噺が創作された明治10年前後の社会風潮によるもので、教科書にまで取り上げられてますます教育的な使命を負わされるに至る。幕末の「累ヶ淵」や「牡丹灯籠」と比べて演じられる機会が少ないのは、教育的で面白みに欠けるからであろう。
子供の頃は全体は知らないが、馬と別れを告げる場面だけは知っていた。コントなどでもよく演じられていたのだ。
三遊亭圓生(6)も圓朝作品を早くから取り上げていたが、この噺には食欲がそそられず、演るとすれば「青の別れ」だけだろうと語っていたという。1965(昭和40)年の圓朝祭で初演、その後何度か取り上げて録音も残っているが、発端から母娘と原父子との密通まではほぼ地噺で運び、付文の罠の辺りからじっくりと話し込む方式とスパッと切って落とす結末まで演出は同じ。「百席」には入っていないが、続編に入れようと思ったのか、分からない。
一方古今亭志ん生(5)は二人の角右衛門の下りをカットし、簡単な経緯の後、闇討ちの場面からじっくり語る。
【一言】
私が聞いた限りでは、亡くなった志ん生師の『山口屋』……道連れ小平が山口屋善右衛門の店先で金をかたりとろうとして、多助に見あらわされるところ……と、これも亡くなった今輔さんかあるいは講釈のほうで、七代目の貞山ではなかったかと思いますが、『戸田屋敷』……多助が戸田能登守のお小屋で、実父の角右衛門と障子越しに体面するところ……近年では、そのくらいしか演ぜられる部分はなかったといえるでしょう。そして『青の別れ』を圓生師以前に聞いた記憶が、どう思い返しても、私にはないのです。
(山本進)
○
私たちで、どうやったって(圓生のような)ああいう切りかたは出来ません。江戸へ出て、昌平橋で身投げをしようとする、あのあたりまでもっていかないと、どうしてもおしまいにならないんですよ。(三遊亭圓楽(5))
○
三遊亭円朝が、五代目菊五郎の塩原多助を見ていると、馬の別れで、はじめから青という愛馬を見ながら、セリフをいっているので、「余計なことですが、馬に話しかけてもわからないというつもりで、正面を向いて、独り言のように、しゃべっているうち、ふと馬の涙に気がつき、それから、馬の顔を見たほうが、よくはありませんか」といった。菊五郎が喜んで、助言通りにした。菊五郎がその時、円朝にいった。「師匠は、みんな一人でできるからいいね」(戸板康二)
-
落語「は」の14:ばかのむき身(ばかの… 2025.11.19
-
落語「は」の13:馬鹿竹(ばかたけ) 2025.11.18
-
落語「は」の12:歯形(はがた) 2025.11.17
PR
Keyword Search
Comments
Freepage List