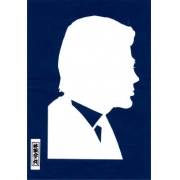【粗筋】
茶店をやっている夫婦、客が来ないので浅草田圃の真ん中にある太郎稲荷にお願いに行くと、とたんに客が来て売れ残っていた草鞋を買って行く。売れ残りを売ったのでもうないと思ったら、天井にいつのまにか草鞋がぶら下がっている。それを売って客が店を出るとたんに、新しい草鞋がぞろぞろっと出てくる。これを見た向かいの床屋、自分も信心しようとお稲荷さんへ出掛け、商売繁盛をお願いして帰ってくると、店は客で一杯になっている。早速最初の客の髭を剃ると、新しい髭がぞろぞろッ。
【成立】
九州の座頭話をもとにした上方噺が江戸に移植されたものとされている。九州の話というのは有名で、打出の小槌で米と蔵を出そうとして、「米倉、こめくら」と言うと小さな盲人がぞろぞろと出て来たというもの。これが原話なのって、ちょっと疑問。
大阪では赤手拭神社が舞台、東京では四谷のお岩稲荷だが、橘家円蔵(4)から林家彦六らに受け継がれた舞台が太郎稲荷。ここは立花左近将監(筑後柳川11万9600石)の下屋敷に祭られていたもので、『たけくらべ』で美登里がお参りに出掛けたところ。
神様が登場するのと登場しないのがあるようだが、登場すると何だか有難味がなくなった例しか聞いていないような気がする。実は立川談志(7:自称5)が、神様の方を主人公に作り替えた。神様の気まぐれ、移り気を描いたのだ。物足りない事例は、そこを中途に取り込んだからだろう。
【一言】
お岩稲荷のほうが確かにすご味が出るのですが、太郎稲荷というと、なにかとぼけた味があって捨てがたいので。(林家彦六)
【蘊蓄】
草鞋は、底・紐・乳・かえしから構成される。
-
落語「は」の17:白日の告白(はくじつ… 2025.11.22
-
落語「は」の16:バク(ばく) 2025.11.21
-
落語「は」の14:ばかのむき身(ばかの… 2025.11.19
PR
Keyword Search
Comments
Freepage List