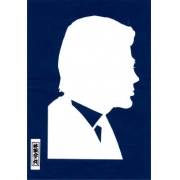【粗筋】
旦那に会って一杯おごってもらおうとするが、旦那の方は用事があるという。用事がすんでから飲ませてくれればいいと、図々しく付いていくと、旦那が訪れた家で、
「よいところへお越し下さった。ちょうど家内の五月着帯の祝い、御酒を一盞差し上げたい」
といわれて入り、男は表で待つことになった。中では旦那がおめでたいことを並べるのですっかり喜び、
「三つ重ねの杯がありますから、一番下の大きな盃
で2、3杯召し上がって下さい」
「いや、上の軽い方で、ちょいちょいと何杯もあやかりたい」
ということになって、表の男を追い返す。当てが外れた男、自分も腹の大きい人を見付けて飲ませてもらおうと探し出したのが、貧乏所帯のかみさん。祝いどころではないのだが、そう言われると行き掛かり上仕方なく、なけなしの20銭を出して酒を買って来た。全てに旦那の真似を始めるが、最後の杯のところで台詞を忘れてしまった。
「大きい杯は大盞だな。じゃあ、小盞でチビチビやりたい」
「縁起でもない。小産とは子供が流れることです」
「えっ、そうか。流れるのなら今の20銭で利子を入れておけばよかった」
【成立】
上方噺。桂南光(前)の速記が残っている。「小産」とも。
最初のやり取りに「大
盞」が出ないし、説明不足に感じる。尚、「盞」は盃(杯)のこと。どこから出たのか「大きいのを杯、小さいのを盞という」というのがネットで出たが、出典・根拠を明らかにしていないので分からない。それならこの噺の盃は、「小さい盃の中で大きい物」ということになる。三つ重ねなのだからねえ……今でもネットで時々見かけるから、根拠を説明していないのは信用しない方がいい。

-
落語「は」の16:バク(ばく) 2025.11.21
-
落語「は」の14:ばかのむき身(ばかの… 2025.11.19
-
落語「は」の13:馬鹿竹(ばかたけ) 2025.11.18
PR
Keyword Search
Comments
Freepage List