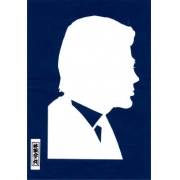【粗筋】
妓夫太郎(ぎゅうたろう)に勧められるまま、「明日になれば金をこさえるから」と、無一文で登楼した男がいる。「昨日表で勧めた妓夫(牛)が、今日はのこのこ馬となる」という文句の通り、翌朝催促に行くと金がないと言って妓夫太郎を連れだすが、朝湯に入り、湯豆腐で一杯やり、勘定は全部立替えさせ、早桶屋の前へ来ると、叔父さんに相談するから、ちょっと待てと一人で中に入り、「外にいる男の兄が腫れの病で死んだので、図抜け大一番の小判型の早桶をこしらえてもらいたい」と頼み込み、妓夫太郎には「叔父さんが引き受けてくれた」と言い置いて逃げてしまう。早桶屋と妓夫太郎の会話がおかしくかみ合う。
「すぐできるから、安心しておいで……どうも大変だったね。長かったのかい」
「えッ……いいえ、夕べ一晩でございます」
「急に行ったんじゃないのかい」
「はい、夕べ突然においでになりました」
「じゃあ夕べがお通夜だ」
「へえ、芸者衆が入りまして」
「ふうん、じゃあにぎやかな通夜で仏様も喜んだろうなァ」
「ええもう、馬鹿なお喜びようで」
まではまだ良かったが、
「どうやって持って行きなさる」
「はい、紙入れに入れまして」
あたりからおかしくなってきた。さあ、早桶が出来上がって、だまされたことに気付いたがもう遅い。5円に負けておくと言われても、男に立て替えたためもう一文無しだ。
「仕方がねえな……奴、吉原までこいつの馬に行ってこい」
【成立】
文化4(1807)年の喜久亭壽暁のネタ帳『滑稽集』の「人参代」が原型という。当時春風亭柳枝(3)の演じていた「人参かたり」にヒントを得て廓に舞台を移したものという。現行のものはほとんど柳家小さん①の演出を踏襲している。「つけうま」「付き馬の付き馬」「早桶屋」とも。
江戸落語。上方では前の晩に料金を払ってしまう、いわゆる「宵勘」であり、付き馬ということ自体が存在しない。
【一言】
無一文で登楼し、存分に楽しんだ翌日、店の若い衆をひっぱり出してさんざん引きまわし、その間になんだかんだと小銭を立替えさせたり、釣り銭をまきあげたあげく、通りすがりの早桶屋のおやじにたくみに若い衆をおしつけて、そのままぷいといなくなってしまう手口は、あざやかといえばあざやかだが、あくどいといえばあくどい。『突き落し』のように乱暴をしたり、『居残り』のように開き直ったりするわけではないから、一
見、罪は軽いようだが、料金をふみ倒した上に、若い衆のとぼしい小遣いをまきあげたり、
何のかかわりもない葬儀屋のおやじに「図抜け大一番小判型」の特製早桶を注文してとんでもない迷惑をかけたりした行為は、やはり相当に悪質である。(江國滋)
●
【蘊蓄】
早桶屋は葬儀屋であり、棺桶を作っておくと死ぬのを待っているようで縁起が悪いということから、死人が出て急いで作ることからこの名がある。
『三人吉三廓初買』(万延元)では、「駒込の早桶屋へ行って、早桶に経帷子(きょうかたびら)一式揃えて、二人前勝って(買って)来てくだせえ」と1分をやる。2人前で1分だから1人前なら2朱(500文)になる計算で、安いものだったらしい。
隣に早桶屋はあるし、向こうはお寺なり。何どき死んでも事はかかねえな(十返舎一九『臍くり金』)
-
落語「は」の14:ばかのむき身(ばかの… 2025.11.19
-
落語「は」の13:馬鹿竹(ばかたけ) 2025.11.18
-
落語「は」の12:歯形(はがた) 2025.11.17
PR
Keyword Search
Comments
Freepage List