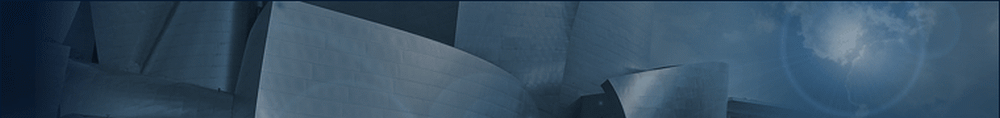全7419件 (7419件中 1-50件目)
-

山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その8) ふれあいK字橋
また目黒川沿いの道を歩きます。そして、この橋を渡って左岸側に渡りました。この橋の名称は「ふれあいK字橋」(→→→こちら)。1995年、目黒川に掛けられた人道橋です。上流側にあるこの湾曲した鉄骨のせいで、上から見るとKの字形をしているので、K字橋と名付けられたそうです。橋の上からは、目黒川を渡るJRの鉄橋と、東急池上線の五反田駅に向かう鉄橋が見えるトレインビュースポットでした。しかし、よく見ると東急五反田駅ってビルの4階に相当する高さにあるんですね。毎日、通勤でこの駅の階段を昇り降りしていると足腰鍛えられそう。(高輪ゲートウェイから渋谷コース)【つづく】人気ブログランキング山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その8) ふれあいK字橋
Nov 26, 2025
コメント(4)
-

和食と日本の酒の魅力体験フェア
山手線一周の駅間歩きの途中ですが、昨日(11月24日)、日本橋で面白そうなイベントがあったので、のぞいてきたきた報告です。場所は、日本橋三越の近くの江戸桜通りの地下歩道で、開催された和食と日本の酒の魅力体験フェア(→→→こちら)です。のぼりにあるように「楽しもう!にほんの味」という趣旨で、農林水産省が共催しているイベントです。まあ、「楽しもう!にほんの味」といわれても、こうお米の値段も高いと、なかなか楽しめないとは思うのですが。開場にはまだ早かったので、スタッフの皆さん準備中でした。こちらは日本の酒試飲体験ができるところ。試飲といっても朝から飲むのはちょっと気が引けて、一杯だけ日本酒頂きました。その他、お茶の試飲、郷土料理の販売、石臼体験、かつお節削り体験などができる催しでした。MoMo太郎が納得できなかったのは、この全国各地の人気料理を各都道府県ごとに紹介したもの。福岡県の人気料理が博多ラーメンとありましたが、これはおかしいです。東京にも進出している「資さんうどん」を知らないのか、福岡県のソウルフードは「うどん」です。埼玉県民はゼリーフライとありましたが、埼玉県民のソウルフードは「山田うどん」でしょ。そんなイベントで、参加した景品は栄太郎飴、5粒でした。人気ブログランキング和食と日本の酒の魅力体験フェア
Nov 25, 2025
コメント(30)
-

山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その7) 大崎駅
大崎駅の近くにあるゲートシティ大崎。ちょっと理解不可能な彫刻?が、何をイメージしているのかな(→→→こちら)?大崎駅です。1901年開業。山手線、山の手貨物線、東海道貨物線のジャンクション駅です。かって周辺は工場地帯だったのが、1980年代後半より始まった大崎駅東口地区の再開発によって、大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎などの複合施設が相次いで開業し、東京副都心の一つとして東京でも有数のビジネス街になりました。山手通りを逸れて、山手線沿いの道を歩きます。すぐ脇を山手線の列車が通り過ぎていきます。そして、成田エキスプレスも通り過ぎていきます。道路沿いに設置されている腰掛け。「しながわお休み石」とあったので、ここに腰掛けてペットボトルの水を飲んでひと休みしました。こちらにもちょっと変わったオブジェが、グローイング・ガーデナー(→→→こちら)というそうです。赤い長い帽子をかぶった庭師(ガーデナー)の妖精といったことでしょうか。(高輪ゲートウェイから渋谷コース)【つづく】人気ブログランキング山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その7) 大崎駅
Nov 24, 2025
コメント(16)
-

山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その6) 居木橋
目黒川に架かるこの橋は、居木橋(いるきばし)です。ここから山手通りに沿って歩きます。南仏プロヴァンスを模したデザインの建物がありました。ここは大崎ゲートシティ(→→→こちら)という複合再開発施設だそうです。(高輪ゲートウェイから渋谷コース)【つづく】人気ブログランキング山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その6) 居木橋
Nov 23, 2025
コメント(24)
-

山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その5) 大使館と翡翠原石館
御殿山庭園から大崎駅に向かって歩いて行くと、途中にミャンマー大使館がありました。ミャンマー、色々と問題のありそうな国ですが、かなりのミャンマー人が日本に滞在しているみたいなので、やっぱり大使館はちゃんとあるんですね。そして、近くには「翡翠原石館」(→→→こちら)という施設もありました。一度訪れてみたいですね。大使館の周辺、かなりの高級住宅街が広がっています。周辺の施設の案内図です。地元(北品川)の歴史を記した案内板がありました。(高輪ゲートウェイから渋谷コース)【つづく】人気ブログランキング山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その5) 大使館と翡翠原石館
Nov 22, 2025
コメント(26)
-

山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その4) 御殿山庭園
都会の中にあっても品川区北品川の3~4丁目に位置する御殿山。住宅街や高層マンション、オフィスが立ち並ぶエリアとして知られています。そして、複合施設「御殿山トラストシティ」には「東京マリオットホテル」や「御殿山庭園」などが入り、観光スポットとしても有名だそうです。なかでも「東京マリオットホテル」の南側に位置する「御殿山庭園」は、江戸時代の桜の名所である御殿山の、昔ながらの面影を今に伝える日本庭園です。このような人工的な滝があり、このような池があり水辺の憩いもあります。こちらが池の全景、向うに見えるのは東京マリオットホテルの建物です。こんなホテルに一度泊まってみたいものですね。御殿山の地名は、かつて江戸時代に将軍家の別邸「品川御殿」があったことに由来するそうで、徳川吉宗の時代には、園地解放によって御殿山の一部は庶民の行楽地に。吉宗が櫨(はぜ)や白膠木 (ぬるで)を植え、紅葉が美しい秋の公園として整備されたようです。その後、桜が多く植えられたことで「江戸屈指の桜の名所」となり、その賑わう様子は多くの浮世絵にも描かれているのだとか。この御殿山庭園は、約2000坪の広々とした敷地で、都会にあってもこのように木々が植えられ、自然豊かな空間になってます。この建物は、「有時庵(うじあん)」と名付けられた茶室。日本を代表する建築家である磯崎新氏の設計により、1992年に建てられた作品です。池の脇のベンチでのんびりする人もいました。このような石橋もあって、ちょっとした登山気分も味わえたりして、庭園の中にあった白い石像、この区域は立ち入り禁止となっていて、どなたの石像なのかはわかりませんでした。(高輪ゲートウェイから渋谷コース)【つづく】人気ブログランキング山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その4) 御殿山庭園
Nov 21, 2025
コメント(26)
-

山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その3) 新八ツ山橋付近のトレインビュースポット
再び国道15号(第一京浜)を南に向かって、新八ツ山橋を目指します。新八ツ山橋から山手線、東海道本線、横須賀線、そして東海道新幹線を見下ろすことができました。架線が邪魔ですが、ここもなかなかのトレインビュースポットになりますね。新八ツ山橋を渡らずに、線路に沿って御殿山トラストシティ(→→→こちら)に向かって歩いて行きます。この道沿いもトレインビュースポット。(高輪ゲートウェイから渋谷コース)【つづく】人気ブログランキング山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その3) 新八ツ山橋付近のトレインビュースポット
Nov 20, 2025
コメント(20)
-

山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その2) 品川駅へ向かいます。
高輪ゲートウェイシティを後にして、そして、国道15号(第一京浜)を南の品川駅に向かいます。途中で京浜急行の車両が見えました。このあたり京浜急行の線路とJRの線路が並行しています。品川駅前に到着です。駅前の品川プリンスホテルが見えますね。ここが品川駅です。品川駅の開業は1872年。新橋駅までの正式な鉄道開業以前に品川~横浜間が仮開業したため、東京都内としては最古の駅になります。(高輪ゲートウェイから渋谷コース)【つづく】人気ブログランキング山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その2) 品川駅へ向かいます。
Nov 19, 2025
コメント(22)
-

山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その1) 高輪ゲートウェイ駅
山手線が誕生したのは、明治18年(1885年)。現在の山手線西側半分と、埼京線の1部(赤羽線)をつなげることで品川~赤羽間を結ぶ山手線(当時の名前は品川線)がスタートした。1919年頃は現在の様にぐるっと一周つながっていたわけではなく、路線の形がひらがなの「の」の字ような、少し歪なルートでした。そして大正14年(1925年)に現在の環状運転が完成。今年2025年は山手線環状運転100周年の記念すべき年となりました。そして、MoMo太郎がよく楽しんでいるJR東日本の「駅からハイキング」というイベントでは山手線を一周するスペシャルコースが企画され、そのイベントに参加してきた報告です。最初のイベントとしては高輪ゲートウェイ駅から渋谷駅までのコースが開催されました。ということで、高輪ゲートウェイ駅にやって来ました。山手線は長らく29駅でしたが、令和2年(2020年)にこの高輪ゲートウェイ駅が誕生して、現在は30駅となりました。高輪ゲートウェイ駅は、東京総合車両センター田町センター(旧:田町車両センター)の設備や車両留置箇所の見直しによって創出される約13ヘクタールの再開発用地を利用して造られた駅なので、駅の東側にはこのように車両基地として利用されています。こちらが駅舎の外観です。デザインには建築家の隈研吾氏がかかわっているそうで、「2020 年度 グッドデザイン賞」を受賞しています。駅からハイキングに参加していただいたもので。ルートを示したマップと駅スタンプを押すスタンプ帳、そして記念品としてクリアファイルがありました。駅に隣接する「TAKANAWA GATEWAY CITY(高輪ゲートウェイシティ)」(→→→こちら)です。ホテル、レジデンス、オフィスそして商業施設などが入るビルです。この高輪ゲートウェイシティにある商業施設の「NEWoMan高輪」です。また、高輪ゲートウェイシティの壁には、鉄道の歴史を説明する写真などが展示されていました。(高輪ゲートウェイから渋谷コース)【つづく】人気ブログランキング山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋谷(その1) 高輪ゲートウェイ駅
Nov 18, 2025
コメント(20)
-

孤独のグルメ お得だった天丼セット
久しぶりに小諸そばへ行くと、普段は税込み920円の満腹天丼セットが税込み750円となって、しかも海老天が一本増量となっていました。お得だということで迷わず、今日は満腹天丼セットをいただきました。期間は11月21日までらしいので、その日までに小諸そばの近くに行くことがあれば、また食べてみたいです。人気ブログランキングへ孤独のグルメ お得だった天丼セット
Nov 17, 2025
コメント(32)
-

思い出の佐賀へ(その8) 七つ釜と鏡山、そして虹の松原
唐津市呼子町の加部島から唐津市の七ツ釜(→→→こちら)を観光しました。七ツ釜(ななつがま)は、玄武岩がその波の荒々しさで知られる玄界灘(げんかいなだ)の荒波にさらされ浸食されてできた景勝地で、国の天然記念物に指定されています。火山から噴き出た溶岩がここでゆっくり冷えて固まり玄武岩となり、そこに規則正しく割れ目が入った柱状節理となっています。そして、最後に訪れたのは鏡山(→→→こちら)です。鏡山の名前は、神功皇后が三韓征伐の戦勝を祈願し山頂に鏡を祀ったことに由来するそうです。鏡山は標高284mの山で、眼下に市街地はもちろん、国の特別名勝・虹の松原や唐津湾、そのかなたに壱岐の島影をも望む、絶景を誇る名所です。こちらが虹の松原(→→→こちら)です。虹の松原は、幅約500 m、長さ約4.5 km にわたって弧状に約100万本のクロマツの林が続く特別景勝です。パノラマ写真に加工して載せたかったのですが、パソコンをWindows 11に更新したので、その加工できるレタッチソフトが使えなくなりました。この虹の松原は、17世紀初頭、唐津藩の藩主である寺沢広高が新田開発の一環として、もともとの自然林から防風林、防砂林として植樹を行ったことでできたそうです。そして、これが唐津城です。また鏡山は佐用姫伝説(→→→こちら)の舞台でもあるそうです。佐用姫が、朝鮮半島へ船出する大伴狭手彦をいとおしみ、鏡山の頂上から領布を振り名残りを惜しんだということで、その佐用姫の石像も建てられてました。今から思えば、唐津で勤務していたことは、まだ若く駆け出しだったため、経験を積み、自分の腕を磨くために仕事ばかりしていて、こんな自然や歴史に恵まれた素晴らしい所に住んでいながら、しっかりとこの地域の魅力を味わえなかったことに悔いが残ります。そして、もうひとつ佐用姫のような素敵な女性にも縁がなかったことも心残りです。わが青春は悔いだらけです。【了】人気ブログランキング思い出の佐賀へ(その8) 七つ釜と鏡山
Nov 16, 2025
コメント(24)
-

思い出の佐賀へ(その7) 呼子大橋とイカの活造り
唐津市呼子町には多くの観光スポットがあります。そのひとつの呼子大橋(→→→こちら)を渡って加部島へ渡りました。呼子大橋は、唐津市の離島である加部島と九州本土を結ぶ道路橋です。呼子大橋と呼ばれていますが、橋の親柱には加部島農道という銘板があり、元々は佐賀県農林部が農林水産省補助事業として計画した橋だそうです。この橋を同行した友人たちと歩いて渡りました。車を運転してくれていた佐賀市に住む友人は車で先に橋を渡って待っていてくれました。建設当時はPC斜張橋としては日本国内最長の支間距離を誇っていたそうで、昭和63年度土木学会田中賞受賞(→→→こちら)、プレストレストコンクリート技術協会作品賞受賞。平成元年度農業土木学会上野賞受賞(→→→こちら)。ちなみに田中賞というのは、関東大震災後の首都の復興に際し、帝都復興院初代橋梁課長として、隅田川にかかる永代橋や清洲橋といった数々の名橋を生み出した、田中豊博士に因む表彰です。また、上野賞というのは、忠犬ハチ公で有名な上野英三郎博士(→→→こちら)に因んだ表彰です。これが呼子大橋の全景です。呼子大橋の中に添架されているパイプラインで運ばれた農業用水で潤されている加部島の畑です。昼食は呼子で有名なイカの活造りです。またイカの下足は天ぷらにしていただきました。今年はイカが不漁らしく、予約しておかないと食べらなかったそうです。このお店を予約してくれた古川君の心づかいありがたいです。【つづく】人気ブログランキング思い出の佐賀へ(その7) 呼子大橋とイカの活造り
Nov 15, 2025
コメント(28)
-

思い出の佐賀へ(その6) 呼子朝市と呼子港
唐津で一泊して、朝から呼子朝市(→→→こちら)を訪れました。呼子朝市は、唐津市呼子町呼子朝市通りで開かれる朝市のことで。石川県輪島市の輪島朝市、千葉県勝浦市の勝浦朝市、岐阜県高山市の宮川朝市に次ぐ規模と歴史を有し、日本四大朝市とも称されるそうです。呼子町は漁業が盛んで新鮮な海産物が手に入り市場に並べられるほか、農業も盛んで季節の野菜や花、果物などの品が並べられています。でも平日の朝ということもあって、まだ観光客はまばらでしたが、休日などは賑わうんでしょうね。呼子朝市通りのそばには呼子港があり、近隣の島々へ渡る船が発着するほか漁船も多く停泊しています。こちらの船は、ゴミをおろしていました。おそらく周辺の島で出た廃棄物を運んできて、唐津市内の処分場で処理しているんでしょうね。小さな港ですが、生活に密着した港ですね。【つづく】人気ブログランキング思い出の佐賀へ(その6) 呼子朝市と呼子港
Nov 14, 2025
コメント(20)
-

思い出の佐賀へ(その5) 名護屋城博物館と曳山展示場
佐賀県唐津市鎮西町にある佐賀県立名護屋城博物館(→→→こちら)へも訪れてみました。この博物館が開館したのは平成5年(1993年)10月30日だそうで、MoMo太郎が佐賀県唐津市で暮らしていた40年近く前には、こんな立派な博物館はありませんでした。雨が降ってきて、傘をさしたまま撮影してしまい、なんか傾いた写真になって申し訳ありません。この模型が名護屋城になります。名護屋城は豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)に際して出兵拠点として築かれた城です。1592(文禄元)年の開戦から秀吉の死で諸大名が 撤退するまで、7年の間大陸侵攻の拠点となった城で、城の面積は約17ヘクタールにおよび、当時では大坂城に次ぐ規模を誇っていたそうです。また、周囲には130以上に上る諸大名の陣屋が構築され、全国から20万人を超える人々が集ったとされています。現在では名護屋城跡と23箇所の陣跡が国の特別史跡に指定されています。これは、朝鮮出兵の際に使われた船の模型です。帆があるのは日本の軍船(安宅船)で隣の平べったい船は朝鮮軍が使った亀甲船だそうです。、その他、秀吉が名護屋城に造った黄金の茶室も復元されており、なかなか見応えのある展示物がありました。これだけそろえて入館料が無料とは、無料大好きのMoMo太郎には有り難い施設ですね。そして、唐津市内で一泊するため、唐津市の中心街に戻ってきた時に訪れたのが、唐津市の曳山展示場です。こちらは入場料310円が必要です。ここでは、毎年、11月2日から4日にかけて行われる、唐津市内最大のお祭り「唐津くんち」で町内を巡行する14台の曳山が一堂に公開されています。というか、大変貴重な曳山なので、ここで地震や火災から守るために、こちらで保管されているといったものでしょうか。「唐津くんち」とは、ユネスコの無形文化遺産に登録されている唐津神社の秋季例大祭で、の事をいいます。唐津くんちの御神輿の渡御にお供して、この曳山が町内を巡行します。曳山は木組み・粘土で原形をつくりその上から和紙を数百回張り重ね、麻布を張り、漆を塗り重ね、金銀を施して仕上げたものです。曳山1台あたりの重さは2~4トンあり、1台あたり曳き子200~400人で曳いていくのですが、浅草の三社祭のように、浅草に住んでいない人でも神輿が担げるというものではなく。この曳山を惹くためには、それぞれの曳山を持つ各町内に住んでいる氏子又はその血縁者で、しかも内孫は曳くことができますが、外孫は曳けないという、厳しい資格審査があるそうです。【つづく】人気ブログランキング思い出の佐賀へ(その5) 名護屋城博物館と曳山展示場
Nov 13, 2025
コメント(22)
-

思い出の佐賀へ(その4) 佐賀県玄海町、浜野浦の棚田
佐賀市内に住む友達の車に乗せてもらって、むかし働いていた佐賀県唐津市の方へドライブしてきました。こちらは玄海町にある浜野浦の棚田(→→→こちら)です。農林水産省主催の「日本の棚田百選」に選ばれています。そして、「恋人の聖地」(→→→こちら)にも選定されているそうです。恋人の聖地というのは、NPO法人地域活性化支援センターが取り組んでいる「恋人の聖地プロジェクト」によって選定されるそうです。このプロジェクトの目的は「少子化対策と地域の活性化への貢献」ということで、地域を代表する観光施設・地域が選ばれているそうです。そして、この幸せの鐘「エターナルロック」を鳴らせば、永遠の愛が誓えるんだとか。佐賀県遺産としても登録されています(→→→こちら)。この説明板によれば、戦国時代から江戸時代にかけて先人たちの偉業により山を切り開き、石を積み上げ築かれてきた。棚田の石垣は、加工を施さない自然石を使った野面(のづら)積みが一部残り、名古屋城の石垣、穴太(あのう)積みの特徴が見受けられる。とありました。確かに、自然石を使った野面積みが残っていますね。【つづく】人気ブログランキング思い出の佐賀へ(その4) 佐賀県玄海町、浜野浦の棚田
Nov 12, 2025
コメント(30)
-

思い出の佐賀へ(その3) 佐賀市には恵比寿様が多い
こちらの建物は佐賀市役所です。この佐賀市には何故か恵比寿様が多いそうです。その数は佐賀市内だけで830体以上あるそうです。佐賀駅前にもその恵比寿様を三体を見つけました。これは「よかよか恵比寿様」です。駅前の宝くじ売り場のそばにありました。佐賀駅バスセンターにあった「葉がくれ恵比寿」です。これは市役所の近くにあった「だっこ恵比寿」だそうです。もともと佐賀で恵比須信仰が始まったのは、鍋島藩初代藩主の鍋島勝茂公が兵庫県西宮市にある“えびす宮総本社・西宮神社"に崇敬が深かったことに由来するといわれています。【つづく】人気ブログランキング思い出の佐賀へ(その3) 佐賀市には恵比寿様が多い
Nov 11, 2025
コメント(18)
-

思い出の佐賀へ(その2) 佐賀駅前にあった銅像
佐賀駅です。佐賀駅前広場にあった「面浮立(めんぶりゅう)」(→→→こちら)の像です。面浮立とは、佐賀県を代表する民俗芸能として全国的にも有名なもので、いかめしい鬼の面を被った勇壮な掛け打ち姿の舞い手を主役として、浮立(フリュウ)行列が鉦(カネ)や太鼓・笛などを囃して行うものだそうです。実物を一度見てみたいものですね。こちらの三名の銅像は、左から、古賀穀堂・鍋島直政・鍋島茂義の銅像だそうです。その隣に、「名将・鍋島直正と直正を支えた賢人たち」という説明板がありました。鍋島直正(→→→こちら)は肥前佐賀藩10代藩主だった人で、維新後に軍防事務局輔、開拓長官、大納言などを歴任したそうです。古賀穀堂(→→→こちら)は、江戸時代後期の朱子学者・佐賀藩年寄として藩政改革に取り組み、鍋島直正が西洋技術を佐賀藩に積極的に導入する素養を育んだ人物だったそうです。鍋島茂義(→→→こちら)は、武雄鍋島家9代当主。28代佐賀藩自治領武雄領主です。日本の封建領主で最初に高島秋帆に弟子入りして西洋式砲術や科学技術を究めると共に、義弟で10代藩主・斉正(直正)に大きな影響を与え、幕末期の佐賀藩の高度な軍事力・技術力開発のさきがけとなったそうです。人気ブログランキング思い出の佐賀へ(その2) 佐賀駅前にあった像
Nov 10, 2025
コメント(18)
-

思い出の佐賀へ(その1) 羽田空港
羽田空港の第2ターミナル展望デッキから沖を行く船を撮影しました。ここから飛行機に乗って、福岡空港経由で佐賀へ向かいました。佐賀はまだ30代の頃、暮らした土地です。思い出の佐賀県唐津市への旅に出発です。【つづく】人気ブログランキング思い出の佐賀へ(その1) 羽田空港
Nov 9, 2025
コメント(4)
-

727とは
一昨日から楽天ブログつながりにくくなっていて、どうなっているんでしょうかね。そして、皆さんのところへ訪問できず、失礼しました。今はなんとかつながっているみたいですが、どうなっているんですかね?さて、新幹線に乗っていると、よく見かける野立の看板。そのなかでも、気になったのはこの「727」という看板。下に「COSMETICS」(化粧品)と書かれているんですね。調べてみると「セブンツーセブン」(→→→こちら)という化粧品メーカー会社でした。しかし、普通に小売りはされていなくて、美容室専売で、一般消費者へは契約美容室を通じて化粧品を販売しているそうです。でも、どこの美容室へ行けば買えるんでしょうかね。人気ブログランキング727とは
Nov 8, 2025
コメント(12)
-

日暮里界隈散歩(その10) 田端から三河島へ
向陵稲荷神社から台地の上の道を歩いていくとあった田端台公園です。この公園の近くからは、新幹線や在来線を見下ろせることで、鉄道写真の撮影のポイントみたいですね。新幹線の車両センターへ入庫したり出庫したりする新幹線も撮影できそうですね。JR田端駅のあたりにやって来ると、雨が降り始めました。とりあえず駅からハイキングのゴールの三河島駅へ向かいました。こちらは、常磐線の起点となる日暮里駅を出発して一つ目の金杉踏切です。日暮里~三河島間にある常磐線のカーブ、都内でも有数の大カーブになるそうです。上にある高架橋は京成線の高架橋です。こちらは三河島方面を撮影しました。この鉄路がずっと青森まで続いていると思うと、なにか旅情を感じました。そして、こちらが三河島(みかわしま)駅です。この「三河島」という地名の由来には、以下のような諸説があるそうです。〇三つの川(中川・古利根川・荒川)に囲まれた中洲状の土地であったため。〇太田道灌の時代に、武家歌人の木戸三河守孝範が当地に暮らしたため。〇徳川家康の関東入部の折、三河国から従ってきた人が知行したため。〇徳川家康の関東入部の折、三河国から従ってきた農民を住まわせたため。しかしながら、戦国時代の「北条氏所領役帳」にはすでに「三河ヶ島」の地名が見られるので、、徳川家康にまつわる由来説は江戸時代に生まれた俗説とみられるそうですが、しかし、徳川家康が江戸へ移転した時、開墾のために三河から連れてきた伊藤氏(伊藤七家)などの農家が居住して稲作を行っていたそうで、明治時代には上野の戦いから逃れた彰義隊の残兵が伊藤家に匿われた経緯も史記に残っているそうです。駅は島式ホーム1面2線だけですが、ほとんどの常磐線快速電車および中距離電車が停車する駅です。(日暮里界隈散歩コース)【了】人気ブログランキング日暮里界隈散歩(その10) 田端から三河島へ
Nov 7, 2025
コメント(6)
-

日暮里界隈散歩(その9) 向陵稲荷神社
開成高校の敷地の脇にある坂道です。向陵稲荷(こうりょういなり)坂という名称です。この坂道を登っていくと、神社がありした。名称は「向陵稲荷神社」です。こちらの向陵稲荷神社縁起によると、当社は向陵稲荷大明神(宇迦之御魂神)を主神とし祭祀を行い、祭神の神徳をひろめ本神社を信奉する人々を教化育成し、家内安全・商売繁盛及び学業成就の神であります。 当社は江戸時代初期より佐竹右京太夫の屋敷内に祀られておりましたが、大正の初期渡辺町(現西日暮里4丁目の一部)の開設されたときにひぐらし公園(現開成学園中学校の校庭)に祀られ、町の鎮守と崇められていました。後当初に移転しましたが、昭和20年の大戦災で全町焼土と化しましたが当社は不思議にも戦火をまぬかれ神威赫々として現存し、昭和46年社殿を改築社務所を新設し、宗教法人向陵稲荷神社となりました。と書かれていました。折角来たのでお参りさせていただきます。社額の字体が篆刻に使われるものでした。開成学園の裏にあるので、受験合格祈願にもご利益ありそうですね。(日暮里界隈散歩コース)【つづく】人気ブログランキング日暮里界隈散歩(その9) 向陵稲荷神社
Nov 6, 2025
コメント(18)
-

日暮里界隈散歩(その8) 開成学園
西日暮里駅です。この坂道を下って、道灌山遺跡(→→→こちら)と佐竹屋敷と渡辺町(→→→こちら)の案内板がありました。道灌山遺跡は、開成学園の第2グラウンドを中心に広がる、縄文時代から江戸時代にかけての複合遺跡だそうです。また、佐竹屋敷と渡辺町とは、この付近一帯は、秋田藩主佐竹右京太夫の広大な抱屋敷であったそうです。その後、大正5年に二十七銀行(後の東京渡辺銀行)頭取渡辺治右衛門が入手し、近代的田園都市を目指した高級住宅地を建設・分譲したそうです。そして、こちらにあるのは、「ペンは剣よりも強し」の校章で有名な開成学園(開成高校・開成中学)(→→→こちら)です。個々の卒業生、MoMo太郎の同業者にもかなりいるのですが、意外と下町にあった学校だったんですね。(日暮里界隈散歩コース)【つづく】人気ブログランキング日暮里界隈散歩(その8) 開成学園
Nov 5, 2025
コメント(24)
-

日暮里界隈散歩(その7) 芦田愛菜さんの母校
諏方神社を出ると小学校の校門があります。この学校は、「日暮里第一小学校」です。あまり知られていないと思いますが、芦田愛菜さんの母校です(→→→こちら)。ちなみに愛菜さんの通っていた幼稚園は兵庫県西宮市、甲子園球場の近くにある光明幼稚園で、MoMo太郎が通った幼稚園です。そういうことで、芦田愛菜さんの浅からぬ因縁を感じるMoMo太郎、今度生まれ変わったら芦田愛菜さんの父親になりたいと諏方神社にお願いしておきました。校門の脇にあった石碑です。こちらの説明板によると、これは、高村光太郎書「正直親切」の記念碑だそうです。「正直親切」の文字は、本校卒業生である高村光太郎(→→→こちら)の直筆で、昭和26年岩手県山口小学校の児童のためにかかれたものを高村規氏、財団法人高村記念会のご厚意により創立百周年記念碑に使わせていただいものだそうです。高村光太郎 は、明治23年に下谷区練塀小学校から日暮里小学校(当時は、現在の福祉館の場所に校舎がありました)に転校、ここで勉強し小学校を卒業した縁からここに建立したそうです。また、「フクロウ」の像は、石彫家飯田雅光氏の作で、校歌にもある〝諏訪の森かげ、みどりの風に〟ふさわしい《森の知者》として、一日小の子どもたちのシンボルとされているものです。ふりがなもふってあって、低学年の子供たちには有り難いですね。(日暮里界隈散歩コース)【つづく】人気ブログランキング日暮里界隈散歩(その7) 芦田愛菜さんの母校
Nov 4, 2025
コメント(22)
-

日暮里界隈散歩(その6) 諏方(すわ)神社
冨士見坂を登り切ったところにあった神社です。新東京八名勝日暮里諏方神社という大きな石碑が建立されていました。新東京八名勝(→→→こちら)とは、昭和7年(1932年)に報知新聞が選定した東京の8ヵ所の名勝地だそうです。池上本門寺(大森区)・西新井大師(足立区)・北品川 天王社(品川神社)(品川区)・日暮里 諏訪神社(荒川区)・赤塚の松月院(板橋区)・目黒の祐天寺(目黒区)・洗足池(大森区)・亀戸天神(城東区)だそうです。区名は当時の区名です。この神社が八名勝に選ばれたのは、神社がJR山手線の線路沿いの高台にあり、江戸時代には、筑波や日光の連山などが見えたことから、景勝の地として知られていたことからでしょう。荒川区の建立した諏方(すわ)神社(→→→こちら)の案内板がありました。元久2年(1205年)の創立で、豊島左衛門尉経泰が勧請したとの伝承があります。「諏方神社」の「諏方」(すわ)は、本崇社である信州諏訪大社の古い神社名と伝わっており、それを使っているとのこと。江戸時代、三代将軍徳川家光に社領五石を安堵され、日暮里(旧 新堀)・谷中の総鎮守として広く信仰を集めているそうです。境内はなかなか広いです。例祭は毎年8月。境内や周辺の道路に露店が立ち並び、多くの人々で賑わそうです。また3年に一度の御神幸祭と呼ばれる大祭では、本社神輿が町内を渡御するそうです。手水舎、手をかざすと竜の口から水が出て、樋を流れてくる仕組みがちょっと面白かったです。こちらが社殿です。(日暮里界隈散歩コース)【つづく】人気ブログランキング日暮里界隈散歩(その6) 諏方(すわ)神社
Nov 3, 2025
コメント(24)
-

日暮里界隈散歩(その5) 冨士見坂
この坂道は、冨士見坂(→→→こちら)と呼ばれています。この坂道を登ってみると富士山が見えるかも。ダイヤモンド富士山も見えるんでしょうか、坂の途中にここから撮影した写真が展示されていました。しかし、平成25年6月頃に建物により富士山の姿は見えなくなったそうですが、今でも建物と建物のすき間から見えることもあるらしく、その時の写真だそうです。こちらは、建物が建てられても富士山が見えていた時代の写真だそうです。坂の上には、荒川区の設置した案内板がありました。平成16年11月に国土交通省関東地方整備局より「関東の富士見百景」に選定されていたそうです。坂の上から富士山が見えるかどうか試しに撮影してみましたが、曇りで富士山は見えそうではなかったです。ちょっと坂を下ったこのあたりなら、ひょっとしたら見えるかも。今度天気のいい時に挑戦してみようかな。(日暮里界隈散歩コース)【つづく】人気ブログランキング日暮里界隈散歩(その5) 冨士見坂
Nov 2, 2025
コメント(24)
-

日暮里界隈散歩(その4) 谷中ほたるさわポケットパーク
谷中銀座商店街の近くあるポケットパーク。「谷中ほたろさわポケットパーク」というそうです。昔はこのあたりに蛍が群れ飛んでいたんですね。このあたりは路地が入り組み住居や商店が密集しているので、地域の防災性向上のために整備されたポケットパークだそうです。そして、こちらは人気の谷中銀座商店街です。天気は雨が降りそうてしたが、人出はおおいですね。谷中銀座商店街を横切って、谷中の住宅街の中を進んでいきます。道路脇に石碑が何が書いてあるのか、わかりませんでしたが、わざわざ残してあるところをみると、由緒ある石碑なんでしょうね。「ろくあみだみち」と刻まれた石碑がありました。六阿弥陀詣(→→→こちら)に使われた道だったんでしょうか。ちなみに六阿弥陀詣りとは、江戸市中および近郊の6つの寺に安置されている阿弥陀如来木像またはその寺のことで、春秋の彼岸にこれらを巡拝することが元禄年間(1700年前後)から盛んになったそうです。(日暮里界隈散歩コース)【つづく】人気ブログランキング日暮里界隈散歩(その4) 谷中ほたるさわポケットパーク
Nov 1, 2025
コメント(30)
-

It's Halloween
今日はハロウィン。ということでThe Shaggs (→→→こちら)というガールズバンドが演奏する"It's Halloween "という曲をお楽しみ下さい。「なんだ、これは」と思いながら、最後まで聞き通した方は大したものです。音楽を構成する三大要素はメロディ・ハーモニー・リズムの3つと言われていますが、この内どれか一つでも欠けてしまうと音楽とは呼べなくなるものですが、このThe Shaggs(シャッグス)というバンドそんなことは、お構いなく、下手と言うのも憚られるほど演奏技術が全く無い。にも関わらず、一部界隈では非常に知名度が高いバンドです。シャッグスは'60年代末からアメリカのニューハンプシャーの田舎町で活動していた実の姉妹によるロック・バンドで、アマチュアの上ティーンエージャーでしたから活動場所は地元だけでした。そして、1975年にはマネージャーだったお父さんの逝去によって解散し、その後メンバー全員が家庭の主婦になりました。しかし1980年に通好みの渋いリリースで定評のあるインディー・レーベル、ラウンダー・レコーズからの再発売によって知名度が上がり、ローリング・ストーン誌のカムバック・オブ・ジ・イヤーを受賞します。シャッグスはアメリカのロック界の巨匠、フランク・ザッパが'70年代半ばのプレイボーイ誌のインタビューで「シャッグスという誰にも知られていない、ビートルズ以上のバンドがいるよ」と言ったことがきっかけで、ローリング・ストーン誌の受賞につながったようです。でも、考えてみれば、ビートルズだって、天才ピアニスト清塚信也だって、音楽を始めた頃は、こんな拙い演奏だったろうし、作った歌詞もこんなに無垢な内容です。It's Halloween, it's HalloweenIt's time for scares, it's time for screamsIt's Halloween, it's Halloweenハロウィンです。ハロウィンです。怖い時間です。 叫び声の時間です。ハロウィンです。ハロウィンですThe ghosts will spook, the spooks will scareWhy, even Dracula will be thereIt's time for games, it's time for fun幽霊は怖がらせます。お化けは怖いです。なぜ、ドラキュラもそこにいるでしょう。ゲームの時間です。お楽しみの時間です。Not for just one, but for everyoneThe jack-o-lanterns are all lit upAll the dummies are made and stuffedBy just looking you will see, it's this time of year againIt's Halloween, it's Halloween1人だけのためではなく、みんなのためにジャック・オ・ランタン(ハロウィンには欠かせないカボチャをくり抜いた提灯)が全部ライトアップされる。ぬいぐるみも作られます。わかるでしょう。またこの時期になった。ハロウィンです。ハロウィンです。All the kids are happy and gayThere doesn't seem to be a cloud in their wayBut when it's over, and they've had all their funThey'll wish that Halloween had just begun子供たちはみんな幸せで陽気です。彼らの前に遮る雲はないようです。しかし、それが終わり、彼らはすべての楽しみを味わったとき彼らはハロウィーンが始まったばかりだったらいいのにと思うでしょうOh, there are witches, goblins, vampiresDemons, Frankensteins and zombiesAnd there are tramps, Cinderellas, pirates, angels and gypsiesSo let's have lots of fun and give many cheersFor Halloween comes but once a yearああ、魔女、ゴブリン(子供を食べる鬼)、吸血鬼、悪魔、フランケンシュタイン、ゾンビがいますそして浮浪者、シンデレラ、海賊、天使、ジプシーがいます。だから、ハロウィンの間は、たくさんの楽しみがあります。そしてたくさんの歓声をあげる でもハロウィンは年に一回だけ。It's time for games, it's time for funNot for just one, but for everyoneIt's Halloween, it's Halloween, it's HalloweenIt's HalloweenIt's Halloweenハロウィンです。ハロウィンですハロウィンです。ハロウィンです人気ブログランキングIt's Halloween
Oct 31, 2025
コメント(14)
-

日暮里界隈散歩(その3) 岡倉天心記念公園
谷中の住宅街を歩きます。この谷中、根津、千駄木って、第二次世界大戦中でも戦災がなかった地区だと聞いてましたが、入り組んだ路地などが残っていて、なんかスッキリしない街並みですね。まあ、またそこが風情ある町並みというのでしょうかね。この広い空地は「防災広場初音の森」(→→→こちら)というそうです。区営のスポーツセンター跡地に台東区民のための防災公園として整備されたそうです。隣接している建物は谷中防災コミュニティセンターです。この「防災広場初音の森」から少し谷中銀座商店街の方へ歩くと、こじんまりとした公園があります。この公園が「岡倉天心記念公園」(→→→こちら)です。岡倉天心(→→→こちら)といえば、東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)の設立に大きく貢献し、後年に日本美術院を創設した。近代日本における美術史学研究の開拓者であり、日本の近代美術の先駆者だった人です。東京都指定史跡岡倉天心旧宅旧前期日本美術院跡と刻まれた石碑も建てられていました。公園の様子です。岡倉天心宅跡ということで、公園としては小さいですが、滑り台を置いてあったりして、小さいな児童遊園のようですね。こちらの建物は、岡倉天心史跡記念六角堂で、この中には平櫛田中作の天心坐像が安置されているそうです。発覚堂の前には、「讃 岡倉天心史跡記念堂」という碑文がありました。(日暮里界隈散歩コース)【つづく】人気ブログランキング日暮里界隈散歩(その3) 岡倉天心記念公園
Oct 30, 2025
コメント(28)
-

日暮里界隈散歩(その2) 旧吉田屋酒店
日暮里第二小学校から尾竹橋通りを鶯谷駅の方に向かって歩き、今度は言問通りを通って、谷中・根津方面に向かいます。JR山手線を跨ぐ寛永寺陸橋の上から、北の方を撮影すると、京成電鉄の車両がJR線の上を渡っていくところが撮影できました。言問通りを歩いて行くと、古くからあるような商家の建物がありました。看板には、吉田屋本店とありました。建物の前にあった案内板です。台東区のしたまちミュージアム付設展示場の「旧吉田屋酒店」(→→→こちら)です。台東区谷中6丁目で江戸時代から代々酒屋を営んでいた「吉田屋」の建物が移築され、酒類の販売に用いる道具や資料が展示されているそうです。建物は明治43年(1910年)に建築されたもので、当時の商家建築の特徴をよく伝えているものだそうです。谷中の歴史やそこに住んだ人々の生活を私たちに知らせてくれる、貴重な民俗資料となっています。店内の様子です。こちらには酒瓶などが展示されています。また、宣伝用のポスターなども展示されていました。店に置いてあった五玉そろばん。MoMo太郎の祖父は、ずっと五玉そろばん使っていました。最近は小学生の間で習い事として、「そろばん」が人気あるようで、この間も電車の中で、小学生の女の子が母親に向かって「私の好きな習い事は、そろばんと水泳」と話していました。でも五玉そろばんは、使ったことがないでしょうね。旧吉田屋酒店と道路を挟んで向かい側あった喫茶店(→→→こちら)。ちゃんと営業しているみたいです。(日暮里界隈散歩コース)【つづく】人気ブログランキング日暮里界隈散歩(その2) 旧吉田屋酒店
Oct 29, 2025
コメント(22)
-

日暮里界隈散歩(その1) 夕焼け小焼けの記念碑
10月4日(土)、JR東日本が開催している駅からハイキング「日暮里駅・三河島駅開業120周年軌跡をたどるハイキング」に参加しました。その報告です。出発は、ここ日暮里駅からです。「にっぽりせんい街」と呼ばれる日暮里中央通りを歩いて行きます。日暮里は布の街だそうです。日暮里中央通りに面して、荒川区立日暮里第二小学校(→→→こちら)がありました。こちらにあった石碑には、「学校敷地四百九拾坪寄附 記念碑 元金杉」と刻まれていました。小学校の建設にあたって490坪の敷地を寄付したことの記念碑なんでしょうね。ちなみに金杉とは日暮里のこのあたりの地名のようです。そして、こちらの石碑は、「夕焼け小焼けの記念碑」(→→→こちら)です。童謡「夕焼け小焼け」の歌詞が刻まれていました。この「夕焼け小焼け」を作詞した童謡詩人・中村雨紅(1897年~1972年)が、大正5年(1916年)に第二日暮里小学校へ教師として赴任、そして近くにある第三日暮里小学校へ転勤した後の大正8年(1919年)に作詞した作品だったことから、ここに石碑が建立されたそうです。ちなみに、日暮里第三小学校では、この童謡にちなんだ記念塔があるそうです。(日暮里界隈散歩コース)【つづく】人気ブログランキング日暮里界隈散歩(その1) 夕焼け小焼けの記念碑
Oct 28, 2025
コメント(22)
-

練馬区の公園で見つけた石碑
練馬区豊玉北にある北新井公園、西武池袋線江古田駅近くにある武蔵大学の裏にある住宅地の中の公園です。この公園の片隅に立派な石碑が建立されています。この石碑は、「中新井町第三区画整理組合之記」(→→→こちら)というもだそうです。昭和の初めごろは不況で、農家の生活はどこも大変だったので、また、練馬大根が不作も重なり、転入者に家や宅地を貸して豊かになろうということで、村全域に区画整理が行われることになり、その事業が完成したことを記念して建立されたもののようです。このような経緯を丁寧に調べて、論文にされている方もおられたんですね(→→→こちらとこちら)。石碑って町の歴史を教えてくれるものなんですね。人気ブログランキング練馬区の公園で見つけた石碑
Oct 27, 2025
コメント(22)
-

行田を歩く(その23) 秩父鉄道行田市駅
駅からハイキング「行田が誇る田んぼアートと足袋蔵の街並みを歩く」もゴールの秩父鉄道行田市駅にやってきました。駅前にある妖しい雰囲気の夜お店。どんな熟女がいるのかな。JR高崎線には行田駅(→→→こちら)というがあります。元々は1921年(大正10年)にこちらの秩父鉄道のこの駅が行田駅として開業していたのですが、高崎線に1966年(昭和41年)に行田駅が開業にともない行田市駅となったそうです。島式ホーム1面2線だけの小さな駅でした。昔、東急電鉄で見かけたようなこの列車で羽生に戻ります。車内で天井を見ると、エアコンもあったけど懐かしい扇風機がついていました。(行田を歩いたコース)【了】人気ブログランキングへ行田を歩く(その23) 秩父鉄道行田市駅
Oct 26, 2025
コメント(32)
-

行田を歩く(その22) 「観光物産館ぶらっと♪ぎょうだ」と「時田蔵」
この建物は行田市商工センターです。この建物の半地下のフロアにあるのが、「観光物産館ぷらっと♪ぎょうだ」(→→→こちら)です。行田のお土産がたくさん並んでいます。でも塩あんびん(→→→こちら)は見かけませんでした。行田市商工センターの前にあった昭和天皇行田市行幸時の陰碑だそうです。昭和天皇が行田市に行幸したときに詠まれた歌を侍従長の入江相政氏が記したものが刻まれていました。忍警察署跡を記した石碑もありました。忍者の警察署ということではないですよね。商工センターの裏側の通りにあったのが、こちらの足袋蔵と住宅です。時田啓左衛門商店が昭和15~16年頃建設した和洋折衷住宅、明治36年(1903)竢工と大正初期頃建設の2棟の土蔵造りの足袋蔵だそうです。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その22) 「観光物産館ぶらっと♪ぎょうだ」と「時田蔵」
Oct 25, 2025
コメント(24)
-

行田を歩く(その21) 国登録有形文化財もありますよ
行田市、否、埼玉を代表する銘菓「十万石まんじゅう」(→→→こちら)の十万石ふくさや行田本店店舗。こちらは明治16年(1883年)棟上の元山田呉服店の重厚かつ豪勢な店蔵。後に足袋蔵に転用され、現在は埼玉県を代表する和菓子店の店舗になっていますが、国の登録有形文化財となっています。こちらの石造りの蔵から、こちらのモルタル造りの蔵までが、保泉蔵です。元行田随一の足袋原料商店の昭和元年(1926年)建設の石造の店蔵・主屋、明治後期と大正5年(1916年)建設の土蔵、昭和7年(1932年)棟上の石蔵、昭和戦前期建設のモルタル蔵が、敷地東側に一列に並んでいます。こちらは武蔵野銀行行田支店ですが、国登録有形文化財です。足袋産業の資金面を支えた忍貯金銀行が昭和9年(1934年)に竣工させた本格的銀行建築の店舗です。戦後は足袋会館(足袋組合事務所)となり、行幸で昭和天皇も訪れているそうです。街角に展示されていた「浮き城の町行田」のモニュメントです。浮き城とは、関東七名城に謳われた忍城ことです。文明年間(1469~86年)の初め頃に築城され、上杉、北条氏との戦いにも落城せず、石田三成の水攻めにも耐えた、戦国の世を生き抜いた名城です。【謹んで訂正】昨日の記事で、TVドラマ「陸王」(→→→こちら)で傾きかけた足袋業者から一流ランニングシューズメーカーに転身した「こはぜ屋」さんの工場ですね。と書いていましたが、そのことで本当に、足袋製造からランニングシューズメーカーになった会社があると多くの人が思われたようです。あれはあくまで池井戸潤氏の小説のことで、フィクションです。みなさんの誤解を招くような記事を書いてしまい誠に申し訳ありませんでした。ここで謹んでお詫び申し上げます。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その21) 国登録有形文化財もありますよ
Oct 24, 2025
コメント(24)
-

行田を歩く(その20) 「こはぜ屋」さんです
行田八幡宮の裏手にあったのが、この工場。どこかで見た覚えのある工場?。思い出しました、むかしTVドラマ「陸王」(→→→こちら)で傾きかけた足袋業者から一流ランニングシューズメーカーに転身した「こはぜ屋」さんの工場ですね。「こはぜ屋」ってあったんだと思ったら、イサミコーポレーションスクール工場だったんです。工場の中にははいれませんでしたが、工場の裏側に回ってみたら、大正6年(1917)建設のノコギリ屋根の旧足袋工場がちょっと見えました。こちらは改装中の建物ですが、小川源右エ門蔵という商品倉庫です。近江商人のカネマル酒店が昭和2年に建設した商品倉庫。戦前の行田を代表する大型の石蔵だそうです。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その20) 「こはぜ屋」さんです
Oct 23, 2025
コメント(20)
-

行田を歩く(その19) 行田八幡宮
行田の総鎮守神社とされている行田八幡宮(→→→こちら)です。行田八幡宮の御由緒と社伝虫封御祈祷に関する案内板です。御由緒としては、元和・宝永・弘化の年間における行田町大火の際、再三の類焼の災禍に会い、旧記重宝等を焼失して御創祀の次第は判然しないそうですが、口碑によると源頼義・義家が、奥州討伐のためこの地に滞陣した折、戦勝を祈願して勧請されたと伝えられています。また、行田八幡神社は、「封じの宮」と称され、子供の夜泣きやかんの虫を封じる虫封じをはじめ、癌の病、難病や悪癖の封じ、お年寄りのぼけ封じなどの封じ祈願が秘法として継承されているそうです。というありがたいお宮なので、早速お参りさせてもらいました。こちらが拝殿です。皇紀2650年を記念して造営が進められ、平成元年11月に竣功したものだそうです。ご祭神は、誉田別尊(ほむだわけのみこと)[応神天皇]応神天皇にして、弓矢の神として尊崇せられると共に、大陸の文化を取り入れられ、わが国文教の祖、殖産興業の神として崇められています。気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)[神功皇后]仲哀天皇の皇后にして神功皇后と申し上げます。応神天皇とは、御母子であらせられることから、安産、子育ての神として信仰があります。比売大神(ひめのおおかみ)市杵島姫命・田霧姫命・湍津姫命の三神にして天照大御神の神勅により宇佐島に天降り給いし神で、道中安全・交通安全・学芸の道を司り給うご神徳があります。大物主神(おおものぬしのかみ)別名大国主神と申し上げ、縁結びの神として有名です。神素盞鳴尊(かむすさのおのみこと)天照大御神の弟神で邪悪なるものを追い払い、人々の苦しみを除いて守護される神として知られています。結構、多くの神様が祭られているんですね。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その19) 行田八幡宮
Oct 22, 2025
コメント(20)
-

行田を歩く(その18) 足袋蔵の町を歩く
行田市の町の中心部にやって来ました。埼玉県北部に位置する行田市は江戸後期〜昭和中期にかけ「足袋」の生産で栄えた街です。その頃の名残として今も街なかに点在する 主に「足袋蔵」があることから、平成29年(2017年)に「和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田」として日本遺産に認定されたそうです。その足袋蔵を順次巡っていきます。こちらもその足袋蔵のひとつ「大澤家住宅旧文庫蔵・住宅・土蔵」です。7代大澤専蔵が大正15年(1926)に竣工させた市内唯一のレンガ造りの足袋蔵だそうです。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その18) 足袋蔵の町を歩く
Oct 21, 2025
コメント(24)
-

行田を歩く(その17) 古墳通りを歩く
埼玉古墳群、世界遺産の登録を狙っているんですね。頑張って下さい。観光物産館さきたまテラス(→→→こちら)です。お土産でも買おうかと思って立ち寄りましたが、クッキーとか煎餅だったので、さきほどの「塩あんびん」(→→→こちら)を買っとけばよかったと思いました。埼玉県道77号行田蓮田線、行田市では「古墳通り」と呼ばれている道を北西方向、秩父鉄道の行田市駅に向かって歩きます。途中で再び武蔵水路を横断します。人工の水路みたいですが、一級河川になるんですね。古墳通りというだけあって、歩道の舗装ブロックに埴輪の絵が描かれているんですね。道端に石碑があったので、見てみると、「忍城十五門の内八軒口御門跡」と刻まれていました。このあたり忍城(→→→こちら)の城下町だったんですね。古墳通りを歩いて、古墳時代から中世近世にワープしてきた感じですね。行田名物のフライ(→→→こちら)だそうです。フライといっても揚げ物ではなく、クレープのようなお好み焼きだそうです。フライ、食べてみたかったです。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その17) 古墳通りを歩く
Oct 20, 2025
コメント(26)
-

行田を歩く(その16) 埼玉」の地名の語源となった前玉神社
「埼玉」の地名の語源となった前玉(さきたま)神社(→→→こちら)に参拝の続きです。石鳥居は行田市指定文化財だったんですね。社号碑も歴史を感じさせますね。延喜内社ということは延長5年(927年)にまとめられた延喜式神名帳に記載された神社のことで、10世紀初頭には朝廷から官社(朝廷から供物が支給される神社)として認識されていた神社ということです。社殿までは結構距離がある広い境内の神社です。鳥居の背後にある林は、浅間塚古墳(せんげんづかこふん)です。この墳頂に前玉神社の社殿が鎮座しています。ちなみに浅間塚古墳は埼玉古墳群(→→→こちら)の一部になるのかどうかはよくわかりませんでした。前玉神社の創建は不詳ですが、埼玉古墳群内に鎮座していることから、古墳群の首長層が前玉神社における古代祭祀集団と推定されて、古墳時代に古墳群を守護する形で祀られたのが創祀になると推測する説もあるのだとか。また、社名「前玉(さきたま)」の由来も明らかではないのですが、神亀3年(726年)の戸籍帳である「山背国愛宕郡雲下里計帳」(正倉院文書)にも「武蔵国前玉郡」の表記が見えることから、この「前玉」がのちに「埼玉(さきたま/さいたま)」へと変化したと考えられているそうてです。鳥居に掲げられた神額です。前玉神社の絵馬は、なぜかみんな猫の顔になっています。絵馬というより絵猫なんですね。こちらの神社は、古墳の中腹にある浅間神社(→→→こちら)です。こちらは、近世初頭、忍城中にあった浅間神社を勧請し、古墳上にある社を「上の宮」、中腹にある社を「下の宮」と呼んで、浅間さまの名で親しまれるようになったそうです。浅間神社なので御祭神は、木花開耶姫命(コノハナサクヤヒメ)になります。そしてこちらの階段の上にあるのが前玉神社本社になります。この本社に登る階段をはさむように建立されている2つの燈篭。これは、元禄10年(1697年)10月15日、氏子のみなさんが所願成就を記念して奉納したものですが、この地を詠んだ万葉集の歌、「小崎沼」と「埼玉の津」が刻まれているので「万葉燈篭」(→→→こちら)と呼ばれています。万葉集の「小崎沼」と「埼玉の津」の歌はそれぞれ次のようなものです小埼沼(巻9、1744番、作者不詳) 万葉仮名文前玉之 小埼乃沼爾 鴨曽翼霧己尾爾 零置流霜乎 掃等爾有欺 訓埼玉の 小埼の沼に 鴨そ翼(はね)霧(き)る己(おの)が尾に 降りおける霜を 払ふとにあらし埼玉の津(巻14、3380番、作者不詳) 万葉仮名文佐吉多万能 津爾乎流布禰乃 可是乎伊多美都奈波多由登毛 許登奈多延曽禰 訓埼玉(さきたま)の 津に居(を)る船の 風をいたみ綱は絶ゆとも 言(こと)な絶えそね歌にある「小埼沼」は前玉神社から東方にあったと比定されいるそうです。前玉神社の御祭神は、「古事記」にある出雲系の神である前玉比売神(サキタマヒメノミコト)。そして前玉彦命(サキタマヒコノミコト)の二柱です。女神と男神が一緒に祀られていることから、恋愛成就や夫婦円満の神社として参拝する方が多いのだとか。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その16) 埼玉」の地名の語源となった前玉神社
Oct 19, 2025
コメント(22)
-

行田を歩く(その15) 前玉神社の門前にある製菓店
「埼玉」の地名の語源となった前玉(さきたま)神社(→→→こちら)に参拝しました。埼玉県道77号行田蓮田線(古墳通り)に面して前玉神社の入口があります。前玉神社の門前にあるこの製菓店(→→→こちら)、かなり歴史がありそうな店構え、調べてみると安政5年(1858年)の創業だそうです。幟には「塩あんびん餅」とありますが、農林水産省のホームページ(→→→こちら)では、久喜市や加須市、行田市といった埼玉県北部から東部にかけての地域では、新米の収穫を祝い古くから「塩あんびん」を食べてきた。「塩あんびん」とは、砂糖の代わりに塩を使って味付けしたあんをもちで包んだもののことで、小豆やもち米本来の甘みを塩が引き立てているのが特徴。現在では甘いあんが主流だが、こちらは江戸時代中期に生まれたもので、当時砂糖は大変貴重だったため、庶民はめったに口にできなかったと言われている。「塩あんびん」が伝わる地域では、地元民の身近な郷土料理のひとつであるが、収穫祝いを始めとするハレの日に多く食べられてきた。ということでした。隠し味として塩を使ったということですね。確かにスイカを食べる時に塩をふりかけたりするのと同じなんですね。やっぱり埼玉古墳群の近くあるので、こういう最中も販売しているんですね。この最中の餡にも隠し味で塩が使われているのかな?ということで前玉神社へお参りします。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その15) 前玉神社の門前にある製菓店
Oct 18, 2025
コメント(24)
-

行田を歩く(その14) 埼玉県立さきたま史跡の博物館
こちらの建物が「埼玉県立さきたま史跡の博物館」(→→→こちら)です。史跡に関する資料及びその他の考古資料の収集、保管及び調査研究を行うとともに、その活用を図ることにより、教育、学術及び文化の発展に寄与するための施設です。入館料は200円です。、入口にあるのは、埴輪の顔だパネルです。こちらの「さきたま体験工房」ではまが玉づくりや、図書を使った調べ学習などができる体験学習ができるスペースです。体験工房にあるこの戸棚は、ハンズオン(さわれる土器)コーナーとして、実際に土器を触って確かめることができます。また、土器のほか、石包丁や土偶など当時の生活用品を再現した模型も展示されています。このように土器のかけらに触れることができます。こちらは国宝展示室にあった復元した土器です。発掘された土器の破片を組み合わせて土器を復元するのですね。とても難しい立体ジクソーパズルみたいです。この地図は関東にある古墳の位置図でした。関東にも各地に古墳があることがわかりました。こちらの国宝展示室では、国宝「武蔵埼玉稲荷山古墳出土品」をはじめとする、埼玉古墳群の各古墳から出土した貴重な文化財を常時展示しているそうです。これは、埼玉古墳群で最も古く、最も北に位置する古墳の稲荷山古墳(→→→こちら)にあった礫槨(れきかく)埋葬想定図です。「礫槨」とは、古墳の木棺を埋める際に、棺の下方および側方に礫を詰め上方を被覆したものを言うそうです。そして、これはこの博物館の象徴である国宝・金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん)(→→→こちら)です。展示されているのは複製品ですが、金錯銘鉄剣は、5世紀末の古代史の手がかりとなる超一級資料。この剣は稲荷山古墳の礫槨から出土した鉄剣で、剣身に表面57文字、裏面58文字の計115文字の銘文が金象嵌で刻まれています。こちらが表面にあった銘文で、辛亥の年七月中、記す[2]。ヲワケの臣。上祖、名はオホヒコ。其の児、(名は)タカリのスクネ。其の児、名はテヨカリワケ。其の児、名はタカヒシ(タカハシ)ワケ。其の児、名はタサキワケ。其の児、名はハテヒ。というように書いてあるそうです。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その14) 埼玉県立さきたま史跡の博物館
Oct 17, 2025
コメント(20)
-

行田を歩く(その13) 埼玉県名発祥之碑
さまたま古墳公園内にある埼玉県立さきたま史跡の博物館へも訪れました。道沿いには「特別史跡埼玉古墳群」の幟が並んでいました。史跡と指定されたのは昭和13年(1938年)のことですが、国の特別史跡に昇格したのは、令和2年(2020年)のことで、幟も結構新しいものですねむ。この道の途中にあったのが、こちらの「埼玉県名発祥之碑」です。石碑の揮毫は、この碑が建立された昭和62年(1987年)当時の埼玉県知事、畑 和(はた やわら)氏。こういう石碑等をみると県知事とか市長といった職業の人には、大学の卒業証書なんかより、その卒業証書の文字に書けるような、書道の技能が必要なのかもしれませんね。この石碑の脇にあったのが、埼玉県名の由来を説明した銘板でした。簡単に言うと、明治4年(1871), 廃藩置県によって 埼玉県(県庁所在地:岩槻)と入間県(同:川越)ができた。そして、明治6年(1873) 入間県は群馬県と合併し 熊谷県と改められた。そして、熊谷県の群馬部分が群馬県となり、明治9年(1976), 埼玉県と熊谷県が合併し 現在の埼玉県になり,その時かなりの面積を占めていた埼玉県が県名となったとのことです。その埼玉県の埼玉の名前の始まりが、律令の頃に前玉と呼ばれていたこの地であったということのようです。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その13) 埼玉県名発祥之碑
Oct 16, 2025
コメント(24)
-

行田を歩く(その12) 将軍山古墳
埼玉古墳群の北東部に位置する将軍山古墳も行ってみました。案内板によれば、全長90mの前方後円墳です。明治27年(1894年)に横穴式石室が発掘され、多くの副葬品が出土しました。この石室には、千葉県富津市付近で産出すね「房州石」が用いられており、古墳時代の関東地方における地域交流を考える上で重要な古墳です。周囲には長方形の堀が中堤をはさんで二重に巡り、後円部と中堤には造出しと呼ばれる張り出しががあります。稲荷山古墳・二子山古墳と同じ形態です。古墳の造られた時期は、出土した遺物から6世紀後半と推定されています。平成21年(2009年)3月 埼玉県教育委員会との説明が書いてありました。この古墳の内部には、複製の石室や遺物の置かれた状態を見学できる施設、「将軍山古墳展示館」(→→→こちら)が整備されており、同じさきたま公園内にある埼玉県立さきたま史跡の博物館の入場券(200円)を持っていれば、無料で見学することができます。ちなみにMoMo太郎は先に博物館の方を訪れていたので、その入場券を見せて無料で入りました。こちらが、展示館の入口になります。墳丘の内部が展示室となっているいて、二階建てとなっています。中に入ると、墳丘崖面の土の層を剥ぎ取りしたパネルが展示してあり、昔の人たちの土工事の手法を知ることができます。将軍山古墳から出土した馬具の複製品を付けた馬を展示しています。この馬冑と呼ばれる馬の武装用の冑は、国内の出土が3例と少なく、大変珍しい遺物だそうです。2階には、実物大の横穴式石室の一部と埋葬時の様子を復原しています。古墳の中には、こんな感じで葬られていたんですね。大変貴重な展示を見ることができました。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その12) 将軍山古墳
Oct 15, 2025
コメント(27)
-

孤独のグルメ 帰ってきた東京チカラめし
行田を歩くの途中ですが、まだ、つぎの記事が書けていないので、最近食べたランチの話です。東京都千代田区にある九段第二合同庁舎の地下にある食堂に、この看板が、「東京チカラめし(→→→こちら)」。10年以上前は東京の街のあちらこちらにあった牛丼チェーンでしたが、いつのまにか見かけなくなっていました。しかし、税務署や国土地理院関東地方測量部などの国関係の出先事務所が入居する合同庁舎で営業していました。おそらく東京チカラめしの運営会社が官公庁などの食堂受託事業をしている関係で、この東京チカラめしを営業しているんでしょうね。ということで、普通の定食などのメニューもありましたが、ここはやはり焼き牛丼(大盛り850円税込み)を食べました。牛肉を「煮る」ではなく「焼く」という調理方法で提供するのが東京チカラめしのスタイルでした。もう久しぶりに食べたので、以前はどうだっか味の比較はできませんが、かってはワンコインで食べられたような記憶があって、それでこの値段なら、積極的には食べないかも。それでも、官公庁の食堂ですが一般の人も自由に入ることができますから、昔を懐かしみたいなら、九段の第二合同庁舎で食べてみるのも一興かもしれませんよ。人気ブログランキングへ孤独のグルメ 帰ってきた東京チカラめし
Oct 14, 2025
コメント(26)
-

行田を歩く(その11) さきたま古墳公園
丸墓山古墳を下りて、「さきたま古墳公園」(→→→こちら)の中を歩いて行きます。さきたま古墳公園は「特別史跡 埼玉古墳群」を含む公園です。昭和42年に文化庁の「風土記の丘設置構想」に基づいて史跡公園の整備に着手し、全国で2番目の風土記の丘「さきたま風土記の丘」として開園しました。そして、昭和51年以降は、史跡周辺を含めた都市公園「さきたま古墳公園」として整備が進められています。公園の施設ではありませんが、公園に隣接してこちらの海東山天祥寺(→→→こちら)がありました。このお寺、なかなか歴史のあるお寺で、お寺にあった天祥寺由来を見てみると、奥平松平下総守家の藩祖松平忠明公(天祥院殿)が開基となり、寛永年間大和郡山に創建されたそうです。その後、松平家の移封毎に播州姫路、奥州白河、羽州山形、備州福山、勢州桑名等へ寺も移転したそうです。奥平松平家は、9代目忠堯の代に、文政6年(1823)に桑名藩より忍藩(行田市)へ移封、天祥寺も当地へ移転してきたということです。天祥寺の横にあるこちらも古墳です。埼玉古墳群の前方後円墳で最小となる愛宕山古墳(→→→こちら)となるそうです。墳頂には、かつて愛宕神社が座していたことがあるので愛宕山古墳というそうです。前玉(さきたま)神社へ向かう古墳通り(埼玉県道77号行田蓮田線)を歩いて行く途中から見えた、二つの山があるように見えた大きな古墳は、埼玉県最大の前方後円墳の二子山古墳(→→→こちら)です。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その11) さきたま古墳公園
Oct 13, 2025
コメント(22)
-

行田を歩く(その10) 丸墓山古墳
まず最初に見たのは、こちらの古墳です。丸墓山古墳(→→→こちら)です。6世紀初めに築造された日本最大級の円墳です。大きさは直径105.0m、高さ17.2m。埼玉古墳群で最も高い標高をもっているそうです。古墳の頂上までは、この急な階段を登っていきます。この古墳は、忍城攻めの舞台としても歴史に登場しています。平成24年(2012年)に公開された映画「のぼうの城」(→→→こちら)をご覧になった人はわかると思いますが、天正18年(1590年)、小田原征伐に際して、忍城攻略の命を受けた石田三成が、この丸墓山古墳の頂上に陣を張ったと伝えられています。この案内板によれば、天正十八年(1590)、豊臣秀吉の命をうけた石田三成は、総延長28km(一説には14km)の石田堤を築き、忍城を水攻めしました。丸墓山古墳は高さが19mあり、周辺を一望できることから、三成の陣が張られたと言われています。北の利根川水系、南の荒川水系の水を流し込んでの城攻めは成功せず、豊臣秀吉が唯一落とせなかった城とも言われています。とありました。古墳の上からよく見ると向うの方に、忍城の姿が見えました。天正18年の頃にはこのあたり一帯、水が張られていたんですね。古墳の上から見下ろせば、砂利道が見えますが、この砂利道に沿って、桜の並木があり、この道が、石田三成が築いた堤防の「石田堤」の跡になるようですね。またこの道には、石柱が建てられていて、石柱には「埼玉村古墳群」と刻まれていました。ということは、このあたり昔は埼玉県北埼玉郡埼玉(さきたま)村(→→→こちら)だったという、埼玉の中の埼玉だったという場所だったんですね。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その10) 丸墓山古墳
Oct 12, 2025
コメント(20)
-

行田を歩く(その9) さきたま古墳公園へ
行田タワーを後にして、旧忍川(きゅうおしかわ)(→→→こちら)沿いのサイクリングロードを歩きます。平坦な水田地帯の道を歩きます。サイクリングロードだったけど自転車の人には出会わなかったです。水田の中に小高い丘がいくつか見えてきました。これは自然の地形というより、人工的にできた盛土。つまり、この形からわかるように古墳ですね。このあたり「さきたま古墳公園(→→→こちら)」と呼ばれるところです。さきたま古墳公園とは、「特別史跡 埼玉古墳群」を含む公園です。埼玉古墳群(さきたまこふんぐん)は、埼玉県行田市埼玉にある、9基の大型古墳からなる古墳群のことです。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その9) さきたま古墳公園へ
Oct 11, 2025
コメント(26)
-

行田を歩く(その8) 行田タワーと田んぼアート
古代蓮の里にある古代蓮会館に行ってみました。この高さ50 mの展望タワー、行田タワーが目印です。ちなみに入館料は大人400円となっています。古代蓮会館の一階は展示室となっています。展示室では、行田の自然や蓮の生育、蓮に関する文化など、模型やジオラマや映像によって説明されています。こちらは行田市の自然や、そこに暮らす生物の様子を紹介しています。こちらの展示は、古代蓮の生態にふれることができるコーナーです。行田タワーの展望室が二階となっています。ここからは360度の大パノラマが楽しめます。そして、9月頃には古代蓮の里の東側に隣接する水田(約2.8 ha)に稲を植え付けてできる田んぼアートが楽しめます。田んぼアートを見物するための展望室の窓には、このような円形の穴があいた円盤状の物が設置されていました。この円盤を使わずに眼下の田んぼアート(→→→こちら)を撮影すると、窓ガラスに写り込んでしまいますが、円盤の穴にカメラのレンズを差し込んで撮影すれば、このようにガラスへの映り込みを避けることができます。この田んぼアートは、平成20年(2008年)より始められ、平成27年(2015年)にはにギネス世界記録の認定を受けているそうです。壁面には歴代の田んぼアートの写真が展示されていました。平成25年の田んぼアートは、「古代蓮の精」ということで天女の姿が作られていました。令和4年の田んぼアートは、サッカー漫画の「アオアシ」(→→→こちら)だっんですね。こちらは、田んぼアートの田植えに参加されたボランティアの皆さんの写真です。随分大勢の人が参加されているんですね。展望室からの景観も撮影してみました。こちらは北東側の古代蓮の里です。こちらにも行田蓮の池があったんですね。北側を向かって撮影すると、古代蓮の里の全体がわかります。行田蓮の広い池と敷地の真ん中を流れる水路がありました。北西側に広がる埼玉県行田浄水場です。西側です。この方角で天気が良ければ、赤城山などの群馬県の山が見えるのでしょうね。南西方向の風景、こちらも天気が良ければ富士山が見えたかもしれませんね。最後に鬼滅の刃の田んぼアートをもう一度撮影しておきました。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その8) 行田タワーと田んぼアート
Oct 10, 2025
コメント(26)
-

行田を歩く(その7) 行田蓮
古代蓮池と名付けられた行田蓮の繁殖している池にやってきました。行田蓮(古代蓮)とは、原始的な形態を持つ1400年~3000年前の蓮であると言われて、行田市の「天然記念物」に指定されているそうです。昭和46年(1971年)に古代蓮の里にほど近い公共施設建設工事の際に、掘削によってできた場所に水がたまって池となり、地中深く眠っていた蓮の実が静かに目覚めたのです。昭和48年(1973年)には、池の水面に多くの丸い葉が浮いているのが発見され、その後専門家の調査により、おおむね1400年から3000年前のものと推定されているようです。しかし、地中深く眠っていた多くの蓮の実が出土し、自然発芽して一斉に開花した事は極めて珍しいことですね。7~8月の花期を過ぎた9月中旬ですが、ピンク色の花が咲いていました。「蓮は泥より出でて泥に染まらず」、泥水の中から生じ清浄な美しい花を咲かせる姿は穢れた人道から天道へと至る輪廻転生の仏の教えに通じるものを感じますね。古代蓮の池は東池と西池の二か所あり、こちらの東池の広さは3,200ヘクタールだそうです。この池で採れたレンコンって、お土産で売ってたりしないですかね。古代蓮レンコンとかなんか売れそうですけどね。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その7) 行田蓮
Oct 9, 2025
コメント(20)
-

行田を歩く(その6) 蓮の花を楽しむ
こちらが古代蓮の里の入り口です。行田市のコミュニティバスでも来れますが、多くのはマイカーで来られるのでしょうね。駐車場も広くとられていました。入り口にあった石碑です。埼玉県名発祥の地 行田市の観光案内図です。色々な名所があるようですね。こちらが古代蓮の里の案内図です。作詞・作曲 小林 亜星 歌唱 ダークダックスの「蓮の故郷」の歌碑です。このうた「蓮の故郷」はダークダックスの「ゲタさん」こと喜早 哲(きそうてつ)さんが平成12年7月に古代蓮を訪れた際に行田蓮の美しさに感動し、友人の作曲家小林亜星さんに作詞/作曲を依頼され造られたものです。世界の蓮園として世界各地の蓮が植えられているエリアがありました。こちらが世界の蓮園。蓮の品種名が記されたプレートがあり、蓮に対する知識が深められます。もう、蓮の花の盛りは過ぎていましたが、まだ花を咲かせている蓮もありました。水の中から咲く蓮の花、綺麗ですね。ハス(蓮)は原産地はインド亜大陸とその周辺で、日本では帰化植物として繁殖しているそうです。花は早朝に咲き昼には閉じるので、訪れた時間帯では、そろそろ花が閉じかけ始めていたんですね。(行田を歩いたコース)【つづく】人気ブログランキングへ行田を歩く(その6) 蓮の花を楽しむ
Oct 8, 2025
コメント(26)
全7419件 (7419件中 1-50件目)