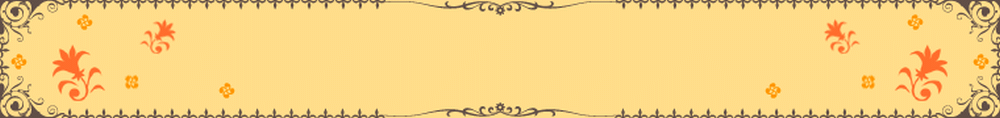-
1

透かしドルマンカーディガン
〜透かしドルマンカーディガン〜☆編み図 毛糸のピエロさんの無料編み図から☆使用糸 毛糸のピエロ シャンベル 色番01☆かぎ針3号この糸、だいぶん前に違うものを編もうと思って買いました。モチーフを編みつなげるサマーセーターだったのですが、モチーフが細かくてかぎ針3号で、私の目が辛くて結局やめてしまったのでした。で、この糸を使って何か編めそうなもの、できればモチーフじゃないもの、ということで、ドルマンカーディガンとなりました。さて、来年の春夏、どれくらい着用するでしょうか。この「編みたい」と「着たい」と「似合う」が違うのがなんともどうしようもないところなんですけどね。
2020.10.21
閲覧総数 1644
-
2

葛西臨海水族園へ
2024/11/05混雑予想カレンダーによると5日はゆっくり見られるよってことだったので、久しぶりに行ってきました、葛西臨海水族園!前回行ったのは去年の9月だった。遠足で来てる子どもたちがいたけれど、本当にゆっくり見れました。左上:オレンジシーペン。羽ペンっぽい?ってこと?右上:バローウィングアネモネ。なんかかっこいい名前。下:フジツボの仲間のピコロコ。蔓脚がピロピロしてて面白くて好き。見えているのに見つからない…左下:オニダルマオコゼ。正直、魚には見えない。でも、これがここにいる。右下:プレイス(カレイの仲間)目だけがかろうじて見えるwマグロ水槽。椅子に座ってゆっくり眺める。マグロ水槽動画 YouTube横の水槽をシノノメサカタザメがの〜んと横切る。迫るシノノメサカタザメ動画 YouTube北極・南極の海コーナーにいた、パルボルラシアコッルガトゥス、舌噛みそう。左下:シモフリシマハゼと目があった。右下:チゴガニがちまちまと餌を食べてる様子は見てて飽きない。で、ワレカラが見たかったんだけど、残念なことにワレカラの展示は終わってしまったようでいなかった…がっかり。悲しいので、去年のワレカラ動画を…泳ぐワレカラ動画 YouTube動くワレカラ動画 YouTubeさまざまな顔をもつ東京の海、こうやって見ると東京の海、広いなぁ。左下:ねじねじの不思議なものがいたのだけど、名前がまさにネジレカラマツ。中下・左下:どっちがどっちかちょっとわからないけどヒガサウミシダ、シモフリウミシダ。泳いでるところが見たかったけど、今日はじっとしてた。海鳥の生態、ウミガラスとエトピリカのところに「ここにいるよ」ってお知らせがあったので探してみたら、1匹発見。クロソイ。10匹いるらしいけど、他は見当たらず。ペンギンの展示場は現在補修工事中。他の水族館へ移動してるペンギンもいるそう。で、現在レストラン前の仮設展示場ではオウサマペンギンが見れる。ワレカラ見れなかったけど、オウサマペンギンの鳴き声聞けたから良しとしよう。オウサマペンギン鳴く動画 YouTube海中のゴミも一緒に展示してる水槽があって、環境のことも考えさせられる。そしてショップで、海洋ゴミから作ったキーホルダーを買った。種類がいろいろあって、それぞれにゴミの採取地が書いてある。私のは保戸島。虫探しついでにゴミ拾いしてるけど、もうちょっと虫探し回数を増やそうかな。
2024.11.11
閲覧総数 154
-
3

「丸木舟ラボ〜縄文の舟にまつわる4つのはてな」北区飛鳥山博物館
2025/05/18予告を見て楽しみにしてました。飛鳥山博物館は2度目。午後は遺跡学講座に参加です。縄文時代に使われていたのは1本の木をくり抜いて作る丸木舟。北区では4艘が見つかっていて、そのうちの1艘が展示されていました。いつもは常設展示室のケースに入っているのだけれど、今回はケースなしなので、かなり近くでじっくり見れました。中里遺跡出土、全長579m。丸太をくり抜いているので、先端部分を見ると年輪が見えます。舟には表面加工の焦げ跡が。この舟は乾燥劣化しないように、ポリエチレングリコールで処理してあるそう。そういえば前に水中考古学の展示で見た海から引き上げた木製のいかりはトレハロースで処理してたっけ。実際に当時の道具を使ってやってみる実験考古学。丸木舟を作る様子が動画で流れていました。木を切るための縦斧、木を加工するための横斧。使い分けてたのか。とはいえ縄文時代はまだ鉄はないので石斧。鉄製の斧で切るよりも木の繊維がもじゃもじゃしています。このもじゃもじゃを、焼くことで滑らかにしていたらしい。それが舟に残っている焦げ跡!なるほど〜。動画を見てから舟を見るとまた違った風に見えてきます。舟に使った木はムクノキ。硬くて粘りつよい木材なんだって。そして北区の縄文人はその舟で何をしたのか?漁をする、物を運ぶ、遠くのムラと交流をする。左は中里貝塚の貝層剥ぎ取り標本一部。マガキとハマグリが主体の貝層。縄文中期。幅100m、長さ500m〜1kmと広い範囲に及ぶ。高さは高いところでは4.5mにもなる。貝の量がかなり多いことから、ここは貝の加工場だったと考えられる。浜辺で貝を蒸すか茹でるなどして身を取り出し、干貝にして周辺のムラとの交易に使っていたらしい。そして!ここにも!貝輪が!もしかしたら干貝と交換で手に入れていたのかもしれない。千葉の貝輪製作所、余山貝塚で作られた貝輪を手に入れていたのかもしれない。古作貝塚の貝輪入り土器。しかもこれ、東京大学総合研究博物館所蔵のレプリカじゃないやつじゃん!展示スペースは小さいけれど、みっちり詰まった展示でした。図録と野帳のセットなんてのがあったので買いましたよ。企画展は無料で見れます。続いて常設展示室へ。こっちの貝層剥取り標本はでかい!左下に見える空の展示ケースが舟の入ってたケース。とにかくでかいw剥取り標本の前に立って見上げてみる。すごい。説明のところに貝層の下に立ってる人が写ってる写真があるんだけど、とにかくよくこれだけの貝を加工したなぁって思う。およそ200年分だそう。右上:土偶(北区指定有形文化財)縄文後期 東谷戸遺跡出土右下:筒形土偶 縄文後期 西ヶ原遺跡出土午後の遺跡学講座は座学の後、実際に遺跡のあったところを歩きました。これは丸木舟ラボに展示してあった縄文時代の飛鳥山博物館周辺模型。博物館のあるあたりはちょうど武蔵野台地のへり。崖の下が浜辺になっていて、中里貝塚はこの浜辺にあった。住居跡は見つかっていないのでおそらく近くの御殿前遺跡、七社神社裏貝塚、西ヶ原遺跡に住んでいた人たちがここへ来て加工していたのではないかと考えられる。1983〜1984年に東北新幹線延伸工事のための調査だったので、調査が済んだところから工事が進められるような状況だったそう。歩いた経路はこんな感じ。黄色で斜線を引いたところが中里遺跡。博物館をスタートして、七社神社裏貝塚(今は神社が建ってる)を通り、御殿前遺跡のあったところ(今は国立印刷局の東京工場、公園がある)を通ります。御殿前遺跡はこの辺りでは1番大きなムラだったそう。JRの線路沿い(武蔵野台地のへり)を歩く。この崖が縄文時代からあるんだと思うとまた違った味わいが。歩道橋を渡って中里貝塚へ。ちょうど空き地があって、そこを見ると貝殻が散らばっているのが見えます。この周辺一帯が貝塚である証拠。そして常設展示にあった写真の場所がここ!今は普通に公園になってます。ここを4.5mも掘り下げたのもすごいけど、この下に4.5mの貝層が埋まってるのかと思うとなんかすごいよね。ゴールは現在整備中の中里貝塚史跡広場。丸木舟を模したベンチがあります。今は芝生養生中。まだ整備半ばですが、貝塚のことがわかる案内表示だったり展示物だったりができるそう。楽しみです。帰りは上中里駅から電車に乗って帰りました。ホームから見る武蔵野台地の崖。地学も面白そうなんだよな。学生の頃に習ったことはもう本当にすっからかんに忘れてるんで、今からでも!断片的にでも!すぐ忘れちゃうかもしれないけど!勉強しよ。
2025.05.27
閲覧総数 186
-
4

オオスカシバ、サナギに
さて、室内飼育のオオスカシバ幼虫。20日の夜に茶色くなってきました。葉っぱも食べずじっとしているので、そろそろサナギになると思い、ケースに裂いたティッシュを入れてそちらに移してやりました。翌日見ると、マユを作っていました。そして、23日、サナギに変身。…で、このまま越冬するのか、それとも羽化するのか。ちょっと微妙な感じ?でも、以前もこれ位の時期で越冬だったからな。ようやく、春のお楽しみができました。
2017.09.24
閲覧総数 1650
-
5

セスジスズメ、羽化
サナギになんとなく翅の模様が透けてきたのが4月の終わりころ。それからぐっとサナギの色が濃くなってきて、黒っぽくなってきました。あるブログで、羽化が近くなると、それまでカチカチだったサナギが柔らかくなると書いてありました。試しにちょっと触ってみたら、柔らかい。これは羽化が近いに違いない。とは思ったものの、何時に羽化するかなんてわからないので、いつも通りに夜11時に就寝。今朝5時ころトイレに起きた時に見てみたら、羽化していました。設置した割り箸につかまっている感じがなんともかわいいです。スズメガ系の蛾は、前足2本でブラ下がるようにとまるようなんです。写真を撮っている間に、翅をブルブルと震わせ始めました。アゲハと違って、飛ぶ時の羽音がブブブブ、ブブブブと聞こえます。重量級の音です。窓を開けたら、ブブブブ〜っと飛んで行きました。カラーの葉っぱがたくさんあるから、いつでも卵を産みにいらっしゃい(いや、メスかどうかわからないけど)それから、昨日、クロアゲハサナギその2が羽化しました。エアコンの室外機の裏にコロンと落ちていたサナギですが、ちゃんと羽化しました。残るは、セスジスズメその2のみ。こちらも黒っぽくなってきているので、GW中に羽化するかな。
2017.05.04
閲覧総数 2940