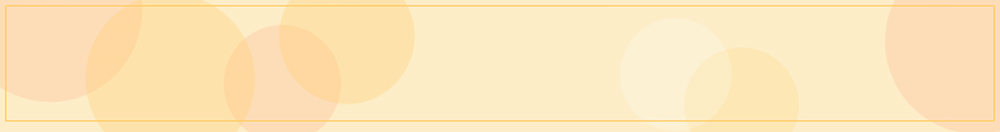PR
X
Calendar
Freepage List
Comments
カテゴリ: 小説
『何を言ったんだ?比翼。』
『俺だってたまには頭使うの。ま、今回は黙って見てろよ。』
煌びやかなシャンデリアがいくつもついた長い廊下を進むと金色のノブがついた白い扉に行きあたった。案内をしてくれた黒いスーツの護衛二人が両開きのドアのノブをそれぞれ引くと、乳白色に輝く大理石を敷き詰めた豪奢な部屋が眼前に現れた。ドアから部屋の中央にあるテーブルまでは濃緑色の絨毯が敷かれ、いまにも飛び立ちそうな姿勢をとった鷲の剥製が隅に据えられている。導かれるまま二人は繊細な刺繍が施された布張りのソファーに腰掛けた。
「なにこの椅子。かってぇな。」
「こういうのが貴族の中では流行りなんだろ。」
「流行りだかなんだかしらねぇけど、ったく肩のこる部屋だぜ。」
どうにもリラックス出来ない部屋で待つ事10分あまり、館の主人が現れた。裏町で流れ者の世話をしていたときは質素で機能的な衣服だったが、今日はところどころ銀糸の縁取りがついた真紅のシフォンのドレスを身にまとっていた。扇で口元を覆ってはいるが、その老いは隠せない。あの時見た彼女は30代半ばほどであったが、本来の年齢は70を優に越していると思われ、皺だらけの手と華美な衣装とのギャップがひどく不気味だった。
暑くもないのに扇を軽くそよがせながらソファーに腰を下ろすと、なんの挨拶もなく唐突に夫人はこう尋ねた。
「あなたたち?私の欲しいものをくれるというのは?」
『ちょっと比翼、何のはな・・・』
『いいから、お前は黙っとけ。』
小声で素早く連理を制すると、比翼は女に向き直った。
「それは後ほど。まずは我々の質問に答えていただいてからです。」
連理が驚いて比翼を見た。
へえ、こいつこんな口の利き方もできたんだな・・・。
「あら、エルフが一人前に人間と交渉ってわけ?」
「私が奥様の望むものを提供できるというのは一目見ればお分かりでしょう。取引に見合う価値のある情報をそちらがお持ちかどうか、それが分かって初めて商談に入れるというものです。」
「ずいぶんと強気なのねぇ。力ずくで奪うことだって出来るのよ?」
「それがいかに難しいかはよくご存知のはず。だから取引のため、この部屋に通したのでのでしょう。屋敷の護衛がエルフを生かしたまま捕らえることができるかどうか、お試しになられますか?」
比翼は端正な顔に悠然とした笑みを浮かべて、そう言い放った。不穏な発言とは裏腹に紅茶を啜り、足を組んでくつろいだ様子に戦闘の意思は微塵も感じられない。
くくっ。
ブルボン公爵夫人は扇で口元を隠してくぐもった笑い声を漏らした。
「面白い子ね。あなたの勝ちよ。なんでも聞いていいわ。」
話をするのを嫌ったわけではなく、単にからかおうとしただけらしい。不適な笑みは何を話そうと自分の立場がけして揺らぐ事はないという自信の表れだろう。
篤志家の仮面をつけて集めた流れ者をフィロウィに差し出していた女。自らの欲望のために何百人もの人間を犠牲にしてきた彼女の罪を問うことはもう誰にも出来ない。バリアートのメディチ家が火事になり、全ての証拠は灰燼に帰してしまったのだから。しかし今そんなことはどうでもいいことだった。
『これで俺の任務終了~。あとはお前、上手く聞けよな。』
『え?』
『・・・これ以上この喋り方やったら吐く!見ろよこの鳥肌!!』
『あは、分かったよ。よく頑張ったな、比翼。』
この後の質問は連理が担当することになった。
「セラチアのことはご存知ですね?」
「ええ、もちろんよ。とても仲良くしていたわ。古くからの友人よ。」
「いつからのお知り合いですか?」
「私たちが花のように美しかった頃から、よ。」
スミレの砂糖漬けをつまみながら夫人は謳う様に言った。はぐらかそうというのか、あるいはこちらがやきもきするのを楽しむつもりなのか・・・。この調子でぼんやりとした問答を繰り返している暇はない。そこで連理はカマをかけてみることにした。
「ビガプールの娼館でご一緒だったのではないですか?」
「あら、そんなことまで知っているの・・・?」
夫人は余裕に満ちた笑みにわずかに暗い影を滲ませた。セラチアと同様、そのときの事は記憶から抹消したいほどに嫌な思い出らしい。
「そう、私たちは同じ娼館で出会った。私が23歳、セラチアが16の時よ。」
思い出すように目を閉じ、夫人は言葉を紡ぎ始めた。
「私はいい働き口があると騙されて田舎から連れてこられたのだけれど、あの子は実の父親に売られて来たっていうじゃない。まだ幼さの残る彼女が不憫でね。お互い身の上話をしてよく二人で泣いたものよ。」
己が身を切り売りする毎日。地獄のようなその場所で、夫人とセラチアは傷ついた小鳥が身を寄せ合うようにして生きてきたのだろう。そんな二人に強い絆が生まれるのは全く不思議のないことだと思われた。
「フィロウィという男の事を知っていますね?」
「知ってるといえば知ってるけど、私は一度も会った事がないの。セラチアを通して話を聞いただけ。」
「いつどこで出会ったのか、ご存知ですか?」
「ビガプールには国王の誕生祭というものがあるの。広場には食べ物とワインがふんだんに用意され、町中の人が仮面を着けて踊る、とても賑やかなお祭りよ。その日ばかりは娼婦も貴族もなく、皆が音楽とお酒に酔いしれる。娼館の女たちは滅多に館からは出られないのだけど、年に一回、その日だけは外出が許されるの。祭りの間は門が閉められて街の外には逃げられないから。
娼館に来て何年か目の誕生祭の夜、セラチアが目を輝かせて戻ってきたのを覚えているわ。彼女は『私たちを助けてくれる魔法使いを見つけた』と言っていた。それがフィロウィよ。」
「助けてくれる魔法使い・・・ですか。」
「私もセラチアも美しかったから、娼館のなかでも特に高級とされているところにいたの。客はもっぱらお金持ちやお忍びの貴族。良いように聞こえるかもしれないけど、とんでもない変態も多くてね・・・つらかったわ・・・。年をとって容色が衰えれば安い娼館へ下げ渡されるだけ、少しでもお金になるうちは決して解放される事はない。私たちは終身刑を宣告された囚人だった。老婆になる前にそこを抜け出すには死ぬか、客に身請けしてもらうかしかない。けれど一度は身請けしてもらっても、金持ちは気まぐれだから飽きればまた売られるなんてこともある。
けれど魔法使いはこう教えてくれたそうよ。
『もし心底惚れさせることができたら・・・?』と。
彼にもらった惚れ薬を馴染みの客に飲ませたの。私はブルボン公爵に、セラチアはメディチ家の当主に。」
娼館で働いていたはずのセラチアが何故メディチ家当主の妻の座につくことが出来たのか、これで納得がいった。
フィロウィは火傷の痛みに悩まされず、再び日の当たる場所で活動できる美しい体を手に入れるため、ホムンクルスの研究を進めたかった。実験に必要な人間や動物、広い施設や物品を得るには強力なパトロンが必要だ。セラチアの心の闇を嗅ぎつけたフィロウィは惚れ薬を調合して渡し、金持ちの男に飲ませて身請けしてもらうよう唆したのだ。彼女をパトロンにするために。
「その後セラチアは夫と共に故郷のバリアートに戻ったけれど、親交はずっと続いていた。彼女と私は血の上では他人だったけれど、辛いときも悲しいときも共に過ごしたんだもの、並みの姉妹よりも心の結びつきは深くて魂は双生児のように似ていたわ。
幸福だった数年が過ぎると、私たちはたびたび同じ不安に襲われるようになった。
『惚れ薬の効力はどのくらいもつものなの?』
『年を取って美しくなくなったら夫の気持ちが離れてしまうのでは?』
彼女は再び救いを求めに魔法使いの元を訪れた。するとその魔法使い、今度は交換条件を出してきたというの。これからずっと私たちの力になってくれる代わりにセラチアには実験施設を、私には生贄となる動物と人間を・・・。」
最初にとろける甘い菓子を与え、その味を忘れられなくさせてから自分の本性を見せる。フィロウィらしい汚いやり方だと連理は思った。
「そして惚れ薬や若さを保つ薬、土地を肥やす薬を手に入れていた、というわけですね。」
「そうよ。一度手にした幸せを手放すことなんて出来なかった。もう一度あの地獄へ戻るくらいなら死んだほうがまし!セラチアも私も、良心などかなぐり捨てて生きてきたの。そりゃ最初は胸が痛んだけれど、過去を取り戻すように美しい衣服や宝石でその身を飾り立てているうちに何も感じなくなっていったわ。何百という人間を殺す片棒を担いできたというのに私、申し訳ないとかそういうこと、全然思わないのよ?心を守るために欺瞞と虚栄を盾にしているうち、いつしかその全てが自分に同化していったんだわ。」
泣いているような、笑っているような、不可思議に歪んだ顔で夫人はこちらに視線を向けた。黄ばんだ白目の真ん中に浮かんだ瞳はどんよりと濁り、その奥を覗くと深い闇に引きずり込まれそうな気がした。
「流れ者たちをどうやってバリアートまで運んだのですか?」
「裏町の南東のはずれに一軒、誰も住んでいない古い家があるの。その家の地下に移動装置があるから、そこに集めて連れて行ったわ。『もっといい働き口があるから』と言うと彼らは一も二もなく飛びついてくるから人を集めるのに苦労はしなかった。あら・・・私、自分がされたのと同じ騙し方をしていたのね。うふふ、気が付かなかったわ。」
「その家に案内していただけますか?」
「案内などしなくてもすぐに分かるわ。もう使う事はないと思って戸口に木の板を打ち付けて塞いであるから。竈の灰の下に地下室の入り口があるの、探して御覧なさい。」
夫人は優雅な身のこなしで部屋の端にあるチェストまで歩いていき、取り出した錆びた銅の鍵をテーブルに載せた。どうやらその空き家の鍵らしい。連理はそれをズボンのポケットに滑り込ませた。
「私の知っていることはこのくらいよ。ご質問は以上かしら?」
「はい、ご協力ありがとうございました。」
連理が席を立とうとすると、夫人は扇を閉じて連理の額のすぐ前へすっと差し出した。
「待って。こちらはちゃんと答えたのだから、お約束のものをいただきたいわ。」
すると比翼がすくっと立ち上がり、床が絨毯に覆われていない場所まで出るとこう言った。
「何か容器を持ってきてください。」
ブルボン公爵がテーブルの上の呼び鈴を鳴らすと、黒いスーツの男が美しいクリスタルの瓶を捧げ持って入ってきた。
「ではここで、失礼します。」
比翼は腰から細身の剣をすらりと抜き、おもむろに両手で構えると一気に左の胸を貫いた。
「な・・・比翼っ!!!」
慌てて駆け寄ろうとした連理を目で制止し、ゆっくりと剣を引き抜くと血が噴水のように飛び散り白い床を濡らした。比翼は呻き声一つ立てず、胸から断続的に吹き出る血をクリスタルの瓶の細い口に伝わせて中に注いでいった。
心臓から噴き出る鮮血でいっぱいになった瓶に蓋をして床に置くと、夫人は奪い取るように飛びついた。夫人は部屋の外に出る二人に目を向けることもなく、うっとりした目で丹念に舌を瓶に這わせ、瓶の外側に付着した血を全て舐め取った後は床に零れた血に手を浸し、皺だらけの顔や手に丹念に塗り込め始めた。
全身を血で真っ赤に染めたブルボン公爵夫人は我知らず涙を流し、こう呟いた。
「セラチア・・・私たち、なんて遠くまで来てしまったのでしょうね・・・?」
⇒ つづき
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[小説] カテゴリの最新記事
-
ネタがないから小説第七弾~翼の行方編そ… August 21, 2009
-
ネタがないから小説第七弾~翼の行方編そ… August 21, 2009
-
ネタがないから小説第七弾~翼の行方編そ… August 21, 2009
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.