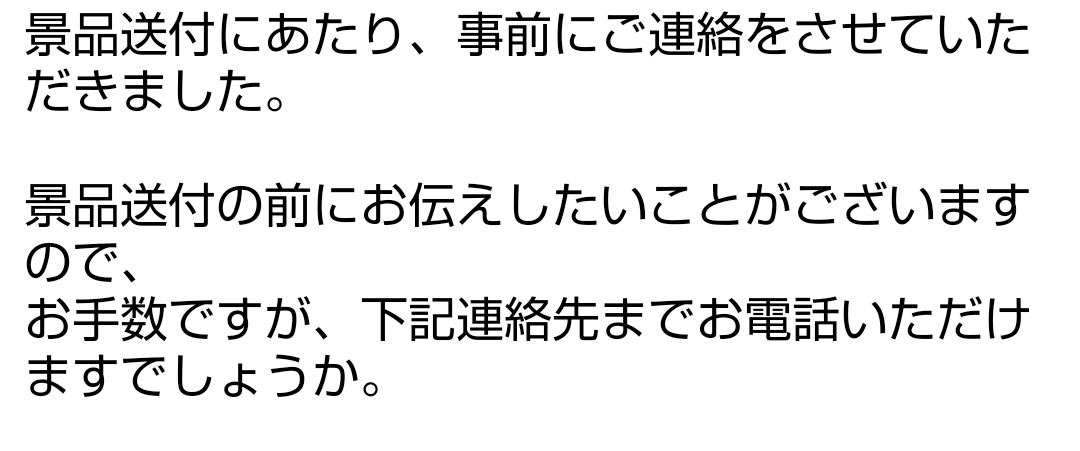-
1

大江健三郎v.s.伊集院光1
日曜の午後、マンションの排水管の点検のため、自宅で過ごす。この時間帯には外に出ていることが多いので、手持ちぶたさんとどうつきあったらいいか、よくわからない。しかたなくラジオのスイッチをひねる。TBSラジオの伊集院光の番組が流れている。ゲストを迎えてのクイズ・コーナーだ。ゲストが何十年も前に受けた雑誌や新聞のインタビュー記事をもとに、その時の答を覚えているかどうかを試すという、まあ、たわいのないおちゃらけコーナーである。私はベランダの「ひめうつぎ」や「るりまつり」の枯れ枝をはさみでぱちんぱちんと切りながら、それを聞くともなく聞いている。コーナーが始まる。女性アナウンサーがゲストを紹介する。「本日のゲストは大江健三郎さんです」。うん?大江健三郎?「伊集院光の日曜日の秘密基地」のゲストが大江健三郎?はて、面妖な。思わずはさみを置いて、リビングに戻り、ラジオのボリュームを上げる。大江の声が聞こえてくる。こういう場合、司会者が恐縮、恐懼して、ひたすら礼賛のことばを発するというケースが多い。なにしろ相手はノーベル文学賞受賞者である。そうなったら切っちゃおう。なんだかいたたまれないしな。私は伊集院光の話をラジオで聞くのは嫌いではない。この人はたしかにおちゃらけタレントだが、そのおちゃらけを真剣にやっている気配がある。そこにいくばくかの好感をもつ。おちゃらけをおちゃらけでやられてはかなわない。もしもバスター・キートンがニコニコ顔だったら、ずいぶんと面白さが減じるだろう。そういうことである。しかし、予想はいい意味で裏切られる。テーマはいきなり「文体」だ。「ぼくは、とにかく書き直しをよくします。何度も何度も繰り返し、繰り返し書き直します。私の妻は私の仕事にはおおむね好意的で、批評めいたことはまず口にしないのですが、以前、こういったことがあります。『もしもあなたが最初に書いた、そのまんまの形で世間に発表する機会が一度でもあったらどんなにいいでしょうね』と。」伊集院は質問する。「先生のおっしゃる文体は、こういう文体というものがまずあって、それに近づけて書き直しをされるわけですか、それともそういうものはなくて、まず書いてそれを修正する中で結果的に文体ができあがっていくんですか」この質問を聞いただけで彼がどういう姿勢でこの話に臨んでいるかがわかる。彼はひるんでいない。本気である。おべんちゃらや追従を捨てて、正面から大作家に向き合おうとしている。まことによい度胸である。私は倚子に腰を下ろす。「それは後の方ですね。最初から文体というものはないんです。僕の知っている作家に三島由紀夫という人がいて、彼は最初から何を書くかがほとんど決まってたんですね。実際に書く時に、彼はそのイメージに装飾をほどこすようにして作品を完成させていった。でもぼくはとにかく最初はこういうものを表現したいという漠然としたイメージのようなものはあるんだけれども、それが何なのかはよくわからない。だからとりあえず書いてみる。でも読み直すとぜんぜん書けてないし、だいいち、読者はなにが書いてあるかわからないだろう。だから、ああでもないこうでもないと表現を変え、視点を変えて、延々と書き直すことになるわけです。その作業を繰り返して、最終的にやっとなんとか読めるものになり、その過程で自分なりの文体というものができあがっていくんです。」「最終的に読者に伝わる文体ができると」「でも実は、私の文章は読み手にあんまりよく伝わらないみたいで、難解とか、むずかしいとか、よくいわれるし、本としてもあまり売れないんですよ」(笑)まことにいい雰囲気で話が続いていく。しかし、大江氏、いかんせんラジオには慣れていない。CMやコーナーお決まりのクイズをすべて無視して、延々としゃべる。司会者はとうぜんそれがわかっているのだが、大江氏の話を途中で遮らない。30分近く、そのままノンストップのNHK第一放送状態で話が進んでいく。まことにみごとな司会者ぶりといわねばならない。そして、その後、大江氏はなんと伊集院光について、語り始める。「私はあなたは少年のころの思い出を、単なる記憶としてではなく、あるひとつの広がりをもった出来事として大事にする人であるように思います。その記憶をいろんな角度から立体的に語ることのできる人であるように思うんです。人間にはふたつのタイプがあって、一つは自分の個人的な思い出をただそれだけのものとして平板に語る人、もう一つはあなたのように様々な角度から立体的な出来事として語ることのできる人」このことばを聞いた伊集院氏の心境はいかばかりのものだったろうか。大江氏の話はさらに続く。「ぼくはね、昔の出来事を物語る時、たとえば、その時、私は左を見た、と書く時、はたしてその時、右手には何があったんだろう。自分の見ていなかったところに何があったんだろう。あるいは、その私を後ろから誰かが見ていただろうか。そういうふうに考えるんです。そして、それを書こうとする人間なんです」伊集院氏。「先生、僕は基本的にラジオは生しか出ないんです。録音だと取り直しができます。そうやって何度も何度もある話を取り直していると、ある時、ディレクターから『伊集院君、君の話、最初は面白いと思ったんだけど、なんか何度も話しているうちに、怖い話になってきてるよ』といわれたんです。気がつくと、もう別の話になってるんですよね。それも怖い話に。先生はそんなことはないですか」「それでぼくの小説はいつも『怖い、怖い』っていわれるのかなあ」(笑)伊集院氏。「ぼくは先生の「自分の木の下で」を読んで、読み終わってから、何度もおんなじ話をするじじいがいるじゃないですか、そういうじじいが大好きになりました」「ほう」「そういうじいさんって、同じ話をしながら、微妙に今日はここをカットしようとか、ここをふくらまそうとかしてるんですよね。それを何度も何度も聞いているうちに、その話があっちこっちにふくらみだして、それが単なる話じゃなくて、なんだか実際にそれを経験したような気になるんです。つまりじいさんの経験を自分も同じように経験している気持ちになる。それで『このじいさんの話って、結局、タイムマシーンなんじゃないか。タイムマシーンって実は発明されてたんじゃねーか』って思うんです」「うん、うん」この調子で話が展開する。やがて、話は大江の友人、伊丹十三の話になる。この話は延々と続く。10分以上、彼は訥々と語り始める。「伊丹は私の古い友人で、彼の妹は今の私の妻です。伊丹はある頃から映画を作り始めます。でもぼくはめったにその感想を述べたりはしません。妹には試写会の招待状がくるけど、ぼくには来ない(笑)。ぼくもあまり積極的に感想を言おうとは思わなかった。 でも、彼がテロリズムに関する映画を撮っているという話を聞いた。私は彼のテロリズムに対する姿勢に敬服していたので、これは見なければならない。そう思って、封切りの映画館へお金を払って見に行って、その夜、彼の事務所に電話をかけました。すると伊丹が自分で出たんです」「そうですか」「彼はどうだった、あの映画のどこが面白かったかと聞く。私は知っているのですが、彼は漠然とした抽象的な感想を許さないところがある。『あの映画はポストモダン的でよかった』なんて、そういう言い方は絶対に許しません。ぼくはそれをよく知っている。とにかくあの場面がこういうふうに面白かった。そう具体的に述べないと納得しない。私は心を決めて、あるシーンについて語り始めたのです」「はあ」「それは一人の小太りの警官が登場するシーンです。その彼のところに出前持ちが昼飯の注文を取りにくる。彼はなかなかペーソスに富むというか、ふてぶてしいような、とぼけたような、意地悪なような、人がいいような、そういう感じでその出前持ちをからかう。そこがとても面白いと思った。 その小太りの警官はどうもあまり仕事ができるというタイプではないようで、昼休みに本を読んでいたりする。上司が何を読んでいるんだと聞くと、サリンジャーだったりする。そして上司から警官というのはもっと現実に向き合うべきものだと説教をされる。 そんなある日、その小太りの警官は田んぼの真ん中にあるカラオケ・ルームに歌を唄いにいく。女の店員が「お客さん、仕事はなに」と聞く。すると、彼はふてぶてしいというか、なんというか、「学生」と答えたりするんです。 そして、偶然、隣の部屋にいる客が、自分が追っているテロの犯人であることがわかる。彼はいったんトイレにいって、落ち着け、落ち着け、と自分に言い聞かす。 そして、犯人の部屋に入って、口にカラオケのマイクを突っ込んで逮捕しようとする。犯人はドアから逃げる。彼は追う。店の通路の突き当たりに「通用口」という表示があって、二人ともそこに体当たりをする。ドアがこわれる。その向こうは田んぼだ。二人は田んぼに落ちて、格闘になる。 その小太りの警官は、日頃の言動には似合わず、なかなかよく闘うんです。そして最終的には見事に犯人を逮捕する。 まあ、ここまでは普通の監督さんでもそれなりに撮るのではないかと思うんです。私が印象に残ったのはその後のシーンです。 泥だらけになった犯人の背中を小太りの警官がホースで洗ってやる。これもまあわかるんです。でもしばらくすると、カメラが引いて、その警官の背中を店の女の子がホースで洗っているシーンが映し出される。 ぼくはこのシーンがすばらしい、いかにも伊丹らしくて面白かった。そう言いました。」「……」「すると、伊丹が妙なことを言うんです。そうか、それでね、健ちゃん、あの女の子の役名なんだけど、「みどり」ちゃんっていうんだよ。で、役者さんの名前は早乙女○○さんっていうんだ。健ちゃん、覚えた?」「私はこう言いました。あのさ、岳(たけ)ちゃん(伊丹の本名)、ぼくは小説家だよ。その小説家のぼくが、なんで「みどり」ちゃんとか、早乙女なんとかいう人の名前を覚えなければならないんだろうか」「彼はこう言いました。「それもそうだね、でもついでにいっておくね、あの小太りの警官役の人の名前なんだけど」「……」「伊集院光っていうんだよ、と」話はここで終わる。スタジオが一瞬沈黙に包まれる。伊集院はぐっと胸にこみあげるものがあって、うまくしゃべれない。そのことが、その沈黙から伝わってくる。
2008.03.03
閲覧総数 66698
-
2

大江健三郎v.s.伊集院光2
泥棒の背中を洗う警官、その警官の背中を洗う女店員。ここには物語を、文体を立体的にする複数の視点が存在している。その伊丹の視点に大江は共感する。そのことばは伊丹を深く励ましたであろうと思う。伊集院が静かに語りはじめる。「伊丹さんにはよく意味のわからないNGと、よく意味のわからないおっけーがあったんです。なぜ今のがだめなのか、なぜ今のがいいのか、やってるこっちにはよくわからない。でも役者はとにかく淡々と何度でも繰り返し演じるしかない。でも、あのシーンでは最初の出前持ちをからかうシーン、最後の背中を洗うシーン、あれはとにかく延々と繰り返し演技させられたのを覚えています。伊丹さんはその大江さんのことばを聞いて、きっと「報われた」と思ったと思いますよ」ひとつの物語を複数個の視点から立体的に浮かび上がらせる。大江はこの話を周到に準備してきたのである。けっして語りがうまいとはいえない彼の話は、伏線から、最後の一語まで、実にみごとだった。そして私は思う。この話にはもうひとつのしかけがある、と。この同じ話が、一般のリスナーと目の前の伊集院ではまったく異なる受けとられ方をしている。リスナーは最後の一言で警官が伊集院であったことを知り、伊集院は最初の一言でそのことを知る。同じ話がまったく違う受けとられ方をしているのである。複数個の視点の重要性を物語るエピソードを、複数個の受けとられ方をするように物語る。この話は入れ子構造になっているのである。マトリョーシカ人形になっている。そして、それこそが物語の本質なのである。大江にこれだけの話をさせる伊集院光という人はかなりの人物であるということになるのではないだろうか。そして、私はふと気づく。彼がその話の中で「小太り」「小太り」という言葉をさかんに連発していたことを。「小太り」の「光」。それはまた大江の息子に連なるのではないか、と。この話はいったいどこまで入れ子構造になっているのだろう。物語の要諦、それは自分の後頭部を想像の目で見ることだ。そんなことを思いながら、私は日曜の午後、日の当たるリビングでひとり静かに配水管のチェックを待つのであった。
2008.03.03
閲覧総数 24267
-
3

ファンになれる人、なれない人
仕事始め。鼻づまりで夜中に何度も目が覚め、ようやく寝入ったかと思うと、遠い意識の向こうから目覚ましがけたたましくなりひびく。やれやれ。切れ切れの眠りは次々に異なる夢を見せてくれるのだけど、分析する気持ちの失せるような内容なのはなぜだろう。だって、アパートの一室で謎の諜報活動をしている、なぜか秋吉久美子がサンダル履きで実家の庭先にやってきて、電話回線を4つも引いたんだけど、どれがどれだかわかんなくて弱ったというぐちを私の父親に延々と話し、その姿を私が二階の屋根越しにじっと見下ろしている、なんて夢をあなたは分析する気になれますか。だいたいなぜ秋吉久美子なんだろう。さっぱりわけがわからない。 さて、そんなことを言っていても仕方ない。鼻のせいでアタマがどんよりと曇っているので、ろくなことは書けそうにないが、「ファンになれる人、なれない人」というお題はどうだろうか。 世の中にはたくさんのファンがいる。「いつもみてまーす」「だいすきでーす」「そんけーしてまーす」という、例のあれですね。 でも私は誰のファンなんだろうと思うと、どうも誰のファンでもないような気がする。ブログのコメント欄やトラックバックにもたくさんのファン気質というか、ファンことばが氾濫している。でもどうもああいうワーディングになじめないんですよね。いってることわかってもらえますかね。 もちろん好きな作家や文筆家はいる、よく聞くミュージシャンも好きな脚本家も映画監督も役者もいる。でも誰のファンともいいきれない。「冷めてるんじゃない」といわれるかもしれない。でも、どうも逆のような気がしてならないのだ。 高校生の頃だったろうか、3歳違いの兄と映画の脚本か何かについて話したことがある。その当時、私は映画のシナリオに興味を持っていて、新藤兼人のシナリオ修行の本を読んでいた。その中に、あるシナリオを読んで、頭の中心部がかぁっと熱くなって、いてもたってもいられなくなる、そういう瞬間のことが描かれていた。ひょっとすると、それはシナリオではなくて、映画だったかもしれない。あまりにも感動的な作品に出会って、「わあー、すばらしい」「なんていい映画なんだろう」と思った後に、頭の中心部がかぁーと熱くなって、いてもたってもいられなくなる。やみくもに自分でも「なにかしなくちゃいけない」という気持ちにとらえられ、とりあえずそこらへんにあるノートにへんてこなシナリオだかコンテだかわからないものを書いてはみるのだが、書き終わってしばらくして、それを見ると、あまりのひどさにがっかりする。そういう経験を何度もしたように思う。 新藤兼人の本にもそのような瞬間が活写されていたので、「ほんと、こういうことってあるよね」と兄に話したら、「そんなもんないよ」と即座に否定されてしまった。すごい作品に出会った時に感動したり、呆然としたりすることはある。でも、「自分で何かしなくちゃ」という気持ちにとらえられて頭がかぁーとなることなんて俺にはないよ、と。 たしかに言われてみれば、そちらのほうがずっと正常な反応であるように思える。凄い作品に出会ったら、その作品の凄さに圧倒されていればいいのである。そんなときに自分で何か作ろうとしたって、その作品との落差が際立って、自分に絶望するに決まっている。その通りである。 でもこの感覚は理屈ではないのだ。とにかく理屈抜きに頭が「かぁー」として、「なにかしなくちゃ」と思うのだから。 ひょっとすると、この時の頭の中の温度が一定値を越えてしまう人は誰かのファンにはなれないのではないだろうか。常識的には逆のようにも思えるが、ファンというのはその熱狂がある一定の枠内に収まる人のことをいうのではないか。そして、両者の違いは、他者の作品のもたらす感動が、そのまま他者に向けられるのか、それともくるっと一回りして自分に向かってくるかの違いであるようにも思える。 どうも人間は、他者の作ったものから得た感動を他者に向けたままで満足できる人間と、その感動をまるでブーメランのように自分の方へ旋回させて、自分を駆り立てる刺激ととらえてしまう人間のふたつに分かれるのではないだろうか。 すぐれた文章にもふたつあるように思う。ひとつはその文章のすごさに圧倒されてしまうだけの文章。もうひとつは、すごさに圧倒された後に、自分でも何かを書きたくなるような文章である。 両者はどちらが上とかレベルが高いとかいうのではない。とにかくある種の文章は「すごい、でも自分では書かない」という反応を引き起こし、ある文章は「すごい、自分でも何か書いてみよう」と思わせるのである。たとえば、私の場合、村上春樹、内田樹という人たちのつぼにはまった文章(愛読者の方はわかりますよね)を読むと、何かを書かずにはいられない気持ちにおそわれることがしばしばである。 でもおそらくそういっても「え、なんで、それってどういうこと」という顔をしてぽかんとする人がいるだろう。その人の文章がすごくいいと思うなら、いいじゃない、その人のファンになってれば、といって。 たしかにそうだ。それで満足できれば十分だと私も思う。でも、それができない。ある種のすごい文章を読むと、自分でも何かを書かざるをえない気持ちにおそわれる。そして実際に自分で書いてみて、彼我の違いにぼうぜんとし、深く失望する。 こういう人間はファンにはなれないのだ。不幸なのか幸福なのかはわからない(あんまり幸福そうには思えませんけどね)。それで懲りずにまたこんな文章書いては、がっくりと落ち込むのである。 やっぱ、ファンになれないって不幸なことなのかなあ。
2006.01.05
閲覧総数 1793
-
4

人はなぜ振り込め詐欺にだまされるのか
昨日、NHKの「クローズアップ現代」で、振り込め詐欺特集をやっていた。いくつかの事例がとりあげられていたが、たとえばこういう新手のやり方があるそうである。「もしもし」「ああ、あのー、オレ、オレやけど、今度携帯の番号変わったから、ちょっとメモしといてんか」そういわれて、電話に出た高齢の男性は、このくらいの年齢で自分が知っているのはと考える。ああ、そうか、おいの○○か。「ああ、わかった。ちょっと待ってな。いま、ペン持ってくるから。ああ、うん、○○○の○○○○やな。よし、わかった。」「そう、じゃあ、またな」がちゃんと電話が切れる。もちろん男性は何も疑わない。変更した電話番号を告げるだけの電話に不信感をもつ人間はいないだろう。まさかこれが振り込め詐欺の序章だとは夢にも思わないはずである。翌日の夕方、同じ声で電話がかかってくる。「あのなあ、オレ友だちと最近株をはじめたんやけど、ほら、こないだ株の暴落騒ぎがあったやろ。あれで俺の買うた株がえろう下がってしもうてな。今日中に75万円振り込まんとたいへんなことになるんや。頼むから振り込んで、頼むわ」その電話の発信番号は昨日告げられた番号である。男性はあわててATMに駆けつけ、指示通りの金額を振り込んでしまう。世の中には悪知恵にたけた人間がいるものである。営業にはアプローチ、商品説明、クロージングという三つの段階がある。「こんにちは、○○さーん」から始まって、玄関先に客と一緒に腰を下ろすまでがアプローチ、そこから商品説明が始まり、それが一通り終わって、契約書が取り出されるところから大詰めのクロージングというわけである。トップセールスはアプローチを重視する。もちろん技術的な面で、簡単にアプローチアウトをくらわないように、ありとあらゆるテクニックが駆使されるのはもちろんだが、下手にアプローチがうますぎると、最初からぜんぜん買う気のない客に延々と商品説明をして、契約書を取り出したとたんに「わたし、いらないわ」の一言で徒労に終わることになってしまう。これでは商売にならないので、トップセールスはアプローチ段階で相手の心理を鋭く見抜く洞察力に例外なく秀でているものなのである。先の振り込め詐欺の事例で私が感心したのは、犯人が巧妙なアプローチを考案していたからである。最初に「電話番号が変わったからメモしといて」といって、「あんた、いったい誰や」といわれたら、これはだまし通すのがむずかしいという判断がつくだろう。そこで切ってしまえば、詐欺どころか、単なる間違い電話で済む。「ああ、これは失礼しました。まちがえました」で終わりである。この作業を繰り返して、こちらが名乗るまでもなく、向こうのほうで勝手に自分の知り合いと思いこむ人間に出会うのを待つ。そういう人間に出会ったら、あえてそれ以上話し続けることなく、いったんは電話を切る。そして、翌日かけ直す。ここまでの下準備をした後で、やおら「実は」といって銀行振り込みをもちかけるというわけである。営業の勝負所は「相手を座らせる」ところにある。この電話の場合、もう相手はべったりと犯人の隣に座ってしまっている。座っているどころか、ほとんど「落ちて」しまっているといってもいい。その後の振り込みの操作とか、振り込むための理由は、実はたいした問題ではない。振り込め詐欺の手口もずいぶんと洗練されてきたものである。しかし、それにしてもこれだけ連日、警察やマスコミが振り込め詐欺撲滅キャンペーンを繰り広げているのに、なぜ依然としてだまされつづける人がいるのだろう。そうお思いの方も多いのではなかろうか。私はこのキャンペーンが、実は振り込め詐欺の隆盛に一役買っているのではないかとにらんでいる。「私はこんな詐欺にはぜったいに引っかからない」という意識が世の中の人々に浸透すればするほど、実は自分の置かれた状況を「これは詐欺ではない」と信じる力が強まるということがある。現に詐欺にだまされつつある状況下で「自分はだまされない人間である」と堅く信じる人間は、その前提から「今、自分が直面している事態は詐欺ではない」という確信に導かれやすい。「私はだまされない」⇒「今も私はだまされていない」⇒「だから、これはけっして詐欺ではない」というループの中にすっぽりと入ってしまい、結果的にまんまとだまされてしまうのである。だから、マスコミは「これだけ教えてやってるのに、まだだまされるアホがいる」というトーンで番組を作るのではなく、そう思っている人間に限って、それを逆手にとられてこんなふうにだまされるという角度から番組を作るべきなのである。「なんで、この人たち、だまされるんやろ、アホやなあ」という感想を視聴者に与えるのではなく、「あら、これやったら、私かてひょっとしたらだまされとるわ」と感じさせる番組を作らないと、犯罪防止には役立たないのである。もうひとつ。振り込め詐欺に引っかかる人間が後を絶たない理由は、だまされる側の「私は人を助けている」という意識にあるように思う。現代に生きる高齢者に「人に頼りにされる」機会がどれほどあるだろう。都会の老人などはとくにそういう機会が少ないと思われる。誰にも頼りにされず、一人きりで寂しい日々を送っている高齢者は「はたして自分が生きることにどんな価値があるのか」、「私ははたして人様のお役に立っているのだろうか」、そういう思いを抱きつつ生きているのではないか。地域の共同体から切れ、親族と疎遠になり、孤独な日々を送る高齢者にとって、自分を正当に価値づけるための唯一の手がかりは、ひょっとすると自分の預金通帳の残高なのかもしれない。そういう人のもとに、ある日「助けてくれ」というSOSの電話が入る。「あなたが頼りなんだ。いますぐにお金を振り込まないとたいへんなことになる。頼むから助けてください」そういう電話を受けて、彼らはどう思うだろう。実にひさびさに自分が頼りにされている。私を救えるのはあなただけだとこの人は言っている。しかも、助ける手段は自分を正当に価値づけているところの銀行預金だ。今となってはこれだけが自分をアイデンティファイしてくれる貴重な「財産」だ。それを必要とする人に送金手続きをすることによって、もう誰にも頼りにされなくなったこの自分にも再び復権のチャンスがめぐってくる。自分を頼りにし、救いを求める人々を助けることによって、自分が正当に評価される時がやってきたのだ。彼らがそう思ったとしても不思議ではない。そう信じ込んだ老人にとって(別にこれは老人に限ったことではないが)、「ちょっと待ってください。それはひょっとすると振り込め詐欺ではないですか」と言って振り込みを制止しようとする偉そうな銀行員や警察官はどう見えるだろう。おそらくは彼らの正当な自尊心の発現を邪魔する「敵」に見えるのではないだろうか。だって、彼らは自分に向かって「おまえはマスコミでこれだけ騒がれている振り込め詐欺に、まんまとだまされつつあるおろかで無価値な老人なんだぞ」と面と向かって言われていることになるわけだから。彼らが「だいじょうぶです。ほっておいてください。これは詐欺なんかじゃありません」といって、銀行員や警察官の手を振り払おうとする気持ちが私にはわかるような気がする。自分の価値を認め、助けを求める人間のために働こうとする自分の行動を邪魔し、自分を愚か者として否定する背広や制服に身を固めた人間に、誰が唯々諾々と従うだろうか。こう考えると、振り込め詐欺の根は意外に深いところにあることがわかる。被害者はただ単に巧言にひっかかった受身の存在というよりも、むしろ人を助けようという積極的な意思の持ち主なのである。彼らはだまされたというよりも、むしろ積極的、能動的に自分をだます詐欺行為に参加していると見ることもできる。「自分は無力な人間ではない」、「自分は社会に参加し、人を支え、助ける力をもっているんだ」――そういう気持ちを高齢者たちが確かにもつことが、そして、それを可能にするような社会の仕組みを作ることのほうが、今行われている振り込め詐欺キャンペーンよりもはるかに有効な防止策ではないかと、私はひそかに考えるのである。
2008.11.20
閲覧総数 1594
-
5

「バビロン再訪」を読む
先日村上春樹訳で「バビロンに帰る」を読み終わったばかりだが、今度は同じ作品を野崎孝訳で読み返す。野崎訳のフィッツジェラルドは「グレート・ギャツビー」以来だが、この訳が予想以上の出来だったので、村上訳がまだ出ていない作品も掲載されている「フィツジェラルド短編集」(新潮文庫)を買ったのである。野崎孝の訳はレベルが高い。私見では翻訳の質を決めるのはスタイル(文体)に対する意識の高さではないかと考えるが、野崎訳はとくに地の文において文体への意識が鮮明である。ギャツビーに関しては、村上春樹訳を待望する読者も多く、私もその一人ではあるが、すでにある野崎訳も十分な水準に達していると感じる。後半部の会話のリズムがうまくつかめないという難点はあるものの、総じてレベルは高い。同じ作品を野崎訳で読み直すと、情景描写に関しては村上訳で頭の中のイメージがややぼんやりとしていた部分がくっきりと焦点を結び、鮮明な映像が浮かぶ部分が何カ所かある。しかし、会話におけるリズム感や、そのせりふの背後に話者の微妙な心理や意識を感じさせる点においては村上訳に一日の長がある。まあ、あくまでも訳文のみを読み比べた場合の、きわめて漠然とした印象批評にすぎないわけだが。しかし「バビロン再訪」(村上訳は「バビロンに帰る」)に関しては、再読した時の方がすぐれた作品という印象をより強く感じた。これは訳の優劣とは関係ない。もっとこの作品の本質に関わるものだと思う。まず読み返して感じるのは、「たったこれだけの分量だったのか」という意外感である。むだなものを削ぎ落とし、時系列を微妙にずらし、ある一定の時間から時を逆方向にたどる、そのことによって冒頭で述べられる主人公の心情が徐々に立体的なものへと彫琢されていく。その呼吸は実に見事である。これは一読するだけではなかなか読みとれない。結末からさかのぼっていってはじめてわかるような書き方がなされており、その意味でも再読の価値がある作品といえるだろう。この作品はご存じの方もあるだろうが、春樹氏が絶賛してやまない短篇である。とくに書き出しのすばらしさをエッセイにも書かれていたと記憶している。それはバーのウェイターと主人公とのさりげない会話で始まるのだが、一見なにげないふうでいて、実にうまい。放蕩時代の知り合いの消息を尋ねるという形をとりながら、主人公の苦い心情、客観的な状況説明、後半部への伏線が巧みに示されている。これも再読してはじめて感得されたものだ。初読の際には、春樹氏が絶賛しているわりにはもうひとつかな、という印象を正直持ったのだが、読み返してみると、自分の読みの浅さを痛感する。どこにもむだがなく、簡潔でありながら、微妙な心情が的確に描かれ、人間心理への深い洞察が随所に見られる。バーのカウンターでのウェイターとの会話などは春樹氏の初期作品をほうふつとさせる。さらにラストの部分。苦みをおびた悔恨と不安、悲劇への予感を伴いながらも再起を期する主人公の決意とかすかな希望の光。読後に独特の余韻がただよう終結部は、春樹作品のそれを想起させる。表面的ではなく、深い部分で、この作品は村上作品のさまざまな部分に投影されているのを感じる。この短編集を私は順序を逆に読んでいる。まずあとがきを読み、最後の作品の「バビロン再訪」(しかし、このタイトルはすばらしい。Babylon Revisitedという音の響きもいい。ほんとうはこの音の響きを残して訳なんかしたくないと訳者は思うんだろうな。しかも作品中にバビロンということばは一回も出てこないのだ。)を読むというふうに。そのあとがきに意外にも村上春樹の名がでてくる。これには驚いた。やはり両者の間には世代一つ分のへだたりがあるという意識がこちらにあるので、村上氏が野崎訳に言及することはあってもその逆はないだろうと思っていたのだ。しかし、この部分は両者の人柄があらわれていて実にいい。ここを読んで、私は野崎孝という人が好きになってしまった。最後にその部分を引用する。「最後になったが私は、これまでにこれらの作品を翻訳・発表された訳者たち、なかんずく村上春樹氏にお礼の言葉を記さねばならない。翻訳はできるだけ本邦初訳のものをというのが私の原則であるが、今回は冒頭に記したような事情で選択した結果がごらんのような形になり、中に村上氏のものと重複するのが三篇も含まれてしまった。そればかりではない。氏が使われた訳語以上に適切な言葉が思いつかぬままに、それらをそのまま利用させて頂いた個所も二、三にとどまらない。盗用の非難を避けたいばかりに、先人の成果よりも見劣りすることを承知しながら、あえて拙劣な自分の訳語を使うというのは、私は寧ろ賛成致しかねる。その旨を述べて村上氏の許諾を求めたところ、快諾を得た。ここに明記して感謝する次第である。」(「フィツジェラルド短編集」新潮文庫、野崎孝「解説」より)この両人の心意気やよし、である。
2005.12.21
閲覧総数 2762
-
6

幸田文「藤」
好きな文章というものがある。その内容以前に、ことばを紡ぎだす書き手のこころの律動が、こちらの胸の奥にある音叉と共鳴して、微かな「うーん」という音をこころのなかに響かせる文章。ひとつの文をたどりながら、その少し先や、あるいはその少し奥が、布地に垂らしたインクのように周囲に静かににじみ、広がっていく文章。ひとつの文から次の文への流れが予測通りであることがよろこびとなり、予測通りでないことがまたよろこびとなる文章。そういう文章がある。もう一方で、「好き」ということばが必ずしもふさわしくない文章もある。もちろん「嫌い」なわけではないが、こちらから望んで積極的に読むことは少ない、ただ、何かの折にふとその文章に触れると、「はっ」と息を呑んでしまう文章。それまで無意識のうちに曲がってしまっていた自分の背筋を思わず伸ばしてしまう文章。何気ない一節に張りつめた「気」がこもっている文章。そういう文章がある。私にとって幸田文の文章は後者に属する。たとえば「藤」という随筆がある。大正十三年。文は家族ともども町へ引っ越す。それまでの草木に親しんでいた暮らしから、玄関わきに椿が一本、茶の間の前にかなめもちが一本、隅に椎が一本というようなわびしい景色の中に移り住むことになる。草木の少なさに不服を述べる家人に向かって、父、露伴はこう言う。「そこ(庭)は盛り土がしてあり、以前の表土の上に木屑や石くれが積んであるので、植えても木は枯れるだろうし、枯れていく木を眺めていられるほど自分の神経は、むごくはないのだ」。家人はそのことばに納得し、それ以後、何も言わなくなる。文は嫁ぎ、その後、夫と別れ、小さな娘を連れてうちに帰ってくる。「父なし子になってしまった孫娘に、祖父はあわれをかけてくれた。」そんなある日、町に縁日が立つ。「父は私に、娘をそこへ連れていけ、という。町に育つおさないものには、縁日の植木をみせておくのも、草木へ関心をもたせる、かぼそいながらの一手段だ、というのだった。」この縁日の短い描写に、私は小さく息を呑む。「水を打たれた枝や葉は、カンテラの灯にうつくしく見え、私は娘の手をひいて、植木屋さんとはなしをした。『これだけしゃべらせて、なんだ、買ってくれねえのか』といわれたりすると娘は私の手をかたく握って、引っ張った。」「娘は私の手をかたく握って、引っ張った。」ーー文章の神様がそっとウィンクしてくれなければ、けっして書くことのできない一節である。文章の神はこういう細部に好んで棲みつくものらしい。春になり、お寺の境内に植木市が立つ。露伴は文にガマ口を渡し、「娘の好む木でも買ってやれ」という。汗ばむような、晴れた午後、文と娘は連れだって植木市へ行く。娘は藤の鉢植えがほしいといいだす。「鉢ごとでちょうど私の身長と同じくらいの高さがあり、老木で、あすあさってには咲こうという、蕾の房がどっさり付いていた。子供はてんから問題にならない高級品を、無邪気にほしがったのである。」とてもガマ口の小銭で買える代物ではない。文は笑って他の草花をすすめ、娘は小さな山椒の木を選ぶ。彼女は山椒の葉としらすぼしを醤油でいりつけてごはんにぱらぱらとまいた弁当が好物だったのである。のどかな光景である。小さなしあわせのともしびがほんのりと浮かび上がるような情景だ。しかし、この空気が帰宅後、一変する。父、露伴はその話を聞いて、みるみる不機嫌になる。文の書く露伴のことばはいつも私の胸を衝く。それはひょっとすると露伴のことばそのものではないのかもしれない。そのことばを聞いたときの文のこころの震えや怯えや畏れごと、それらは紙の上にすくいとられているように思える。ここに書かれた露伴のことばもまさにそうである。少し長いが、以下に引く。「(父は)藤の選択はまちがっていない、という。市で一番の花を選んだとは、花を見るたしかな目をもっていたからのこと。なぜその確かな目に応じてやらなかったのか、藤は当然買ってやるべきものだったのに、という。そういわれてもまだ私は気がつかず、それでも藤はバカ値だったから、と弁解すると父は真顔になっておこった。好む草なり木なりを買ってやれ、といいつけたのは自分だ、だからわざと自分用のガマ口を渡してやった、子は藤を選んだ、だのになぜ買ってやらないのか、金が足りないのなら、ガマ口ごと手金に打てばそれで済むものを、おまえは親のいいつけも、子のせっかくの選択も無にして、平気でいる。なんと浅はかな心か、しかも、藤が高いのバカ値のというが、いったい何を物差にして、価値をきめているのか、多少値の張る買い物であったにせよ、その藤を子の心の養いにしてやろうと、なぜ思わないのか、その藤をきっかけに、どの花をもいとおしむことを教えてやれば、それはこの子一生の心のうるおい、女一代の目の親しみにもなろう、もしまたもっと深い機縁があれば、子供は藤から蔦へ、蔦からもみじへ、松へ杉へと関心の目を伸ばさないとはかぎらない、そうなればそれはもう、その子が財産をもったも同じこと、これ以上の価値はない。子育ての最中にいる親が誰しも思うことは、どうしたら子のからだに、心に、いい養いをつけることができるか、とそればかり思うものだ。金銭を先に云々して、子の心の養いを考えない処置には、あきれてものもいえない」と。このことばは文のこころに深く沁み入る。娘は大きくなっても花を見て、きれいだというだけ、木を見ても、大きな木ねというだけで、それ以上心が動かない様子を見せる。「ほかには優しい心をもつほうなのだが、野良犬にふみ倒された小菊を、おこしてやろうともしない固さなのである。」文章の神がまたウィンクをしている。しかし、娘の嫁いだ夫は望外に花を愛する人であり、その感化で娘もやがて花を愛ずるようになる。文はほっとこころをくつろがせ、一度どこかへ藤をたずねたいと思うようになる。そして東京近郊に見事な藤を見つけ、ひとときの間、それに見惚れる。しかし、その目は上を仰ぎみた後、下へと向かう。幸田文の文章の真骨頂が始まる。「しかし、花よりもその根に、おどろいた。千年の古藤というからには、根まわり何十尺と数える太さもさることながら、その形状のおどろおどろしいのには、目が圧迫された。うねり合い、盛り上り、這い伏し、それは強大な力を感じさせるとともに、ひどく素直でないもの、我の強いもの、複雑、醜怪を感じさせた。花はどこまでもやさしく美しく、足もとは見るもこわらしく、この根を見て花を仰げば、花の美しさをどうしようとおろおろしてしまう。だが、それならといって、立去れもしなかった。こわいものの持つ、押さえつけてくる力があって、連れの人にうながされるまで、私は佇んでいた。」ここで文は花を見、根を見ながら、人を見、人の生きる姿を見、人の生きる世界そのものを見ている。そこには美があり、同時に醜がある。そして、そのふたつは離れがたく結びついている。美に魅惑があるように、醜にも強い力がある。それをどう考えるべきか、しかし、答はない。答のない世界に棲む生き物の恍惚と不安と恐怖。それをこれほど短い文章に掬い取る幸田文の文章の凄みに、私は好意よりもむしろ恐怖を感じる。彼女の文章がこれほどの凄まじい凝縮力を感じさせるのは、彼女の目がおそらくここに書かれた以上のものをありありととらえていたからである。そして、彼女はそれを書かないことを通して、それらを言外の余韻として読む者に感じさせる。文章の神のウィンクばかりでなく、その鬼のような形相を垣間見た人間だけが、このような文章を書くことを許される。そう思いながら、私は文庫本にしてわずか15頁のこの作品を読みおえ、深く溜息をつくのだった。
2008.02.10
閲覧総数 1780