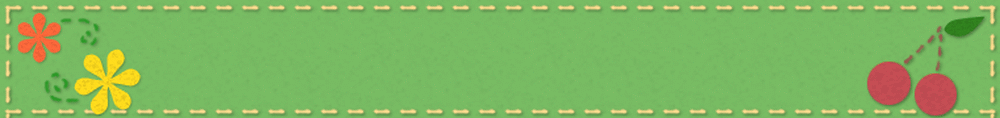全26件 (26件中 1-26件目)
1
-
レタス生きたまま!
毎週日曜のAM8時から岐阜市の梅林公園の前にある『グループホームひなたぼっこ』の駐車場で野菜市を開いています! 微生物発酵させた有機物を90%以上使用した『こだわりの土』を使い、プランターにて栽培された無農薬のレタス・サニーレタスを主に販売しています! しかも、プランターに生きたまま販売しているので『新鮮さならどこにも負けません!』その場で収穫してお渡しします。(収穫したい人はどうぞ!) 是非、お越しください! 販売場所を提供してくださったひなたぼっこの加来社長ありがとうございます!
2009年06月03日
コメント(22)
-
ひさびさに更新
約2年前に三重から岐阜に引っ越してきました。岐阜県下に2ヶ所農地を借りて今年から本格的に農業をはじめています!写真はプランターでの栽培です。レタスでいうと一般の露地栽培の約2倍の作付けができます!
2009年04月08日
コメント(1)
-
じゃがいも
徐々におおきくなっています!三重県で4月に新ジャガはあまりないのかな?と思ってます。楽しみです!
2007年03月03日
コメント(1)
-
貴船栽培
ジャガイモの芽が大きくなってきました!
2007年02月05日
コメント(1)
-
貴船栽培
室内設置〔鶏舎)での貴船栽培です。霜の心配が要らないので助かります。ジャガイモの芽が出てきました!季節はずれのジャガイモです。(今年度三度目)
2007年01月05日
コメント(0)
-
貴船栽培 菊
花が咲きました!どう収穫すればいいのでしょうか?
2006年12月25日
コメント(2)
-
委託販売してもらいます!
近所の農業屋さんに新しく出来た農家の産直市場「みのり」に野菜を出品させてもらう事になりました!!価格は自分で設定できます。いろんな人に食べてもらいたいです!
2006年12月21日
コメント(2)
-
貴船栽培
自慢の野菜達です!毎回、収穫の時は緊張します。
2006年12月20日
コメント(0)
-
貴船栽培
貴船栽培での作土は90%以上リグニン・ヘミセルロースが主の発酵物を使用しています。通気性の良い貴船の中で、ふかふかの土になります。ジャガイモを掘り出すと色白の皮の薄いものが収穫できるようです。
2006年12月13日
コメント(0)
-
貴船栽培じゃがいも連作
7月に続き、今年2回目(連作)のじゃがいもを収穫しました!茎と葉が霜にやられたので心配しましたが、芋は無事でした。少し病気も出ていたので、まだまだ課題も残りますが、とりあえず食味も7月の芋と同じ感じなので安心しました。
2006年12月08日
コメント(2)
-
貴船の特徴
貴船の特徴のひとつに水はけの良さがあげられます。設置した地面と貴船の底に隙間をあけている為です。大雨が降っても余分な水分は貴船の底から漏れていくので、土壌中の水分が腐ったり、倦んだりせずに常に水分率が安定しています。通気性の確保にもつながります。野菜づくりに水はけの良さが大切なのは言うまでも無いようですが?僕の経験した畑は土壌が粘土質で雨が降るとなかなか水が引かなくて、しばらく農作業が出来なかったり、または、部分的に水はけが悪かったり、畑の下半分の水はけが悪いなど全体的な野菜の品質が安定しませんでした。重機をいれて暗渠排水をするにしても、水はけが悪いために病害虫が発生しやすくなり農薬を撒くにしても、かなりのコストがかかりつづけます。もちろん、排水工事中は、作物の栽培は出来ません。農業は天候や土、畑の位置、場所、害虫、動物などの周りの環境に大きく影響されすぎます。ただ指をくわえて見ているわけにはいきません!貴船栽培は農地から畑を切り離した農業です!
2006年12月04日
コメント(2)
-
貴船栽培人参
人参の間引きをしました。(だいぶ遅れましたが)水はけの良さがいいのか?貴船では根菜の出来がとても良いです。
2006年12月02日
コメント(2)
-
イチゴの受粉
蜂がやってきました!
2006年11月30日
コメント(9)
-
貴船栽培イチゴ
順調です!
2006年11月29日
コメント(0)
-
貴船栽培イチゴ
1000×1000の貴船にビニールを張れるようにしてイチゴを育ててます。
2006年11月26日
コメント(4)
-
室内での貴船栽培
廃業した鶏舎の跡地での栽培です。花とイチゴを育ててます。室内コンクリートの床ですから、長靴要らずです。私服で楽しめる農業公園のイメージで作りました。台風・獣の被害もありません!夏は涼しく、冬は冷えない室内栽培!1年4期のジャガイモ作りにも挑戦します!
2006年11月25日
コメント(0)
-
「好気的な環境」による堆肥づくり
放線菌を含め、「好気性菌」(分子状酸素で有機物を酸化分解してエネルギーを獲得する)を主体とした発酵分解(堆肥化)を行う時、当たり前のことですが、堆肥舎全体、もしくは堆肥の培地全体が常に通気性を確保した「好気的な環境」であることが絶対条件です。しかし、自分のかかわってきた大多数の堆肥舎は壁面・床面ともコンクリート構造で通気設備・廃水処理設備はありません。もしくは機能していません。せっかく、うまく発酵しかけた堆肥物の蒸発水分は床や壁のコンクリートの界面で、結露反応を起こし、再び液体に戻ります。そのときついでに空気中の水分も取り込み、水分が更に増加します。培地底部は排水が不備であれば、徐々に水溜りとなってしまいます。従って、培地の各所で「嫌気環境」が生じ病原菌なども含む嫌気性菌の温床となってしまいます。その結果、嫌気性菌の作用により、アンモニア臭などの、悪臭の発生が顕著になります。もちろん、発酵物の分解の遅れも発生します。その他、牛糞〔水分)と副資材〔チップ・バーク)の配合が悪くゲル状になって、通気しないなど、色々な嫌気環境を作り出す原因がある。つまり、如何に堆肥舎全体、そして培地全体を「好気的な環境」に整えるかが堆肥作りの明暗を分けると言ってもよいと考えます。逆に私達、人間には目的とする微生物の環境整備しかやれる事はないみたいです。(それが難しいのですが。) つづく写真は嫌気的堆肥舎の例です。
2006年11月22日
コメント(0)
-
高濃度菌体表面被覆法
私達が堆肥作り(有機物の分解)をするとき、自社開発の高濃度菌体表面被覆法を用います。放線菌群を高濃度に増殖させた菌体を有機物の培地表面に被覆する手法です。放線菌群を選んだ理由は、有機物の分解能力に優れている事もそうですが、もうひとつは放線菌群の体外酵素です。多数の抗生物質が放線菌から見つけられているように、雑菌が増殖する事への抑止効果があります。その匂いはよく「土の匂い」に例えられます。竹林の土の匂いと言ったほうがイメージしやすいかも知れません。多くは土中にすみ、有機物を分解して生活していますが、堆肥作りの前段階で放線菌群を低栄養培地で高濃度に集積培養して、家畜糞などの栄養培地の表面に被覆し、有機物の分解、菌増殖を繰り返します4週間程度で高速発酵が行われ、分解過程で臭気発生や害虫の飛来は99%ありません。つづく
2006年11月16日
コメント(4)
-
貴船でさつま芋!
今日はさつま芋を収穫しました。今年は自分一人で掘りましたが、来年は色々な人に貴船のさつま芋畑に来てもらい、掘って、焼いて、食べて貰いたいです。そんな思いを胸に養護施設にさつま芋を食べてもらおうと持って行きました。ついでに、ひとつだけ焼き芋にして持って行ったら、喜んでもらいました。
2006年11月15日
コメント(0)
-
楽な農業における土作りについて その1
堆肥と一言で言っても、牛糞堆肥・豚糞堆肥・鶏糞・籾殻堆肥・生ごみ堆肥・腐葉土・バーク堆肥・土ぼかし・・・etcありますが、実は堆肥の定義はありません。作った人、使う人が堆肥と言えば、生糞だろうが、生籾・生オガ粉でも堆肥となります。よく議論がごっちゃになりますが、僕は堆肥=「肥料」とは捉えていません。堆肥=「土の母材」としています。農業で言う「良好な土」、「腐植に富んだ土」とは、有機分解物と粘土鉱物の複合体です。有機分解物とは、小動物・微生物の体内を通過したり、酵素分解を受けたものです。粘土鉱物とは、岩石が風化して極微細化した物質で主成分はケイ酸です。腐植の富んだ土は保水力と通気性のバランスが良く、陽イオンの交換能に優れています。以上の事から、僕が作る堆肥の判定基準はいかに木質などの有機物〔リグニン・ヘミセルロース・セルロース等)の分解が進んだのか?という事です。判定方法は主に「匂い」と「手触り」での判断になります。 つづく。
2006年11月13日
コメント(3)
-
貴船栽培
車椅子に乗った子供もお手伝い!
2006年11月11日
コメント(4)
-
畜糞尿堆肥化指導
農業高校での堆肥化指導。放線菌群を高濃度に増殖させた菌体を有機物の培地表面に被覆する手法で堆肥づくりを行います。貴船栽培の「土」になります。〔白く見えるのが放線菌群の菌層部分 生糞に着菌後30日目)
2006年11月10日
コメント(1)
-
貴船栽培
貴船1基〔2000×1200)のサイズで200本の人参が収穫出来ます。畝たて、溝きりの必要はありません。
2006年11月09日
コメント(1)
-
聖護院大根さん
今日は聖護院大根とブロッコリーを収穫して近くの養護施設に持って行きました。チンゲン菜に続いて2回目です。車椅子を使っている人でも出来る農業なので、いつかは多くの養護施設や空き地に貴船を設置してもらい、野菜作りを楽しみながら、たくさんではなくてもお金を稼いでいただくシステムを構築したいです。
2006年11月08日
コメント(4)
-
貴船栽培。〔無農薬・無化学肥料)
三重県津市の農場にて。
2006年11月07日
コメント(6)
-
農地からはたけを切り離す!
農地から畑を切り離しました! なぜ切り離すのか? それには色々な利点がありますが、まず、第一に「もっとラクに農業がやりたい!」自分は高校時代に農業の経験があります。真夏の畝立て、永遠を感じる草引き、腰を曲げ地を這う農作業は精神面、体力面では相当に鍛えられますが、そこまでしても天候や病害虫や野生動物の被害など影響を受けます。目的は野菜作り?それとも修行? 修行好きな人もいるみたいですけど・・・。そんな経験から、もっと簡単に楽な農業が出来ないか?コーヒー飲みながら、服も汚さずに出来ないか?素人でも車椅子に乗ってる人でも農業で食えないか?そんな所を原点とし、尊敬している先生を中心に発酵技術、土作り、新しい農業のビジネスプランを日々、研究・開発しています。 〔自分はまだまだ基礎勉強中の身ですが。) 写真は廃業した養鶏場の跡地を借りて、屋内型でのプランター〔名称 貴船)栽培です。貴船のサイズは変更可能なので、空いてるスペースに合わせて設置できます。
2006年11月07日
コメント(2)
全26件 (26件中 1-26件目)
1