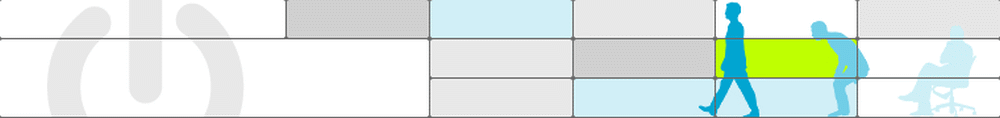2009年02月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
指導医講習会
やや精神的に疲れて、しばらく更新を放置していました。訪問してくださっている皆様には感謝いたします。まだブログ閉鎖をするつもりはありません。これも自分の中のモチベーションでしょうか。 さて、先日、臨床研修指導医講習会なるものに参加してきました。 聞き慣れない方もいると思いますが、5年前から始まった臨床研修制度は、大学を卒業したての新人医師が各病院に散らばって、そこで臨床を学ぶわけですが、当然指導をする医師がいることになります。資格好き、制度好きのお役所が、「あなたは研修医を指導して良い資格を与えますよ」と言わでもがなのことを押し付けるようにひねくりだしたものです。 もともと、臨床の現場では新人医師の指導はごく当たり前に行われています。1年目の医師には2年目が、5年目の医師には2,3年上の先輩医師がお手本になるのは当然のことです。卒業したての医師がいきなり20年目の医師のようになれといっても不可能ですし、どうしても指導を仰ぐのは話のしやすい若い医師になってきます。逆に言えば、20年目の医師が1年目の医師を指導すると、若い医師の今求めている答えをなかなか与えられずに、時にはお説教で終わってしまう事が往々にして多いのです。 少し考えれば当たり前のことですが、お役人というのは全くそんな現場のことを分かりません。「臨床研修指導医」という資格を与えることで現場に一体何のメリットがあるのかなんで考えたことは無いでしょう。 2日間にわたり行われた講習会はワークショップ方式で行われ、一言でいえば臨床で忙しい現場の医師をいじめ抜くだけのものです。通常の講演、講義ではなく、小グループに分けてそれぞれのテーマを討議させ、1時間に1回ほど進行状況を発表させるような方式なので、ほとんど休み時間はありません。それでもテーマが実際に役立つものであればまだしも、作り上げた結論は何かに反映されるものではないので、講習のあとにはむなしい疲労感だけが残りました。この講習会の参加費用は三万円で、50人ほどが参加していました。150万円はどこに使われてゆくのでしょうか? あまりきついことは書かないように気をつけていますが、言わずには居れません。 厚生労働省も、お役人も、そしてそれにへつらう保健所や大学病院などのお偉い医師も、どこかネジが一本抜けています。腐ってゆくこの国の医療制度を何とかしなければいけないのですが、すくなくともhead&neckには具体的な解決策は見当たりません。現場で我慢するだけですが、我慢にも限度が来る日が近いのではないかと感じたのでした。
2009.02.25
コメント(2)
-

見えざる危機
医師不足はもはや常識的な概念となり、いろんなところで医療の改善が提案され議論されつつあります。一向に改善されないことも大きな問題ですが、一般の人たちからは見えないところにもひたひたと崩壊の波は押し寄せて来ています。 先日、大学病院に勤める友人と話をしました。彼は今、生理学の教室で学位をとる、つまり医学博士になるために研究の日々を過ごしています。一昔前までは、医師と言えば8割方医学博士を持っていて、やや安売りされていた感は否めません。しかし、日本ではもともと医学部の卒業生がそのまま基礎医学の講座に入局する数は少なく、臨床医が大学院等に入学した期間、基礎医学の教室に在籍して勉強しつつ研究をするというシステムでした。こうした期間限定の医師たちによって日本の基礎医学は支えられていたという面は意外に知られていません。一方、基礎医学は全ての臨床医が学ぶべき学問で、どんな臨床医であっても有る程度の基礎医学、例えば生理学や生化学の知識なくしては正確な診断は出来ません。中学校の数学をやらずに高校の数学が出来ないのと同じで、詳細まで極める必要はありませんが、臨床を学ぶ上での土台となりますから、基礎なしで臨床をミス無くこなすのは危険なのです。 今、この基礎医学の講座が絶滅の危機に瀕しています。元々医学部に入学する人間の大多数は臨床医に憧れて入学してきています。6年間の大学生活で基礎に目が行く学生は少数派です。その上、基礎医学は大学以外ではポストは皆無に等しいため少ない人数でやりくりを余儀なくされています。それでも数年は基礎で過ごした後、臨床医になるという意識で基礎医学講座に入る人たちもいましたが、臨床研修医制度の施行で、医学生は卒業後臨床医として医療を行うために2年の研修が義務付けられ、最初に基礎医学を選ぶ学生数は激減しました。大学病院に所属する医師の減少で、期間限定で研究をする臨床医も減り、いま、基礎医学は人不足にあえいでいるのです。 基礎医学講座の崩壊は、そのまま医学教育の崩壊を意味します。マスコミや、政治家は臨床の医師不足にばかり目が行き、医師を育てるシステムまでは気が回らないようですが、医学教育の現場では静かに危機的状況が進行しているのです。 いつか、まともな医者が作れなくなる日がくるかもしれない。そう考えると、ぞっとするとともに不安を隠しきれないのでした ←参加しています。一日一回のぽちを。
2009.02.19
コメント(1)
-

外来と入院の収支 その2
さて、間が空きましたが、赤字と黒字の話です。 前回述べた病院の収入は複雑な診療報酬点数で国が定めて、2年に一度ずついじくりまわされます。その都度、病院や診療所は請求を変更しなければならないので、これだけでも相当な手間ですが、外来診療、特に病院の外来報酬は低く抑えられています。同じ病気で病院にかかるより、開業医にかかったほうが高いのですから、病気という不安を持つ患者が、検査機器のそろった病院を受診したがるのは当然です。病院のほうでは、医師の応召義務がありますから、来た患者さんは断れません。厳密に言うと「完全予約制外来」は医師法違反なのです。あちらこちらで言われる、「軽症患者が大病院に受診して混雑する」という現象は全く改善されません。受診にバリアをつけるため、特定初診料といって、紹介状の無い人からは2000円から5000円位の負担をしてもらうような制度が数年前に出来ましたが、焼け石に水です。かくして、軽症の患者の診療に時間をとられて重症患者を充分に診察できず、見逃しやミスに繋がります。 はっきり言うと、最も効果ある方法は紹介患者もしくは救急疾患以外は病院に受診してはならないという法律を作ることです。荒療治ですが、現在の医療崩壊を食い止めるには必要だと考えています。 次に、入院患者の診療ですが、これは技術料が圧倒的に低く抑えられているのは周知の事実です。たびたびこのブログでも述べているように、医師が10年以上かかってやっと身に付ける技術は全く評価されません。しかも全く根拠の無い改定に右往左往させられ、複雑怪奇な診療点数表が出来上がっています。個人的には、全面的な見直しと、先進国の平均並みの点数への引き上げが必要と思っています。更にドクターフィーが全く無いことも問題で、このあたりの意見を集約することは難しいのであれば、上限と下限を決めて医師自身に値段を決めさせる仕組みがいると思います。いわゆる悪徳医師や儲け主義を排除する罰則さえ設ければ不可能なことではないはずです。そこのところの手綱を引き締める役目こそが国や厚生労働省の役割ではないでしょうか。 いずれにせよ、老朽化してゆがみ極まる現行の制度は、小手先の改定ではもうどうにもならないところまで来ています。皆がそう感じていながら代えることの出来ない状況がこの10年続いていますが、崩壊する前に変わるのか。暗雲を見つつ今日も医療を行うのでした。 ←参加しています。一日一回のぽちを。
2009.02.09
コメント(2)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 11/24限定!衝撃の50%OFF!プレミア…
- (2025-11-24 15:16:27)
-
-
-

- 懸賞フリーク♪
- なんばグランド花月貸し切り公演を見…
- (2025-11-24 11:30:05)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-