全131件 (131件中 1-50件目)
-
移転のお知らせ
移転することになりましたので、とりあえずここは閉じさせていただきます。移転先は、http://blog.goo.ne.jp/dema02です。今までありがとうございました。
2010.12.29
コメント(0)
-

東海漬物
これはなにかといいますと、実は、沢庵のパッケージです。 中身はおいしく食べちゃいました。 深夜の人気アニメ「けいおん」に出てくるメンバーの1人、「ムギちゃん」の絵が描かれています。アニメの中でムギちゃんのまゆ毛が実は沢庵であったという夢を見るというエピソードが1回だけ出てきます。そのエピソードをそのまま商品にしてしまったというわけです。 こういうしゃれっ気で作られる商品ってけっこうあるし、珍しくもありません。 ただ、この沢庵の場合、製造、販売元が「東海漬物」とあるのを見て、びっくりでした。 どっかの小さな店か、ベンチャーみたいな会社が、若者のトレンドを敏感に察知して、よしやってみよう!みたいな感じで作るならともかく、天下の東海漬物です。キュウリのキュウちゃんで有名な漬物の王手の会社です。そんな会社がこんなしゃれみたいな商品を作るなんて・・・脱帽です。
2010.09.21
コメント(0)
-

ケニー・エドワーズを悼む
ケニーとカーラ ケニー・エドワーズが亡くなりました。8月18日、まったく突然のことで、おどろきました。ショックでした。 うそでしょ?というのが最初の思い。 ケニー・エドワーズといっても知っている人は少ないと思いますので、簡単に説明をします。 1960年代後半、リンダ・ロンシュタットと共に、「ストーンポニーズ」というバンドを組み、活動していました。ヒット曲も出しています。70年代になり、リンダがソロデビュー、ブレイクします。 ケニーは、リンダ・ロンシュタットのバックバンドでベースを弾き、日本にも来ました。来日公演行きましたが、その時のケニーの印象は、黙々とベースを弾く物静かな兄ちゃんという感じでした。 それからしばらくたってから、彼のソロの歌声を聞くようになりました。ただのバックミュージシャンだと思っていたのに「何だ、この人、ソロでやるんじゃん。」と、ちょっとおどろきました。やさしげな目をしたいいおじさんになってました。若いころとはおおよそイメージが違います。 日本はもちろん、あちらでもほとんどヒットはしなかったと思います。アルバムも、なんとか細々と売れたという感じではないでしょうか。 でも、この人のなんともいえない暖かみのある歌声は、地味ながら、魅せられるものがありました。 昨年の、カーラ・ボノフの来日公演の時も、バックで演奏しながら、1曲だけソロで歌いました。しみじみとした歌声を聴かせてくれたのをよく覚えています。ぜんぜん売れっ子じゃないけど、ぼくのお気に入りの一人でした。 日本では発売のないアルバムを、直接注文した時、ケニー自身が「代金が足りないよ。払ってください!」というメールをぼくにくれました。(もちろん英語で書いてありましたよ)なんか、ちょっぴりうれしかったです。でも、ほんとに細々とビジネスやってるんだなあと思いました。 彼の弾くフラットマンドリンに影響されて、ぼくもフラットマンドリンを始めました。そういう意味でも大きな存在でした。 音楽のメインストリームからははるかに離れて、「知る人ぞ知る」シンガーソングライターであった彼の死を、はるか離れた日本にいるファンとして悼みます。 合掌・・・ちょっと遅くなりましたけど・・・
2010.08.30
コメント(4)
-
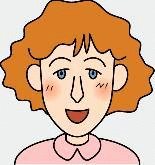
ホームステイ
我が家にアメリカ人のお客様が来ました。 息子の高校のイベントに参加するアメリカ人のお嬢さん2人のホームステイを受け入れたのです。 我が家は元々そういうことはやったことはないし、家の中はいつも散らかっていてきたない、普段客を呼ぶこともない家ですので、家の中の掃除に大わらわでした。 家に来たアメリカ人は、ブロンドのお嬢さんと、小柄なアジア系の顔をしたお嬢さん。なんと、この人は日本語をしゃべれる(両親が日本人)ということで、英語でコミュニケーションと構えていたのでちょっと拍子抜けしました。それでもできるだけ英語で話をすることができるようにと片言英語で話しかけてみました。もう一人のブロンドとは、やはりヒアリングを受けているようなぎりぎりのやりとり、ちょっと苦労しましたが、面白かったです。 「うちは父も母も小学校の教師をしているんだ。」と言ったら、2人も、教師になることに興味を持っているということでした。仕事はどうかと聞かれたので、「日本の教師は、アメリカの教師とは違って、学習指導に専念するのではなく、清掃指導や集金、下校後の生徒指導や事務処理等、いろいろな仕事をしなければならない。」ということを説明しようとしましたが、「生徒指導」という言葉をどう訳したらいいのかわからず、結局十分には伝わらなかったかもしれません。ただ、「雑用が多い」ということはわかってくれたと思います。 2人とも、食べるものは意外にオールマイティーで、梅干しもOK、刺身や海苔も大丈夫だということでした。さすがに納豆はすすめませんでしたが。それでもやはりごはんよりもパンが好きなようで、両方あるとそちらに手が伸びました。 日本語がある程度できるということで、短い間におどろくほど打ち解けて、いろんな話をしました。日本人とはちょっとちがうなと思ったのは、日本人が当然遠慮する、控えめにするだろうと思われるところで、堂々とはっきりものを言います。そういうところがぜんぜん嫌みでないのは、慣れたからなのでしょうか、それとも彼女らの人柄なのでしょうか。 ただ、香水のにおいにはちょっぴりまいりました。 彼女たちは歌が好きで、いっしょにギターやフラットマンドリンを弾きながら、歌を歌いました。「故郷に帰りたい」”Take me home country road”を、みんなでうたったら、なんともいえない一体感、高揚感で、胸がいっぱいになりました。 音楽っていいな!と思います。カラオケもいいけど、こういった形で楽器抱えて生で声を合わせて歌うのは、特に好きです。 帰ったら、もう彼女たちはいませんでした。「なんだかさびしいね。」「うん。」 妻とこんな会話を交わしました。 初めは正直言って、「この忙しい時期に・・・」という思いもあったのですが、彼女らを迎えて本当によかったと今は思っています。気を遣う部分ももちろんあったけど、我が家にとって、すばらしい体験になりました。
2010.07.08
コメント(0)
-
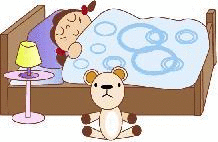
サッカー日本代表16強入り
日本代表が予選リーグを突破したのは快挙。これ以上めでたいことはないです! 以前のブログでも書きましたが、私は今回のワールドカップの日本代表にはほとんど期待していませんでした。それだけによけいにうれしいです。 日本代表の戦いぶりを見ていると、個々の能力以上のものを、チームとして発揮したなと感じます。個人能力を数値化して足し算した合計以上のものが出ていたと思うのです。これは、チーム作りがうまくいったと言うことでしょう。あえて川口能活を23人の中に入れた岡田監督の卓見ではないかと思います。カメルーン戦で勝てたのが、それに弾みをつけました。ちょうど日本の逆に。個人の能力は高いのに、チームとしてそれを発揮できずに敗退した国がいくつもありました。 決勝トーナメントのパラグアイ戦、TBSが昼間からバカ騒ぎをやっていたので、何かいや-な感じはしていました。予感は当たって、日本はPK負けをしてしまいました。残念です。 でも、ここまでやれば、日本代表あっぱれですね。 いいゲームとは言えなかったけど、死力を尽くした戦い、そして、最後は不運としか言いようのないPK負け。 見ていて悲しかったけど、やはり感動しました。 そんな余韻にひたちたかったのですが・・・・・ あっちでもこっちでも「感動」「感動」「感動」「感動」・・・・ こういう状況になると、ぼくはなぜかちょっとしらけてしまうんですよね。 シビアな勝負、勝つか負けるか、紙一重の運命の泣き笑い・・・これがスポーツの感動するところ、それに感動するのはいいと思います。けっこうそれは自然な感情でしょう。それに、日本代表の選手達と共に戦っているような一体感、そのエネルギーが最後にそういう形で放出されたのだと思えば、ごく健全なことだと思うのです。 でも、さいごのPKを外した駒野をなぐさめる姿に感動したとか、控えの選手達が出ている選手をサポートしたことに感動するとか、悪くはないんだけど、「それなら高校サッカーや高校野と同じじゃん」と思ってしまうぼくは、やはりひねくれているのでしょうか。もっとも、高校生と同じ事をいい歳した大人がやっていること自体に、ちょっとグッと来るものはありますが。 ニュースや特集番組を見ると、日本代表が、あまりにもファミリーであることが強調されすぎて、逆に違和感を感じてもしまっています。 ぼくが一番感動したのは、PK戦の時に、本田が手を合わせて祈っている姿が映されたところ。「ああ、あの本田が祈っているんだ!」と、不思議な思いがしました。自分に自信を持ち、厚かましいまでに自己主張する男が、祈っている姿、ああ、ぎりぎりの、人間の力ではどうにもならない世界に踏み込んで、純粋な気持ちでなにかにすがっているんだなあと、その光景がぼくには美しく感じました。 今回のワールドカップの日本代表の戦いに感動してくださっているみなさんに一言おねがいです! いい時の日本代表にだけじゃなくて、この先、どん底に落ち込んだり、さえなくなった時でも日本代表を見続けていってやってください! もう30年以上日本代表を応援し続けている物としては、そう願ってしまうんですよね。 かつては、ワールドカップ出場がかかった大一番の試合に、新聞の紙面の、巨人戦の記事の半分も割いてもらえなかったサッカー不遇の時代からは想像もつかないような恵まれた状況です。 でも、やっぱり、いい時ばかり注目される、そうでない時はみんなそっぽ・・・だとさみしいです。 最後に一言。声を大にして言いたいことですが、 次のワールドカップ、グループリーグ突破は当たり前なんてぜったいに思っちゃだめ! 日本は決してサッカー強国ではありません。 今回はいろいろなことがうまくいった結果なのです。 「次はベスト8だ」なんて思い上がると、ドイツ大会の二の舞です。 まずは本大会出場を目指し、現実的に、グループリーグ突破を目標にすべきです。 マスコミも舞い上がってないで、現実的なことを言ってほしいです。
2010.07.04
コメント(0)
-

サッカーのせいで
ワールドカップが始まりました。サッカーのせいで寝不足です。 そろそろ寝たほうがいいなと思う時間にちょうど試合が始まります。なにかちょっと片づけや洗濯干しなどをしながらついつい見てしまいます。見だしたら最後、気がついたら1時まで見てしまっています。 今大会は、強豪国が、期待されていなかったチームに敗れたり引き分けたりといった試合が多く、番狂わせ大好き人間としては、興奮してしまい、目がさえてしまって、1時間、2時間さらに寝られなくなってしまうのです。 それにしても、「弱小国」が、強豪国を破るのは、なんとも痛快、胸のすく思いがします。これは、サッカーならではのおもしろさではないでしょうか。 でも、フランスの予選リーグ敗退は、最後、ちょっと悲惨な感じがしました。時期も時期なもので、ワーテルローの、最後のフランス軍総崩れの光景と、自分の中でだぶってしまいました。 前回のエントリーで、「アフリカ勢負けろ」といったことを書きましたが、本当に負けてしまっているのには驚きです。アフリカの大会で、まさかこんなにアフリカ勢が苦戦するとは。どうしてしまったのだろうという感じで、ちょっぴりエールを送りたくなってしまいます。 日本は意外にも予選最終戦まで希望をつないでいます。今の時点ではわかりませんが、なんとか決勝トーナメントまでいってほしいと願っています。 日本の試合はどの試合もしぶとく泥臭い試合ばかりで面白くありません。サッカーとしてはほめられたものではありませんが、ドイツ大会での苦い敗戦や、オランダに3-0で敗れた親善試合などの教訓が生かされていることは評価できます。90分の戦いであることを常に頭に入れて、ゲームの流れを意識し、ペース配分をしていくというサッカーです。 組織で守り、攻める、日本みたいなサッカーは、実はもっとも「サムライ」的でないサッカーだと言えると思います。武士は本質的に自分の武勇を第一に考えるエゴイストなものだし、一騎打ちを名誉なものと考えるものです。 ヨーロッパでは、古代ローマの時代から、隊列を組んだ集団戦が根付いているのに対して、日本は、江戸時代になっても、きちんと隊列、フォーメーションを組んで射撃や白兵戦をするという戦術が根付きませんでした。(銃撃は、ある程度隊列は組みましたが・・・) 日本の合戦は、あくまで「首取り」の戦いだったのです。相手の名のある武将と戦って討ち取り、首を取る、それによって恩賞を得る、この慣行が最後まで残りました。それが「武士」つまり「サムライ」なのです。 日本の組織だった規律正しい集団戦は、どちらかというと「農民的特性」と言えると思います。だから、サムライと言うよりも農民といった方が適切だと思います。 相変わらずマスコミの豹変ぶりには辟易とします。ちょっと前までボロクソに叩きまくっていた岡田監督や、日本代表を、ちやほやしまくり。これで、また負けたらまたバッシングを始めるのでしょうね。 おっと、今日は早く寝ます!
2010.06.23
コメント(0)
-

ワールドカップへの期待
サッカーワールドカップが開幕しました。 ずっと昔の西ドイツ大会以来、ずっとこの4年に1度のサッカーの祭典を楽しみにしてきました。 でも、今回は、はっきり言って自分自身、すごく情けないことを考えてます。 それは、「アフリカ勢負けろ!」ということです。 今回の日本代表は、残念ながら、ほとんどめざましい活躍を期待できません。次の大会、次の代表、次の代表監督に期待したいです。 今回、初めてアフリカでの大会、アフリカ勢がたくさん予選リーグを突破してしまうと、当然のことながら、アフリカ協会は、次の大会のアフリカ勢の出場枠を増やせとFIFAに要求するでしょう。アジア勢が全滅したりしたら、アジア枠を減らされてアフリカ勢枠に振り分けられてしまうことは目に見えています。そうしたら、次の大会での日本の出場は厳しくなってしまいます。だから、アフリカ勢に勝たせたくないのです。 ヨーロッパや南米は、すでに枠が多いという事実があるし、けっこう鷹揚にかまえること思います。力を持つ大国は現行枠だけでも十分だと思っているし。 アジアの代表の中では、予選を突破できる力を持っていそうなのは韓国ぐらいのもの。今回に限っては、韓国を大いに応援します。 アジア枠のためにがんばれ! なんか情けない応援のしかただなあ。 日本代表、もっとがんばってくれよ!
2010.06.11
コメント(2)
-
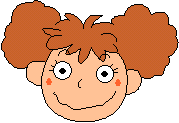
オープンスペース
日曜日、テレビを見ていたら、公立学校に、教室の仕切りのない校舎を作るといった取り組みについてのドキュメンタリーをやっていました。 この番組の「エンターテイメント」としての部分に、私の中でちょっぴり疑問符がつきました。それについて。 この番組の作りは、「常識を破ろうとする設計者」と、「今まで通りを望む教師」の対立という構図を中心に描いています。「まわりの音が気になって子どもが落ち着かないのではないか」と懸念する教師を、実際に壁を取り払った学校をじかに見る機会を設け、「なんだ、それほどでもないね。」というつぶやきでエンディングをむかえます。 常識を破ろうとする新しい試みが、苦難の末に理解を得、前進するという「ストーリー」に構成されています。 しかし、物事そんな単純な物ではありません。見る人がすっきりするように、一方向の筋書き以外の物をそぎ落としてしまっているのを感じました。テレビはしばしばニュース報道をする時にこういうことを露骨にやります。ぼくに言わせると、「エンターテイメント」です。 教室の壁を取り去るという試み、これは、メリットもあればディメリットもあります。 実際にこういった学校はすでにいくつも作られています。ぼくも何度かこういう学校に見学に行ったことがあります。ぼくはどちらかというとあまりいい印象を持ちませんでした。 隣のクラスの声はあまり気にならないといえば気にならないかもしれません。ただし、音楽を始めたら別です。音楽の授業をやる時は、学年で合わせるとか工夫するという話を聞きました。 番組の中で、教室の壁を取り去ることが、「閉鎖的でない開かれた教育」というイメージを喚起させ、政治の改革や情報公開などとイメージをダブらせ、「いいぞいいぞ」と心の中で喝采を送った視聴者も多いのではないかと思います。 でも、「開く」ことにも、メリットとディメリットがあります。ただ開けばいい教育ができるとか、子どもが良くなるとかいうものではありません。 閉じられた学級、壁に仕切られた学級は、ある意味、子どもを伸ばし、育てる可能性を無限に持っています。 閉じられた学級の中には、独自の規範があり、その学級だけの独自の空気、独自の共有意識、共感が作られます。その中でだから自分を出せる子、その中だから安心してバカがやれる子、教室は日常と切り離されている分、一種独特の「世界」ができあがるのです。 普通だったらしらけることが、その学級の中で、先生といっしょだとなんか夢中になってやれるみたいな物を提供してくれるのは、閉じられた学級なのです。 たとえば、学級対抗球技大会で、学級の作戦を立てたり、または意見が食い違ったりもめたり、けんかになったりで学級がぐちゃぐちゃになって、泣きながらなじり合い、やがて相手が自分と違うことに気づいて、少しずつ思いやる気持ちを持てるようになり・・・共感し・・・気持ちがひとつになる一体感を学級みんなでもって、だれかが「応援団を作ろう」なんて言い出して・・・といったドラマチックな盛り上がりは、閉ざされた「世界」の中だからこそ作られる物ではないでしょうか。 この報道番組に出てきた人は、この設計者も教師もそのまわりの人も、子どもが落ち着く落ち着かないだとか、学力がどうのとか、そういうことしか意見しないように見えます。(たぶん、それ以外のつぶやきは、番組編集の段階でカットされてしまっているのでしょうけど) ぼくは、壁のある、閉じられた教室の良さをここでは主張しました。しかし、公平な目でという意味で、「閉じられたスペース」にも、たいへんなディメリットがあるということも最後に付け加えておかなければなりません。 ひとりの教師と閉じられた「世界」を作る従来の学級は、もしもその教師が極端に偏った性格で、その人が子どもを強力に支配したりしたら、この閉ざされた世界は子どもにとって、「地獄」になります。 何でもそう単純じゃない。両面あるでしょう。 不登校気味の子のことを考えると、オープンスペースって、あんまりよくない気がします。こういういろいろな人の視線にさらされるような環境は、登校しにくいのではないでしょうか。 また、子ども達は、まわりで授業をやっていても、なれればそれほど気にはならないと言っていましたが、ADHD(注意欠陥多動性症候群)の子は、そうはいかないでしょう。
2010.06.09
コメント(3)
-
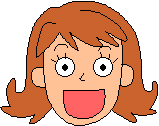
クラシック音楽
ぼくは小さいころ、歌謡曲や演歌がどうも好きになれませんでした。父は、そんなぼくに、「年をとれば良さがわかるようになるさ」と言いました。 そんなもんかなあと思っていましたが、大人になって、いいおじさんにとっくになってもいまだに良さはわかりません。要するに、これは、年齢になるとどうのというものではなく、体質的にあわないんだなあと思います。 ぼくは音楽ではロック、フォーク、カントリー、それにケルト音楽っぽいのが好きです。特に70年代のウエストコーストロック(死語ですね)が、やっぱり一番好きです。 ところで、ぼくは、はっきり言って、クラシック音楽というのがあまり好きではありません。音楽の授業とか、テレビの番組とかで、クラシックに触れる機会はたくさんありました。 「自分には良さがまだよくわからないんだな」とずっと思ってきました。「とっつきにくいものだから、最初は良さがわからないもんなんだよな」と思ってきました。 自分の中で、いつかは良さがわかるはずだと思ってきました。いや、ぼくの中ではもっと強迫的なものでした。 「クラシックこそ本物の音楽なんだから、その良さがわからなければ本物じゃない。早く良さがわかるようになりたい。」なんていう思いが心の底にありました。たまにクラシックのCDも買いました。部分的にはいいと思うことがあっても、聴いているうちに、自分の中で違和感がこみ上げてくるのはどうしようもありませんでした。あえてクラシックを聴き続けるのは、ちょっとかったるくなってきました。 ずいぶん後になってから、自分の中で気づきました。「ぼくはクラシックがわからないんじゃない!ぼくにはクラシックがあわないんだ!」 どうということのない、当たり前のようですが、ぼくの中では、「クラシックこそが本物の音楽なんだ」という信仰のようなものがあったので、それを覆すのはたいへんなことだったのです。 クラシック音楽は、歴史があります。また、今の音楽教育はクラシック音楽をベースにしているのでクラシックがすべての音楽の元であるかのように思われがちですが、考えてみると、ヨーロッパ中部の、中世から近世にかけて愛好された音楽です。そう考えてみると、沖縄民謡やアメリカのカントリーミュージックと同じように、ある地域のある時代の音楽のひとつに過ぎないのです。 そう考えると楽になりました。 クラシックを「あたりまえ」だと思わないで聴いてみると、全体としてリズムの抑制が特長になっていることに気づきます。アフリカのリズムを強調した音楽などと聴き較べてみるとはっきりとわかります。 リズムは人間の鼓動から来ているものだと思います。あるいは、2足歩行で歩く人間のテンポの表現から始まったのかもしれません。このリズムは「ビート」と言ってもいいと思います。クラシックでの打楽器は、同じテンポを刻んでいくというよりは、抑え気味から、いきなりティンパニーがドーンとすごい音を鳴らしたり、人間の鼓動や動きとは異質なもののように思います。クラシックが人間的なリズムを抑制しているのは、人間でなく、「神」を意識したものだからではないでしょうか。クラシックは禁欲的なキリスト教の空気を根底に持った、けっこう特殊な音楽なのではないか・・・これがぼくの結論です。 ちなみに、ぼくはバイオリンの音があまり好きではありません。あのキリキリ言わせて弾くソロは特に苦手です。でも、カントリーでのバイオリンは好きです! 「大草原の小さな家」では、あのお父さんは、たまにバイオリン弾いて、それにあわせて子ども達がフォークダンス踊ってました。ああいう雰囲気好きです。 おっと、だいぶ昔の話になりました。
2010.06.02
コメント(2)
-
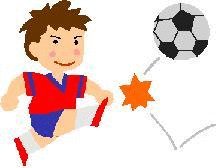
1年生と遊ぶ
昼休み、最近は結構子どもたちと遊んでいます。これはうちの学校だけなのか、全国どこもそうなのかわかりませんが、昼休みに1年生の子どもたちと、外で一緒に遊ぼうと思ったら、普通じゃできません。周到な準備をして、1秒でも無駄にしないでオニのように仕事をこなして余裕を作るか、または、「もういいや、どうにでもなれ!」と覚悟を決め、仕事をほっぽり出して外に出るかです。ただし、それプラス、子どもたちの誰かが「誰々ちゃんにバカって言われた~」なんて言って泣きながらけんかしてる子とか、階段でふざけてけがして保健室に行く子とか、給食で牛乳を倒す子とかが出ないことが前提です。 子どもと遊ぶと、なにか忘れていたものに触れられるような感じがします。他愛のないボール投げ遊びでも、キャハキャハ喜ぶ子どもたち。すべり台で思わずキャーッと叫び出す子ども。「せんせーい」と、手をぎゅっと握ってくる子ども。 よく、「教師は授業で勝負するものだ」と言う人がいますが、僕は正直言って、勝負なんかどうでもいいです。遊んでいる子どもが好きです。授業中の子どもは、「先生僕を見て」「評価して」と言っているみたいで、時にえらくさめてしまうときがあります。がんばって、お勉強という要求に応えようとしているみたいで、あるいは先生の要求に応えようとがんばっているみたい・・・ 遊んでいるときの子どもって本物です。 子どもたちと一緒に遊ぶと、自分の中の何かがリフレッシュされるような気がします。だから、少し無理をしてでも子どもたちと遊ぼうと思ってます。
2010.05.24
コメント(4)
-

1年生の楽しみ
ある意味1年生担任はつまらないです。 なぜかというと、1年生には冗談が通じないからです。中学年や高学年あたりで通じるダジャレがことごとく通じません。高学年相手にダジャレを言うと、子どもたちは、「つまんねえ」「またオヤジギャグ言ってるよ。」「チョー寒いんだけど。」とか冷たい反応をします。 でも、これはリアクション、寒い、しらけると言われるコミュニケーションもまた楽しです。そんなことを言っている子が、そのうち自分からダジャレを言い出すものです。 ところが、1年生ときたら、ダジャレにしらけるどころか、まるで「ポカ~ン」としてしまうのです。 先日、食の献立に揚げパンが出た日、「あげぱんほしい人!」と聞きました。たくさんの子がハーイと元気に手を挙げました。「はい、手を挙げて、たたくよ、パン!はい、あげパンでした。」という冗談を言いました。 1年生の子どもたちは、ただポカーンとしていました。なんのことやら意味をまるで理解していない。4年生の中には、ムキになって抗議してきた子もいるというのに・・・ それから、「先生、トイレ行っていいですか」と来た子に、「いっトイレ!」というワンパターンの初歩的ギャグもまるで効きません。何度か言っても反応した子はいません。 つくづく、今まで自分は子どもと冗談言うのを楽しみに教師やって来たんだなあと実感しました。 ところで、最近、そんな1年生と楽しむ方法を発見しました。 1年生相手に、給食の時間に手品をやっているのです。手品と言ってもごく簡単なものですが、それでも1年生は目を丸くして「お~、すごーい!」と、感心しています。 やったのは、「指を右手から左手に移す魔法」「両面牛乳キャップ」「指が手から離れる魔法」などです。「先生は魔法を練習したからできるんだよ。みんなも訓練すれば、大人になるころにはできるようになるよ。」とか言うと、半ば本気にしているのがかわいい! さらに悪のりして、「公園で木の棒を拾ってきて、ハリーポッターみたいに魔法の練習をすると、こういうことができるようになるんだ。」といったことを言いました。 でも、さすがに、インチキを見破っている子もいます。 わかっている子とわかっていない子、そのからみがまたおもしろいです。ほとんど信じている子、本当なのかなと疑ったり、どうしてかなと首をひねったりする子、そんな子たちのやりとりがなんともほほえましく面白いです。 1年生には1年生の楽しみ方があるものですね。 でも、今日は、給食食べながら連絡帳書きと宿題のマルつけ、なかなか子どもとふれ合う時間がありません。それが残念。
2010.05.18
コメント(2)
-
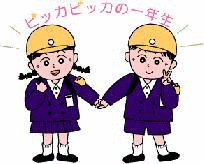
1年生の授業参観
1年生の子ども達と出会ってちょうど1か月がたちました。 給食も始まり、掃除も始まりました。覚悟していたほどの困った問題もなく比較的平和にここまで来たと思います。僕同様不慣れな他の担任達も、なんとかこなしてきたようです。 まあ、正直言って、いまだに子ども達がかわいいなんて思えるゆとりはありません。朝来てから子ども達が帰るまで、精神的にはずっと「臨戦態勢」のようなものです。 金曜日、初めての授業参観。 子どもに描かせた絵を壁に貼りました。中には2時間かけて画用紙が真っ白の子もいます。3時間目はつきっきりで、やっと画用紙の端っこにほんのちょっぴりだけようやく絵のようなものを描きました。 「描きたくないものを描かせる必要はないだろう」という方もいますが、それは一面的なものの見方。自分の子どもの作品がないことを知った親は傷つきます。その傷つきを教師への攻撃に向けます。そして、事情を説明したら、おそらく攻撃は我が子へと向かうでしょう。 教師の仕事は子どもの教育というのが筋ですが、「親へのエンターテイメント」という部分も避けて通れないのです。 さて、授業参観の日は早めに連絡帳にプリントを貼り、用意をしていると、配らないはずだったプリントが配布ということで回ってきました。ガーン!(やめてくれー!間に合わないよ)連絡帳1冊1冊、貼り付けたプリントの「配布物なし」を消して、「プリント1まい」に修正しました。こっちは冷や汗ですが、子ども達は無邪気に粘土で遊んで楽しそうでした。 4時間目が終わって給食、女の子が泣き出しました。お気に入りの6年生のお姉ちゃんといっしょに給食が食べたいと言って。学校生活に疲れたところで、五月の連休が終わって、また学校生活が始まって、ちょっと退行しているなと思いました。「いいよ、そうしようね。」と言ってあげたいところですが、直感的に、拒絶しました。「だめです。給食は順番通りにしましょう。そのかわり、昼休みいっしょに遊んでもらおうね。」 ここで許すと周りの子の甘えが一気に爆発しそうな雰囲気を感じたのです。みんな、甘えたいのです。でも、ここはそれをしない場所というつっかえ棒を心の中でして、自分を支えているのです。それをいったん崩してしまうことは危険なことです。あっちこっちで先生に甘えてだだをこねるぐらいならまだしも、自分の中に持っている育ちのゆがみや、親子関係の問題まで噴出させてしまうこともあるのです。学級崩壊のうちのかなりは、こうやって始まります。こう考えると、学校というのは、子どもにとって、「あきらめの場所」といえるのではないでしょうか。 しかし、子どもは「あきらめ」の代わりに、もっと大きな満足や喜び、達成感を得ることができるはずです。それを与えるのが私たちの仕事です。その喜びや満足の中で、子どもが持っていた心の傷や育ちのゆがみが少しずつ癒されていく-それが教師として子どもにできることです。 どうしてもそこで甘えや荒れを出さねばならない子ども-その子はおそらく「セラピー」が必要な子なのです。 セラピーは教室の中ではできません。どんなベテラン教師でも、安易にやってはいけないものなのです。 さて、給食も食べずに泣き続けた子、それもごちそうさまが近づくと、少しずつ泣き止み、給食を食べ出しました。 やれやれ 遅れを取り戻すべく慌ただしく授業参観の準備、 さすがに1年生、親がぎっしりと教室にやって来ました。 授業が始まって・・・・ひとりの男の子が机に突っ伏して泣き出しました。 授業を進めながらもその子のことが気になって・・・ ようやく練習問題を子ども達にやらせて、その間にその子のところに行きましたが、どうして泣いているのか何も言おうとしません。ただ泣きじゃくるだけ。なぐさめるのだけれど、原因がわからないからただ背中をなでながら「大丈夫だよ」と言うだけ。 授業がわからないのか、それとも他のことがあるのか、原因はわからずじまい。 子どもの泣き声を聞きながら、授業参観の授業を進める・・・それを親が回りでじっと見ている・・・ こっちが泣きたくなりました。 けっきょくリズムが狂ったままちぐはぐな授業で終わりました。 あとでお母さんに聞きました。赤鉛筆が折れてしまって・・・それを言い出せなくて、泣いていたんだそうです。 原因がわかってよかったです。 笑っちゃいました。 何がおかしいって、赤鉛筆1本で授業がムチャクチャになってしまったというのに笑えます。おろおろしてしまった自分にも笑えます。 これが1年生ですね。 ああ、1年生担任満喫してます。
2010.05.11
コメント(0)
-

「校長が変われば学校が変わる」
「校長が変われば学校が変わる」 10日ぐらい前ニュース23で、こんな特集をやっていたので見ました。 校長を集めて研修をやって、トップに頭を柔らかくしてもらって、学校改革を行っていこうという文科省の取り組みを扱ったものでした。 これを見た人はどう感じたでしょうか。 校長が集まって子どもみたいに無邪気にわいわいやっている研修風景に、ほのぼのとしたものを感じた方が多いのではないでしょうか。また、まるで新入社員みたいに真剣な顔で研修を受ける姿に好感を抱いた方も多いと思います。 番組の中でもいろいろな斬新な取り組みが紹介されていました。 番組は、おおかたこの取り組みを好意的に報道していました。 見終わって、悪いことではないと思うけど、なにかちょっとこれをほのぼので終わらせるには違和感を感じてしまいます。 校長が変われば学校が変わる・・・・校長が改革に目覚めれば、学校は改革されるということを言っているのです。裏を返すと・・・ その校長がいなくなって、次の校長が来た時、どうなるのでしょう。「校長が替われば、学校はまた変わる」のです。学校は変な方向に変えられちゃうかもしれないということでもあるんです。 今、校長の権限は強いです。バカな校長が来ると学校はすぐダメになります。 日教組の影響力が弱くなった今の学校では、校長次第なのです。 私は今の学校で、子ども達を、教育相談的な視点に立って、大事に見ていこうということを呼びかけています。ことあるごとに、そういった見方を他の職員に呼びかけています。 でも、もしも「子どもはビシビシときたえるのが教育だ」「甘えをゆるさないのが教育だ」「学力テストやスポーツの大会の成績で自分の実績を見せたい」みたいな校長が来たらどうなるでしょう。 もちろんそうなったら抵抗はするけど、いろんな形で大事に育ててきたものが踏みつぶされますね。そういう校長が来ないことを切に願うしかないというのが現実です。 今のところそんなひどい校長にあたってはいませんが、それでも、校長が変わるたびにいろいろなことのやり方ががらっと変わって、職員はみな振り回されます。 「校長が変われば学校が変わる」という言葉は、裏を返せば 「今の教育はトップダウンだ」ということなのです。 若い先生が多い今の学校では、その傾向がより強くなっています。
2010.05.06
コメント(0)
-
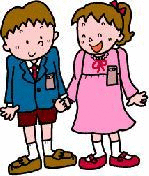
1週間たって
1年生の子どもたちとご対面して、はや1週間と2日がたちました。 朝来て、自分のカバンの中からお道具を出したり、プリントを後ろに回すこととかできるようになりました。チャイムが鳴ったら席に着くと言うことも理解できてきたようです。ようやく最低限の小学校生活ができるようになってきました。 毎日毎日うんざりするのは、子どもたちのドリルやワークブックへの名前書き。ただでさえ字がへたなのに。 親からの連絡帳への返事も結構大変です。何でこんなこともいちいち聞いてくるの?とか思うこともありますが、初めて子どもが学校に通うことで、不安なのですね。 今まで、1年生の先生たちが、子どもたちを早く帰してしまうのを見ていて、内心、ちょっとうらやましく思っていることもありましたが、とんでもない!早く帰すから大変なのです。 子どもが学校にいる間に連絡プリントを連絡帳に貼る、連絡帳に返事を書く等々めまぐるしく仕事をこなさなければなりません。 目が回るような1週間でした。 ところで、昨日、子どもとあっち向いてホイをやりました。時間的にはちょっと無理をしたのだけれど。「あ、かわいい!」と思いました。 初めて思いました。 1年生の初めって、特に不慣れな者にとっては、子どもをかわいいと思うゆとりすらないのですね。 月曜日からは、給食が始まります。 恐怖です。 牛乳瓶割るなよな~
2010.04.17
コメント(2)
-
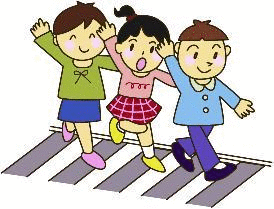
宇宙人との遭遇
昨年度末、新年度の学年を校長から告げられました。「1年生、学年主任をやってください。」「え、そんな・・・!」 学年はどこでもよいとは書きました。しかし、暗に、括弧付きで(1年はのぞいて)と書いたつもりだったのです。2年生はやりましたが、細かさを求められる低学年は、やっぱり自分には向かないなあと思っていた矢先でした。やはり自分は、学級集団をダイナミックに動かすような学級経営が、持ち味だと思います。 それが、1年生とは。もちろん、今まで1年生など1度もやったことはありません。 サッカーにたとえるなら、「ポジションは攻めでも守りでもいいですよ。」と言ったら、「じゃあ、ゴールキーパーたのむね。」と言われたようなものです。 でも、引き受けたものはしょうがない。学年の先生と顔を合わせたらまたびっくり。 1人は2年目の先生。もう1人は講師で、担任の経験がない人。副主任をやってくれる人は1年担任の経験が豊富ですが、他の学校から転任してきた人。なんでこんな人事になったのだろう? 不安いっぱいの船出となりました。 新学期始まって、まずは入学式の準備に向けて、手配するもの、書きこむもの、打ち込むもの、依頼しておくもの・・・あっちこっちに聞きながら・・・それでもボロボロ漏れが出る。 副主任はさすが頼りになりました。大いに頼りまくり。でも、ことあるごとに「前の学校では・・・」わかります。学校変わるとやり方変わるし、それに適応するのってものすごいストレスなのです。わけわかんね~と、内心ぼやきながら、でも、のこりの2人はもっとわからないので細かにケアをしなければと気を遣います。 実感したのは、今まで1年生とはずいぶん遠いところにいたんだなということ。通学路ひとつでも、けっこう曖昧にしか理解していなかったことを知りました。 そんなこんなでみんなに頼りながらも、ほとんどへとへと状態でむかえた入学式。 なんとか終えることができました。 全てが終わったような脱力感・・・・ でも、本当にたいへんなのは翌日でした。 子ども達が大きなランドセルを背負って学校にやってきました。 まだ緊張していて、いい子にしています。 でも、学校に来て、まず、何をするのか、どうするものなのか、まるで知らない子ども達です。「はやくおべんきょうしたーい。」「そとであそびたーい!」「もうあきた~」「はやくおうちかえりたい」 勝手なことばかり言うな!このジコチューども! とか、内心では思いながら、時間を気にしながら、連絡帳にプリントは貼り付けます。 ふつうわかりそうなことがぜんぜんわからない子ども達、幸い、お漏らしする子はいませんでしたが、だれだれちゃんがぶっただの、砂をかけただの、ちょこちょこ面倒なこともあります。そして、次々と勝手なことを言いに来ます。時間とハプニングとの戦いでした。 1年生は宇宙人だとよく言いますが、まさにその通り。宇宙人達の中で、たったひとりで奮闘する孤独な地球人。 その時、去年担任していた3年生の子たちがやって来て「せんせ~い!」と声をかけてくれました。 ああ・・・・地球人だ! うれしくて、目がうるうるしてきそうです。 なんとか2日間が終わりました。 土曜日はぐったりでした。 かわいいかわいい宇宙人達、早く地球人になってもらわなければ・・・
2010.04.11
コメント(4)
-
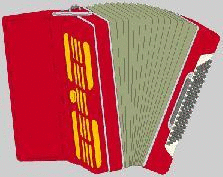
学級じまい
3学期が終わりました。 2年生のちびっ子達と、ガチャガチャうるさい、そして楽しい1年間が幕となりました。 3学期最後には、まるで高学年の子ども達と過ごすような、いい一体感、高揚感を学級みんなで共有することができました。 最後の「お別れ会」は盛り上がりました。子ども達の出し物はみんなそれなりによくできたし、楽しかったです。中には悪のりする子もいたけれど、「ある程度」をちゃんとわきまえてくれていて、声を張り上げて注意したりすることもありませんでした。 うれしかったのは、友達の発表を、「だいじに」してくれたこと。 今回は、全員が必ずなにか出し物をやろうということになりました。今まではやりたい人だけがやる形だったのですが。手品や合奏、なわとびやペープサートの劇などもありました。 はっきり言って、あんまりうまくないものや、人に見せる、聞かせるようなものでない発表もありました。それでも、みんなよく拍手してました。あったかい声援や、「すご-い」とか、声が聞かれました。 おともだちの少ないSちゃんの発表。Sちゃんはひとりで歌を歌うということになっていました。おとなしいSちゃんがひとりで歌を歌う?大丈夫かな?と心配していました。 Sちゃんの順番が来ると、やはり心配通り、前に立ってもじもじしたまま、歌い出せません。すると、いたずら坊主のOくんが「Sちゃんがんばって」と声をかけます。他の子からも、暖かい声援が飛びます。 あとでもいいよと声をかけようかと思ったそのとき、Sちゃんが歌い出しました。 「セーラームーンのテーマ」(時代が違うんでないの?)ちょっと早口だったけど、みんな、しーんとして聞いてました。 歌い終わったとたん、みんなから割れんばかりの拍手。緊張で顔を紅潮させたSちゃんの顔がにっこりとほころびました。 ああ、いいクラス・・・! 僕も胸が熱くなりました。 最後に、前日に書いた友達からの一言、本人は見ることのできなかった一人ひとりへの寄せ書きを、全員に配りました。しばし黙ってそれを読んでいた子ども達。 自分への寄せ書きを手に一言ずつ、涙をぽろぽろ流す子も何人かいて・・クラスがバラバラになるのが残念だというほとんどの子ども達、きっとウソではないだろうなあと思いました。 僕も、この子達の担任を離れるのがすごく悲しい気持ちになってしまいました。 いい別れ、いいクラスじまいができました。
2010.03.28
コメント(0)
-

この忙しいのに
学期末、この忙しいのに・・・ ジャクソンブラウンとシェリルクロウのコンサートに行ってきました。 忙しいのもあるけど、フラットマンドリンを買ってしまったので、今回はがまんしようと思っていたのですが、やっぱりがまんできませんでした。(笑) 僕はなんといってもジャクソンブラウンがめあてでした。彼は来日するたびにほとんど行ってますから。アルバムも全部持ってます。 でも、会場に入って、まわりの人の会話を聞いていると、8割くらいはシェリルクロウめあてで来たんだなとわかりました。「おれ、ジャクソンブラウンってほとんど知らねえよ。」とか言ってるのを聞くと、ちょっとムッとします。ちょうどサッカーの試合でアウェーのスタジアムに乗り込んでいったみたいな気持ちです。 コンサートが始まると、第1部はジャクソンブラウンのステージ、いつまでも青年のようなナイーブな歌声、美しく、そして楽しいメロディーの演奏に酔いしれました。みんな彼の曲を知らない人がほとんどなので会場は静か、ノリもイマイチでした。まあ、その分じっくりと聴けましたが。 会場の声にていねいに応える彼は、途中でギタリストにひそひそ、観客のリクエストに応えて演奏ナンバーを変更してしまったようです。人がいいというか物好きというか。 最後の「孤独のランナー」「テイクイットイージー」は、さすがに会場総立ち、ノリノリでした。 バックのバンドもすばらしく、大満足の1時間半でした。 第2部のシェリルクロウ、さすがに現役の人気者、1曲目から会場は総立ち、1時間半立ちっぱなしでした。 かわいらしい女性シンガーだと思っていたら、とんでもない、ぎんぎんのロック姉ちゃんでした。かわいらしく踊る場面なんてほとんどなく、ほとんどギターをかき鳴らしながらロックンロールナンバーのオンパレードでした。でも、ギターを持った彼女はすごくチャーミングでした。 そんなによくは知らなかったんだけど、気がついたら1時間半、足を踏みならし、手が痛くなるほど手を叩きながら、大盛り上がりの1時間半でした。シェリルクロウはいい! 終わったあとはどっと疲れが来ました。でも、ロックコンサートはこうでなくちゃ。そういえば、昔はよく行ったっけなあ。 なんか、カタルシスありましたね。学期末、忙しいときに行った甲斐ありました。
2010.03.13
コメント(0)
-

これからここで生きていく?
先日、放課後、呼ばれました。「○○先生、先生のクラスの子が木に足をはさんじゃって・・・すぐ保健室に来てください。」「え、足を木にはさんじゃったって?」 どういうことかわかりませんでしたが、とにかく保健室に急いで行きました。 担任しているA子ちゃんが保健室の長いすに腰掛けて、しくしくと泣いていました。「だいじょうぶ?」 A子ちゃんはこっくりとうなずきました。 そのあと、保健の先生から詳しく事情を聴きました。 A子ちゃんは数人の友だちと、学校の近くの公園で遊んでいたのだそうです。遊んでいる中でA子ちゃんは、木に登りました。そして、そこからするすると下りて行くとき、根本のあたりから二股に分かれた木と木の間に、足首がすっぽりとはまってしまい、抜けなくなってしまったのだそうです。 なんとか抜けようともがいてもだめ、友だちも助けようとしましたがどうにもできません。A子ちゃんはパニックになり、泣き出してしまいました。 その時、たまたま近くにいた学童の先生が、泣いているA子ちゃんに気づき、助けてくれたというわけです。 幸い、けがと言うほどのけがはなく、ホッとしました。 でも、A子ちゃんにとっては、かなりのショックだったようです。「びっくりしちゃったんだね。けがしなくてよかったね。」と、なぐさめてあげました。 そのあと、迎えに来たお母さんといっしょにお家に帰りました。 翌日、公園で遊んでいたときの状況など、A子ちゃんにお話を聞いてみました。 A子ちゃんは、もうショックもなく、すっかり元気でした。「先生あの時ねえ、私、足がぬけなかったら、ずっとここで生きて行かなきゃ行かないのかなあって思っちゃったの。」 本人はけっこうまじめな顔で言っていたのですが、思わず笑い出してしまいました。こんな風に思うなんて、なんともかわいい。 そのあとでちょっと悪い気がしました。「うーん、そりゃあ大変だ、あそこで生きていくのはつらいよね。」 2年生ぐらいの子どもは、実際そんな感覚になるのだろうなと思います。 大人じゃあり得ないよなと思うことも、ほんとうにあるかもしれないなんて想像してしまう。トイレの花子さんなんかでも、ほんとうにこわがります。 だから子どもって、「夢がある」んでしょうね。
2010.02.28
コメント(3)
-
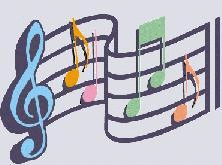
フラットマンドリン
日曜日、神田の神保町にいってきました。 学生のころはしょっちゅう行っていました。最近はちょっぴり疎遠になったけど、やっぱり神田は好きな町です。 神田(というよりは、お茶の水、水道橋界隈)は、古本屋、スポーツ用品店、そして、楽器店がたくさん集まっています。若者、学生の街ですね。 ふと立ち寄った楽器店、少し前からフラットマンドリンが気になっていました。できたら手にして弾いてみたいなと思っていたのです。 私がフラットマンドリンに惹かれるのは、ロッドスチュワートの「マギーメイ」(弾いているのはリンディスファーンのレイ・ジャクソン)それからバンドのレボンヘルムの弾くフラットマンドリンの音に魅了されたからです。あと、忘れてはいけないのはブリンドルのケニーエドワーズですね。あの高音の繊細な音色には魅力を感じます。 店の前に、「中古・キズあり 9700円」という1台のフラットマンドリンがありました。 これは買いだ!と思いました。 私のようにただ楽器にさわっていたずらしたいだけの人間にはうってつけです。さっそく店員さんに見せてもらいました。試しに弾いてみましたが、小さくて軽いのにおどろきました。「同じものですが、こちらですと、今、入門者キャンペーンで、弦と教本がついてきますよ。」と、1万6千円のものを薦められました。 それでも、この値段の差は大きいです。私の気持ちは揺らぎませんでした。 なのに、そのあとの一言が、重いパンチになってきました。「フラットマンドリンは、けっこう不具合が起きやすい楽器なんですよ。中古だと3か月保証ですが、こちらは保証が3年つきますよ。」 たしかに・・・この軽さはヤワさにつながるだろうなあという気がします。 そのあと迷いに迷ったあげく、1万6千円のものにしてしまいました。さらに、ハードケースまで買って、約2万5千円・・・うう、この出費は大きい! もちろんこれもフラットマンドリンの中では最も安い部類に入るものなのですが。 うまいこと買わされてしまった気もします。目玉商品というのはこうやって使うものなのでしょう。 家に帰って、毎日弾いてます。少しずつ弾けるようになると楽しいです。フレットの間がなにしろ小さくて、弦の間も狭くて、太い指のぼくとしては多いに苦労させられます。 バンジョーと違って,音が比較的小さいので、夜でも弾くことができるのがうれしいです。 今、バンドの「Atlantic city」と、ロッドスチュワートの「Maggie May」を練習してます。 当分の間楽しめそうです。
2010.02.21
コメント(2)
-
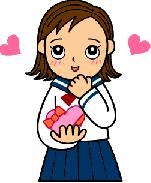
段ボール箱の中の子ども(その2)
段ボールの中の子ども 子どもを受容しようとする、いわゆる教育相談的な姿勢を持った先生が、学級経営で苦戦しているという話をあっちこっちから聞いています。高校では、強面の先生の前ではおとなしくしている子ども達が、子どもを理解し、受け入れようとする先生の授業では態度が悪くなって荒れ出すことがあったそうです。また、子どものことをきめ細かによく考える、人間的にも尊敬すべきベテランの先生が、厳しい家庭環境の中で荒れてしまっている子どもを担任した時、その子の内面を理解し、受け入れようとしたら、かえってひどくなり、学級全体が荒れ出してしまったそうです。その先生は、心労から、けっきょく病休を取ることになりました。 段ボールの中に座った子どものモデルを使うなら、窮屈な思いをしていた子ども達は、先生にあたる面の段ボールを蹴破って楽になったということになります。 子どもを理解しようとする先生はだめなのでしょうか。 厳しくて、付け入るすきをまったく与えないような教師ならばうまくいくということなのでしょうか。 強圧的な、あるいは真綿で首を絞めるような巧妙で執拗な支配のワナを仕掛けてくるような教師の前では、子どもは荒れを出すことをあきらめるでしょうから。 子どもは、自分のために親身になってくれる先生であっても、付け入るすきがあればその足を引っ張ります。カウンセラーのような受容的なスタイルで子どもに接するのはよほど自分の力量に自信を持っている先生でなければおすすめしません。 それでは、すきのない、厳しい先生にビシッと締められている子どもは、家でも、その他でも特別荒れていないとしたら、その子たちは「段ボールの中」で、どうしているのでしょうか。 段ボールの中の子ども達は、窮屈な姿勢で、じっと耐えて、がまんし続けなければなりません。そんな子ども達は、そのつらさに耐えるために、「鈍く」なります。自分の感覚を鈍磨させていくのです。極貧生活や、収容所での生活を続けると、喜怒哀楽を感じる感覚が鈍くなってくるといいます。「感じない」事で苦痛に耐えるというわけです。 子ども達は、体育がつぶされても、給食の時間に完全な沈黙を要求されても、その他意に沿わないことを先生から強要されても、多少のことに不満を感じないようになります。先生や親にこうしろと言われたものは、自分の感覚や欲求に照らし合わせることなく、素直に受け入れるようになるのです。 厳しく、子どもが自分の意に沿うよう、プレッシャーをかけ続ける先生がいました。その先生のクラスになった悪ガキ達が、次第に羊のようないい子になっていってしまうことがあります。(多くは先生のすぐれた指導力と解釈されます) 子どもは何も感じないようにすることで、親に、教師に合わせているのです。 自分は何も感じないようにしながら、親に合わせ続けて成長した子・・いわゆるこれがアダルトチルドレンですが、教師に対しても同様です。何も感じないようにして、ただ1年間先生に合わせ続ける子は、1年間、自分の感覚を麻痺させることで1年間を生き抜くのです。 子どもが荒れるのも、子どもがフリーズしてしまうのもいいことではないでしょう。 でも、そのどちらでもなく、子どもを生かす道はあると思います。 それは、「夢中になれるもの」を子ども達に与えることです。 それがあれば、その子は狭い段ボールの中でもそれを忘れて楽しく過ごすことができるのです。 たとえば・・・ 生き物、スポーツ、学級遊び・・・・ あの手この手、きっとひとつじゃだめですね。 教師は「まじめに」「いっしょうけんめい」「基礎学力」だけじゃだめだと思うのです。
2010.02.07
コメント(4)
-
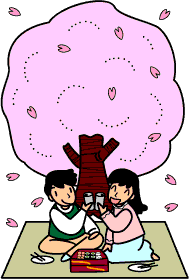
段ボール箱の中の子ども (1)
久々の教育相談だよりです。 以前、ちょっと難しい子に関わりました。 学校では、ちょっとしたことでキレて友だちに暴力をふるいます。一度キレると人が変わったようになり、しばらく元に戻りません。しばらく別室でクールダウンさせるとようやく落ち着きます。先生のちょっとした言葉に腹を立てて固まったまま、そのまま給食を食べなかったりするなどということもありました。 特徴的なのは、「うちの人に報告する」ということを極度にいやがり、というよりは恐れていました。 お母さんと学校で話をしました。 お母さんの話によると、家ではまったくそのようなことはなく、いい子なのだそうです。「学校でだけ荒れるというのは、学校での指導に問題があるのではないでしょうか」というのがお母さんの言い分でした。 家ではいい子なのに学校で荒れる→学校の指導が問題 学級崩壊状態になった学級での問題行動を取る子の親御さんがしばしばこういう事を指摘されます。 最近、これがはっきりと間違っているという確信が持てるようになりました。 乱れてしまった学級、崩壊しかかった、あるいはほとんど崩壊状態の学級をたくさん見てきました。また、逆に子どもをびしっと引き締める担任の学級の子ども達も見てきました。それらを観察する中で、自分なりにわかってきたことがあります。 子どもは、選択的に荒れを出すということです。 子どもは学校生活、家庭生活、習い事、友だちづきあいその他すべての生活の中で蓄積するストレスへの反応を、それが出せる場面でのみ表出するのです。 学校で荒れを出すのは学校でストレスがたまるからではなく、学校で荒れを出しやすいからなのです。実際には家で親子関係での緊張感などからストレスを感じて、それを出すことができない家でなく、学校で出していたという例は、けっこうあるのではないでしょうか。 学級崩壊などでは、周りがそのようは雰囲気、他に落ち着かない子がいるなどの環境があるので、自分の中の荒れを非常に出しやすいのです。 これを、モデルにしてみました。子どもが段ボール箱の中に体育すわりをしています。この段ボールは、子どもを包む家庭や学校などの環境だと想定してみます。狭い箱の中で脚を折ってじっと座っているのは疲れます。この疲れが、生活の中で子どもにかかってくるストレスだと考えてください。 この子は、できることなら段ボールをぶち破って足を伸ばして楽になりたいと思っています。そこで、段ボールを足でつついてみます。前面はしっかりしていてびくともしません。今度は右側、左側、後ろと、段ボールの作りの弱そうなところはないかともがきます。左側が弱そうだと見ると、子どもはそこを思い切り蹴飛ばして、箱を破ってしまいます。そして、子どもは箱の左側から足を外に出して楽になります。 段ボールの箱の弱い面、実際は家庭、学校、友だち関係など、生活する局面の、もっともやわらかい部分(やさしい、脅迫的でない、荒れて見せても受け入れてくれそうな感じがする相手)を選んで荒れを出すのです。 親御さんが保護的で、過保護で、子どもの言いなりになってしまっている場合、子どもはわがまま放題、母親に対してまるで暴君のように振る舞います。子どもは、「母親との人間関係」という箱の弱い面を突き破って足を出しているのだと言えるでしょう。 学校でそれほど目立った悪でもなく、家庭でも普通にしているのに、友だちに陰湿ないじめをしているという例もよくあります。 これらはみんな、子どもが、自分を取り巻く環境の中で、出しやすい場面を選んで荒れを出している結果だと言えるのではないでしょうか。
2010.01.26
コメント(2)
-

深夜放送
最近、夜寝られない時に、ラジオを聞いています。 学生の時はいつも夜聞いていたのですが、いつしかFEN専門になってしまい、そのうち聞かなくなってしまいました。 最近ラジオを聞いて、昔の深夜放送との様変わりにちょっとビックリです。 昔の深夜放送のようなDJ、パーソナリティーのスタイルは、今はほとんど消えてしまっています。今の深夜放送は、ほとんどの局は数人がマイクの向こうでトークをしている、あるいはたまに1人でしゃべっている人がいると、たいていその人は有名な歌手かタレントです。時代は変わったのね~と、しみじみ感慨にふけりました。 ところで、昔の深夜放送ってどんなだったのか・・・ おさらい 昔の深夜放送は、僕のいる関東地区だと、日本放送の「オールナイトニッポン」、文化放送の「セイヤング」、TBSの「パックインミュージック」のどれかを選んで聞いていました。すべてAMですが、FM局はもっと気取った、あるいは音楽に特化したみたいなプログラムでした。 当時のパーソナリティーは、谷村新司、愛川欽也、山本コウタロー、亀淵昭信、落合恵子、みのもんた、土井まさる、高島ひでたけ、南こうせつ、北山修、小室等、ソラマメ(本名忘れました)、馬場こずえ、林よしお、吉田まゆみ、野沢那智、白石冬美、広川太一郎、かぜこうじ・・・といった面々で、有名人もいれば無名の人、歌手から声優、アナウンサーまでいろいろでした。(もう亡くなっちゃった人もけっこういますね) それぞれが、曲を挟みながら、聞いているリスナーに語りかけたり、リスナーから寄せられるハガキを読んだりで、その時間、パーソナリティーとおしゃべりをしているような錯覚を楽しんでいたように思います。 僕も毎週のようにハガキを書いて、けっこう読まれました。リクエストもかかったなあ・・ そういう独特の距離感は、テレビにも雑誌にもない世界でした。この「世界」は、今のラジオからはほとんどなくなってしまってしまっています。個人的にはちょっとさびしいです。 でも、この深夜放送の、なんともいえない、似たもの同士が寄り集まってだべっているようなコミュニティーは、今はインターネットの掲示板やブログに取って代わられたのではないでしょうか。それならそれで、時代の流れですね。 昔ふつうのDJ(ディスコのDJじゃないですよ)だったみのもんたさん、テレビに出てあんな人気者になっちゃったのって不思議です。人間とんでもない形でブレイクすることってあるもんだなあって、しみじみ思います。
2010.01.18
コメント(0)
-
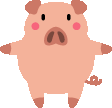
正月のスポーツ
ずっと前は正月といえば山の上にいたものですが、最近はすっかりいえ、そして妻の実家行って、のんびりのったらと過ごすようになりました。 だらだらとテレビを見ていると、やたら芸人が出てきてドタバタやるバラエティばかりなので、そういうのが嫌いな人間は、自然にスポーツをやっているチャンネルを選ぶようになります。(それならテレビを見なければ一番いいのですが・・) 正月はスポーツが目白押しです。毎日毎日いろんなスポーツがテレビを賑わしています。 元日は天皇杯サッカーを見てました。別にどちらを応援していたわけでもないのですが、遠藤の、ひょいひょいとディフェンスをかわすドリブルからのシュートが見られたのでお得な気分になりました。ぜんぜん迫力もスピードも感じないんだけど、ひょうひょうと2人を外すテクニック、ちょっといいものを見ました。ワールドカップでああいうプレーを見せてほしいです。 2日、3日は箱根駅伝を見ました。どちらかといえばただ走っているだけの駅伝はあまり見ないのですが、僕の母校が優勝候補ということで、見ました。見てたら優勝しちゃいました。やはりうれしいものですが、数年前まで毎年下位にいて、また今年もシード権を取れなかったなんてことが続いてたので、下位の学校が気になります。 駅伝はチームスポーツですが、一人がだめになると全員失格というところがちょっと残酷で好きになれません。その残酷さは、PK戦と同じ種類の残酷さです。走り終わってたすきを渡した選手が「ごめんなさい」と言って倒れ込む姿を見て、楽しい気にはなりません。もっとみんなの個性が絡み合って、創造的なものを作っていくようなチームスポーツが好きだな! 高校サッカーを今年も見てました。福島県代表の尚志高校は、メンバー表を見ると、千葉県出身者が多いのに驚かされました。山梨学院付属はFC東京のU15出身が実に多いです。みんな、首都圏の激戦区じゃない地方の高校に行って、全国大会に出ることを考えている選手、それにそういう子を積極的に集める地方の私立高校の利害が一致した結果と言えるかもしれません。これじゃ地区代表の意味があるのかな?なんてちょっと思ったりして。(ヨーロッパのクラブチームも同じかも) 高校サッカーはそれぞれチームカラーが出ていて番狂わせも多くて見ていて楽しいです。特に今年は決まった強豪校でないチームが勝ち進んでいるのがいいですね。(サッカーは、スポーツの中で、もっとも番狂わせが起こりやすいスポーツです) 何十年も前からずっと気になっていることがあります。キー局の日本テレビの青春、感動演出の露骨さ、いやらしさが鼻につきます。広島観音高校対矢板中央の試合をダイジェストで扱っていましたが、レポートは100パーセント広島観音サイドでなされたもの。監督の信念、選手選考の場面での涙、選手達のエピソードなどを細かく紹介しながら構成していきます。そして、優位と言われながらのまさかの敗北、最後まで必死に応援する応援席、そして選手達の涙、それが放送のすべてです。 劣勢を覆して会心の勝利を挙げた矢板中央のことは触れなくていいのかい? これはニュース、報道ではありません。意識的に、感動させるようなドラマを作ろうとしているのです。使えそうな事実を切り貼りして。 もっと普通にサッカー放送を作ってほしい-これが、一サッカーファンとしての願いです。
2010.01.09
コメント(0)
-

新年 ひさびさのエントリー
4か月モブログを休んでおりました。 病気とかしてたわけではないのですが、なぜか気持ちがブログに向かなかったのです。 気持ちがちょっとトンネルに入っていた感じかも知れません。 しばらくブログをはなれてたまに見てみると、面白いことに気づきます。 もう放置状態、草ぼうぼう状態なのにもかかわらず、アクセセス数はほとんど変わらないということです。たまにのぞきに来るとこれはすごく不思議でした。 いったいだれが休業状態のブログをのぞきに来ているんだろう。 答えは簡単ですね。あやしげな業者のシステムがあっちこっちのサイトを自動的に巡回していて、それがここにもやってきていたというわけでしょう。あやしげな書き込みはけっこうたまってました。 業者のみなさんご苦労様・・・といいたいところですが、自動で巡回しているだけですから実際は誰も来ていないことになります。それならブロックする方法はないものでしょうか。 ここで新たにわき起こる疑問・・ああいうことして利益になってるのかなあ? あの書き込みで客を呼べてるのかなあということ。 ぼちぼちまた書いていきます。
2010.01.05
コメント(2)
-
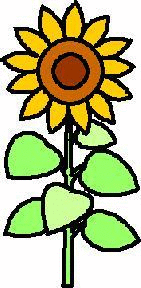
忙しかった~
9月第1週が終わりました。 月曜日8月31日はゆったり半日勤務にしたので、子どもが来てからは4日間お仕事したことになります。 つかれた~ 止まっている車がいきなり急発進、トップギアに入れて100キロのスピードを出したような感じです。 初日から給食、毎日家に帰るのは9時過ぎ。ごはんを食べてから持ち帰り仕事をして、おふろに入って寝るのは1時過ぎ。 こう忙しい理由は、今年は運動会が約1週間早い(12日)からです。学年の運動会種目の詳細を決めて、練習予定を組み立てます。種目の小物を作ったりの準備もします。一週間でみっちり練習しました。今年はインフルエンザの流行があるので、特に急いで準備、練習を進めました。 夏休み明けは、子どもの作品がどっと来ます。読書感想文、科学作品、絵日記、観察記録と、その上生活表なんて、子どもにとってやっかいなものもあります。子ども達も休みの間がんばってきたので、一応赤ペンでコメントを入れないといけません。これが、いくらやってもやっても終わらない。 その上、「読書感想文コンクール」「科学作品展」代表を出すようにせかされます。 その他に、ポスター応募作品とかもまとめなければなりません。 おそらく、日本のほとんどの学校の先生は、似たり寄ったりの状況でやっているのではないのでしょうか。まあ、毎年この時期は忙しいです。 我々教師も忙しいけど、子ども達もたいへんでしょう。夏休みだったのが、学校始まって、いきなり時間時間できびきび動いて集団行動「ちゃんとしろ!」なんて先生からうるさく言われて。 よく、「まったく、子ども達だらけててしょうがないよ。運動会間に合うのかね。」ってぼやく先生がいるけど、考えてみれば、忙しくて時間がなくて焦っているのは教師側の事情。子どもは先生に合わせているわけです。しゃんとしててあたりまえというのは教師の身勝手かもしれません。 教師も子どももあんまり忙しいのってよくないですね。 見えるはずのものが見えなくなります。教師が子どもにこれでもか、これでもかって課題を与えてって、自分も夜遅くまで必死にそれを見て、お互いぎりぎりまでがんばってがんばってがんばって・・・これってはたから見るとすごくいびつな図でしょうね。 また授業進度は遅れそうだけど、教室ではちょくちょくクイズやゲームやって遊んでます。まじめな学校で、せめて少しでもふまじめな教師になろうと心がけています。
2009.09.05
コメント(2)
-

答志島エンカウンターグループ
久々に、ベーシックエンカウンターグループに参加しました。 ベーシックエンカウンターグループとは、カール・ロジャースの来談者中心療法の考え方による、集団カウンセリングのような意味合いを持った、心理的なグループワークです。「エンカウンター」というと、構成的グループエンカウンターのことを指すのがほとんどです。こちらの方は、教師の間ではけっこう知られています。 「構成的」と、「ベーシック」の違いは、構成的の方が、「このセッションではこのエクササイズをやる」と、決められているのに対して、ベーシックの方では、基本的には決まったものが何もなく、その場で思ったことをぽつりぽつりと話し合うというところです。 職場でも、また自分自身にも、満たされない思いや、不全感のようなものを抱えていて、もやもやとした気持ちで過ごすことが多く、自分の中のエネルギーが枯渇してしまっているような気持ちでした。だから、人とのつながりの中で、癒しを得られたら、そして、自分をリフレッシュしたいと思い、参加しました。 新幹線、近鉄を乗り継いで、三重県の鳥羽まで来て、そこから船で15分ほど。答志島の桃取というところにやって来ました。 海がきれいで、波も静か、景色もやさしげでのんびりとした漁村です。たまに小さな漁船が港を出て行きます。海鳥がゆっくりと水面近くをすべるように飛んでいきます。夕焼けが美しくて、それを見ているだけで心を洗われるような思いでした。 美しい海、自然。でもここはぜんぜん観光地化されていません。まず観光みやげというものをまったく見かけないし、近くにはなんでも売っている店が1軒だけ。あたりを散歩すると、狭い路地をのったりのったり歩いているおじいちゃんが人のよさそうな笑顔でこっちを見て、会釈してくれます。農作業をしているおばあちゃんの動きもどこかのんびりしていて、ここだけ違うペースで時間が流れているような気になります。 大学の時、バックパッキングをして歩いた感じを思い出しました。荷物を背負ってキャンプをしながら毎日毎日歩いた夏合宿、あの時も、こんな観光地化されていない良さに触れたっけ。考えてみたら、最近は旅行というと観光地化されたところばかりだったなと気づかされました。 それにからもう一つ特筆すべきは、「海ほたる」きれいです!なんとも神秘的。 夜の海で釣り竿を振り回すと水面が不思議な輝きを放つのです。これを見られただけでもすごく得した気分です。夜、みんなで遅くまで防波堤の上で飽きることもなく海ほたるに見入っていました。 宿に入って、さっそくベーシックエンカウンターが始まりました。1時間半から2時間くらいのセッションを、午前、午後、それに夜、夕食後に行います。 20人ぐらいの人が車座に座り、ただ黙っています。みんな何も言わず、黙っている時間が長くつづきました。この沈黙の中で、自分の心の中に浮かぶもの、心が動くことなどがあるのですが、教師生活に慣れた僕にとっては、はじめはこの沈黙がとても苦痛です。だいたい教師はじっと待ったり沈黙していたりするのが苦手ですね。子どもが何も言わないで黙っていると、「何か言いなさい」と怒り出す先生もいます。 しばらくたって、だれかがなにかを言うと、それに刺激されて、他の人がまたなにかを言います。人の話を聞きながら、自分の心の中ではいろいろな思いが「動き」ます。 今自分が感じている気持ちって何なんだろう? なぜかわき上がってくるこのもやもやしたものは何なのかな? 話を聞いているうちに、自分の中で共鳴するなにかがある そんなことを感じながら、みんなが話すのを聞いています。そして、ときどき自分も思うことを語ります。 こんなことをしながら筋書きのないグループセッションが、2回、3回と繰り返されます。これを繰り返すうちに、なぜか自分の心の深いところにある物が見えてくる、感じられてくるから不思議です。そして、まわりの人たちと気持ちのつながりができてきます。3日目ぐらいにはほんわかとあったかい、そこにいるとリラックスして安らげる空気があるのに気づきます。 3泊4日のエンカウンターグループのセッションを通じて、まわりに合わせすぎていた自分、協調を意識して自分を萎縮させてしまっていたことに気づきました。自然と人に癒されて、もっとのびのび自分を表現していた、「ほんとうの自分」を思い出した気がします。 行ってよかった。 別れ際は、やっぱり目がうるうる状態でした。 ところで、ベーシックエンカウンターグループのセッションでは、一人ひとりがリラックスできる姿勢で参加していいので、あぐらの人もいれば、足を前に伸ばして背中を壁にもたせている人もいます。コーヒーを飲んでいる人も、あめをなめている人もいます。中には、ごろんと寝っ転がっている人もいます。 ファシリテーター(リーダー、講師)の人が、セッションの中の場面をとらえて、カウンセリングについて、みんなに話をしているのに、そのとなりの人が寝っ転がって聞いている、これは他の研修では考えられない光景です。でも、これもありなんです。思わず笑ってしまいました。
2009.08.28
コメント(2)
-
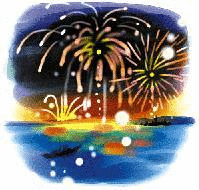
野球とソフトボール
今、デニーズでこのブログのテキストを打っています。「ポメラ」を買ったので、早速使っています。便利です。ずっと前に使っていたワープロのフィーリングがあって妙に懐かしく、なんとなくうれしいです。素っ気ないモノクロ液法画面がそれっぽいのかも。キーボードはちょっと打ちにくいかな。まあ、そのうち慣れるでしょ。 2016年のオリンピックの新種目の候補がゴルフと7人制ラグビーに決まったとか。ゴルフにはぜんぜん興味がないんで、どうでもいいですけど、7人制ラグビーというのはちょっとおもしろいかも。 日本がプッシュしていた野球とソフトボールは両方ともだめでした。失望の声があちこちで聞かれます。 野球というスポーツは、チームスポーツとして、ちょっとばかり「くせ」が強いように思います。1チーム9人の中で、ピッチャーが占めるウェイトがあまりにも大きいのです。これは、ほかのチームスポーツにはみられません。 抜群にいいピッチャーがいると、他はたいしたことなくても勝ててしまうということがよくあります。サッカーだってすごいストライカーがいると強いけど、それだけじゃ勝てません。やっぱりそのストライカーにいいボールを供給できないと。 その辺が、野球が世界中に広まらなかった一つの原因じゃないでしょうか。あと、アメリカのメジャーリーグが、例によって世界大会をまじめにやる気がない。その辺が足を引っ張った結果でしょう。 ソフトボールが落選したのは残念です。でも、内心、「やっぱりな」という思いがあります。 ひろく広まっていくスポーツとして、やはりなにか欠けているものがあるような感じがします。 ソフトボールは、野球とはっきりと差別化できていません。ヨーロッパの人とかからみれば、「下投げしてる以外、野球とどこが違うの?」と言いたくなるでしょう。「野球とは違うのだよ。野球とは!」(どこかで聞いたようなセリフですが)といえるものを持ちたかったですね。 下手投げで100何キロの剛速球を投げるのはすごいです。脱帽するし、素直に敬意を表したいです。 しかし・・・ソフトボールって、そもそもどうして生まれたの?野球との違いってそもそもなんなの?と考えてしまいます。 ソフトボールの歴史を少しひもといてみると、クリケットがアメリカでアレンジされてさかんになり、それが、より競技志向の強いものが野球へ、よりレクリエーション志向が強いものがソフトボールへと発展していったということが書かれていました。 そもそも下投げにしたのは、剛腕投手が打者をねじ伏せる野球と違って、みんなが打てて走れて、楽しめるという競技として生まれたからのはずでしょ。だったら剛速球投手が活躍する競技になっちゃったら、スポーツ本来の方向性と全く逆じゃないですか。ソフトボールで剛速球ピッチャーが活躍するようなら、いっそ上投げを許可しちゃったっていいだろうと思ってしまうのは僕だけでしょうか。 競技としてやれば、みんな一生懸命になって技を磨くし、どんどんすごい選手が出ます。でも、そのスポーツの特性というものに立ち返って、ルールを見直してみてはどうでしょうか。
2009.08.16
コメント(1)
-

あずまんがとナポレオン
どちらかというとあまりマンガは読まない方です。 でも、たまーに読みます。 コンビニで「あずまんが大王」を見つけておどろきました。それも、昔出ていた電撃コミックスでなく、小学館からリニューアルされて出ているのでびっくりでした。 このマンガは、女子高生のなんということのない日常、学校生活を淡々と描いた4コマ集です。恋愛ネタなし、エロネタもなしだけど、なんかおもしろい。僕は個人的にすごく好きでした。「小学館から発刊されたか、出世したねえ!」などと変な感慨にふけりながら、「そんなにおもしろいもんだったんだっけ?」と思って、DVDをかりてきて観たら、やっぱりおもしろかったです。 詳しくは http://www2.ttcn.ne.jp/~tot23/page040.html参照 マンガといえば、コミックが出るのをいつも心待ちにしているのが「ベルセルク」と、「ナポレオン 獅子の時代」です。 「ナポレオン」 は、得も内容も、とにかく濃いです。男っぽい。一人ひとりの人物の個性、性格が大事に丁寧に描いています。 よく、「勇猛」「豪胆」「男らしい」「卑怯」などのキャラクターを人物にあてがい、ステレオタイプ的に描いていくといった構成の仕方があります。まとまりはいいのですが、どこか平板な感じがします。特に歴史ものでは、主人公を引き立てるために、わざとらしく作った感じがしてしらけてしまいます。 この「ナポレオン」では、その正反対です。登場人物一人ひとりが、いいところも、しょうがない面も、両面持った「生きた人物」として描かれます。いや、人間の性格や資質を「よい」「悪い」「すぐれている」「劣っている」などと分別しない描き方がされているのです。そんな人物たちが絡み合って物語(史実)を作っていくからおもしろいです。 僕が特に気に入っているのは、ナポレオンの部下でも特に人気のあるランヌ元帥の描き方です。忠実で勇猛、プライドが高く命知らずのガスコーニュ出身として知られています。この男を、作者の長谷川哲也さんは、粗食に耐え、体を鍛練し、常に兵士の先頭を切って走るように行軍し、真っ先に敵陣に突撃をかける勇者として描いています。しかし、一度キレると相手を半殺しにしてしまうまで止まらないある種の「異常性格」のようにも描いています。 陰謀家として悪名高いジョセフ・フーシェは、単なる悪党ではなく、自分の娘の死には涙する父親としての一面も描いています。 そしてなにより、主人公のナポレオン ぜんぜんいい人じゃない。 戦争をなくして人民を幸せにするんだとか、革命の理想を成し遂げるんだとか、そういうきれい事は一切出てきません。他人を平気で利用するし、そんなずるいところもちゃんと描かれてます。 大砲で自分に反対する市民をいっぺんに処刑しようと考えた議員が、大砲を借りに行くと。指揮官に「大砲は処刑の道具ではない」と貸与を拒絶されます。それを聞かされたナポレオンは、「何だ、おれに頼めばいくらでも貸してやったのに。」と言います。ここに出てくるナポレオンは正義もクソもないのです。 主人公がこういう人物でもおもしろく読ませてしまうところがこのマンガのすごさです。 どうしても主人公は理想化してしまったり、やたらいい人にしてしまったりしがちです。(NHKの大河ドラマみたいに・・)でも、そうでなくてもこれだけおもしろいものが描けるのは、やはりなんといっても作者の長谷川哲也という人の力量だと思います。 コミックアワードというちょっとマイナーな雑誌に連載中です。 僕のイチオシのコミックです。
2009.08.10
コメント(0)
-

ちょっと違う
先日、受験の息子の高校説明会に行ってきました。 はじめに学校紹介のビデオを観たあと、校長が出てきて挨拶、学校の特長、教育方針などについて話をしました。この人、ビジネスマンの臭いをプンプンさせている感じだったので、「もう帰ろうかな」と思ってしまいました。私学というのはこんなものなのだろうなと思いました。 そのあとで、見学がありました。そこまでで帰ろうと思っていたのに、帰りはぐってしまい、ついつい他の見学者とともに見学・体験のフロアに行ってしまいました。 その学校は、いくつかのコースに分かれており、その中の「パフォーマンスコース」というコースを見学させてくれるということでした。階段を上がってフロアに行くと、そこにいる高校生たちが、次々に、明るく「こんにちは!」と元気に挨拶してきます。演出じみたわざとらしい歓迎に内心ちょっとうんざり。 教室に入って、少し戸惑いました。どの子も臆することなく見学者である我々の目を直視してきます。どの顔もどこかうきうきした感じ。かすかに流れている音楽に合わせて体を動かしている子もいます。何かやりたくてうずうずしているような雰囲気。 なんか変だぞ? そのうち簡単な紹介があり、ダンスが始まりました。技術的にはやはりプロのダンスとはレベルが違います。でも、なにか生き生きしています。この子たちは踊ってて本当に楽しいのだなと思いました。 途中、先生が子どもたちに話を聞きます。中学校の時不登校だった子がけっこういるそうです。このコースに入ったときはおとなしくて暗かったと目を輝かせてしゃべる子もいました。まわりの子どもたちがざわざわはやし立てます。ダンスを高校で初めてやった人と聞くと、3分の2くらいの子が手を挙げます。だらしない感じはしないけど、なんともリラックスしてファミリーな感じ・・ なんだこの雰囲気は!いい感じじゃないか! そのあと、また、ダンス、それにみんなで歌を歌って聞かせてくれました。 みんなが1つになっているのがわかりました。一人ひとりが自分を表現できているのだなあと思いました。 このパフォーマンスコースというのは、ダンスや演技の技能を教えるのではなく、自分を表現する時間と場を作り、そして、それを暖かく受け入れる空気を作ったんだなあと思いました。 ここにいる子たちは、この場で自分を表現することが楽しくてしょうがない感じ、正直言ってこんなの初めて見ました。ちょっとした衝撃でした。 自分が学校でやっていることは、子どもたちを評価すること。でも、この子たちは、評価されることで伸びたんじゃなくて、自分を出すこと、他人とつながることが楽しくて、それをやったんだなと思いました。 なにか、かつて自分が夢を持って教育に向かっていたときと似たものがここにある気がしました。 自分も、このまま普通のガッコのセンセで終わりたくないな・・・そんな気にさせられる体験でした。
2009.08.06
コメント(2)
-
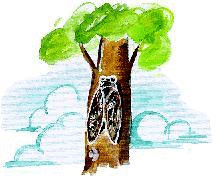
夏山遭難に思う
北海道大雪山系、トムラウシ山で夏山遭難が起きました。 亡くなられた方には心からご冥福をお祈りいたします。 このニュースを聞いて、「元山ヤ」としては、やはり関心があります。 ニュースを聞くたびに「どうして?」「どうして?」と首をかしげました。 報道を聞いて断片的な情報が入っているだけの段階ではありますが、理解に苦しみました。「そんなのあり得ないだろう。」という思いでいっぱいになりました。 夏山で疲労凍死、これはあり得ることです。しかし、ガイドが3人もついているという状況でなぜ起こってしまったのか。高齢者が多くて、全体に疲労しており、気温も低い。雨が降っていたら、迷わず戻るだろ?少なくとも僕ならぜったいそうしたと思います。 それなのに、プロのガイドがなんでそんなむちゃをしたのか。それがどうしてもわかりませんでした。 これは、登山家としての判断以外の要素が、何か作用していたとしか考えられない。 そう感じました。 プロのガイドというのはどんな仕事なのでしょう。 ツアー客の安全を守ること そして同時にツアー客を満足させなければならないということもあるのでしょう。 おそらく後者が大きなプレッシャーになっていたのではないでしょうか。「せっかくツアーで来たのに山に登れないで終わってしまった。」みたいな不満を言われるとつらいでしょう。それに、そういう不満が多いと、ガイドもクビになってしまうかもしれないし。 僕は、山に登りに行って、天候が悪くて何もしないで帰ってきたことはいくらでもあります。頂上を目の前にして撤退したこともあります。山というのはそういうものだと思っています。 でも、登山に商売がからむとそうできなくなることもあるのでしょう。登山ツアーというのは危険をはらんだものだなあと思います。 考えてみると、登山ツアーというのは他にも危険な要素いっぱいですね。 みんな経験不足の人が集まる、知らない者同士のパーティー、装備は心もとない・・・ ただ、こういうことがあったから、山はこわい、山はいやだってみんなに思ってほしくないですね。 ところで・・また山行きたくなったなあ、 、、
2009.07.24
コメント(2)
-

無謀な企画
1学期が終わりました。やれやれです。 解放感がうれしくて、フットサルをやって汗を流してきたら、かえってそれがいけなかったのか、4時過ぎまでねむれません。とほほほ・・ 子どもたちは夏休み。 教師は、しばらくの間は普通の勤務、もちろん子どもがいないのは楽ですが。 話題変わって、「へびが出る!」というのを1学期やっていました。2年生の子どもたちがざわざわうるさいと、手でへびの形を作ります。手で作った首を1回転させて、,口をぱくっとやる間に気づいて静かにしないと「へびに食べられてしまった」ことになり、黒板に×が1つ書かれます。もちろん間に合えば○を書きます。(初めはきつねだったのですが、「きつねのお客様」のイメージに影響するといけないのでへびに変えました) なんか、ただ静かにするとかじゃつまんないから始めたんですけど、なかなか楽しかったです。それでも、しばらく続けてくると、さすがにマンネリしてきます。 そこで、無謀な企画を思いつきました。「先生が毎日お話を書いてくるから、みんなの○と×でストーリーが変わるよ。」という企画です。 つまり、○が多ければ次の日は主人公が活躍するし、×が多ければ主人公が苦しみ、ずっこけた展開になるというわけです。 ストーリーは、コン太くんというきつねが武者修行の旅に出て、いろいろな敵と出会い、冒険んをするという子どものゲームに出てきそうな他愛のない物です。 でも、書いてみると、やっぱりなかなかに悩むものです。○×を展開に反映させようなんて、素人には無謀でした。それに、細かいところをはしょって展開を早くしないと子どもたちは飽きてしまうし、挿絵も描かないとそっぽを向かれます。 そして、もう一つ苦労したのは、戦いの場面。相手を殺すのはしたくないし、血を流したり傷つけるのもなあ・・・それもみんななしで展開していくのは・・・頭が痛い。 学期末の忙しいときに、ああ、なんて無謀なことを始めてしまったのだろうと思いました。 毎日これで睡眠時間を削ってしまいました。 終業式の日はお休みにしたら、けっこう何人もの子に「先生、今日はあれないの?」と聞かれました。けっこう楽しみにしていてくれたのだなあと思います。 大変だったけど、この無謀な企画、それなりにおもしろかったかな?と思います。 僕がこういう「おあそび」をやりたがるのは、「まじめ」「一生懸命」を至上の価値として尊ぶ学校の風潮(もちろんこれはしかたのないこと)への反発が、自分の中にあるのかな?と思います。
2009.07.17
コメント(2)
-
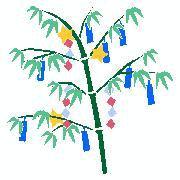
「井戸の底」の思い出
僕は、今年の夏は、ベーシックエンカウンターグループに参加したいと思っています。僕はこのベーシックエンカウンターグループ(BEG)というのが好きです。 いったい何をやるのかというと、10人ぐらいの見ず知らずの人と、いっしょのグループを作り、それに、ファシリテーターという心理の専門家がついて、3泊4日ぐらいの合宿をやるのです。たいていは、都会からは離れた宿舎で行われます。その間は、何をやるかというと、部屋の中で車座になって、2~3時間、テーマを決めず、何かを話すのです。たいていこういう「セッション」を午前、午後、それに夜行います。たまに散歩したり軽いスポーツで汗を流すこともありますが、ほとんどこのセッションを繰り返します。 こう書くと、ずいぶんかったるいことをするんだなあと思う人が多いでしょう。僕もそう思いました。実際、今でもそう思います。セッションの中では、1時間以上もみんな黙ったままの沈黙が続くこともあるのです。やってるさいちゅうに、「いったいなにやってんだか?」と思うこともあります。 それでも、BEGはいいんです。 僕が最後に参加したBEGは、河口湖のそばの大学寮で行われました。 セッションが始まり、いろいろな話が出ました。もちろんみんな、世間話や週刊誌的な雑談をするために集まったのではないという意識があるので、自分の中の気持ちのこだわりや、他人の話に触発された自分の経験談や思いなど、会話を通じてだんだん自分の内面を掘り起こしていきます。 ただ、このグループでは、心理的に深く入ろうとする人がいる一方で、そういう雰囲気に水を差す人もいました。お互いの話しに共感してもっと自分のことを語りたくなるようなときに、「そういうのは私はわからない」とか、「心理の人はやたらそういう見方をしたがるけど、私はそういうのは好きじゃない」といったことを言って、グループの雰囲気をもり下げます。 そのうちに、「こんなことをやってもあまり意味がない気がする」と言い出したり、または一般的な雑談をしようとします。 グループの相互の気持ちが深く行こうとするのに抵抗しているようです。そして、その人たちの「妨害」に対する反感を持つメンバー、双方をなんとか納得させ、グループをまとめようとするファシリテーター。 2日目の夜には、僕自身、もういやになってしまい、セッションをぬけてしまいました。 3日目の午前のセッションでは、もうみんな疲れてしまい、停滞した雰囲気でした。 でも、その中で「自分の心の中にあるものが知りたい。でも、深くまで行ったら、忘れていたトラウマを呼び覚ましてしまうかもしれない。自分の心の中深くに入っていくのって、井戸の底を探るような怖さがある。」 と、僕が最初の日に言った言葉をだれかが持ち出しました。 そして、セッションが終わるとき、ファシリテーターが、「疲れたから、午後はもう休んじゃいましょう。井戸の底・・・うん、井戸の底じゃないけど、みんなで風穴を見に行きませんか?」と提案しました。 午後はセッションお休み。みんなで富士の風穴を見に行きました。ひんやりすずしい暗い洞窟の中。わいわい楽しみながらも、このとき、何かこのグループに変化が起き始めていました。 風穴を見たあと、みんなで喫茶店でお茶を飲みました。みんなわいわい雑談で盛り上がる店の隅で、ファシリテーターの人が、グループに抵抗していた人の話をしきりに聞いていました。 夜のセッション、突然グループの空気が変わっていました。あれほど抵抗していた人が、自分の気持ちを語り出したのです。こうなると、お互いの話しに次々に刺激され、自分の心の深くにあるものが次々とわき上がってくるのです。そして、それを言葉にする。 この仲間といっしょだから、向き合える、このグループにいるから、自分の「井戸の底」に下りることができるのだなあと思いました。 お互いの共感、一体感、これは感動という言葉も超えたものでした。 翌日、午前のセッションが終わり、グループは解散、お別れになりました。しかたがないのだけれど、いつまでもここで、この人たちといたいという思いでいっぱいでした。 帰りに何人かを車で駅まで送りました。 握手をして、別れると、僕は車のエンジンをかけてその場を去りました。運転するうちに涙があふれてきて、思わず車を止めて、しばらくボッとしてました。 こういう思いを味わえるのは、やはりBEGだけなんですよね。
2009.07.02
コメント(2)
-

金のおのと正直者
先日、2年生の道徳で、「金のおの」というのをやりました。話の内容は、もうすでに知っている方がほとんどでしょう。 正直者の木こりがじぶんの斧を泉に落としてしまうと神様が出てきます。神様は金の斧を持って、木こりが落としたのはこのおのかと聞きます。木こりはそれを断り、その次に持ってきた銀の斧も、それは自分のではないと断ります。最後に鉄の斧を持ってきたとき、それは自分のものだと言ったので、褒美にすべての斧をもらったという話です。 「みんなだったら金の斧くれるって言ったらほしいよね。」 そう問いかけてみると、意外にも「いらなーい!」という子が大部分。聞いてみると、鉄の斧がないと木こりは続けられないから、鉄の斧がいい、鉄の斧があればいいんだという意見。 おやおや・・・「金の斧を売ったら、鉄の斧は100本も買えるよ。それに、ごちそうもたくさん食べられるし、ハワイ旅行も行けるよ。そうだ、Wiiも買えるし、Wiiスポーツリゾートも買えるよ。そのほかゲームのソフト全部買えちゃうよ。」こう言ったら、子どもたちの気持ちはにわかに変わってきました。「やっぱり金の斧ほしいでしょ。」「ほしい!」こうこなくちゃいけない。 さて、ここでこの授業の核心部、「この木こりは、なんでそれはわたしのではありませんなんて、言ったんだろうね。」「木こりは正直だからだと思います。」「そうか、正直なんだね。でも、金の斧はほしかっただろうにね。なんで正直に自分のじゃないなんて言っちゃったのかな?」 ここで出てきた子どもたちの考えは、ちょっと考えさせられるものでした。「それは、神様だから、ウソをついてもわかっちゃうと思ったからだと思います。」「おなじでーす!」 なるほど、子どもたちはこう考えるのか・・子どもたちは「正直」というのをこうとらえているのか、と、ちょっと刺激的な発見でした。「じゃあ、神様にぜったいばれないんなら、木こりは金の斧をわたしのですって言っただろうか?」 ここから正直とはなんだろうと、子どもたちに考えさせることができて、なかなかおもしろかったです。 低学年の子どもは「正直」です。 ばれるからウソをつかない、あるいはもしもばれたら自分がとても不利な立場になってしまう・・・これが万人の「正直」の起源なのではないでしょうか。そういうものがやがて内面に取り込まれていき、「良心」と呼ばれるものになっていく。 大人だって、心をほんとに丸裸にしちゃったら、「ばれない保証があるならウソついてもいいや!」というところに行くのではないかな?という気がしてしまいます。 良くも悪くも低学年の子どもたちは正直で、人間の素の部分を見せてくれるなあと思います。
2009.06.23
コメント(4)
-
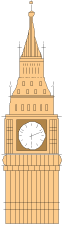
ヤゴのいる教室
生活科でヤゴ取りをしました。 「ヤゴ救出大作戦」と銘打って、プール掃除をする前の汚い水の中で生きているトンボの子どもを救ってあげようというのです。 2年生の子供たちは、最初は汚いプールに入るのをためらっていましたが、ちょっと入るともうなれてしまって、大喜びでヤゴを取りまくります。 泥の中にあみを突っ込んでかき回すと、おもしろいようにうにょうにょ動くヤゴが取れます。 どちらかというと救出というよりは漁に近い感覚です。子どもたちはみんな面白がってキャーキャーいっています。 みんな大漁(?)取りまくって家に持って帰りました。 半分は学級で飼うことになりましたが、すぐに嫌になりました。「先生、共食いしてるよ。」 こんなご報告が何度も来ました。ヤゴは餌が足りないとすぐに共食いしてしまうのです。こんな生態を子どもたちに見せるのは教育的じゃないなあと思います。そういう現実を子どもたちに見せるのはいいことだなんて書いてあるものもありますが、個人的にはやはり抵抗を感じます。だって、生き物教材はかなりの場合、擬人化して扱ったりしますから。(例えば、「ひまわり、水やりしてもらって、きっとありがとうって言ってるよ」とか)感受性の鋭い子なんかは、傷ついてしまうと思います。 でも、そんなこっちの心配をよそに、子どもたちは平気な様子。 案外たくましいというか、感じないというか・・・ ヤゴを飼うのに厄介なのは、餌の調達です。イトミミズなど、それも生きているのでないと食べないという贅沢ぶり。 上州屋に行って、釣り用の赤虫を買ってきて、やりました。赤虫って、ウニョウニョ動いてはっきり言って気持ち悪いです。 ヤゴたちは喜んで食べます。「あ、食べてる!」 と、それを見ている子どもたちも大喜びです。子どもたちの表現を借りるなら、「そうめんを吸い込むよう」に食べるのだそうです。僕もこの目で見ました。たしかにそうですね。 餌を食べてくれて、共食いをしないでくれるならこちらとしてはうれしいのですが、どこか複雑な気持ちになります。一つの命を生かすために他の命を潰していく・・・それを人間の手でわざとやっているのだと思うと嫌な気持ちになります。(花壇の草むしりをしているときもこんなことを考えるときがあります) 幸いにというか何というか、子どもたちはそこまで考えないようで。 そういう子どもたちの考えの浅さに、正直救われています。 何はともあれ、育てていたヤゴも少しずつ羽化して飛び立っていきます。 教室でバタバタ不慣れな様子で飛び回っているトンボを見つけて子どもたちが大騒ぎしていました。 みんな無邪気に大喜びでした。 命を救っていいことをしたという気は少しもしませんが、「ああ、育ったんだな」って感じ、ぼくもちょっぴりうれしくなりました。
2009.06.14
コメント(4)
-

ウソはともだち
子どもが友達といじめたとか、ものを取ったとか、あるいはお金がらみの問題を起こしたとき、まずは事実を確かめるためにじっくりと子どもの話を聞きます。(実はきのうも夜8時過ぎまで子どもと話をしていたのですが) 子どもの話を聞きながら、つじつまの合わないところとか、状況が不自然なところ、話す表情のおかしなところとか、聞き返し、聞き返し、だんだん真実にせまっていきます。子どもを信じる心は大切ですが、こういうとき、ある程度疑ってかかることも必要なようです。 言うと叱られるとわかっていることは、できるだけ言わないでおきたい、あるいは、じぶんの責任を少しでも軽くしておきたいという方向に行くのはやむを得ないことだと思います。子どもでも大人でも。 ただ、こちらが本当に心配している、親身に思っているということが伝わると、あるいはごまかし続けることがむずかしいと思うと、正直に話すようになります。(子どもが正直に言っているときは、不思議に雰囲気でわかるものです) ところが、中にはあくまでしらを切り通す、見え見えのウソでもぎりぎり追い詰められるまで真実をしゃべろうとしない子がいます。まるで本能的に言っているのかと思うような、反射的なウソのつきかたをする子もいますね。 こっちはいい加減腹が立ちます。思わず怒鳴ってしまうこともあります。どっと疲れてきて、やりきれない思いになります。 子どもが信じられない、そんな気持ちはなんともいやなものです。 そんな子たちに今まで何度も出会ってきました。 そういう子たちは多くの場合、ある共通したことを感じます。 それは、親御さんが、おかあさん、おとうさん、あるいは両方、子どもにひどく強圧的な態度を取るか、あるいは、キレて激しく怒る傾向が見られる場合が多いということです。感情にまかせて子どもに怒りをぶつけていたり、自分の気分やつごうで子どもに当たり散らす未熟な親御さんに多いように感じます。 まあ、はっきりと統計を取ったわけではないのですが・・・ 子どもたちは叱られることだけはなんとしても避けようとしているかのようです。そのためになりふり構わずウソをつくことで「防衛」しているように感じます。 正直に言ったらこっぴどく叱られるだけだと思ったら、本当のことは言わないでしょう。 そういう子にとって、親に叱られるのは「災難」としか感じていないのではないでしょうか。 きつく叱るのもは時には必要でしょうけど、あくまで、「自分のことを思って叱っているんだな」と子どもが感じることがなければ、それはただの「災難」でしかないのかもしれません。
2009.06.03
コメント(2)
-
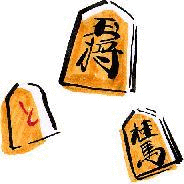
帝国が揺らぐかも?
今、仕事その他でメインで使ってるパソコンは、中古のダイナブックSS、OSはウインドウズXPが入ってます。 最近、Ubuntu Linux(ウブントゥ・リナックス)というOSを入れて、デュアルブートにしてみました。使ってみると、この無料のウブントゥというやつ、意外に使いやすく、びっくりしました。ほとんどウインドウズと同じような感覚で操作できます。プリンタ、無線LANまでかんたんに認識してくれるし、細かい諸設定もやりやすい。動画も見られるし、ウインドウズでできることはだいたいなんでもできます。 ちょっと前のリナックスといえば、CDひとつマウントするにしても、英語のコマンドをちまちま打っていかなければならなかったし、プリンターなんて、中古のものしか認識してくれませんでした。最初からサーバーとして使うことしか頭になくて、個人で使うメリットなんかほとんどないといった代物でした。 ところが、このウブントゥは、ちゃんとデスクトップとして使うことを想定して作られています。初心者でも使えるようにという配慮もけっこう随所に見られます。 「ソフトさえそろえば、ウインドウズなんかいらなくなるかも」 なんていう気分にさせられます。 でも、この、「ソフト」が大きいのです。ビジネスの圧倒的スタンダードになってしまった、マイクロソフトのワード、エクセルが、ウインドウズのシェアを支えているといってもいいのではないでしょうか。パソコンを扱う人の多くが、仕事でこのオフィスソフトを使っているのです。 リナックスにも、「オープンオフィス」というすばらしいビジネス用ソフトがあるのですが(しかも無料です)、ワード、エクセルのファイルを読み込むと、微妙なずれが出ます。互換性はまだ完全とはいえません。 ところが、ウインドウズ用ですが、ワード、エクセルのほとんどコピーといっていいようなソフトが出ています。(値段は半分以下)互換性もほぼ完全だし、外見もそっくり、ロゴまで似ているというものです。もしもこういうソフトがlinux版で出たら、(言い方を変えるなら、ウブントゥのようなソフトを見て、これに乗ってビジネスをしようというソフト会社が出てきてくれたら)ウインドウズは不要になってしまうのではないでしょうか。 もしも役所で使っているパソコンで、ウインドウズ、マイクロソフトのオフィスソフトを完全に使わない環境で、OSをリナックスにして、廉価なオフィスのコピーソフトを導入したならば、どうなるでしょう。100台パソコンを使っているとしたら、これだけでマイクロソフト株式会社に支払っていた多額のお金のうち、ざっと200万円は節約することができるでしょう。 もしもこういう環境が普及してくると、数年ごとにOSとビジネスソフト、それにパソコンを買い換えねばならないように仕向けるマイクロソフトのあこぎな商売も、どうどうとはできなくなってくるのではないでしょうか。 かつてはパソコンといえば、NECのPC98シリーズと、ワープロソフトの一太郎の天下でした。それが今は時代が変わって、消滅、あるいは衰退しています。昔は考えられなかったことです。 今、絶対的なシェアによる「マイクロソフト帝国」の支配も、将来同じ道をたどるかもしれません。 そうなることをぜひ期待したいですね。
2009.05.18
コメント(0)
-

久々のコンサート
今日、コンサートに行ってきました。ずいぶん久々。カーラ・ボノフ聞きに行ってきました。昨日は一日臥せっていたというのに・・・カーラボノフといってもあんまり知られてないと思いますが、70年代後半に出てきた女性シンガーソングライターで、30年以上のキャリアがありながらわずかアルバム5.6枚という寡作です。マイペースなところがこの人の魅力のひとつでもあると思います。そして、いくつになっても清楚な雰囲気は変わりません。僕にとって、いわゆる「アイドル」のような存在かもしれませんね。(もうとっくに50は超えているはずなんですけど) 今日行ったのは、コンサート会場と言うよりは、ライブハウスという感じで、「ワンドリンク」といわれてとまどいました。ほんの数百人の小さな会場、息子の合唱祭を聞きに行ったときよりも、もっと間近にカーラの顔を見て、歌声を聞けました。 こういう小さいところで歌を聴くと、声がマイクを通してアンプから聞こえる強い音となってしまうのがすごく残念です。 だから、ピアノで穏やかに弾き語りするようなナンバーの方がぐっと来ました。 思えば、初めてコンサートに行ったのは、中三の時、シカゴのコンサートでした。「コンサートのチケット代でアルバム買って千円おつりが来るよな・・・」なんて思ったのを覚えています。 でも、コンサートって、なんとも言えない興奮、胸の高鳴りがありますよね。昔のドゥービーブラザースの時のような、頭の中が真っ白になるようなカタルシスっぽいのとは違うけど、静かだけど、CDにはない、「雰囲気」を楽しんできました。 会場には、僕と同じような、中年過ぎのおじさん、おばさんがたくさんいました。僕と同じような思いを持っていたのかもしれません。 もっとも、意外に若い人もけっこういましたが。 やっぱり何度聞いても「Water is wide」は名曲だなとおもいました。
2009.05.11
コメント(0)
-

1日休むと
連休、疲れが出たのかひたすらダウンの日々。かったるくてかったるくて、慢性疲労症候群かななんて本気で思ったりして。 連休が終わって、なんとかなるかと思ったら、朝起きて、ダメ。 めまいがする。体が重い。やむなく休みをもらいました。 校長に電話したら、なんかやな感じ。この校長、年休取るというといつもいやな顔をする。 果たして、今日、学校に行って校長のところにあいさつに行くと、「きのうは大変だったんだ。行事はあるし、年休者は多いし、休むタイミング悪いんだよ。」 と言われました。 具合が悪いのにタイミングもクソもあるかよ・・・と思いつつ、がまんしました。でも、次言われたらキレそうな気がします。 こっちのことを考えてくれているなと思うと、こっちもそれに報いたいなと思うもの。こういう風に言われると・・・どこか投げやりな気持ちになりますね。もっとも子ども相手の仕事だから、投げやりになるわけに行かないのですが。 今までいましたね。この人のためならとことんがんばっちゃおうって気持ちにさせられる上司が。そういう意味では、今はほんと「がまん」の時かも。 それにしても、病み上がりで出勤すると必ず待っているのが、ノート、プリントの山。マルつけに夜遅くまでかかってしまいました。残ったプリントは持って帰りました。 来週はなんかいいことあるといいな~
2009.05.08
コメント(4)
-
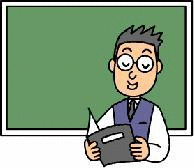
ふやけた子ども
きちんとした厳しい担任の先生が、クラスをびしっとまとめます。 ところが、その次の年、担任の先生が代わると、クラスが急に乱れ出す・・・そんなことってよくあるように思います。 このとき子どもに起こっている変化ってなんでしょう。 子どもの気がゆるむ 子どもが甘える 子どもが先生をなめる 子どもがだれる こういったことがあるかもしれません。 でも、僕はしばしばこんな印象を持ちます。「子どもがふやけてる」 「厳しい先生」といってもいろいろあります。おこるとこわい先生、口うるさい先生、宿題忘れをすると執念深くやらせる先生、などなど・・ でも、子どもにとって本当にこわいのは、きっとこういう先生でしょう。 自分の意に沿わない、自分の方向性に従おうとしない子どもには、様々な形でプレッシャーをかけ続け、「私の思い通りになろうとしないなら、1年間針のムシロよ」という無言のメッセージを送る先生。 こういう先生に担任された子どもたちは、嬉々として、顔を輝かせて先生の望む子どもになって行きます。そうなることができない子どもたちは、先生に反抗して、先生の要求をある程度拒絶することで現状と折り合おうとします。しかし、それができない子どもたちの場合、あるいはそれをゆるさないほど先生の圧力が強い場合は、子どもは、自分を「フリーズ」させてしまいます。 先生が要求することに自分がどう感じるか、本当は自分がどうしたいのか、嫌悪感や好み、嗜好など、「何も感じないように」してしまうのです。それは、兵士が戦場で、かわいそうだと思う感情や良心を感じないようになってしまうのに似ています。自分の感情をフリーズさせて、感じないことで、逆らうことのできないいやな先生と1年間うまくやろうとするのです。もちろん、無意識に。 ずっと前の話ですが、おもしろおかしいこと大好きな、しょうがないわんぱく坊主A君が、S先生に担任されて、おとなしいいい子になってしまったのにおどろきました。S先生好みの、みんなで歌を何曲か歌って、おとなしいゲームを織り交ぜた、まことにお行儀のよいお楽しみ会に、A君がいい子で参加していたことに、違和感、というよりは気味の悪いものを感じました。 また、業間の休み時間、子どもたちは外に出ることもせず、いやな顔もせずにあたりまえのように係活動をしていました。あのA君も。 翌年、その先生のあと、A君は荒れました。荒れるというよりは、わけがわからない感じ。まるで幼くなったみたいで、フニャフニャして収拾がつかない感じでした。A君の他にも何人かはそうでした。 A君は、S先生に担任された1年間、自分をフリーズさせていい子にしていました。そして、この先生から離れて「解凍」したのでしょう。そして、解凍したA君の心は「ふやけた」感じそのもの。S先生との1年間、A君の心、はフリーズさせていたからぜんぜん成長していなかったのだと思います。 先生の要求、それに対して自分の内面の感情があり、時には文句を言い、時にはサボタージュし、時には渋々従う。また時には先生の気持ちもわかり、道理もわかり、自分で納得してそれをします。いろいろな場面、いろいろな形で先生や学校生活と自分の間でうまく折り合いをつけ、時には妥協しながらうまくやっていく、そんな作業を繰り返すことで、相手や自分を理解し、社会性を身につける、それが成長でしょう。 フリーズしていた1年間、彼は全く成長がなかったのだと思います。 全部が全部じゃないけど、「力のある先生」「学級経営のうまい先生」の中の何パーセントかは、子どもをフリーズさせるだけの先生であるように思います。 先生が、自分の指導を子どもに徹底させようとするのはいいと思います。やはり教育は先生から子どもに発信するという要素は大きなウェイトを占めるものです。だけど、そういう先生ほど、人間として、どこか弱いところやぬけたところ、穴がないと、子どもにとってつらいと思うのです。
2009.04.25
コメント(4)
-

ローソンの謎
再開第一弾は、いきなり教育と思いっきり関係ない話題から。 ぼくが今研究していること、それは「ローソンの看板」 何をいっとるんじゃとおもわれる方が大部分でしょうけど、あの、コンビニのローソンの水色の看板には二種類あるのです。知っていましたか? 水色の地にLAWSONと書かれていているのはどちらも同じなのですが、その下の方に注目すると、明らかに二種類あるのです。 ひとつは、水色の下の方に紺の細いラインが入り、そのすぐ下にピンクのラインが入り、一番下に水色のラインが入る「3本ラインタイプ」。 もう一つは、水色の下の方が白くなっていて、そこにピンクの細いラインが1本だけ入っている「1本ラインタイプ」(ぼくが勝手にそう名付けました) 同じローソンなのになんでそんな違いがあるのか、そんな小さな違いを作ってなんの意味、メリットがあるのか? それについて長い間考え続けてきたのですが、今のところ、店舗の新旧ではないかという説が有力です。どうも3本ラインタイプの方が古くからある店が多いようです。しかし、古いはずなのに1本ラインタイプの店もあり、謎が多いです。 あっちこっちのローソンをめぐり、看板を観察しているうちに、新たな謎が浮かび上がってきました。それは、3本ラインタイプの看板の一番下の水色ラインについてです。昼間見ると、明らかに水色をしているのに、夕方、看板のバックライトがつくと、なんと、水色でなく紺色に見えるのです。つまり、夜見ると、看板は、下の部分は紺、ピンク、紺に見えるのです。ミステリーだ! ローソンは、奥深い・・・・! しかし、それにしても妻をはじめ周囲の人にこの発見を話しても、ほとんど感激する人がおらず、「ああ、そう~」と、話を合わせてくれているのが見え見えという人ばかりなのが残念です。 今度ローソンの店長に聞いてみようと思うのですが、聞いてしまったらつまらないという気もあります。今しばらく研究してみようと思います。
2009.04.13
コメント(8)
-
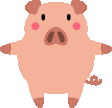
再開します
長らくお休みしていましたが、仕事の方がちょっとおちつきましたので、またブログ再開したいと思います。「教育相談」に狭く限定しないで、いろんなことを書いていこうかなと思います。
2009.04.12
コメント(4)
-
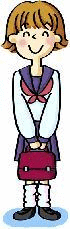
しばらくおやすみ
このブログ、しばらく続けてきましたが、やっぱり最近ちょっと忙しくて、更新が滞りがちです。そんなわけでしばらくの間休止しようかなと思います。まあ、迷惑コメントはしょっちゅう来ると思いますので、たまにのぞきに来て消してこうかと思ってますが。また、そのうち少し余裕ができたら再開しようと思ってます。それではまた!
2008.10.19
コメント(6)
-

学力テストの結果公開?
大阪府の橋下知事が、学力テストの結果、市町村ごとの得点を公開しろとさかんに言っておられるようです。 ブログや掲示板では賛否両論、と一応はなっているのですが、じつは賛の方が圧倒的に多く、おどろいています。まあ、こんなものなのかなあという感じです。 橋下知事は、就任以来、財政、教育、福祉その他なんでもやることが一貫しています。問題点を明確化・単純化 → 一喝 → 締め付け → がんばらせる → 業績を上げるという手法ですね。 一喝の前に(世論を煽る→バッシング)というのが入るかもしれません。 この手法、ちょっと無理があるなあと感じます。 締め付けることで業績を上げていこうというやり方は、企業のモーレツ社長のやり方です。 また、軍事史上では、部下を締め付けて無理にでもがんばらせ、大きな成功を収めた将軍はたくさんいます。兵士をものすごいスピードで行軍させることで戦略的な偉業を成し遂げたナポレオン、それからちょっと落ちるけどロンメル将軍や羽柴秀吉、または義経やカエサルなんかもそうかもしれません。 部下を叱咤し、無理を強いて無理矢理がんばらせても、最後にそれで大きな実績を上げれば、無理を強いられた部下たちも納得します。達成感があります。次も、また無理をしてでもやってみようという気になります。 企業や軍隊は、それができるのです。なぜならば、単純な達成目標を設定することができるからなのです。企業ならば大きな利潤を上げること、軍隊ならば戦いで勝利を挙げることです。目標がすっきりしているのです。 ただし、行政や福祉、教育ではそれを単純に設定することがきわめて難しいのです。役所だったら、より行き届いたサービスを提供することと、効率化、ローコスト化が、しばしば正反対、矛盾することになります。どちらもなんて、現実的な目標になりません。 教育もそうです。学力テストの平均点を上げることと、子どもの個性に対応すること、子どもが楽しい学校にすること、このどれかだけを目標にして、他を切り捨てるなどできません。 もしも、学力アップを絶対目標にして、締め付けをしていったなら、土日なく部活指導にがんばっている先生や、深夜まで生徒指導に奔走している先生方は「やってられない」です。そんなことやめて、補習や教材研究しようと思うでしょうね。子どもの学力だけでなく、その子の個性や問題行動、家庭での生活や個人的悩みなど、もろもろすべて包含してアバウトに「教育活動」と呼んでしまっているのが今の学校なのです。橋下知事のしようとしている「問題点の明確化・単純化」は、このよい意味でのアバウトさをなくしてしまうでしょう。 やっぱりこの人のやり方には無理があると思います。 あと、雲の上から教育委員会をクソ呼ばわりする前に、学校現場にいる先生ともっと話してほしいですね。マスコミ相手にパフォーマンスする時間があったら。少なくとも、大阪の教育、学校の現場を、自分の足を運んで、じかに見て、考えてほしいですね。1日でも学校のセンセやって、子どもとつきあってみていただきたいですね。数字や理屈で表せないものが少しは見えてくるんではないでしょうか。 学力テストの平均点を市町村ごとに公開したなら、次は絶対に学校ごとに公開ということになるでしょう。なぜなら、市町村の差よりも、学校の差のほうがはっきり出るでしょうから。 でも、この「差」が何を意味するものなのか?市町村、学校間の「努力の差」なのか? おそらくは、「地域の差」「家庭の差」が表に出てきてしまうのではないでしょうか。 学校で勉強することはすでに塾で学習してしまっているという子が半数を超える地域と、放任が普通で、連絡帳に目も通してくれない親が大半の地域、この差がはっきり学力テストの平均点に出てしまうのではないかと思えるのです。 学力テスト平均点を公開するのはなんのため?
2008.10.04
コメント(0)
-

ソーランでバトル
最近すっかり更新をサボってしまっています。 原因の一つは、今年学校を移って、教育相談、特別支援教育と縁が切れてしまったことがあります。今まで校内で教育相談だよりというのを出していて、その記事をブログにも載せていたのですが、それをやめてしまったので、教育相談関係の記事が減ってしまったというわけです。 いっそ、「教育相談」という看板を下ろしてしまおうかな・・・ということも考えていますが。 というわけで、今後も教育相談関係の記事は少ないと思います。 さて、運動会が終わりました。練習は天気に恵まれ、順調に行えたのですが、本番は雨!あちゃー・・・という感じです。 今年は4年生、私はダンス、ソーラン節の指導を担当しました。 ダンスでソーラン節をやろうということは夏休みの初めの頃に担任で相談して決めました。夏休み後半は、ビデオを見ながら毎日踊りの練習をして、腰が痛くなってしまいました。夏休み終わり頃には衣装のことまで決めてしまいました。4年生にはちょっと速くて難しいので、細かい動きはちょこちょこ改造しました。 学年主任の先生は、なんでも仕事を早く進めたがる人で(ぼくの正反対)、練習を始めて3日目にはもう隊形移動について詳しく計画を出すようせっつきます。 実は、ここでぼくにはすごく引っかかっていることがありました。それは、ダンスについてすべて教師が決めてしまってきたことです。能率優先でなんでも教師が決めてしまうのでは子どもは育ちません。少しでも子どもに任せる、子どもたちの意志にゆだねる部分がなければならないと感じました。 そこで、隊形を提案した時、学級の位置は子どもたちにクラスごとに希望を取って決めさせようということを提案しました。 予想通り、学年主任の先生には猛反対を受けました。この先生は、子どもがどうのよりも、行事など、やたらきれいに、きちんとしたものを見せるのにこだわる人です。「そもそも、子どもに聞いたら、真ん中がいいというに決まっている。そんなのは教師で決めてしまった方がぜったいいいでしょ。」 でも、ここは譲れません。「それはわかりません。真ん中は最後の隊形変更の時、移動距離が長くなるし。子どもに考えさせてみませんか。」「そういうものは子どもに決めさせることじゃなくて教師が決めることじゃないの。」「いや、なにか子どもに決めさせないと、先生のいうとおりにやっただけになってしまいます。それでは子どもが育たない。」 そのあと学年主任の先生は、指導のやり方や、細かに変更を伝えなかったことなどの不満を言ってきて、それに対して私の方も、今まで子どもの意志を顧みなかったことや踊りの変更など細かに伝える時間を取ってくれなかったことについて反論、最後はなじり合いの激しいバトルになりました。 教師同士でこんな激しいバトルをやったのは10年ぶり?たまにはこういうのもいいものですね(!?) 結局ぼくの意見が通り、子どもたちがクラスで話し合い、どこの場所がいいかを選ぶことになりました。(それ以来、学年主任の先生が、心なしかこちらを向くのを避けているように感じるのは気のせいでしょうか) できることなら、ダンスをやる前に3つぐらい候補を出して、子どもたちに、「さあ、君たち、どれがやりたいか決めよう」というところからやるのがぼくの理想です。 今の学校、能率優先で、高学年になっても教師主導で決めてしまうことが多すぎるなと感じぶるのはぼくだけでしょうか。 教師のいうとおりにやってうまくできたことは、子どもの自信につながらないし、子どもを育てることにもなりません。 親から心理的に独立して自分を確立することに失敗してしまい、引きこもりになってしまった青年のケースをなぜか思い出してしまいました。
2008.09.21
コメント(4)
-

キャンプでのこだわり
何かこだわりを持っている人っていますね。 まわりの人から見るとどうでもいいようなことに意地になったり、ムキになったり、あるいはやたらと選り好みをしたりと。 ブランドにこだわる人、いますね。アディダスの3本ラインの入ったサンダル(スリッパ)を履いた人をよく見ますけど、ぼくなんかは安いのでいいなあと思ってしまいます。性能的に変わらないでしょうから。 ぼくの母なんかは同じものでもブランドにこだわります。「やっぱり違うわよね。」とかいうことをよく言ってます。ぼくは母のこの性質は全く受け継ぎませんでした。ノーブランド大好きです。 うちの妻は、「バトミントン」と聞くと、「違う、バドミントンだ」と言います。ぼくなんかは「どっちでもいいんじゃないの」と言っても、本人にとってはどうでもよくないのだそうです。 高校時代からバトミントン、いや、バドミントンをやっていた妻は、国体やインターハイなどであまり注目されないマイナーなスポーツであることに、悔しい思いをしてきたそうです。テニスは派手で注目されるのに、それに比べてバドミントンは・・・ 「高校野球なんかは全試合全国に放送される、同じ高校生のスポーツなのになんでこんな待遇に差があるんだ!」と言っていましたが、これには同感ですね。 さて、妻のことはさておき、自分自身、何にこだわりがあるのだろうと考えてみました。 ぼくのこだわりは、おそらく「キャンプ」だと思います。 ぼくは、もともと山をやってたので、荷物は背中に背負うのがほんとだという意識があります。背中に背負えないほどのものは最初からキャンプに使わなくていいという感覚です。基本的にオートキャンプはどこか「チョンボ」という気がしています。 オーストラリアを旅行する機会に恵まれ、オーストラリアの広さ、自然のスケールの大きさ、人口密度の低さを知ると、あそこではオートキャンプもありなのかなと思えました。 でも、狭い国土、人間いっぱいの日本では、オートキャンプはやたら人ばかり。休みの日なんかひどいもんです。テントの張り綱に引っかからないように歩くだけでも一苦労。密集の住宅地をそのまま移してきたみたいです。キャンプに人混みはいらない。シャワーもいらないから、もっと静かな自然を味わいたいとぼくは思ってしまうのです。 山でビバークした時、本当に自然の中にいる感じがしました。自分の中では「自然の中にいると実感できる」これがキャンプですね。 ぼくの中ではテーブルやバーベキューキットなんかは「邪道」。ステンレスのコッヘル(キャンプ用の鍋)なんか重くて使えない。アルミに限ります。(これはかなりのこだわりですね) でも、最近、オートキャンプじゃないキャンプ場ってほとんどなくなってしまいました。すごく残念です。 最後に一つだけ。 ここに書いたのは、あくまで個人的なこだわりですから、他の人の楽しみをどうのこうの言うものではありません。不快な思いをされた方がいたらお詫びいたします。
2008.08.26
コメント(0)
-

オリンピック代表敗退
オリンピックで日本男子サッカーは負けてしまいました。3戦全敗で勝ち点1も取れずに予選敗退でした。 正直言ってがっかりです。個人的にはオリンピックの楽しみの半分が終わってしまった感じです。 期待して応援していた人たちは、代表を応援することに注ぎ込んだ心のエネルギーが大きいほど、負けてしまうとその「エネルギー」の処理に困ります。しばしば持て余したエネルギーが暴走して、フーリガンみたいになります。物を投げたり、相手にけんかをふっかけたり、まわりの物を壊したりします。 フーリガンのようにならないとしても、相手チームのプレーを汚いとかいって中傷したり、審判の判定に攻撃を向けたりしてエネルギーを発散する人もいます。 それもしない人は、攻撃を自分の代表に向けます。自分たちが応援していた代表選手を、あるいは監督を厳しくこき下ろします。さらに「日本なんて所詮こんなもんだ」「日本はだめなんだよ」という自虐的な方向に攻撃のエネルギーを向けます。 「辛口コメント」とかいっても、初戦は自分の失望や怒りをぶつけているだけなんだと思って見ています。 今回のオリンピック、一昨年のワールドカップの時よりもやや冷静なコメントが目立ちます。それだけ初めから期待が低かったということなのでしょうか。正直言って、ぼくも「もしかしたらいいかも、でも、まあきついだろうな」という風には感じてました。 ぼくがテレビで見たのはアメリカ戦と、最終のオランダ戦の前半だけでした。 ぼくが見た感じでは、悪くはなかったなという印象です。特にアメリカ戦、運動量では勝っていたし、つないでえぐってという形をチームとして意図的に作れていたなと思いました。いい形ができてきて、リズムが良くなってきてからの、ワンチャンスからの失点。リズムがいい時に1点でも決められていたら、全然違っていたのではないでしょうか。 「~たら~ればを言ってもしょうがないだろ」と言われそうです。 たしかに今更言っても後の祭り、結果が変わるわけではありません。しかし、それを承知の上で「~たら~れば」を言ってもいいスポーツだと思うのです。サッカーは。 サッカーは、特に点が入りにくいスポーツなので、攻めて攻めて攻めてもカウンター1発で負けるということも結構あるのです。「マイアミの奇跡」の他、歴史に残る番狂わせも、挙げていったら枚挙にいとまがありません。 ポコンと入った1ゴールが大きな流れを作ってしまうことがよくあるのです。この辺、バスケットボールやバレーボールとは全然違うのです。 そういう意味で、やっぱり1本決まっていれば・・・と思います。 ただ、まだまだ日本サッカーは世界には追いついていないという現実はたしかでしょう。焦らないで応援していきましょう。メキシコだって、世界大会でいつも上位に行くようになるまで何十年もかかっているんですから。
2008.08.15
コメント(0)
-
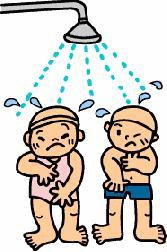
夏休みのプール指導
夏休み、プール指導がありました。 この夏休みのプールというのがどういう位置づけなのか、いろいろな考えがあります。先生によってもとらえ方がいろいろで、「やる気のある子の泳力をのばしてやろう」という先生もいれば、「授業じゃないんだから、遊びでいいんじゃないの?」という先生もいます。 ぼくはどちらかというと後者なんですけど、でも、泳力別に分かれての時間になんかなると、ついいっしょうけんめいになってしまうこともあります。 かったるいけど、子どもが楽しそうに来ているから、まあ、いいかな・・とか思いながら数回の指導に参加しました。「どうせおれなんか・・・」というのが口癖のS君が毎日いきいきと参加していたのが、一番の収穫でした。 毎年、プール指導をしていて、いつも感じることがあります。 子どもたちがシャワーを浴びる時。「はい、3人ずつ順番に並びなさい」といって、子どもたちを並ばせると、「はい、入って!」といって1列目を進ませます。シャワーを浴びてキャーキャー歓声を上げる子どもたちに、「はい、次」と、だいたい5秒おきに前に進ませます。こうして百人以上の子どもが順番にシャワーの下を通っていきます。 自分でやっていて、実に機械的。 まるで工場で、流れ作業で製品を作っていくようです。 よく考えてみると、これはシャワーに限ったことじゃないですね。 授業でも、生徒指導でも、みんな同じかも。 学校って、すごく合理的に作られてる場所なんだよなあと、しみじみ思ってしまいました。 気を抜くと、つい、子どもたちをロードローラーでならすような教師になってしまっている自分に気づくことがたまにあるんですよね。
2008.08.02
コメント(2)
-

Y君との日々-3-
Y君とのすったもんだの日々、Y君に共鳴するようにS君も荒れだし、毎日その2人の対応で手一杯という状態でした。 Y君は3時間目ぐらいになると、たいてい「腹減ったなあ」と独り言を言います。「朝飯食べてこなかったのか?」と聞くと、「うん」と答えます。「母ちゃんが起きてなかったから・・・」とか言うことが多いです。 掃除の時間にほうきを振り回して女の子の額に当ててしまい、ついに親御さんからの苦情が来ました。これは困ったことになったなと思いました。もうすぐに手を打たなければならない事態です。 授業の中では特に音楽の時間がひどかったです。音楽の専科の時間はいつもいっしょについて行かなければなりませんでした。それでもふざけて授業妨害をするY君、ついに先生と協議の末、Y君は次の音楽の時間、別室で別課題をすることになりました。 Y君と2人きりで話をするとY君は素直ないい子で、家でお母さんがいないことが多いこと、妹の世話をするのが嫌なこと、今の自分がまずいと思っていることなどを話してくれました。 率直に言ってしまいました。「おい、おまえ、他の子がうらやましいなって感じてるんだろ。」「うん。」 こんな唐突な問いかけに即答とは・・・ これを素直に受け取っていいものかどうか。(振ったのは自分なのに) そのあと、Y君に少し強い調子で言いました。「先生はY君を大事に思ってるし、Y君がつらいこともわかってる。だけど、今のままを続けてたらY君はみんなの嫌われ者になってしまうし、乱暴者だっていって、クラスの中で居場所がなくなってしまう。先生はこれから、おまえが誰かに暴力をふるったり、誰かを傷つけるようなことをしたときは、オニになって怒るからな。オニだぞ。いいな、覚悟しとけよ。それがおまえを守ることになるんだぞ。」 その通りにしました。でも、オニといっても暴力はふるわないオニです。おそらくさんざんひっぱたかれて育ってきたY君にとってはそんなにこわくないでしょう。それでも賢いY君は、私の言葉を意識し、暴力をふるわないことを自分なりに意識して、行動はやや落ち着きました。 親御さんとも2回目の話し合いをしました。あくまで母親の気持ちをデリケートにとらえながらと思ったのですが、同席の校長は、きっぱりと現状、それに家庭への要求という形で話を進めました。 親御さんとの間では、学校でよかったこと、家庭でよかったことを知らせ合って、両面でY君を認め、ほめていきましょうということになりました。 解決したわけではありませんでしたが、Y君の状態は少しは落ち着きました。朝ご飯も食べて来たという日が多くなりました。 校長をはじめ、まわりの先生たちは、「Y君に甘くしたから荒れたんだろう」「厳しくしたからY君は落ち着いたんだ」という見方をしているようです。「教育相談は子どもを甘やかすからだめだね」みたいなことを思っているでしょう。正直言って、それがすごく悔しいです。 そんな単純なものじゃねえ! Y君は俺だから、わかってくれる相手だから荒れを出したんだ と言いたいですね。 とはいえ、そんなことを言ったところで「はあ?」と言われてしまうでしょうけど。
2008.07.31
コメント(4)
-

Y君との日々-2-
お母さんとの面談をして、Y君の行動はやや落ち着くかに見えました。家でやさしく接してくれるよう気をつけてくれてるんだなあと思いました。 しかし、すぐに元に戻ってしまいました。もっとエスカレートするようになってしまいました。同じように落ち着かないN君とちょっかいを出し合ってはトラブルになり、荒れるようになりました。2人が交互にパニック状態になり、時には同時に荒れることもありました。さらに自閉気味のT君ともちょっかいを出し合い、日常的にトラブルが起きやすい状態になりました。 ちょっと教室を空けて戻ってくると、必ず何か起きていました。うかうかトイレにも行けない状態です。教師はもろもろの雑務を教室で子どもたちが課題をやっている時間など、暇を見つけてちょこちょこやるものですが、それもできません。目を離せないのです。 こうなると、その3人に引っ張られるようにして、クラス全体がわやわや落ち着かない雰囲気になってきます。その3人に次いで不安定要素を持っているような子どもたちが、騒ぎに乗じて悪のりしたり、学習など、いい加減にやろうとします。 ここで、緊急の策として、暇な時など、管理職の先生に教室に入ってもらうことをお願いしました。 それに、学級の子どもたちには、少し厳しく締めていくことをはっきりと告げ、その通りにしました。先生の話をまじめに聞かない人、それにその時間に必要なものを出さない人は、机の中の物、あるいは机そのものを廊下に出してしまうことにしたのです。 もちろん3人も例外ではありません。授業中、机がなくなってしまった子はちょっとかわいそうでしたが、これは効きました。 あと、ほめました。自習の時間、ちゃんとやっている子を見つけて紙に書いてもらい、その子をほめました。毎日クラスの子をほめることを考えました。 とりあえず、クラスの雰囲気は落ち着きを取り戻しました。 しかし、Y君は相変わらずでした。帰りの会の歌を邪魔する、気に入らないことがあると、まわりの子の悪口を言う、冷やかす、挙げ句の果ては上履きで叩くと、毎日そんなことの繰り返しです。 もしも1対1で対応できたなら、違ったのでしょう。Y君は1人の大人にじっくりと向き合ってもらって、関係を構築することがおそらく必要なのです。でも、三十数人の中で生活すると、友だちの方はY君に特別寛容にはなってくれません。友だちに悪さをしたら、必ず謝らなければなりません。そのこと自体がY君のストレスとなってまた荒れます。そんなことの繰り返しの毎日・・・ Y君を観察していて、ちょっと違った感じになってきたのに気づきました。 怒りにまかせた暴力的な、攻撃的な要素は減ってきたように感じました。友だちに対するちょっかい、嫌がらせがやたら目立つようになりました。 3時間目になると、しょっちゅう「はらへったよ~」とつぶやくY君。「朝飯食ってこなかったのか?」と聞くと、「食ってない」とほとんど答えます。 何かY君が「まわりの奴らがうらやましいんだ」とアピールしているみたいだと思いました。
2008.07.19
コメント(0)
-
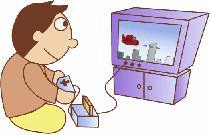
Y君との日々-1-
1学期ももう終わりです。 この4ヶ月間は大変でした。なんか思い出してみると、疲れて毎週末寝込んでいたような・・・ 疲れた一番の原因は、Y君との日々の格闘でした。(残念ながら、Y君以外にも原因はあります・・・) 4月はじまった時は、Y君の問題行動は、それほどではありませんでした。むしろ、保健室登校のRさんや自閉傾向のT君の方がこのクラスの注目児とされていたのです。 5月ぐらいからY君の行動の荒れは目立ち出しました。友だちが悪口を言ったの言わないだのでけんかになることが日常化しました。授業中の態度が悪いのは最初からでしたが、さらにそれはエスカレートして、茶化して関係のないことをわざと言ったり、友だちのあげあしを取ったりと、授業妨害とも言えるレベルにまでなりました。カバンを取りにロッカーに行くついでに友だちの頭を叩いていったり、たいした理由もないのに友だちを押したり蹴ったり、いたずらとも悪意とも判別つかないような感じでした。 Y君の内面に何かがあるのだということは感じました。 怒って壁を蹴っ飛ばしていたY君を抱きかかえて押さえつけたら、妙におとなしくなって抵抗しなくなるのを奇妙に感じました。また、2人だけで話をするとすごく素直でやさしげな面を見せ、自分の気持ちを話すY君には、ただの善悪指導ではない何かが必要だろうということは確信として感じていました。 しかし、集団の中でY君が他の友だちに悪さをした時は、Y君の内面云々については頭で考えながらも、他の子どもたちに謝らせ、もうしないように強く指導しなければなりません。 こちらが注意すると、Y君はもっと荒れます。校内を走って追いかけ回すこともあれば、押さえつけたり抱きかかえることもあります。怒鳴って首根っこを押さえつけたこともあれば、別室で肩を抱いてしばらく話をしていたこともあります。 終わりのない追いかけっこをしているようでした。 Y君を見ていて、自分なりに次のような見立てをしました。○わざと相手を怒らせるようなことをしばしばするY君の行動は、被虐待児の行動に近いものがある。家庭で両親が、そのように接しているのではないか。○Y君はがまんができない。不愉快なこと、自分が感じるストレスをすぐに友だちへの行動という形で出してしまう。ストレスを心で受け止めるだけの気持ちの余裕がない。○場をわきまえて行動するようなところがあるので、発達障害という感じがあまりしない。(もちろん完全に否定はできないが) 5月の下旬に、お母さんと面談をしました。 はじめから仏頂面のお母さん、看護婦さんをしていて、相当忙しいということです。 お母さんを責めるということではなく、Y君のためにどうしたらいいのかという話をするように努めました。 抱きかかえられるとちょっとうれしそうだということを言ったら、「おそらく私が甘えさせてあげていないのだと思います。」ということを言い出しました。生まれてすぐ、託児所に預けてしまっていたのだそうです。普段から、子どもに甘えさせることが苦手で、そして、怒る時はものすごい勢いで怒ってしまうそうです。しばしば手も上げるということも言ってくれました。ある程度見立ては当たっていたなと感じました。 ここでは、担任から家庭にあまりプレッシャーをかけることはしないから、暴力的な接し方は避けてくれるよう、それに、できるだけ子どもに手をかけてあげてほしいということをお願いしました。いい感じで話し合いを終えることができました。 しかし、事態は良くなりませんでした。
2008.07.13
コメント(2)
全131件 (131件中 1-50件目)











