在宅福祉
在宅福祉サービスは、高齢者の尊厳と意思を尊重し、かつ高齢者が直面する問題を受容することによって、社会生活の上でも、また意識の上でも、高齢者が「当たり前」の人間として生活できるように援助することを目的としている。従って在宅福祉サービスは、入所老人を地域社会から隔離し、個人の尊厳と自由を奪いがちであった施設収容中心主義へのアンチテーゼとしての役割を果たしてきた。同時にそれは、問題が発生する地域を問題の解決を予防の場にするというサービスの機能性と効果性を強調した必然的な対応の帰着である。
その在宅ケアサービスの主なものを下記に挙げる。
1) ホームヘルプサービス事業
ホームヘルプサービスは、市町村が直接又は社会福祉協議会等へ委託して、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の老人(65歳未満であっても初老期痴呆に該当している者を含む)のいる家族が老人の介護サービスを必要とする場合に用いる。その利用者の家庭に訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣し、入浴の介助、身体の清拭、洗髪等の身体の介護サービス、調理、衣類の洗濯、補修、住居等の掃除等の家事援助サービス、及びこれに付随する相談・助言を行い、日常生活を支援することを目的とするものである。
2) ショートステイ事業
居宅において、おおむね65歳以上の要介護老人を介護している者が病気、出産、介護疲れ等の場合に代わって当該寝たきり老人等を一時的に特別養護老人ホーム等に保護し、介護者の負担の軽減を図る等、寝たきり老人等及び、その家庭の福祉の向上を図ることを
目的として昭和53年度から事業が開始された。
在宅福祉の展開を図るわが国最初の本格的研究として、全国社会福祉協議会編『在宅福祉サービスの戦略』(1979年)が刊行された。その中で社会福祉ニーズを「貨幣的ニーズ」と「非貨幣ニーズ」に分類し、非貨幣的ニーズに対応する対人福祉サービスを、公(国、都道府県、市町村)、私(民間組織、地域住民)の役割分担のもとに提供する方策が示された。
在宅福祉サービスは、高齢者が居宅で生活し続けることを支援するサービスで、高齢者が地域社会で暮らし続けることが重視され、またノーマライゼーションの理念の普及によって、それまでの施設中心の福祉に代わり、在宅福祉の導入が進んだ。具体的には1990年、福祉関係八法の改正で、在宅福祉サービスが社会福祉事業法上の事業となり、「在宅三本柱」が、施設福祉サービスに並ぶものとして明確に位置づけられた。この3つのサービスのほか、日常生活用具(車椅子・特殊ベッド緊急通報装置など)の給付、食事や入浴サービスなどがある。同時に、市町村には在宅サービスの積極的な推進が求められ、この円滑な実施のために、国の補助が拡充された。また事業の委託先の対象要件は緩和され、委託先の多様化も進んだ。
そして同年、地域における高齢者にかかわるサービス調整機関として在宅介護支援センターが創設され、24時間体制で総合的な相談と、保健・福祉サービスの連携による総合的な支援の中心となっている。
公的在宅福祉施策として、高齢者を対象とした福祉サービスは、1989年ゴールドプランが策定され、高齢者に関する保健医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。さらに1994年新ゴールドプランでは数値目標を修正した見直し案が発表され、その後介護保険制度(1998年制定、2000年施行)導入などなどをふまえ、2000~2004年の5ヵ年計画でゴールドプラン21が策定された。
在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
近年、福祉サービスを利用する利用者の置かれている環境や、利用者の状況が複雑化・多様化している。そのため、利用者の多種多様なニーズに対応するためには、様々なかたちの福祉サービスや、援助者の柔軟な対応が求められる。福祉サービスの利用者は、その大半が高齢者であり、その多くの場合は家族と共に生活をする事や長年住んでいる地域を離れずに余生を暮らしたいと望んでいる。そこで、援助を行う場所として適切な場所はその高齢者が現在暮らしている場所、つまり在宅でのサービスである。
(1)介護保険
我が国は、世界に類を見ないスピードで高齢化が進んでいる。そのため、寝たきりや認知症などで介護を必要とする高齢者は、今後ますます増えていく。現在すでに寝たきりの人の半数が、長期に渡る寝たきり生活を送っており、介護の長期化が目立っている。また、家族は長く続く介護から、介護をしている相手に対して憎しみが生まれたり、虐待があったりなど、精神的な疲労から悲惨な事件に結びつくことさえある。特に、介護をする人の5割以上が60歳以上の高齢者である老老介護は共倒れのもとである。介護の問題は、誰もが避けて通れないものとして、国民全体が考えなくてはならない。
老いて介護が必要になったときに、その時に有する能力を最大限活用した生活が営め、そして介護をする人の負担を少しでも軽くしようといったニーズから生まれたのが、介護保険制度であり、高齢化社会において
(1)介護保険制度による場合
(2)介護保険によらない場合
本文の内容一部
在宅福祉サービスとは、可能な限り自宅での生活維持ができるように提供される各種の福祉サービスをいう。
高齢者の在宅福祉サービスを、その内容・形態によって類型化すると次のようになる。
1[要援護者の訪問型サービス]ホームヘルプ、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問歯科ほか2[要援護者の通所型サービス]デイサービス、デイケア、通所リハビリテーションほか3[要援護者の滞在型サービス]ショートステイ、グループホーム、グループリビング、高齢者生活福祉センターほか4[要援護者の生活・住環境改善型サービス]住宅改造、福祉用具給付、バリアフリー化ほか5[高齢者の生活の軽度支援型サービス]外出支援、配食サービス、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス、買い物ほか6[高齢者の生きがい・健康つくり型サービス]食生活改善事業、運動指導事業、生活管理事業等ほか7[要援護者の緊急事態に対応するサービス]緊急通報サービス、火災対応福祉用具給付ほか8[要援護者の家族支援型サービス]介護手当て等金品支給、家族介護教室ほか高齢者在宅福祉サービス供給主体と方法は大きく次の二つに分けられる。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- しんくぱっど
- 【続】X1 Carbonの電源ボタンが機能…
- (2025-10-19 19:42:00)
-
-
-

- 3DCG作品
- 続・初めての飛行機プラモ 19
- (2025-11-23 06:30:06)
-
-
-
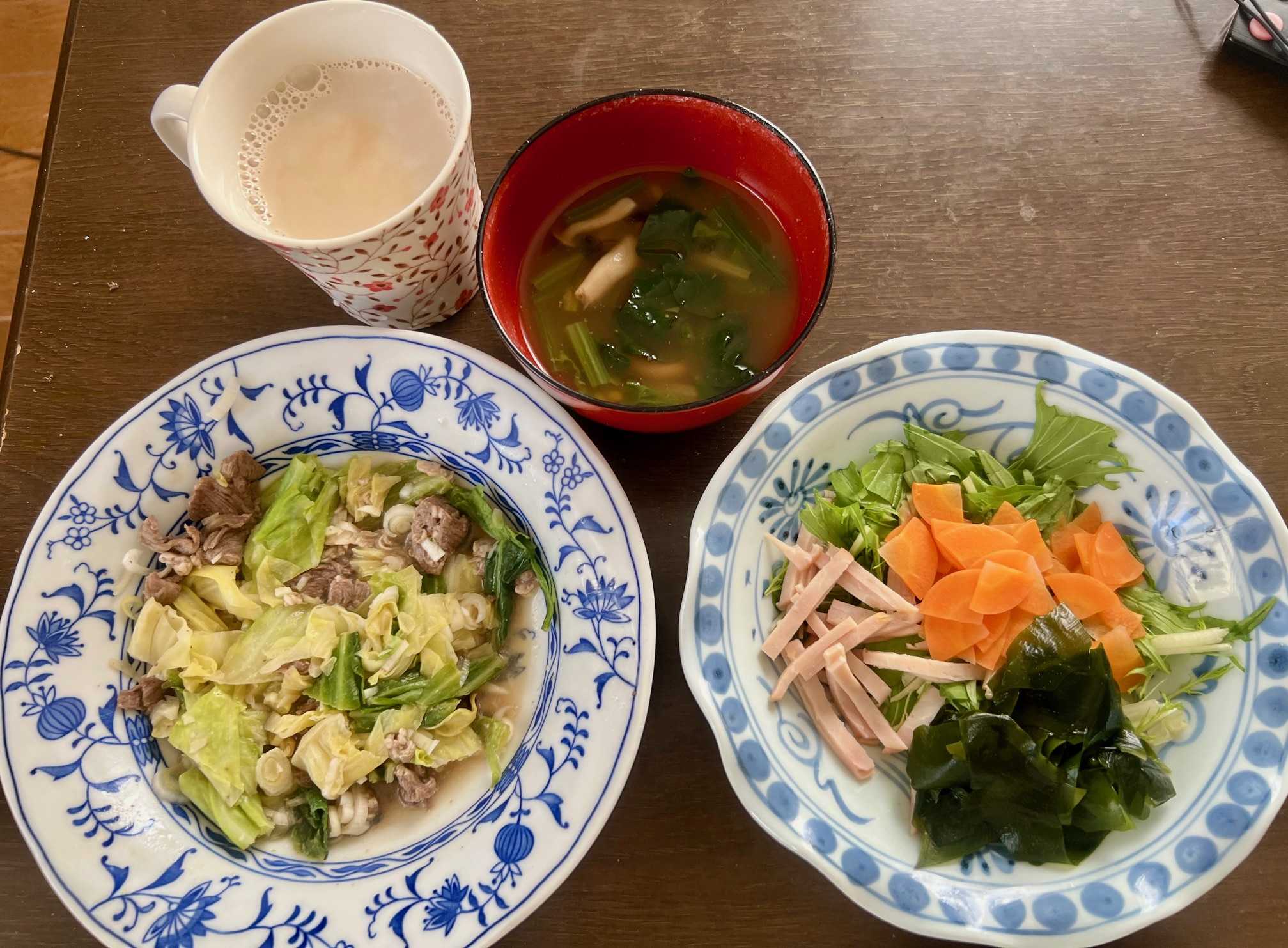
- ブログ更新しました♪
- その日の日記は、その日のうちに、書…
- (2025-11-27 00:10:38)
-
© Rakuten Group, Inc.



