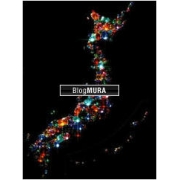PR
Keyword Search
 New!
Pearunさん
New!
PearunさんMちゃんママから長… New! flamenco22さん
^-^◆ 学びの宝庫・…
 New!
和活喜さん
New!
和活喜さんWリーグトヨタ紡織チ…
 クラッチハニーさん
クラッチハニーさん風に向かって クリス…
 千菊丸2151さん
千菊丸2151さんComments
Freepage List
Calendar
![]()
![]()
![]()
「前田慶次」
上杉謙信の養子であった上杉景勝は、秀吉の許で五大老の一人となった。
その彼の宰相で智謀天下に鳴り響く直江兼続に惚れぬいた武将がいる。
加賀百万石の前田利家の義理の甥、前田慶次利大(とします)である。
彼は前田家で五千石を食んでいたが、窮屈な武士の生活を嫌って出奔し、
放浪の旅の後に直江山城守兼続に逢って、その人柄に惚れこんで僅か
千石で上杉家に仕官したのだ。
彼は気象が烈しく和漢の書に通じ、「源氏物語」 「伊勢物語」を、
三条大納言公光(まさみつ)に学び、和歌、連歌は里村紹巴(じょうは)に学び、
茶は古田織部、千宗易に学んだ。更に謡曲、猿楽にも長じ、武芸十八般の
達者と聞こえていた。その名は天下に聞こえ、諸大名は高禄で召抱えようと
したが、彼は全てを断って気侭に生活していた。
彼は日頃から異風を好み、異様な振舞えで人々を驚かしていた。
天正十八年、秀吉の小田原攻めに慶次は利家にしだがって参陣するが、
北条が降伏し秀吉の天下統一が成ると、天下は平穏となった。
この波風のたたない世は、どうも慶次の気象にあわない。武士の堅苦しい
掟に従って、小心翼翼と我が身の安泰を図る生活に我慢が出来ず、その鬱積
が奇行となって発散された。
利家は事ある度に慶次を叱り諭したが、それが慶次には笑止で煩わしかっ
た。彼は五千石にも未練はなく、貞淑な妻と一男五女の子供等も彼を引き止め
る絆にはならなかった。ついに加賀藩を出奔し自由気侭な生活を送ろうと決め
た。その為にこっそりと逐電するのも味気ないと、常日頃から小言を食らう、
利家に置き土産をして行こうと、ある一計を企んだ。
天正の極寒の季節に、利家に慶次から書状が届いた。
茶の招待であった、利家は思いもかけぬ慶次の招待で喜んで屋敷に出向い
た。神妙な態度で慶次は、茶の前に風呂に入って躯を暖めて下されと、巧妙
に利家を風呂に誘い込んだ。喜んだ利家が風呂に入ると水風呂であった。
「おのれー」と怒り声を揚げた時には、慶次は愛馬、松風に騎乗し京を目指し
駆け去っていた。
出奔した慶次は京の一隅に屋敷を借り、召使を雇っている。かなりの路銀を
持ち出したようだ。愛馬、松風には贅を尽くした馬具で飾り、毎日、京の市中
を引きまわらせ、加茂川で馬を洗わせた。
その際、流行っていた「幸若(こうわか)」の節を面白おかしく歌わせ、
最後には「前田慶次の馬にて候」と小者に歌わせたと云う。
この京で彼は諸国の著名人と知りあった、そんな中に直江兼続が居たのだ。
慶次はあれほど嫌った仕官を、兼続を通じ景勝に願い出た。
条件は「禄は問わないが、気侭に勤めさせて貰いたい」この一つであった。
無論、景勝に否やはない、千石で召抱えた。時は慶長三年、景勝が越後から
会津、佐渡、米沢、庄内の一部などを加え百二十万石の太守となった時期で
あった。会津で景勝に目通りを許された際、彼は剃髪し黒の長袖を着用し、
「穀蔵院 瓢戸斉(こくぞういんひよっとこさい)と称し、手土産に大根三本を
盆にのせ差し出した。いぶかしく見つめる景勝に、
「この大根のように見掛けは、むさ苦しくとも噛めば噛むほど味の出る人間
でござる」と大真面目に答えたと云われる。
その彼が真価を発揮したのは、慶長五年七月の関ヶ原の合戦の時である。
徳川家康が上杉家に謀反あふりと、上杉征伐軍を起こし小山の陣を敷いて
いたが、石田三成の挙兵の報せで馬首を西に向けた。
白河で軍勢を集結し、徳川勢に対していた上杉勢は一転して徳川方の最上
義光を攻めた。
義光の本城、山形城の支城である長谷堂城攻撃中に、関ヶ原の石田三成の
大敗の急報が届き、軍勢を引きあげる最中に、この慶次が奮闘した。
智謀神の如くと云われた直江兼続をもってしても、伊達勢の加勢をうけた
最上勢の攻勢を凌ぐのは、無理があった。
ここに最上の役の最大の激戦が展開された。
三万の上杉勢が苦戦の真っ最中に、兼続の許に慶次が駆けつけて来た。
「殿軍は拙者にお任せあれ」 と叫ぶや朱色の大身槍を振るって阿修羅の
ように、最上義光の本陣に突き入った。
その猛烈な突撃で、最上勢の本陣は四散し義光は命からがら逃げ延びた。
こうして関ヶ原の役後、景勝は三十石に減封されて居城を米沢へと移した。
前田慶次も禄、三百石に減らされたが、無為に隠居できる男ではない、
彼の奇矯は死ぬまで止む事はなかったと云う。
堂森の屋敷を無苦庵と称し、慶長十七年六月四日に波乱の生涯を閉じた。
米沢の宮坂考古館に、朱塗りの異形な甲冑に円錐形の前立のない、一文字
に庇(ひさし)のついた甲冑が、展示されている。
いかにもかぶき者らしい、前田慶次の具足であると云う。