2024年11月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
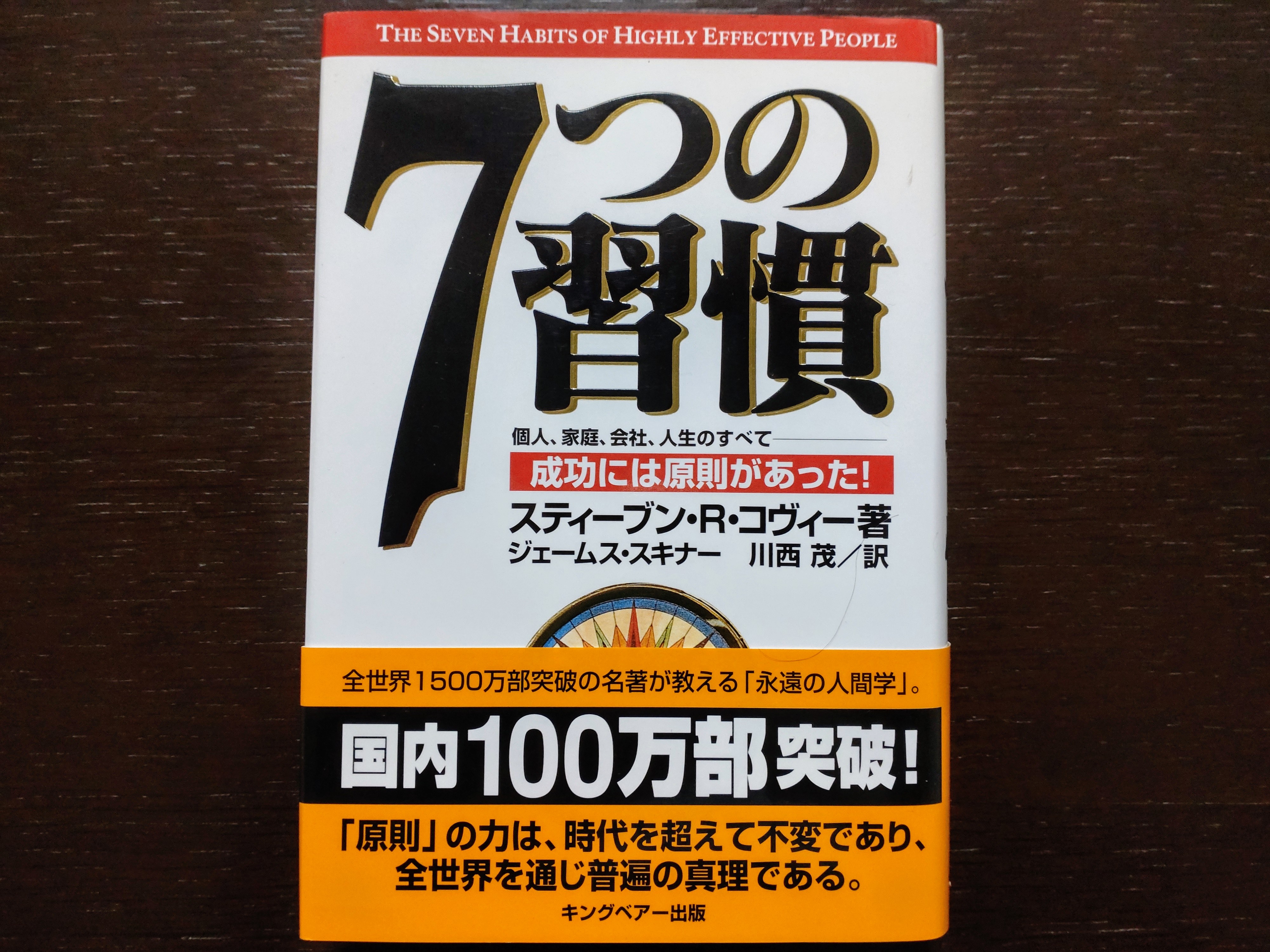
第二の習慣「目的を持って始める」(「7つの習慣」スティーブン・R・コヴィー)
著者(スティーブン・R・コヴィー氏)が「永続的な幸福と成功を支える基本的な原則」とする「7つの習慣」の2つ目。【第二の習慣「目的を持って始める」】(以下、勝手な要約と勝手な感想)ざっくりまとめると「ゴールを決めてから歩き始めなさい」と説いている。「第一の習慣」で、今自分が置かれている状況を人のせいにしない意識を身に着けたら、「第二の習慣」では自分が進む先にどんなゴールが待っていて欲しいか、これを具体的に考えなさい、と。・例えば自分のゴールとして、「自分の葬儀で、どんな弔辞を読んでもらいたいか」を考えてみる。自分が死んだ後、告別式で何と言われたいか。娘から「良き父だった」と言われたいか、職場の部下から「良きリーダーだった」と言われたいか、あるいは友人から「いつも明るくて楽しい奴だった」と言われたいか…・これがイメージできれば、それが人生の最終目標になる。後はそこに向かって歩き始めるだけ。目的地が見えているので、途中で脇道に逸れることもなくなる、と著者は言う。僕も考えてみた。自分の葬儀でどんな弔辞を読んでほしいか。。。…しばらく考えたけど、弔辞の言葉は何も出てこなかった。思い浮かんだことと言えば…「弔辞はいらないなぁ、周りを煩わせたくないし、できればそっと静かに消えていきたい、そもそも誰にも評価されたくないし、勝手に枠にはめられたくない…」みたいなことばかりだった。著者の意図は理解しつつも、こんなことしか頭に浮かんでこない自分に少しガッカリした。一旦切り替えて…・また別のゴールとして「自分が働いている組織が成功している状態」をイメージしてみる。・自分の職場の一人ひとりが素晴らしい働きをしている状態、理想の職場の姿を職場の全員で考え、文章(ミッションステートメント)にまとめ、それを全員で共有する。・この時の注意点は、仕事の上手な進め方(経過)を考えるのではなく、成功している状態(成果)をみんなで想像すること。それを上から押し付けるのではなく、全員で考えること。「これなら僕の職場でもある程度やっているかも…」と一瞬思った。5年後の組織の姿を計画に落とし込んでいるし、その5年後に向けた1年刻みの目標も毎年立てている。一人ひとりの年間目標も、全員が自分で考えて書いている…。うん、まずまずできてるかも…と思いつつも、すぐに別の思いが浮かんできた。形の上では「やっている」と言えるかもしれないけど、頑張らなくても達成できそうな目標しか立てようとしない奴らはいるし、僕の目標にもそんなゴマカシが隠れているかもしれない。形だけ整えていかにも出来ているように見せかけている部分はきっとある。そして思う…そもそも組織全員が良心と向上心で一丸となることなど、どんなシステムを作っても夢のまた夢なのではなかろうか…そんなことを考え始めてしまったので、正直少し辛くなってきた。できない理由を並べ立てているだけの僕…。ということで、この本が求めるレベルに僕はちょっと…と今のところ思っているけど、もうしばらく頑張ってみることにして「第三の習慣」に進もうと思う。
November 28, 2024
コメント(0)
-

おまかせの一日 @Tokyo Disney Sea(千葉県浦安市)
東京ディズニーシーでの休日。ここに最後に来たのは10年以上前のこと。その時は僕がいろいろ作戦を立てて回っていたけど、今回はすべて子どもにお任せ。チケットをアプリに入れたり、入場ゲートを過ぎたらすぐにアプリからアトラクションの抽選を申し込んだり…。東京ディズニーリゾートのシステムは以前と大きく変わっていた。自分でやれと言われても難しかったかもしれない。JR舞浜駅からパークに行く途中、この日泊まるアンバサダーホテルに手荷物を預け、ディズニーシーの入場ゲート前には朝の7時過ぎに着いた。横に広がる開演待ちの列には、ざっと見ても千人を余裕で超えるゲストたちが並んでいて、僕たちの後ろにも列がどんどん伸びていった。繁忙日にはチケット代がついに一万円を超え、若い世代にはディズニーリゾートは遠い存在になってしまった…。そんな感じのネガティブな報道も近頃目にしていたし、それとは別な理由でオリエンタルランドの株価も一時期より下がっている。だから、パークの混雑は以前ほどではないのかも、と思う気持ちも(期待も込めて)あったけど、少なくともこの日はとても賑やかだった。入場ゲートは予定の9時よりも早く開いた。手荷物検査と金属探知機とチケットゲートを通って園内に入ると、辺りは一面の人・人・人。だけど、そこはさすが夢の国。どんなに混んでいても園内で行き交うどの顔も楽しそうだったし嬉しそうだった。ディズニーリゾートに来てはしゃぎ回るような世代からは外れてしまった僕にとっても、パーク内を歩いているだけでも楽しかった。ドリンクを飲みながらの休憩時間も心地良かったし、アトラクションにも思ったよりたくさん乗れたし、今年オープンしたばかりのファンタジー・スプリングスにも入れたし…。体の中が浄化されるような1日を過ごすことができた。何よりも子どもとまたここに来られたことが嬉しかった。天気も良くて、幸せな一日だった。パークの雰囲気はクリスマス。凝っている、と言うか、こだわっている、と言うべきか、デコレーションはどれもすごい質感でなかなか圧倒された。
November 23, 2024
コメント(0)
-

潮見駅から散歩(東京都江東区)
東京駅を出てからしばらく地下を走るJR京葉線。それがポンッと海上に浮上するあたりに潮見地区がある。車窓からは海に浮かぶ島のようにも見える潮見エリアを、今回少しだけ歩いてみた。この日、一番印象的だったのは夕方の風景。見えているのが川なのか運河なのか、それとも海なのか…良くわからないけど、沈んでいく夕陽とビル群の影が水面に映し出されて、なかなかの美しさだった。JR潮見駅は小さな駅で、平日の午後の時間帯、乗り降りする人はそれほど多くはなかった。背後にはAPAホテルなどのホテルが何棟か建っていて、駅の周りには飲食店やコンビニがちらほら。大きめのスーパー「マルエツ」も見つけた。潮見地区は一つの区画がとても大きい。そして交差点の間に横断歩道がないので、道路の反対側に渡るのは少し大変。配送センターやオフィスビル、製造業、研究所などが工業団地のような雰囲気で立地していて、まとまった空き地もまだ残っていた。潮見地区は埋め立て地だから地盤が弱いのではなかろうか…。歩きながらこんなことが頭をよぎったけど、例えば、この広い空き地の奥には大きなマンションが見えるし、他にもタワーマンションのような公団住宅があったり、一軒家もたくさんあって、思っていたよりたくさんの人たちが潮見地区で暮らしていた。今は建築物の基準も厳しくなっているはず。このマンションも基礎がしっかり岩盤まで届いていて耐震の問題はないのだろう。さらに言えば、江戸は元々湿地帯だったし、今の東京には江戸時代になってから埋め立てられた土地がたくさんある。余計な心配は無用かもしれない。夜になると潮見駅にはディズニーリゾート帰りの幸せそうに疲れ切った人たちが続々と到着し、駅近くのホテルに向かって歩いていった。
November 18, 2024
コメント(0)
-
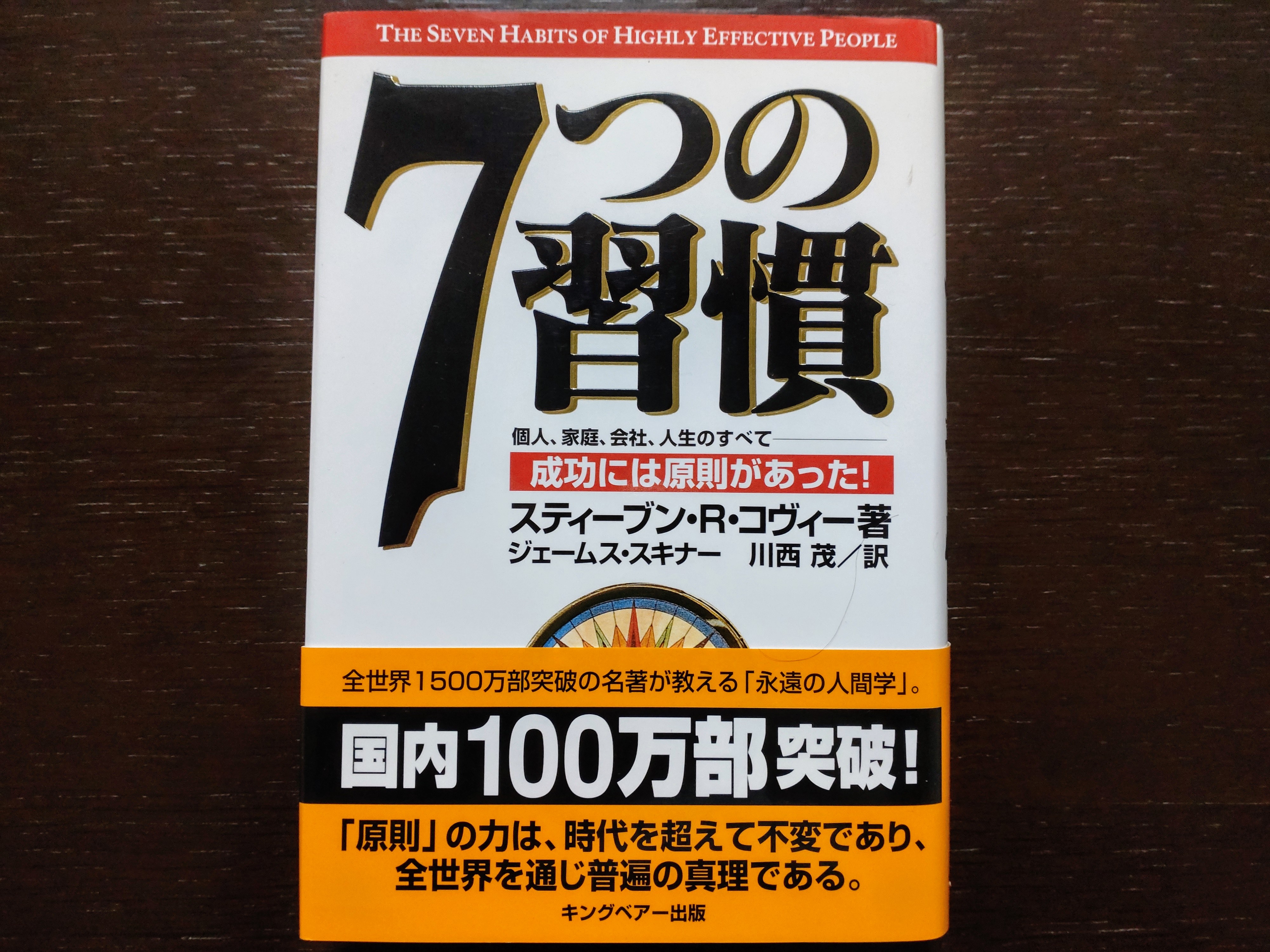
第一の習慣「主体性を発揮する」(「7つの習慣」スティーブン・R・コヴィー)
長く書棚に眠っていた「7つの習慣」に目が止まり、久しぶりにページをめくり始めた。そこそこ分厚い本の巻末を見ると「1996年12月25日初版第1刷発行。2007年10月25日初版第56刷発行」と書いてあるから、おそらく15年振りくらいの再読になる。オレンジ色の帯に「永遠の人間学」とあるこの本を、当時の僕は何を思って手に取り、買ったのだろうか…。きっと何かに悩んでいてこの本にすがりたかった、そんな気はするけどまったく覚えていない。ただ僕の残念な性格から察するに、当時は自分にとって都合の良いところだけを拾い読みし、「大丈夫、俺はできてる」とか呟きながら満足して、この本を読み終えたつもりになっていた可能性が高い。だから今回は、著者の意図を時間がかかってもきちんと理解してみたいと思った。目次を見ると、“極めて有能な人たち”の「7つの習慣」とは…①主体性を発揮する②目的を持って始める③重要事項を優先する④Win Winを考える⑤理解してから理解される⑥相乗効果を発揮する⑦刃を研ぐとなっている。なんのことやら…。一度読んでいるはずなのにどの項目も言わんとすることがわからない。ちゃんと読み通せるかな…と少し弱気になりつつも、まずは「第一の習慣」を読んだ。【第一の習慣「主体性を発揮する」】(以下、勝手な要約)・例えば、大バカ野郎のせいでどうしようもない事態に陥ったとする。この時、僕はどうすべきか。・①大バカ野郎に復讐する。②大バカ野郎にバカを自覚させ少しでもバカを治してやる。③大バカ野郎には構わず、この事態を自分で何とかする。④ひたすら神に祈る。・さて、どれか正解だろうか。・①〜④を同時並行でやって事態をなんとか乗り切らないといけないのではないか。少なくとも張本人には何か言ってやらないと気が収まらない…と僕なら考えるが、著者は「大バカ野郎のせいでどうしようもない事態に陥った」との認識がそもそも間違っている、と言う。・自分にはどうしようもない事態に陥っているかどうかは自分が主体的に決めていることだ。「AのせいでBになった」のではなく「AのせいでBになったと自分が感じている」に過ぎず、自分の考え方次第でBはCにもDにもなる。つまり「B」は「A」の結果ではなく、「A」と「B」の間に「自分の主体性」がある。・だから大バカ野郎に腹を立てても解決にはならないし、そもそも他人を変えようとしてもそれはムリ。変えるべきは自分の認識。「どうしようもない…」と感じる状況に置かれても、そこで自分が主体的に取り組めることは何かある。それを見つけてその部分にエネルギーを集中すべき。・自分がコントロールが及ぶ範囲を少しずつでも広げていくことで、自分の力で「B」を「C」に変えていくことができる。・その一方で、他人を自分の思い通りに変えようとすることを含めて、自分のコントロールが及ばないことは諦めて受け入れた方が良い。淡々と受け入れることで心の平安を守れるのであれば、その選択は正解だ。自分のフィルターを通すとこんなサマリーになってしまうけど、このくらいまで崩してみても【第一の習慣】を自分のものにすることはものすごく難しい、ハードルが高い、僕はそこまで立派な人ではない、と感じてしまう。一方で、こんな人になれたらそれはそれで良いことに違いない、と思っていることも確か。まずは今の気持ちを頭の片隅に置きながら【第二の習慣】に読み進んでみようと思う。
November 13, 2024
コメント(0)
-

僕が生まれた街(札幌市東区北十三条東1丁目)
僕が生まれた時、本籍は「札幌市北区北二十四条…」にあった。だから僕はずっと北二十四条…で生まれたと思っていた。だけど今年、札幌市内で働く働くいとこが「東区北十三条東一丁目」の近頃の様子を割と詳しく知らせてくれた。「なぜその話を僕に…?」と思いながら聞いていると、どうやら僕が産まれた場所はそこだったらしい、ということがわかってきた。早速、母に聞いてみると「あんたが生まれた時は、そこに住んでたね」とサラッと言われた。「北二十四条は?」と聞くと「おとう(僕の父)の実家さ」とあっさり言われた。知らなかった…。そして、せっかくなので行ってみた。地下鉄東豊線の北13条東駅を降りると、駅の近くに札幌諏訪神社があり、お祭りなのだろうか、境内の入口にシャボン玉が舞っていた。この神社は明治15年からこの地にあるそうだ。神社から少し歩くと天使病院が見えてきた。ここが僕の産まれた病院だということは小さな頃から知っていたけど、病院と当時の自宅がこんなにご近所だったとは知らなかった。そして、僕がこの病院で生まれた理由を今更ながら理解した。この辺りは札幌駅から地下鉄でたったひと駅。しかも駅近でありながら空地が目立ち、比較的古い建物も残されていた。石狩街道沿いに百地商店という名の酒屋さんを見つけた。おそらく今は営業していない。サントリーの文字とウイスキー(サントリーオールド)の絵に歴史と懐かしさを感じた。札幌諏訪神社の裏手に回ると、ここにも築何十年だろう…という建物があった。僕が産まれた頃は、こういう建物が並ぶ街だったのかも、と思った。ここが僕が産まれた時に住んでいた街か…。と呟いてはみたものの、住んでいたのは2歳くらいまでなので、当時の記憶は全然ない。歩き回ってもピンとくる風景には出会わなかった。それでも今回、天使病院の今の姿が見られたのは良かったし、余談ながら病院の隣には天使大学があって目がくぎ付けになった。「天使大学」アニメに出てきそうな学校の名前。看護大学なのかな…とか思いながら校門の前を通り過ぎた。
November 9, 2024
コメント(0)
-

仙台の旧町名「元鍛冶町」(元鍛冶丁が一般的。今の青葉区国分町二丁目ほか)
元鍛冶町(もとかじまち)仙台三越の南側の道路を西(仙台城址方向)に少し歩くと、かつての元鍛冶町がある。昭和45年2月1日の住居表示前の町名は「元鍛冶町」(もとかじまち)となっているが、地元では「元鍛冶丁」(もとかじちょう)と呼ばれていたようで、公園の名前も元鍛冶丁公園になっていた。かつての「元鍛冶町」は今、青葉区国分町二丁目と立町のそれぞれ一部になっている。町名の由来は…伊達政宗が仙台に城下町を建設する際、この場所に鍛冶職衆を配置し「鍛冶町」とした。しかし程なく、鍛冶職衆は南鍛冶町と北鍛冶町に移され、鍛冶町は侍屋敷の町に変わった、ということらしい。(参考:仙台市HP「道路の通称として活用する歴史的町名の由来」)鍛冶職衆がいなくなった鍛冶町は「元」鍛治町となり、その際「町」の文字も、武士の町を示す「丁」になったのではないか、と勝手に推察してみた。だから、一般に使われている「元鍛冶丁」が藩政時代の町名としては正しいのだろうと個人的には思っているが、そうなると住居表示前の町名が「元鍛冶町」だった理由がわからなくなる。もしかすると「町」と「丁」の区別は、ある時期から余り意識されなくなっていたのかもしれない。ドン・キホーテの北東角に《元鍛冶丁》通りの標柱が建っていた。元鍛冶町は今の町割りでは赤線で示したこの辺り。
November 5, 2024
コメント(0)
-

日本赤十字産院の跡地(渋谷区広尾‐かつての宮代町)
かつての笄町 (こうがいちょう。今は港区西麻布の一部) を訪ねた折に、かつての宮代町 (今の渋谷区広尾) にも行ってみた。今は「広尾北公園」になっているこの辺りが、かつては宮代町だったと思われる。周囲にはいわゆる広尾っぽい高級そうなマンションがいくつも建っていた。そして、公園から坂を下ると日本赤十字社医療センターがあった。すごく大きな病院。母は時々「宮代町の日赤病院で産まれた」と言うので、きっと戦後になって坂の上からここに移転したのだろうな、とその時は思っていた。だけど、病院のウェブサイトを見てみると、1891年(明治24年)に飯田町から現在地に移転して以降、移転はしていない。どういうことだろう…と思いながらウェブサイトを読み進んでみると、「1972年(昭和47年)11月には日本赤十字社産院と統合」と書いてあった。この「産院」が宮代町にあった、ということか…プチ発見を喜びながら更にネット検索をすると、次のような文章を見つけた。「日赤産院は渋谷区宮代町にあって、白亜の高層建築日赤中央病院と隣り合わせであるから同病院の一病棟でもあるかのように見られるが、産院と病院とはそれぞれ特異な性格を持っていて産院はもちろん独立して存在しているのである。」「大正10年4月、日赤本社は直営の産院を設立。」(以上、医学書院1952年2月発行「助産婦雑誌1巻2号」より)「独立して存在しているのである」のくだりから、病院と一緒にされたくない産院側の強い気持ちが伺われるが、母のような一般人から見れば、当時から病院も産院も「病院」だったのだろうと思う。自分のルーツをまた一つたどることができた。
November 1, 2024
コメント(2)
全7件 (7件中 1-7件目)
1










