2012年01月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-

いまだからこそ老子道徳経を学ぼう
老子道徳経は、中国の春秋時代の思想家の老子が書いたと伝えられている。道經と徳經とを合わせて八十一篇からなる。 老子については、春秋時代末の楚国の役人で、道家の創始者であるとされている。しかし、諸説あり、架空の人物であるとする説もある。教えは「無為」を至上としている。 ともあれ、日本では、老子道徳経が独訳や英訳されて後に理解が深まったという曰くがある。中国は近い国として古来から大きな影響を受けていながら、漢文としてしてのみ解釈してしまう官学の弊害が出た結果である。 型どおりのセオリーに固執し、自由でオープンな議論や創作を封鎖する状況は依然として変わっていない。 にほんブログ村 クリックをよろしく
2012.01.18
コメント(0)
-
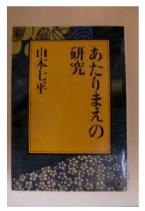
手っ取り早くある言葉にまとめてしまうこと
新年を迎えた。自分を含めて人の考えや主張を他の人に伝えたり、論評するときに、くくりとして手っ取り早くある言葉にまとめてしまうことの短絡性について、これをどのようにとらえていく必要があるのかということを考えてみた。 山本七平 氏は、いろいろと論評されて来た人物の一人である。この度、氏の「あたりまえの研究」を読んだが、氏の論点を少しは理解ができたと思う。手っ取り早くある言葉にまとめてしまうと、氏は二項対立の論理を基盤にしているように感じた。例えば、宗教としての規範を持つ国と持たない日本、一神教と多神教、砂漠とモンスーン等。 ただ、これを基盤にして論じるあまり、「あたりまえ」の概念の中に入れることが矛盾することまで、無理矢理押し切ってしまっているとも感じた。この辺りに誤解の原因と論理の脆弱性があるのだろう。もう少し他の著書を読みながら考えてみたい。 クリックをよろしく!!
2012.01.15
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
-

- ちょっと、お出かけ。
- ご ぶ さ た
- (2025-02-08 16:53:39)
-
-
-

- フライフィッシング【flyfishing】
- ウエットフライ ティールブルー?
- (2025-02-17 12:57:36)
-
-
-

- キャンプを楽しむ方法
- 最新 大型風防板 ウインドスクリーン…
- (2025-02-17 13:50:17)
-






