PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
Comments
まだ登録されていません
カテゴリ: 観照 [再録]
さて、今回の主目的である講座「平清盛とその時代」の内容です。
3つの講義を聴講しました。 [観照まとめ:2013年2月時点]
「平清盛とその時代」 木戸雅寿氏
「近江の緑釉陶器と日宋貿易」 畑中英二氏
「平家物語と祇王-妓王寺と祇王井-」 行俊 勉氏
木戸、畑中両氏は滋賀県教育委員会文化財保護課、行俊氏は野洲市歴史民俗博物館所属の専門職の方々です。
当日、「近江水と大地の遺産2」として発刊されたばかりのこの A4サイズの冊子が
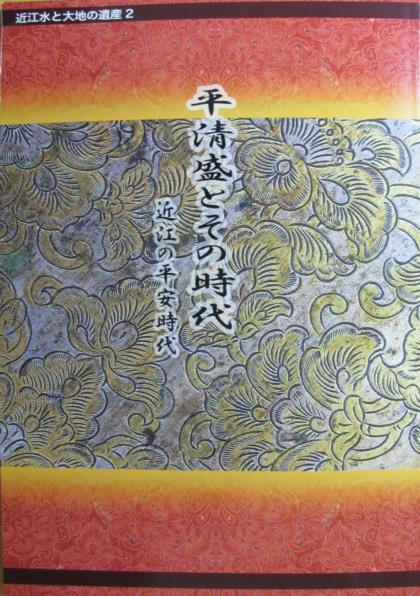 講座資料として配付されました。
講座資料として配付されました。
「その時代」とは「近江の平安時代」に焦点をあてるという意味
簡単にご紹介します。
<< 平清盛とその時代 >>
木戸講師は、この配布冊子の概略案内という主旨で、平清盛の時代において近江が関わった史実と史跡を紹介されました。講義に出てきた関係人物と近江の関連史跡をまとめると、ほぼこんなリストになります。
*西行(=佐藤義清、元北面の武士) 近江にある西行伝説
西行水と泡子塚(米原市醒ヶ井)、西行屋敷跡(大津市、現瀬田小学校敷地内)
*源義朝 平治の乱の際、敗走し途中で武運長久を祈った神社
還来 (もどろき) 神社(大津市) 白羽鏑矢を献じたという。ここで頼朝と合流。
*源頼朝 平治の乱で敗走する頼朝が逃げて身を隠した寺
大吉寺(長浜市)この後、池禅尼による清盛への歎願で伊豆への流刑にとどまる。
*平重盛 日本海と琵琶湖を結ぶ運河計画を抱いたのだとか。久安6年(1150)ころ。
*源義経 遮那王と呼ばれていた牛若が、比叡山を脱し、奥州平泉をめざします。
義経元服池、白木屋(=義経宿泊の館)、烏帽子掛けの松、義経元服の盥
鏡神社 (すべて、竜王町・鏡の里)
*祇王・祇女 清盛が寵愛した白拍子の姉妹の故郷、祇王伝説
祇王井、妓王寺、祇王屋敷跡、土安 (てやす)
*木曽義仲 寿永2年(1183)に上洛、朝日将軍と称されるが、1184年頼朝軍に敗れる
義仲寺、今井兼平の墓 (ともに大津市)
*平宗盛・清宗父子 平氏の終わりは壇ノ浦ではなく、近江が平氏終焉の地
宗盛胴塚(野洲市・近江国篠原宿)、清宗胴塚(草津市・「勢多」(野路))
私は2011年来、近江探訪の企画に結構参加してきましたので、史跡探訪は数カ所を残すだけになりました。
<< 近江の緑釉陶器と日宋貿易 >>
畑中講師の講演は、前段として唐三彩と奈良三彩の話。そして緑釉陶器の話に展開されました。8世紀、奈良時代の終わりころから11世紀前半にかけて緑釉陶器が造られていたそうです。近江では平安時代中期(10世紀)、主に食器を量産していたようです。それが11世紀前半になるとぱたりと消滅します。それはなぜか。平忠盛(=清盛の父)が日宋貿易を始め中国から陶磁器を大量に輸入したためだそうです。おもに青磁の代替品であった緑釉陶器が中国製陶磁器の大量輸入により、その存在意義を失うのです。
この日宋貿易による蓄財が、平家勃興の主要因になったのだといいます。
甲賀市春日北遺跡出土の緑釉陶器の紹介や、大津市関津遺跡出土の輸入陶磁器その他の実例紹介がありました。
私は、京都国立博物館の常設展示品で唐三彩そのものをよく見ていたのですが、深くは考えていませんでした。唐三彩が墓に埋葬する副葬品目的で造られたものであることと、20世紀に発見されるまで、その存在があまり知られていなかったということを今回初めて知りました。
唐三彩と奈良三彩の識別法を教えていただいたのが興味深いことでした。
<< 平家物語と祇王-妓王寺と妓王井- >>
行俊講師は、レジュメを準備されており、それにそっての講演でした。
いくつか要点をご紹介します。
*祇王、妓王、義王のいずれも様々な文献での表記に使われているとのこと。
大字○○という8つの地域が明治22年(1889)に町村合併して「義王村」が誕生。明治27年8月、「祇王村」に改称されたのだとか。
*白拍子としての舞姫時代に「妓王」を使い、尼に出家した以降に「祇王」を使うのが多いイメージがあるようだとのこと。
*「ぎおう」は実在したのか? 伝後白河法皇宸筆の「現在過去牒」(長講堂所蔵)、建暦2年(1212)源智造立の阿弥陀如来立像の像内納入・結縁交名にも名が記されている(浄土宗所蔵)。やはり実在したのでしょうということ。
*京都の祇王寺は真言宗大覚寺派の尼寺。野洲市中北の妓王寺は浄土宗の尼寺。
*現在は「祇王井川」と呼びますが、本来の呼び方は「祇王井」なのだとか。
用水のことを「ユ」または「イ」と呼ぶのだそうです。
野洲川を水源とし、三里(約12km)の長さのある古くからの用水で、地元では大井とも呼ばれているのです。
本来は、この地域の荘園の治水のために開発されたものではないか。限られた水量を村々が共有・分有せざるを得なかった歴史と祇王伝説が重ねあわされた上で、祇王井として維持管理されてきたのではないかというご説明と理解しました。
この他、現地を探訪して見ていた北村季吟の句(石碑)や、平家終焉の地についても具体的な説明がありましたが、省略します。
この講演を聴き、祇王と祇王井について、過去の見聞の再整理ができてよかったと思っています。
講座は予定どおり終了し、この後、博物館2階にある企画展示室で、野洲市教育委員会文化財保護課の花田氏から、テーマ展「木部天神前古墳と御明田古墳」について、展示品の解説をお聞きしました。
これらの古墳発掘調査からわかるのは、この野洲において、御上神社がある山側と、これら発掘古墳のある湖岸側と、それぞれに大きな勢力を持った人々がいたのではないか。それが御上神社と兵主神社という大きな神社が現存していることにつながるのではないか。また、湖西の方で勢力のあった人々のことは記録に残っているのだが、湖東のこの地域は記録がほとんどないけれども、考古学的な発掘結果が歴然と大きな勢力を有した人々の存在を裏付けている。
これは私が受けとめた要点ですが、具体的なご説明を興味深く拝聴しました。
大岩山から発掘された銅鐸群と併せ、大規模古墳があったこの野洲という地域に一層のロマンを感じる次第です。
このあたりで、今回の観照記録とします。
ご一読ありがとうございます。
【 付記 】
「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。
ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。
再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。
少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。
補遺
唐三彩 :ウィキペディア
唐三彩 :「考古用語辞典」
施釉陶の出現-奈良三彩 :「日本の陶芸史」
三彩有蓋壺 :「文化遺産オンライン」
(77)奈良三彩と唐三彩 :「奈良文化財研究所」
須恵器と緑釉陶器 :「大坂大学考古学研究室」
平安期の緑釉陶器 田中愛子氏
時代別 平安時代 :「陶器の歴史」
緑釉四足壺 :「文化遺産オンライン」
野洲市にある古墳
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
観照 [再録] 滋賀・野洲 銅鐸博物館にて -1 弥生の森 へ
観照 [再録] 滋賀・野洲 銅鐸博物館にて -2 博物館ロビーと展示室 へ
3つの講義を聴講しました。 [観照まとめ:2013年2月時点]
「平清盛とその時代」 木戸雅寿氏
「近江の緑釉陶器と日宋貿易」 畑中英二氏
「平家物語と祇王-妓王寺と祇王井-」 行俊 勉氏
木戸、畑中両氏は滋賀県教育委員会文化財保護課、行俊氏は野洲市歴史民俗博物館所属の専門職の方々です。
当日、「近江水と大地の遺産2」として発刊されたばかりのこの A4サイズの冊子が
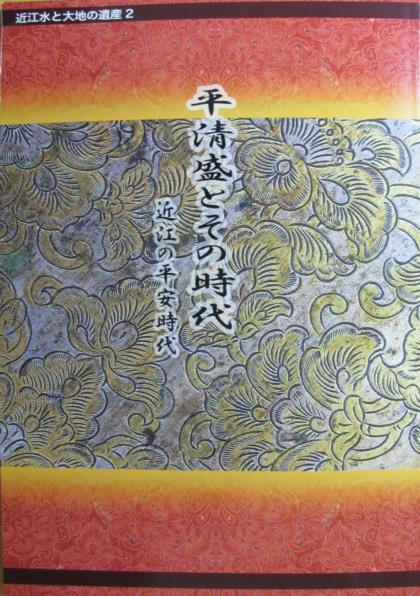 講座資料として配付されました。
講座資料として配付されました。「その時代」とは「近江の平安時代」に焦点をあてるという意味
簡単にご紹介します。
<< 平清盛とその時代 >>
木戸講師は、この配布冊子の概略案内という主旨で、平清盛の時代において近江が関わった史実と史跡を紹介されました。講義に出てきた関係人物と近江の関連史跡をまとめると、ほぼこんなリストになります。
*西行(=佐藤義清、元北面の武士) 近江にある西行伝説
西行水と泡子塚(米原市醒ヶ井)、西行屋敷跡(大津市、現瀬田小学校敷地内)
*源義朝 平治の乱の際、敗走し途中で武運長久を祈った神社
還来 (もどろき) 神社(大津市) 白羽鏑矢を献じたという。ここで頼朝と合流。
*源頼朝 平治の乱で敗走する頼朝が逃げて身を隠した寺
大吉寺(長浜市)この後、池禅尼による清盛への歎願で伊豆への流刑にとどまる。
*平重盛 日本海と琵琶湖を結ぶ運河計画を抱いたのだとか。久安6年(1150)ころ。
*源義経 遮那王と呼ばれていた牛若が、比叡山を脱し、奥州平泉をめざします。
義経元服池、白木屋(=義経宿泊の館)、烏帽子掛けの松、義経元服の盥
鏡神社 (すべて、竜王町・鏡の里)
*祇王・祇女 清盛が寵愛した白拍子の姉妹の故郷、祇王伝説
祇王井、妓王寺、祇王屋敷跡、土安 (てやす)
*木曽義仲 寿永2年(1183)に上洛、朝日将軍と称されるが、1184年頼朝軍に敗れる
義仲寺、今井兼平の墓 (ともに大津市)
*平宗盛・清宗父子 平氏の終わりは壇ノ浦ではなく、近江が平氏終焉の地
宗盛胴塚(野洲市・近江国篠原宿)、清宗胴塚(草津市・「勢多」(野路))
私は2011年来、近江探訪の企画に結構参加してきましたので、史跡探訪は数カ所を残すだけになりました。
<< 近江の緑釉陶器と日宋貿易 >>
畑中講師の講演は、前段として唐三彩と奈良三彩の話。そして緑釉陶器の話に展開されました。8世紀、奈良時代の終わりころから11世紀前半にかけて緑釉陶器が造られていたそうです。近江では平安時代中期(10世紀)、主に食器を量産していたようです。それが11世紀前半になるとぱたりと消滅します。それはなぜか。平忠盛(=清盛の父)が日宋貿易を始め中国から陶磁器を大量に輸入したためだそうです。おもに青磁の代替品であった緑釉陶器が中国製陶磁器の大量輸入により、その存在意義を失うのです。
この日宋貿易による蓄財が、平家勃興の主要因になったのだといいます。
甲賀市春日北遺跡出土の緑釉陶器の紹介や、大津市関津遺跡出土の輸入陶磁器その他の実例紹介がありました。
私は、京都国立博物館の常設展示品で唐三彩そのものをよく見ていたのですが、深くは考えていませんでした。唐三彩が墓に埋葬する副葬品目的で造られたものであることと、20世紀に発見されるまで、その存在があまり知られていなかったということを今回初めて知りました。
唐三彩と奈良三彩の識別法を教えていただいたのが興味深いことでした。
<< 平家物語と祇王-妓王寺と妓王井- >>
行俊講師は、レジュメを準備されており、それにそっての講演でした。
いくつか要点をご紹介します。
*祇王、妓王、義王のいずれも様々な文献での表記に使われているとのこと。
大字○○という8つの地域が明治22年(1889)に町村合併して「義王村」が誕生。明治27年8月、「祇王村」に改称されたのだとか。
*白拍子としての舞姫時代に「妓王」を使い、尼に出家した以降に「祇王」を使うのが多いイメージがあるようだとのこと。
*「ぎおう」は実在したのか? 伝後白河法皇宸筆の「現在過去牒」(長講堂所蔵)、建暦2年(1212)源智造立の阿弥陀如来立像の像内納入・結縁交名にも名が記されている(浄土宗所蔵)。やはり実在したのでしょうということ。
*京都の祇王寺は真言宗大覚寺派の尼寺。野洲市中北の妓王寺は浄土宗の尼寺。
*現在は「祇王井川」と呼びますが、本来の呼び方は「祇王井」なのだとか。
用水のことを「ユ」または「イ」と呼ぶのだそうです。
野洲川を水源とし、三里(約12km)の長さのある古くからの用水で、地元では大井とも呼ばれているのです。
本来は、この地域の荘園の治水のために開発されたものではないか。限られた水量を村々が共有・分有せざるを得なかった歴史と祇王伝説が重ねあわされた上で、祇王井として維持管理されてきたのではないかというご説明と理解しました。
この他、現地を探訪して見ていた北村季吟の句(石碑)や、平家終焉の地についても具体的な説明がありましたが、省略します。
この講演を聴き、祇王と祇王井について、過去の見聞の再整理ができてよかったと思っています。
講座は予定どおり終了し、この後、博物館2階にある企画展示室で、野洲市教育委員会文化財保護課の花田氏から、テーマ展「木部天神前古墳と御明田古墳」について、展示品の解説をお聞きしました。
これらの古墳発掘調査からわかるのは、この野洲において、御上神社がある山側と、これら発掘古墳のある湖岸側と、それぞれに大きな勢力を持った人々がいたのではないか。それが御上神社と兵主神社という大きな神社が現存していることにつながるのではないか。また、湖西の方で勢力のあった人々のことは記録に残っているのだが、湖東のこの地域は記録がほとんどないけれども、考古学的な発掘結果が歴然と大きな勢力を有した人々の存在を裏付けている。
これは私が受けとめた要点ですが、具体的なご説明を興味深く拝聴しました。
大岩山から発掘された銅鐸群と併せ、大規模古墳があったこの野洲という地域に一層のロマンを感じる次第です。
このあたりで、今回の観照記録とします。
ご一読ありがとうございます。
【 付記 】
「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。
ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。
再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。
少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。
補遺
唐三彩 :ウィキペディア
唐三彩 :「考古用語辞典」
施釉陶の出現-奈良三彩 :「日本の陶芸史」
三彩有蓋壺 :「文化遺産オンライン」
(77)奈良三彩と唐三彩 :「奈良文化財研究所」
須恵器と緑釉陶器 :「大坂大学考古学研究室」
平安期の緑釉陶器 田中愛子氏
時代別 平安時代 :「陶器の歴史」
緑釉四足壺 :「文化遺産オンライン」
野洲市にある古墳
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
観照 [再録] 滋賀・野洲 銅鐸博物館にて -1 弥生の森 へ
観照 [再録] 滋賀・野洲 銅鐸博物館にて -2 博物館ロビーと展示室 へ
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[観照 [再録]] カテゴリの最新記事
-
観照 [再録] 大阪 あべのハルカス初見聞… 2018.01.25
-
観照 [再録] マンホールのふた見聞考 -9… 2018.01.24
-
観照 [再録] マンホールのふた見聞考 -8… 2018.01.23
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










