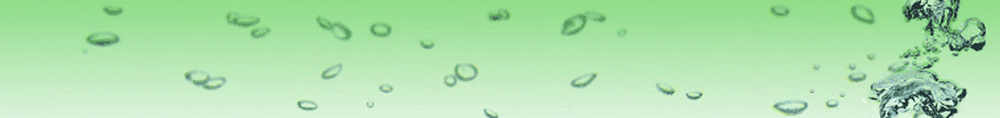テーマ: 年の瀬に思うこと(25)
カテゴリ: 年末回顧録
大阪で過ごした2018年は、NGOとの繋がりを新たに作り、またTwitterを始めて、環境研究系組織のコメントをフォローし始めることで、新たな思考アプローチを構築できた1年と言えるだろう。
もともと私は環境系NGOの仕事に興味があった。言い換えるとパブリックコメントに近い意見を国に向けて提言できる事に非常に魅力を感じていたということだ。私は社会人8年目で、多少ながら国の役人や研究所とのネットワークは構築してきており、そこから学ぶこと、考えること色々あった。しかし今年NGOと関わることで明確にわかったことがある。いや正確に言うと、大学時代に感じていた違和感の正体に近づくことが出来たのではないだろうか。
日本と海外での、国におけるNGOのプレゼンスは全く違うのだが、少なくとも日本の環境系NGOがやっていることは、誤解を恐れずあえて苦言を呈すると、理想を掲げて、声高に理想を叫ぶに過ぎない。
もちろんCOP24が開かれた今年、パリ協定において一定の枠組みで合意に結びつけた背景にNGOの力が大きくあったことは理解している。そして、この合意にハードルを乗り越えた末の合意であったかは、私の想像を遥かに超えたものだろう。しかしそれでも本当に大変なのは、それを実行するのはやはり国であり、テクノロジーであり、民間企業なのだと、私は思っている。
全ての領域において官民一体となって改革を行っていくことが必要である。そこには国、民間、自治体の役割がそれぞれ多分にある。国は制度を作る必要があり、その制度設計はひとつ間違えると、思わぬ結果をもたらす。エネルギー問題も当然で、例えばFITは、太陽光の未稼働案件を多数産むこととなり、バイオマスでは海外のパーム油での発電が横行し、環境被害がむしろ助長されることとなっている。こういうことは制度が出来て、その中で市場原理に任せて始めてその制度設計の欠陥がわかることが多く、制度作成前にわかれというには酷な注文だ。ただし現在非難の的になっている、石炭火力発電のような、やる前から問題であることがわかっていることを認可してしまうような制度設計は、石炭火力発電を導入したい民間企業のロビー活動の賜物であろうが、残念ながら今の世界の潮流からすると、決して褒められることではない。ただし言い換えると、民間企業のロビー活動により、褒められるようなテクノロジーの導入に対して政府が後押しするような潮流を作ることができるとも言える。
私は今年短い期間ながら環境NGOの話を聞いたり付き合ったりする中で、彼らの特徴をラフに分析した。長所は市民の声として地方の情報を集めて、それを一つの大きな声にまとめあげ、提言する組織システムを持っていること。一方欠点は理想を現実のプロジェクトに落とし込むだけのリソースを全く持たないことに気付いた。邪推だが、そもそも民間企業を悪だと思って遠ざけてきた結果、テクノロジーと金と制度設計に関する戦略を持つということを一切してこなかったからなのではないかと思っている。
さて、この話の締めとなるが、NGOの長所を生かしながら、官民一体NGO一体で出来る何かが間違いなくあると何となく思えたのが、今年1年で気付いたことだ。そして社会人8年目にして、漸く民間企業にいる自分の役割がぼんやりと見えてきた1年だった。
以上が環境問題における私の立ち位置についての話だが、その他でも一つ大きな経験があったので触れておく。今年の漢字「災」の一つでもある岡山の豪雨、この復興ボランティアに参加した。真夏の暑い時期に汗だくになりながらも、チームで統制を取らされながら取り組んだ。現実のボランティア活動を体験できたことは、人生経験として間違いなく大きなものとなった。
もともと私は環境系NGOの仕事に興味があった。言い換えるとパブリックコメントに近い意見を国に向けて提言できる事に非常に魅力を感じていたということだ。私は社会人8年目で、多少ながら国の役人や研究所とのネットワークは構築してきており、そこから学ぶこと、考えること色々あった。しかし今年NGOと関わることで明確にわかったことがある。いや正確に言うと、大学時代に感じていた違和感の正体に近づくことが出来たのではないだろうか。
日本と海外での、国におけるNGOのプレゼンスは全く違うのだが、少なくとも日本の環境系NGOがやっていることは、誤解を恐れずあえて苦言を呈すると、理想を掲げて、声高に理想を叫ぶに過ぎない。
もちろんCOP24が開かれた今年、パリ協定において一定の枠組みで合意に結びつけた背景にNGOの力が大きくあったことは理解している。そして、この合意にハードルを乗り越えた末の合意であったかは、私の想像を遥かに超えたものだろう。しかしそれでも本当に大変なのは、それを実行するのはやはり国であり、テクノロジーであり、民間企業なのだと、私は思っている。
全ての領域において官民一体となって改革を行っていくことが必要である。そこには国、民間、自治体の役割がそれぞれ多分にある。国は制度を作る必要があり、その制度設計はひとつ間違えると、思わぬ結果をもたらす。エネルギー問題も当然で、例えばFITは、太陽光の未稼働案件を多数産むこととなり、バイオマスでは海外のパーム油での発電が横行し、環境被害がむしろ助長されることとなっている。こういうことは制度が出来て、その中で市場原理に任せて始めてその制度設計の欠陥がわかることが多く、制度作成前にわかれというには酷な注文だ。ただし現在非難の的になっている、石炭火力発電のような、やる前から問題であることがわかっていることを認可してしまうような制度設計は、石炭火力発電を導入したい民間企業のロビー活動の賜物であろうが、残念ながら今の世界の潮流からすると、決して褒められることではない。ただし言い換えると、民間企業のロビー活動により、褒められるようなテクノロジーの導入に対して政府が後押しするような潮流を作ることができるとも言える。
私は今年短い期間ながら環境NGOの話を聞いたり付き合ったりする中で、彼らの特徴をラフに分析した。長所は市民の声として地方の情報を集めて、それを一つの大きな声にまとめあげ、提言する組織システムを持っていること。一方欠点は理想を現実のプロジェクトに落とし込むだけのリソースを全く持たないことに気付いた。邪推だが、そもそも民間企業を悪だと思って遠ざけてきた結果、テクノロジーと金と制度設計に関する戦略を持つということを一切してこなかったからなのではないかと思っている。
さて、この話の締めとなるが、NGOの長所を生かしながら、官民一体NGO一体で出来る何かが間違いなくあると何となく思えたのが、今年1年で気付いたことだ。そして社会人8年目にして、漸く民間企業にいる自分の役割がぼんやりと見えてきた1年だった。
以上が環境問題における私の立ち位置についての話だが、その他でも一つ大きな経験があったので触れておく。今年の漢字「災」の一つでもある岡山の豪雨、この復興ボランティアに参加した。真夏の暑い時期に汗だくになりながらも、チームで統制を取らされながら取り組んだ。現実のボランティア活動を体験できたことは、人生経験として間違いなく大きなものとなった。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[年末回顧録] カテゴリの最新記事
-
2024年年の瀬に思う 2024年12月29日
-
令和5年の年の瀬に思う 2023年12月23日
-
令和三年の総括 2022年01月03日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.