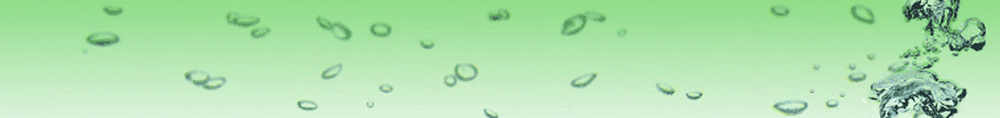全160件 (160件中 1-50件目)
-
『神話でも戦争美化でもない靖國神社』を読んで
読書をしたらその振り返りをブログにしようと一時期は頑張っていたが、もはやそのブログもこっちとライブドアブログの乱立及び五年ほどサボっていることが分かりました。年末の振り返りは今でも毎年こちらに書いているので、こちらで復活しようと思います。ということで本題本書は東條英機のひ孫にあたる東條英利さんと、近代史研究科であり神社の知識も深い久野潤先生の対談本。まず率直な感想で言うと、いかに自分がまだ歪んだ歴史観から脱せておらず、また知識も浅いことを認識し、忸怩たる思いだ。対談本とあって読みやすく、一気に2回読んだが、まだ咀嚼しきれていない。そんな状況ではあるが整理したい。【靖國神社の建立】もとは地方での国士の殉難者を招魂祭として一時的に場を整えて執り行っていたものが、遂には恒久鎮座の社殿を構えるに至ったもので、建立は明治二年の東京招魂社が前身、靖國神社と社号を改めたのが明治十二年。御柱は約二四六万六千あり、その大半はもちろん大東亜戦争での殉難者。ただし忘れてはならないのが、これは明治維新において国のために命を捧げた人達、例えば吉田松陰らも鎮座されているのであって、決して大東亜戦争賛美のための神社ではない。【国士殉難者鎮魂のための神社】そもそも日本の歴史を辿れば、殉難者を神様として祀るという行為は、神武東征の際に命を落とした瓊瓊杵尊を祀った龜山神社に端を発する。それ以来神話ではなく実在の人物が御祭神となる神社は数多く建立されてきた。残念ながらルール上官軍側ではない人達は祀られていない。過去に西郷隆盛など賊軍とされた側の人たちも合祀してはどうかという動きがなかったわけではないが、結果としては未だ合祀されるに至ってない。また、靖國神社には軍人以外が祀られているのも大きな特徴。というわけで、靖國神社だけが明治以降にできた戦争賛美のための新たな風習という言説は、全くの嘘。また形は違えど、殉難者を鎮魂し顕彰するという意味での石碑や博物館は世界各国に見られるものであって、日本だけが非難される話では決してない。【靖國神社のイメージ】靖國神社は、歴史ではなく公民で、国際問題に取り上げられる神社として教育される。靖国問題として学生は靖國神社を認識する。これが一番悪いイメージを植え付けられる諸悪の根源。ただし最近では学生のアンケート結果からも一時期より靖國神社に対しフラットに考えることが出来る土壌が出来ているようだ。戦後取り壊しの対象になりかけた靖國神社の生き残り戦術でもあったかもしれないが、盆踊りをやって、楽しく慰霊しようじゃないか、という祭りが始まって、今ではみたままつりといって、年に一度催される夏の風物詩的イベントが開催されており、殉難者たちからしても、このように楽しい場を提供する神社という立ち位置になることは歓迎されるべきことではないかとのご意見であった。【靖国問題と政教分離】度々神社や奉納に公金が投じられることで訴訟に発展することがあるようだ。政教分離に抵触するからというのが表向きの理由だが、実際は共産系議員の偏った意図によって訴訟を起こしているようだ。全ての訴訟において違法の判決が出ているわけではないが、難しい線引きの中でそれぞれ判決が下されている。ただ、神道は経典もなければ、戒律もなく、およそ宗教的な色はなく、日本の慣習と言っていいようなもの。これを宗教として扱い、神社を宗教法人として内務省管轄から外し、結局神社そのものの影響力を日本から消し、弱体化させるのが、つまりは共産党の活動なのだ。また、A級戦犯合祀を中国側が抗議する動きもあるが、これも元を辿れば中曽根元総理が参拝した時に、朝日新聞が猛反発、これに呼応して中国側が反発。これ以降毎年のように靖國神社参拝が問題化した。さらには在任期間中参拝し続けた小泉元首相の靖国参拝最後の年に、日経新聞記者が富田メモという天皇陛下の非公式の言葉の記録が流出し、A級戦犯への議論が紛糾した。このようにして靖国問題は国内の反日分子や経済的関係性から作られ、大きくされている。【日本を守ってきた人への感謝】神道の根底にあるのは自然信仰、皇祖霊信仰、御霊信仰などであり、それが日本人の信仰心を形作ってきた。言い換えると、おかげさまの心を大事にしてきたのだが、今その心が薄れつつある。今や人は、自分の人生一度きり、自分のためにやりたい事をやろう、という風潮が主流だが、果たして幸せを掴むことは出来ているのだろうか。おかげさまの心があると、いかに人や自然に生かされているかに気付くことができ、人に感謝する心が生まれてくる。なによりご先祖様を大切にすることは、今の自分の存在に感謝する心である。神社のお参りに打算的に願い事する人も多いようだが、感謝を述べ、またお礼参りをして神様に報告をする、といった姿勢で参拝するのが本来のあるべき姿。この辺りは異論の余地もないことで、私も以前より共感する点だ。【自問自答と雑感】恐らく本来功績を残して神社に祀られるのは、その功績を称える賛同者が多い、また時代が過ぎて振り返った時に、その功績が大きい場合に、その気持ちが神社建立を後押しするし、人々の支えによってその存続が可能となる。今の私の明治維新の理解は、やはりペリー来航以来、西洋列強に立ち向かうべく、国のあり方を見直さなければ飲み込まれてしまう恐れがあったからこそ、一致団結する必要があり、結果として大政奉還という国の中心的存在を天皇陛下に戻すに至った。その結果として日本は急激に近代化を遂げ、西洋列強と肩を並べ、遂には日露戦争に勝った。確かに日本のために戦った人がそこにはいた。しかし大東亜戦争時は、メディアが戦争を煽り人々を熱狂させ、軍部は国のために殉難することこそが国民の進むべき道と洗脳し、現存の靖國神社に祀られるというある種の死後の魂をも保証する形で戦争に参加させた。そういう意味において、靖國神社は興奮剤として利用された点がないとは言えないだろう。勿論これも今の価値観の人間が判断したらそう見えることなので、非難するわけではない。当時の世界情勢からすると、共産主義の脅威、西洋列強の傲慢さ、植民地化の恐れ、エネルギー安全保障の危機など、全方位で日本は危機に陥っており、より強固な団結は必要だった。そう思うと、なるほど東條英機の幻の遺書にある、『しかし国際的の犯罪としては、無罪を主張した。いまも同感である。ただ力の前に屈服した。自分としては国民に対する責任を負って、満足して刑場に行く。ただこれにつき、同僚に責任を及ぼしたこと、また下級者にまでも刑が及んだことは実に残念である。天皇陛下に対し、また国民に対しても申し訳ないことで、深く謝罪する。』が全てなのかもしれない。軍部はある種今風に言うと、天皇陛下を政治利用したのであり、靖國神社も利用した。そして左翼風に言えば国民を捨て駒として戦わせ、靖國神社に祀られるという事を担保に、お国のために命を捧げさせた。横井庄一氏と小野田寛郎氏の二人が日本軍の生き残りとして見つかったが、この二人の対照的な主張、つまり一方は捧げさせられたのであり、もう一方は捧げたという受け取り方の差異こそが、当時の日本人の心情を物語っているのではないか。この雑感を今後の思想構築の種としておく。
2025年09月25日
コメント(0)
-
2024年年の瀬に思う
2024年は自分の中で大きな動きのあった年だった。きっかけはなんともくだらないことではあるが、携帯ゲームに1ヶ月程度ハマったことだった。この時期の無駄を悔やみ、かつ視力までも犠牲にした反動で、本当にやるべきことに目を向ける意思が強くなった。一つ目はなんと言っても、おみくじアプリ制作の活動再開だ。今や生成AIが何でも生成してくれる時代、アプリのコーディング、コンテンツ作成、画像作成とも自分の手をかけずとも作り出せるようになった。デジタル製品の販売事業においては、製品戦略と販売戦略に注力し、コンテンツはデジタルで終わらせる時代になったといっても過言ではないだろう。これに関しては、「子曰、君子訥於言而敏於行」そしてもう一つは論語為政第二より、「子曰:導之以政,齊之以刑,民免而無恥;導之以德,齊之以禮,有恥且格。」に向き合ったこと。これまで何度か目にしたは一説であるにもかかわらず認識できていなかったことは自省すべきだろう。さて、これを認識した私は、次なるアナロジーに目を向けた。それは技術者の技術倫理観の問題だ。詳細は来年以降の探究に任せるが、これが私の理系人生としての天命なのではと勝手に思うようになった。来年異動してくる人への教育に向けて思想を形にしつつ、社内政治的な観点から、技術士を取得した上でこの思想を徐々に浸透させる事で、社内の技術思想を、さらには日本の技術思想を転換させ、技術立国の復活の一助になればと思っている。来年からは忙しくなる。
2024年12月29日
コメント(0)
-
令和5年の年の瀬に思う
今年は激動の1年だった。社会人生活においては管理職に昇格し、家庭においては第一子を授かった。一個人の存在であった私も、課長さんと呼ばれ、お父さんと呼ばれることとなった。毎年政治問題を考える年末回顧録が殆どだが、今年はあまり自分の身の回り以外に気を配る余裕がなかった。そんな中でも日本国史学会に顔を出し、新たなコミュニティとのコネクションが出来たのは大きな意味があったように思う。おかげさまで立場が個人から管理職であったり父親になったりするタイミングで保守的な思想が少しずつ確立してきた気がしている。過ぎたるは猶及ばざるが如し、中庸の考えもまた自分の思想の確立の一助となっている。ボーダレスのグローバリズム資本主義が、自作自演のエビデンスを盾になりふり構わず人類を相手に搾取している。しかもそこには命を救うだの世界を救うだのといった欺瞞に満ちた偽善で溢れかえっている。しかし、資本主義がイノベーションを産み、人類が未知の想像の世界を大きく広げたといって間違いない。こう考えるとやはり純粋で誠実な道徳性あっての資本主義でないと、社会は決して良くならないということがわかる。コロナ騒動によって、医療ビジネスの闇が暴かれた。政権の中枢に医薬業界から巨額の資金が流入し、それが何倍にも膨れ上がって国民の税金が業界に流出していく。御用学者がエビデンスと呼ぶにはお粗末な主張をお茶の間で流し、反対派は異常であるという空気を作り出し、国民の洗脳と対立構造が出来上がる。子育ても同じのようだ。母子手帳は戦後GHQが作り出した、母親への洗脳工作の道具らしい。母親は母子手帳を見て子育てを学び、これから外れることを恐怖するようになり、更には外れた親の子供は、自治体に拉致される仕組みまで作り上げている。こういう構造を見ると、現代の日本はどうもグローバリズム資本主義と社会主義が結託して出来上がっている社会に仕上がっているらしい。結局民間企業は国に献金をし、大量の税金が民間企業にキックバックされるが、結果民間企業が提供するサービスは国民の幸せには繋がっていない。幸せどころか、健康にも全く貢献しなかったのがコロナ騒動である。このような欺瞞に満ちた社会にあって私は管理職になり、親になったのである。社会にこのような危険が潜んでいる以上、私はその魔の手から部下なり子供なりを救ってあげる必要がある。そうなると結局その救いの手とは、逆の洗脳に他ならないのではないかと思うのが現在たどり着いている自分なりの答えである。今の若い世代はもはや何のために生きて、何のために社会人となっているのかわからないでいる。これから墨で真っ白な半紙に思想をしたためられるのだ。下手に指針なく学び始めた時、その思想は真っ赤に染まるのは、私の経験から言って間違いない。同じ轍を踏まないよう、丁寧に地道に少しずつ逆の思想へと導くのが課長の役割の一つであろう。一方子供はこれから成長していくものであり、私からの吸収も大いにするだろう。薫陶を与え、直接指導もし、大切なことは道徳心であることを学び、真に国に貢献できる人物に育てていこうと思う。さて薫陶を与えるにはまずは自らを律する必要がある。其の家を斉えんと欲するものは、まずその身を修む。「大学 経一章」私自身もまた正しい道を外れることなく生きていこうとここに誓う。四十にして惑わず、とはいかず、学問を志す程度であろうか。それでも偽善的国家現代日本において、学問を志しただけでも貴重ではないかと自分なりに及第点を与えながら、令和五年を締めくくろうと思う。
2023年12月23日
コメント(0)
-
2022年の年の瀬に思う
今年は2つのことについて大きな気づきがあったので、この2点に特化して考えを整理したいと思う。【日本とは】よくネット上で「日本がなくなる」という言説を見る。私自身も近々そのような日が来るのではないかと心配しているわけだが、改めて日本とは何かを深く考えた年だった。次に例えばもし中国が日本を侵略して同化政策を取ったとしたら、この場合そこにいた日本人の遺伝子はなくなる。この場合日本人がいなくなり中国に吸収されるという意味で日本が消滅する。このシナリオは数年後に明らかな脅威として認められないとも限らない。そしてもう一つの例として考え付くことこそ、今の平和な日本の延長にありながら日本がなくなるシナリオとして私が考えた「日本がなくなる」だ。それは、日本の文化が消滅するということだ。実はその意味では既にかなり消滅していると言ってもよい。戦後GHQによる日本無力化政策により、古き良き日本文化は黒塗りにされ、隠蔽され、忌避される対象とされてきた。恐らく戦後すぐは、表面的に消し去っても、人々の心に確かにあっただろう。しかし世代交代が進むにつれて、その政策は結実し、今や日本文化は風前の灯火となった。自然を崇め、勉学を大切にし、芸事にも長け、そして勤労により国を豊かにし、皆が幸せを享受してきた日本は今や、自然をコントロールできると勘違いし、受験のために教科書を暗記し、文化は金にならないと言い、お金のために働き、己だけでも勝ち組になろうと必死に生きているが、世界でもトップクラスの自殺率を誇り、自分も他人も、そして日本という国も愛することが出来ない不幸な人たちの集まりになってしまった。既に海外の移住者も多くなり、ハーフやクオーターも珍しくない日本。戦前に存在した極東アジアの血は少しずつその色を変えているが、その血が日本色に染まる限り、日本は日本であり続けるのだと思う。しかし海外の圧力や左翼の破壊工作により、不穏な移民や難民が日本になだれ込み、血の色は残念ながら少しずつ元の色から遠ざかる。エントロピーは増大するため、元の色に戻ることはないだろう。こんなことを考えていると、三島由紀夫は生前、産経新聞に「このまま行ったら日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜け目がない、或る経済大国が極東の一角に残るのであろう」と50年以上前に残していたことを思い出した。【お金】人々の生活はもはや全てがお金によって得たサービスやモノによって成立している。だから我々はお金がないと生きることが出来ない状態になってしまった。しかし実は、ちょっと前まではここまでお金に依存しきってはいなかったことは忘れてはいけない。人々は親子関係や地域の人の支えによって、無償のサービスやモノを提供されていた。それがいつからか、お金を稼ぐために親子関係を割き、家庭内でやることもお金で解決するようになっていった。また地域の人は他人になり、無償で町の人で支えあうのではなく、仕事としてサービスを提供したり売買をしたりするようになった。お金とは信頼である、と言うが、確かに人々にもはや信頼はなく、お金に信頼が着くようになってしまったようだ。そしてお金で人が動くようになることで、街を豊かにすることが出来なくなったのではないかと思うようになった。昔はそもそも町を豊かにするために、その町の長が待ち人をけん引して、必要なサービスやライフラインやセーフティーネットを構築していた。つまり町は人々の信頼と共助により成り立っていた。しかし今はお金で動く時代。つまりお金がその自治体にあるかないかで、供給能力があるにもかかわらず供給できないという残念な不都合が生じる。これは中央、つまり国の方針により予算配分がされるからだろう。では国は効率的に予算配分しているのか。性善説に基づけば、最適ではなくとも、国の成長に必要であると思われることに集中配分される。配分の結果ある分野で困ることはあっても、国民の生活の質は上がるだろう、と考えるわけだ。しかし現実は違う。それはコロナ対策費用に多額の予算が計上され、必要なお金はあからさまに医療業界に消えたことにより明白となったように思う。私のコロナに対する見方は、よく言われるウイルスとワクチンの両建てによるマッチポンプ構造。ウイルスという恐怖に慄き、ワクチンという救世主にお金を出す市民。残念ながら結果だけ見るとただお金が吸い上げられているだけだ。コロナによって炙り出されたこのマッチポンプ商法は、実は色々な業界で生み出されている。そのたびに市民が無駄に金を吸い上げられていると思うとやるせない。無駄なのだ。何故なら何も意味のあるものを生産していないから。敢えて言えば生産しているのは不安や恐怖と安心感、つまり人々の感情の揺らぎぐらいだろう。GDPという数値は、国民の生産量を表す指標としてよく使われる。しかし、マッチポンプによりGDPを高くすることが出来ると気づいてしまった。ということは、GDPが人々の幸福度合いに直結することは全くないのだ。日本はGDP世界3位の経済大国だが、もはや世界3位も虚しく響くのみだ。日本は加えて賃金が平均して横ばいが続き、ジニ係数は上昇している。この意味するところは、中間層以下が金銭的に貧困になったということだ。そして前半で述べた通り、人々の信頼によるサービスやものの提供もなくなってしまった。加えて国は無駄な生産にもかなり力を入れている。そりゃ貧困と感じるに決まっている。【まとめ】日本の危機について、今年は二つの視点から考察してみた。まず一つ目は日本文化が消滅しつつあり、人々が自信を失っていること。二つ目は人々が金に支配され必要なサービスを享受できなくなったこと。これをシンプルにまとめると、日本人は元々日本が持っていた文化とはまるで違うグローバル主義の拝金主義に陥っている状況にあるということだ。日本人は約80年という時間をかけて文化を失ったわけで、これを一朝一夕に取り戻すというのは不可能だ。我々世代は、取り戻す未来を夢見ながら、社会の流れに抗いながら、辛抱強く次世代の若者に失った文化と精神を伝えていかなければならないと強く感じた年だった。来年は三島由紀夫の著書をいくつか読もうと思う。
2022年12月31日
コメント(0)
-
令和三年の総括
毎年恒例で一年を振り返るこのブログも今回で10回目、10年続けていると思うと感慨深いかと言えばそうでもなく、淡々と10回目を迎えている。ただいつもは前年のブログを振り返り、自分の変化と成長を感じながら一年を総括するが、今回は10年前から振り返ってみた。10年前というと東日本大震災の年で、日本は絶望の淵に身を置きながらも復興のために強い気持ちで立ち向かっていたと感じていたようだ。今年はコロナ対策としてワクチンを打ちながらも自粛ムードで3/4が過ぎ、なんとか最後の数ヶ月は束の間の普通を楽しむ人もいれば、年末に登場したオミクロン恐怖の扇動に呼応して自粛を続ける人がいて、結果としては大人しくも何とか活動は見られる一年だった。この感想を比べると、この10年で日本は全体として元気がなくなったのかと虚しい気持ちになる。さて自分のこと。今年は神道とロスチャイルドに出会った。去年までお茶外交のNPO法人に身を置き、日本の良さを世界に発信するという使命感で活動をしていたが、どうやら私は日本の文化も歴史も何も理解してなかったようだ。なんとも恥ずかしい思いだが、学びとはいつも点であり、そのうちその点と点が線になるもので、これが面になるように日々勉学に励むしかない。さて、本質的な歴史に触れた今、私の社会の見方は大きく変わりつつあるように思う。本来の日本が持つ神道精神は日本の(そして開国以降は世界人民の)ためにあった。しかし情報統制により現在跋扈する為政者は、SDGsという絶対的で偽善的なな正義を振り翳し、社会主義的政策を推し進める。社会貢献意欲の高い優秀な人たちは、本来国民や歴史文化を守るべきであるにもかかわらず、SDGsを錦旗の如く掲げてこれを破壊しようとしている。GHQが作り上げた自虐史観及び徹底的に隠蔽された日本の歴史と神道精神は甚大であり、GHQの戦略の凄まじさを認識した。環境問題に興味を持った高校時代、環境問題は社会的問題と気付き研究した大学時代、人脈を作り政治に興味を持った社会人初期、何もわからず左翼的活動に共感した大阪時代、出会った価値観はどちらかと言うと現代情報統制社会の産物であったように思う。しかしコロナに端を発したこの極端で偽善的なうねりの中、疑問を持ち、情報に流されず学び考え続けてきた結果、私は神道に出会うこととなった。これは必然であるように思う。私はこれから神道をより深く学び、それを実践し、日本という素晴らしい国を守る一助となりたい、そう思うようになった。そんな令和三年だった。
2022年01月03日
コメント(0)
-
2020年 年末回顧録
今年も一年が終わろうとしている。 今年は殆どの人にとって人生が変わった大きな一年だったと思う。コロナと言う未曾有の脅威に人々が混乱し、人々の生活は大きく変わった。私に関して言えば、外との接触が制限され、自分の時間が増えたし、テレワークも一般的なものとなった。業種によっては売り上げが激減し、倒産を余儀なくされた人もいる。医療従事者は正義感から仕事に向かうも、限界に近い状況に追い込まれている人達が少なくない。 しかし私にとって今年が特別大きな意味を持っていたのは、コロナによるものだけではない。というのも今年から一人の女性との付き合いをスタートさせ、更には結婚にまで至り、人生の大きな転換点を迎えた事があり、もはや個人の自由のもとに生きることは出来なくなった。 この二つの事は本当に多くの事を考えさせられた。 今年は長期政権を築いた安倍内閣も終わり、菅内閣が誕生した。自助共助そして公助と言うフレーズが話題となった。野党は執拗にこれを叩いたが、これは誰を主眼に置くかでこの考え方は変わる。つまり自分が生きると言う事において、周りや国を信用してもダメで、やはり生きる知恵と行動は絶対的に必要である。しかしコミュニティに属する人としては、間違いなくコミュニティを良くするために協力し合うのがいい。これは所謂ゲーム理論でいう囚人のジレンマ構造を持った多人数ゲームだ。つまり自分が少しの代償を払ってでもコミュニティ全体が共助する事で、コミュニティ全体がより良いものになるという事だ。この協調の創発には相手が特定される事が望ましいが、残念ながら都心においては、隣人すら赤の他人であり、このような共助は望むべくもなく、結果金銭を払って共助できる部分も自助に頼ることとなる。裕福な人はいいが、そうでない人は地方であれば共助で得られる筈のものも得る事が出来ない。これが都市化の大きな弊害の一つなのだろう。 この話の本質的なところは、信用というものを本来の意味での信用として捉えていない点にある。人との関係性が信用によってではなく金銭によって繋がっていると言う、なんとも悲しい現代的価値観である。 そして政治家や公人と云うのは国家や地域の代表であり、公助のために政策を作り上げていく事を生業にするのもである。当然自分の利益(金銭のみならず)のために治政してもらっては困る。そんな中政治家のやっていることといえば、メディア統制による国民への欺瞞と、行きすぎた経済至上主義的法改正。そしてその裏で蠢く金食い虫達。為政者達もまた、国を治める立場にありながらそれをせず、金によって結ばれた関係性で物事を判断しているのだろう。だから誰からも信頼されていない。 どうやら自分勝手の金儲け主義がいよいよ日本社会に根付いてしまったようだ。日本が元来持っていた儒教精神は戦後教育の中で徐々に破壊され、自由と自己責任のもと生きる事を善とする思想が浸透してしまった。確かにそれにより一個人の力で若くから巨万の富を得る人が現れたし、自己表現の世界において、世界的に活躍する人が現れた。そういう人たちは自由社会の中で輝く事ができた。しかしそれは一握りである。その他大勢はどうだろう。泳げない人間がいきなり大海に放たれても泳ぎ出す事ができないように、自由という社会に身を置いても、自由に事故を表現し生きていける人間なんて殆どいないのだ。だからある程度の統制があって、レールがあって、そのレールの上を生きていく道を選ぶ人が多いのだ。勿論事なかれ主義で変化を求めない事が正しいとは思わない。寧ろ私自身どちらかというと人が進むレールを踏み外しながら人生を歩んできた側だ。だから自由にしたい人が自由を奪われるようなのも間違っていると思っている。しかし自由を謳歌するには倫理道徳が備わっていてこそ許されるものである。今の社会は自由を履き違えている、そう思わずにはいられない。 さて現在の憂国日本を創り上げた張本人である米国はどうだろう。今年は世界の今後を占うアメリカ大統領選挙があった。結果国民は二分し、強烈にお互いがいがみ合った。投票には大きな不正が働いたとか、不正はデマだとか、誤情報の応酬でさらに憎悪が増幅。 こんな国の何を見習うべきなのか。GAFAのような企業が誕生する事がそんなに偉い事なのか。実態として一方では貧困が著しく進んでおり、弱者に寄り添った政治なぞ何もされていない。寧ろ無国籍企業がアメリカを統治し、彼らに都合の悪い情報は統制されるようになり、人権も剥奪され(投票行動の無効化)、まさに白い顔しただけの中国共産党のような様相だ。もはやアメリカという国は、金を持つものの金を持つものによる金を持つもののための自由を謳歌する下品な国である。 今年はパンデミックと世界政治の動き、そして自分の情報収集のやり方の変化から、本当に多感な一年だったと感じている。果たして自分はそんな社会において何ができるというのだろう。ただ大きな事をするには身の回りで出来てこそである。結婚を機に先ずは自分の家族という小さなコミュニティで、人情味溢れる家庭を構築しよう。そして会社における自分の立場が上がっていく中で、組織や社会に対して信頼関係とより良い社会創りに貢献しよう。そんな思いを強くする一年であった。
2020年12月28日
コメント(0)
-
2019年の総括
毎年恒例の一年の振り返りです。 今年はとにかく本当に学びと動きの多い一年でした。 まず学びとして大きかったのが、MMTの出現です。アメリカからMMTが持ち込まれたことで、財政健全化の是非について議論され始めた今、金融政策としてどうすることが日本にとっていいのか、今の知識では自分で判断できないと思い、貨幣について勉強しました。 少し話は逸れますが、私は元々ハードのインフラ技術者のレベルの低下を、国が抱える大きな問題の一つとして見ていました。これをどう解決すればいいのかについて、当事者としてずっと考え、少なくとも自分の目の届く範囲においては自分なりの考えを教育を通じて実行に移していました。しかしそれはミクロの問題ではよくなるかもしれないけれど、マクロ的な日本スケールでの技術レベルの低下は避けられないことはわかっていました。 そこでこのMMTを通じて結びついたのが財政政策と技術力の関連性。つまり元々日本が技術力を伸ばしてきたのは、その技術が必要とされ、成長させる必要が常にあったから。そして衰退している今を作り出したのはこの逆で、もう必要とされなくなってしまったから。そこには国策が存在し、投資があるということが前提だったということ、これに気付いたわけです。もちろんこれを受けて企業の方針というものが存在するので、企業がそれに気付いて手を打っていれば、投資規模が減ってもどうにか出来たかもしれません。しかし企業は営利があっての活動であることから、長期的に手を打つのはよほど敏腕でない限り無理だったかと思います。ただいずれにしてもこのような状況を作り出した根本原因に気付けたというのが、今年の大きな学びでした。 さて次に動きの方ですが、今年は大きな動きが2つありました。 1つ目は友人の行なっているNPOに事務局としてボランティアで参加しているのですが、この躍進がめざましかった事。年初はまだ理念だけで動いており、それだけでは先がないと思っていたのですが、漸くビジネスとしての道筋が見えるにまで昇華されました。そして普段特に何もサポート出来てない中で、その道筋を見るきっかけとなった機会に自分が多少なりとも関われた事が何よりも大きかったです。 2つ目は自分の会社内での話ですが、社内ベンチャー的な制度において、自分の提案が採択された事。アフリカにおいて発電ビジネスを展開したいということが採択されたのですが、既に採択されて動き出している別のアフリカでの発電プロジェクトがあり、これがたまたま最近自分の部署に異動してきた人のプロジェクトで、これに相乗りしながら動く事になりました。 さて、この二つは一見すると全く違うビジネスですが、理念としてはかなり近いものがあります。それはどちらも世界における日本のプレゼンスに危機感を抱き、これを真っ当な日本人としての調和の精神をして変えていく、という事です。私がこのように思う背景には大きく2つあります。(NPOの代表が思う背景はもっと現場で感じているものでありもっと別にあります。私は所詮日本国内にいて思う程度) 1つ目は多くの民主主義国家において保護主義が世界を席巻するようになり、世界中が憎悪に包まれているように感じます。経済成長が鈍化し、これに国民が憤慨し、個人主義が必要以上に強くなってしまった、完全なる民主主義の失敗です。 そしてもう一つが中国の台頭です。社会主義ながらも民意をコントロールし、金にものを言わせ、国としては明かに力をつけてきている。もちろんその成長の背景には中国国民から人権が剥奪され、また不要な人間が切り捨てられるという犠牲の下に成り立っており、許容し難い事態ではあるものの、結果として中国が世界をじわじわと支配しつつあることは否めないように思います。私は中国国内においてそのような問題が起こっている事に対して口出しすることは、ある種の内政干渉であり避けますが、世界的にも金と軍事力にモノを言わせ支配を強めていく状況は、世界の平和と秩序を守るという観点から何としても食い止めなければいけないことと思っております。 私たちのこれらの活動を通して、微力ではあるかもしれないですが、間違いなく世界の平和の為になると信じて、2つの活動はスタートを切りました。来年はこれらの活動を育てていき、仲間を増やし大きな力に変えて、日本の再建に役立っていきたいという所存です。
2019年12月31日
コメント(0)
-
2018年の総括
大阪で過ごした2018年は、NGOとの繋がりを新たに作り、またTwitterを始めて、環境研究系組織のコメントをフォローし始めることで、新たな思考アプローチを構築できた1年と言えるだろう。 もともと私は環境系NGOの仕事に興味があった。言い換えるとパブリックコメントに近い意見を国に向けて提言できる事に非常に魅力を感じていたということだ。私は社会人8年目で、多少ながら国の役人や研究所とのネットワークは構築してきており、そこから学ぶこと、考えること色々あった。しかし今年NGOと関わることで明確にわかったことがある。いや正確に言うと、大学時代に感じていた違和感の正体に近づくことが出来たのではないだろうか。 日本と海外での、国におけるNGOのプレゼンスは全く違うのだが、少なくとも日本の環境系NGOがやっていることは、誤解を恐れずあえて苦言を呈すると、理想を掲げて、声高に理想を叫ぶに過ぎない。 もちろんCOP24が開かれた今年、パリ協定において一定の枠組みで合意に結びつけた背景にNGOの力が大きくあったことは理解している。そして、この合意にハードルを乗り越えた末の合意であったかは、私の想像を遥かに超えたものだろう。しかしそれでも本当に大変なのは、それを実行するのはやはり国であり、テクノロジーであり、民間企業なのだと、私は思っている。 全ての領域において官民一体となって改革を行っていくことが必要である。そこには国、民間、自治体の役割がそれぞれ多分にある。国は制度を作る必要があり、その制度設計はひとつ間違えると、思わぬ結果をもたらす。エネルギー問題も当然で、例えばFITは、太陽光の未稼働案件を多数産むこととなり、バイオマスでは海外のパーム油での発電が横行し、環境被害がむしろ助長されることとなっている。こういうことは制度が出来て、その中で市場原理に任せて始めてその制度設計の欠陥がわかることが多く、制度作成前にわかれというには酷な注文だ。ただし現在非難の的になっている、石炭火力発電のような、やる前から問題であることがわかっていることを認可してしまうような制度設計は、石炭火力発電を導入したい民間企業のロビー活動の賜物であろうが、残念ながら今の世界の潮流からすると、決して褒められることではない。ただし言い換えると、民間企業のロビー活動により、褒められるようなテクノロジーの導入に対して政府が後押しするような潮流を作ることができるとも言える。 私は今年短い期間ながら環境NGOの話を聞いたり付き合ったりする中で、彼らの特徴をラフに分析した。長所は市民の声として地方の情報を集めて、それを一つの大きな声にまとめあげ、提言する組織システムを持っていること。一方欠点は理想を現実のプロジェクトに落とし込むだけのリソースを全く持たないことに気付いた。邪推だが、そもそも民間企業を悪だと思って遠ざけてきた結果、テクノロジーと金と制度設計に関する戦略を持つということを一切してこなかったからなのではないかと思っている。 さて、この話の締めとなるが、NGOの長所を生かしながら、官民一体NGO一体で出来る何かが間違いなくあると何となく思えたのが、今年1年で気付いたことだ。そして社会人8年目にして、漸く民間企業にいる自分の役割がぼんやりと見えてきた1年だった。 以上が環境問題における私の立ち位置についての話だが、その他でも一つ大きな経験があったので触れておく。今年の漢字「災」の一つでもある岡山の豪雨、この復興ボランティアに参加した。真夏の暑い時期に汗だくになりながらも、チームで統制を取らされながら取り組んだ。現実のボランティア活動を体験できたことは、人生経験として間違いなく大きなものとなった。
2018年12月31日
コメント(0)
-
2017年の振り返り
個人的には東京と大阪への2回の引越しを伴い、慌ただしく落ち着かない1年だった。また関西での生活は初めてで、今のところ社外コミュニティの開拓も出来ておらず、見聞を広める機会を逸していることもまた、気持ちの面でも落ち着かない状況に拍車をかけている。さてそのような状況においても、何とか仕事以外の知識を広げようとしたものに、人工知能とシンギュラリティ、および量子コンピューターがある。人工知能はもはや流行りのワードとして、デジタルデバイスやシステムの全てに使われていると言っても過言ではない。そして10年前には無理と考えられていた、プロ棋士に囲碁で勝利するということも過去の話、今やプロ棋士を倒したアルファ碁に100戦全勝するアルファ碁ゼロが開発されており、この分野の成長の早さには正直度肝を抜かれてばかりだ。また全人口の知能をコンピュータの処理が上回るというシンギュラリティにおいては、コンピュータの処理能力の向上が前提になっているが、その上で量子コンピューターの活躍は必須。そしてその量子コンピューターを製作する会社がとうとう現れた。なぜか量子コンピューター元年はひっそりとした印象だったが、2年目となる今年は去年とは全然違う盛り上がりが期待される。こうなるといよいよ人工知能が現在の人に取って代わる流れが現実味を帯びることになる。ここでインフラ事業に目を向ける。というのは私がエネルギーインフラ関係の仕事をしているからであるが、自分勝手な奴であるという点はご容赦いただきたい。さてこのインフラ事業、とりわけEPCのような複雑なエンジニアリング業務やプロジェクト、現場のコントロールが求められる事業において、人工知能がどのように活躍するのかよく考えるようになった。私の中で人工知能はデータがあって初めて成立するものだと考えている。しかし案件数、言い換えると母数としてそう多くない対象となる分野に対しての活躍は、正直見当がつかない。例えば今ある仕事の一部は人工知能に取って代わるだろう。しかしエンジニアの能力が人工知能にとって代わるとは思えない。こうなると、エンジニアリング力の向上は今後ますます重要になるだろう、というのが今のところたどり着いている解である。インフラ製品のモノづくりはどうだろうか。こちらに関しては違う見方を持っている。エンジニアリングされ終えたものというのは、データに出来る内容である。データに出来るということは人でなくてもその後のプロセスは対応できると言い換えることが出来る。インフラというのは家電や生活必需品のような量産品ではないので、実際データは少ない。しかしデータはやがて蓄積され学ばせることは出来るだろう。こうなったモノに人は必要ない。もしとある会社が全てを人工知能を用いて全自動で設計以降を行おうとすれば、おそらく達成可能であろう。そんな時代がやってきた場合に必要になるのは一体どんな仕事だろうか。例えば人工知能に関するリテラシーを持ちながら、現在人が行っているプロセスを把握して、システムを構築または管理できる人などであろう。こういった潮流の中で私が大きく懸念していることがある。現場エンジニアの不足問題だ。実はこれは今に始まった事ではない。現在30代の技術者は非常に少ない。これはかつて理系といえば土木、建築、電気、機械の時代にITが出現し、ITの成長とともにITがそれ以外のパイを少しずつ奪っていったいったことが一つにある。そして人工知能と量子コンピューターの成長に伴いこの流れは加速し、現場のエンジニアが更に減っていくだろう。今年は一年の振り返りというより、一つのインフラエンジニアの思いをまとめたという形になった。ただ冒頭書いた通り、今年はこの問題に非常に関心があったし、他に何か新たな発見や出会いがあったわけでもない。言い換えるとまとめるとこの程度だったという、何とも寂しい一年だったことがわかる。しかし今年はもう少し現職でのエンジニアとしての腕前を上げる一年にしていこうと思っており、広く何かをするという活動は、今年も抑え気味になるかもしれない。※人工知能が人の仕事に取って代わる、という内容の著書はかなり多く出版されている。私はこの類の本を読んだわけではないですし、この類の専門でもない。ここで書かれた内容はあくまでも個人の考えであることはご容赦下さい。
2018年01月02日
コメント(0)
-
シンギュラリティは近い
この言葉を理解するには、やはり深い考察がされた書籍をよまなければならない。なぜならば一般的に理解されるシンギュラリティは技術的特異点ではなく、AIが人に勝つ程度のことであり、馴染みがあるようにメディアが広めた狭義の意味であるからだ。 本書は間違いなくシンギュラリティに人生を捧げた人によって書かれた書である。私が読んだ本は約10年前に書かれた書のエッセンシャル版であるが、今書かれたと言っても気づかないくらいほど、未来の考察に長けている。この著者、レイ・カーツワイルは、外部からGoogleのこの道の技術責任者としてヘッドハンティングされていることからも、その凄さが伺える。 さて、そのレイ・カーツワイルは、シンギュラリティに至るにあたり鍵を握るのは、”全てのテクノロジー”というのがこの本の主張であり、またそれを達成する見込みは明らかだとも主張している。その一部ではあるが以下紹介する。 まず情報処理技術。ムーアの法則と呼ばれる、Intelの創業者が予想した開発スピードは、当時信じる人が少なかったというが、蓋を開けてみたらやはりコスト、処理能力、導入量において指数関数的に進歩している。この速度はこれからも保たれることで、2020年代後半には、全の人類の脳の情報処理速度を超えることとなる。当然人とコンピューティングでは処理の得手不得手があるが、少なくとも合理的判断に基づく演算においては、到底人類では敵わない領域に辿り着く。 次にバイオサイエンス。実は人の脳の謎は未だ殆ど解明されてない。これは脳で起こるシナプスの働きを電気信号のやり取りでしか捉えられていないことが大きい。しかし今後人間の脳内で起こっていることを直接観察するナノボットと呼ばれるテクノロジーが進めば、一気に展望が開ける。人間の思考回路の究明されるのみならず、特定の細胞にアクセスすることで、問題を修復できたり変化させたりすることが可能になる。 ある程度ナノボットのテクノロジーが確立され、また人間の脳内で起こっている現象の究明が進むと、今度は知識や思考、体験などが外部にアップデートされ、またそれをダウンロードすることが可能になる。今でこそ馴染みが出てきたVRも、完全なるリアリティとなって実現される。 さて、このような領域に行き着いた時、人は思うだろう。 意識とは何か。機械には意識はあるのか。いや、そもそも我々人間には意識というものが存在するのか。 人とは何か。例えば肺の移植手術をしたAさんはやはりAさんと認識して疑わない。では臓器を全て入れ替えると、それはAさんなのだろうか。脳を入れ替えた場合はどうだろう。 自分ではその時どういう”意識”であるのだろう。 このような哲学的議論にも本書は及んでいる。 シンギュラリティという何か想像を絶するこの事象は、もうあと10年20年で達成されることなのである。そう、我々はシンギュラリティという未知の時代への突入が不可避の運命にあるのだ。何やら恐ろしいようなすごいようなよくわからない状態ではあるが、それでも我々はその時代を生きる準備をしなければならない。
2017年07月05日
コメント(0)
-
2016年の総括
2016年は振り返ると、面白い出会いが多かった一年でした。 まず一番大きかったのはHAKUTOとの出会い。すんなり行き着いたはけではないですが、結果としては自分の職を続けたことが吉と出た年でもあり、よしとします。 社会人のあり方についても少し考えさせられる年でした。オープンイノベーションに出会い、プラットフォーム型の事業にも出会い、いよいよ名刺ではなく、個の力を求められる時代に近づいていると感じました。そしてそのようなコラムも散見されたように思います。ただ一方でプラントのような長期で関わる必要があるようなプラントエンジニアは、まだ今の日本の雇用形態の方が、日本人にはあっているようにも思えます。おそらくこの手の仕事では中途採用の活用であったり、プロジェクト単位で雇用するほど器用に人を使いこなせないでしょう。ただ残念ながらそうは言ってもエンジニアの技術力はだんだん落ちている思っていて、この点をどう挽回していくか、これが日本のプラント会社やメーカーが世界で生き残っていく唯一の道と考えています。これは日頃の私の周りで起きている事象を感覚的に捉えた意見ですが、社内外ともそう見えるので、間違ってない感覚と思っております。 逆に今年私が出会ったHAKUTOを見るに、ベンチャーは勢いがあるし、出てくる会社は技術があるのが前提ですので、頼もしい限りです。こういった勢いと技術がある会社がもっと活躍出来るよう行政が動くことが重要のようですが、少なくとも個人としてこういう会社の一つであるHAKUTOを積極的に応援していくのは、一つの社会貢献であり、技術応援であり、個の新たな挑戦でもあります。 2016年は時間の使い方に関しても多く考えさせられる年でした。週末もお陰さまで殆ど潰れるようになったとともに、プライベートも忙しくなったこともありました。仕事がどうにも終わらない状況も味わいました。そして特に仕事でわかったこと、これも技術力(知識)と経験が圧倒的にスピードを変え、効率を変え、生産性の向上に繋がるということ。恥ずかしながら、今年お客様に休みだろうが何だろうがプレッシャーをかけられて、まいった時期がありました。しかしこの経験を乗り越えた時、一気に一皮向けた自分を実感しました。そしてそれ以降かなり仕事の効率があがりました。身をもって当たり前のことを学ぶのも、まだ社会人としてひよっ子のありがたみかと思います。 そんな1年、終わってみればいい1年でした。2017年はこの流れをより前に進めるべく頑張っていきたいと思います。
2017年01月02日
コメント(0)
-
遅めの2015年の総括
2015年はインドネシアでのインターンシップを2月に終えると、まるでインターンシップが夢のようだったかのように、インターンシップ前後での変化のない仕事で一年を終えることとなった。個人的にはこの一年はこの経験を活かしたものになると妄想していただけに、無念の気持ちでいっぱいだが、正直これを環境のせいにしている自分がいることもまた自戒の念に苛まれている。プライベートでも残念なことに、2015年とうとう体重が大台を突破した。自分ではこれまで自制できるとの自信があったことから、なんとも情けない気持ちである。なぜこのような事態になったのか、個人的に分析した。すると自分ではそれなりにストイックと信じていたのだが、そうではないという結論に行き着いた。つまり先に述べた通り、環境のせいにするのだ。でも自分としては環境さえあればもっと個を高める努力をすることも知っている。ということは自分に甘くならないよう、自らをよりよい環境に置くということは、自分の性に逆らわない範囲での解決策ということになるのではないだろうか。そんなことを思った一年だった。2015年の書初めは、あまり常識に捉われないよう、自分の考えを柔軟に持というという思いで「柔」としたが、終わってみればふにゃふにゃの決意とぶよぶよの身体となった「柔」な一年だった。例年であればここで社会的関心を取り上げ、自分はそれに対してどう思うのか、どう関わっていくのかを述べるものだったが、今回そうなっていないことも、自分の社会への関心を低くしてしまっているところだろう。実際全くないわけではないが、やはり熱い思いをここにぶつけるほどのものが今はない。この一年の振り返りを踏まえ、2016年は締まりある年にしようと思う。
2016年01月05日
コメント(0)
-
遅めの2015年の総括
2015年はインドネシアでのインターンシップを2月に終えると、まるでインターンシップが夢のようだったかのように、インターンシップ前後での変化のない仕事で一年を終えることとなった。個人的にはこの一年はこの経験を活かしたものになると妄想していただけに、無念の気持ちでいっぱいだが、正直これを環境のせいにしている自分がいることもまた自戒の念に苛まれている。プライベートでも残念なことに、2015年とうとう体重が大台を突破した。自分ではこれまで自制できるとの自信があったことから、なんとも情けない気持ちである。なぜこのような事態になったのか、個人的に分析した。すると自分ではそれなりにストイックと信じていたのだが、そうではないという結論に行き着いた。つまり先に述べた通り、環境のせいにするのだ。でも自分としては環境さえあればもっと個を高める努力をすることも知っている。ということは自分に甘くならないよう、自らをよりよい環境に置くということは、自分の性に逆らわない範囲での解決策ということになるのではないだろうか。そんなことを思った一年だった。2015年の書初めは、あまり常識に捉われないよう、自分の考えを柔軟に持というという思いで「柔」としたが、終わってみればふにゃふにゃの決意とぶよぶよの身体となった「柔」な一年だった。例年であればここで社会的関心を取り上げ、自分はそれに対してどう思うのか、どう関わっていくのかを述べるものだったが、今回そうなっていないことも、自分の社会への関心を低くしてしまっているところだろう。実際全くないわけではないが、やはり熱い思いをここにぶつけるほどのものが今はない。この一年の振り返りを踏まえ、2016年は締まりある年にしようと思う。
2016年01月05日
コメント(0)
-
パリで起きたテロ 〜報道と反応に対する個人的な感想〜
ISの活動もとうとう欧米に及び始めたかという事件だった。前回の記事で明確に書けなかったが、ISの活動は基本的に地場を固め、強いスンニ派の国をつくることである。今の国際社会において、国の領土は決して戦争の結果や、国民の思いで決められるものではない。だからこそ、というかこれだけが本当の理由かもしれないが、ISは国際社会において認められる存在にはなり得ない。少し話は逸れるが、一時期パレスチナのガザ地区での抗争が報道され続けた時期があった。もともとパレスチナの領土だったのが、イスラエルがその土地を広げており、そこにはアメリカの後ろ盾があることは、あまり大っぴらに報道しないが、これだって実際許されるべきではない。ただしアメリカの俗国要素を秘めている日本において、あからさまにアメリカを悪者とする報道は出来ない。そう思ってISの問題を改めて考えた時、ISはテロ行為をやっている以上、倫理的に許容できないが、では欧米は正義なのかというと、これも疑問である。そもそもISを作ってしまったのは、権益を守りたい欧米の政治にもあるのだ。私たち日本人はやはりISに日本人を殺されており、かつ欧米と仲間意識を持っているので、ISを敵視する。ISは一度ならず二度までもパリという先進国の代表的中心街にテロ行為を行った、許せない。確かにそうだが、ISからすれば欧米からの空爆で多くの犠牲者が出ている。テロは一般市民を巻き添えにするので、そもそも空爆とは違うと言うかもしれない。ただし、空爆が戦闘員だけを標的にしている確証はどこにもない。この問題、感情を抜きにして一歩引いてみた時、一つひとつをどう判断するか、非常に難しい。少し話は変わるが、フランスの国旗をフェイスブックの顔写真に重ねる活動に対し、疑問の声が上がっている。以前の同性愛を認めた時の流れや、ALSのアイスバケツチャレンジと同じだ。Facebookやyoutubeの普及でこのような活動に乗っかる人が増えたという。人は慈善活動を行っていることを人に見せて、善者振りたくなるということが理由のようだ。先日とあるフォーラムで、福島でのボランティア活動に参加する人は二種類に分けられる、という話を聴いた。一つはボランティアをしたいという純粋な気持ちでボランティアに参加している人達。このような人達はどんな隅っこでの目立たないボランティアもするし、多少地元の人達から嫌味を言われても、彼らの気持ちがわかるから、素直に聞くそうだ。もう一つはボランティアをしている自分が好きな人達。こういう人達は人に見られて初めて意味があるため、隅っこで活動するのを嫌がり、嫌味を言われると文句を言うそうだ。これはボランティア受入をやっていた人達の生の声なので、事実そうなのだろう。そしてこれがまさに写真を変える活動と重なるのは、感覚的にではあるもののほぼ間違ってないと言えるだろう。エコレンジャーは別にISを擁護するわけでもないし、Facebookの写真を変える人には心から追悼の意を捧げている人だっているはずだ。ただ、報道や人々の反応、対応、バッシングなどを見ると、大きな違和感を覚えずにはいられなかったので、書き留めておいた。
2015年11月16日
コメント(0)
-
イスラム国とは何なのか
「イスラム国 テロリストが国家をつくる時」 ロレッタ・ナポリオーニエコレンジャーがインドネシアにいた時、日本人2名がイスラム国によってその命を日本人を恐怖で慄かせることに利用された。このことは瞬く間に日本中で騒がれたが、ムスリムが90%を占めるインドネシアでは殆どといっていい程報道されなかった。この頃にイスラムに興味を持って手に取ったのがこの本。著者は海外のテロファイナンス会議の議長を務める、テロ組織に精通している方で、日本国内での偏向報道では一切見えてこないイスラム国の実態を赤裸々に説明してくれる良本である。エコレンジャーが中東戦争や湾岸戦争について知識が乏しいため、中々理解が進まなかったが、それでも非常に学ぶことは多かった。ここでは恐らく日本での報道だけでイスラム国を想像しては誤解が生じるであろう点をまとめてみた。私の想像する平均的日本人が持つイスラム国のイメージ(あくまでも私の意見です。)・残酷なテロ集団・無差別殺人集団・やっぱりイスラム教は怖い・アルカイダの後継もし仮にこれを読んで、全然違うわ!!という意見があったら是非お聞かせくださいm(__)mさて私が本を読む限り以下のようです。・アルカイダの狙いは欧米列強。これに対しイスラム国はあくまでも地元の政治に対して反感を持っている人たちの支持を集め、地元で着実に領土を増やしている集団。彼らは領土を広げながら、自分たちの領土のインフラ整備を行い、住民に対して生活の質を向上させる働きをしている集団。・メディアネットワークを駆使し、内外での支持を増やしている。ばりばりの資本主義社会国ではイスラムはマイノリティであることが多く、不満を持っているところに、イスラムの力強いメッセージは、心に響くようだ。結果強く同調したものはイスラム国の地に向かったり、自爆テロが発生したりするようだ。その数はかなり多いようで、報道では空爆で何人やっつけたと報道しているが、減るより増える方が今の所多いらしい。また、著名人の残虐な殺し方をネット上に流すことで、過激な同調者を興奮させ、世界中を恐怖に陥れている。彼らはこのようにメディアネットワークを駆使することで得られることを理解しながら敢えて行っている頭脳的集団。・中東には権益がしっかりと存在し、結局はその権益を牛耳っている政府、そしてそれを支援する欧米。欧米は基本的にこの権益を守るために、色んな集団に武器や資金を支援している。代理戦争が複雑になってきているようで、誰が敵なのかわからない状況になっている。アメリカではイスラム国に資金援助したという報道がされており、もう何が何だかわからない、混沌とした状況だ。・イスラム教の自体は怖いことをする宗教団体ではない。ただしこれは歴史が証明しているが、宗教はしばしば戦争の理由として登場する。キリスト教対イスラム教の領土争いは過去にあった。これは宗教の争いではなく、権力と領土の奪い合いの戦争である。余談だが、インドネシアにいてイスラム教が怖いとは一切思わなかった。特に中東で起こっていることは理解するのが難しいが、これからもっと深掘りすると、よりこの本の理解が深まるのだろう。でもイスラム国についての誤解を多く解けたという意味で、この本に出会えてよかったと思っている。メディアは今年の夏頃にはイスラム国を掃討しているだろうと報じた。これに対し、こおジャーナリストはこれから勢力を拡大していくだろうと言った。いかに報道が適当か、もしくは偏向報道かも簡単にバレるネタの一つだ。こういうネタこそ、色々な人の視点に出会わなければ、本当の意味での考察はできないのだろう。
2015年11月14日
コメント(0)
-
イスラム国とは何なのか
「イスラム国 テロリストが国家をつくる時」 ロレッタ・ナポリオーニエコレンジャーがインドネシアにいた時、日本人2名がイスラム国によってその命を日本人を恐怖で慄かせることに利用された。このことは瞬く間に日本中で騒がれたが、ムスリムが90%を占めるインドネシアでは殆どといっていい程報道されなかった。この頃にイスラムに興味を持って手に取ったのがこの本。著者は海外のテロファイナンス会議の議長を務める、テロ組織に精通している方で、日本国内での偏向報道では一切見えてこないイスラム国の実態を赤裸々に説明してくれる良本である。エコレンジャーが中東戦争や湾岸戦争について知識が乏しいため、中々理解が進まなかったが、それでも非常に学ぶことは多かった。ここでは恐らく日本での報道だけでイスラム国を想像しては誤解が生じるであろう点をまとめてみた。私の想像する平均的日本人が持つイスラム国のイメージ(あくまでも私の意見です。)・残酷なテロ集団・無差別殺人集団・やっぱりイスラム教は怖い・アルカイダの後継もし仮にこれを読んで、全然違うわ!!という意見があったら是非お聞かせくださいm(__)mさて私が本を読む限り以下のようです。・アルカイダの狙いは欧米列強。これに対しイスラム国はあくまでも地元の政治に対して反感を持っている人たちの支持を集め、地元で着実に領土を増やしている集団。彼らは領土を広げながら、自分たちの領土のインフラ整備を行い、住民に対して生活の質を向上させる働きをしている集団。・メディアネットワークを駆使し、内外での支持を増やしている。ばりばりの資本主義社会国ではイスラムはマイノリティであることが多く、不満を持っているところに、イスラムの力強いメッセージは、心に響くようだ。結果強く同調したものはイスラム国の地に向かったり、自爆テロが発生したりするようだ。その数はかなり多いようで、報道では空爆で何人やっつけたと報道しているが、減るより増える方が今の所多いらしい。また、著名人の残虐な殺し方をネット上に流すことで、過激な同調者を興奮させ、世界中を恐怖に陥れている。彼らはこのようにメディアネットワークを駆使することで得られることを理解しながら敢えて行っている頭脳的集団。・中東には権益がしっかりと存在し、結局はその権益を牛耳っている政府、そしてそれを支援する欧米。欧米は基本的にこの権益を守るために、色んな集団に武器や資金を支援している。代理戦争が複雑になってきているようで、誰が敵なのかわからない状況になっている。アメリカではイスラム国に資金援助したという報道がされており、もう何が何だかわからない、混沌とした状況だ。・イスラム教の自体は怖いことをする宗教団体ではない。ただしこれは歴史が証明しているが、宗教はしばしば戦争の理由として登場する。キリスト教対イスラム教の領土争いは過去にあった。これは宗教の争いではなく、権力と領土の奪い合いの戦争である。余談だが、インドネシアにいてイスラム教が怖いとは一切思わなかった。特に中東で起こっていることは理解するのが難しいが、これからもっと深掘りすると、よりこの本の理解が深まるのだろう。でもイスラム国についての誤解を多く解けたという意味で、この本に出会えてよかったと思っている。メディアは今年の夏頃にはイスラム国を掃討しているだろうと報じた。これに対し、こおジャーナリストはこれから勢力を拡大していくだろうと言った。いかに報道が適当か、もしくは偏向報道かも簡単にバレるネタの一つだ。こういうネタこそ、色々な人の視点に出会わなければ、本当の意味での考察はできないのだろう。
2015年11月14日
コメント(0)
-
永遠の0を読んで
もう出版から9年ほど経っており、映画化されて2年が経つがエコレンジャーは今になってやっと手にとって読んだ。最近は戦争に触れ、考える機会が多かったので、これもその一つである。ここで物語の紹介をするつもりもない。本書の中で多くを考えされた特攻と戦争について、感想でも書こうと思う。なおエコレンジャーの戦争に関する知識は一般教育で得た程度なので、かなり無知なので、ここで書くこともかなり稚拙な内容になると思うがご容赦いただきたい。まず特攻について考えてみた。なぜ特攻が戦略として隊員は受け入れることができたのかの一つに、多くの日本人の中にある、何かのために命を賭すという日本人の精神があると考えている。この精神は日本人として誇るべき精神と考えているが、時にこれが間違った方向に行った最たるものが特攻だったように思う。特攻という戦術が間違ったことなのかどうかを戦後の平和に生きた価値観で判断するのは無理がある。ただし特攻という戦術が全く通用しなくなった時点での強行は完全に間違いではあったろう。このあたりは戦時中に 真っ向から軍部に対して特攻に反対した美濃部正が戦後に「特攻以外に効果的な攻撃方法がなければ、特攻もやむなし」と述べている点が非常に興味深い。それから太平洋戦争が始まってからのアメリカとの攻防についてだが、パールハーバー以降の零戦戦闘における戦果は恥ずかしながら知らなかった。零戦を恐れながらも、状況を打開すべくとったアメリカの戦略は、やはりアメリカというべきだろう。ガダルカナルで拾われた零戦を研究し、その零戦の戦闘能力に驚愕しながらも、しっかりと対零戦の戦術を編み出した。その戦術以外で戦うことはタブーとされた。後には零戦を超える飛行能力を携えた戦闘機を開発し、その他の機器も含めテクノロジーと戦略の差で日本に勝ったと思う。もちろん日本には燃料や材料に乏しい国であることから大きなハンデを背負っていることは一般に不言われている不利な点だ。しかしそれでも太平洋戦争が始まった当時の零戦の能力がアメリカやその他の国の戦闘機の能力を遥かに凌いでいたというのは何と素晴らしいことかと感激した。一方の日本の戦略に関しては残念ながら陳腐なものだったろう。本の中で登場するヤクザの景浦が述べたコメントが非常に刺さった。「軍部の連中のとったら、艦も飛行機も兵隊も、ばくちの金と同じだったのよ。勝ってる時はちびちび小出しして、結局、大勝ちできるチャンスを逃した。それで、今度はジリ貧になって負け出すと頭に来て一気に勝負。まさに典型的な素人ばくちのやり方だ。」今日本人は太平洋戦争についてあまりにも知らなさすぎるようだ。なんと悲しいことか。戦争を知らずして、戦争の残酷さと、苛烈さと、虚しさをどうして知ることが出来るのか。との思いは、また別の機会に書かせてもらおうと思う。最近はエコからだいぶテーマがそれとるなぁw
2015年10月10日
コメント(0)
-
天空の蜂 劇場版
天空の蜂東野圭吾作が約20年前に書き下ろしたサスペンス小説。先日、最近話題のこの天空の蜂の映画版を見てきた。残念ながら原作を読んでいないため、原作との比較は出来ないが、話題作とだけあって見応え抜群だった。ストーリー性や映像においても当然素晴らしいが、エコレンジャーの視点では、この時期にあって原発を取り上げる作品を扱うということは非常に勇気が必要であり、それだけで称賛に値する映画かと思う。さてここでは原発に重きをおいて話を進める。映画では高速増殖炉が狙われたが、日本では実際には2つの高速増殖炉が存在する。「常陽」と「もんじゅ」である。これらは商業用ではないので電力会社は一切関係なく、文部科学省管轄の日本原子力機構(JAEA)の設備となっている。高速増殖炉は通常の商用原発炉では使用しないプルトニウムの核分裂反応をエネルギー源とし、かつ核分裂反応で生じる中性子でプルトニウムの核分裂反応を起こすサイクルを利用した原子力発電である。達成できればエネルギー問題がなくなると言っていいほどのシステムだが、制御の面、物理的知見の未熟さ、リスクという意味での危険性が大きいことなどが問題としてあり、実際事故も多発している。その上研究段階での投資額が大きく、かつ見通しも立たないことから、殆どの国で開発から手を引いている。さて恐らくこの原作執筆および映画化に向けてかなりの取材が行われたと思う。なので原子力発電所周辺で何が起こっているかを垣間見るという意味で非常に興味深い。また発電所で働く人達の様子、過激に描写された中央との温度差も中々普段見ることはできないので面白い。もちろんこれだけでは原発に対しての判断は出来ない。なぜならここでは原発という存在に対して、特定の意見を述べるものではなく、やはりあくまでもサスペンス映画であるからだ。しかしそれでもこういった映画を見ることで原発に少しでも興味と知識が増えることは素晴らしいことだと思う。だから見た方がいいというのは変だが、せっかく見るのであればこういった点にも少し意識を持って行きながら見るといいかなぁと思った次第である。以上かたっくるしく書いたので誤解されると困るのでことわっておきますが、サスペンス映画としてとても面白いです。
2015年09月22日
コメント(0)
-
「原子爆弾」を読んで その2
その1は前の記事をお読みください。日本に原爆が投下された理由は幾つか言われている。1部で述べたとおり、人体実験的要素を持っていた、日本を早く降伏させる手段、アジアを制圧したいロシアへの牽制などだ。2つ目の理由は、アメリカの自己正当化に過ぎないと、私は読み取ったが、それはさておき、この時既にソ連は共産党国家として、アメリカと敵対する立ち位置だったことから、すぐさま核開発へ本腰を入れようとする。少し話を戻す。電子は粒子と波の二つの振る舞いをすることを主張したボーアという物理学者は、1944年初頭に既に原爆開発後の管理のあり方に目を向けていた。つまり原爆はもはや軍の手に負えない兵器であり、これを持つ国がこれを独占する限り、軍拡が進む。逆に一般公表し世界でこの知識を正しく共有すれば、軍縮に向かうことになるのではないかと。1945年11月にはこの考えに当時のアメリカの大統領トルーマンが賛同し、国連の指揮下の元で国際委員会を設置することを要請する。1946年3月には原爆の父と呼ばれたオッペンハイマーによる提案がふんだんに盛り込まれた、アチソン=リリエンソール報告書が公表される。これはいかなる資源、設備、原子炉、研究所を国有化し、国有権を世界の機関に譲渡するというものだった。この発想はつまり原爆生産の手段を皆が所有するという脅威による抑止力に繋がるとの発想だ。しかしチャーチルは違った。ソ連に力を持たせることそのものが危険であり、未成熟な国際機関にこの権利を委ねることは間違いだと言った。こうして核拡散へ世界が動くこととなる。こうして本格的に(実際はもう少し前から)ソ連の核開発が始まる。かと言ってソ連にその知見があるわけではない。それではどのようにソ連は原爆に関する知識を得たのか。それはソ連がマンハッタン計画に携わった人間をスパイとして雇ったからである。実際核開発の段階で、情報規制には相当の気を使っていた。フックスはマンハッタン計画のメンバーでも有能だったが、1941年時点で既にスパイとなっていた。彼の提供する情報が一番有益だったとされ、その他のスパイからの情報も合わせて、ソ連は核開発を進めた。1949年、ソ連は最終的に核実験に成功し、原爆の保有国としてその地位を確立することとなった。さて、最終的にソ連のスパイは片っ端から調べ上げられ、捕まっている。しかし何と言っても一番驚くのは、原爆の父と呼ばれ、マンハッタン計画の中心人物でもあったオッペンハイマーがスパイ行為に間接的に加担していたのだ。と言っても実際彼はメンバーに加わる時点で既に熱心な共産党員であることは知られており、どんでん返しでも何でもないが。最後に、原爆の開発に携わった人たちの感情はどのようなものであったか。1000人を超える研究者がいたために、全員がそうとは言えないまでも、原爆投下前の時点で「我々は、戦争の終結をもたらしそうな技術的実演を提案することはできない。〜」という報告書を提出している。また、日本での原爆投下の報告に加え、直後の21日に、マンハッタン計画の中心地ロスアラモス研究所で実験に失敗して被爆した研究者の末路を目の当たりにしており、残酷な兵器を開発してしまったと痛感したことだろう。この本はエピローグでこう述べている。1947年にオッペンハイマーが次にように公演した「戦時中の我が国の最高指導者の洞察力と将来を見据えた判断だったとはいえ、物理学者は核兵器の実現を進言し、支援し、ついにはその達成に大きく貢献したことに、甚だしく内面的な責任を覚えました。」これに対しジム・バゴッドはこう言っている。「罪ではなかった。科学的事実は、まさにその性質上、道徳とは無関係だ。道徳的な意味においては、正しくもなく誤りでもいないし、善でもなければ悪でもない。石や木と同じように単なる存在なのだ。…言うまでもなく、道徳的な意味において、正しかったり誤っていたりするのは人間、善いのも悪いのも人間なのだ。」本書は約600ページあり、ギュッと詰め込んだブログにしたことで、どこか曲げられていたら申し訳ございません。私の解釈が間違っていることもあるでしょう。何卒ご容赦いただきますようお願いします。今回このブログを書いた一番の理由は、内容が膨大すぎて、何処かにアウトプットしないと、確実に何も残らないと思ったのででした。しかしせっかくアウトプットするなら、今や半分以上の若者が、アメリカと戦争したことすら知らないという事実に対し、ホンのの僅かの人にでも興味を持っていただける人が出るといいなと思ったからです。戦後70年、自分の知識の向上もあり、初めて真面目に向き合って考えた戦争。平和のために人は何を考え、どのように行動するのがいいのか、これは戦争史から学ぶことが一番ではないでしょうか。そう思った2015年夏でした。
2015年09月12日
コメント(0)
-
「原子爆弾」を読んで その1
世界的に有名なサイエンスライター、ジム・バゴット著。ウランの核分裂が発見されてから冷戦の核開発競争が繰り広げられるまでの、物理学者と政治の世界を調べ上げた、至高の歴史フィクション。日本という国は原爆を落とされた唯一の国であり、かつ敗戦国であるということから、いかに原爆に対して捻じ曲がった知識を持っているかを思い知ることができた。原爆の開発に結びつく一つの大きな科学的側面による引金は、1938年12月末にウランが核分裂しバリウムに変化し、これが陽子約1/5の質量欠損に相当するエネルギーを生むことを発見したことだろう。この発見は1939年2月の「ネイチャー」に掲載される。このわずか2カ月後、ドイツは国をあげて原爆の研究に乗り出すこととなる。原爆の開発においてナチスドイツに先を越されると、世界が危険に晒されると考えたハンガリー陰謀団がアインシュタインに懇願し、当時のアメリカ大統領ローズベルト宛に、ナチスドイツが新たなタイプの爆弾を開発していると警鐘を鳴らす書簡を送った。こうしてドイツと連合国の核開発競争が始まった。核開発競争は結論から言うと、ドイツは完敗した。ドイツは研究所がたびたび連合国に攻撃されたこと、研究材料供給が絶たれたこと、そして開発メンバーのトップとも言えるハイゼンベルクが、原子爆弾の製造まで辿り着くのは、当時の戦争が終わってからだと思っていたことが要因とされている。少しアメリカの核開発の軌跡を紹介する。上の核開発競争が始まって暫くは、物理的壁に悩まされながら、試行錯誤が進む。この間にドイツも開発が進んでいる情報が飛び込んでくる。この間にプルトニウムの発見や水爆の構想なんかも出てきている。しかし原爆の開発が起動に乗ったのは、科学者と軍が一体となって開発に取組む、所謂「マンハッタン計画」が始まった1942年9月のことだ。これから間も無くの12月、原子炉の核燃料制御に初めて成功している。さて1945年5月にドイツは無条件降伏するに至る。しかしアメリカにとってそのことは核開発の観点からはもはや大きな問題ではなかった。なぜならこの時既にソ連という国との軍拡という意味での核開発がほぼ絶対的なものになっていたからだ。つまり核開発の目的は次の段階に突入していた。そして、核という科学的根拠に基づく、しかし実験的にはその効果がしめされていない兵器は、目で見てわかる実験を行う必要があるのだ、というのが結論だ。そんな中1945年5月には日本を原子力兵器の使用に関しての最終まとめが行われた。ここでは京都(しかしこの後主要都市であり古都でもあるという理由で却下)、広島、横浜、小倉が挙がっていた。1945年7月16日、人類初の核実験、所謂「トリニティ実験」が、ニューメキシコの砂漠の中で行われた。そして、8月6日にはウラン式の原爆「リトルボーイ」、8月9日には長崎にプルトニウム式の原爆「ファットマン」が’投下される。この本はここで半分強。2部構成にします。
2015年09月12日
コメント(0)
-
2014年という変化の年
この一年を振り返ってみると、本当に変化が多い年で、正直前半のことは殆ど覚えていない。4月にインドネシアに行く話が出、その準備をしているうちに会社の仲のいい先輩が会社を辞めた。インドネシア行きが決まる直前、7月の初めに勤務先が変更になり引越し。そして夏休みはインドネシア研修、9月にはもうインドネシア。組合のとある組織の委員長を務めていたが、任期満了前の渡インドネシアにより、竜頭蛇尾(竜頭かはわからないが)の感満載だったが、これもなんとかインドネシアから出来る限りのことはしたと思う。こう振り返っているうちに、思い出が蘇ってくるものの、やはりインドネシアでの思い出が9割を占めている。充実していたかというとわからない。ただし変化というものはそれなりにリフレッシュでき、視野も広くなり、当然オプションで違った知識、違った人脈色々ついてくるわけで、日頃自分の成長を感じることはないが、得たものは大きいようだ。そう思うと、日々もがき苦しんでいることも少しは意味があるようだと思える。さて前置きが長くなったが、例年と違い振り返りが自分中心で、国がどうとか環境がどうとか、そういった感覚がわかないのはこれも現在の生活環境のせいだろうか。それともこちらで色々経験して、くだらない政治の動きに少し冷めた目線を送っているからだろうか。今年はとりとめもない振り返りに終わりそうだ。そんな年がたまにあってもよい。因みにインドネシアで生活していると年末の恒例行事である帰省、忘年会、年賀状、紅白歌合戦、除夜の鐘、何もない。そして真夏ときている。これも例年と違って反芻を妨げているのだろうか。来年日本に戻って、果たしてどのような生活を作っていくか、成長の成果が問われるところだろう。
2015年01月01日
コメント(0)
-
2013年を振り返って~何か出来ただろうか~
書初めで「提供」の文字を書いて始まった2013年。文字自体はなんとなく格好悪いが、去年どうしても受けることばかりだった気がしたので、今年は何か周囲の人に対して教示できる人材になれたらいいなと思ってました。さて振り返るとそんなに人に対して教示するなんておこがましいことは口が裂けても言えず、やはりご教示いただいてばかりだったと思います。でもそれでもいいような気がしました。つまり常に高みを目指してみんなで高めあうことが、結果相乗効果による全体の底上げにつながるのではないかと思うわけです。しかしなんといっても今年一番の出来事は、とある組合の若手委員の集まりで委員長を務めることになったことでしょう。委員長として求められる内外に対する視野、統率力、責任など本当にたくさんのことを学ぶ機会をいただくことができました。確実に成長させてもらってます。さて毎年は世の中に対して物申すスタイルが多いのですが、今年は安倍信三政権がそれなりにしっかりしていたのでミクロでは違う意見があれどマクロでみていい一年だったと思うのでいいです。もし物申したいというのであれば寧ろ韓国と中国に対してですかね。今後のアジアの成長を牽引していくつもりなら、もう少し品格ある言動を取ってほしいものです。そんな感じで大きなことと言えばということですが、そのほか自分の人生についても改めて考えた年でした。来年はそのことが自分の人生にどう影響してくるのかわかりませんが、さらにしっかり考える年になることでしょう。一般公開しているわけではないですが、今年お世話になった皆さんには心から感謝申し上げるとともに、来年も共に成長していけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
2013年12月31日
コメント(0)
-
地方でボランティア
先週末2泊3日で新潟県の高柳市に雪掘りボランティアに行ってきた。ブログに残すということはつまり非常にいい体験ができたからということで、思ったことをここに書き留めておこうと思う。初日は移動とかんじき作り。かんじきとは簡単にいうと、新雪に脚をつっこんでも股まで埋まらないよう、靴に履く草鞋のようなもの。細い円形の木材直径4cmくらいに丈夫な紐を巻きつけて、靴からとれないような引っ掛け部分を作る。こんなの雪国ならではの知恵と技術だ。2日目は家の雪かき。部落には働き盛りの若者がおらず、例えば95歳のおばあちゃんが一人暮らししていることもあり、雪かきする人が必要なわけだ。因みにその土地では約3mの雪が積もっており、雪を掘るという表現をしていた。というわけで、ボランティアで現地に赴いた人間たちで雪掘りをしていくのだ。夜は現地の人と懇親を深めるために、現地の型が振舞ってくれた日本酒を飲む。いろんな話をうちらは聞くわけだ。昔おれたちが若かった頃は毎日のように集まって酒を浴びるように飲んでいた。昔はうさぎを狩りして食べたり、最近は猪が多いかな。食べるものは殆どこの辺りで収穫したものだ。全部の話がとても人間くさく、なんの汚れもないし、考えてみれば当たり前の生活らしい生活を送っているという話。でも自分を振り返ってどうかといえば、全くそんなことはなく、合理的に動いて、人付き合いはやけにしたたかで、毎日を機械的に生活している。なぜならこれが便利であり生産性があり、より過ごしやすい生活をするためだからだ。果たしてどちらがいいのだろうか。エコレンジャーはやはり後者だと思う。そう思ったからこそ日本は世界的に経済大国として認められやっていっている、尊敬される部分が必ずある、そういう国なのだ。ただし一方で今回目の当たりにしたいわゆる人間臭い生活が人間の根本には存在するということも認識していないと、それこそ人間であることの大切さを失ってしまう。自分とはなんなのか、生きるということはなんなのか、そんな素朴なことを素朴な生活の中に見出すことができ、この機会に感謝している。
2013年02月13日
コメント(0)
-
2012年回顧録
2012年の目標は、「人脈をとにかく広げる」だった。今年はある程度これを達成できたと思う。プロジェクトKという霞が関構造改革を推進する人たち、青山社中という社会を変える人材育成と政策シンクタンクを手掛ける中で出会った人たち、創造再生研究所という、林業と文化の共生を重んじる人たち、近所の人たち、社内の人たち。人脈を作るということは、時間とお金がすごくかかることだと実感した。しかし、そこで得たものは、計り知れないほど有益であり、そしてなにより楽しくもあったことが実感としてある。今年一年出会って喋ってきた人たちには本当に感謝してもしきれない。自分はまだまだ若輩で、無知で、非常に優秀な彼らと付き合っていくにはもっと一般教養が必要だ。しかし同時に自分の専門を同時に伸ばしていくことがとても重要だと最近感じる。社会人になってすぐにスペシャリストでありジェネラリストになることを心がけようと思ったが、こういう色々な人と出会って、改めて両立の必要性を感じる。ジェネラルな知識で彼らと会話しても、そこに自分の価値というものはない。提供してもらっているだけで、提供することができない。スペシャルな知識だけで彼らと話しても、スペシャルな人でない人は受け取ることができない。今年の初めに既に来年の目標を決めていた。それは、広げた人脈を実のあるものにすること。この目標は実は定量性どころか定性性にすら欠ける目標だ。だから変更することにする。来年の目標己の価値を高め、人に価値を提供すること
2012年12月31日
コメント(0)
-
原発反対反対
エネルギー・環境会議の報告「エネルギー・環境に関する選択肢」で、日本の今後のエネルギーベストミックスをどう考えるかについて、いや寧ろ原子力を何%残すかというところに議論が集中しているが、シナリオとして0%、15%、25%の3つを提案、検討した。そして最近では多くの人が官邸の前に集まって「原発反対!」とデモを行なっている。またエネルギー政策についての意見聴取会でも、原子力賛成派として電力会社関係の人間が優先的に選ばれたとして話題を集めている。この原発を今後どうしていくか、実際エコレンジャーも去年からよくわからないと書いているが、ようやくひとつの自分の考えが固まってきたので、ここ最近の社会現象も含めて書いてみようと思う。エコレンジャーは原発反対には反対である。一つ目は、こんなに危険なエネルギー資源を用いてまでなぜ原発を存続させようというのかという意見。原子力がなぜ危険と思うのかは、やはり核エネルギー自体のエネルギー量の膨大さだろう。今回のように制御がきかなくなると、その影響は広範囲に人大なる影響を及ぼしてしまう。もし今回の程度ならまだしも、原爆のようなレベルまでの事故に発展したらどうするのか。確かに原爆の被害を受けた日本人ならではの感覚で、否定する気もないが、今回の想定外の災害ですら直接的原因で人は死んでいないのが報告上現実だ。寧ろ津波で亡くなった人のほうがよっぽど多い。むしろ原発より堤防を責めるべきではないのか。極端な話にまで広げれば、車で事故死する人の数は年間5000人程度存在する。これはいいのか。便利という点では原発と変わらない。次に、再生可能エネルギーを普及させて原発に替わればいいという主張。この主張は再生可能エネルギーをあまく見すぎている。とくに風力と太陽光は不安定なエネルギーで、系統の電力に対する割合が増えると電圧変動が大きすぎて問題になるのであまり多くすることはできない。更にはこれら再生可能エネルギーが増えるほどに電力料金は跳ね上がっていくことが、固定価格制度の副作用として存在する。月70円から100円だそうで、年間だいたい1000円上がる。これはみんな許せるのだろうか。東電が電気料金値上げしたことにより、家庭の電力価格は月400円くらいの上昇で許せないのに。結局東電がムカつくという感情で(勿論むかついて当然だが)合理的な議論はできていない。さて、将来的に再生可能エネルギーが原発0%のシナリオ通り普及するとしよう。でもそれに移行するまでに原発をやめれば当然火力発電に依存するしかない。この状況ではCO2排出量が跳ね上がる。実際東京電力での2011年度のCO2排出量は2010年度の13%増との報告だ。これはいいのか。まず日本は京都議定書の約束を守れずに多くの違反金を払うことになる。これは当然国民が負担する。次に、環境そのものへの影響に対してはどう考えるのか。この問題だって将来につけを回している行為であることを認識しているのだろうか。恐らく観点としては他にも沢山あるだろうが、私の結論としえては、こういった問題や議論の余地があるにもかかわらず、原発反対と主張している人は、原発をなくした上で、あとはほかの誰かが何かやってくれるだろうという、これもまた無責任な考えの持ち主が多いような気がしている。感情に任せたって何も始まらないし何も動かない。今行われている反原発デモもお祭りにしか見えてならない。こういった原発反対の流れには正直賛同したくならない。※個人的に原発は残っていいと思っているが、なくなったらダメとは言っていないこと留意願いたい。今回の主張はあくまで原発反対という流れに反対ということ。
2012年08月04日
コメント(0)
-
理想とする一つの社会を考えた
エコレンジャーグリーンです.これまでエネルギー問題や政治問題に対して言いたいことを思うがままに吐いてきましたが,ここ最近エコレンジャーの中で一つの理想のビジョンが見えてきたので,整理の意味も含めて記しておこうと思います.ここ数年の社会の流れを見ていると,どこもかしこも不景気という荒波に対し,馬鹿正直に真正面から突っ込んでしまって,多くの方が,精神的にであったり会社を首になったりして脱落していっている.それが例えば直接的には失業率の増加であったり,それ以外にも自殺や凶悪犯罪が増えたり,ジニ係数が上がったりといったところにもろに現れている.そんな社会において人々はそうなりたくないと思っても,会社で頑張る以外の手段は思いつかない.まさに泥沼だ.地に足が着かない状態で何とか溺れまいと立ち泳ぎしながら誰かが助けてくれるのを待つだけの人生になってしまっている.しかし政治に目を向けても手を差し伸べてくれるやさしさは持ち合わせてなさそうだ.第一党が民主党になって,国民の生活を第一に考えるといって税金という彼らの持つ資源を如何に国民に対し有効活用しようかと色々試みたが,ことごとく不発に終わり,気づいてみれば何も変わらなかったと思える状態に落ち着いた.勿論民主党だけが悪いわけではない,一部野党やマスコミそして族議員等の握る既得権益がそうさせる部分も大いにある.つまり社会を動かすことが出来る立場の人間によって,彼らの都合のいいような社会に出来上がっているので,当然溺れている人が助かるわけがない.さてこんな絶望的日本の状況に最近一つの希望の風が吹き始めた.それは福島第一原発の自己によるエネルギーのあり方の見直しだ.これまで電力会社が一極集中的に発電所を設けるスタイルだったが,これを地域分散型に移行することが望ましいと考える意見が増えてきたこと.地域分散型とは電源喪失のリスク分散でもあるし,スマート化が進む中にあってはコミュニティが小さい方が管理は楽だ.そういった科学的側面の利点は当然あるが,これにエコレンジャーとしては是非地域活性化という一つのキーワードを結びつけて欲しいと思う.自我を取り戻すきっかけとなる文化的側面としてだ.これまでは電力会社という一般市民では手に負えない事業者がいたが,その構図が崩れかけている今,電力形態を,そして社会のあり方を自分たちの手で作り上げていくのだ.これは中々一筋縄ではいかない.数十年前はまだ地域コミュニティに意味があって,地元愛というものが少なからず存在したが,今ではもう地元にいる人なんて殆どいないに等しいのではないか.そんな人に対して,ましてや地元でもないのに地域のコミュニティを大切にする心を取り戻させるなんて,もしかしたら政治家が人のために頑張るようになるほどの心変わりなのかもしれない.でもそんな救世主的政治家が国を動かせる地位に上り詰めるのを待つより自分たちで変わったほうがよっぽどわかりやすく楽しくもある.そんな心変わりを喚起する一つの手段として,エコレンジャーは更に文化的興味の共有が鍵を握るのではないかと思う.今でも熱く継承されている何とか祭りや催し物はあるが,そういったものにもっと地元の人が参加するような流れ,それは硬っ苦しくなくていい,別に今の時代にマッチしたイベントを開催していくことが大切だと思う.例えば街コンは一つの地域活性化であり結婚率の低下している現代のニーズを捉えた一つのイベントだ.種類はいくつあってもいい,目標に向かっていく何かを人と共有出来る機会があれば,自ずと地域は活性化し,そんな中で社会環境もいい方向に改善することだろう.自らの意思で幸せを勝ち取る社会を自ら作ることが出来る社会を創ることが,一つの理想の取り組みとエコレンジャーは考える.エコレンジャーは決して経済発展が悪いと言っているわけではない.恐らく経済発展なくして人々の幸せはないと思っている.しかしそのためだけに何かを犠牲にして生きるというのは間違っている.なぜなら人の欲求としては楽しく幸せに生きたいから生きる.これに異論を唱える人はいないだろう.じゃぁどうすればいいかと問うた時,人は何をすればいいか分からない,面倒なことはしたくない,ましてや面倒なことを企画するのはもっと労力がいる,といった結論に行き着いてしまっている.これでは楽しさを得るのではなく楽しているだけだ.そんな堕落してしまった社会に何か一つのいいきっかけを作って活動できたらいいなと思い,ここに記録させてもらった.つまりこれは不特定多数の人に対して公言したこととする.何人がこのブログを読むのかは知らないが.
2012年06月01日
コメント(0)
-
維新の会に望むこと
こんばんは,エコレンジャーグリーンです.最近エコレンジャーはエコ星に生まれ,技術革新でもって世界に持続可能な社会をもたらすことを使命として産まれてきたのだが,大学途中でゲーム理論に出合い,持続可能な社会は技術によって解決されないとの思いが生じてしまった.そして,社会創りという興味から政治関係に興味を持っているのだが,社会人になってとうとう本領発揮というか,政治的な方面に知識が長けた方々とのお付き合いが増え,亜流に磨きがかかってきた.しかしつくづく思うが,やはり環境問題を変えるのは技術ではなく,社会の仕組みを作る側である.ただしそこで付け加えると,所謂官に属する部門だけがいくら頑張ってもその問題は解決できず,産学官の連携が上手く取れることが最も近道である,との思いが現状エコレンジャーにはある.そう思うと,つくづく社会に興味を持ってよかったと思う.話が早くも発散に向かっているが,橋本徹率いる維新の会に対して,エコレンジャーは今こう思っている.勿論勝手な判断半分入っているのであしからず.維新の会の塾の応募者が殺到している.やはりあれだけのリーダーシップと勢いがあれば,有志は集まるだろう.しかしこの維新の会,興味本位で参加した人もいるように,その集まった人間の質がいまいちわからない.もっとまともな議論とすると,政治にこれまで携わったことがない人でほぼ形成されており,思いはあれどノウハウに問題があるようだ.よって実際に維新の会が政治を牽引する日が来たとしたら,恐らくはちゃめちゃになるのではないかとの思いは拭い去ることが出来ない.しかしこれは処方箋として必ず今の日本に必要ではなかろうか.どうやら民主党が立派なマニフェストを掲げながらも気づけば何も改善されていないのは,彼らの意思が統一されていなかったこと,既得権益という脅威に打ち勝つことができなかったこと,が主な原因と思う.そしてこの二つに関しては維新の会はきっと乗り越えられるとエコレンジャーは期待している.前回の投票では,もはや自民党を選びたくないがために民主党だった.今回は民主党もだめだし,自民党も駄目だし,そういった民意により結果かなり荒れると勝手に踏んでいる.そんな中で,ダークホースとしての維新の会がどういう効果をもたらすか,非常に興味がある.さて最終的にエコレンジャーが言いたかったのは,途中でも言った通り,維新の会は処方箋として必要と思っているだけで,今のところ政策として押しているわけではない.ただ維新の会の存在が既得権益やくだらない社会構造を改革し,社会のために産学官が連携し,本当によりよい社会を構築できるような,そんな環境になるといいなと思っている.そうなることを期待し,メーカーに勤めているエコレンジャーとしては様々なネットワークを構築すると共に,その日を迎えた時には最前線で実質的な社会創りに携わることができるよう,しっかり準備をしておこうと思う.
2012年03月24日
コメント(0)
-
2011年回顧録
エコレンジャーグリーンも気が付けば社会人2年目。学生の頃と比べると視野も視点も変わってきた。今思えば学生の頃からこのブログを始めたが、年末に1年の回顧録をつけておけばよかったと思う。ただ過去を嘆いても始まらないので、今年から1年を振り返って思ったことをここに綴っておこうと思う。今年はその初めの年だ。ワールドワイドな報道紙各紙が、今年は世間を揺るがすニュースが非常に多かったと伝えている。アラブの春、ビンラディン・カダフィ・金正日の死等、社会に及ぼす影響度としては年に一回も起こらないようなものが集中して起こっている。そして当然東北の大地震も、まるで映画でも見ているような、あまりにも非現実的な惨状を現実に生み、2万を超える死者を出し、惨禍の爪痕は今尚色濃く残っている。しかし、日本はこの惨事に対して怯むことなく勇敢に戦ったといえる。自粛ムードがある一方で普段と変わらないように仕事をする姿が海外から批判的に見られることもあったようだが、結果的に正解だったとも思う。そして現在は海外からも改めて日本の活力に畏敬の念を抱いているとの話も聞く。エコレンジャーとしても、半ば諦観していた日本もまだまだ捨てたもんじゃないと、認識を新たにした。そして震災の二次災害的に生じた原発問題も、世界中で原子力発電に対する危機意識、そしてエネルギー基本方針の見直しのきっかけとなった。最終的には各国が夫々の立場でもって選択をしている。これは当然で、原子力発電は諸刃の剣であり、一長一短ある。個人的立場は前回のブログの通り人類が文明を維持する上で必要不可欠なエネルギー源と思っており、相変わらずの推進派であるが、ここではその議論を改めてする気もないのでまた次回。橋本徹が大阪市長になり、「府市あわせ」の状況を打破する特効薬として都構想を掲げている。前途多難とのことだが、是非頑張ってほしい。ところでエコレンジャーはこの橋本大阪市長が言った一つについて一言触れて今年(書くのに時間が掛かりすぎて年越しちゃったw)の締めくくりとしたいと思う。「今の日本の政治に必要なのは独裁。独裁と言われるぐらいの力だ」賛成。本来民主主義は、民意でもって国が成り立つ。では民意とは何か。個々の確固たる意志である。では今の日本人は個々にどのような意思があるのだろうか。消費税が上がる、そんなのいやだ。年金が減る、そんなのいやだ。〇〇です、そんなのいやだ。こういったものは批判でありメディアと同じ。TPPに参加する。それは農業が危ないから反対、輸出が有利になるから賛成。こういったものは場当たり的反応であり政治と同じ。まともな民意はもはやどこにも存在しない(勿論一部の有識者にはある)。個々のこういった思いに耳を傾けることも必要だが、最終的にはそれらを総合して、何をすることによって民(国であれば国民だし市なら市民)が全体的に幸せになるかを考えて、あとはそれを邪魔するものの言うことは無視(正確に言えば邪魔するものも意見の一つ)して実行する。無視する、つまり独裁である。これでしかもはや統治が改善に向かわない。なぜなら、今の民意の大半は結局のところ、悲しいかな「自分のお財布に幾らお金が入るか」なのだから。
2011年12月31日
コメント(0)
-
原子力発電の推進~震災後に思うこと~
津波の影響により冷却機能が失われ、メルトダウンまで引き起こした福島の原子力発電所。メディアでは「安全神話が崩れた」、「想定外の出来事」などと報道。皆様はこういったフレーズをどう受け取っているでしょうか。安全神話について、はっきり言ってエコレンジャーは聞いたことがない。神話を作ったのは政府やメディアであって、元々原子力発電所が安全であるとは、冷静に考えれば虚偽であることは明白である。そもそも安全とはなんであるか。広辞苑には「安らかで危険のないこと」「物事が損傷したり危害を受けたりするおそれのないこと」とある。この意味に則れば、原子力発電は真逆の「危険」であるだろう。なぜなら、原子力は皆様ご存知の通りの、広島・長崎のあの惨状を生み出した、人類史上最も凶悪な顔をはせ持つほどのエネルギーを利用しているのだから。想定外の出来事にも言及しよう。まず想定内とはなんのことなのか、それを説明していただきたい。ひょっとすると説明しているのだろうか。エコレンジャー、最近ネット繋がっていないし、テレビも見る時間が中々とれないので見落としているのかもしれない。しかし、危険なもの(やはり自然と危険と表現されるほどに危険だよな)にはかならずそのリスクを減らすように対処マニュアルやシステムが構築されるものだ。しかし、それは所詮人間が考え付く範囲に過ぎないし、また人間が完璧であることを前提としていることも忘れてはならない。システムは一つが駄目でも二重、三重にすることで安全性を向上させているが、それでも確実に危険が0となることはない。今回はこういったケースとは違い人が想像しなかった天変地異による機器のダウンが生んだ事故である。ではしょうがないかといえば、これもある意味不完全な人が考える範囲での対策しか講じていなかったことによる。そう考えるとこれはやはり人間が生み出したミスでしかない。さて、ここまで原子力発電を罵倒したが、エコレンジャーはそれでも原子力は、人類がこれからこの文明を維持して生きていく上では不可欠なエネルギー源であると思っているし、決して矛盾でもないと思っている。まず原子力に対してのエコレンジャーの結論は、まず政府が原子力を推進するにあたり、国民にその危険性を十分に説明した上で、それでも原子力が必要であることを説明すればいい。それを政府は、この説明するプロセスを経ることにより国民に嫌われるリスクを回避すべく、大丈夫の一点張りに走るのだからお粗末だ。そして電力会社には、真剣にリスクを極力0にするようシステムを構築して欲しい。正直なところ、想定外と大きく騒いだところもあるが、どこまで想定すればいいかというのは難しいところなのはわかる。今回の津波の一件を鑑みた中部電力は浜岡原発を停止した。地震対策といっている。確かに今回のプランでは福島で起こった規模の津波であれば対応可能であるようだ。しかし、それ以上の津波が来たらどうなるか、ということに対しては説明がつかないかもしれない。隕石が落ちてきたらどうするのだろう。テロで狙われた場合は。考え出したらきりがない。0にはならないのだ。しかし、それでも考えることが必要である。考えないことにすると、いざ起こったときに今回のごとく対応、発表が後手に回ってしまうから。そして、考えることで見えてくることもまた多くあるものだから。さて、今回エコレンジャーは原子力発電は国と電力会社とで熟慮した上で推進してくれとの立場をとった。それは今回流し程度に触れているが、原子力エネルギーは日本の電力に欠かせないと考えているからである。ただ、そこの議論をし始めると少々長くなるので、今回はこのへんで終わろうと思う。また時間が出来たときに、そして日本のエネルギー事情をもう少し把握した上で書こうと思う。把握してないのに賛成の立場をとるなと怒られそうなもんだが、これは日頃の情報から感覚的なものとしてあるわけで、そこはブログであるという点で見逃して欲しい。
2011年05月17日
コメント(0)
-
働いてから見えること
約一年ぶりの更新です。エコレンジャーグリーンです。社会人になってから、家がネット環境にないんで、中々更新でけまへんでした。てかさっき受信箱に20000アクセス達成しましたってあって、そういやブログ書いてねーなって感じでした。働き出して、学生の頃と考え方が変わっていると思うので、今思うなんか色々を書いてみようかと思います。国の金の無駄遣いについて最近思うのですが、金の無駄遣いってなんやろ?例えばどうでもいいところに道を造るとする。誰もがそこに道が出来たって意味がない、金の無駄だと言う。でも道を造る人たちやその下請け、材料屋等に仕事を与えていることにはなる。天下った人間が退職金で潤う。その金はどこに行くかというと、例えばゴルフ場や高級料理店、高級車なんかに行って、使ってもらった人は潤う。エコレンジャーがいいたいのは、じゃぁ無駄を容認してもいいやないかってことではなくて、借金でもして無駄なことでもしないともはや日本という国は成り立たない状況なんやないかってこと。環境について最近の技術で注目するのは以下のもの夢の太陽電池酸化鉄化合物を用いた発電装置、現在のシリコン製太陽電池の100~1000倍の光吸収率。ただ、発電能力はよくわかっていない。太陽熱発電太陽光発電より発電能力は優秀。太陽光より場所は限られるけど。ただ、やはりコストを重視したり、政治的背景なんかやったりから、環境が今後改善の方向に向かうことは考えにくい。宗教について日本は宗教という概念があまりない。宗教って多分一言であらわすと、生きる指標である。日本は宗教がない変わりに、口でなんとなく伝えられてきている道徳的観念があって、これに支配されているところが大きいようだ。エコレンジャーは近年のような飽食の時代にこそこの道徳的観念が必要になってくると思う。飽食を味わった人間は、現状に甘んじ、わがままになって、精神的に弱い生き物になりがちだ。加えてここ数年で日本人はネット星人へと成り代わり、人との関わりは表面的になっている。しかし、人は悪く言えば、予定調和の中で生かされている。そう、自分の思い通りにはならないのだ。そのことは、組織の中で生きるまでは気づきにくいことだが。しかし、よく言えば、みんなで支えあっていきているのだ。自分だけでは到底生きてはいけないのだ。だからこそ、自分も人のために何かをしてあげなければいけないのだ。そうやって生きていると、きっとそれだけで幸せって感じることが出来るのではないだろうか。生きることに疑問なんてわかない、だって人生は楽しくて美しくて、生きたくてたまらないのだから。締めは「超訳ニーチェの言葉より」もう一度繰り返したいと思える人生を歩もう。(例によって意味は合ってるけど文は覚えてない。)
2011年02月12日
コメント(0)
-
地球温暖化
弱点が花粉のエコレンジャーグリーンです.日本中に杉を植えたのは失敗だと思います.さて今回はいきなり本題の地球温暖化の話. 気候変動に関する政府間パネルIPCCってのがあって地球温暖化問題はこのIPCCによって一般的に知らされたといっていい.このIPCCの報告は 過去1000年間にほぼ横ばいだった気温が、温室効果ガスの排出が増えた20世紀後半に急上昇したことを示す. というものだ.アルゴアがこれを世界的に広めたところもあるかもしれないけど.ところがどっこいこの話は誤魔化しがあったことが発覚.疑惑が浮上したのは以下の通り(産経ネット) 何者かが気候研究ユニット(CRU)のコンピューターに侵入し,1996年から最近までCRUが外部とやり取りした1000通以上の電子メールをハッキングして匿名サーバーに置いた.さらに,温暖化懐疑派のブログなどにその存在を知らせ,メールの内容が明るみに出た. メールの中で、フィル・ジョーンズCRU所長は1960年代からの気温下降を隠すことで,80年代からの上昇を誇張するデータの誤魔化しがあったことを示唆しており,このことについてジョーンズ所長らは流出した電子メールが本物であることを認めているそうだ. さらにメールでは、2001年にまとめられたIPCC第3次報告書の代表執筆者のひとりだったジョーンズ所長が,懐疑派の学者に対して「報告書に論文を掲載しない」「論文誌の編集からはずす」「CRUのデータにアクセスさせない」といった圧力を加えたことがつづられている. これって目ん玉飛び出るほどびっくりする内容なのに,なんでもっと公に報道されないのか理解できない.当然新聞に載ってるには載ってるものの,テレビニュースでももっと大々的に報道する義務がある.まぁそれはさておき,こうも情報操作されているともはや何が正しいのか,どれを信用すればいいのか何もわからない.こんな状態で環境問題に取り組むといってもそれが環境に悪い方向にベクトルが向く可能性があるわけで,少なくとも科学者は嘘の報告することだけはやめてほしい.科学者はあくまで科学に貢献することしか考えてはいけない立場である.とりあえずジョーンズ所長は終身刑やろ.世界に及ぼした被害はいかばかりか…
2010年03月04日
コメント(1)
-
オーストラリア旅行
今更ですが,今年の年始に卒業旅行としてオーストラリア旅行してきました.オーストラリアには友達が何人かいるので,彼らに会うのが目的だったため一人での旅行でした.友達の一人にオーストラリア人がいるのですが,今回アポなしでオーストラリアについて電話した(てか彼の実家の電話番号しか知らなかった)ら会えることになって,結局実家に泊めてもらいました.彼はミュージシャンの卵なのですが親は大学の先生とインテリ系wまぁ色々と楽しかったけど,一つ印象に残ったものを紹介.彼の家はキリスト教で,食事の時にみんなで手を繋いで,「天は我々に恵みを与えてくださった」っていったか知らんが兎に角お祈りした.食事が終わると今度は聖書を持ち出して,何ページでも今日は読むか,とか言って友人サムにその部分を音読させた.そしてパパがそのことについて意見を述べる,なんてことがとりおこなわれたw我々日本人からすると非常に奇怪な光景だと思われます.その後パパと話していると,「エコレンジャーは何教かね?」みたいなことを聞かれた.当然エコレンジャーは無宗教なわけで,でもこれは過去に経験していたのでまぁ我々は宗教という概念はないが,ある種の行動律はもっている,日本人とはそういうものです,って拙い英語で伝え,逆になぜあなたはキリスト教を信じるのですが?と聞き返した.すると彼はキリストの起こりからなんから紹介されて,挙句の果てにキリスト教を勧められたw日本人には宗教はなじまないようだ,というのは島国根性と,人間味みたいなものを我々は重んじ,全ては神という宗教に対し常に我々は人を見る.その違いはもはや根底から覆されることのない精神として人生の中で叩き込まれているからだ.みたいなことを「日本人とユダヤ人」の中でイザヤ・ベンタンが言っている.多分.でも彼らはキリストという絶対的が存在するのに対し,今の日本人はもう絶対的な精神,所謂過去の武士道たるものを持っていないため,残念ながらもう宗教がなじむかもしれない.
2010年02月24日
コメント(0)
-
長崎県知事選
21日に開票があり,自公推薦の中村法道氏(59)が与党3党推薦の橋本剛氏(40)ら6人を破り初当選した.この背景には民主党幹事長小沢氏や鳩山総理の「政治と金」問題がネックとなっていることが報じられている.前原誠司国土交通相は「首相、幹事長にどうすれば参院選に勝てるか考えてもらわないといけない」と指摘,とある.政治家は非常に難しい立場で,自分が如何に情熱を持って臨んでも,与党にならなければやりたいことが出来ないのが実情である.自民党を離党した田村耕太郎も離党理由をそのようにコメントしていた.でも前原氏のこのコメントから察するに,党全体で見るとなんか結局見ているところは国策ではなく選挙なのかなぁと思うコメントでもあるような気もする.ここはでも報道の仕方によって印象が変わるところではあるのかねぇ.それから長崎県民は一体何を中村氏に望んだのだろうか?民主党もなんか「政治と金」問題で株が落ちたよねぇ,なんて気持ちで中村氏に投票したのならこれは非常に残念でならない.しかし報道の仕方なのかもしれないが,そのような印象を受ける.本来県を動かすのは党ではなく知事本人である.知事の中で誰がいいのか判断することが投票であるといえるから,もしこれが事実ならやはり国民の政治意識の低さというものが窺える.ただこれまでで一番感じたことは,やはり報道側がもっと有意義な情報を国民や市民に見せるべきだということだ.最もそれどころかメディアは情報操作で我々に有意義な情報を意図的に流さないようにしているが.どのローカルテレビ局でも県知事選や市長選があるときは開票結果じゃなくて,キャンペーンの様子や立候補者同士の対談を流してくれたらいいのにと思う.しょうもない情報しか流さないから国民がしょうもない方向に流されているのではないだろうか.
2010年02月23日
コメント(0)
-
エコのゴール
あまりにも用意周到なため,金曜日発表の準備が殆ど終わってしまい,心にゆとりありすぎて本日二度目の登場,エコレンジャーです.突然だがエコって一体何なのか,結構難しい問題であり,エコレンジャーの悩みの種である.これは恐らく資本主義社会の行き着く先なみに難しい問題で,質も似ていると思う.例えば,我々が働く理由というのは生活のためっていう方が多いかもしれないが,少なくとも人のためになっているから金を貰えるのだ.では人のためって何なのだろうか?人がよりよい生活を送るため?幸せになるため?産業革命が興り人々の生活は非常に便利になったといえるだろう.では果たして幸せになったのだろうか?これはいささか疑問である?恐らく農耕民族であった時代の方が平均的には幸せだったのではないでしょうか?ではエコって一体何に向かっているのだろうか?最近ではCO2と気温上昇に関係性はなかったとの結果がIPCCの重役の間で示唆されていたとして問題になっている.この話は今後どのように波紋が広がるかわからないが,一応は低炭素社会を目指しているようだ.現在はこの炭素を食い物にしようと世界中で利権が飛び交い,日本は食い物にされそうな勢いである.日本はこうならないためにも,そして日本というブランドを守るためのエコ活動が重要である.しかし本当のエコではない.では次の話として,仮に技術国が頑張った結果低炭素社会が実現したら終わりだろうか?否,そんなことはなくて,いずれ訪れるエネルギー源の枯渇問題に頭を抱える時期が訪れる.因みにエコレンジャーは低炭素社会の実現の前にこの問題に直面すると思っているが.こうなると今度は新エネルギーの開発に躍起になる.しかし結局太陽エネルギーの効率は劇的に改善されず,その他ゼロエミッションエネルギーも効率は今一つ,結局原子力が発展するものの,これも枯渇に向かい,気づけば人は産業革命以前程度の生活レベルしか保てなくなる.じゃぁ何のためにエコ活動を頑張るかというと,生活レベルの低下を極力スムーズに行うことが重要となるのではないだろうか.これも結局エコというより政治的側面の方が色濃い.じゃぁ仮に夢のようなエネルギーが手に入ったとしよう.以降石油に頼る必要も原子力に頼る必要もないのだ.しかし問題が発生,濃縮ウランや石油に頼っている国は経済破綻,このままではまずいとこのエネルギーの利権争い,果ては戦争でも興りそうなものだ.原子力はもはや核兵器でしか使う意味を失い,原爆がドカーン.こんなことは誰も望んではいない.人が死んではエコもくそもない.結局エコなんてものは利権ありき,生活ありきの話である.エコもある意味ではくだらない.それでもエコレンジャーは頑張る.政治的側面に関しては誰かが上手にカジ取りしてくれることを信じて.
2010年02月15日
コメント(0)
-
国母選手の服装問題
エコレンジャーも人間時の服装は国母選手に非常に近いです,修了間近の忙しさを乗り切っての日記の更新,エコレンジャーグリーンです.エコレンジャーの母がモーグルを見ながらこんなことを呟きました.「最近の日本人選手は度胸があるねぇ,昔は日の丸背負っているってのがプレッシャーになって,中々うまくいかないもんやったけどねぇ.」まさにその通りで,最近はグローバル化が非常に進んで,自分が日本人であることに誇りを持っている人間が格段に少なくなったと思われるのです.更にアメリカの個人主義的な考え方が浸透し,どうしても周囲の存在を軽視しがちなのが最近の傾向ではないでしょうか.いい面2割,悪い面8割ってところでしょうか.ただ最近は品格ブームでなにかと品格が問われる世の中になってしまったのですが,一番品格がないのはやはりメディアでは?と思うのはエコレンジャーだけではないはず.ここで冒頭服装について,国母選手と似たエコレンジャーの意見を.服装,見た目は自己主張でありその人の本質を表面化したものだが,これは決してB系の服着てるから恐いとか,黒いメイク,服装だからメタルが好きだとかそういう単純なものではない.人間深く付き合えば違った一面が見えてくるし,そもそも見た目の持つイメージと実際にギャップがある人間は多い.ただし,服装にはTPOに大きく左右されるものであることは間違いなく,これは時代が変わろうとも決して変わることのないマナーである.じゃぁ今回の移動中の服装ってのはどうだろう?エコレンジャーは別に移動中から気を張り詰める必要は必ずしもないのではないかと思う.この意見にたしても賛否両論だろうが,別にスーツを着たから優勝できるわけでもないし,寧ろそのような慣れない格好をして疲れる方が嫌だ.エコレンジャーの嫌いな日本の文化の一つに,とりあえず見た目だけでも見繕いなさいという風習だ.傍目を気にして中身を磨かないでは意味が無い.寧ろ見た目でどうこう騒ぐ奴らに限って中身がないことが多い.エコレンジャーは思う,国母選手のプレイを見てから彼という人間を判断すべきだと.まぁ会見で少々本質が見え,既にプレイを見る前から正直がっかりしてはいるが…エコレンジャーなら何とバッシングされても,移動中は楽な格好でリラックスしたかったからだ,逆にあなた方はこの会見のせいで私がコンディションを崩して結果が惨憺たるものとなったらどう責任とっていただけるのですか?なんてマスコミその他に喧嘩うってやるけどねw以上,ブログでなら大口たたけるエコレンジャーでした.
2010年02月15日
コメント(0)
-
相撲業界
過去の日記を見返すと,約1ヶ月半振りのようです,久々の登場,エコレンジャーです.年末年始から今日まで非常に忙しく,ほったらかしにしてしまいました.この期間色々あったのですが,そのうち落ち着いたらそのことも書こうかと思います.さて,最近相撲業界は土俵の外で相撲をとることが多いようです.自分なりに朝青龍の引退問題と,その周辺で問題になった品格の問題について考えてみました.相撲とは日本の国技として過去何百年にわたり脈々と受け継がれてきた誇るべき伝統です.この伝統の中にはただの勝負でなく,それ以上に心技体の極みなるものがあると思われるわけです.それが最近の相撲の多国籍化に伴い,どうも試合に勝つことだけが教えられるようになったが為に品格を問われるようになったのではないかと思うわけです.実際見聞きしたわけではないにしても,その様子がこちらに伝わらないということはそうなんだと思うわけです.これは一つに日本の長い歴史の中で培われてきた文化を他国の人間には理解できないことが理由に挙げられますが,これ自体は問題ではないと思います.寧ろそれを諦めて,若しくは見過ごしてお相撲をとる練習ばっかりさせているような気がするわけです.つまり親方の問題であると思うわけです.そしてまさにこの親方の質の問題により,門下生殺人事件が起きたり,今回の朝青龍の暴力事件が起きたり,大麻問題が起きたりするのだと思うわけです.親方が悪いただ,朝青龍は横綱であるなしに係わらず,人に暴力を振るっては流石にいかんな.はい,やはり若乃花親方の主張する改革は必要だと思います.自民党と同じく若返りが必要だと思います.脳タリンジジイが上に立ってていいことは一つもありません.勿論,脳ある年寄りは重宝されるべきだと思いますが.
2010年02月09日
コメント(0)
-
知るのではなく,理解する
どうも,最近研究以外のことを考える時間が非常に多くなっています,エコレンジャーグリーンです.これは一つに,いや,これが殆どを占めるのですが,卒業生に与えられた最後の試練,修士論文の執筆が,恐らくエコレンジャーにとってさほど苦にならないこと,なぜなら修士論文の執筆はエコレンジャーにとって,既に発表した研究を纏める”作業”でしかないこと,もう一つは,最近物事全てにおいて”理解”しようという性質になってきたからなのです.先日,エコレンジャーの祖母の七回忌がありました.ここでもふと,法事にはそもそも何の意味があるのだろうか,と考えてしまいました.これだから理系は嫌ですw法事とは,結果だけ見れば,現世に残されたものの自己満足でしかありません.勿論この結論は,死者にとってはもはやこの法事に意味を持たないから,という魂等の存在を認めない場合のものですが.となればこの法事は我々に意味を持たなければ意味がないのです.さて,ただ個人を偲ぶこと以外に何か意味があるのだろうかと考えていると,坊さんのお経が終わった後,まさに説法でこのことを少し話してくれました.考えていたくせに,あまり詳しく理路を覚えてないのが,エコレンジャーの散漫ここにあり,といった感じですが,つまり,我々現世を生きる人は精一杯生きることが必要である,とおっしゃってました.理路を覚えていないのは,散漫の他に,彼の説く理路そのものを理解しきれなかったのもあります.また,祖父は言いました.このような機会にしか,親戚一同が顔を合わせる機会ってものはないのも皮肉ですが,やはり皆の健康をこの目で確かめるという意味も含め,このような機会を設けました.これはそこそこに納得のいくものでした.話は変わり,勉学について.エコレンジャーは現在家庭教師をしています.現在高校3年生の生徒に数学と物理を教えているのですが,このうち電磁気学というものから離れすぎていて,もはや教えるどころか,こう書いてあるからそうなんやろう,とまるでエコレンジャーが生徒レベル.これはまずいと思い,電磁気学の本を借りて現在読んでいるところです.すると,過去勉強したときと違い,本質を理解しようとする思考パターンになっているために,理解の度合いが過去と比べて雲泥の差であります.これは自分でもびっくりです.やはり物事を知るには,面倒なようで本質を理解することが近道であると,肌で実感した今日この頃でした.
2009年12月16日
コメント(0)
-
ブタがいた教室
どうも,国際学会が終わり現在抜け殻状態のエコレンジャーグリーンです.もはや大学院で取り組んだ勉強もほぼ纏まってしまって,修士論文はもはや形式的なものとなるため,自ずと力が抜けるもんです.こんなんじゃいけないのでしょうが(^^;A)これから卒業までは前回の日記で述べた英語と,小説と,それから映画を出来るだけ見ていこうと考えています.文化的な知識が疎かなのもどうかと思いましたので.まぁ専門知識もアウトローで,今後直接的に役にたつものではありませんが…昨日は「ブタがいた教室」を見ました.これは,密かに天才的芸人江頭2:50が彼のネット配信番組で紹介した映画で,評価の方はもう忘れましたが,そのとき見てみたいと思った作品でした.内容は,ある日妻夫木演じる小学6年生の担任が,クラス受け持つ時に一匹の子豚を持ってきて生徒にこう言う.「人間が生きていくうえで必要なものはなんですか?…(生徒の意見)…そうです,食べ物です.みなさんに子豚を飼って育ててもらい,その肉を食べることで,命の大切さ,ありがたみというものを肌で感じてもらいたいです.」(みたいなこと,毎度ながら台詞は違うと思います.)それから1年間豚を育て,最終的に生徒達に豚をどうするか議論させ,結論を導かせる,というもの.この議論には,大人のすれた意見というものがなく,素直な気持ちでぶつかっていく様子がありありと映し出されて,逆に緊迫感がある.勿論子供の意見のぶつかりだから,中々前には進まないのだが,それもらしくていい.この映画,最終的に生徒の意見が多数決の結果イーブンで最終的に先生に決定を委ねられるのだが,その先生が一番考えがぶれていて情けないと思ったし,最終的に豚は食肉センターにつれていかれることになり,皆の口に入らないのも残念だったが,まぁそこはエコレンジャーとしては,映画評論家ではないのでもはやどうでもいいことである.一人の転校生がこの豚を心から可愛がっており,考えも他の生徒より少ししっかりしているのだが,この子から発せられた疑問が忘れられない.議論の的となる,非常に端的に述べて,この豚はもはや愛着があるため他の豚とは違うか,それとも,やはり豚だから食べるのかということに対して,そもそも豚は食べられるために生まれたのか,という純粋であり本質的な疑問であると思った.人間は命に対してかなり自分勝手である.他の生物の場合は,己の種の繁栄の為に必要なものは食べるし,そうでないものには興味がまずない.種の存続が大切なのであって,命が大切なわけではない.しかし人間の場合は,命そのものの大切さを考える.それも,比較的でかい生物の命を重要と考えている傾向にある.日本では鯨を食べるが,他国では食べないため,日本は責められる.しかし鯨を食べてはいけないとそもそも決めたのは誰だ.豚だって宗教上食べない人たちはたくさんいる.牛が駄目なところもあるし,我が研究室の留学生なんか殆どの動物が食べれない.しかし魚だったらいい.韓国の北の方では犬を食べる.しかし犬はペットとして親しまれている日本人や恐らく他の国の人からしても,犬を食べるのは野蛮だと考えるに違いない.こんな適当なルールはいったい誰が決めて,誰が非難しうるのだろうか.また,人間は虫なら平気で殺す.蚊が腕に止まったとき,一体誰が「嗚呼,この命を奪うのは罪である」と考えるだろうか.ひょっとしたら存在するのかもしれないが.人間はその意味で,やはり自分達が生物界の頂点に立った気でいるといえるのではないだろうか.生物の命を相対評価しているのだから.さて,純粋すぎて困る疑問だが,やはり生物は基本的に種の存続の為に産まれたのではないだろうか.それなのに勝手に人間が命に重み付けをしているだけに過ぎないと思う.しかしこれは理屈であって,エコレンジャーの答えではない.エコレンジャーとしては,結局人間はいつも身勝手で自己陶酔している生き物であり,あえて命の部分で理屈っぽくなるよりは,そここそ一番我がままであることが人間らしくて好きである.だから,個人個人の理屈を他人に押し付けるのもまたよくないと思う.以上,かなり考えさせられた映画でした.
2009年12月08日
コメント(0)
-
国際学会
昨日,今日と国際学会がありました.エコレンジャーは勿論国際学会は初めてです.まぁ国際学会といっても,発表者は結果的に全員日本人,ゲストスピーチが韓国人とOZという顔ぶれで殆ど日本の学会と同じような雰囲気でした.会場も自分の大学だったし...でも英語での発表ということでやはり少しは緊張しましたが,無事にやり終えました.ただここで言いたいのは自分の発表の話ではなく,英語の話.国際学会を通して思ったことですが,日本人というのは英語が恥ずかしい程に下手です.勿論これは人によるし,比較対象が世界という前提の話ですが.でも日本は世界と戦っていかなければならない国で,島国根性で他国が日本語を喋れればいいんだ,という怠惰な欲に負けて英語から目をそらしてばかりではいけないのです.これまで文法レベルだけやたらと高く,喋れないくせに,人が文法間違ったら心中嘲笑しているような国民性の日本人,そのため自分も極力英語の使用を避ける日本人,こんなんではいつまで経っても英語の成長はありえない.いざ英語を使う機会が突然に訪れ,聴衆の前で恥をかくかそれとも普段使える機会に間違って恥(でも何でもないが)をかくかおれはエコレンジャーなのですが,やはり両者とも恥ずかしいのですが,やはり前者はかなりみっともないと感じたので,後者をとろうと思います.しかし,普段でもあまり間違えないために,普段から英語を勉強するべきだとも思いました.以上,今後の目標でした.
2009年12月05日
コメント(0)
-
亀田vs内藤
大のボクシングファンであるエコレンジャーとしては,2年前の次男大毅との一戦から早2年,漸くか,という感じだ.まぁ亀田家自体がごたごたしていたこともあって,これだけの期間が開くのはいたし方のないことではあるが.エコレンジャーの予想では亀田が巧く立ち回って圧勝だろうと思っていたが,まぁ大方予想通りってところだったな.亀田興毅は足を使ったカウンターパンチャー,しかし自分から手を出す積極性も持ち合わせていて日本人の中ではパウンドフォーパウンド的にトップ3には入る選手と思っている.パウンドフォーパウンドというのは,階級の違いをなんとなく包含した場合の順位.つまり実際1階級違うというのはかなりの違いのようで,通常上の階級の方が強い.しかしその差をなんとなく無くしたという仮定の話.現在トップは長谷川穂積だろう,これは間違いない.次は西岡か亀田興毅だろう.試合は面白かったの一言に尽きると思う.しかしどうやら試合の裏では様々なゴタゴタがあるようだ.TBSが今回の試合の興行権を握っていたようだが,結構身勝手な行動をとったようでボクシングの放送時間TBSで本来やっているドラマの主役小出恵介がリングアナウンスを担当し,見事アナウンスミスを犯した.因みに通常はその道のプロがやるもの.海外の世界戦を見ていると,ビッグマッチでは同じ人しか見ない.リングアナウンサーに,最後の判定の採点結果を発表しないように申し出た.採点結果をアナウンスしないってのは例えばフィギュアスケートで,点数を発表せず,1位キムヨナ,っていってるようなものだ.ありえんやろ.(ref. mixiニュース前回の大毅戦で,テレビ局が出しゃばってあれだけ叩かれたのに,懲りずにボクシングを汚そうとする責任者の気が知れない.また,ジムの方でもゴタゴタがあるようだ.詳しくはわかんないけど.神聖な檻の中で戦う二人の世界を邪魔する者は,環境破壊に目をつぶる輩もろともこのエコレンジャーが鉄槌を下してくれるわそれにしても次はポンサクレックか,楽しみすぎる.長谷川もそろそろビッグネームとやってくれんかなぁ,あれだけ強いんだし.
2009年11月30日
コメント(0)
-
シンポジウムin釜山
我が大学院では年に一度交流の意味で韓国の釜山大学校と浦項工科大学校の生徒が集まって意見交換発表会なるものが催されます.口頭発表もあるが,基本的にはポスターによる発表.エコレンジャーグリーンはポスターで今年参加させていただきました.英語での交流ということで,かなり精神力や勇気がいるものですが,まぁ海外経験も実力が伴っていないながらあるし,エコレンジャーは意気揚々と臨んだのですが…日本人も韓国人も基本的にはシャイのようでemoji code="h263" />質問しようとjポスターの前ではってみたが本人は何処か雲隠れエコレンジャーのポスターには誰一人として来ずorzまぁこっちのポスターはお門違いなので仕方ないとしてもだな,逃げるはねぇだろ,一体何しに来たんだよって感じでした.勿論意思疎通レベルの英語が難なくできる人なんかは真面目にやってて,無理やり質問して全く意味わかんなかったけど(笑)日本人も日本人で結構酷くて,ポスターの人は5分の紹介プレゼンが設けられていたのですが,完全に原稿読んでる人が結構存在したし.全体を通してなんか拍子抜けのシンポジウムでした.話は変わって,韓国そのものの印象についても書き留めておこうかと思います.メシ編日本との大きな違いといえばサイドメニューがついてくるところ.焼肉屋ではサラダ,サンチュ他肉以外の食べ物はただで食べれるのが魅力.一番凄かったのは,酒が一合勝手に出てきたこと.これには同じ研究室の韓国人もビックリでした.ただ,必ず辛い食べ物があるのがやはり我々日本人には抵抗あるんじゃないでしょうか.折角のしょうゆ味で味付けしたチャプチェなんかも,他の辛い食べ物のせいで味がよくわかんなくなることがよくある.結局残る感想は美味かったけど辛かっただった.人,街編日本とアメリカのフュージョン国って印象でした.街の造りや電車の中での人の行動なんかは日本人そのものって印象を受けました.電車では若者が携帯か音楽で自分の世界にはいってます.しかし夜の繁華街の様相は日本とまるで違い,ギャルは勿論のこと,普通の大学生までもがクラブかなんかで楽しんでいるのか,道行く人は十人十色でした.それからスーパーマーケットの造りなんかもアメリカ的で,兎に角なんでも揃ってますサイズでした.
2009年11月16日
コメント(0)
-
エコナ油の発癌性
もうほとぼりは冷めてしまったような気もするが,花王が自社のエコナが発ガンの危険性があるとして,自主回収を行っている.この話,巧みなメディアの情報操作によって我々に謝った知識を植えつけていると言える.問題になった成分はグリシドール脂肪酸エステル,これがエコナに含まれており問題になった.この化合物が問題かといえば少し違っており,発がん性が示唆されるのはグリシドールである.グリシドール脂肪酸エステルは勿論その組成にグリシドールを含んでおり,体内で分解されグリシドールに分解される可能性があるが,どの程度かはわかっていない.また,グリシドールの発がん性もまだ,マウスの実験でその可能性を示唆する結果が出た段階で,人間への影響がどの程度かもわかっていない.ただ,消費者から不安を消し去ろうという配慮から花王は回収に踏み切ったそうだ.このエコナに発がん性が全くない,つまり0とは言えないからだ.しかし,はっきり言ってそんなことでごちゃごちゃ言うくらいなら,世の中他にも発がん性物質を含んでいて,それをわかっていながらも摂取しているそちらの方を気にしたほうがいいと思うが,どうでしょう.エコレンジャーは少なくとも酒はやめないな.エコナもやめない.タバコは吸わない,体にいいことなど何もないから.
2009年10月22日
コメント(2)
-
教育の厳しさ
昨日カンブリア宮殿にてモード学園創設者谷まさるがゲスト出演していた.簡単にモード学園を説明すると,専門学校でありながら四年制をとっており,大きくはデザイン系,グラフィック系,看護系の三部門からなる(ホームページを見る限りそうは見えないけれど昨日テレビではそう紹介されていた).完全就職保証制度をとっており,就職希望者の実に100%が内定をもらっているのがモード学園の凄いところである.紹介VTRを見る限り,ここで四年間修業した人なら間違いなく社会で即戦力だなという印象を受けた.就職率100%も頷ける.そう思わせるのはここの教育にある.谷氏の教育方針は・授業に出ろ・課題を提出しろこの二つらしい.これだけ聞くと大したことないように思えるが,その課題の数が相当多いようで,ただ課題をこなしていくことがもう厳しいようだ.この課題を着実に四年間こなしていく上で既に社会で必要な忍耐力が養われそうである.谷氏自身,教育はスパルタだとおっしゃっていた.さらに,人との接し方も身に付くようで,謂わばこの場が既にある種の社会といった感じだ.一点気になったことと言えば,就職率100%は四年間修業したものが母集団であり,脱落者も結構な数になると思ったが,そこには勿論触れるわけもなく,これはエコレンジャーの推論.これも一つの教育.我が研究室の方針は真逆だ.研究室にはコアタイムが存在しない.課題も漠然と与えられるが,期限は存在しない.それは課題が未知への挑戦であるため,これだけやれば結果が出る,と単純にはいかないこともあるが,それ以上に自己のペースを重んじている.聞こえは堕落し放題だが,この方針の裏側には全く逆の思いが潜む.全てが自己責任という状況下で如何に自分を律し,様々な欲に打ち勝って勉強に勤しむか,そこを鍛錬する機会として研究があるというわけである.教育の理想としてはエコレンジャーは後者の方が好きである.しかし後者では滅多に自分の欲との戦いに勝つことが出来ないのが現実でもある.実際はどちらの教育の方が正しいのだろうか.それともやはりどちらも一長一短あって,答えはないのだろうか.
2009年10月13日
コメント(0)
-
不良の改心
ぽんた君っていう一人の青年がいた。昔はけっこうワルだった。色んな奴を虐めたこともあったなぁ。しかし、そんなぽんた君も今ではまじめ。人を虐めることもなけいし、寧ろ改心して極力波風立てぬよう生きている、過去自分がしてきたことを悔やんで、今ではその罪を償っている。なんで改心したかって?過去でかい顔をしていたぽんた君に一つの事件があったんだ。転校生のはっぱ君にぼこぼこにやられたんだ。それ以来ぽんた君はでしゃばるのをやめちゃった。はっぱ君はでかい顔して好き勝手やっている。勿論ぽんた君は文句一つ言わない、彼が怖いから。でも最近はっぱ君は心変わりしたみたい。みんな仲良くしようと言い出したんだ。まだ影では人を虐めているけど。そしてもうみんなを脅すのはやめようと言い出した。自分はみんなににらみをきかせているけど。表面上変わったはっぱ君を見て先生は言った「はっぱ君はみんなの鏡です、みんなはっぱ君の言うとおりにしようじゃないですか。そしてこの勇気ある言動を讃え、おおば君を表彰します。」はっぱ君は恐れ多いといいながらも喜んで賞された。問1ぽんた君はこの表彰をどう感じたでしょうか。A:羨ましいと思った。B:なぜ彼が讃えられたのか理解が出来なかった。C:心から彼を讃えた。D:キレた。正解C解説なぜならぽんた君ははっぱ君が怖いから、いい顔してないと後でどうなるかわからないから。
2009年10月11日
コメント(0)
-
文学小説を読む
学生生活終わりへのカウントダウンを勝手に始め,完全に充実させるための方程式をたてて生きています,エコレンジャーグリーンです.こんな言い方すると,まるで一日一日スケジュールが決まってそうなものですが,決してそういうわけではなく,大雑把にあれとあれはこなすぞ,という意気込みがあるだけです.社会に出るにあたり,どうも文学に触れていないと恥をかくことが多い気がして,そう,まさに「恥の多い人生でした」なんて後悔しなくていいように,学生の間に本を出来るだけ読もうと心に決めました.恥というのはつまり,現在の社会問題の一つである”日本語力の低下”,これを露呈してしまうことです.世界は急速にグローバル化が進み,日に日に英語力が必要であると言われているのだけれど,最近では一方で日本語を疎かにする傾向があると勝手に思っています.また事実そのことを中傷したセミリンガル(2ヶ国語とも生活できる程度には使えるけど,どちらも中途半端な人)なんて言葉がある程です.そこできっと将来英語は否応なく勉強すると判断し,今は日本語を学ぼうって魂胆です.勿論勉強ですので,単語帳なるものを作り,わからない単語があれば書きとめ,辞書で調べるようにしました.すると,ゴキブリが湧いて出てくるが如く,次々と知らない単語が出てくるわけで,改めて自分の語彙のなさを痛感しているところです.そういえば,ブログを始めたきっかけは文章をきちんと構成して書く鍛錬もあったと思い,昔は昔で自分の日本語力のなさをやはり認識していたわけで,そんな過去の自分とシンパシー感じてます.もう学生生活残り半年になりましたが,出来るだけ多くの文学に触れ,せめて日本語に対して引け目を感じることなく社会に出たいという思いです.
2009年10月06日
コメント(0)
-
党再生会議
歴史的大敗を喫した残念極まりない自民党が今後自民党を立て直すために開かれたこの会議.しかし,落選した議員達からは落胆を隠せない面持ちで,不平不満を並べたという…さて,ちらっと新聞で読んだだけやし,今手元にその新聞があるわけでもないので会議の詳しい様子には触れないとして,感想としてしょーもねー奴らがこうも見事に落選すると,コメディとしか言いようがないなぁw仕事が欲しいと漏らし,党の人たちは苦笑したとかあったが,それがまさに現在の我々が切に願うことである.しかも,選挙戦では民主党の中傷ではなくもっとマニフェストに力を入れるべきだったんだと当たり前のことをぼやきながら,きっと半ば幹部のせいにしてるんだろうなと思うと,これまた日本の縮図のようであり,いと面白きことかなw
2009年09月17日
コメント(1)
-
電力分野から見た「持続可能社会」への貢献
こんなタイトルの集中講義が昨日ありました.環境問題の真実と課題みたいな話に触れたのは久しぶりでした.エコレンジャーの環境熱を呼び覚ますのには十分なないようでしたw大まかに話を纏めると,三大難問として水(食料)問題,エネルギー問題,環境問題が挙げられるということで,夫々,特に前者2つが重要として講義された.水問題,これは人類が生きていくに不可欠な資源であり,この問題は過言でもなんでもなく死活問題である.特に最近では砂漠化と地下水の枯渇が問題視されている.これを解決するのはこの講義では解決策として2つ,海水の淡水化と砂漠の緑化であると紹介された.海水の淡水化は人間の英知からすれば解決可能な技術であると思う.砂漠の緑化というのは現実味のない話のように思われる.しかし,この誤った常識はこの講義を持って覆されることになった.元来文明が発達した地域は全て砂漠化したのだが,これは天候が原因ではないようだ.因果が逆で,森林を伐採した結果負のサイクルが出来上がる,つまり水分を含んだ風が吹き抜けるために雲に発達せずに雨が降らなくなったようだ.ということはつまり植林すれば自ずと雨は降り,緑が取り戻せるサイクルが出来るとのこと.俄かには信じがたい話だが…これが本当かどうかは数十年後にわかると思う…エネルギー問題.これは現在の生活レベルを保つのに必要な資源である.エネルギー,特に石油は貴重で,これを巡っての戦争もあるため,ある意味水問題よりもたちが悪い.因みに石油の可採年数は多く見積もって50年,自分の世代が生きている間に起こる話である.改めてそう言われるとやはりこの問題も早期解決が必要である.将来のエネルギー問題を救うのはなんだかんだ原子力が現実的である.現在の軽水炉から高速増殖炉に方式を転換することで現在のウラン可採年数が数十年から数千年,100倍のオーダーとかなり期待出来る技術である.あとはバッテリー.自然エネルギーは安定供給の面で難有りだが,優秀なバッテリーが登場すると,もはやエネルギー問題はほぼ解決と言っていい程だ.環境問題.これは眉唾問題なのでさらっと説明されたし,まぁそんなもんだろう.地球温暖化がかなり問題視されるが,上記の二つに比べれば屁問題.勝手な予想として2050年までに温室効果ガス排出50%削減とか言ってるが,それ以前に第3次オイルショックの到来で温暖化の話はどっかにいってることだろう.来年から就職のエコレンジャーグリーンはまだ職種が決まっていないが自分の中で営業技術が7割,基礎研究が3割くらいの希望度だったが逆転した.
2009年09月09日
コメント(0)
-
エコポイント
約15年使い続けてきた家のブラウン管テレビの寿命が近づいてきており,とうとう液晶テレビを買うことになりました,エコレンジャーグリーンです.テレビは現在主に液晶とプラズマが主流ですが,プラズマは液晶と比べて電気をかなりくうらしく,その他もろもろの条件も加味し液晶に決めました.買うのは親ですけど…しかし,テレビは非常に高い,いいのだと30万近くかかります.その代わり環境基準クリア商品は話題のエコポイントがかなりついてきます.今回の買い物では39000点ゲットしました.しかーし,いざエコポイントを得る立場に立ってみると非常に面倒極まりないシステムであることがわかった.エコポイントは買った瞬間にカードかなんかに加算されるもんだと思いきや,そんな現代のIT化に反した手作業システムである.まず一枚の申請書になんやかんやごちゃごちゃ書き,商品の保証書やら領収書だったかなんか3枚ほど貼っ付ける.ネットでも出来るらしい.このときに商品と交換したい場合は,最大4つまでポイントを商品に変えることが出来る.これも記入する.するとどっかの団体の方が審査をし,2ヵ月後に晴れて商品ゲットとなる.おおまかにはこんな流れらしい.審査ってなんやってまず思う.商品を売り出す前に審査は終わってるだろ.2ヶ月ってなんや,IT化して全部で1週間で終わるよう工夫できたやろ.親曰く,面倒な手続きさせてエコポイント使わせないようにしたいんやない,だって.結局天下り団体のお偉いさんのポケットにいくらか流れる仕組みなんかねぇ.また環境という正義の盾を隠れ蓑にし悪が蔓延る例の流れなのかねぇ.因みにエコポイントで交換できる商品は非常に限られている.折角最近壊れた電子辞書を新調しようと思ったのに…まぁ店の商品券に交換できるからいいっちゃいいけどね.
2009年09月07日
コメント(0)
-
衆議院選挙
歴史的政権交代から二日経ちました.まだメディアは興奮冷めやらぬといった感じです.エコレンジャーグリーンは興奮せずにじっくりと見届けたい所存でございます.最終的に獲得したそれぞれの党の議席数が綺麗に纏めてあったサイトリンクします.http://www.tbs.co.jp/senkyo2009/shu/sys/box.htmリンクシタイガデケン結局民主党の圧勝.自民公明の大物が民主党の悩殺ヒットマンにやられるケースも多く,小泉チルドレンの次は小沢チルドレンかって声も多くあるようですが,民主党のエース原口さんは,彼女達は信念があり,付け焼刃議員ではないと説明していたので,少し安心ではあるかな.ただ,圧勝も圧勝で,ここまで圧勝ってのはやっぱりエコレンジャーとしては望ましくなかったなぁと思うのだが,みなさんはこのような結果を望まれたのでしょうか?ネタとして若干メディアを騒がせた幸福実現党は議席を獲得しませんでした.公明党と共産党はなんと小選挙区での獲得議席0!まぁ今回は特に結果をつらつら述べるだけに留めておこう.だって,特に感想を持てるほど政界に詳しくなく,なんとまぁあの人が落選かよ (-.-)=3 なんて驚嘆もなかったわけで…それよりも今回の政権交代はまさに日本が新たな一歩を踏み出したわけで,自分の意思で投票を行った国民はより政治に興味を持ち,民主党の舵取りを見守り,まさに民主主義国家の一国民として共に歩んでいくのだ.それがなにより楽しみ.
2009年09月01日
コメント(0)
-
選挙でふと思ったこと
最近研究を理由にブログから離れていました,エコレンジャーグリーンです.基本的に真面目に仕事や研究に取り組んでいる人は,物事をその分野の視点で視たり考えたりする傾向がどうもあるようです.腐敗しきった政治に国民が呆れ,民主党が完全に勃興し,その勢いたるや議席過半数もむべなるかといった感じ.自民党は早くも野党のような扱われ方,見ていていたたまれない気持ちになる,とは思うわけもない.自業自得である.民主党が政権をとるとみて間違いないだろう.しかし,民主党の圧勝とはいかがなものかと考える.あまり政治に詳しいわけではないが,日本の政治のいけなかったところというのは一党独裁の状態が長いからではないのだろうか.最良の状態とは民主党が政権を握ることに非ず,複数の政党の人気が拮抗して切磋琢磨しあうことにある,とエコレンジャーは思っている.そう考えると,これはゲーム理論でいうマイノリティーゲームに少し似ているよなぁと思った.もし国民の大多数がエコレンジャーと同じような考えを持っていたら,世論調査ではどこの政党が有利かという情報を得て,それに応じて少し不利だとされる政党に投票する.すると結果的には有力な複数の政党が互角の戦いになる.勿論実際はみんなそんなこと考えていないし,寧ろもっと真面目に政党を選択するだろうから,その方々からすれば非常に不謹慎な話なのだが.でも,例えば民主党を応援している,だから民主党を更によくするために民主党以外に投票する,という考えもありえない話ではないと思いませんか?
2009年08月26日
コメント(0)
全160件 (160件中 1-50件目)