2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年01月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
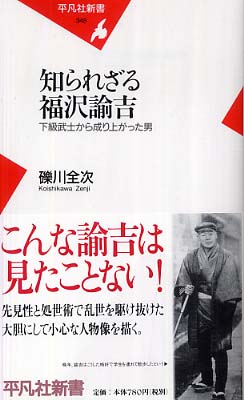
★ 平山洋 『福沢諭吉の真実』の真実 礫川全次 『知られざる福沢諭吉』 平凡社新書(新刊)
▼ こりゃあ、面白い。 一気に読んだ。 ▼ なによりも、さりげないながら、平山洋『福沢諭吉の真実』(文春新書)で展開された、「福沢は古典的自由主義者で、侵略主義者福沢諭吉像は、昭和版全集編集者、石河幹明が全集時に混入させた論説によるものなのだ」への、搦め手からの痛烈な皮肉になっている。 平山洋の詐術?については、安川寿之輔が徹底的に再批判しているらしいので、そっちを読んでもらうのが早い(私は未読)。 しかし、こっちもなかなか。 これまで、「思想」しか語られてこなかった、福沢諭吉本人の「人品」「品格」を問うているのだ。▼ すわ、福沢諭吉とは何ものか。▼ そもそも福沢諭吉は、同時代、平山洋の言うような自由主義者、として批判されることは少ない。 むしろ、思想的なものよりも、拝金主義者、ほら吹き、無節操、変節漢といった人格批判こそ、福沢批判のメインストリームだったのだ。 貧窮の下級武士生まれ。 様々な内職をおこない、徹底的に金銭にこだわり、一族などに幻想を抱くなと説教する、福沢諭吉。 幕末期に開国の利益をとくために執筆した「唐人往来」は、神田孝平の議論を移し替えただけに過ぎない。 しかし、老婆にも分かりやすく伝えようとする姿こそ、かれの明治期の時代の需要に応える啓蒙書執筆、海賊版版本の摘発につながっていくのだという。 かれは、出版を営利事業化して、拝金主義を自ら実演することで、人々の意識改革をせまっていた。 そのため福沢は、しばしば明治の拝金主義を批判するが、説得力に乏しい。 お前こそ教祖的位置だろ、と内村鑑三に批判される始末だ。▼ かれの立身出世は、外国語の原書を盗写(無断筆写)して、緒方洪庵の食客になることから始まった。 福沢は、目的のために手段を選ばない。 彼は、幕末、小野友五郎の使節団の一員として随行してアメリカに渡りながら、本を買う副業に没頭して、なんの役にも立たない。 公金を盗まれるわ、自分の買った本を公金で輸送(「公金私用」)するわ、「手数料請求」して幕府の怒りを買うわ。 挙げ句の果て、彼は蟄居謹慎させられたという。 幕府を倒してしまえ、なんて嘯きながら、幕府から金をもらい、何の活動もおこさないばかりか、幕府に忠勤を励む。 上野戦争の時は、彼は幕府崩壊を尻目に、日課通り講述をおこなっているが、それも幕府崩壊の時は、アメリカ大使館の庇護を受けるための「証明書」をもらい受け、小幡甚三郎に「日本人が外国人の庇護を求めるくらいなら、日本人に殺されろ!」と徹底的な批判を受けたために過ぎなかったらしい。 暗殺を怖れ、ももひきで町中をあるく姿は、なかなか滑稽でユーモラスである。▼ 福沢諭吉は、大阪人を「気品」がないとこき下ろしただけではない(そんな大阪に、慶応大が進出する日がこようとは…)。 かれのアジア認識は、幕末から一貫して、アジア人蔑視であるという。1882年『時事新報社説』「圧制もまた愉快なるかな」において、高値をふっかけた中国人商人を船から追い出したイギリス人に彼は憧れる。 かれは、国威を輝かせ、「ひとり圧制を世界中に専らにせん」と希う… 。 ▼ しかも、『唐人往来』『学問のすすめ』の頃から、福沢は西洋人を「同じ人間」といい友好関係を求めながら、なぜか支那には「国の分限を知らない」「道理を知らない」と批判し続ける。 アヘン戦争も、悪いのは清朝。 平山洋の本を読んで信じた人は、ほとんど詐欺にあったようなものだろう。 これが侵略鼓吹、アジア蔑視でなくて、何だって言うんだ? 福沢の同時代人で、『学商 福沢諭吉』を著した同時代人、渡辺修二郎の福沢批判は、要をえて余すところがない。 福沢諭吉とは、「強者に屈するを以て、自ら智者なり先見者なりと信ず」人間にすぎない、と。▼ かくも、「アジアには居丈高だけど西欧諸国には向こうを張る勇気がない」(BY 内村鑑三)福沢だけど、豚を殺す自らを穢多にたとえ、洋学者=賤民説をとなえるなど、身分制そのものをあからさまに否定する気概も感じられて良い。 大胆にして慎重。 かれは、変節漢とされるが、「脱亜入欧イデオロギー」に関しては、幕末から一貫していた。 福沢は、「品格」を強調したものの、彼自身の「品格」を誇らないばかりか、露悪趣味的な所もあったらしい。 彼の家族観が「近代的」そのものであることが強調されているだけではない。 幕末期以降のアジア蔑視も、かれが幕臣として「開国」の正当化を行わなければならなかった国内事情によるもの、入欧のストレスを脱亜で発散させようとしたもののではないか?と、筆者はどこまでも福沢に暖かい。 とくに、彼の作り出した、通俗にして平易な文体を高く評価する、筆者の福沢理解は、対象を突き放していてかなり好感がもてる。▼ なによりも驚かされることは、福沢諭吉研究は、慶応関係者を中心に福沢礼賛論しかない状況で、福沢批判者は服部之聡・安川寿之輔・丸谷嘉徳くらいしか見あたらない、ということであろうか。 平山洋『福沢諭吉の真実』(彼も慶応関係者)は、そんな福沢礼賛論の最も極端なもの、という指摘には衝撃を受けざるをえまい。 平山洋は、「福沢=侵略主義者」とする研究ばかりかのように言い立て、「石河幹明こそ犯人」とすることで、マスコミの寵児となった。 しかし、その研究史は、平山洋のような礼賛者ばかりというのが現実であって、平山洋こそ研究史の偽造「歴史犯罪」を犯しているのではないか。 実は、安川寿之輔の方が斬新な提起で(彼以前、福沢の侵略性を批判した人物は、服部の簡評しかない)、平山洋の方が陳腐なのである。 井田メソッドは、井田の開発したモノであることを考えると、彼の独自性など、どれくらいあるのだろうか。 こんなこと、研究の現場に居合わせて、当事者ではない第3者が書いてくれないと、なかなか分からないものだ。▼ さらに驚くべきは、「公金盗難」「公金私用」「手数料請求」の悪行を働いた、小野友五郎使節団での一件であろうか。 福沢ですら自己の不明を反省しているというのに、慶応関係の研究者たちは、小野友五郎のことを「官僚的人物」(石河幹明)を手はじめに、こき下ろしまくっているのだ。 はっきりいって、慶応関係者の福沢崇拝は、見ていて気持ち悪いことおびただしい。 ▼ この本を読めば、「なぜ、全集に石河幹明の論説が交じっていることに、誰も気づかなかったのか」などと大仰に問う、平山氏の設問そのものがヘソで茶釜がわく茶番劇にすぎないだろう。 そんなこと、平山洋たち慶応関係者が、福沢信者で目を塞いでいたことが原因、に決まっている(笑)。 丸山や服部のような「先学」が、なんて言っているが、責任を押しつけるとは、責任転嫁も甚だしい。 だいたい、丸山も富田も、「石河幹明が交じっていることに気づいたとしても、福沢諭吉がアジア蔑視・侵略鼓吹者の一面をもつことについては反論できるはずがない」から、福沢=アジア侵略の鼓吹者とする議論に反論しなかったのではないだろうか。 ▼ 亀は甲羅にあわせて穴を掘る、という。 福沢諭吉は、偉大な啓蒙者であると、同時にアジア蔑視・アジア侵略礼賛者であった。 思想家であると同時に、「時局思想家」でもあった。 後者を切り捨て、前者のみで描いた福沢諭吉像は、平山洋の小さな器に大人物福沢を押し込めようとする、「思想犯罪」そのもの、と言えるのではないか、といいたくなってくる。 ▼ 平山洋も、自分のHPで、安川寿之輔『福沢諭吉の戦争論と天皇制論』にコソコソ「注」という名の姑息な反論をおこなうマネをしている。 どうどうと、反論したらどうか。 はっきりいって、安川の本を読んでない人間にすれば、そんな反論が全体としてどのような意味があるのか、はなはだ不明であって、平山洋の人間の姑息っぷりしか感じられない。 安川は、平山の本に対して、著書を刊行することで反論した。 平山も、マスコミの寵児になったんだから、そうすりゃいいのにねえ、とおもってしまう。▼ ただ、ここまで面白いよと書いていながら、若干、評価を低く付けたのは、理由がある。 さすがに、『福沢諭吉の真実』に興味がある人ならいざしらず、福沢諭吉の「品格」「人格」など、普通の人ならあまり知りたいとも思わないだろう。 ▼ 著者にはご容赦いただきたい。評価 ★★★☆価格: ¥ 819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 参考
Jan 30, 2007
コメント(11)
-

★ メモ:NHK番組改変問題 2007年1月30日付東京新聞社説
■番組改変 NHKは政治と距離を 番組改変訴訟の控訴審で、東京高裁はNHKの政治的配慮による改変だったと認定した。政治と報道が信頼されるためには、報道機関と政治家が疑惑を抱かれない距離を保たなければならない。 従軍慰安婦問題を扱ったNHK教育テレビの番組は、問題の責任を追及する市民団体が、取材協力の前提として説明を受けた企画内容と異なる内容だった。いったん完成の後、本来は番組制作に無関係な幹部が介入して修正した結果である。 それ自体、異常なうえ、政治家の介入が疑われたが、高裁判決も政治的改変だったことを認めた。 問題の本質はここにある。改変させた幹部は、政治との距離がNHKに対する信頼にかかわることを認識していなかったのではないか。 高裁判決の骨子はこうである。 報道機関には報道の自由、編集の自由があり、一般論としては取材対象の意に必ずそわなければならないものではない。しかし、あらかじめ企画内容を説明し、それを条件として全面協力を得た、このケースの場合は企画を実現する義務があり、実現しなかったときは理由などを説明する責任がある。NHKはいずれも果たさなかった。 報道機関として致命的なのは、放送が当初の企画からかけ離れたものになった理由だ。当時の最高幹部が国会議員の間を番組の事前説明に回り、議員の発言を受けて当たり障りのない番組になるよう現場に改変を指示した、と判決は認定した。 報道、編集の自由を放棄し、政治家に迎合したのである。これは国民に対する背信といえよう。 こんなNHKの受信料支払いを義務化したり、司法の力を借りて強制的に取り立てることに、幅広い支持を得るのは困難だろう。 政治の側も自省、自戒を迫られている。 判決は「NHK幹部が国会議員の発言を必要以上に重く受け止め、その意図を忖度(そんたく)した」「政治家が一般論として述べた以上に番組に関して具体的な話や示唆をしたとまでは認められない」と慎重な認定をした。 NHKと政治家の日常の関係に照らせば、政治家の発言はもっと具体的で事実上の介入だっただろうことは容易に推察できる。だが、判決通りだとしてもNHK側が無視できなかった事実は重い。政治の側も報道機関との距離を保つべきことを物語っている。 NHK側も政治家も、昨年春に制定した新放送ガイドラインの「放送の自主自律の堅持が信頼の生命線」という条項を肝に銘じるべきだ。(中日新聞)-------------------------------------------------------------■NHK 裁かれた政治への弱さ NHKは国会議員らの意図を忖度(そんたく)し、当たり障りのないように番組を改変した。 旧日本軍の慰安婦をめぐるNHK教育テレビの番組について、東京高裁はこう指摘した。そのうえで、判決はNHK側に対し、取材に協力した市民団体へ慰謝料200万円を支払うよう命じた。 NHKは放送の直前に番組を大幅に変えたことを認めながらも、「あくまで自主的に編集した」と主張していた。その主張は通らなかった。 政治家の意向をおしはかって番組を変えるというのでは、自立したジャーナリズムとはとても言えない。NHKは上告したが、高裁の判断は重い。 裁判になっていたのは6年前に放送された番組で、慰安婦問題を裁く市民団体の「民衆法廷」を取り上げたものだ。ところが、兵士の証言や判決の説明が削られた。このため、市民団体側は事前の説明と異なる番組になったとして訴えた。 一審の東京地裁は被告のうち、孫請けの制作会社の責任だけを認めた。 控訴審に入って、NHKと政治家との関係が大きな争点になった。NHK幹部が放送前に自民党衆院議員らと会い、その後、番組が改変された。そうNHKの担当デスクが内部告発をしたからだ。 東京高裁は次のように認定した。 NHK幹部はこの番組がNHK予算案の審議に影響を与えないようにしたいと考え、国会議員らに会った。その際、「番組作りは公正・中立に」と言われた。NHK幹部はその発言を必要以上に重く受け止め、番組に手を加えた。 NHK幹部は番組への強い批判を感じ取ったのだろう。NHKは予算案の承認権を国会に握られている。それが番組改変の動機になったと思われる。 自立した編集は報道機関の生命線だ。政治家への抵抗力を持たなければ、公共放送もその使命を果たせない。 この問題は朝日新聞が05年1月に取り上げ、政治家の発言が圧力となって番組が変わった、と報じた。今回の判決は政治家の介入までは認めるに至らなかったが、NHKの政治的な配慮を厳しく批判したものだ。 朝日新聞の報道に対しては、政治家とNHKから事実関係について反論があった。これを受けて検証を重ねた朝日新聞は一昨年秋、記事の根幹部分は変わらないとしたうえで、不確実な情報が含まれてしまったことを認め、社長が「深く反省する」と表明していた。 取材される側が報道に抱く期待権と編集の自由との関係について判決が指摘したことにも注目したい。判決は編集の自由の大切さを指摘したうえで、政治家の意図をおしはかった今回のケースは「編集権を自ら放棄したものに等しい」と述べ、期待権の侵害を認めた。 編集の自由や報道の自由は民主主義社会の基本だ。取材される側の期待権の拡大解釈を避けるためにも、メディア側の権力からの自立が求められる。 (朝日新聞)-------------------------------------------------------------当然の判決で、社説が消える前にメモ。ゴミ売新聞が、期待権で編集権が制約されるなどと、ギャーギャー喚いていたが、まったくの論外。 読売は、社説において、自社の記者が書く記事について、編集権を剥奪して当然と嘯いている以上、期待権による侵害もヘッタクレもない。 すでにお前たちの下っ端記者は、とっくに剥奪されている。 NHKは、上層部の「責任」ある編集体制で「自己規制」しただけといって、読売は政治家の圧力による改変を否定した。 ならば、上層部の責任ある編集体制とやらが、取材対象の「期待権」による記事改変を、「自己規制」でおこなえばいいだけの話だろう。 何の問題もないはずだ。 政治家からの「圧力」による記事変更は、「自己規制」で処理できるならば、取材対象からの「期待権」も、「自己規制」で処理できるはずである。 期待権によるジャーナリズムの制約とは、「外部からの圧力」を批判してきた奴らがいうべきことであって、少なくとも読売新聞ごときが、ギャーギャー言う資格はない。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 追伸 おまけ ■ 読売のバカ社説 [NHK番組訴訟]「報道現場への影響が懸念される」 メディアが委縮してしまわないか心配だ。東京地裁に続いて東京高裁が示した報道への「期待権」という新しい考え方に、戸惑わざるを得ない。 いわゆる従軍慰安婦問題を扱ったNHKの番組を巡る訴訟の控訴審判決のことだ。題材となった「女性国際戦犯法廷」を主催し、取材に協力した民間団体が「事前説明と異なる内容に番組が変更された」として、NHKなどに損害賠償を求めていた。 民間団体側は「法廷」のすべてを紹介する番組になると思っていたが、実際には、昭和天皇に責任があるとした「判決」部分などが削除された。このため、裁判では、取材を受けた側の番組内容に対する「期待」が、法的な権利として認められるかどうかが争われた。 これに対し、東京高裁は1審と同様、「取材を受けた側がそうした期待を抱くのもやむを得ない特段の事情があるときは、番組制作者の編集の自由も一定の制約を受ける」との判断を示し、NHKに賠償を命じたのである。 高裁が「編集の自由」を軽く考えているわけではない。「編集の自由は取材の自由、報道の自由の帰結として、憲法上最も尊重される権利」で「不当に制限されてはならない」としている。 また、「期待権」との関係を考えるうえで、ニュース番組を、今回のようなドキュメンタリー番組や教養番組とは区別したりもしている。 ただ、懸念されるのは、編集の自由の制約に関する司法判断が拡大解釈されて、独り歩きしないかということだ。 報道の現場では、番組や記事が取材相手の意に沿わないものになることは、しばしばある。ドキュメンタリー番組や新聞の連載企画などでも、より良質なものにしようと、編集幹部が手を入れたり、削ったりするのは通常の作業手順だ。 「編集権」の中の当然の行為だが、それすら、「期待権」を侵害するものとして否定されるのだろうか。2審では「期待権」の範囲がNHK本体にまで拡大された。そのため、報道機関全体に新たな義務が課せられる恐れが強まった。 この訴訟では、もう一つの焦点があった。番組制作に政治家の“圧力”があったのかどうかだ。朝日新聞が繰り返し介入を報じ、NHKが否定したことで、大きな論争に発展していた。 これについて、今回の判決は「政治家らが具体的な話や示唆をしたとは認められない」との見方を明確に示した。 NHKは判決を不服として、即座に上告した。「期待権」について、最高裁はどう考えるのだろうか。
Jan 29, 2007
コメント(0)
-
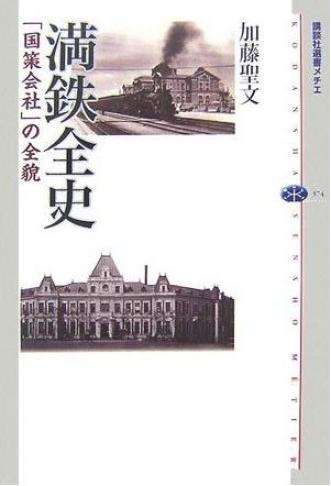
★ 加藤聖文 『満鉄全史』 講談社選書メチエ (新刊)
▼ とても良い本だわ。 何よりもメッセージが明快。 定義できるはずもない「国益」「国策」によって翻弄された、戦前日本を病理を徹底的に暴き出しているの。 満鉄創立100周年の2006年。 時宜をえた本ね。 これを読んだ貴方は、「国家戦略」などと語る奴を信用しなくなるでしょう。 とても良いことだわ。▼ みんな知ってる通り、満鉄は国策を体現する会社だったはず、でしょ。 でもね。 日露戦争時、満鉄の元になった東支鉄道南部支線は、なんの位置づけも与えられていなかったの。 負担を考えて、鉄道王ハリマンに手放す意見もあったんですって。 でも、経済的収益をどうやってあげるのか、経営的成功の見通しもないまま、「血と犠牲」でえられたものだからというエモーショナルな観点で、講和条約では譲渡要求せざるをえなかったのよ。 会社作りという話だけ、先行してしまったの。 また、関東都督府だけでなく、領事館警察を掌握して邦人保護にあたる外務省、満鉄のいわゆる「満州の三頭政治」が始まってしまうの。 役所の縄張り争いのひどさは、今の非じゃないわね。 ▼ 満鉄は、初代総裁後藤新平が経営を軌道にのせるわ。 しかし、満鉄の位置づけの曖昧さに我慢ならなくて、後藤は桂太郎に接近して中央政界に進出するの。 目指すは、全植民地経営を統括する機関の設置ね。 しかし原敬が、立ちふさがるの。 満鉄「経営」を前面に押し出して満州を安定化させたい後藤と、あくまで政府のコマとしか満鉄をみない原。 経営は、2代総裁中村是公の手腕で安定化するんだけど、長州閥と個人的つながりしかない後藤は、政党政治家原敬に屈服する運命にあったのよ。 原以降、満鉄には政党勢力が浸透していって、草刈り場のようになっちゃうのよ。▼ ひどいわよね。 寺内内閣は、3頭政治を解消するために、「満鮮一体」の統轄機関をつくることを考えて、関東都督府に満鉄監督権限を与えるわ。 ところが、原内閣では、都督府を解体して民政(関東庁)・軍政(関東軍)に分割、満鉄中心の植民地経営に舵を切るの。 それは、政治では張作霖を押し出して、経済では満鉄を押し出す政策だったわ。 一〇年間、日本の満蒙政策のスタンダードになるくらいなんだから、やはり立派な政治家みたいね。 政党で政権をえる原敬は、満鉄を政友会の利権にしなければならないの。 満鉄を舞台とした政治資金捻出がばれたのもキッカケとなって、東京駅で暗殺されてしまうわ。 田中内閣になると、今度は「拓務省」による統一的植民地政策の遂行が指向されるの。 いったい、どこまで制度をいじって遊んでいるのかしら。 どっかの国の、首相補佐官制度みたいよねー。 恥ずかしいったらありゃしない。(笑)▼ 結局、満鉄の歴史で一番重要なのは、松岡洋右らしいの。 「満鉄中心主義」が採用された後、理事に入って、副総裁・総裁と一〇年間つとめるから。 とくに、この時代は、ロシア革命以降、満州南北分割の密約が反故にされて、東支鉄道と満鉄が競合する時代に突入したとき。 満鉄拡大政策の陣頭指揮をおこない、支えたらしいわ。 松岡って、国際連盟脱退、日ソ中立条約のバカイメージしかないのけど、ソ連と手をむすぶためには、ソ連を可能な限り満州から駆逐しなければならない、と考えていたんですって。 へー。 この拡大路線をめぐって、外務省と満鉄は激しく対立。 「満鉄―関東軍―張作霖」ラインが形成されるわ。 これは満州事変の時の、軍と満鉄二人三脚の遠因になるそうよ。 山本条太郎社長時代には、副総裁昇格。 満鉄による「製鉄・製油・肥料」の三大国策・重工業化を指揮するの。▼ そんな満鉄全盛期を築いた「山本―松岡」体制だけど、パートナーの張作霖が、全国政権的になってくると、日本の言うことをばかりはいられないのは当然よね。 そんな当たり前のことを理解しないで、関東軍が逆恨みして殺してしまい、ジ・エンド。 バカはどこにもいるものよ。 おかげで、満鉄はパートナーを失い、怒りに燃えて、「国権回収」をめざす張学良に、「満鉄包囲線」で追い詰められるわ。 本当は、銀安によって、安い鉄道運賃の中国側路線に貨物が行っちゃった上、大不況で購買力が減少したためなんだけど、満鉄は逆恨み。 満州事変をおこす関東軍に、満鉄は協力してしまうの。▼ 満州事変以降の満鉄は、「猿回し」の猿のよう。 悪の親玉は、十河信二。 元々中堅・若手は、張学良などへの不満を鬱積させていたのね。 彼は、後に「焦土外交」でしられる時流に便乗しか能のない、内田康哉社長をうまくのせて、満鉄と関東軍の完全な一体化に成功させてしまうわ。 1935年には東支鉄道がソ連から譲渡されて、懸案の1つは解決。 また関東軍は、領事館権限を外務省から接収。 1934年には、満鉄改組騒動を巻き起こしながらも、関東軍は、関東庁権限と満鉄監督権を拓務省から奪っちゃうわ。 これによって関東軍の権力が確立。 満鉄は、事変後、鉄道会社としては絶頂期を迎えるけど、もはや政治的役目は終わって、ただの関東軍・満州国が要求する「国策」を実行するだけの組織に成り下がるの。 満鉄は、自分の死刑執行命令書にサインしたのね。▼ そんなとき、松岡が今度は総裁として戻ってくるわ。 今度は、中国進出なんていうんだから笑っちゃうわ。 そんな野望もむなしく、満鉄は最後のトドメをさされちゃう。 1934年以降、中央から満州に革新官僚がどんどん送りこまれたの。 そうなると、満鉄は産業開発・企画立案でも、用済みになっちゃうわ。 1937年、日産の満州移転にともない、「満州重工業」が発足するわ。 改組しちゃえ!! 鉄道事業以外の付属事業は、切り離しがすすみ、満州重工業などに譲渡させられるの。 これを主導したのは、何あろう、松岡の親戚で、アベ首相の祖父、岸信介。 岸に背後から松岡ちゃん刺されちゃったのね。 やることが違うわ、長州人。 ▼ 第二次大戦になると、大豆流通は壊滅。 大連は衰退するわ、自由闊達な空気は無くなるわ。 「大陸=満州=朝鮮半島」経由で日本に物資輸送を命じられるけど、港湾と停車場設備が未整備のままだから、物資が朝鮮半島で野ざらしなのよ。 おまけに対ソ戦に備えるべく北満向輸送を強化するべきなのか、内地向輸送を強化するべきなのか、迷走しまくり。 結局、どっちもまともにやれていないまま、戦争に負けてしまう。▼ 満鉄の最後は、笑うしかないわ。 満州国も8月18日に消滅。あれほど偉そうにふるまった関東軍が、満鉄に150万人の日本人の命運をすべてを押しつけて、45年9月5日に消滅。 ソ連軍は、満州国の旧日本資産を没収・移送をおこなうなど、12億ドルの大損害を東北地方に与えたのに、没収した資産は、ドイツのも含めてみ~んな野ざらしなのよ。 インフラなしでは鉄くず同然。 いい気味よね。 本書の最後では、満鉄の国策性を忘却してノスタルジーとして扱われることに警鐘を鳴らしているわ▼ 「国策」なるものがいかに無責任か。 満州国がいかに「官僚にとっての天国」にすぎないものであったか。 権力の割拠性がどれほどの被害をもたらしたのか。 日本社会の病理のシンボルこそ「満鉄」であって、今こそ病理に向き合わなければならない。 なかなか格好良くて、痺れるわねー。 ▼ なにより新鮮なのは、田中義一内閣の評価かしら。 陸軍随一のロシア通は、ソ連と満州の利権分割によって取引可能と見ていたらしいの。 政策立案できる有能な軍人で、政党の重要性を理解していた最後の長州閥らしいわ。 また、あの中国残留孤児を生んだ「満州移民政策」は、実は権限は大きいのに組織がなく、リストラされる危機にあった、拓務省の組織拡大・防衛策のため案出されたものなんだって!! 許せないわよねー。 高橋是清なんか、松岡同様、移民で苦労したから、「移民なんて可哀想だから止めとけよ」で予算計上しなかったらしいの。 苦労人がいない、アベ内閣に爪のアカでも煎じて飲ませてやりたいわ。 豆知識も、いっぱい。 複線と単線では、輸送力に3倍以上の差が出るらしいの。 満鉄東京支社は、今、アメリカ大使館になってるそうよ。▼ ただ、やっぱり弱点があるように思うのよねー。 なんといっても、満鉄「全史」のため、政治「事件史」に堕してしまい、満鉄経営の部分や中国ナショナリズムとの衝突など、肝心の部分を把握できかねてしまうわ。 いくら、「国策」と満鉄の絡みを描いているとはいえ、「満鉄」をとりまく満州の状況をもう少し説明して欲しかったわ。 ▼ それに、「権力の割拠性」とか同床異夢の状況などをとりあげて、無責任さが問題視されているけど、これって日本だけの現象かしら。 「国策」「国益」「国家戦略」なるものは、当事者各々が勝手に定義できるがゆえに、徹底的に無責任なものだったのではないかしら。 満鉄と日本をとりあげること自体、あらゆる時代、あらゆる国家の「国策」は、無責任で不統一でテンデバラバラであるという構図を取り逃がしてしまうのではなくって? この次元でこそ、誰も厳密に定義できないがゆえにめいめいが勝手に描いている、「国策」「国家戦略」「国益」の幻想性を批判できるのではないかしら。 また、鉄道線路拡大のときの路線図説明が本当に分かりにくくて腹がたったわ。 それぞれの日中交渉別に色分けするなり図に工夫がほしかったと思う。▼ それでも通史的な価値は、相当なものね。 講談社選書メチエにしては、いい本だと思うわ。 講談社現代新書に買う本がないぶん、すすめておきたいわね。評価 ★★★☆価格: ¥ 1,680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jan 24, 2007
コメント(1)
-
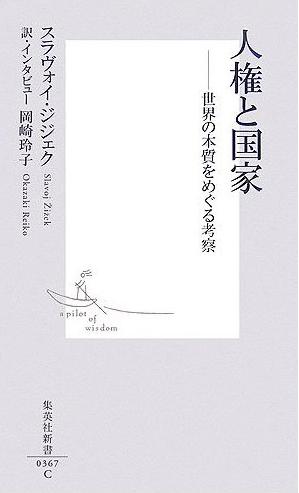
★ スラヴォイ・ジジェク(訳・インタビュー 岡崎玲子) 『人権と国家 世界の本質をめぐる考察』 集英社新書(新刊) 2
(この日記は1からの続きですので、こちらからお読みください)▼ ジジェクは、明快だわ。 ゾーエーとなったとき、その人の人権は古着と同じで、海外に送られ、「人道的介入」が行われることから分かるように、「人」とは市民権を具体化する一連の政治行為によって創出されていることは、確かなのね。 だから、「人権の普遍性」と現実の市民的権利の落差は、たしかに存在するし、「普遍性」と「特殊性」(政治的領域)の落差と捉えてしまうかもしれない。 しかし、それは違うの。 「人権の普遍性」こそ、政治的主体が固有のアイデンティティにおいて非偶然性を主張する権利、社会それ自体の普遍性の行為者として自らを措定する権利を定めるのであって、ひいては「市民の政治問題化」という過程を通して市民的権利を創出をもたらすものなのよ。 政治をどこまでも、見失ってはならないのね。 ▼ とくに示唆を受けたのが、キリスト教・ユダヤ教を家父長的庇護を与える宗教であるのに対して、イスラムとは「孤児」であり、アイデンティティが見つからない場合、共同体をたちあげるのに最適な宗教、という議論よねー。 ジジェクの箴言として、『「多神教―ユダヤ教―キリスト教」のトリアーデは、西洋哲学史で2度反復された、「スピノザ―カント―ヘーゲル」と、「ドルーズ―デリダ―ラカン」である』というものがあるわ。 『仮想化されざる残余』で展開されていた議論だけど、これを思い返すたびに、それではイスラムはこのトリアーデなら何処に入るのかしら?と毒づいていたの。 しかし、イスラムについてのジジェクの新境地が、切り開かれるかもしれないと期待感を抱かせるわ。 楽しみよね。 また、民主主義は相互互換可能であるがゆえに「評価」が欠かせない、そして評価は「公正」であることが問題である、という議論も、面白かったわ。▼ 意外だったのが、ジジェクにとっては、NATOへ肩入れすることは、ヨーロッパを支持してアメリカと対立することらしいのよ。 あと、面白かったのは、文化人類学批判ね。「現地文化を理解しよう試みる人類学者は間違っている、その文化が自らを分かっていない様子をきじゅつしなければならない」……… マルクスにかぶれたような人なら誰しも使いたくなる箴言に、この本は、満ちているわ。 ▼ 「この法律は実践に即しているかもしれないが、理論的水準に到達していない」 「理想的な社会でこそ、死刑制度は―――貧困者を死刑にするなどのバイアスがかからないため―――必要な制度である」 「唯物主義とは、物質的発展へのナイーブな信頼ではなく、現実の完全な偶然性を受け入れることである」 「回転寿司とは、マルクス主義的革命である。なぜなら、生産過程が隠されていない(笑)」 「黒人の暴力やレイプにまつわる噂が、すべてが事実であることが証明されても、人種差別に基づいて広まったなら、「病的な人種差別によるものであって、事実にみせかけたウソなのだ」▼ 雑学も面白かったわ。 さすが知の巨人。 ハイデガーは、ある自著の和訳を日本語も知らないのに好んでいて、なぜだ?と突っ込まれると、「特攻隊員出身だから、私の思想が分かるはずだ」と答えたんですって。 レーニンの愛人と未亡人に対するスターリンの話も、面白かったわ。 アルゼンチンのガウチョ、デリダ本人のデリダ理解、アイデンティティはみーんな、他人が付与するもの……というのも、強調していたわ。 龍安寺の石庭は、石が一度に全部見られないように配置してあるって、修学旅行で見たはずなのに、インタビュアーに言われるまで気づかなかった。 ショックよねー。▼ でもさ、不満も多いのよね。 「本質」を否定するラカン派精神分析で、本書でも散々、「外見」こそすべて、といってるのに、この表題はいったい何考えているのかしら? あと、どうしても、肝心の2つの評論は、ただのアジテーションに読めてしまうのよ。 ジジェクの『厄介なる主体 1 ―政治的存在論の空虚な中心 』青土社の議論を読んでいないと、パディヴ、ランシエール、バリバルの批判者でもあることが分からなくて、たんに援用しているだけに思えるのではないかしら。 あと、インタビューが、面白い爺なのか、バカな爺なのか、わけが分からなく感じさせてしまうのも、難点かしら。▼ ジジェクの仕事は2つに分かれるわ。 『イデオロギーの崇高な対象』に代表されるラカン派理論の哲学史への適用と、現代政治へのアクチュアルな理論提起。 むろん、この2つは、完全に分かれる訳ではないけれど、前者の「黒ジジェク」が難解でわかんない、という人には、後者の「白ジジェク」としてお奨めできるのではないかしら。 ▼ ただ白ジジェクに止まらず、黒ジジェクにいくと、もっと面白い、とだけ言っておきたいわね。 入門書には、立派なもの、という評価はゆるぎないわ。 お薦めかしら。評価 ★★★☆価格: ¥ 756 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jan 17, 2007
コメント(0)
-
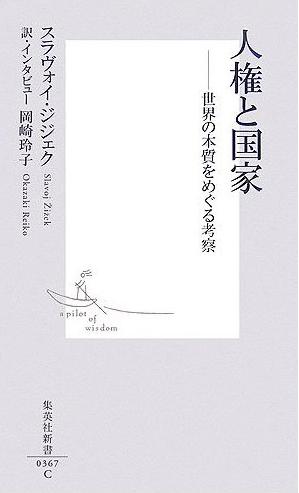
★ スラヴォイ・ジジェク(訳・インタビュー 岡崎玲子) 『人権と国家 世界の本質をめぐる考察』 集英社新書(新刊) 1
▼ この本も、すてきよ。 「初の新書化!」なんて銘打たれていて、「文庫にはなってるじゃない」と毒づきたくなったけどね。 むろん、21歳の近頃売れっ娘のライターが、ジジェクにインタビューしたものと、まだ日本語訳されていないジジェクの論説をあわせたもの。 所詮、小娘になにができるのさ。 そう言われるリスクを覚悟していたでしょうけど、訳文もなんとか読めるものになっていて、なかなかのものよ。▼ ともかく、本書の中身をまとめてみるわね。 ジジェクインタビューは3本からなるわ。▼ 「偶然性を理解すること」 これが、ジジェクのヨーロッパの普遍思想として守り抜くべき、キーワードらしいの。 何度も主張されるのは、「国民は国家を怖れるな!!」、規制こそ、本来の姿だ!。 そして、「集合的意志決定」を復活させよ、何なら地球規模のテロルで決定を強制せよ!。 資本主義による悲惨な事故を「流してしまわない」で、見えない過程まで責任をとろう! 体系的な資本主義の悪に立ち向かおう! かしら。 ロシアの弱さを冷静に指摘するとともに、西ヨーロッパとロシアの提携も唱えているわ。 また南米の「善の枢軸」―――キューバ、ベネズエラ、ボリビアの反米運動も悲観的よね。 あと、ジジェクは、スロベニアでは共産党に干されていたらしいの。 たしかに『厄介なる主体(1)』で書かれていたけれど、彼は薄給だけど完全な自由が与えられているらしいわ。▼ むろん、2本収録されている彼の時事論説も楽しいわ。 「パリ暴動」に関する議論は、とても刺激的。 あの暴動は、具体的な社会・経済活動を要求をおこなうためのものではない。 「存在の証明」「可視化」を求めての、「完全に無意味」な暴力らしいの。 グローバルな資本主義は、「意味」と「真実」を分断して、「意味を持たない真実」という次元を構成しているわ。 だからかれは、保守派、リベラル派双方の対応を批判するのね。 保守派は、「意味」の次元に資本主義を閉じこめようとするし、リベラル派は「意味」の外にある真実を提起しようとするから。 前者は、文明の衝突の代償が避けられない。 両方とも、より「悪い」ものなの。 ▼ 対処策は、問題そのもの転換、イデオロギー的枠組からのシフトよ。 テロリスト原理主義者に欠けているのは、自らの優越性を信じる真の意味の人種差別的思考ではないのか?みたいにね。 エゴイズムに対立する概念は、公共善への精神ではなくて、羨望やルサンチマンによって、自己を犠牲に差し出してまで他者が対象物を手にすることを阻もうとさせる、犠牲的精神ではないのか。 ルサンチマンこそ、自己犠牲をうむ悪なのではないのか。 そして、「公正」な社会によって、「失敗」を制度のせいにできない社会にしてしまうことこそ、ルサンチマンの暴発を引き起こしてしまうのではないか。 ジジェクはそう主張するの。 すべてが選択することができるようになったとき、偽の「自然化」を施された、宗教的・民族的紛争が最適な闘争形態になるわ。 客体の剰余(抽象的普遍性の直接支配)は、主体の剰余(恣意的な思いつき)によって補足されるとするのが、ヘーゲルの真髄。 象徴的な次元において全員を承認するポストモダン的「具体的普遍」では、人種・宗教・性別という、偶然的他者性を絶対的他者性へと高める動きのみが、差異を示す唯一の方法として残されてしまうのではないか。 ジジェクはこういうわ。 彼らフランス青年の絶望的な暴動こそ、過激思想家ではなく、リベラル派の望んだことによってもたらされた、当然の結末ではないか、と。 ▼ 「人権概念の変遷」も、なかなかよ。 ある対象の他者性は、自分たちが抑圧してきた無意識のあらわれなの。 選択とはメタ選択にすぎない。 ヨーロッパ社会では、ヴェールを被るイスラムの女性がとれる選択は、着用しないことしかないの。 なぜなら、宗教的信念に基づいて、着用を選択したとしても、それはイスラム共同体を選ぶことではばく、得意な個性の現われであって、一線を越えれば原理主義として非難されるからよ。 自由な主体とは、固有の生活世界から切り離された存在としてしかありえない。 「他者への寛容」も、他者との接近の恐怖のことであって、相手の存在が薄い限りにおいて許容されるにすぎないのではないか。 ポストモダンにおける「人権」とは、「ハラスメント」を受けないこと、近づきすぎることへの「不寛容」を指すのではないか。 また、ゾーエーに関する議論は、白眉に近いわ。 「顔のない回教徒」を絶対的確実性ととらえるレヴィナスの議論は、主体が「怪物性」から目をそむけるための防御としての飼い馴らしではないか、そう批判されているの。 ゾーエとは、ジジェクによれば、具現化された「実体」の両義性であって、悪そのものと重なって対照的なもの同士が衝突する、「不可能な地点」なのよ。 ▼ ジジェクは、「人権とは権力の剰余からの防御」と整理するわ。 その「剰余」は、代表されるものと代表するものの関係からくる構造的不平等性であり、「主権」といっても良いものよ。 かれはアウシュビッツに代表される20世紀の大惨事の説明を3つにわけるの。 ハーバーマスは、啓蒙主義とは解放であり、残虐性を内包していない、とした。 アドルノ、ホルクハイマーは、大惨事を啓蒙主義の到達点にしたわ。 ジジェクは、3つ目のバリバールの議論に組するの。 自由と大惨事の決着は、まだついていない。 主体をも自滅させる大惨事を理論的に解明するとともに、革命の「文明化」する方法を問わなければならない。 権威を政治的基盤に帰することができない、非政治的権力により運営される軍隊、教会、学校、家族は、「暴力」そのものであって、権力は暴力という「剰余」に決定的に依存しているわ。 この<非政治的><政治以前>の隠れた政治プロセスこそ、見極めねばならないもののよ。追伸1 (その<2>はこちらになる予定。 応援をお願いするわ。 長すぎて1日では終わらなかったの)追伸2 なんか遊鬱さんに、こっちの口調の方が分かりやすい、 と言われたから、やってみたの。 不安ねー。評価 ★★★☆価格: ¥ 756 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jan 14, 2007
コメント(1)
-

★ 「蓮池薫は、北朝鮮の工作員だった」は、哲学的に是認されなくてはならない
▼ なんか、僕がブログから抜けているとき、とても面白い事件が起きていた。 『週刊現代』新年号の渾身のスクープ、それに対する『週刊新潮』の反論、で展開された、イエロージャーナリズム同士の華々しいバトル。 どちらの記事も、読む気はおきないのだが、少なくとも拉致被害者について、不思議と言われてこなかった、ある「ダブー」に風穴を開けたことについて、『週刊現代』を高く評価しておきたい。▼ 読売・産経から新潮・諸君・サピオに至る右派ジャーナリズムには、北朝鮮における国家とその公民の関係について、公式化された見解、というかドグマがある。 「北朝鮮政府が外に送り出した人物は、政府の工作員である」▼ それなら、「北朝鮮政府が送り出した」蓮池薫はどうなるのだろう、と前々から思っていたが、みごとに逆用された形で、愉快痛快このうえない。 まさしく、反骨精神の面目躍如。 『週刊新潮』や右派ジャーナリズム、それに日本政府は、さっそく、情報提供者の身元を問題にすることで否定に躍起だが、それも仕方あるまい。 『週刊現代』の記事は、拉致被害者のもつ、ある重要な何かに、風穴を開けてしまったからである。 それは何か。▼ こういう問いかけをしてみたい。 蓮池薫は、どうして北朝鮮で生き延びることができたのだろう。 ▼ これまで、工作員訓練のための語学教官施設でうんぬん、で曖昧にされてきた次元とは、何だろうか。 それは、語学教官として拉致された人間は、もし「拉致被害者の会」の言うとおりなら何百人もいて、「替わりはいくらでもいた」ことにほかなるまい。 帰還事業で帰国した在日は、日本語が話せたことで、どのような目にあわされてきたか。 ましてや、蓮池薫は外国人。 彼の言葉は、朝鮮人には理解できまい(そのため、日本人を拉致する必要があったのだ)。 彼は、北朝鮮にとって必要でもあったが、同時に朝鮮人が監視できないという点で、危険きわまりない人物でもある。 おまけに、「日本語が喋れる人間」だけなら、蓮池薫クラスはいくらでもいるのである。 ▼ 右派ジャーナリズムの公式見解を総合すると、過酷な北朝鮮社会では、職場の至る所で密告が横行していているという。 また、収容所に入れられ、餓死させられているものも多い。 たぶん、その通りだろう。 にも関わらず、かれは生き延びている。 そして我々は、今もなお多くの日本人が拉致され、北朝鮮政府の下にいると信じているが、さすがに、その拉致された全員が存命しているとは思ってはいない。 自然死以外にも、北朝鮮政府に殺された日本人は、多いと考えている。 ▼ それならば、理由はほかでもない。 彼が、マインドコントロールによって、「北朝鮮体制の忠実な僕」であっただけでなく、それを客観的に「公式」に示してきた ――― 彼は、拉致された「日本人」同胞さえ、北朝鮮当局に密告、売り渡してきた、極めつけ優秀な、「金正日体制」の下僕だったから、ではなかったか。▼ 週刊現代が与えたショックとは、この可能性の「領域」を切り開いた点にほかならない。 そして、家族会や政府のヒステリックな否定的な反応も、この領域に対する否認とみなさないと、ただの事実確認をめぐる闘争に歪曲されてしまう。▼ そもそも、蓮池薫が職場において、朝鮮労働党の信頼する、模範ともよべる優秀な北朝鮮公民でなくして、どうして、北朝鮮から出国することがありえたであろう。 考えてみれば、蓮池薫本人は、あまりマスコミに出たがらない。 いつも、拉致家族会の厳重なガードに守られ、蓮池透が、頼まれもしないのに、しゃしゃり出ているだけである。 その忌避は、何故なのか。 そして蓮池透は、「マインドコントロールが解けるのに時間がかかった」と、常々、語ってきた。 マインド・コントロールの解けない状態とは、かれが優秀な北朝鮮公民と同様の行動をとることにほかなるまい。 社会主義政権下、模範的公民であることのもっとも簡単な当局への証明は、模範ではないものを密告することではなかったか………。 ▼ 北朝鮮核武装によって、北朝鮮打つべし論が下火になって久しい。 右派は、意気地がない。 「体制崩壊するだろう」論と、「だから核武装しよう論」にこぞって、宗旨替えのご様子だ。 あながち、「打つべし論」も、嫌いではなかった。 ひょっとしたら、スパイ警察資料がごっそり押収できて、蓮池薫署名の上申文書なども、日の目を見ることになるかもしれない。 そう考えると、それはそれで面白いと考えたからだ。 「体制崩壊」では、その後の国民和解のことまで考えると、スパイ警察資料が、手先レベルにすぎない、蓮池薫資料まで全面公開されるとは、考えにくい。 この説に、裏が採れないことは、まことに残念でならない。▼ 蓮池薫は北朝鮮の工作員だった、という衝撃的な『週刊現代』のスクープは、やはり哲学的な意味において、徹底的に是認され、肯定され、承認されなければならないだろう。 それは、彼が、「本当に」拉致実行犯だった、という意味でではない。 ▼ それは、蓮池薫の帰還という事実を、蓮池薫の存命によって「失われてしまった可能性」とともに理解することであり、彼が北朝鮮で生きぬいたことそのことによって、「失われてしまった何か」に思いを馳せながら、理解することなのだ。 ▼ そして蓮池薫は、このことについて、何も恥じることはないだろう。 我々は生き残るために、今も、生物を犠牲にして、ひどい場合、命さえ奪っている。 かれは、たかだか、その犠牲の領域に、「同胞の日本人」を何らかの形で加えたにすぎない。 そう。 山本懸藏を亡命先のソ連で密告した、野坂参三・日本共産党元名誉議長と同様の、どこにでもある、ありふれた出来事にすぎないのだ……… ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jan 5, 2007
コメント(2)
全6件 (6件中 1-6件目)
1










