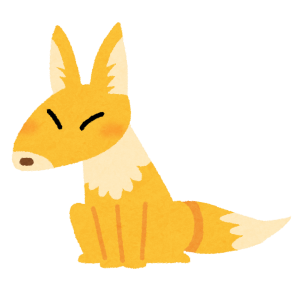全126件 (126件中 1-50件目)
-
ブログ引っ越しのお知らせ
当ブログはこのページに引っ越しいたしました。ヴェネツィアの獅子たち
2009/02/07
コメント(5)
-
ヴェネツィアと十字軍(その8)
略奪と破壊のあと、十字軍側、ヴェネツィア側からそれぞれ六人ずつの代表者が選出されました。その中から、ラテン帝国の初代の皇帝と総司教を決めるためです。 この地域を知り尽くした海の男として、ヴェネツィアのリーダーとして、この十字軍の実質上の総司令官であった総督エンリコ・ダンドロは、12人の候補者の中でも最も有力な初代皇帝候補でしたが、高齢を理由に候補者にされることも辞退します。 投票の結果、初代皇帝にはフランドル伯のボードワンが就くことになりました。そしてビザンティン帝国の広大な領地が、フランスの主な騎士とヴェネツィアとで分割されました。小アジアのニカイア地方を、ブロワ伯。ペロポネソス半島のアカイア地方を、ヴィラルドゥアン家(シャンパーニュ伯の家老職の家柄)。テッサリア、マケドニア地方を、モンフェラート候など。 ヴェネツィアの総督には、この度の分割で「東ローマ帝国の8分の3の統治者」という称号が付け加えられました。 その結果、アドリア海東部にとどまらず、イオニア海とエーゲ海のほとんどの島を所有することになり、ヴェネツィアからコンスタンティノープルの金角湾まで、一直線で結ばれるようになったのでした。 これにより、ヴェネツィアの海の支配権と交易上の優位性は圧倒的に増大し、ヨーロッパの強国の仲間入りを果たします。 しかし、近代から現在の、第四回十字軍のヴェネツィアに対する評価は「理想も思想も持たないヴェネツィア商人が、巧みに十字軍を利用して私利私欲を満たした詐欺的行為」というものです。 ヴェネツィアはただ、手持ちのカードと配られたカードで、自国の繁栄につながるよう臨機応変に行動しただけなのです。 また戦争も、ヴェネツィアが仕掛けたように言われていますが実は反対で、 最終的な攻撃に入る前に、万が一戦争が回避できるならと、アレクシウス5世との交渉を最後まで提案したのも、ダンドロ総督でした。 それに本当に私利私欲なら、ダンドロ総督が高齢であっても、皇帝の座に就いたでしょう。すぐに息子か孫にでも譲ればよいのですから。 もちろんダンドロは、歴代の総督の中でも特に優れた人物ですが、彼が特別なのではなく、そういう動きをしないための制度と気風が、ヴェネツィアにはすでに確立されていたのです。 一つの国も一個人も、まったく「私利私欲」無しの行動は有り得ないと思いますが、敢えて言うなら、この言葉から一番遠くに位置していたのが、ヴェネツィアであったと思います。 現代では、ネガティヴな響きの十字軍の、ましてキリスト教徒を攻撃し大義すら失った第四回十字軍を、すべて「ヴェネツィア商人」のせいにして、「罪悪感」を洗い流そうとする「心理」から来る、西欧の歴史の「検証」を感じでしまうのです。 ラテン帝国は、建設から50年ほどしか保たず、それから200年してトルコがコンスタンティノープルに侵入します。聖ソフィア寺院はモスクとして使われ、コンスタンティノープルは、千年以上呼ばれたその名を、イスタンブール(ISLAM-BOL=イスラムの豊かさ)と変えます。 ヴェネツィア総督エンリコ・ダンドロは、1205年6月1日コンスタンティノープルでその98歳の生涯を閉じました。聖ソフィア寺院に葬られ、名を刻んだ墓石は今でも残っています。(ラテン文字で書かれたエンリコ・ダンドロの名)
2009/01/03
コメント(4)
-
ヴェネツィアと十字軍(その7)
イタリア語の “bizantinismo” “bizantino” には、「ビザンティン様式」、「ビザンティンの」という第一の意味の他に、比喩的な使い方があります。 「結論を先送りして、のらりくらりする態度」「屁理屈好き」「人を欺くようなやり方」などです。言葉になるという事は、それがイタリア人の偽らざる感覚なのでしょう。 どの地域のイタリア人よりも、ビザンティン人と関係の深かったヴェネツィア人は、彼らの性質を熟知していたはずです。やはり彼らの経験に基づく危惧は的中します。 金角湾に泊まっているヴェネツィアの船に、火が付けられたのです。民衆の不満に迎合し、人気の回復を図ろうとしたアレクシウス4世が、十字軍を裏切ったためでした。 何とか火は消し止められ、被害は最小限ですみましたが、十字軍側からすると、これは事実上の宣戦布告に他なりません。帝国内の、ラテン人居住区も焼き払われ、もはや命を守るには戦う事しか残されていないようでした。 そんなビザンティン、十字軍双方ともに張りつめた状況の中、旧老皇帝と息子のアレクシウス4世が殺害されるという事件が起きたのです。権力の座を、これまた奪い取ろうとした、アレクシウス5世(4世の従兄弟)が謀ったことでした。 十字軍にとってこれでいよいよ、キリスト教国ビザンティン帝国襲撃の理由がそろいました。 1204年4月12日朝、コンスタンティノープルへの攻撃が開始されました。 初日こそ、それなりの抵抗を示したビザンティンの大軍隊でしたが、皇帝がくるくると変わる中、戦うモチベーションも指揮系統も失い、翌日の朝には、街の南部が十字軍により制圧されました。そこかしこで火の手が上がり、ビザンティンの住民が逃げ惑う中、コンスタンティノープルは十字軍の手に落ちたのでした。 そこで慣習により、十字軍兵士の三日間の略奪が行われました。緊張の後の勝者の興奮に、舞台は世界一の華やかな都。美しく貴重であればあるほど、彼らの征服欲と破壊欲を満たしたことでしょう。それが宝物であっても、宮中や貴族の女達であっても。 コンスタンティノープルの街は、目も当てられないほどに荒らされ損なわれました。 ヴェネツィアの男達がそれに加わらなかった、という証拠はありません。しかし彼らは、兵士というより商人であったので、貴重な写本やイコン、モザイク画、屏風などなどあらゆるものを持ち帰るのに夢中だったのです。 と言っても、後で転売して儲けようというよりも、ヴェネツィア人にとって、ビザンティン芸術は彼ら自身の誇りだったからです。古代ローマの栄華を継承する唯一の文明として、憧れと同時に彼らの「ルーツ」のようなものを感じていたのです。 この後、広大なビザンティン帝国の、領土の分割が行われます。(その8に続く Gustave Dore コンスタンティノープルの入場)
2008/12/27
コメント(0)
-
ヴェネツィアと十字軍(その6)
ビザンティン帝国の首都、コンスタンティノープル(コンスタンティノポリス=コンスタンティヌスの街)は、紀元前からの街ビザンティウムが、330年ローマ皇帝コンスタンティヌス(在位306-337)の遷都で、こう呼ばれるようになりました。 十字軍の攻撃を受ける1204年までの約千年の間、難攻不落の都市であり、文化、経済レベルとも断トツに世界一の、華やかな都でした。 しかし、大国のその繁栄が頂点に達すると、「お腹いっぱい」で動きが緩慢になり、新しい発想にも危機管理にも鈍感になりがちです。十字軍がやってきたのは、ビザンティン帝国のそういう時期でした。 だから、今度の十字軍が我々を攻めるらしい、と知っても、この街が攻め落とされるような事はまず有り得ない、と皇帝も支配階級の貴族も信じていました。 1203年7月、十字軍とヴェネツィア人の艦隊が、ボスポラス海峡に姿を現しました。フランスの騎士達の部隊は陸側から、ヴェネツィア人部隊は海側からの上陸を試みます。 ガレー船上のヴェネツィア人達は、前面の街を取り囲む城壁と塔の高さに苦戦していました。その時、船上でそれを見ていた総督エンリコ・ダンドロが、「私を城壁の手前の岸に降ろせ」と命じたのです。 それが転換へのきっかけでした。目も不自由な高齢の総督が、先頭を切って上陸したことによって、ヴェネツィア人の動きが変わり、金角湾の城壁を破り始めたのです。 一方、上陸したフランス人騎士部隊は、数では完全に勝るビザンティンの部隊と対峙していました。その知らせを受けた総督ダンドロは、全ヴェネツィア軍とともに加勢に駆けつけます。 それでも圧倒的有利は変わらないはずのビザンティン部隊が、戦わずして退却していったのです。数ではない、総督を始めとする、一人一人の気迫が圧倒したのでしょうか。 皇帝の座をむりやり乗っ取った、アレクシウス3世でしたが、これは不利と見たのか、愛娘イレーネと目ぼしい宝石を持って逃走したのでした。 釈放された前皇帝は、老齢を理由に息子アレクシウス4世に皇帝の座を譲ります。予定通りの十字軍側には問題はなかったのですが、ビザンティンの民衆にとって、アレクシウス4世は、外国人の操り人形であり、裏切り者でした。 そんな、暴動や蜂起が起きてもおかしくない情勢もあり、新皇帝は十字軍に、約束のお金がすぐに払えないのもあるし、滞在の契約期間を延期して、1204年の春まで留まってほしいと頼みます。 聖地奪回を忘れた訳ではない十字軍側は、不満を口にします。一方、出来たら聖地奪回などしたくないヴェネツィア側といえば、今から冬の到来で、ここに留まるのはいいとして、あまりに長引かせるのはまずいな、と感じていました。 彼らヴェネツィア人は、長い交易上のつきあいから、新皇帝の言葉を鵜呑みにするには、ビザンティンの人間の性質を、知り過ぎていたのでした。(その7に続く 城壁に囲まれたコンスタンティノープルの街の絵)
2008/12/20
コメント(0)
-
ヴェネツィアと十字軍(その5)
十字軍への、ビザンティン帝国皇太子アレクシウス4世の依頼に、最初に賛成した人物がいました。モンフェラート候のボニファチオです。10世紀頃ピエモンテ州の丘陵地帯に興った侯爵家で、今回の十字軍の総大将を勤めている人です。 ところで、アレクシウス4世の姉が二度目の結婚で、ホーエンシュタウフェンのフィリップ(ドイツ王1178-1208 神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(通称赤髭王)の末子)に嫁いでいました。 それで、アレクシウス4世は、十字軍にこれらの依頼をする前に、この義兄を頼ってビザンティン帝国の顛末を相談しに行っていたのです。 フィリップは、妻の弟の窮状を助けてやりたいのと、最大のライバル関係にあるヴェルフェン家のオットー4世を出し抜きたい気持ちもあって、義弟アレクシウス4世の要望を受け入れます。 この時に、このドイツ王と縁戚関係である、上記のモンフェラート候もフィリップのもとを訪れていたのです。彼らの間で、十字軍への依頼とその見返りについての、事前の根回しが出来ていたのは間違いないようです。 ヴェネツィアは、ビザンティン帝国での「お家騒動」の件は把握していましたが、ドイツ王とモンフェラート候が加わった、アレクシウス4世の王座奪還計画の情報まではつかんでいなかったので、ザーラでのビザンティン皇太子の登場は、想定外の出来事だったのです。 しかし、総督エンリコ・ダンドロも、すばやく賛成を表明します。ヴェネツィアにとって、ビザンティン帝国との決着を付ける時が来ていたからです。 ここ何十年か、ビザンティン帝国はイスラム教徒との戦いの他、国内の有力貴族達の賄賂の横行で腐敗がすすみ、市民が暴徒化することが多々ある等不安定な状態でした。 そんな中、ヴェネツィアが伝統的に受けてきた交易優遇措置を、突然打ち切ったり、元に戻しても年々不利な条件にするような「なめられた」外交状態であったのと、帝国内のヴェネツィア人が、庶民の憎しみの対象となって殺害される事件も多発していたのです。 熟考したのは、フランス人の騎士達でした。一度ならず二度までも、キリスト教徒を襲うのはいくら何でもまずいのでは、とのためらいがありました。 けれども、総大将であるモンフェラート候が賛成したこと、そして見返りとしてアレクシウス4世が出した、「東西キリスト教会の統一」が実現すれば、結果的に神のためになるのだという「大義」に押され、彼らも目的地をエジプトからコンスタンティノープルへ変えることを承諾したのでした。 最終的に「大義」が勝った理由として、大金30万マルクの存在は関係なかった、とはやはり言えないでしょう。 これを知った法王インノケンティウス3世は、怒ります。しかしあくまで表面的にです。彼は、「東西キリスト教会の統一」への野望にくすぐられていたからです。それを示すように、今回の具体的な懲罰はありませんでした。 1203年春、十字軍はいよいよ世界一の都、コンスタンティノープルに向けて出発します。(その6に続く イスタンブールの聖ソフィア寺院(アギアソフィア)で、かつての正教会の総本山。4本の尖塔は15世紀オスマン帝国支配後に設置)
2008/12/13
コメント(0)
-
ヴェネツィアと十字軍(その4)
イストリア、ダルマツィアの街は、これまで目にしたこともないような艦隊を見ただけで、すぐに恭順を誓いました。 一方、ザーラの街は抗戦の構えだったので、十字軍の襲撃を受け、再びヴェネツィアの支配下に入ることが約束されたのでした。 しかし、これを知った法王インノケンティウス3世は激怒し、十字軍を破門します。ハンガリー王国もこの沿岸地方もキリスト教徒の民だったからです。 フランスの騎士達はあわてて、法王に「ヴェネツィア人に、さもなければ船を出さない、と脅されやむを得ず」と「状況の説明」をし、なんとか破門は撤回されました。 一方ヴェネツィア人は、破門には慣れていたので、破門されたままでした。 たしかに、異教徒征伐の十字軍が、キリスト教の民を襲撃するのは、矛盾しています。しかしそれなら十字軍は、異教徒と交易することで成り立っている、ヴェネツィア共和国総督の提案は受けてはならなかったし、そもそも矛盾の元は、支払い能力があるかどうかも分らずに、大事業を企てたことにあります。 一方、ヴェネツィアの行動の判断基準は、「国益」にかなうかどうか。短期、中期もしくは長期的な視野から、国のためになるか否かで、首尾一貫しています。 さて1203年、ザーラで春待ちのために停泊中の十字軍に、ある人が面会を求めにやって来ました。 ビザンティン帝国(東ローマ帝国)の皇太子アレクシウス4世です。彼の父、皇帝イサク2世は兄弟であるアレクシウス3世の謀反にあい、失明させられたうえ投獄されていたのでした。 アレクシウス4世は、父の仇である叔父を追放し、皇帝の座を取り戻す協力をしてほしい、そうすれば代わりに、30万マルク(20万マルクの説もあり)の現金、イスラム教徒との戦いのため1万人の軍隊、全ビザンティン帝国領土で、カトリック教会の権威の承認を約束するというものでした。 アレクシウス4世のこの依頼が結果的に、第四回十字軍の運命を変えることになるのです。(アレクシウスの肖像 その5に続く)
2008/12/06
コメント(0)
-
ヴェネツィアと十字軍(その3)
さて、この時のヴェネツィア総督エンリコ・ダンドロは、1107年生まれとあり、総督に選出された1192年に、すでに85歳。第四回十字軍の依頼があった1201年には、94歳ということになります。 この生まれ年が正確かどうかは、はっきりとは分りませんが、とにかく相当の高齢であり、なおかつ衰えを見せない判断力、決断力の持ち主であったことは間違いないようです。 この経験豊かな「老巨人」は、その大規模な十字軍側の計画を知り、輸送準備をするだけでなく、ここはひとつ自分たちも船と人を出して参加し、今後の交易にさらに有利になるよう開拓しようと、ヴェネツィア政府首脳とともに考えたのでしょう。 十字軍の依頼とは別に、ヴェネツィアの費用で、50隻のガレー船と人員を出すことを決めます。 そしてその十字軍の依頼とヴェネツィア政府の決定が、サンマルコ寺院に集まった一万人のヴェネツィア市民に承諾され、国を挙げての準備が始まりました。 一年後の1202年春、ヴェネツィアはすべての契約内容を果たし、たくさんの新しく作られた船が、出航を待っていました。しかし十字軍側といえば、集まるはずだった兵士の数も、お金もまったく足りていなかったのです。 85000マルクのうち34000マルクが未払いのままでした。このままではヴェネツィアの大幅な赤字になるため、船を出す訳にはいきません。十字軍側は資金集めに奔走しますが、やはり足りない。さて、どうするか。 総督エンリコ・ダンドロが、打開策としてある提案を十字軍側に持ちかけます。アドリア海南下の途中で、イストリア地方の街と、最近ハンガリー王国に占領されたザーラの街を取り戻すのを手伝ってくれたら、不足分は後で結構です、というものでした。 アドリア海に面したイストリア、ダルマツィア地方(現在のクロアチア沿岸部)の街は、ヴェネツィアにとって、商船の通行上譲れない重要なポイントのため、以前よりヴェネツィア共和国の支配下にあったのですが、時折反乱することがあったのです。 十字軍側は考慮の末、この提案を受け入れることにしました。ヴェネツィアに集合してから資金不足のため出発のめどが立たなかったのが、これでようやく動き出せるからです。 1202年10月、総督ダンドロをはじめ、多くのヴェネツィア人を含む十字軍は、二百隻以上からなる艦隊でヴェネツィアを出航します。「世界」「巡礼者」「天国」と名付けられた3隻の大きなガレー船は、長さ60メートル幅10メートルで、一列に25人ずつ左右各二列で計100人の漕ぎ手と、そびえ立つ3本のマストが見るものを圧倒しました。(その4に続く)
2008/11/29
コメント(0)
-
ヴェネツィアと十字軍(その2)
ビザンティン帝国は、第一回十字軍の成功により、領土の回復に成功していましたが、1176年に再びトルコ勢に再び破れ、帝国は衰退していました。 1198年に選出された、若き法王インノケンティウス3世(1160-1216)は、すぐさま第四回十字軍編成に着手しました。しかし、第一回十字軍から100年が経ち、第二回、第三回の不成功もあって、人々のあいだに以前のような熱狂はなく、法王の計画はなかなか具体化できないでいました。 そこで、パリ近郊出身のフォルコ修道士に、白羽の矢が立てられます。パリの神学校で学んだこの修道士が、抜群の記憶力と、人に感銘を与える巧みな弁舌の持ち主であることを、法王が知っていたからです。 フランスの騎士達が会した場所で、自ら、赤い十字の形の布を、僧衣の背に縫い付けたフォルコ修道士の演説が始まりました。「位のある者も、ない者も一丸となり、聖地を守り抜かねばなりません!神がお望みになるのです。そう、神がお望みになるのなら、私たちは怖れることはなにもない。この十字架を手に、私たちの勇気と血で、汚れた者の手から取り戻そうではありませんか!」 数分後にそこは、熱気と興奮に満ちた劇場のような空間と化していました。こうして第四回十字軍が動き出したのです。 フランスの名のある騎士達が参加を表明し、シャンパーニュ伯、ブロワ伯、フランドル伯から二人ずつ計六人が、細事の決定の代表として選出されました。行程は海路とし、輸送全般は、ヴェネツィア共和国に依頼することが決定しました。 1201年の春、この六人の代表はヴェネツィアにやってきます。この度の十字軍輸送の委託交渉のためです。「4500人の騎士、4500頭の馬、20000人の歩兵、9000人の従者を運ぶ船と、それらの一年分の食糧」これが、十字軍側が、ヴェネツィアに頼んだ中身でした。 これは単なる移動手段というのではなく、ヴェネツィア側にとっても国をあげての大事業で、失敗はできない大きな資本投下を意味していました。これを、85000マルクで1202年の6月29日までに用意をする、というのが契約の内容でした。 さて、この時のヴェネツィア政府トップは、エンリコ・ダンドロです。この第41代総督は、しかし齢八十を超え、以前のケガで視力も十分ではない状態でした。(その3に続く)
2008/11/22
コメント(0)
-
ヴェネツィアと十字軍(その1)
「十字軍」という言葉は、理想又は信念に基づく、集団的な抗議行動をさす意味に使われたりもしますが、歴史的には中世カトリック教会の、異端征伐のための軍隊や戦争のことです。 具体的には、1096年から1099年までの第一回十字軍遠征から、1270年の第八回までのことで、キリスト教発祥の聖地パレスティナを、イスラム教徒から奪回する目的で行われた戦争です。 11世紀、中央アジアからトルコ系遊牧民であるセルジューク朝が台頭し、ビザンティン帝国(東ローマ帝国)の領土を侵食し始めていました。11世紀後半には、首都コンスタンティノープルも含む、アナトリア半島(小アジアとも。現在のトルコの大部分)を占領されます。 ビザンティンの皇帝アレクシウス1世は、ローマ法王ウルバヌス2世に援軍を依頼します。 ビザンティン帝国は、東方正教会とはいえキリスト教の民です。そこで、この教会改革と異教徒征伐に燃える法王は、1095年クレルモン教会会議で、十字軍遠征を宣言します。 この第一回こそ、ビザンティン帝国の領土奪回に成功し、エルサレム王国を建設、当初の目的は達成したと言えますが、それ以降は第四回を除き、イスラム諸国の反撃にあい、基本的にはほとんどが失敗しています。 現在でこそ、これらの十字軍遠征は、「聖戦」に名を借りた完全な侵略戦争であった、と考察されています。というのは、十字軍遠征への参加者は、宗教的な正義感というより、名誉欲や領土欲、または免罪符を手に入れるという、世俗的なモチベーションに動かされた者も多かったことなどからです。 一方で、純粋な宗教的な正義感から、自腹を切って参加する者も、当然多くいました。これらの人々は、動機が純粋な分、もっとタチが悪いのです。「正義」という美酒に酔いしれると、他に耳を貸すだけでも不純だとでもいうように、脇目もふらず突き進んで行ってしまうからです。たとえ、その「正義」がキリストであれ、天皇であれ、マホメットであっても。 さて、ヴェネツィアが関わったのは、第四回十字軍で、1202年から1204年のことです。当初ヴェネツィアの役割は、遠征に必要な装備(船、馬、食料など)を準備することでした。それが、どういう訳で主力として関わるようになったかを、次回からたどってみましょう。(その2に続く)
2008/11/15
コメント(0)
-
ヴェネツィアとイタリアの歴史観(その5)
この大きな潮流、つまりローマ教会とフランスの影響の少ないイギリスやアメリカでは、19世紀から現代まで、たくさんのヴェネツィア史の研究がなされ、その政治や経済、ヴェネツィア人の特殊性に関する書物が多く出版されています。 日本では、塩野七生さんが『海の都の物語-ヴェネツィア共和国の一千年』を書いておられ、その取材力の広さと洞察力の深さだけでなく、読み物として素晴しく面白いこの本は、以前のヴェネツィア人の真骨頂と、かつてのこの街の空気を生き生きと伝えてくれます。 この街に、アルヴィーゼ・ゾルジという歴史家がいます。総督も輩出しているヴェネツィアの古い家系の末裔で、現在のヴェネツィア文化、歴史の重鎮ですが、氏の著書『街、共和国、帝国 ヴェネツィア697-1797』の前書きに、こう書かれてあります。 「いつの日か近い将来、恨みや先入観から解き放たれた新しい歴史家たちが、情熱と鋭い見識をもって、否定され中傷されて来たヴェネツィアの歴史を、きちんと検証する時が来るだろう」と。 しかし、この大きな権威の潮流が変わる気配はないし、まず何よりも、今のヴェネツィア人である、この街の地元住人の多くが、自分たちの歴史について関心がないからです。 有名なこの街の出身である事や、名の知れた建築や芸術についての、ネームヴァリューゆえのプライドはあっても、自分たちの祖先が、何故どのようにして繁栄していったのかについて知りたいと欲するような、深く内なる誇りが見受けられないからです。 なので私は、「そんな日」(いつかヴェネツィアの歴史がきちんと検証される日)は、とりわけイタリア人の手によっては、持たらされはしないと、悲観しています。
2008/11/08
コメント(0)
-
ヴェネツィアとイタリアの歴史観(その4)
「1202-1204年、ヴェネツィア商人に煽動された第四回十字軍、コンスタンティノープルを奪取」 「第四回十字軍、ヴェネツィア人は、封建小領主のような野心を持って、コンスタンティノープルに進路を曲げ、ビザンツ帝国の商業戦略拠点を奪い取った」 と、定義されています。フランス語もしくは英語の原文を、忠実に日本語に翻訳された文だと思います。 この本の十字軍の記述は、それまでにあった「聖地奪回という、十字軍の純粋な聖なる目的」には、多少疑問を呈しているけれども、「金儲けしか頭にない狡猾なヴェネツィア商人にだまされた」という責任転嫁の被害者意識からは抜け出ていません。 出来るだけ客観的な描写をと配慮されている、この欧州共通教科書でさえ、こういう表現なのですから、ヨーロッパでも日本でも上記の内容が「常識」となっています。 「常識」というのは、しばしば権威によって作られるものです。例えばテレビというのは、現代の大きな権威の一つで、「テレビで言っていた事」「テレビに出ていた人」は、それだけで説得力を持つものです。たとえそれが事実の中に、無知によるデマや、感情による偏りが散りばめられていても、です。 ヴェネツィア創成期、ビザンティン帝国の傘下だった時期以降、18世紀にナポレオンに倒されるまで、ずっとどの権力にも属さずに独立と自分たちの主義を貫いてきたヴェネツィア。 その千年にわたる歴史の中で、フランスは強大な国でありながら、なぜかヴェネツィアに裏をかかれて知恵で敗北するような、苦い出来事が多々あります。ローマ教会にしても、カトリック教徒にとって「死」と同義語の「破門」でさえ、ヴェネツィア人は幾度の破門にもまったく動じない、許しがたい国でした。 ローマ教会とフランスという国に、結果的に恥をかかせたヴェネツィア共和国の歴史は、現代でも大きな権威であるこの二つの潮流から無視されている。また、イタリア国内では郷土主義が強い上に、歴史を扱う仕事の人、つまり歴史家や大学の教授や作家、いわゆる知識人達は、フランスに顔が向いてる事が多い。 これらが、ヴェネツィアの歴史をイタリア国内でもヨーロッパでも過小評価し続ける理由、ではないかと思います。(その5に続く)
2008/11/01
コメント(0)
-
ヴェネツィアとイタリアの歴史観(その3)
ヴェネツィア以外の国、例えばフィレンツェなどはどうでしょうか。 共和国と言っても実際は、メディチ家の独裁体制だった300年ほどの歴史は、その内外に大きく知れ渡っています。 グエルフ(教皇派)とギベリン(皇帝派)の争いはあったにせよ、全体的にはローマ教会との深いつながりは否めないこと。ルネサンス(芸術などの新しい表現や人文主義などの文化革新)の保護者のイメージが定着していること。現代イタリア語の基礎が、トスカーナ方言をもとに構築されていること、などの理由が、フィレンツェの歴史を「拡大解釈」させている、と言えると思います。 次に、「ヨーロッパの歴史」という大きな枠組みで、大まかにどういう視点から歴史が語られているかというと、フランスからの視点ということになるでしょう。 それは、18世紀の終わりに起きたフランス革命に起因していると思われます。それまでの封建社会を廃棄した市民革命は、フランスのみならずヨーロッパを近代へと導いた出来事として、位置づけられているからです。実際、フランス革命がヨーロッパに放出した、「自由」や「平等」といった概念の多大な影響に疑問の余地はありません。 ここに、『ヨーロッパの歴史-欧州共通教科書』(総合編集フレデリック・ドルーシュ 東京書籍)という本があります。 1993年のEU(ヨーロッパ連合)発動に伴い、(ある程度の)歴史観を共有する、という目的で、12人の国籍の異なるヨーロッパの歴史家たちによって編纂されたものです。 長い間、覇権をかけて争いを繰り返して来たこのヨーロッパ大陸で、共通教科書という概念を持つ書籍が、実際に生み出されたことは、画期的なことだといえます。 EUの目的は主に、大国アメリカ、日本、そして中国などとの経済戦争に負けないために一枚岩で戦うための経済戦略ですが、実行、維持には多大な費用と、地域主義、愛国主義を超えた人間の知性が要求される大事業です。「アジアの共通教科書」など、ほど遠い現状からは、ヨーロッパ人の知恵に感嘆せざるを得ません。 ではこの本の中で、ヴェネツィアがどういう風に語られているか。例えば「第四回十字軍」についてはどうでしょうか。(その4に続く)
2008/10/24
コメント(0)
-
ヴェネツィアとイタリアの歴史観(その2)
ローマ教皇領に王国や公国、共和国などが、覇権を争ってきたイタリア半島で、では、現在どの視点から歴史が語られているかというと、それは「ローマ」から見た歴史です。 現在の首都であるというよりも、ヨーロッパ文化の源である古代ギリシャ文明の後を継ぐ、栄光のローマ帝国発祥の地であること。そしてもっと大きな要因は、ローマカトリック教会の総本山の地であること、です。 初代教皇とされる聖ペテロ(紀元60年頃)から数えて、現在の265代目のベネディクト16世まで、そのほとんどがイタリア人である教皇の2000年の歴史は、今日もなおイタリア社会に、目には見えないほど透明で、しかし強靭な影響力を与え続けています。 先代のヨハネ・パウロ2世も現教皇も、好々爺的な微笑みをたたえ、こじんまりとしたヴァチカン市国から、世界の平和を願う、というイメージが強いのですが、良くも悪くもそれだけではないでしょう。 何も、その微笑みの後に、陰謀が隠されている、ということではありません。ただ、ヴァチカンの国自体は小さくとも、ローマ教会の組織は巨大であり、特にイタリアでは、あらゆる場所の草の根まで浸透しているため、尊厳死問題や家族のあり方等に関する教皇の発言や姿勢は、直接人々の、宗教というよりモラルの基準として、無意識のレベルにまで影響を与えているからです。 とはいえ、歴史観の統一という立場に立てば、どこかに照準を合わさなければ収拾がつかないので、大きな権威を持つ「ローマ」からの視点になることも、仕方のないことかもしれません。 ただ、例えばヴェネツィアのように、ローマ教会に対して「恭順」とは反対の姿勢を貫いた国では、ヴェネツィアの知将も、「イタリアの歴史」では単なる悪者として描写されることが、しばしば起きてしまうのです。 人物の評価はもちろん、ヴェネツィア人が始めた先進的な政治的機構や社会制度、経済政策等も過小評価もしくは、まったく言及すらされないことが、理不尽なほど多々あります。(その3に続く)
2008/10/17
コメント(0)
-
ヴェネツィアとイタリアの歴史観(その1)
イタリア半島は、ローマ帝国滅亡のあと、北から南から、西から東から、様々な民族が侵入を繰り返し、異なる文化を持つ大小の国々が建設されて来ました。 南部はイスラム、スペインの影響を強く受け、中部から北イタリアでは、小都市国家が分立していました。 今では「世界最小の国」であるヴァチカン市国も、かつてはローマ教皇領として、ナポリの北側からローマ周辺はもちろん、(フィレンツェ、シエナを除き)東部はヴェネツィアの手前まで達していました。 容姿もメンタリティーも、まったく違う民族が散らばって国を形成し、国境付近だけでなく、一つの国の中でも地域や区域ごとに、小競り合いと衝突を繰り返してきた場所です。 そして、19世紀になって、ようやく「イタリア」という国として統一されたのですが、地方の特色や地域同士のライバル意識は色濃く残っています。 広い視点でいえば、南北での大きな違い―「倫理感」から経済的な格差。狭い視点では同じ街の中での違い―小さなそれぞれの区域が持つ、方言から食の伝統に至る土着性。 これらの大小にわたる、決して譲り合わない頑固さが、風土となり文化となり、イタリアの面白さや奥行きを形作っていることは間違いありません。 イタリアのイタリアらしさは、イタリアという概念を取り去ったところにあります。つまり、イタリアという額縁を無視して、ひとつひとつ異なる輝きを放つモザイクのかけらを観察しないことには、意味がありません。 イタリアという額縁で囲まれた全体像としてのモザイク画に何が描かれているのかは、あまりにも混沌としてイタリア人自身にも外国人にも分からないのですから。 イタリアという国はあっても、パスポート上はイタリア人でも、実際にはイタリア人は存在しないと言ってもいいくらい、郷土色が強いからです。シチリア人は、本土へ行くのに「イタリアへ行く」という言い方をするし、例えば同じような地震が起きても、フリウリ地方の人々とカンパーニア地方では、反応もアクションも全く違うことでも分かります。 ですから、イタリアとしての共通の歴史観を持つのは、それはそれは困難を極めるというものです。それでも教師の知識や教科書は、当然ある程度統一した物が必要なわけです。(その2に続く 写真は18世紀のイタリア。クリーム色がローマ教皇領)
2008/10/11
コメント(0)
-
ヴェネツィアの第四の橋(その3)
なぜか、この橋で転倒する人が多く、市の関係者が建築家カラトラヴァ氏に至急、調査と対策の要請をしたということです。そして先日の新聞によると、カラトラヴァ氏が出した解決策は、いくつかの踏み段を取り替える、というものでした。 実際、私も歩いてみました。橋がオープンしてからすぐに「転びやすい」ことが報じられていたので、前半はそれなりに気を付けて歩いていました。が、後半下る時には景色や行き交う人を眺めながら、「気を付けること」を忘れていたためか、つまずきそうになったのです。 ちょうど、階段の幅が今までの幅から倍になっている部分で、歩くリズムが変わってしまうことと、材料の大理石とガラスのつなぎ目の微妙な段差が原因のようです。 雨の日や、高齢者の場合、つまづきそうになったでは済まないで、転倒してしまうのは容易に想像がつきます。 ということは、そもそも著名建築家のプロジェクトが間違っていたのか?だいたいそんなこと(人間の一般的な歩幅やリズム)は、設計の段階で何度も精査されるべきことではないのか?橋の設計で有名な氏も、車の通行しない「人間だけの橋」は初めてだったから? 地元の疑問は尽きません。 市側は、踏み段を取り替える費用はどこが出すのか、責任はどこにあるのかなどをはっきりさせないままでは、踏み段の取り替えはしない、という方針のようです。 「転びやすい」という、この橋の機能の問題からすれば、景観や現代建築うんぬんなど、些末なことになりますが、この「憲法の橋」という名前についてもどうかと思うのです。 決定には紆余曲折あったらしいのですが、どうしてまた「Ponte della Costituzione」などというイタリア語でも固い響きの名前にしたんでしょう。 今年はイタリア憲法60周年だから、とのことですが、これではまったく耳かき一杯程の想像力もかき立てられないというものです。間違いなく、地元の誰もこの名前では呼ばず、「ローマ広場の橋」か建築家の名前で呼ばれることでしょう。 カラトラヴァ氏が、ヴェネツィアの街へのオマージュとして「寄贈」したと言われるこのプロジェクトですが、 とは言え、橋の両側の手すりの最初と最後の計四カ所にある、彼の紋章の存在については、違和感を持たずにはいられません。 この橋の、特に機能性についての問題は、まずデザインや概念ありきで、実際に使う人間やその後のメンテナンス等を後回しにした結果ではないかと思います。 実際に使えること、続けられること、そして効果的であることに重きを置いてきたかつてのヴェネツィアの政治。プラグマティズムという言葉が生まれる前から、それを貫いてきたヴェネツィア人。それから思うと、この橋にまつわるあらゆることが、「ヴェネツィアらしさ」からは遠いもの、になってしまっている気がします。
2008/10/03
コメント(2)
-
ヴェネツィアの第四の橋(その2)
常に批判の的になってきた、この橋の建設にかかった18億円近い経費については、それが高いの妥当なのか、私には判断のしようがありません。それ以前に、この橋が本当に必要だったのか、ということもよく分からないのです。 あれば多少の便利さは増すでしょう。でもたとえこの橋がなくても、駅の前のスカルツィ橋で、十分今まで通用してきたので、あえてお金をかけて、更に便利さを補う必要があったのか、という疑問は残ります。 それでも、その多少の便利さと、ヴェネツィアへの入り口でありながら、なおざりにされたようなゾーンであった、「ローマ広場と駅周辺」を再整備するという目的については、意義があったと思うので、橋の存在自体の疑問は良しとしましょう。 次の疑問は、なぜ「現代建築」にこだわるのか、ということです。かつてのヴェネツィアは、現代建築のメッカでした。ヴェネツィア共和国政府が決定した公共工事の設計コンペには、内外の有名建築家がたくさん参加して、美しさや奇抜さだけでなく最新の技術やアイデアを駆使して、このヴェネツィアという街に自分の作品を残そうと競い合いました。でもそれはヴェネツィアという街が、当時ヨーロッパでもトップクラスの経済都市で、人と物が集まるメトロポリスであったからです。 至極簡単に言ってしまえば、以前のヴェネツィアは今の東京で、今のヴェネツィアは現在の京都、ということです。なぜ、千年の都の玄関口に、あえて現代建築なのか(京都駅でも論争がありましたが)。旧いものがすべて素晴しい、というつもりは全くありませんが、長い歴史と文化を持つ街には、それを誇り、お金に換えるだけではない、維持するという十字架のような責任があるはずです。最新の科学技術を利用しつつ、見た目はアンティークに仕上げることも可能だと思うのですが。 次に、「禁止事項」について。この橋の脇に、この橋を使用する上での「注意事項」の立て看板があるのですが、そこには、(1)20キログラム以上もしくは1メートル四方以上のカートや荷物の運搬の禁止(2)タバコの吸い殻やガムのポイ捨ての禁止(3)汚したりゴミの廃棄の禁止、とあります。(2)と(3)については、当然のモラルで、この橋に限った話ではないはずです。この橋だけ特別にこうして「通告」する意味が分かりません。 この橋が「芸術作品」だから、というのでしょうか。それなら、この街すべてが貴重なアートであるわけで、そこに平気で飼い犬のフンを放置する、ゴミを捨てる、小便をする(人間!)、スプレーの落書きをする、地元の人間の教育から始めるべきではないでしょうか。 そして(1)についてはもうナンセンスとしか言いようがありません。大きな荷物を抱えた観光客も多く利用するこの場所で、エコノミークラスの重量制限よろしく20キログラム以内のみとは。公道というのは、あらゆる人があらゆる理由で通る訳ですから。 とりわけ、車のないヴェネツィアでは、多くの物が人間の手によって運ばれます。この街に橋を造るという根本的な意味を、建築家も行政も無視しているとしか思えません。リアルト橋などは400年以上も前から、朝から晩まで業務用の台車やカートの往来に耐え、磨り減りながらも独特の風合いを出しているというのに。 しかし、それよりももっと重大なことがあります。この橋はどうも「転びやすい」のです。(その3に続く)
2008/09/26
コメント(0)
-
ヴェネツィアの第四の橋(その1)
車での玄関口である「ローマ広場」と、鉄道の入り口「サンタルチア駅」を結び、大運河にかかる橋としては、四番目になる「憲法の橋」が完成し、先日9月11日の夜お披露目されました。 大運河に第四の橋を、カラトラヴァ氏の建築で架けようという話が出たのが10年以上前で、工事が始まったのが4、5年ほど前だったと思います。しかし、工事はいつのまにか中断され、長い間そのままになっていました。 工事の大幅な遅れはもちろん、公共工事が中断され、再開されずに放置されるのは、北イタリアでさえよくあることですから、「役所のやることだから」と、ヴェネツィア市民の誰も不思議にも思ってはいなかったでしょう。 それが、去年の夏突然再開され、先日の落成となったわけです。 市幹部によると、この橋は『過去の栄光とその遺産にたよるだけでない、未来を見つめて今を生きる、この街のためのシンボル』であり、『旧いヴェネツィアの街に、素晴しく溶け込んだ現代建築』なのだそうです。 この橋のデザイナー、著名な建築家でエンジニアでもあるスペイン人のサンティアゴ・カラトラヴァ氏も言ってるそうです。『この橋は、私の数ある橋の中で、一番美しい』と。 たしかに、この長さ94メートルの橋は、美しいことは間違いありません。そのゆるやかなライン、欄干はガラスで、階段部分は大理石、足下には照明も埋め込まれています。夜にライトアップされた時は幻想的な感じさえします。 けれどもやはり、この橋についてのいくつかの疑問は残り、ある「禁止事項」には、少々驚きました。(その2に続く)
2008/09/19
コメント(1)
-
ヴェネツィアの「サンマルコ行政官」
『モロジーニ家は、ヴェネツィアで最も古く、由緒ある家系のひとつで、4人の総督と27人のサンマルコ行政官を輩出し‥‥‥』と、かつてのヴェネツィアの著名な家系が紹介される時よく目にする文章です。 共和国の代表で、政治のトップである総督(ドージェ)の次に書かれてある、この「サンマルコ行政官」は、その序列通り総督の次にあたる要職でした。 それまでの功績や実績と人物を総合的に考慮して、ヴェネツィア共和国の大評議会で選出され、任期が終身であることも総督と同じです。 では、サンマルコ行政官(プロクラトーレ)とは、どういう任務であったかというと、サンマルコ寺院建設の管理と監督でした。 この街の象徴で、守護聖人でもある聖マルコのための寺院は、9世紀始めに完成し、その後も増築や改築、改修を15世紀頃まで行っていました。それらの工事や補修の監督ならびに、数々の宝物の管理が具体的な仕事でした。 最初は一人であったこのサンマルコ行政官は、三人になり、六人になり、15世紀半ばには九人にまで増やされました。寺院の監督以外にも任務の幅が広がったためです。 ヴェネツィア人の心の拠り所であったサンマルコ寺院には、毎年相当な金額の遺産や寄付が集まっていたのです。その財務管理が必要になったからでした。九人の内訳と責務は、「スープラ」と呼ばれる三人は、サンマルコ寺院とサンマルコ広場の管理、監督。「チトラ」と呼ばれる三人は、大運河の向こう側の3地区(サンマルコ、カステッロ、カンナレージョの各地区)の慈善事業と遺言書の管理。「ウルトラ」と呼ばれる三人は、大運河のこちら側の3地区(ドルソドゥーロ、サンタクローチェ、サンポーロの各地区)の慈善事業と遺言書の管理。 遺言書の管理は、遺産の分配が遺言者の書状通りに行われているかを、監視する仕事です。 慈善事業の内容は、サンマルコ寺院に寄付された財産を使って、困窮者に家を提供したり、クリスマスと復活祭前に、貧しい者に「慈悲手形」という配給券を配ったり、孤児や精神障害者の援助にも役立てられていたのでした。 サンマルコ寺院に集まる莫大な財産を、13世紀当時すでに教会ではなく国家が、社会的弱者への援助を、制度として確立し運用していたこと自体、とても先進的なことですが、もうひとつ、ヴェネツィアならではのスタイルがありました。 普通、大聖堂や寺院に寄付される財産は、教会の資産としてその土地の司教が管理、運営するのですが、ヴェネツィアは、それをさせませんでした。 聖マルコを崇めての寄進であって、そこの司教や枢機卿、はては法王を崇拝してのものではないので、ヴェネツィア人にとっては自分たちで管理するのが当然だったのでしょうが、9世紀から15世紀の間では、非常に独自な考え方だったのです。(写真は、サンマルコ広場両翼の行政館。行政官の住居であり事務所であった)
2008/09/13
コメント(0)
-
ヴェネツィアの「サン・ポーロ広場」
フィレンツェから逃げて来ていた、ロレンツィーノ・デ・メディチ(1514-1548)が、1548年2月26日に叔父と一緒に暗殺された場所として有名な、サン・ポーロ広場は、「カンポ=広場」と名のつく所では、一番大きな広場です。 昔から、ここはその広さから、たくさんの催し物やお祭り、宗教行事などに使われて来ました。牛追い、仮面舞踏会の会場、夜は花火大会、馬上槍試合、色々な展示会や市場などです。 1540年頃、朝日の中を、近くに住むある紳士がこのサン・ポーロ広場を散歩をしていました。するとどこからか、新生児の泣き声が聞こえます。その声の方へ近づいてみると、カゴがネコにひっくり返されて、赤ん坊が地面で泣いていたのでした。 その紳士に引き取られ、 1563年にサン・ポーロ教区の司祭となった、アントニオ・ガットは、夜のサン・ポーロ広場に、生まれてすぐに置き去りにされた捨て子でした。 朝になれば、広く常に人のいるこの場所なら、親切な誰かが拾ってくれると考えたのでしょう。 「ガット」という名字を付けられたのは、夜のこの広場で、一番最初に彼を見つけたのが、ガット(=ネコ)だったからなのかもしれません。 今も、このサン・ポーロ広場は、色々なイベントに使われています。冬は、仮設の小さなスケートリンクが作られたり、ミニ移動動物園が来たり、カーニヴァルの会場にもなります。今の時期は、映画祭の一環で、野外映画が連日上映されています。 秋は、掃いても掃いても積もる落ち葉を、ザクザク言わせながら、この広場を横切って、なるべく人通りの少ない路地へと消えるのが、地元の歩き方です。
2008/09/05
コメント(0)
-
ヴェネツィアの孤児院
ヴィヴァルディ(ヴェネツィア生まれ1678-1741)が、ヴァイオリンや作曲、合唱などを教えていたことで有名な、ピエタ教会付属の音楽院ですが、それより以前から教会付属の孤児院がありました。 その孤児院があった側には、写真のように、子供を置き去りにする人間を強く非難する内容の、大理石の掲示が、今でも残っています。 ここは、経済的な理由で、どうしても親元では育てられない子供のための慈善院でした。しかし、15世紀から16世紀にかけて、財力があるにもかかわらず、子供をここへ置き去りにする人々が急増しました。 赤ん坊が巻かれている上質の織物や入れられたカゴ等ですぐに分かったのです。 この時期は、ヴェネツィアが国として最も繁栄している時代と重なっています。貴族や財を成した商人たちが、愛人の間に出来た子供らを、ひそかにここへ連れて来ていたのです。 これに業を煮やしたヴェネツィア政府は、このような掲示をしました。 「嫡出であれ非嫡出であれ、十分に養育する財産、能力があるにもかかわらず、ここに子を置き去りにすることは、法王パウルス3世の教書にもあるように、許しがたく、破門に処され、必ず天罰がくだるものである。1548年11月12日」 ローマ法王庁とヴェネツィアは、決して良好とはいえない関係にあったし、この法王パウルス3世(1468-1549)も、反宗教改革に乗り出す等、ヴェネツィアの方向性とは違っていました。が、使えるものは何でも使うというか、あらゆる権威を駆使してでも、この裕福な家からの捨て子を減らしたいという、意志があったのでしょう。 当時はそれが普通とは言え、結婚が許されないカトリックの聖職者のトップでありながら、その法王パウルス3世自体、自分の孫たちとともに肖像画に収まっているし、その幼い孫たちにも、枢機卿というような高位を与え、同族主義との批判は免れません。だから、という訳ではありませんが、教書の「効き目」は、ほとんどなかったのではないかと思います。
2008/08/29
コメント(0)
-
ヴェネツィアの「カ・ドーロ」
「カ・ドーロ」、すなわち「黄金の家」と呼ばれる、15世紀のヴェネツィアンゴシックの宝は、大運河の中でも最も有名な館のひとつです。 名前の由来は、最初のオーナーが、ファサードを黄金と極彩色で覆わせていたためです。 この左右非対称の、きらびやかな彫刻の窓を持つ館は、1424年から1430年の間に、マリーノ・コンタリーニが注文し、ジョヴァンニとバルトロメオ・ボン父子(兄弟の説もあり)が設計したものです。 その後、孫娘の結婚の持参金として他家のものになり、19世紀には当時のオーナーの趣味で、ひどい変更がほどこされました。 1894年に、ジョルジョ・フランケッティ男爵が、自分の絵画のコレクションを展示し公開するためにこの館を買い取りました。そして、より15世紀のオリジナルの形に近い修復をかさねていきました。 1916年に、男爵は絵画のコレクションごと、この館を国に譲渡し、1927年には、「ジョルジョ・フランケッティ美術館」としてオープンしました。 ティツィアーノの「ヴィーナス」や、マンテーニャの最後の作品、カルパッチョの「受胎告知」などが見られます。 館の内部はもちろん、テラスから眺める大運河と、対岸のリアルト市場近くからファサードをゆっくりと味わいたいものです。
2008/08/22
コメント(0)
-
ヴェネツィアの「救護の橋」
ドルソドゥーロ地区に「救護の橋」というのがあります。この橋の前に、写真で見える白い建物の「救護所」があったからです。現在のこの橋は、19世紀の終わりに修復されたものですが、最初の橋は、その救護所が出来た当時の16世紀後半に作られ、他の多くの橋のように、欄干はありませんでした。 かつてヴェネツィアには、たくさんの「救護所」がありました。巡礼の途中で行き倒れた人のための宿泊所。ハンセン病患者のための救護所。貧しい人々のための避難所に孤児院など、ヴェネツィア本島内にも周りの島にも散らばってありました。 この橋の前にあった救護所は、コルティジャーナ(高級娼婦)として名を馳せた、ヴェロニカ・フランコ(1546-1591ヴェネツィア生まれ)が設立した、娼婦たちのための救護所でした。 美しさだけでなく、文学、特に詩人としての才能で、ヨーロッパの宮廷や貴族の男たちに賞賛されていたヴェロニカのような女たちは、以前書いた「おっぱい橋」のまわりにいたような娼婦たちとは、全く別のカテゴリーに属するものでした。 扱われる時は貴婦人で、行動には貴婦人よりもずっと自由があり、男たちからだけでなく、女たちからも憧れられる美と知性を持っていたからです。 本当の共和制に近い政治形態を持っていたヴェネツィアでは、「市民」の力が強かったため、女性も他の国よりは、比較的自由に振る舞っていたようです。それでも、女性が自分で選びとった意志で自立して生きるのは、ほぼ不可能な時代でした。 ヴェロニカの残した詩や手紙の中にも、それを嘆く言葉が見られます。だからこそ、名を馳せ財を成した後も、女性、とりわけ人々からも蔑まれる貧しい娼婦たちを援助したい気持ちがあったのでしょう。 病気を移されたり、経済的に困窮した娼婦たちを一時的に救護し、転職したい者には、手仕事を教える、職業訓練的なところも持っていました。 この救護所は、ヴェロニカが亡くなった後も、200年以上続いたということです。
2008/08/15
コメント(0)
-
ヴェネツィアのリド島
8月の終わりから9月の初めに毎年開催される「ヴェネツィア国際映画祭」は、リド島で行われます。 リドは、ヴェネツィア本島の東南に位置する長さ12kmの細長い島です。「LIDO」は、砂州、砂浜という意味のイタリア語なので、ヴェネツィア以外でもリドは存在するのですが、一番有名な「リド」は、このヴェネツィアのリドということになるでしょう。 文字通り、ラグーナとアドリア海との間に出来た砂州で、遠浅の場所で波が沖合で砕け砂が堆積してできたものです。 19世紀までは、サン・ニコロ教会とサンタ・マリア・エリザベッタ教会の他は、菜園と松林があるだけで、人はほとんど住んでいませんでした。ただ、ヴェネツィア入りする船の最初の入り口でもあったため、過去には要塞や見張り台などの役目を持っていました。 19世紀になってリゾート地として注目され始め、20世紀の初めには映画祭の開催にもともない、高級リゾート地として定着しました。 現在のリドは、かつてほどの高級感はありませんが、今の時期砂浜では、たくさんの地元ヴェネツィア人たちで賑わっています。ヴェネツィアの人はヴァカンスに、土の感覚と緑を求めて山に行く人が多いのですが、夏は、他のイタリア人同様やはり海も欠かせないようです。 このイタリア人の「ビーチ通い」には、ほとんど「信仰」もしくは、「強迫観念」に近いのではないかと、思う時があります。テレビで皮膚科の専門医の「紫外線の浴び過ぎは危険です」の警告も耳に入らないように、せっせと砂浜に通い、デッキチェアに寝そべり、うわさ話をしたり居眠りをしたりして午後中を過ごさないと、夏は終われないようです。 これには、戦後以降の二つの観念があると思います。太陽をいっぱいに浴びることは、とにかく健康的という観念。日に焼けた姿は、良いヴァカンスを過ごす経済的なゆとりがある、というイメージ。 その固定観念も、たいがいもう古いかなとも思うし、猫も杓子もとも思うのですが、その中に、長いヴァカンスを満喫するイタリア人への、一抹の「嫉妬」がないと言えばウソになるでしょう。
2008/08/08
コメント(2)
-
ヴェネツィアの「ブリコラ」
『水に上に築かれ、水に囲まれた、ヴェネト人の神聖なる街ヴェネツィアでは、城壁の代わりに水によって護られている。よって、これに損害を与える者は、いかなる者も敵とみなし厳罰に処す。この法律は未来永劫にわたり不変である。』 こういう内容のラテン語の碑文が、1505年にヴェネツィア共和国の「水の行政官」庁の壁に刻まれました。人文学者ジャンバッティスタ・チペッリによる文で、現在、この大理石の碑文は、コッレール美術館に保存されています。 この文章からもわかるように、特殊な沼沢地にある都にとって、「水の扱い」は最重要事項でした。具体的には、淡水と海水の流れの調節と、飲料水と水路の確保です。 この水路の目印となっているのが、写真の「ブリコラ」または「ブリッコラ」と呼ばれる杭です。ヴェネツィアの運河にあるのは、ほとんどが「パーリ」「パリーナ」と呼ばれる、舟を繋ぎ止めるための棒杭ですが、「ブリコラ」は、広いラグーナ上の通行可能な水路があることを示す標識で、島から舟で少し外に出てみると、すぐに目にすることが出来ます。 だいたい三本くらいの太い杭を、金属のベルトで結びつけてあり、先端部分には浸食を防ぐためのタールが塗られています。その中で「ダーマ」(写真右)と呼ばれているのは、三本もしくは四本のうちの一本が、長く突き出ていて、水路の始まりを示しています。 これらの材料には、穴を開け害を与えるフナクイムシに強いことから、カシやクリの木が使われています。 カモメの止まり木にもなっているこのブリコラは、 それでも、バクテリアとフナクイムシが原因で、十年程で朽ち果てるので、新しい物に立て替えられます。舟を係留するための、「パーリ」は、太さにもよりますが、二、三年から七、八年で取り替え時期が来ます。 最近は、運河の中にある「パーリ」の中で、プラスティックのものが出て来ました。表面には木目のような加工もしてあって、よく見ないことには、その材質が木なのかプラスティックなのかはわかりません。材料費は木材より高くつきますが、立て替えがほとんど必要ないので、結果的には経済的だからです。 夕暮れのラグーナで、朽ち果てたブリコラに、カモメがとまっているのはそれなりの風情があるのですが、それは旅人的な感傷というものかもしれません。経済的な上に、新たに木を消費しなくて済むという「エコ商品」となれば、反対する理由もなくなるでしょう。 まだ今は、正式には認可されていないプラスティックのパーリは、その材質ゆえにちょっと見下されている感じですが、そのうち「エコ-パーリ」「エコ-ブリコラ」などという名前がついて、少しずつ、木にとって替わって行くのではないかと思います。
2008/08/01
コメント(0)
-
ヴェネツィアのパオロ・サルピ(その10)
年が明けた1623年1月、七十歳のサルピに最後の時間が近づいていました。 12日になって、容態が悪化した彼は、修道院長を呼びます。自分の持ち物すべてを修道院に寄付することを伝え、臨終の聖体を依頼しました。服を着替えベットの上に座り、修道院の僧たちが集い見守る中、臨終の聖体を受けました。 14日になると、もう起き上がることは出来ませんでした。しかし精神はとてもクリアで、知らせを受けて最後の挨拶に訪れた多くの要人たちに、いつもの明るさで対応したといいます。 サルピのベットを取り囲み、涙を流す修道士たちに『おやおや皆さん、そんな湿った顔をして。私は今まで、あなた方を出来る限り慰めたり、勇気づけたりしてきましたよ。今こそあなた方の番ではないですか、私を励ましてくれるのは』と、冗談まじりに言ったそうです。 医師が診察に訪れ、サルピに残り時間がわずかであることを告げます。すると彼は、微笑みながら医師にこう言いました。『神がお望みになるのなら、この最後の仕事(死ぬこと)を、きちんと成し遂げましょう。』 「信仰」というものは、このためにあるのか。これほどまでに心おだやかに、むしろ喜びさえともなって、人生の幕を引くために、存在しているのかと、信仰というものを持たない私などに思わせるほど、死を前にしたサルピの心は、晴れ晴れとしたもののようでした。 しばらくしてほんの少しの間、サルピは意識を失います。そしてうわ言で『サンマルコへ急ぎましょう。たくさんの処理すべき交渉があるのです。』とつぶやいた後、我に返ります。時計を見るともう夜の12時を過ぎていました。そしてこう言ったのでした。『さあさあ皆さん、もうお休みになって下さい。私は以前いた場所―神のところへ帰りますから。』 誰もその場所を動く者はいません。そしてそれが最後の言葉になりました。僧たちの祈りとすすり泣きの中、サルピは息をひきとりました。1623年、日付は1月15日になっていました。 神学者でもあり、サルピの愛弟子であったミカンツィオが、後に『パオロ・サルピ神父の生涯』という伝記の本を出版しています。その後19世紀後半に再評価のブームがあったのか、多くのサルピに関する研究や伝記本が出されました。その中で1894年にロンドンで出版された、ロバートソンの『サルピ神父~The Greatest of The Venetians~』で、「サルピは、最大で最後の偉大なヴェネツィア人であった」と、締めくくっています。 実際、ヴェネツィア共和国がサルピと組んで、法王庁と対決した1606年の出来事は、おそらく最後のヴェネツィアらしいエピソードという気がします。 最後まで、サルピを全面的に信頼しサポートし続けたヴェネツィア。信念と行動で、ヴェネツィアの一番大切なもの―「誇り」を守り通したサルピ。 パオロ・サルピを失ったヴェネツィアは、まるで誇りまで一緒に無くしてしまったかのように、国としての力を少しずつ後退させてゆき、国際舞台から遠ざかって行きます。 時代はすでに、建築様式から大げさなカツラの流行まで、これでもかと誇張され飾り立てられた、バロックへと移り始めていました。 パオロ・サルピという人は、ヴェネツィアという独特の沼沢地の中に、ずっと昔に蒔かれた種が満を持して咲いた、奇跡の蓮の花ではなかったか、と思うときがあります。(写真はカンナレージョ地区にあるサンタ・フォスカ広場の、サルピの銅像)
2008/07/25
コメント(2)
-
ヴェネツィアのパオロ・サルピ(その9)
サルピの暗殺に失敗したローマ法王庁は、その後も再三にわたって実行しようとしました。この執念深さは、「ローマ教会」という絶対的な権威が少しずつ失墜しつつある中、ヨーロッパのインテリ達の間ではもはや有名なサルピが、大衆の支持を得れば、第二のマルティン・ルターになり得る、これに対する大きな危惧からでしょう。 サルピの理念は、プロテスタント達の唱えた信仰の解釈等と共通する部分も多いのですが、神学者として、ルターとは違うタイプでしたし、科学者としてもガリレオとは異なっていました。視点が違うというか、あらゆる学問を深めながら、同時にずっと遠くを見据えているとでも言うのでしょうか。 ガリレオが、教授として18年間をパドヴァ大学で過ごし、フィレンツェへ移った後も、サルピとの交流は続いていました。 地動説だけでなく、空気にも重さがあることを主張したりと、当時の専門家でも理解されない最先端の学問だけに、ローマ教会から圧力を受けることも多く、落ち込むガリレオにサルピが「いつの日か人々が、貴公の偉大さを理解するときが来るはずです」と励ます手紙を送っています。 また、ガリレオが重力や天体についてサルピに書いた手紙は、科学史上もっとも重要な資料の一つだと言われています。 この専門的な内容の手紙のやりとりからも、サルピの天文学、物理学、数学のレベルは当然ガリレオと同程度であったことは疑う余地はありません。 神学者、歴史家、文筆家として、何冊かの本や学術論文を執筆しています。『パウロ五世による聖務禁止令についての論文』『パウロ五世によるヴェネツィア共和国への懲罰に関する考察』『トレント公会議の歴史』『教会の特権についての論文』などです。これらの本に書かれた文章のスタイルが、またサルピその人を端的に表しています。 というのは、当時の主流の文体というのは、修飾され誇張された、つまりドラマティックで大げさな文章が良いとされ、圧倒的な流行でもありました。一方サルピの書く文章はシンプルで簡潔。物事を、それ以上でもなく以下でもない表現で描写する。直接ズバリと核心を突くにもかかわらず、攻撃的な感じがしない。完璧に研がれた刃物が、その切れ味の良さゆえに軽さの感覚しかない、のと似ているでしょうか。 そのシンプルな文章には、大衆に向けてという彼の思いがありました。そのためには判りやすい文章でないといけない。学問は、知識階級の自己満足や自己陶酔の手段ではなくて、多くの人々の役に立たないと意味がない、ということです。 学問にしても宗教にしても「実際に使える、人の生活をより豊かにするもの」であることが、サルピにとってより重要なことでした。だからこそ、組織の権力と地獄の恐怖とで、人々をあやつり縛りつけるローマ教会を批判したのでしょう。本来の宗教は、人を解放するものである、と。 もう一つ象徴的な意味が、簡素な文体の中にあったと思います。それは、「外観と中身の一致」です。壮大で華やかな文章ではあるけれど、内容はあまりない、口では立派な理想を語るけれども、実際の生活態度は矛盾している、というようなことは、人がはまりやすい落とし穴ですが、サルピは、極力それから自分をいましめようとしていたのだと思います。 彼は一つのノートを持ち歩いていました。そこには自分の間違いや直すべき欠点が、折にふれて記入され、それらがその日は改善されたかどうか、一日の終わりに自分を検証するためのノートでした。 少年の頃より天才と呼ばれ、あらゆる学問に精通し、各地のVIPに助言を求められ、修道会ではゴボウ抜きで出世、ヴェネツィアでは英雄視されていたサルピ。このような人がこんなノートを持っていた。このような人が慢心することなく、こんな地味な努力を重ねて自分を律していた。 いや、おそらく自身に厳しい眼差しを向け「慢心する自分」を自覚していたからこそ、常に修正することを続けていたのでしょう。 神学校で教えること、そしてヴェネツィア共和国の法学コンサルタントとしての仕事に献身していたサルピですが、1622年の12月25日、クリスマスの挨拶のため部屋に訪れた弟子のミカンツィオにこう告げます。「これが、私の最後のクリスマスになるでしょう」(その10に続く)
2008/07/18
コメント(0)
-
ヴェネツィアのパオロ・サルピ(その8)
サンタ・フォスカ橋のたもとでサルピが刺客に襲われてから、わずか二日後の1607年10月7日、ヴェネツィア政府は三人の容疑者の氏名を突き止め、その逮捕に懸賞金をかけます。また、犯人をかくまった者や、居場所を知りながら告発しない者は厳罰に処す、と発表しました。 しかし三人の犯人は、その頃すでにローマへ戻っていました。コロンナ枢機卿のもとに身を寄せて、さてどれほどのご祝儀が法王様から頂けるものかと、期待に胸を膨らませていたのです。 ところが、「なんというスキャンダル!サルピ神父襲撃の黒幕は法王庁だった!」「スキャンダルどころか!こんなことは昔から、法王庁には朝飯前さ!」といったデモが展開され、風刺のビラがまかれたのです。 面目を失った法王パウロ5世は、三人を投獄することに決めます。任務は完全には果たさなかった上に、今となっては邪魔な存在、ということなのでしょう。 実際それまでの歴史で、神の名においてローマ法王庁が直接、もしくは秘密裏に、どれだけの思想家、宗教家、科学者、そして異教徒たちの命を奪い、また、たくさんの女性たちを「魔女」とし殺害してきたことでしょう。(法王庁を激しく批判したプロテスタントやカルヴィニズムの教会でも、自分たちの教義や立場を絶対とし、違う信仰を持つ者を迫害し、魔女狩りも続いていました) ヴェネツィア市民がサルピ襲撃のニュースを聞いた時、犯人をかくまっているに違いないと、すぐにヴェネツィア駐在の法王庁大使の住居に押し寄せている所を見ても、ローマ法王庁の「やり口」は周知の事実だったのでしょう。 さて一命をとりとめたサルピですが、二度と同じことが起きてはならないと、彼の身の安全に関する提案が、1607年10月27日ヴェネツィア共和国の議会で可決されます。 その内容は、護衛付き私用ゴンドラの提供、総督宮殿近くに助手とともに住める住居の提供、そして年俸を倍増の800ドゥカーティに引き上げる、というものでした。 しかしサルピは、それらの申し出のすべてを鄭重に辞退します。信念を貫いた結果とはいえ、今自分は、たくさんの修道院の仲間達の献身や、他の多くの人々に支えられて生きている。 この時彼は、五十五歳。 九死に一生を得てなおさら、一人の修道士として純粋に地味に、そして自分の姿勢と知識を通して人の役に立てるように、残っている自分の時間を捧げたいと願ったからではないでしょうか。 あきらめきれないヴェネツィア政府は、「隠し渡り廊下」の建設を提案します。修道院から誰にも見られずに、直接ゴンドラに乗り込むことが出来る、という通路です。(当時のゴンドラは屋根付きでした) 信念の人サルピも、このヴェネツィア政府の必死の申し出は、有り難く受けたのでした。(写真は、サンタ・フォスカ橋近く サルピの修道院 その9に続く)
2008/07/11
コメント(0)
-
ヴェネツィアのパオロ・サルピ(その7)
ヴェネツィアに「聖務禁止令」を出し、サルピを破門したローマ法王パウロ5世ですが、ヨーロッパ各国の動きから見ても、本当の戦争に持ち込んでヴェネツィアを叩くには、全く不十分な状況でした。 1607年4月、ヴェネツィア共和国と法王庁の抗争は、ヨーロッパ各国(フランス=アンリ4世、スペイン=フェリペ3世、イギリス=ジェームス1世、ドイツ=ルドルフ2世、サヴォイア公、マントヴァ公)の取り持つ、和解調停に委ねられることになりました。 しかし、ヴェネツィアは一歩も譲る気はありません。ヴェネツィアの和解の条件は一つ、「法王庁が、我々の司法への口出しをやめること」。 ヴェネツィアは、聖務禁止令の解除、教会財産規制法の撤廃要求の取り下げ、サルピらへの破門の撤回という条件がすべて満たされたのを確認して、ようやく、二人の罪を犯した聖職者だけは、ローマへ引き渡します。つまり和解と言っても、ヴェネツィア側の事実上の勝利でした。 1607年9月、ローマ駐在のヴェネツィア大使コンタリーニが、ヴェネツィア政府にある報告をしていました。それは、サルピの暗殺をたくらむ不穏な動きがある、というものでした。 ヴェネツィア政府は直ちに、サルピに護衛をつけようとしますが、サルピは断ります。彼にすれば、すべて想定済みというところでしょうか。なので、今になって自分の信念はもちろん、生活スタイルさえも変える気はさらさらなかったのでしょう。 とはいえ、いくら予想はしていたと言っても、実際に自分の命が狙われているとはっきりした中で、護衛を断り、通常の生活を送るというのは、ふつう出来ることではありません。こういったところに、静かで強靭な精神と気骨ある彼の生き方が表れています。 サルピが刺客に襲われたのは、1607年10月5日の夕暮れ時、弟子と供の者とで修道院へ帰る途中の出来事でした。ちょうどサンタ・フォスカ橋のたもと、あと一歩で修道院という場所です。 短剣で首を二カ所、三カ所目は右耳の後から入った刃が、鼻と右頬の間に突き抜けるというものでした。たまたまそれを見た付近の女たちの悲鳴で、人々が駆けつけるのを見て、刺客達は火縄銃を発砲しながら走り去っていきました。 崩れ落ちるように倒れたサルピを供の弟子が抱え、もはや万事休すかと思いながら、刺さったままの短剣を抜くと、なんと息をしているではありませんか。急いで近所の家に入り応急処置を施した後、舟を呼んだのでした。 サルピ襲撃のニュースは、その夜のうちにヴェネツィア中に広がります。ヴェネツィアを救った英雄サルピの容態を少しでも知ろうと、修道院のまわりには連日人々が取り囲みました。 ヴェネツィア政府は、パドヴァ大学(医学のレベルは当時世界最高峰)から最高の外科医によるチームを派遣し、毎日詳しく容態の報告をさせました。そして、怒りに燃える市民には、とにかく我々のサルピ修道士は生きていること、犯人逮捕に全力をあげることを伝えます。(その8に続く。写真はサルピが襲われた場所 サンタ・フォスカ橋。右手に見えるのがサンタ・フォスカ広場に立つサルピの銅像)
2008/07/04
コメント(0)
-
ヴェネツィアのパオロ・サルピ(その6)
法王庁からの戒告が届いた日から、19日後の1606年5月6日ヴェネツィア政府は「神以外の、地上の誰であれ、我が国の尊厳を傷つけることはできない」と宣言し、領土内の聖職者に対し、法王の通達を無視し、宗教行事は通常通り行うこと。通達の張り紙を見た者は、直ちに破り捨てること、を命令しました。 この19日間、ヴェネツィア共和国が何をしていたかというと、戦争に備えての、物資の調達をしていたのでした。法王の勅書を無視することは、法王庁に対する宣戦布告も同然であったからです。 さて、このヴェネツィア共和国の理論的な後ろ盾には、もちろんサルピがいました。彼はまず、「神を崇めるのに、法王の許可は不要である」とし、「法王庁の権限は、教会法によって制限されているはずである。しかし、今回のヴェネツィア共和国に対する措置は、その乱用にあたる。これは、あらゆる混乱とスキャンダルの元であり、ひいてはキリスト教精神の危機にもつながる重大な問題であり、明白な教会法違反である」と法王庁を非難しました。 サルピの理論は、支持者からはさらなる賞賛を得、反対に法王庁からは怒りを買いました。ヨーロッパ各国はというと、オランダは、明確にヴェネツィアの支持を表明。狂信的カトリック国スペインは、法王側。ドイツ、フランス、イギリスは、曖昧な態度もしくは、ヴェネツィアよりの姿勢でした。 1606年9月、サルピの仕事に満足したヴェネツィア政府は、年俸を倍の400ドゥカーティに昇給することを決定します。こう書くと、大企業やVIPの利益を守るために、契約で雇われた有能な弁護士のようなイメージになってしまいますが、決してそうではありません。 神学者として、またキリスト教の信仰を持つ者の理想と信念に基づく理論が、ヴェネツィアという国の誇り高い姿勢と一致していたのです。その共通点は「人間の尊厳」と言い換えてもいいかもしれません。 キリスト教の原点である、福音書の教えに戻った上で、教会のあらゆる世俗性(昇進、財産、権力など)を取り払い、霊的な関心だけが唯一最大のモチベーションであるのが彼の理想とする教会の姿でした。その慈悲の中にこそ、宗教の神髄があるのであって、形式を重んじること、法王庁の認可、恩赦をとりつけることは、本質からははずれているとしました。教会が本来の誠実さを取り戻し、本当の意味で人々の心の支えになるような宗教が広がってゆくことを、彼は強く望んでいたのです。 1606年10月20日、サルピは3人の弟子とともに、ローマ法王庁に召喚されますが、サルピは、身の安全が保障されていないとして、これを拒否。年が明けた1607年1月5日、これによりサルピらは破門されます。(その7に続く)
2008/06/28
コメント(2)
-
ヴェネツィアのパオロ・サルピ(その5)
1591年、ヴェネツィアに戻ったサルピは、研究に没頭し、異端裁判についての本を執筆、出版します。しかし、気鋭の神学者としてもはや名の知られた彼は、司教など高位の教会関係者から依頼された、いくつかのややこしい係争を常に抱えてもいました。 その頃ヴェネツィアとローマ法王庁の関係は、二つの事件をめぐって険悪なものになっていました。ヴェネツィアの自国運営の方法と法律に、ローマ法王庁が強い不快感を表していたのです。(以前「ヴェネツィアとイエズス会(その3)(2007/12/12)」の記事で、この二つに事件に触れました) それは、教会財産に対する規制法(市民は、ヴェネツィア政府の許可なしに、一定以上の財産を教会に贈与してはいけないという法律)と、重犯罪をおかした聖職者二人を、ローマの宗教裁判所に送らずに、自国の法律で裁いたこと、の二点です。 ローマ法王庁にとってヴェネツィアは、以前からずっと一度叩いておきたい国でした。人文主義、宗教改革、啓蒙思想などという言葉の出回るずっと昔から、ヴェネツィア共和国は、ローマ法王庁の「神の権威」を笠に着た「脅し」が通用しない場所だったからです。 禁書に指定されたはずの本が、ヴェネツィアでは街角の本屋で普通に売られていたし、ガリレオのような「危険な」科学者達も、この街の知識人のサロンで歓迎されていました。「いまいましいヴェネツィア人め。好き勝手なことをしよって!」当時の法王パウロ5世(1552-1621)はそう言ったに違いありません。 1605年頃よりヴェネツィア政府は、サルピにアドヴァイスを求めるようになります。そして、これは早晩大きな政治的衝突になると読んだヴェネツィア政府は、自国の法的、宗教的立場の正当性を、論理的に専門的な見地からかためようと、パオロ・サルピにヴェネツィア政府の法学顧問となることを要請します。 サルピは、承諾の前にある一つの条件を出します。その条件とは、「ヴェネツィア政府は、私を死ぬまで守ること」というものでした。 自分も教会法学者として信念をもって戦うから、 政府も現在の観点を最後まで貫いてくれ、つまり、「腹をくくってくれ」という意味だと思います。 ヴェネツィア共和国が政治的妥協等で、立場を微妙に変えるようなことなく、一枚岩でのぞむ覚悟の有無を見極める必要があったのでしょう。自分が任されようとしている仕事が、学者、修道士としての生命だけでなく、まさに命そのものを危険にさらす熾烈な戦争であることをサルピはよく自覚していたのです。 法王庁は1605年12月、教会財産規制法の法律を撤廃すること、罪を犯した聖職者を法王庁に引き渡すこと、この二つをただちに実行するようにという、警告にあたる勅書を出します。これを受けたヴェネツィア政府は、さる要求は一国の独立国の土台を揺るがす重大な問題であり、内政干渉であると反発します。 ここで法王庁は、枢機卿会議を開き、ヴェネツィア共和国に「戒告」を出すことを決めます。「24日以内にこの二つの件が解決されない場合は、破門も視野に入れた聖務禁止令に処す」この文書がヴェネツィアに届いたのは、1606年4月17日のことでした。(その6に続く)(写真は、当時の第90代ヴェネツィア総督レオナルド・ドナ1536-1612)
2008/06/20
コメント(0)
-
ヴェネツィアのパオロ・サルピ(その4)
今回も、知の巨人パオロ・サルピが生きた時代背景を少し書いておきます。 ローマ法王庁の、〈我々が認めないものは、すべて「邪」である〉という、絶対主義的なやり方、「信仰」「善行」の解釈の仕方(特に資金集めのための)に対して、各地の知識人が批判するようになります。 寄進や寄付、その他の「善行」ではなく、「信仰心」だけで人々は救われるべきなのに、救済が売買されているとして、ルターや他の宗教家、神学者たちが非難していたのです。 科学の分野でも時代は変わりつつありました。万能レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)が登場し、コペルニクス(1473-1543)が地動説を発見し、コロンブス(1451-1506)の新大陸発見などもあり、それまでの古典崇拝(ギリシャ、ローマ学説の盲信)ではなく、自然現象を観察することで、新しい事実を発見しようとする姿勢がでてきたのです。 一方、保守カトリックの牙城、ローマ法王庁は、ルターのような、新しい信仰の解釈を危険思想とし、提唱する人間が「過ちだった」と認めない場合は破門に処しました。異端審問を強化し、該当されるとする人物を、投獄や火刑にし、書物は禁書に指定するなど、弾圧を徹底させていきました。 法王やカトリック教義の批判をしたわけではない、科学者たちも「異端視」されていました。コペルニクスは教会からの圧力を恐れ、存命中は地動説の理論を発表しなかったと言われています。ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)も、宗教裁判で地動説を捨てることを誓わされました。(ローマ法王庁が誤りを認め、ガリレオの名誉回復がなされたのは、前法王のヨハネ・パウロ2世時の1992年のことでした) さて、パオロ・サルピは、カトリックの修道士であり神学者、法学者として、徹底的にローマ法王庁、法王の姿勢、解釈を批判した上に最先端の科学者でもありました。またローマ法王庁にとっての「問題児」であるヴェネツィアを完全に擁護し、法王に「ノー」と言ったのですから、睨まれない訳がありません。(写真の絵は、ガリレオの宗教裁判の様子 クリスティアーノ・バンティ画1824-1904)その5に続く
2008/06/14
コメント(0)
-
ヴェネツィアのパオロ・サルピ(その3)
パオロ・サルピの後半生を書く前に、14-15世紀のヨーロッパの状況に触れておきましょう。 14世紀初頭から、ヨーロッパの人口は増加していきますが、食物生産量はそれに伴わず、穀物の価格上昇をまねきます。貧富の差がさらに著しくなり、各地で、貧困層による、暴動や蜂起が頻発しました。それにペスト(黒死病)の蔓延が追い打ちをかけ、大きな社会的不安が広がっていました。 人間の意志だけではどうにも出来ない、未曾有の疫病や天災を前にした時、いつの時代も、人々が頼りたくなるのが宗教というものです。 それらの人々の、せめてもの心の平安に一役買うべき教会は、機能不全どころか、背景にある社会不安を利用する形で、堕落、腐敗していたのです。聖職者による賄賂はあたりまえ、窃盗や殺人などの重犯罪も珍しいことではありませんでした。 全ヨーロッパの教会を統括すべきローマ法王も、権力の座を手にした後は極端な縁者贔屓の人事で、法王の一族が主要なポストを独占し潤う、愛人や子供を設けるのも普通のことになっていました。 そういった時代背景に登場したのが、マルティン・ルター(1483-1546)に代表される宗教改革運動です。プロテスタント誕生の機となったルターの、ローマ法王庁への批判のポイントはいくつもあったのですが、とりわけ徹底的に非難されたのが、サンピエトロ寺院建設費用確保のための、免罪符の大量発行でした。 ローマ教会は、「天国」という場所への予約席を取り扱う、特約代理店と化していました。教会に寄進をするという「善行」を行うことによって、過去の罪が償われ、大小の罪悪感は一掃され、天国行きのビザがもらえる(購入できる)のですから、人々は喜んで寄付や財産の贈与という「善行」を積みました。 「地獄の沙汰も金しだい」とはまさにこのことですが、お客は満足、代理店は大繁盛でこんないい商売はありません。オーバーブッキングやクレームとも無縁です。「ビザ」をもって出発した人は、二度と戻っては来ないからです。(その4に続く 写真はローマ、サンピエトロ寺院)
2008/06/06
コメント(0)
-
ヴェネツィアのパオロ・サルピ(その2)
『今までに出逢った、一番のエンサイクロペディアだ!!』と、交流のあったナポリの著名な物理学者ジャンバッティスタ・ポルタに評された、パオロ・サルピですが、彼の主な経歴(一部)をまとめてみます。〈1552年〉 8月14日、父で商人のフランチェスコ・サルピ、母のエリザベッタ・モレッリの間にヴェネツィアで生まれる。父は幼少の頃に死亡。〈1566年〉 11月24日、14歳で「マリアの下僕会」に入信し、僧衣を着る。そこで、哲学者、神学者、数学者として高名な修道士、ジャンマリア・カペッラに出会い科学の道へ誘われる。ギリシャ語、ヘブライ語から数学、化学などあらゆる学問を吸収。〈1567-1574年〉 弱冠15~18歳で、数々の哲学論文、神学、科学論文を、成熟した論文で支持、又は反論し注目を集める。彼の広大な知識だけでなく、厳格な品行と信仰心に惚れ込んだマントヴァ公に請われ、20~22歳頃まで、マントヴァ公国の神学アドヴァイザーを勤める。 サルピが14際の時に入信した「マリアの下僕会」は、「イエズス会」や「フランシスコ会」などと同様のカトリック修道会のひとつで、13世紀にフィレンツェで創設されました。 サルピの学問、とりわけ科学への入り口となった、ここの修道士ジャンマリア・カペッラは、ヴェネツィアの街で天才少年の噂を聞きつけて、「スカウト」したのでしょう。優秀な人材を確保することは、修道会の将来のためには不可欠であったからです。 そこで、それほど時間が経たないうちに、『「残念だが、君に教えることはもう何もない」と教授が言ったほど、このかぼそい少年は、凄まじい記憶力と深い思考力を兼ね備えていた』と、のちに弟子のミカンツィオが伝記の中で書いています。〈1575年〉 23歳。ミラノのカルロ・ボッローメオ大司教にも目をかけられ、ミラノ滞在を懇願される。が、しばらくして彼の所属する修道会上層部から、ヴェネツィアで哲学を教えるよう要請され、ヴェネツィアへ帰る。 〈1578年〉 26歳。神学の大学講師となる。同年5月15日、パドヴァ大学で神学の学位を取得。〈1579年〉 4月。わずか27歳で、所属する修道会のヴェネト支部長に選出される。 〈1582年〉 30歳。修道会の基本理念を見直す、法学者の一人に選ばれる。〈1585-1590年〉 33歳。6月8日、ボローニャで開かれた、修道会参事総会で、法律長官に任命される。このためローマに滞在し、修道会がかかわるあらゆる訴訟の弁護を担当。この時期、ローマの古文書館、図書館へ通い、古典教義や学説を研究する。 「マリアの下僕会」は当時、13の支部 (フィレンツェ、ローマ、ミラノ、ヴェネツィア、パドヴァ、マントヴァ、ジェノヴァ、ナポリ、サルデーニャ、バルセロナ、マルセイユ、コルシカ、インスブルック)で構成されていました。 修道会という細かいヒエラルキー社会で、サルピのキャリアは、会社で例えると、400年近い伝統を持つ、海外にも支店のある会社で、27歳で取締役、30歳で常務、33歳で専務という昇進ぶりのようなものです。 推察される彼の人柄から、「人の上に立つこと」やりっぱな肩書き等に、興味はなかったと思われますが、明白に他とは抜きん出た能力をもってしては、好むと好まざるとにかかわらず、当然な経緯だったのしょう。(その3に続く。写真は、サルピの伝記の本)
2008/05/31
コメント(0)
-
ヴェネツィアのパオロ・サルピ(その1)
科学者で、歴史家、思想家でもあり、またヴェネツィア共和国の教会法学コンサルタントをつとめ、生涯を修道士として生きた、パオロ・サルピは1552年8月14日ヴェネツィアに生まれました。 ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)の友人で、彼にして『誇張ではなく、本当にヨーロッパ随一の博識である』と言わしめ、ヴェネツィア共和国とローマ法王庁との「戦争」で、その才気と洞察力でヴェネツィアを救った、知の巨人です。 しかし今では、彼の名は、「パオロ・サルピ通り」や「パオロ・サルピ高等学校」などという名前とともにのみ発音され、イタリアはおろかヴェネツィアでもその人物像を知る人は多くはありません。 科学者といっても、サルピの研究範囲は膨大で、ガリレオと同分野の天文物理学、数学をはじめ、 化学、光学、機械学、植物学、鉱物学、医学などの専門家で、実際に人体の瞳孔の縮小と拡大のメカニズムや、心臓を中心とした血液循環のシステムを発見した人物だと言われています。 ガリレオ自作の望遠鏡を、サンマルコの鐘楼に上って、ヴェネツィアの総督に披露したのも、サルピの橋渡しによるものでした。 また、歴史家、文筆家として彼が記した『トレント公会議の歴史』は、当時のヨーロッパの知識人の間で話題を巻き起こした、注目の書でもありました。 というのは、この本は、ローマ法王の主催するその宗教会議で、1545年から1563年にかけて北イタリアのトレント(トリエントともいう)で行われた会議のてんまつを、法王に対し、明確に批判的な立場で書き表されたものだったからです。 単なる歴史家からの視点でなく、パドヴァ大学で神学の学位をとった、神学の専門家として、ローマ法王庁と法王の姿勢を真っ正面から論破した、頭脳だけでない、とても肚の据わった人物でした。(その2に続く)
2008/05/24
コメント(0)
-
ヴェネツィアのゴンドラ(その2)
このゴンドラというタイプの船は、用途によっていくつかに分かれています。 イベントやお祭り用のゴンドラには、凝った装飾がほどこされていて色も様々ですし、競技用のそれは反対に、色も形もとてもシンプルな作りになっています。 その中でも一番よく目にするのが、観光用のゴンドラで、船首部分には「ferro」(フェッロ=鉄)と呼ばれるシンボルがついているのが特長です。 そのフェッロをよく見てみると、くしのような形をしていて、片側にひとつ、反対側に六つの突起があるのがわかります。 この6+1の突起には意味があって、ヴェネツィアの地区を表しています。 ヴェネツィアの地区のことを「sestiere」(セスティエレ、sestoは6の、6番目の意)と言って、六つに分けられた区域のことをいいます。 まず、島の北側部分にあたるのが「Cannaregio」(カンナレージョ区)、東部を「Castello」(カステッロ区)、中心部分に「San Polo」(サンポーロ区)と「Santa Croce」(サンタクローチェ区)。 西部から南一帯を「Dorsoduro」(ドルソドゥーロ区)、そしてサンマルコ寺院がある「San Marco」(サンマルコ区)の六つです。 シンボル左側の一つはと言えば、「Giudecca」(ジュデッカ)の島を表しています。ジュデッカ島は、ヴェネツィア本島の南側に横たわる細長い島です。 行政上の区域としては六つに分かれているこの島ですが、実際にはたくさんの小さな島を、またたくさんの橋でつなげているのがヴェネツィアの姿なのです。 小さな島の数は120個以上で、それが400個前後の橋でもってつながれています。そのたくさんの橋の下をゴンドリエーレ(=ゴンドラ漕ぎ)の操る黒いゴンドラが、滑るように音もなく通り過ぎてゆくのです。(以前の、『ヴェネツィアの地区』の記事を加筆しました)
2008/05/17
コメント(0)
-
ヴェネツィアのゴンドラ(その1)
ヴェネツィアにはたくさんの種類の伝統的な手漕ぎ船がありますが、その中の一つで一番有名なのがやはりゴンドラでしょう。 ゴンドラという言葉の語源は、古代ギリシャ語の「kondis」(=貝の意味)と、古代ペルシア語の「kondy」が、ラテン語になり「gondus」「gondula」になり、イタリア語化して「gondola」になったと言われています。 単純な小舟から、ヴェネツィアで進化し、ゴンドラの特徴でもあるのが、船体の非対称です。 船体が右側に傾いているのは、一人の船頭が最後尾の左側に立って、一つのオールで漕ぐ時に、推進力を与え進路を安定させるためです。 14、15世紀のヴェネツィアでは、ゴンドラは移動の手段だけでなく、ひとつのステータスシンボルとなっていました。 富裕層は、個人専用のゴンドラに御抱えのゴンドラ漕ぎを持ち、そのゴンドラの作りも競うように派手になっていきます。 個人の好み、流行を取り入れ、金箔や大げさなデコレーションをほどこし、豊かさを誇示する道具となりました。 サイズもどんどん大きくなっていき、決して広くない運河の通航を妨げるようにさえなったのでした。 1492年の、コロンブスのアメリカ大陸の発見以来、世界情勢が少しずつではあるけれど、ヴェネツィアに不利に変わりつつあるのを、ヴェネツィア共和国の上層部は分かっていました。 ヴェネツィア政府は、1562年ゴンドラの規制法を可決します。法律で、ゴンドラの色は黒、長さは11メートル、重さは600キログラムと決められたのです。 アメリカ大陸の発見による、直接の不利益はまだほとんどなかったのですが、政府にしてみれば、ばかみたいに華美なゴンドラを作って、浮かれている場合じゃない、というところだったのでしょう。 まだまだ十分に国としての力と勢いがあった16世紀に、こういう「兜の緒を締める」ような法律を施行させるところが、かつてのヴェネツィアのヴェネツィアらしいところでもあります。(その2に続く)
2008/05/10
コメント(0)
-
ヴェネツィアの「アカデミア美術館」
ドルソドゥーロ地区、アカデミア橋のたもとに、アカデミア美術館があります。 1750年9月24日に、ヴェネツィア評議会の決定で、アカデミア美術学校が創設されました。1807年には美術館が併設されます。学生の作品の展示のためと、1797年に崩壊したこの国の、ヴェネツィア共和国時代の芸術財産、閉鎖された教会の宝物の保護の目的のためです。 1817年に、美術館は一般に公開されるようになり、現在は国立の美術館として、14-.17世紀を中心に、貴重なヴェネツィア絵画が一挙に見られる場所です。 正確さと人間的な暖かみを併せ持つ画風の、ジェンティーレ、ジョヴァンニ・ベッリーニ(1429頃-1507、1430頃-1516)の兄弟。 彼らの弟子であるカルパッチョ(1455頃-1526)、大気まで感じさせる風景画、肖像画でも有名なジョルジョーネ(1477頃-1510)。 ルネサンスの巨匠ティツィアーノ(1490-1576)などの他、ヴェロネーゼ(1528-1588)、ティントレット(1518-1594)、ヴェネツィア派最後の大家といわれるダイナミックな構図のティエポロ(1696-1770)。 そして写真のような精密さと美しさのカナレット(1697-1768)まで、ヴェネツィア絵画の至宝が集められています。 先日は、「最後のティツィアーノ」と題した、彼の晩年の作品の特別展で、多少列ができていましたが、内部は比較的ゆったり見ることができました。 ひとつひとつの絵の前にたたずんで、色使いや構図に驚いたり、遊び心のある画家のサインを見つけたりという、静寂でゆたかな時間を味わうことができます。 直接、絵の前に立つと、写真集や解説書で見るときにはない、困惑にも似た感動につつまれることがあります。それが本物の醍醐味というものなのでしょう。
2008/05/03
コメント(0)
-
ヴェネツイアと「赤髭王」その3
この神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(バルバロッサ=赤髭)に対抗した「ロンバルディア同盟」の戦いと、和解のためのヴェネツィアの仲介という出来事は、後々のそれぞれの市民にまで大きな影響を与えるような、象徴的なエピソードとなりました。 まず、北イタリアのコムーネにとっては、自治独立を守り抜いた義勇的歴史エピソードとして語り継がれ、それぞれのコムーネに強い誇りとアイデンティティをもたらしました。 そして「ロンバルディア同盟」の結束と勝利は、現在のイタリアの政党の一つ「北部同盟」(今月の総選挙で、議席を大きく増やしました)の心理的ルーツにもなっています。 一方、ヴェネツィアにとっては、ヨーロッパの二大勢力を自国に呼んで仲裁するという大役をやってのけ、ヴェネツィア人はますます自信を深めてゆきます。 まったくの無名で3Aのチームでプレーしながら、そのうち大リーグでMVPに選ばれると信じて疑わない、夢見る若い野球選手が、9世紀頃のヴェネツィアとすると、今の12世紀のヴェネツィアは、大リーグに定着しあなどれない力を見せ始めた頃でしょうか。 ヴェネツィアという国は、自分の国に対する「愛国心」を持った初めての国と言われています。 自国への誇りと自信、さらに思い込みが激しい、「熱い」人々でありながら、他国を見下したり宗教的イデオロギーに片寄ったりすることがなかったのは、独特のヴェネツィア人のすぐれたバランス感覚のおかげでしょう。 この独特のバランス感覚は、自国の乏しい資源も関係しているでしょうし、野球が一人では出来ないことを、よくわかっていたからでもあったでしょう。 このエピソードは、ヴェネツィアにとって、それからの300年以上の歴史の海原を「大国」として歩んでいく、「はずみ」をつけるきっかけになったのでした。(写真の絵は、カナレット(1697-1768ヴェネツィア生まれ)の、サンマルコ広場)
2008/04/26
コメント(0)
-
ヴェネツィアと「赤髭王」その2
レニャーノの戦いで敗れ、「ロンバルディア同盟」と休戦せざるを得なくなったフリードリヒ1世(神聖ローマ皇帝=赤髭王バルバロッサ)は、まず、当時のローマ法王であるアレクサンデル3世(1105-1181)を、正統な法王として認めることから、和解の一歩をふみだしました。 以前からヨーロッパ中でずっと続いている、皇帝派(ギベリン)と、法王派(グエルフ)の分裂の中で、皇帝フリードリヒ1世は、ローマ法王選挙の際、アレクサンデル3世ではない別の人物を擁立して、失敗している経緯があったのです。 このため、その後ローマ法王になったアレクサンデル3世を、正統な法王として承認していなかったのでした。 この戦争は、北イタリアのコムーネと、ドイツ皇帝フリードリヒ1世との戦いなのですが、ロンバルディア同盟の頂点には形式上、ローマ法王の名があるため和解する当事者は、皇帝と法王という図式になるのです。 次は、休戦調停の調印の場所選びでした。ボローニャかヴェネツィアかというとき皇帝がボローニャを嫌い、結局ヴェネツィアが和解の指揮をとることになり、アドリア海の端っこの小さな島に、ヨーロッパ中のVIPが集結したのでした。 法王側として、教会弁護士団、ノルマンディー王の大使、ロンバルディア同盟各コムーネの代表者。 皇帝側として、ドイツからマインツ、ケルン、他都市の司教。仲介者として、フランス王、イギリス王の代表者、ヴェネツィアの総督セバスティアーノ・ヅィアニ。 そしてもちろん、ローマ法王アレクサンデル3世と、皇帝フリードリヒ1世。 1177年7月24日、フリードリヒ1世はヴェネツィアのリドのサン・ニコロ教会で総督、大司教エンリコ・ダンドロ等と面会します。 そして法王アレクサンデル3世を待つため、サンマルコ寺院へ向かいました。 そこで、法王の足下にキスをし敬意と恭順を誓い、8月1日正式な6年間の休戦合意の調印がなされたのでした。 6年後の休戦期限まぢかの、1183年6月25日、今度はピアチェンツァで完全な停戦が締結されました。(写真の絵は、サンマルコ広場で法王の足元にキスをする、赤髭王。その3に続く)
2008/04/19
コメント(0)
-
ヴェネツィアと「赤髭王」その1
時は、1177年。『カノッサの屈辱』からちょうど100年のこの年、またしてもドイツ皇帝(神聖ローマ皇帝)には、少々屈辱的な出来事がおこりました。 11~12世紀にかけて、北イタリアの都市は、他の王国や公国、伯領といった形態とは違い、自治権をもつ、いわゆる「コムーネ」(コミューン)に成長して、少しずつ領土も広げていました。 これを不快に思っていた、ドイツ皇帝フリードリヒ1世(シュタウフェン朝国王、1122-1190、バルバロッサ=赤髭王のあだ名)は、これら北イタリアのコムーネを壊滅させようと、1162~1176年にかけて、計6回のイタリア遠征を行います。 しかし、北イタリアの自治都市も反撃に出ます。 東部は、ヴェローナ共同体(ヴェローナ、パドヴァ、ヴィチェンツァ、トレヴィーゾ)が団結します。 西部は、ミラノ、クレモナ、マントヴァ、ベルガモ、ブレーシャ、フェラーラの各都市が同盟を組んで対抗しました。 1167年12月1日、この二つの同盟が合体し、さらに、ボローニャモデナ、ピアチェンツァ、パルマの都市も加わり、「ロンバルディア同盟」が生まれます。 ヴェネツィアは、ドイツ皇帝による直接の被害はなかったのですが、ヴェローナ共同体に対して資金援助をしていました。 商品流通の交通路の確保は、欠かせないものだったからです。 さて、「ロンバルディア同盟」は、「ドイツ人圧制のくびきを振り落とせ!!」のスローガンのもと、一致団結して徹底抗戦を展開しました。 1176年5月29日、「レニャーノの戦い」(ミラノ近くの街)で決定的な勝利を収め、ドイツの赤髭王を休戦せざるを得ないところまで持ち込みます。(その2に続く 写真はドイツ皇帝フリードリヒ1世の肖像画)
2008/04/12
コメント(0)
-
ヴェネツィアの「グーリエ橋」
カンナレージョ運河にかかる、「グーリエ橋」は、4本の尖塔(guglie)があるところからその名がついています。 1285年に木の橋が建設され、15世紀の終わりには大きな船でも通れるように、跳ね橋に替えられました。 現在の石橋は、総督ジョヴァンニ・ダンドロの時代1580年に作られたものです。 経済の中心である、リアルト地区の、リアルト橋が1591年の完成で、このグーリエ橋がそれより少し早いのも、この周辺が交通の要所であったことを示しています。 サンマルコが南東の玄関なら、このカンナレージョ運河は昔から、北西側の主要な入り口でした。 19世紀に、本土とヴェネツィアの島を結ぶ「リベルタ橋」が出来る前は、文字通り北部からの玄関口でした。 サンタルチア駅から、以前スペイン大使館があったことから呼ばれている、「Lista di Spagna」を通るとこの橋があり、橋の北側にはゲットーがあります。 橋を渡ってすぐの右手には、お土産から果物、野菜などの露店が並んでいる、生活感のある活気ある界隈が続いています。 16世紀後半に建てられたこの石橋は、その後何度も補強、補修工事がほどこされ、現在でも400年前の大理石のオブジェを味わうことが出来ます。
2008/04/05
コメント(0)
-
ヴェネツィアの「時計塔」(その2)
この美しく精巧な時計を作り上げたジャンカルロ・ライニエーリと、その父ジャンパオロが制作終了後に「他の場所で、同じ時計を二度と作れないように」と「ヴェネツィア政府により、目玉をくり抜かれた」という伝説があります。 これがもし本当のことなら、こんな酷い話はありません。傑作を作ったがゆえに、その腕を疎まれ、職人生命と人間としての尊厳を奪われるなんて。 しかしこれは、後々の噂好きの人々が作り上げた、あくまで「お話」であって、事実ではないでしょう。 まず、「ライニエーリ父子は、その後家族でこの時計塔に住み、時計の調節、修理を任された」という記述があります。 傑作といっても、絵画や彫刻と違って、歯車が複雑にからみあった、しかけのある「機械」です。 さらに、時計は風雨や雷などにもさらされる外にあるのでメンテナンスは不可欠だったでしょう。 専門の知識と技術が求められる修理を「失明した」状態で任されたとは、まず考えられません。 もう一つの理由として、ヴェネツィア共和国は「技術立国」であったことです。 魚と塩しか資源のない、この国の豊かさは、様々な分野の徹底した職人達の技術で成り立っていました。 モザイクやガラス職人、土木建築、造船、印刷技術から船乗りや商人まで、あらゆる方面の妥協しない高い技術と発想が、国内外の信用と名声になり、国に富をもたらしていたのです。 この伝説のようなことがもし起これば、職人達は直ちに反発し、優秀な技術を持つ者は、国外に流出し、結果国の衰退につながることを、政府側は十分承知していたはずですから。 彼らも、国の権力が一人の人間や、一家族に集中しないよう、工夫を重ね技を高めた、政治家という職人達でした。 「二つと同じ傑作を作らせないために」失明させるなどという、権力者のとんでもないエゴは、独裁政治の下では起こっても、ヴェネツィア共和国ではリアリティーが、ないと思うのです。
2008/03/29
コメント(2)
-
ヴェネツィアの「時計塔」(その1)
ヨーロッパの街角の要所には、必ずといっていいほど古い大時計があります。 内部は複雑なしかけの、外側は芸術性の高い装飾をもつ時計は、15~16世紀には、富と繁栄の象徴だったからです。 サンマルコ広場にある、この時計塔も、ヴェネツィアが国としてもっとも栄華を誇っていた時期に作られました。 1493年、ヴェネツィア政府は、エミリア地方で時計職人として名声を得ていた、ライニエーリ家に時計の制作を依頼します。 時計塔の場所は、リアルトへと続く道に通じているサンマルコ広場北側で、海から船でヴェネツィア入りした際も、正面に見える位置に決定されました。 このため、それまでこの場所にあったビザンティン様式のアーケードが取り壊され、1496年、時計塔の建設が始まりました。 1499年2月1日、完成した時計の文字盤は、直径4.5m、金とブルーのエナメルで星と12宮が散りばめられた大変美しいものでした。 文字盤の上部は、聖母子像の左右に、ローマ数字で時間が、アラビア数字で5分毎の時を告げています。 その上には、ヴェネツィアのシンボル、翼のあるライオンの像があり、隣には当時の総督アゴスティーノ・バルバリゴの像もあったそうですが、1797年のヴェネツィア共和国崩壊時に、破壊されたということです。 最上部には、高さ2.6mのムーア人のブロンズ像が、決まった時刻に鐘を鳴らしています。(その2に続く)
2008/03/22
コメント(0)
-
ヴェネツィアの(呪いの)『ダリオ館』(その2)
「ダリオ館」悲劇の続きです。 70年代の犠牲者は、ロックグループ「WHO」のマネージャークリストファー・ランバートでした。 「ダリオ館」は、すでに「呪われた館」として有名になっていましたが、彼はこれまでの出来事を、くだらない迷信としてまったく気にかけませんでした。 「悪いことは言わないから、あそこは止めた方がいい」という忠告にも「そんな、前近代的な!」と、一笑に付しました。 しかし契約直後、ロンドンの家で階段から転落して亡くなってしまったのです。 80年代の挑戦者は、ヴェネツィアの実業家で、姉とともに移り住んだとたん、彼は破産、姉は事故死してしまいます。 次のイタリア人テノール歌手が、買い取りに向け、契約のためヴェネツィアに赴こうとしたところ、交通事故に遭い、命はとりとめますが、契約は白紙となります。 そして最後のオーナーは、投資家ガルディーニで彼もまた破産した上、贈収賄容疑のスキャンダルに巻き込まれ、自殺しています。 そして15年以上の沈黙の後、この「ダリオ館」をアメリカ人企業家が購入し、再び光が当てられようとしています。 15世紀にこの館が計画される以前、この場所は墓地だったという話があり、そこに建てたのが、第一の過ちである?とする説などもありますが・・・。 ゴシックの建築様式で、ファサードはルネサンス風の少し傾斜しているこの美しい館に、「滞留した負のエネルギー」のようなものがあるのでしょうか。 だとしたら、今回の変化で新しい風と光が入りそうした「負の連鎖」のようなものが、一掃できるといいのですが。
2008/03/15
コメント(2)
-
ヴェネツィアの(呪いの)『ダリオ館』(その1)
アカデミア橋を過ぎ、グッゲンハイム美術館近くに「ダリオ館」(カ・ダリオ)はあります。 1487年に、ヴェネツィア政府の評議員であったジョヴァンニ・ダリオの依頼で、建築家ピエトロ・ロンバルドが手がけた、ルネサンス様式のファサードをもつ、色大理石がとても美しい館です。 この館は2年ほど前、アメリカ人企業家によってたったの800万ユーロ(約12億8千万円)で落札されました。 大運河に面している上、この建物の歴史的価値を考えると、市価の、おそらく10分の1程度の値段だったと言えるでしょう。 長い間買い手がつかず、素晴らしいルネサンスの宝が15年以上ホコリだけを住人とし、最近ようやく決まった取引は、破格の安さであったのには、訳があります。 「ダリオ館」の、代々の所有者のほとんどが、なぜか悲惨な死を遂げている、ヴェネツィア一の「呪われた館」と言われているからです。 1494年にジョヴァンニ・ダリオが亡くなった後遺産として、娘夫婦に受け継がれます。 しかし、夫婦は破産し、夫が刺されて亡くなった後妻は自殺し、息子はクレタ島で戦死します。 その後アルメニア人の富豪がこの館を買い取りますが直後に破産。 次の持ち主は、不倫スキャンダルを苦にして愛人とともにこの館で自殺。 次のアメリカ人の購入者は、ホモセクシャルであると噂されることに耐えきれず、メキシコに逃避しますがそこで愛人が自殺。 次のイタリア人オーナーは、この館で同棲していたクロアチア人の18歳の若者に、この館で殴殺されこの若者は殺人の後ロンドンに逃亡しますが、そこで何者かに殺されています。 悲劇はまだ続きます。(その2に続く)
2008/03/08
コメント(0)
-
ヴェネツィアのサン・ジョルジョ・マッジョーレ島
サンマルコ広場の南からラグーナを望むと、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島があります。 この島にあるサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会の鐘楼は、遠くから見ると、サンマルコの鐘楼と色合いが似ていて見間違えることがありますが、サンマルコの鐘楼は角錐で高さ97m、サンジョルジョのそれは、円錐で高さは63mです。 987年に、聖ジョルジョに捧げられた教会が建てられます。1443年には、コジモ・ディ・メディチ(1389-1464)が、政敵によりフィレンツェから一時追放されていた時、この教会で逗留しました。 そのもてなしを感謝して、図書館を建てています。 その後16世紀から17世紀にかけて、パッラーディオやロンゲーナといった当時の一流建築家が、増築や修復を任されています。 鐘楼は、1442年の嵐で崩落し、再建されましたが、1774年に再び倒壊しています。 現在のは、1791年に建替えられたもので、鐘付き部屋の部分にはイストリア産の白い大理石がつかわれています。 1951年には、企業家で郵政大臣もつとめたヴィットリオ・チーニが、この島に文化財団を設立しました。 飛行機事故で亡くなった息子を記した、ジョルジョ・チーニ財団は、文化、歴史、芸術、音楽、演劇、ヴェネツィアの歴史など多岐にわたる活動を支援する拠点となっています。 木製の、鉛と銀でメッキされた、鐘楼のてっぺんの天使の風向計は、1994年の落雷で焼け落ち、その後修復されています。
2008/03/01
コメント(0)
-
ヴェネツィアの「ため息橋」
総督宮殿と後側の建物を結ぶこの「ため息橋」は、この街を訪れた人が「とりあえず行く」場所のひとつです。 この橋がよく見渡せるパーリア橋では、「ため息橋」の写真を撮ろうとする人々を必ず見かけます。 1589年ヴェネツィア共和国は、新しい牢獄を総督宮殿横に建てることを決定します。それでこの新しい牢獄と、総督宮殿内にある裁判所をつなぐ橋が必要になりました。 構造は、警備上の安全を第一に考慮され、空中で屋根のある渡り廊下式の橋になっています。 一方外観は、イストリア産の白い大理石の素材で、優雅な装飾が施されています。 橋の設計は、この新しい牢獄やリアルト橋の設計などを任された建築家、アントニオ・ダル・ポンテの孫(甥の可能性も)である、アントニオ・コンティーノによるもので、1600年に完成しています。 「ため息橋」の名前の由来は、この橋を通るであろう、刑を宣告された者のため息を空想した地元庶民が、そう呼んだことからついています。 19世紀には、多くの文筆家がこの「ため息橋」にイマジネーションをかきたてられ、ハーレクインロマンス的なお話がたくさん生み出されたのでした。 『悪名高いヴェネツィアの「十人委員会」(政府の重要決定機関)により、無実で投獄された善良な若者の、愛しい人との別れ』の物語が、最後の涙を落とす場所として、この橋を舞台にまことしやかに書かれました。 19世紀当時、すでにヴェネツィア共和国はなく、現実の場所と作り物が物語の中で混ぜられ、人々の涙を誘い人気を得たため、歴史的根拠のないフィクションであるにもかかわらず、しっかりと信じられてきたのです。 実際のヴェネツィア共和国は、罪人に弁護士をつけた最初の国のひとつでもある、司法制度の先進国であったのですが、共和国崩壊後のヴェネツィアは、反論しようとする気力さえ持ち合わせていなかったのでしょう。
2008/02/23
コメント(0)
-
ヴェネツィアの道と広場
ヴェネツィアの道と広場につかわれている地面の材質は、そのほとんどが粗面岩(trachite)という石です。ここから30キロほどのところにある、エウガネオの岩山で採石されるアルカリ火山岩で、ローマ時代から建築材料として使われてきました。 ヴェネツィアの街づくりの中で、最初、道は土を打ち固めたものでした。雨のたびにぬかるんで、女たちは服を汚さないために、高下駄のような高さ30センチもある木靴を使っていましたが、15世紀の初めには禁止されています。 13世紀には主要な道が、土からレンガを埋めて舗装されるようになった、と資料にあります。サンマルコ広場周辺が、レンガで舗装されたのが1267年という記録があり、どうもこれ以前の舗装の記録がないのですが、これ以前のデータが残っていないことが、それより前に舗装された道や広場がなかった、という意味にはならないでしょう。 13世紀前半、すでに国際的な物流と市の拠点であったリアルト周辺が、泥でぬかるむ道だったとは考えにくいものがあるからです。 実利主義のヴェネツィア人のこと。儀式や式典などで使うサンマルコ広場より、商業の中心のリアルト地区を先に整備した可能性も十分にあると思うのです。 広場の中心にある井戸の周りにしても、雨水を貯めてろ過させるためには、地面に緩やかな傾斜をつける必要があったので、なんらかのマテリアルで舗装していたと思います。 その後16世紀になって、レンガから、より耐久性の高い今の材質であるこの粗面岩という石に置き換えられるようになったようです。 ほとんどの部分がグレーで、たまにうす茶色のものがあり、縁石や橋の縁などには白い大理石が使われています。
2008/02/16
コメント(0)
-
ヴェネツィア「アルメニア人のサン・ラザロ島」その3
1715年4月、命からがらヴェネツィアへの船旅を終えた12人のアルメニア人修道士たちは、サン・マルコの埠頭で、検疫のための40日間を過ごします。モドーネに残っている人々や修道士たちへの祈り、祖国アルメニア語を忘れないための読書、そして新天地の言葉ヴェネツィア語の勉強に、隔離された不自由な時間も有意義に過ぎてゆきます。 その中で、メキタルは確信します。『あらゆる観点からも、ヴェネツィアは神の啓示だったのだ。』と。おそらくそれは、もう後がない彼の、ミッションへの覚悟でもあったのでしょう。 しかしヴェネツィア政府は、新たな修道会の拠点をヴェネツィアの街におくことは禁じていました。にもかかわらず、ヴェネツィア人のアルメニア人への好意的な感情と、とりわけメキタルに対する敬意や賞賛が、たくさんの推薦書や嘆願書となって、政府の「禁止」の解釈をやわらげることになったのでした。 「島々は例外とする」こうして、メキタルは第一候補のサン・ラザロ島へ下見に行きます。島が放棄されてから時が経ち、かつての教会も朽ちて深い茂みにおおわれていました。しかし、メキタルの目には、未来の信仰と知の、光り輝く場所として映っていたのです。 1717年9月8日、メキタル以下アルメニア人修道士たちが、小さいけれど(7000平方m、甲子園球場の半分)島全部が永遠に彼らのものであるサン・ラザロ島に入ります。 1749年4月に黄疸で亡くなるまで30年以上の日々を、メキタルは神と祖国への愛情の二本柱で、伝道とアルメニア文化の維持、発展に尽くします。 何世紀にもわたって、アルメニア人修道士たちが収集したり、寄贈されたりした工芸美術品が今では博物館として展示され、図書館とともに、アルメニアの文化保存センターとしても機能しています。 書籍については収集だけでなく、1729年にオランダから購入した印刷機で、出版や編集にも力を入れ、コレクションも合わせた蔵書は15万冊にものぼります。(写真は、バイロンも過ごした修道院の回廊)
2008/02/09
コメント(0)
-
ヴェネツィア「アルメニア人のサン・ラザロ島」その2
ビザンティン帝国時代から、東方の国々へ行き来していたヴェネツィア人と、アルメニア人の関係は古く、1717年にサン・ラザロ島がアルメニア人修道士の拠点になる何世紀も前から、たくさんのアルメニア商人がヴェネツィアに住んでいました。 その上、15から17世紀にかけてキプロス島やギリシャの一部がヴェネツィア領で、アルメニアの領土ももっと広かったことを思えばヴェネツィアにとって遠い国ではありませんでした。 このアルメニア教会メキタル修道会の創立者、メキタル(ピエトロ・マヌーク)は、裕福な商人だった親の反対をおして、修道僧の道を選びます。1696年20歳で司祭に任命され、伝道者の育成の他、とりわけ祖国アルメニア人の精神と文化的な向上に力を注ぎます。その溢れるような情熱とあたたかい人間性で、人々や他の修道士の心を動かしてゆきます。 しかし、コンスタンティノープルでは、オスマン帝国下でのカトリック教徒に対する迫害が増しており、メキタルも人々を煽動したとして、ブラックリスト上の一人でした。 見つかれば即逮捕という中、彼は女装で身を隠し修道院を出、まずカプチン会の修道院でかくまわれます。それからフランス大使館経由で、なんとか当時のヴェネツィア領モドーネ(現ギリシャ、ペロポネソス半島の南西部)へたどり着いたのでした。 そこで、1701年9月8日25歳のメキタルは、弟子達とともに新たな修道会をたちあげます。修道院と教会の建設、運営のための借金をようやく返済し、貧しい人々へ還元が出来始めた時は、すでに10年以上が過ぎていました。 さてこれからという時、しかし、この土地も追われることになります。ヴェネツィアとトルコの最後の戦争が勃発したからです。 1715年39歳のメキタルは、血のにじむような思いで築き上げた修道院で、最後の祈りを捧げます。ヴェネツィアまでの弟子達の船旅に、神のご加護がありますように。(その3に続く)(地図の青い部分がペロポネソス半島)
2008/02/04
コメント(0)
全126件 (126件中 1-50件目)